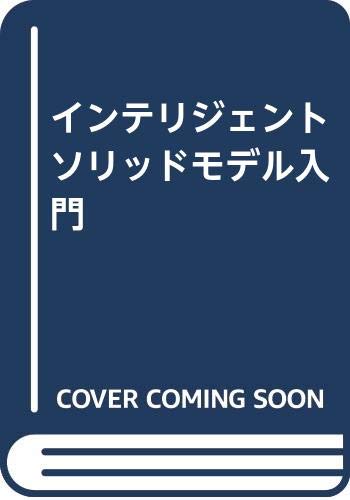1 0 0 0 OA サラエヴォ事件のモニュメント
- 著者
- 大平 晃久
- 出版者
- 長崎大学教育学部地理学研究室
- 雑誌
- 浦上地理 (ISSN:21893179)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.17-20, 2020-05-01
1 0 0 0 OA サイト・スペシフィック・アートとモニュメント―国東半島芸術祭の事例から―
- 著者
- 大平 晃久
- 出版者
- 長崎大学教育学部
- 雑誌
- 長崎大学教育学部紀要 = Bulletin of Faculty of Education, Nagasaki University, Combined Issue (ISSN:21885389)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.25-37, 2019-03-01
長崎大学教育学部紀要:人文科学 通巻 第85号(Bulletin of Faculty of Education Nagasaki University: Humanities, Vol.85) 池田俊也准教授・堀内伊吹教授 退職記念号
1 0 0 0 OA 長崎原爆落下中心碑にみるモニュメントの構築
- 著者
- 大平 晃久
- 出版者
- 九州地区国立大学間の連携事業に係る企画委員会リポジトリ部会
- 雑誌
- 九州地区国立大学教育系・文系研究論文集 = The Joint Journal of the National Universities in Kyusyu. Education and Humanities (ISSN:18828728)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.1, pp.No.15, 2017-09
本稿は,長崎原爆落下中心碑と爆心地にどのような表象が向けられ、どのように構築されてきたか,場所の系譜をたどった。そして,1980年代まで等閑視されていた中心碑・爆心地が,1990年代になって,行政による「聖域化」と,中心碑撤去反対運動を契機として,重要な,そして広く知られる「記憶の場」として確立したことを明らかにした。その上で,中心碑・爆心地を含む長崎原爆関連モニュメント聖地化の空間的な特徴として,西村明が示した「シズメ」と「フルイ」という慰霊の二側面が分離していること,すなわち,死者の追悼と生者に対する平和祈念という慰霊の両側面を兼ね備えた中心碑・爆心地と,平和祈念に特化した平和祈念像・平和祈念像地区が空間的に峻別された,極めて意図的・操作的な聖地形成がみられることを明らかにした。
1 0 0 0 OA 長崎原爆落下中心碑にみるモニュメントの構築
- 著者
- 大平 晃久
- 出版者
- 長崎大学教育学部
- 雑誌
- 長崎大学教育学部紀要 = Bulletin of Faculty of Education, Nagasaki University, Combined Issue (ISSN:21885389)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.1-16, 2017-03-01
長崎大学教育学部社会科学論叢 通巻 第79号(Bulletin of Faculty of Education, Nagasaki University: Social Science, Vol.79)
1 0 0 0 OA 負の記憶と記念碑--沖縄本島中南部の米軍基地跡地の事例から
- 著者
- 大平 晃久 Teruhisa OHIRA 東海学院大学 Tokai Gakuin University
- 雑誌
- 東海学院大学紀要 = Bulletin of Tokai Gakuin University (ISSN:18827608)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.155-160, 2011-03-20
- 著者
- 金今 直子 大山 直子 清水 万里江 坂東 誉子 田和辻 可昌 松居 辰則
- 出版者
- 日本感性工学会
- 雑誌
- 日本感性工学会論文誌 (ISSN:18845258)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.123-133, 2022 (Released:2022-02-28)
- 参考文献数
- 25
In this study, we conducted an experiment that compared 27 schizophrenia patients and 29 healthy subjects in perception of emotions expressed by an NAO humanoid robot. We programmed the robot to express the eight basic emotions proposed by Plutchik (1984) which were anger, anticipation, expectation, joy, trust, fear, surprise, sadness, and disgust using Teshi et al. (2015)’s method of dynamically changing the robot’s eye color. We found a significant difference between the two groups of subjects in their judgements of the robot’s emotions. The results showed that the schizophrenic patients had difficulty in recognizing the robot’s emotions. In addition, the two groups showed different patterns of emotion misperceptions. The schizophrenic group’s misperceptions mistook positive and negative emotions. The misperception of schizophrenic patients may be caused by the similarity of colors and fast blinking cycles. We consider it resulting from the decline in information processing abilities of the schizophrenic patients.
1 0 0 0 OA 本学における教育の質保証と学習成果の可視化
- 著者
- 木村 弘子 保田 洋 中野 久美子 堀田 浩之 永藤 清子
- 出版者
- 学校法人 甲子園短期大学
- 雑誌
- 甲子園短期大学紀要 (ISSN:0912506X)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, pp.51-60, 2022-03-15 (Released:2022-04-18)
- 著者
- 葛西 恵里子 久保 裕史
- 出版者
- 一般社団法人 国際P2M学会
- 雑誌
- 国際P2M学会研究発表大会予稿集 2022 春季 (ISSN:24320382)
- 巻号頁・発行日
- pp.37-51, 2022 (Released:2022-04-18)
- 参考文献数
- 11
クラウドファンディングとは、インターネットを介して不特定多数の人々から少額ずつ資金を調達することであり、近年急速に市場が成長し、認知されつつあり、将来ものづくりに携わる希望をもつ大学生にとって、インターネットを活用したマーケティング4.0を学ぶための非常に実践的な手段として活用が可能である。クラウドファンディングは成功に至るまで様々な活動が必要なプロジェクトの集合体であり、全体として目標達成に向けた活動を行うプログラムであると位置付けられる。しかし学生とプログラム契約ができない下で、各プロジェクトを確実に実行できるかが不透明というリスクを持ち、運営には困難な側面も多い。本稿では、効率的かつ教育としての実のあるクラウドファンディングを実践するにあたり、P2Mにおける3Sモデルの各段階における統合マネジメントを採用し、必要な各プロジェクトを明らかにするとともに、リスク対策として、評価指標の共有による学生の能力と意欲の見える化を進めることで、意欲の持続化をはかることを提言する。
- 著者
- 伊澤 映子 神崎 博之
- 出版者
- 一般社団法人 国際P2M学会
- 雑誌
- 国際P2M学会研究発表大会予稿集 2022 春季 (ISSN:24320382)
- 巻号頁・発行日
- pp.29-36, 2022 (Released:2022-04-18)
- 著者
- 中田 龍三郎 久保(川合) 南海子 岡ノ谷 一夫 川合 伸幸
- 出版者
- 一般社団法人 日本発達心理学会
- 雑誌
- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.3, pp.133-144, 2018 (Released:2020-09-20)
- 参考文献数
- 42
- 被引用文献数
- 1
怒りを構成する要素である接近の動機づけが高まると,前頭部の脳活動に左優勢の不均衡状態が生じる。この不均衡状態は怒りの原因に対処可能な場合に顕著になる。これらの知見は主に脳波を指標とした研究で示されてきた。本研究では近赤外線分光法(NIRS)を用いて,脳活動に左優勢の不均衡状態が生じるのか高齢者と若齢者を対象に検討した。ドライビングシミュレータを運転中に渋滞する状況に遭遇した際の脳血流に含まれる酸化ヘモグロビン量(oxy-Hb)を測定したところ,高齢者では左右前頭前野背側部で左優勢の不均衡状態が顕著に認められたが,若齢者では認められなかった。自動的に渋滞状況と同じ速度にまで減速する条件では高齢者と若齢者の両者の脳活動に左優勢の不均衡状態は認められなかった。この結果はNIRSでも接近の動機づけの高まりと相関した脳活動の不均衡状態を測定可能であることを示しており,高齢者は思う通りに走行できないという不快な状況(渋滞条件)において,明確な妨害要因の存在が接近の動機づけ(攻撃性)を高めると示唆される。接近の動機づけ(攻撃性)には成人から高齢者まで生涯発達的変化が生じており,その結果として高齢者は若齢者よりも運転状況でより強い怒りを生じさせる可能性がある。
1 0 0 0 OA 毎日年鑑
- 著者
- 大阪毎日新聞社, 東京日日新聞社 編
- 出版者
- 大阪毎日新聞社
- 巻号頁・発行日
- vol.昭和6年, 1930
1 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1896年04月27日, 1896-04-27
1 0 0 0 OA 2. ゲノム編集によるブルーギルの不妊化駆除技術開発
1 0 0 0 インテリジェントソリッドモデル入門
1 0 0 0 OA 酸化的フッ素化反応による有機フッ素化合物の合成
- 著者
- 黒星 学 檜山 爲次郎
- 出版者
- The Society of Synthetic Organic Chemistry, Japan
- 雑誌
- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.12, pp.1124-1133, 1993-12-01 (Released:2009-11-16)
- 参考文献数
- 103
- 被引用文献数
- 19 21
Methods for preparation of organofluorine compounds are reviewed from the view point of the reagent system consisting of fluoride ion and an oxidant. Reagents like N-halo imides are often used as the oxidant, which may be replaced by electrochemical oxidation. These methods provide us with various types of fluorinated compounds efficiently and selectively under mild conditions.
1 0 0 0 OA 作業体験を有する者の就労意識 ─デイケアを利用する統合失調症者を対象者として─
- 著者
- 藤田 さより 新宮 尚人
- 出版者
- 一般社団法人 日本作業療法士協会
- 雑誌
- 作業療法 (ISSN:02894920)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.4, pp.469-480, 2019-08-15 (Released:2019-08-15)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 1
本研究の目的は,「作業体験」が統合失調症者の就労意識にどのような影響を与えるのか明らかにすることである.方法は,統合失調症者12名に就労に対する思いと,作業体験について尋ねる半構成的インタビューを実施して,質的記述的分析を行った.結果として,参加者は就労に対し不安を持ち,支援を必要としていた.作業体験により,【作業体験によるポジティブな感情】,【作業体験によるネガティブな感情】,【作業体験からの気づき】のカテゴリが抽出された.作業体験は,自己効力感や作業能力を向上させ,困難を乗り越える力を与え,また自己の能力を適切な客観的評価に近づけることで職種とのミスマッチを防ぐなど,就労に有用な影響を与える可能性が示唆された.
1 0 0 0 OA O-019 一般就労を目指す統合失調症をもつ成人期女性のライフヒストリー
- 著者
- 森山 香澄 大森 眞澄 石橋 照子
- 出版者
- 一般社団法人 日本看護研究学会
- 雑誌
- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.3, pp.3_414, 2019-07-31 (Released:2021-04-18)
1 0 0 0 OA 日本全国基督教信徒同盟会演説集
- 著者
- 杉山重義, 山鹿旗之進 記
- 出版者
- 警醒社
- 巻号頁・発行日
- 1887