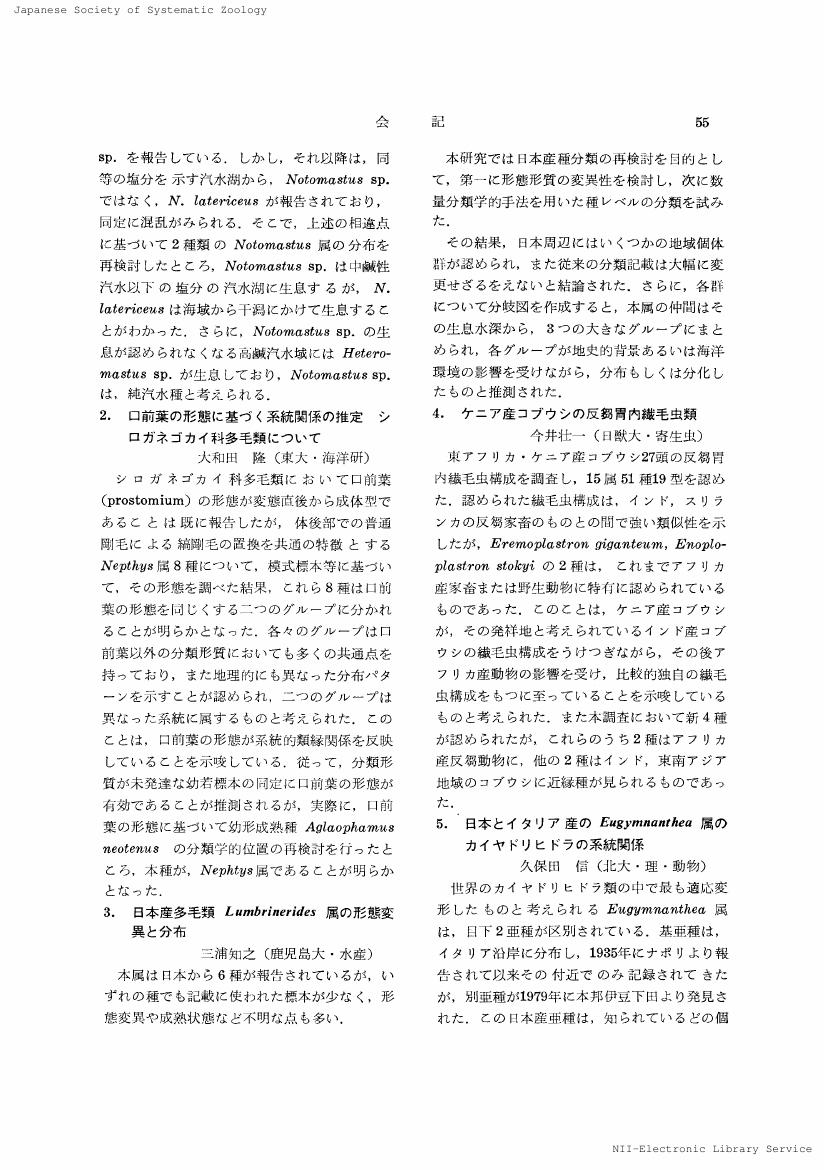1 0 0 0 OA ALOS-2/PALSAR-2データを用いた2そうびき漁船の検出
- 著者
- 髙﨑 健二 齋藤 勉 大関 芳沖 稲掛 伝三 久保田 洋 市川 忠史 杉崎 宏哉 清水 収司
- 出版者
- 一般社団法人 水産海洋学会
- 雑誌
- 水産海洋研究 (ISSN:09161562)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.2, pp.89-99, 2020-05-25 (Released:2022-03-17)
- 参考文献数
- 11
本研究では,灯火を用いない漁業の観測が可能な合成開口レーダを用いて2そうびき漁船の検出を行った.2そうびき漁船の自動検出は,画像からすべての船舶を抽出した後,それぞれの船舶において周辺船舶との距離を調べ,船舶間距離が最小となる組み合わせを漁船ペアとすることで可能となった.漁船ペアが間違っているものについては,組み合わせの修正方法を提示した.また,対象海域における2そうびき漁船の活動を把握するため,2そうびき漁船の密度と船舶間距離を求めた.本研究により,漁期中に十分な画像データが得られれば,漁獲努力量を推定できる可能性が示唆された.
1 0 0 0 OA 樺太におけるアヘン製造の歴史
- 著者
- 木下良裕
- 出版者
- 北海道
- 雑誌
- 北海道立衛生研究所報
- 巻号頁・発行日
- no.26, 1976-06
1 0 0 0 OA 資源低水準期における相模湾および相模灘で漁獲されるマアジの成熟特性
- 著者
- 髙村 正造 鈴木 勇己 荻原 真我 古市 生 渡邊 千夏子
- 出版者
- 一般社団法人 水産海洋学会
- 雑誌
- 水産海洋研究 (ISSN:09161562)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.2, pp.79-88, 2020-05-25 (Released:2022-03-17)
- 参考文献数
- 30
相模湾および相模灘海域で漁獲されたマアジについて,雌雄の生殖腺の組織学的観察や生殖腺重量指数(GSI)に基づいて,性成熟や産卵期などを調べた.GSIの月別変化から,雌雄ともに3–9月にGSIの高い個体が出現し,雄は5月,雌は6月にGSI平均値が最大となった.生殖腺の組織学的観察結果から,雄では精子で充たされた精巣を持つ個体が3–7月に,雌では胚胞(核)移動期および成熟(吸水)期の卵を持つ個体が4–7月にそれぞれ出現した.当該海域における最小成熟年齢は,雄では0歳,雌では1歳であるとともに,雄では11歳,雌では23歳の成熟個体も認められた.半数成熟尾叉長は雄では188.2 mm,雌では230.6 mmであり,雄は雌よりも小型・若齢で成熟することが示唆された.年齢とGSIの関係から,高齢魚ではGSIが低下する傾向が認められたが,当該海域の本種は初回成熟・産卵後から10年以上に渡って産卵に寄与し続けていると考えられた.
1 0 0 0 OA 房総沿岸で小型漁船まぐろはえ縄漁業(かじき縄)により漁獲されるメバチ大型魚の漁獲特性
- 著者
- 石井 光廣 石黒 宏昭 篠原 徹 野口 秀隆 鈴木 正男 堀川 宣明 滝本 豊 余川 浩太郎
- 出版者
- 一般社団法人 水産海洋学会
- 雑誌
- 水産海洋研究 (ISSN:09161562)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.2, pp.71-78, 2020-05-25 (Released:2022-03-17)
- 参考文献数
- 20
房総沿岸で小型漁船はえ縄漁業(通称:かじき縄)によって漁獲されるメバチ大型魚の漁獲特性を整理した.かじき縄は,11月から翌年6月頃に房総沿岸の黒潮流路周辺で,日中に釣針の到達深度約70 mの浅縄操業を行い,主に尾叉長110 cm以上のメバチを漁獲していた.メバチの漁獲位置の月平均表面水温は18.5–23.2°Cであり,これまでのメバチの知見と異なり,日中に水深が浅く高水温の海域で漁獲されていた.
1 0 0 0 OA 土佐湾におけるニギス仔稚魚の成長
- 著者
- 梨田 一也
- 出版者
- 一般社団法人 水産海洋学会
- 雑誌
- 水産海洋研究 (ISSN:09161562)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.2, pp.61-70, 2020-05-25 (Released:2022-03-17)
- 参考文献数
- 20
ニギスは日本周辺における沖合底びき網漁業の主要な漁獲対象種の一つである.魚類発育初期の成長の良否は生残を左右し,資源加入にも影響を及ぼすと考えられるが,ニギス仔稚魚の成長・生残に関わる知見は少ない.2008年4月から2010年3月にかけて,日本の南西部に位置する土佐湾において小型のオッタートロール網を用いてニギス仔稚魚を毎月採集した.標準体長(SL)組成の経時変化により,2–7月頃に小型個体(SL<40 mm)が加入し,約100 mm SLに成長するまで連続的に採集された.明確に識別されたコホートを複数月にわたり追跡し,採集日の間隔と耳石輪紋増加数がほぼ一致することから耳石輪紋の日周性が確認された.採集個体の第一輪形成日(DFRF)を年毎に集計した結果,いずれの年も2–7月に緩やかなピークを持つ単峰型であったことから,土佐湾のニギスは初春から初夏に産卵盛期を有すると考えられた.このことは,日本海におけるニギスが春季と秋季に二つの産卵期を持つという従来の知見とは異なっている.月別のDFRF分布から2008年には春季と夏季の2つのグループが示されたのに対し,2009年では一つのグループ(春季)のみが示された.成長パターンを明らかにするため,2008年と2009年の各グループにおいて第1輪から第56輪までの耳石輪紋間隔を5日ごとに平均した.2008年および2009年春季グループは2008年夏季グループに比べ耳石輪紋間隔は狭い傾向であったが,特に早く採集された個体(短期生残個体)は遅く採集された個体(長期生残個体)に比べ耳石輪紋間隔が狭かった.しかし,2008年夏季グループにおいては短期生残個体の方が長期生残個体よりも耳石輪紋間隔が広い例がみられた.以上により,土佐湾のニギスは発育初期の環境に恵まれなかった場合には成長選択的に生残することが示唆された.
1 0 0 0 OA 二、三の生活樣式より觀たる瀬戸内小島及來島の地誌學的研究 (其二)
- 著者
- 日野 文雄
- 出版者
- 公益社団法人 東京地学協会
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.2, pp.77-90, 1938-02-15 (Released:2010-10-13)
- 参考文献数
- 20
1 0 0 0 OA 二、三の生活樣式より觀たる瀬戸内小島及來島の地誌學的研究 (其一)
- 著者
- 日野 文雄
- 出版者
- 公益社団法人 東京地学協会
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.1, pp.19-30, 1938-01-15 (Released:2010-10-13)
1 0 0 0 OA 豆の調理における硬化・軟化の解析と浸漬操作の影響
- 著者
- 郡山 貴子
- 出版者
- 一般社団法人 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会誌 (ISSN:13411535)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.3, pp.129-137, 2019-06-05 (Released:2019-06-21)
- 参考文献数
- 47
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 『万里の長城』における「男性」と「労働」の位置 : カフカのシオニズム理解を手がかりに
- 著者
- 川島 隆
- 出版者
- 京都大学大学院独文研究室
- 雑誌
- 研究報告
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.63-90, 2004-12
1 0 0 0 OA 豆の煮熟硬度に及ぼす塩の影響
- 著者
- 中村 泰彦
- 出版者
- The Japan Society of Home Economics
- 雑誌
- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.5, pp.427-433, 1991-05-15 (Released:2010-03-10)
- 参考文献数
- 9
普通の大豆とエイジング処理した大豆に対する塩の軟化効果を試験し, 以下の結果を得た.(1) 試験した陰イオンにはいずれにも軟化作用が認められ, その効果は概して陽イオンよりも大きかった.陰イオンの中では, 炭酸水素イオンが群を抜いて軟化作用が強く, つづいて多価カルボン酸, 1価カルボン酸の順であった.(2) 陽イオンでは, アルカリ金属はいずれも軟化作用を示したが, アルカリ土類金属は組織を硬くするように作用した.2価の鉄は普通の大豆に対しては軟化促進的に働くが, エイジング大豆では逆に組織を硬くした.(3) 食塩や第一鉄塩は単独では軟化作用はそれほど強くなかったが, 両者を組み合わせると軟化の強い相乗効果が認められた.(4) 塩溶液浸漬による豆からのCa2+の溶出の程度と煮豆の軟らかさとは比例関係にあったが, 炭酸水素塩や第一鉄塩は特異であった.
1 0 0 0 OA 統合失調症を患う高齢者の栄養状態低下の要因
- 著者
- 髙瀬 理恵子
- 出版者
- 一般社団法人 日本摂食嚥下リハビリテーション学会
- 雑誌
- 日本摂食嚥下リハビリテーション学会雑誌 (ISSN:13438441)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.3, pp.214-224, 2018-12-31 (Released:2019-04-30)
- 参考文献数
- 40
- 被引用文献数
- 1
【目的】精神科病院に入院中の統合失調症を患う高齢者における栄養状態低下の要因を明らかにすることを目的とした.【方法】対象は,精神科病院に入院中の65歳以上の統合失調症患者66名とし,3食経口摂取可能な者とした.この対象の栄養状態をGeriatric Nutritional Risk Index(GNRI)により評価した.栄養状態の低下に影響しうる要因として,基本属性,ADL(障害高齢者の日常生活自立度判定基準),摂食嚥下機能(現在歯数,repetitive saliva swallowing test: RSST回数),社会機能(Rehabilitation Evaluation Hall and Baker: Rehab),認知機能(Mini-Mental State Examination: MMSE)を調査し,GNRIとの関連を,単変量解析およびステップワイズ回帰分析を用いた多変量解析にて解析した.【結果】単変量解析でGNRIと有意な関連が認められた項目は,罹病期間,入院期間,Rehab下位項目のセルフケアおよび社会生活の技能であった.ADL,現在歯数,RSST,MMSEとの有意な関連は認められなかった.GNRIを独立変数としたステップワイズ回帰分析でGNRIと有意な関連が認められた項目は,入院期間と社会生活の技能であり,GNRIに強い影響を与えている順に入院期間(β=-0.40,p= .001),社会生活の技能(β=-0.23,p= .045)であった.【結論】統合失調症を患う高齢者の栄養状態低下の要因は,入院期間の長期化と社会生活の技能の低さであった.高齢の統合失調症患者の栄養状態の低下には,不足したエネルギーや栄養素を補うだけでなく,日中の過ごし方が活性化するような場の提供と,主体的に生活を楽しむための社会生活の技能や自信の回復が必要である.
1 0 0 0 OA デイケアに通所する統合失調症患者の居場所感とQuality of Lifeとの関連
- 著者
- 茅原 路代 國方 弘子 岡本 亜紀 渡邉 久美 折山 早苗
- 出版者
- 一般社団法人 日本看護研究学会
- 雑誌
- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1, pp.1_91-1_97, 2009-04-01 (Released:2016-03-05)
- 参考文献数
- 31
本研究は,デイケアに通所し地域で生活する統合失調症患者83名を対象に,居場所感とQOLの2変数の関連を明らかにすることを目的とした横断研究である。調査項目は,日本語版WHOQOL-26,精神障害者の居場所感尺度(3下位尺度からなる2次因子モデル),個人特性で構成した。想定した居場所感とQOLの因果関係モデルを共分散構造分析を用いて検討した結果,適合度指標は統計学的な許容水準を満たし,モデルはデータに適合した。居場所感が大きいことは,より良いQOLであることが明らかになり,その寄与率は44%であった。このことから,在宅生活をする統合失調症患者がより良いQOLを獲得するためには,彼らの居場所感を高める支援が有効であることが示唆された。
1 0 0 0 OA 精神科病院に長期入院中である統合失調症患者が捉える老いの認識と自己の将来像
- 著者
- 藤野 成美 脇崎 裕子
- 出版者
- 日本精神保健看護学会
- 雑誌
- 日本精神保健看護学会誌 (ISSN:09180621)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.1, pp.105-115, 2010-06-30 (Released:2017-07-01)
- 参考文献数
- 28
本研究の目的は,高齢期の長期入院統合失調症患者がとらえる老いの認識と自己の将来像について明らかにし,看護実践への示唆を得ることである.研究対象者は,精神科病院に10年以上入院中である65歳以上の統合失調症患者7名であり,半構造化インタビューを実施し,質的帰納的分析を行った.その結果,老いの認識は「加齢に伴う心身能力の衰え」「精神科病院で老いていくしかない現状」「満たされることのない欲求の諦め」「死に近づく過程」であり,自己の将来像は「期待が心の糧」「成り行きに身を任せる」「将来像を抱くことを断念」であった.長期入院生活で老いを実感した対象者が語った現実は,社会復帰は絶望的であるという心理的危機状況であったが,現状生活に折り合いをつけて,心的バランスを保っている心情が明らかとなった.退院の見通しがつかない現状であるが,その人がその人らしく生きていくために,少しでも自己実現のための欲求を満たすことができるよう支援する必要がある.
1 0 0 0 OA 手術創に壊疽性膿皮症を合併した潰瘍性大腸炎の1例
- 著者
- 佐々木 寛文 内野 基 坂東 俊宏 松岡 宏樹 池内 浩基 冨田 尚裕
- 出版者
- 日本臨床外科学会
- 雑誌
- 日本臨床外科学会雑誌 (ISSN:13452843)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.11, pp.2902-2906, 2010 (Released:2011-05-25)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 2
症例は28歳,男性.18歳時下血で発症の潰瘍性大腸炎,再燃寛解型,全大腸炎型.ステロイド抵抗性,難治性のために,分割手術として大腸全摘,回腸嚢肛門吻合術,回腸人工肛門造設術を行った.初回手術後は良好に経過し,ステロイドを漸減していたが,術後第40病日に絞扼性イレウスを併発し,イレウス解除術を行った.術後第2病日より,正中創に急速に進行する壊疽性膿皮症,壊疽性筋膜炎を認め,ステロイド全身および局所投与を要し治療に難渋した.壊疽性膿皮症は腸管外合併症として知られ,大腸全摘により軽快することが多い.しかし自己免疫異常に関連し,術後にも出現することがある.診断,治療に難渋することがあり,文献的考察を加え報告する.
- 著者
- Munekazu Kishimoto Tetsunan Yamamoto Yuta Kobayashi
- 出版者
- The Japanese Society for Horticultural Science
- 雑誌
- The Horticulture Journal (ISSN:21890102)
- 巻号頁・発行日
- pp.UTD-314, (Released:2022-01-28)
- 被引用文献数
- 5
In grapes, the ripening time of bunches on lateral or secondary induced shoots, led by simultaneous treatments of current shoot cutting and flower cluster removal, is typically delayed until the cooler seasons. The aim of this study was to estimate the effects of lateral or secondary induced shoot use in the cultivation of ‘Merlot’ grapevine phenology, including number of bunches and weight, yield, and fruit quality. The timings of flowering, coloration and harvest of lateral and secondary induced shoot grapes were delayed by around one month compared with those of vines grown under standard cultivation, which were used as a control. However, there were substantial differences between treatments in terms of number of bunches and weight, yield, and fruit quality. When lateral shoots grew after the current shoot was cut and the flower clusters were removed, the number of bunches decreased, and yield was significantly reduced. In contrast, when the secondary induced shoot germinated after the current shoot, flower clusters, and growing lateral shoots were removed, a stable number of bunches was observed and there was not a severe decrease in yield. Skin anthocyanin content in both the lateral shoot and secondary induced shoot grape berries was increased compared with control. This effect was comparatively stronger in secondary induced shoot grapes subjected to comparatively lower air temperatures during ripening. The results of this study underscore the importance of discriminating between lateral and secondary induced shoots in the process of shifting grape ripening to a cooler season by removing current shoots and flower clusters.
- 著者
- 大和田 隆
- 出版者
- 日本動物分類学会
- 雑誌
- 動物分類学会誌 (ISSN:02870223)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.55, 1987-12-25 (Released:2018-03-30)
1 0 0 0 OA 手紙論としての手紙 : カフカの恋文をめぐって
- 著者
- 池田 あいの
- 出版者
- 京都大学大学院独文研究室研究報告刊行会
- 雑誌
- 研究報告
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.95-114, 2005-12
1 0 0 0 OA コンピュータシミュレーションによる眼内レンズ挿入眼の網膜像作成手法
- 著者
- 今井 新太郎 玉木 徹 Raytchev Bisser 金田 和文 曽根 隆志 木内 良明
- 雑誌
- 研究報告グラフィクスとCAD(CG)
- 巻号頁・発行日
- vol.2015-CG-158, no.11, pp.1-6, 2015-02-20
白内障手術の際に眼内レンズが挿入されるが,後遺症として光源とは別の位置に光のぎらつき (グレア) を知覚することやコントラストの低下が挙げられる.Quality of Vision (QOV) の向上のために眼内レンズ挿入眼の見え方の質について調査することは重要である.本研究では,遠近に焦点を合わせることができる多焦点眼内レンズの見え方の質について調査することを目的とし,光線追跡シミュレーションに基づく網膜像作成手法と Modulation Transfer Function (MTF) を算出する方法を開発した.網膜像による定性的評価と MTF による定量的評価により,多焦点眼内レンズの見え方の質を単焦点眼内レンズと比較検討した.