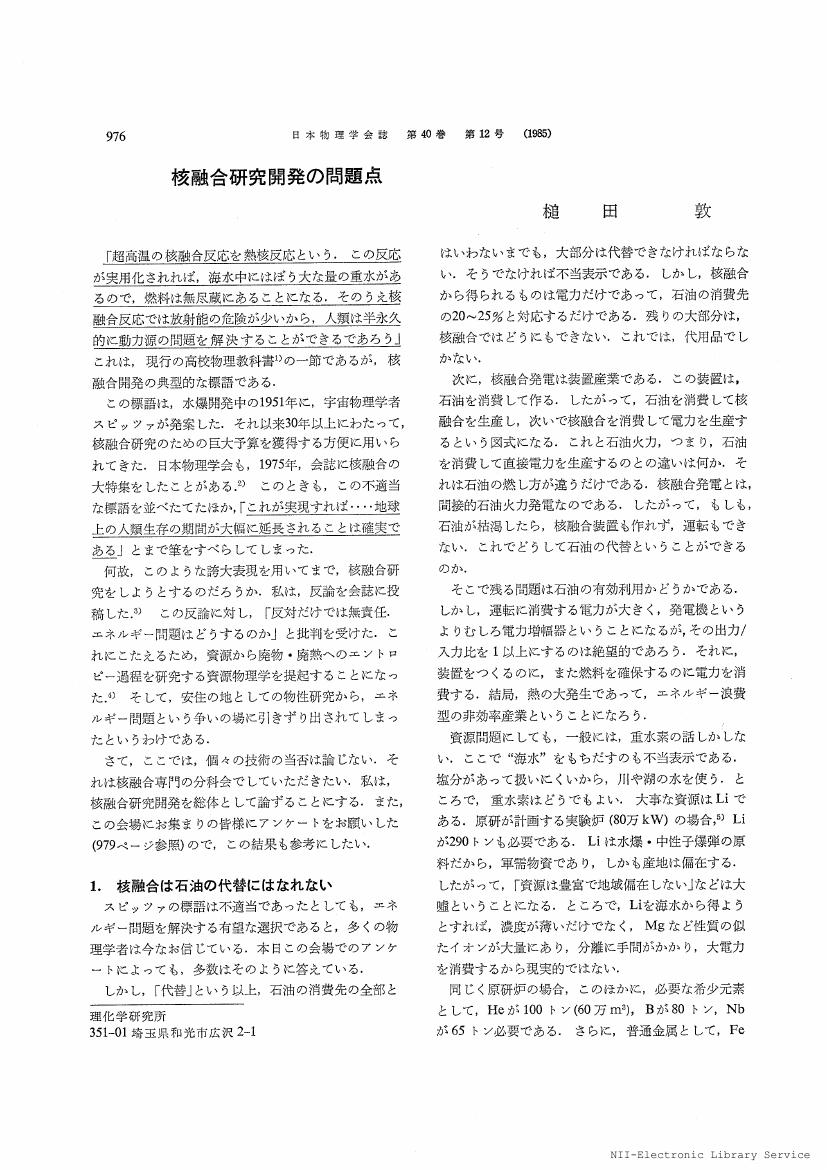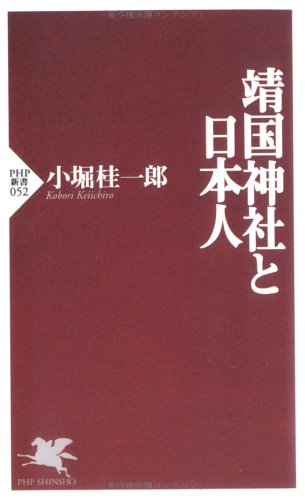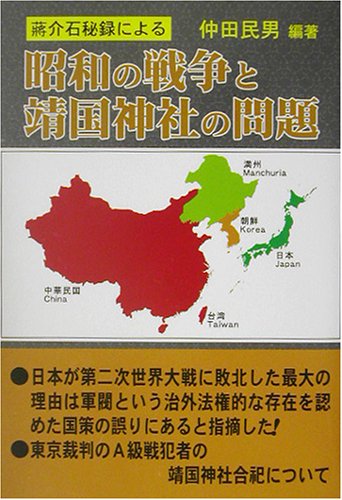1 0 0 0 OA 核融合研究開発の問題点
- 著者
- 槌田 敦
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.12, pp.976-980, 1985-12-05 (Released:2008-04-14)
- 参考文献数
- 10
1 0 0 0 OA 小児期の口臭に関する調査― 口腔内状態とVSCレベルの関連性について―
1 0 0 0 ヒトクイバエによるハエ症の1例
- 著者
- 中川 有夏 田嶋 佐妃 浅井 純 竹中 秀也 加藤 則人 山田 稔
- 出版者
- 日本皮膚科学会大阪地方会・日本皮膚科学会京滋地方会
- 雑誌
- 皮膚の科学 (ISSN:13471813)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.6, pp.415-420, 2014 (Released:2015-05-02)
- 参考文献数
- 36
47歳,女性。ウガンダに渡航して7日目に右前腕屈側にそう痒を伴う紅色丘疹が出現した。帰国後,紅色丘疹が増加したため渡航20日目に近医皮膚科を受診した。副腎皮質ステロイド含有軟膏の外用を開始したが,右肩と腰部の紅色結節が増大し疼痛を伴うようになったため,渡航24日目に当院を受診した。数日後紅色結節の中心に虫体を認め,局所麻酔下に4匹の虫体を摘出した。虫体はクロバエ科のヒトクイバエの3齢幼虫と同定した。摘出1ヶ月後,潰瘍は上皮化し,その後症状の再燃は認めていない。ヒトクイバエは衣服や布団などに付着した虫卵を介して寄生する。寄生を予防するためにはヒトクイバエの生息地域への渡航後は衣服にアイロンをかけることが重要であり,ハエ症を疑った際には,身近な人の渡航歴も聴取する必要があると考えた。(皮膚の科学,13: 415-420, 2014)
- 著者
- 西山 侑汰 名頭薗 亮太 辰見 康剛
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.4, pp.595-599, 2021 (Released:2021-08-20)
- 参考文献数
- 24
〔目的〕肩関節痛の既往歴を有する大学女子ソフトボール選手の肩関節外旋および内旋筋力と関節可動域の特徴について明らかにすることを目的とした.〔対象と方法〕大学女子ソフトボール選手23名を対象にした.肩関節痛既往群と健常群で肩関節外旋および内旋の等尺性筋力と関節可動域を両群間で比較した.〔結果〕利き手/非利き手の肩関節内旋可動域は,肩関節痛既往群の方が健常群よりも有意に低値を示した.〔結語〕肩関節痛の既往歴を有する大学女子ソフトボール選手は,肩関節内旋可動域が低値を示す特徴があった.
1 0 0 0 OA 臨界次元という概念はゲージによっては定義できない(放談室)
- 著者
- 中西 襄 阿部 光雄
- 出版者
- 素粒子論グループ 素粒子論研究 編集部
- 雑誌
- 素粒子論研究 (ISSN:03711838)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, no.1, pp.8-10, 1993-10-20 (Released:2017-10-02)
1 0 0 0 良寛だより : 新潟県良寛会会報
- 著者
- 新潟県良寛会 [編集]
- 出版者
- 新潟県良寛会
- 巻号頁・発行日
- 1988
1 0 0 0 蒋介石秘録による昭和の戦争と靖国神社の問題
1 0 0 0 OA 長期在院中の統合失調症患者における3 年後の身体機能,薬剤,転倒の比較
- 著者
- 辻 陽子 明﨑 禎輝 勝村 仁美 原 臣博 澤下 佑紀 垣崎 仁志 森 耕平 由利 禄巳 野村 卓生 平尾 文雄
- 出版者
- 保健医療学学会
- 雑誌
- 保健医療学雑誌 (ISSN:21850399)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.1, pp.38-44, 2021-04-01 (Released:2021-04-01)
- 参考文献数
- 41
要旨 本研究では,在院中の統合失調症患者の3 年後の身体機能,抗精神薬投与量,転倒回数の変化を調査することにより,身体機能に対する介入の必要性について検討することである.対象者は統合失調症患者12 名(男性6 名,女性6 名)であった.年齢は64.2±5.6 歳であった.除外規定としては,車椅子レベルの者,精神疾患による認知機能障害により説明の理解が困難な者,脊椎損傷など整形疾患が原因でADL が低下している者とした.調査は2014 年8 月,2017 年9 月にそれぞれ実施した.調査項目はBMI,筋力(30 秒椅子立ち上がりテスト),バランス能力(開眼・閉眼片脚立位時間,Functional reach test,Timed up and go test),柔軟性(長座位体前屈距離),歩行速度(10m最大歩行速度),抗精神薬投与量,転倒回数であった.統計解析はWilcoxon の符号付き順位検定,対応のあるt 検定を用い分析した.結果,30 秒椅子立ち上がりテストは,初回平均17.4±4.5 回から3 年後には平均13.0±4.8 回へと,開脚片脚立位時間は,初回平均 17.0 ±18.0 秒から3 年後には平均7.7±7.1 秒へと有意に低下した (p<0.05).その他の項目に有意差は認められなかった.在院中の統合失調症患者は,3 年間の経過で,特に下肢筋力と静的バランス能力が低下していることが明らかになった.これらから,身体機能の維持・改善への介入が求められる.
1 0 0 0 OA 分光・偏光イメージング技術による皮膚のシミ・微小循環の観察
- 著者
- 前田 憲寿
- 出版者
- 日本医用画像工学会
- 雑誌
- Medical Imaging Technology (ISSN:0288450X)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.1, pp.3-10, 2012 (Released:2012-02-22)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 2
肌の見た目や肌表面の状態は,肉眼やマイクロスコープで見れば明らかである.しかし,より詳細に皮膚の状態を観察するためには,何らかの方法で皮膚の特徴を抽出して解析する技術が不可欠である.本稿では,美容皮膚科や機能性化粧品分野において有用な分光・偏光イメージング技術を用いてシミと微小循環血流の状態を画像表示して解析する方法について紹介する.紫外線または青緑色光を利用して皮膚を撮影し,さらに独自の成分解析法を適用することによって,メラニンやヘモグロビンなどの光吸収成分の分布を画像表示することができる.たとえば,紫外線ストロボを用いると,シミの状態を解析することができ,皮膚に青緑色光を入射させることで毛細血管網の状態を解析することが可能である.微小血管観察装置を用いて頭皮を観察したところ,毛髪の多い部位には微小循環(毛細血管)が観察されたが,毛髪が少ない部位には微小循環はほとんど観察されなかった.
1 0 0 0 OA 文芸を介した連帯 -現代日本における「読書会」の展開
- 著者
- 安川 和貴
- 出版者
- 早稲田大学大学院社会学院生研究会
- 雑誌
- ソシオロジカル・ペーパーズ (ISSN:1340721X)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.77-84, 2020-02-26
1 0 0 0 OA 演技指示の工夫が与える音声表現への影響 : 表現豊かな演技音声表現の獲得を目指して
- 著者
- 宮島 崇浩 菊池 英明 白井 克彦 大川 茂樹
- 出版者
- 日本音声学会
- 雑誌
- 音声研究 (ISSN:13428675)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.3, pp.10-23, 2013-12-30 (Released:2017-08-31)
This paper explains the procedure to enhance the expressiveness in acted speech. We designed our own "format of acting script" referring to the theory of drama and created 280 acting scripts. We presented these acting scripts as acting directions to three actresses and collected 840 speech data. For comparison, using typical emotional words as acting directions, we also collected 160 speech data from each actress. Then, we compared tendencies of various features of each data type and each speaker and found that our acting scripts are effective on the enhancement of expressiveness in acted speech psychologically/acoustically.
1 0 0 0 秋田に於ける昭和時代の農業と吉田三郎氏に関する研究
- 著者
- Donald・C Wood
- 出版者
- 秋田大学
- 雑誌
- 基盤研究(C)
- 巻号頁・発行日
- 2018-04-01
I have made considerable progress over the last two years. The core project of my research - the translation of Yoshida Saburo's 1938 book - is nearly complete. About 75% of it has been typed, and about the same percentage of the illustrations have been prepared (including the original photographs). However, because it is an extremely complex document - illuminating the life and community of a small-scale subsistence farmer and his family through a sequence of daily entries spanning the period from March of 1935 to March of the following year - there is still much work to do. During the final year, more typing will be done, and the final work on the illustrations and proofreading and editorial adjusting will be completed. Also during the final year, a publisher will be sought for the English language version.
- 著者
- 伊藤 嘉浩
- 出版者
- 日本経営学会
- 雑誌
- 日本経営学会誌 (ISSN:18820271)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, pp.87-99, 2014-12-10 (Released:2017-08-01)
- 被引用文献数
- 1
The purpose of this paper was to shed light on the processes through which companies formulate superior business models by conducting a case-study analysis of Askul, a new business launched by Plus Corporation that is well known for having a superior business model. Another aim was to help Japanese companies to rebuild their organizational capabilities by learning about the remarkable success story of a new business that was launched before such concepts such as resultism and individualism had taken root. For the paper, people involved with the new business at the time were interviewed, and it was found that the Askul's business-model creation process was as follows: (1) learn from the failures of other businesses in their early stages, (2) craft a basic analytical plan in advance, (3) craft a detailed analytical plan in advance, (4) verify viability by launching the business on a small scale, (5) devise an emergent business model, (6) obtain approval for and implement the emergent business model despite opposition from inside and outside the company, and (7) get into the black and expand the business. Of these steps, (1) and (5) were discovered in the course of producing this paper; they had not been proposed in previous studies. One of the main achievements of this paper was that it showed that the emergent business model contributed to the creation of the eventual business model and the success of the business. This case analyzed for this paper also showed that the absence of excessive resultism or individualism, which is often seen at Japanese companies nowadays, was important in the creation of the business model.
1 0 0 0 OA 「人に教えるために書く文章」の書き方に影響を及ぼした理由および契機の分析
- 著者
- 野口 聡 田中 雄也
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.Suppl., pp.45-48, 2021-12-20 (Released:2022-02-02)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1
本研究では,人に教えるために書く活動において,その文章を書く方略を変えた理由や契機を明らかにする.その前提として,初期と19ヶ月後における書くための方略の出現単語の傾向から分析した.その結果,初期と19ヶ月の時点に差が見られた.そのため書くための方略を変えた理由や契機の自由記述をKJ 法で分類し,4つのカテゴリが生成された.「評価の意識」は学習評価に関わるもの,「失敗の予期や経験」「他の参考」は試行錯誤によるもの,「学びの気づき」は取り組むことの気づきに関わるものであり,それらによって書く方略を変化させたことが示唆された.
1 0 0 0 OA 電気的交互脈-われわれの経験した6症例について
- 著者
- 村田 和彦 吉田 忠義 鈴木 忠 河合 恭広 金沢 紀雄 高瀬 真一 佐々木 豊志 塩原 雄二郎 乾 迪雄 土屋 純
- 出版者
- The Kitakanto Medical Society
- 雑誌
- 北関東医学 (ISSN:00231908)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.5, pp.317-322, 1980-12-20 (Released:2009-11-11)
- 参考文献数
- 17
電気的交互脈は比較的まれな心電図異常であり, その正確な頻度は不明であるが, 心電図検査10,000回におよそ5回程度みられるものであるといわれている.本所見は通例心異常のあるものに認められ, その出現はしばしば心膜液貯留の診断の手がかりとなるが, きわめてまれながら, 他に心異常のない症例に電気的交互脈の出現をみたとの記載もある.以下, われわれが最近約15年間に経験した6症例を報告する.
1 0 0 0 OA 異型適合血を用いたAB型患者に対する緊急大量輸血の問題点
- 著者
- 中川 博文 東 俊晴 松原 由紀 白石 成二 中尾 正和 山崎 京子
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.2, pp.334-338, 2008 (Released:2008-04-16)
- 参考文献数
- 10
厚生労働省の 「輸血療法の実施に関する指針」 が2005年9月に改定された後, AB型患者の大量出血に対して異型適合血輸血を考慮した2症例を経験した. 緊急輸血に携わる医療従事者は, 異型適合血輸血の適応に関する認識を新たにするとともに, 危機的出血に際して迅速に適合血の選択を確認できるよう小冊子を配置し, 定期的な勉強会を開催するなど, 速やかな緊急輸血実施のための院内体制の整備に努める必要があると考えられた.
1 0 0 0 OA Mato細胞の形態と機能 ―特に病態時における―
- 著者
- 間藤 方雄
- 出版者
- 日本蘇生学会
- 雑誌
- 蘇生 (ISSN:02884348)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.13-22, 1998-04-20 (Released:2010-06-08)
- 参考文献数
- 14
脳細血管には生理的条件下において, マクロファージ系の細胞 (間藤細胞: M細胞) が纏絡する。同細胞は血管周囲隙にあり, 水解酵素に富み蛍光性を有する顆粒を多数含み, 血管・脳室内に投与された蛋白, 脂質を効率よく摂取する細胞である。本稿では間藤細胞の一般的な性質に加え, 病態時, 特に脳に凍結傷害を与えた場合の間藤細胞の浮腫性変化, LPSによって刺激した際の変化とミクログリアとの関係, 再灌流実験における同細胞の退行性変化等について述べた。再灌流実験における皮質・海馬にみられる神経細胞変性と本細胞との関連については現在研究中である。