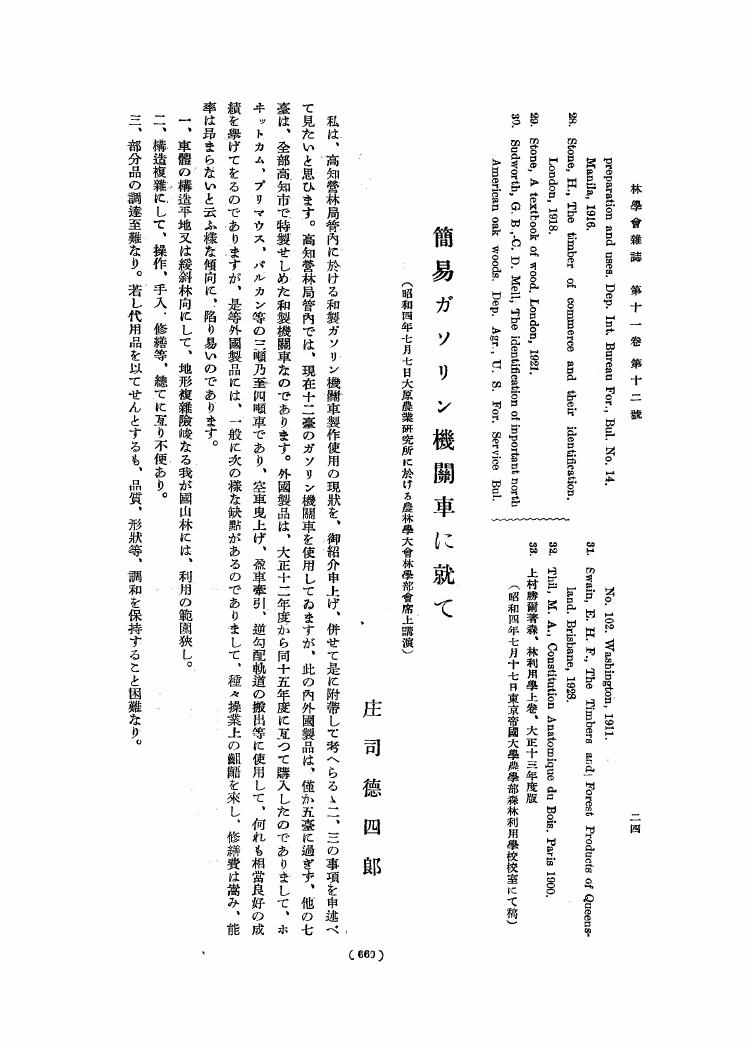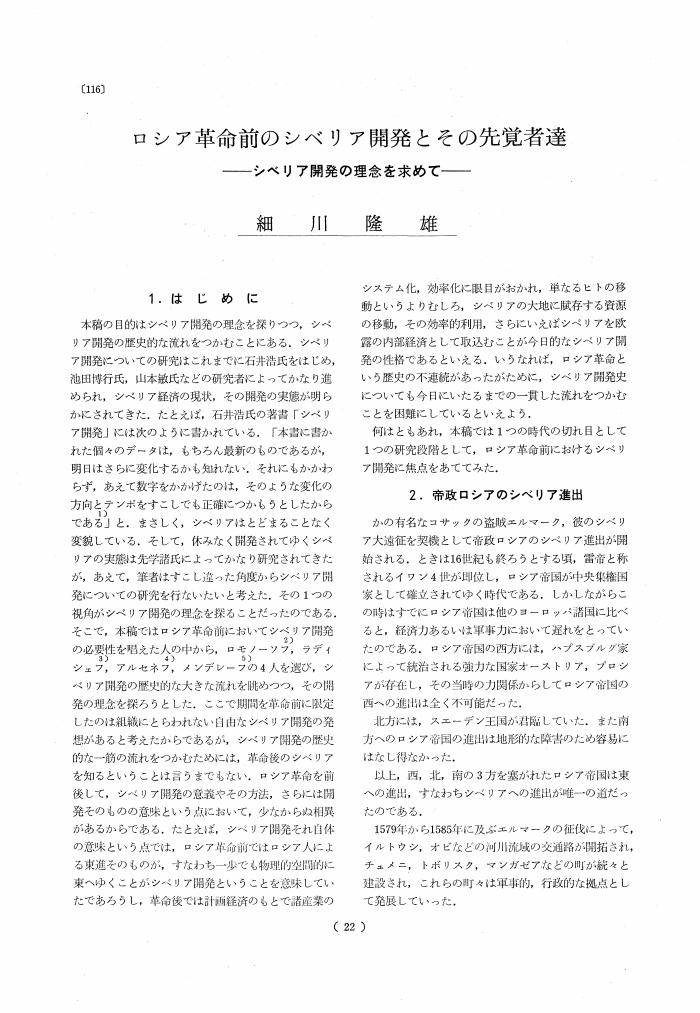2 0 0 0 OA 三草山のコナラ属堅果を食害する鱗翅類
- 著者
- 大野 泰史 広渡 俊哉 上田 達也
- 出版者
- 日本鱗翅学会
- 雑誌
- 蝶と蛾 (ISSN:00240974)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.2, pp.99-107, 2000-03-31
- 被引用文献数
- 1
Fauna of Lepidoptera that infests acorns of Quercus acutissima, Q. aliena and Q. serrata was investigated in Mt Mikusayama forests of Osaka Prefecture, Japan in 1997. Quercus acorns were infested by a total of 13 lepidopterous species, representing 7 families.
2 0 0 0 OA 簡易ガソリン機關車に就て
- 著者
- 庄司 徳四郎
- 出版者
- 日本森林学会
- 雑誌
- 林學會雑誌 (ISSN:21858187)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.12, pp.660-669, 1929-12-10 (Released:2009-02-13)
- 著者
- 北方 雅人
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ベンチャ- (ISSN:02896516)
- 巻号頁・発行日
- no.278, pp.104-107, 2007-11
青果物を大きさや品質によって選別する選果機の最大手。高い技術力で業界をけん引してきた。「お家騒動」で創業家が退き、メーンバンクから社長が3代にわたって送り込まれる。市場縮小の中、売り上げの確保を優先し、リストラやコスト削減が後手に回った。監査法人の交代がきっかけで不明朗な在庫評価が発覚し、既に瀕死状態だった会社を直撃した。
2 0 0 0 OA ロシア革命前のシベリア開発とその先覚者達
- 著者
- 細川 隆雄
- 出版者
- 地域農林経済学会
- 雑誌
- 農林業問題研究 (ISSN:03888525)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.3, pp.116-123, 1976-09-25 (Released:2011-09-05)
- 参考文献数
- 9
2 0 0 0 IR 図書館・情報学諸領域における「知識」の位置付け
- 著者
- 武者小路 澄子
- 出版者
- 三田図書館・情報学会
- 雑誌
- Library and information science (ISSN:03734447)
- 巻号頁・発行日
- no.52, pp.1-42, 2004
原著論文Knowledge' is closely related to the notion of 'information', which is one of the central notions in Library and Information Science, and is itself one of the most important notions in this field. In order to study how the notion 'knowledge' is situated in Library and Information Science, various articles and books which involve this notion were selected from reference books and textbooks in Library and Information Science. In examining those articles andbooks, 10 research areas which involve the notion 'knowledge' were selected. Based on the ethnographic methods, such as 'coding' and categorization, each of the articles and books was coded as to what kind of notion is assumed under the term 'knowledge', and how it is used. This sequence of coding produced 5 main analytical points to examine the notion and usage of 'knowledge' in each of the research areas. These analytical points are (1) how the term 'knowledge' is related with the term 'information', (2) how far it is generalized, (3) whether it is held as 'being personal' or as 'being shared', (4) in what way it is evaluated, and (5) where it is conceptually located.The notion and usage of 'knowledge' in each of the research areas were then explicated through these analytical points, and how 'knowledge' is situated in Library and Information as a whole was further inferred based on the analysis. Finally, some unexplored aspects of this notion are pointed out, and some direction within the study of 'knowledge' is suggested for Library and Information Science.
2 0 0 0 IR 経営者リーダーシップと組織戦略 : ジャスダック上場企業の調査から
- 著者
- 加藤 茂夫
- 出版者
- 専修大学経営研究所
- 雑誌
- 専修経営研究年報 (ISSN:03858936)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, pp.1-29, 2006-03-20
- 著者
- 甲斐 知彦 鈴木 博和 小井出 桂祐子 松本 芳孝 今井 正裕 Tomohiko Kai Hirokazu Suzuki Keisuke Koide Yoshitaka Matsumoto Masahiro Imai
- 雑誌
- スポーツ科学・健康科学研究 (ISSN:13440349)
- 巻号頁・発行日
- no.11, pp.11-18, 2008-03-31
2 0 0 0 IR 啓蒙時代における愛と市民
- 著者
- 菅 利恵 SUGA Rie
- 出版者
- 三重大学人文学部文化学科
- 雑誌
- 人文論叢 = Bulletin of the Faculty of Humanities and Social Sciences,Department of Humanities (ISSN:02897253)
- 巻号頁・発行日
- no.32, pp.29-42, 2015
私的な愛の関係性に与えられる文化的な位置づけや意味は、近代化の過程で大きく変わったとされる。この変化と近代的な市民社会の発展との関連性は、一見して思われるほどに自明なわけではない。新しい愛の観念が広められたドイツ語圏の18世紀において、市民社会の発展ということはあくまでも「文化的な現象」であり、政治的、経済的な実力を持った市民層はまだ形成されていなかった。また「市民的」という言葉に込められる意味は様々であり、18世紀における愛の観念の変化には「市民的な」価値意識から明らかに逸脱するようにも見える部分もあった。このように愛をめぐる言説と市民社会との関係には簡単に整理のつかない部分があるため、従来の研究では、この関係自体が否定されたこともある。本稿は、そうした研究の流れをふまえて、近代化の中で生まれた新しい愛の言説における「市民的なもの」をあらためて検証しなおそうとする試みである。啓蒙時代における愛の観念の変化を、近代初期の社会思想との関連性において論じることによって、私的な愛をめぐる言説が、市民社会の形成過程においてどのような意味と役割を持ったのかを明らかにする。
2 0 0 0 OA 作用素環の表現論における双対性
- 著者
- 竹崎 正道
- 出版者
- 一般社団法人 日本数学会
- 雑誌
- 数学 (ISSN:0039470X)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.4, pp.208-215, 1967-03-01 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 19
2 0 0 0 文体及びツイート付随情報を用いた乗っ取りツイート検出
- 著者
- 上里和也 奥谷貴志 浅井洋樹 奥野峻弥 田中正浩 山名早人
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 研究報告データベースシステム(DBS)
- 巻号頁・発行日
- vol.2013, no.21, pp.1-8, 2013-11-19
Twitter のユーザ数が増加を続ける一方で,不正に ID 及びパスワードを入手され,他人によってツイートを投稿される被害が増加している.これに対し,我々はアカウント乗っ取りによって投稿されるメッセージの一部であるスパムツイートの検出手法を提案し,8 割程度の正答率を得ている.同手法では特定の単語が含まれているスパムツイートを検出対象とし,検出の有効性を示している.本研究では同検出対象を広げ,アカウントの所持者以外が投稿したツイート全体を 「乗っ取りツイート」 として定義し,これを検出する手法を提案する.また本研究では,以前提案した手法に対してパラメータの再調整を行うと同時に,頻繁に用いるハッシュタグの種類及びリプライを送る相手が各アカウントにおいて特徴的であることを利用し,F 値の向上を図った.100 アカウントに対して評価実験を行った結果,我々が提案している従来手法と比較し,F 値を 0.1984 向上させ F 値 0.8570 を達成した.
2 0 0 0 OA 歩行を模擬した足底振動刺激による身体近傍空間の拡張
- 著者
- 雨宮 智浩 池井 寧 広田 光一 北崎 充晃
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本バーチャルリアリティ学会
- 雑誌
- 日本バーチャルリアリティ学会論文誌 (ISSN:1344011X)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.4, pp.627-633, 2016 (Released:2017-02-01)
- 参考文献数
- 26
The representation of the peripersonal space is remapped by body action such as integrating tactile stimuli from the body's surface with multisensory stimuli presented within a limited distance from the body. Previous study showed that boundaries of the peipersonal space extend while walking with listening to a looming sound, but it is unclear whether the boundaries change when a sensation of walking is induced with no physical body motion. Here, we examine the change using a technique to induce a sensation of pseudo-walking by presenting vibrotactile stimuli of recorded footsteps sound at the feet soles. Experiments were performed to compare the reaction times to detect a vibrotactile stimulus on the chest with listening to a looming sound toward the body, taken as a proxy of the peripersonal space boundary. Experimental evaluations showed that the peripersonal space seems to expand when a sensation of pseudo-walking was clearly induced.
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.1028, pp.44-48, 2000-02-14
三菱商事と資本・業務提携の合意を交わした直後の1月下旬、ローソンの藤原謙次社長は、欧米の機関投資家に上場計画を説明するため渡航した。 「欧米の機関投資家は、Eコマース(電子商取引)の拠点となる日本のコンビニエンスストアに強い関心を示している。
2 0 0 0 IR 大学における教育方法の改善・開発(<特集>大学教育の改善・FD)
- 著者
- 鈴木 克明
- 出版者
- 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.3, pp.171-179, 2012
- 被引用文献数
- 1
本稿では,大学における教育方法の改善・開発について,教育設計学に依拠しながら解説した.まず,出入口と三層構造で大学を俯瞰し,教育設計学の立場を教育工学研究への前提として整理した.次に,大学の授業改善の動向をFDに言及しながら概観し,授業以外の学習環境構築の先進例として米国における学生支援の動向を紹介した.最後に,大学教育に情報通信技術を利用して取り組む際の要素を整理した「サンドイッチモデル」を提案した.
- 著者
- 村上 正行 山田 政寛
- 出版者
- 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.3, pp.181-192, 2012
本論文では,FDに関する歴史や政策の動向,定義,推進主体などについて説明した上で,大学教育・FDに関する研究について調査,分析を行った.授業,カリキュラム,組織的なFDの3つのレベルに分類し,紹介した.そして,教育工学研究者が大学教育やFDに対してどのような役割を担うべきか,今後どのような研究を行なっていくべきか,について検討した.教育工学研究者は,大学教育やFDにおける現代の問題について,教育政策も踏まえながら,実践を通した研究を行うことが求められていると言え,今後,大学教育の改善やFDに関する研究を発展させていくことが必要であると考えられる.
2 0 0 0 OA ビジネス・ミーティングにおけるトピックの展開 : 課題決定場面を中心とした韓日の違い
- 著者
- 李 志暎
- 出版者
- お茶の水女子大学
- 雑誌
- 人間文化論叢 (ISSN:13448013)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.291-303, 2006
Based on a preceding study that a lot of patterns circulated throughout the development of a topic in a business meeting between Japanese, tending to put off a conclusion, this study provides a comparative analysis with a meeting between Koreans. As a result, the big difference with J (Japanese) was scarcely observed to be about the number of patterns for all topics. However, a difference became clear for the process of a topic reaching a decision. As for J, the ratio of circulation topics emerged highly "before decision", and for K (Koreans), "after decision". This suggested that the process before decisions were made were different between the two groups. In this way it is thought that the expectations of Koreans engaged in business towards making a decision rather than discussing related topics are different from that of Japanese. Thus, this may be another factor that contributes to the perception that "the Japanese do not give conclusions".
- 著者
- 武田 敬
- 出版者
- 公益社団法人日本薬学会
- 雑誌
- 藥學雜誌 = Journal of the Pharmaceutical Society of Japan (ISSN:00316903)
- 巻号頁・発行日
- vol.117, no.6, pp.368-377, 1997-06-25
- 参考文献数
- 46
- 被引用文献数
- 2
This review describes a highly efficient [3+2] annulation based on the Brook rearrangement for functionalized cyclopentenols, which we have recently developed, and its application to the synthesis of natural products.
2 0 0 0 ディジタルオシロスコープDLシリーズ
- 著者
- 横河電機 (株) 測定器事業部
- 出版者
- The Society of Instrument and Control Engineers
- 雑誌
- 計測と制御 (ISSN:04534662)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.1, pp.96-97, 1990