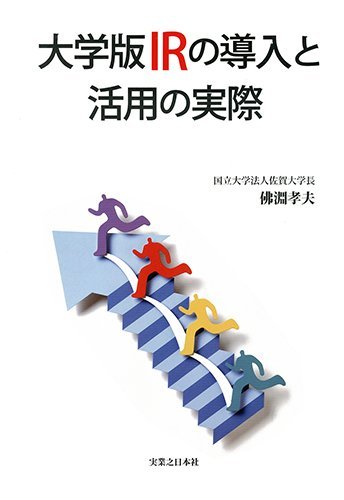- 著者
- 青木 弘 安斉 博 奥村 真悟 河本 知和
- 出版者
- 一般社団法人日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学會誌 (ISSN:00214728)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.716, 1978-07-05
- 著者
- 石神 正浩 依田 潤 岩井 鶴二 堀江 忠男
- 出版者
- 一般社団法人日本物理学会
- 雑誌
- 秋の分科会講演予稿集
- 巻号頁・発行日
- vol.1966, no.4, 1966-10-11
2 0 0 0 IR 濱田庄司と朝鮮陶磁 ―個人作家としての美意識―
- 著者
- 裵 洙淨
- 出版者
- 関西大学大学院東アジア文化研究科
- 雑誌
- 文化交渉 東アジア文化研究科院生論集 (ISSN:21874395)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.21-42, 2015-11-01
東アジアの言語と表象Hamada Shoji (1894−1978) was a representative potter in Japan. He is usually regarded as a member of the mingei society together with Yanagi Muneyoshi(1889−1961), who was also the founder of the mingei (folk crafts) movement. Because of this, Hamada is often called a mingei artist. However Hamada preferred to be called a 'potter' rather than an artist. In other words, Hamada thought of himself as an individual potter influenced by the philosophy of the mingei movement. The aim of this study is to reveal the aesthetic sense of Korean ceramics through the point of view of mingei (folk crafts) and also by looking at a number of works by Hamada Shoji. Hamada often said "I found my way in Kyoto, started in Britain, learned in Okinawa, and grew up in Mashiko." However he also studied many of the forms and techniques of Korean ceramics, especially Punchong ware with its iron-painted on brushed white slip (hakeme), and the faceted jar (mentori). Furthermore, Hamada thought that Korean ceramics were composed of crafts, potters, and lives. As a result of his study of Korean ceramics, Hamada found an aesthetic of freedom and developed his own sense of modern beauty. In conclusion, Korean ceramics contain the ultimate aesthetic, with which Hamada, Yanagi and the mingei society shared.
2 0 0 0 OA 1984年3月6日 鳥島近海地震
- 著者
- 強震観測事業推進連絡会議
- 出版者
- 独立行政法人防災科学技術研究所
- 雑誌
- 強震速報
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.1-"18-1", 1984-04-28
- 著者
- 下川 理英
- 出版者
- 法政大学
- 雑誌
- 法政大学大学院紀要 (ISSN:03872610)
- 巻号頁・発行日
- no.56, pp.47-55, 2006
2 0 0 0 高流動高じん性モルタルを用いた上面増厚工法の開発
- 著者
- 早川 智浩 富井 孝喜 青木 茂 古城 誠
- 出版者
- Japan Concrete Institute
- 雑誌
- コンクリート工学 = Concrete journal (ISSN:03871061)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.4, pp.338-344, 2012-04-01
- 参考文献数
- 13
上面増厚工法の増厚材に高流動高じん性モルタルを用いた新しい上面増厚工法(タフスラブ・ラピッド工法)を開発した。本工法は,従来工法である鋼繊維補強コンクリートの課題であった機械設備のコンパクト化,充てん性および一体性の確保,薄層施工,鋼繊維による防水層への影響を解決した。本稿では,新しく開発した増厚材の性質およびその増厚材を用いて実施した施工性能確認試験とその結果について述べる。
- 著者
- 佐藤 洋一
- 出版者
- 都市出版
- 雑誌
- 東京人 (ISSN:09120173)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.12, pp.82-85, 2016-09
- 著者
- 野口 由里子
- 出版者
- 法政大学大原社会問題研究所
- 雑誌
- 大原社会問題研究所雑誌 (ISSN:09129421)
- 巻号頁・発行日
- no.694, pp.27-40, 2016-08
2 0 0 0 防衛技術アーカイブス 戦争と灯台
- 著者
- 粟井 次雄
- 出版者
- 防衛技術協会
- 雑誌
- 防衛技術ジャーナル (ISSN:09198555)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.8, pp.29-33, 2016-08
- 著者
- 西田 善行
- 出版者
- 法政大学大原社会問題研究所
- 雑誌
- 大原社会問題研究所雑誌 (ISSN:09129421)
- 巻号頁・発行日
- no.694, pp.14-26, 2016-08
- 著者
- 清水 善仁
- 出版者
- 法政大学大原社会問題研究所
- 雑誌
- 大原社会問題研究所雑誌 (ISSN:09129421)
- 巻号頁・発行日
- no.694, pp.3-13, 2016-08
- 著者
- 土井 隆義
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- no.38, pp.78-96, 2013-10-15
日本の少年犯罪の摘発件数は,2003年から減少を続けている.分母に少年人口を置いても,それは同様である.本論考は,この現象に寄与していると考えられる要因のうち,統制側の摘発態度の変化の可能性については保留し,少年側の心性の変化の可能性から説明を試みたものである.犯罪社会学において,逸脱主体の動機形成に着目した犯罪原因論には,伝統的に大きく2つの流れがある.1つは社会緊張理論であり,もう1つは文化学習理論である.そこで本論考は,この両者の視点から現在の日本を観察し,それらの理論が自明の前提としていた社会状況が,いまや見られなくなっていることを明らかにした.逸脱行動は,社会緊張がもたらすアノミーに晒されることによってノーマルな日常世界から押し出され,逸脱文化への接触とその学習によって逸脱的な下位世界へと引き込まれることで促進される.そうだとすれぼ,社会的緊張が弛緩し,また逸脱文化も衰退してくれば,それだけ逸脱行動への促進力は削がれることになる.それが現在の日本の状況である.現在,そのような状況が見られるのは,すでに日本が前期近代の段階を終え,後期近代の黎明期を迎えているからである.そして,この時代の特徴の一つといえる再埋め込みへの心性から派生した新たな宿命主義が,この現象をさらに背後から促進している.犯罪の多くは不満の発露であり,不満の多くは希望の裏返しだからである.
2 0 0 0 モルディブにおけるインド洋津波の現地調査
- 著者
- 藤間 功司 鴫原 良典 富田 孝史 本多 和彦 信岡 尚道 越村 俊一 藤井 裕之 半沢 稔 辰巳 正弘 折下 定夫 大谷 英夫
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 海岸工学論文集 (ISSN:09167897)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, pp.1381-1385, 2005
- 被引用文献数
- 2
2004年12月26日に発生したインド洋津波は, 震源から2, 000km離れたモルディブでも人的・物的に大きな被害をもたらした. そこでモルディブで現地調査を行った結果, モルディブの痕跡高が0.6-3.4m程度であること, リーフが発達している場所でも必ずしも痕跡高が小さくなっているわけでないこと, また南マレ環礁で複雑な流れが観察されており, 環礁内の津波の挙動が複雑であることなどが分かった. モルディブの津波に対する安全性を高めるには強固な構造物や人工地盤などの整備が必要である.
2 0 0 0 OA 失行を中心に多彩な認知機能障害を呈した脳梗塞症例に対するリハビリテーション
- 著者
- 鈴村 彰太 大沢 愛子 植田 郁恵 森 志乃 近藤 和泉 前島 伸一郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本脳卒中学会
- 雑誌
- 脳卒中 (ISSN:09120726)
- 巻号頁・発行日
- pp.10430, (Released:2016-09-15)
- 参考文献数
- 20
失行は日常生活活動(activities of daily living: ADL)に大きな影響を及ぼすが,症候が複雑で行為の誤り方に個別性・多様性が存在するためリハビリテーション手法の確立は困難で,その障害や治療に関する詳細な検討もほとんどない.我々は左頭頂側頭葉のアテローム血栓性脳梗塞で,ごく軽度の右片麻痺と感覚障害に加え,観念失行・観念運動失行・肢節運動失行を呈した82 歳女性を経験した.特に食事動作に関し,右手では困難な動作をまず左手で実施し,その後道具を右手に持ち替える方法を取り入れ,誤りなし学習を徹底したところ,動作の自立を果たした.本症例の改善機序として,左上肢の使用により右上肢の体性感覚が補われたことで,誤りの認知や道具使用に関する意味概念への到達が可能となり,正しい運動プログラムの惹起が促進されて,右手の運動学習につながったものと推察された.
2 0 0 0 バーチャルバンド支援システムの開発
- 著者
- 山下 直人 伊藤 淳子 宗森 純
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告グループウェアとネットワークサービス(GN) (ISSN:09196072)
- 巻号頁・発行日
- vol.2008, no.31, pp.97-102, 2008-03-21
好きな曲目が演奏でき,かつ,セッションできるギターの魅力を体験でき,さらにエアギターのような自由な動きができる,"バーチャルバンド支援システム"を開発した.本システムは入力にテンキーパッドとジャイロマウスを使用する.数字表記の楽譜による読譜の支援に特徴がある.他のギターシミュレータのインターフェースの比較実験と,ネットワークを介したセッションの実験を行った.比較実験の結果,他のギターシミュレータと比べて楽しく,操作,楽譜がわかりやすいということがわかった.また,セッションの実験の結果,遅延が発生するが,1人のときよりも楽しいということがわかった.We have developed a virtual band support system. We can play favorite music and play coordinately by the system. We can also play freely like a "virtual guitar". The input of the system consists of a ten-key pad and a gyro mouse. The reading music with the score of the number notation is one of the characteristic of the system. We performed a comparison experiment about the interface of guitar simulators and a session experiment through the network. The results of the experiments indicated that the system was superior to other guitar simulators from the viewpoint of pleasure, operation and reading score. As a result of experiment of the session, a delay occurred, but we understood that we were more pleasant than a stand alone experiment.
- 著者
- 勝山 康晴
- 出版者
- 早川書房
- 雑誌
- 悲劇喜劇 (ISSN:13425404)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.7, pp.33-35, 2007-07
- 著者
- 山下 松蔵
- 出版者
- 國學院短期大学
- 雑誌
- 國學院短期大学紀要 (ISSN:09185275)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.A109-A141, 2003-03-15
2 0 0 0 大学版IRの導入と活用の実際
18年度の成果として、以下の点が挙げられる。まず、研究テーマに基づく先行研究を体系的に理解することを目指した。つまり(1)これまでのインドにおける女性・フェミニズム運動についての基礎文献をたどり、(2)ダリットや非バラモン主導による解放運動について、歴史的背景とそのおおまかな流れを把握した。これら二つの流れをたどりながら、そこから浮上してきた幾つかの事例から、"主流派"女性運動とダリット女性両者の接点についての考察を深めることができた。そのうちの一事例として、1970年代末、マハーラシュトラ州オーランガバードを起点として広まりをみせた、通称Namantar運動(大学改名要求運動)が挙げられよう。この運動は70年代末以降、ダリットがマラートワーダー大学からDr.ババサヘーブ・アンベードカル・マラートワーダー大学へと大学名の変更を要求したことがきっかけとなり、その後マハール・カーストを主とした非ダリットとダリットとの政治的対立構造が顕著となっていった。この運動については多くが男性政治家・運動家によって記されているが、なかでもダリット女性および非ダリット女性がこの運動をどう理解し、どのように関与したかについては未解明な部分が多い。したがって存在する数少ない資料を掘り下げ、また実際運動に関与した当事者(ダリットおよび非ダリット女性運動家、フェミニストら)に聞き取り調査をおこなった。その結果、この運動には実に多くの人々が賛同し、改名を擁護したことが明らかとなったが、特に草の根レベルにおいて多くの女性が果敢に参加したことについて、記録としてほとんど存在しないことや、賛同したダリット女性や非ダリット女性がいかに運動内で協働し合ったか、あるいはし合わなかったかについては、まだ十分に解明されてはいないことなどが明らかとなった。つまりのそ未解明な部分を明らかにするために、ダリット女性と非ダリット女性の両者の意識がせめぎあう場としてこの運動を位置づけ、それを起点に、当時から現在まで続いている両者の連帯、そして分裂について理解を深めようと試みた。この研究は現在も継続中であるが、2006年10月の日本南アジア学会にてその一部を発表した。今後も引き続き研究を続行させていく予定である。さらに、ダリット女性と非ダリット女性の意見の対立が際立つその他の事例にも注目しており(特に、異なるカースト女性のカースト別の議席配分について)、また近年起きている様々な女性運動家および女性団体での意見の相違についても事例を収集し、その分析を続行させている。これらについても今後も継続して研究を行っていく所存である。
- 著者
- 中田 正浩
- 出版者
- 奈良学園大学人間教育学部
- 雑誌
- 人間教育学研究 = Journal for humanistic education (ISSN:21889228)
- 巻号頁・発行日
- no.3, pp.155-166, 2015-12
As educational establishments of the early modern period, Shoheizaka Gakumon-jo for buke (samurai)education that was under the direct control of Edo bakufu, 'han-ko' (feudal domain schools) of each domain, andprivate schools and 'terakoya' (community schools) for general people were established. The education of Edo periodwas based on the educational thoughts and culture formed in 250-plus-years of Edo bakufu, and it is not the same asthe modern education of the West. However, the modern education was, in the rapid modernization driven by Meijigovernment after the Restoration, taking the western education as a model, but at the same time built on the foundationof the education of Edo era and its tradition. This article is to conduct research (May 22 – 24, 2015) on the existingelementary school architectures( eleven schools) in Nagano prefecture that were built directly after the 'school system'had been issued, and to overview the educational thoughts and culture of that time through collections of the materialsand interviews to the curators.