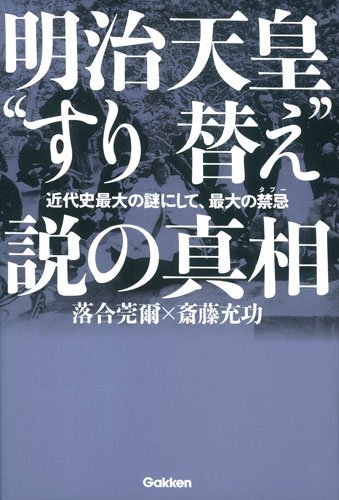1 0 0 0 OA 新型コロナに関連する疑似科学的言説への態度を規定する要因の分析
- 著者
- 山本 輝太郎 久保田 善彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本科学教育学会
- 雑誌
- 日本科学教育学会研究会研究報告 (ISSN:18824684)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.4, pp.23-26, 2022-03-27 (Released:2022-03-24)
- 参考文献数
- 13
新型コロナウイルスの世界的な流行によるいわゆる「コロナ禍」において,科学的根拠に乏しいとみなしうるさまざまな説(疑似科学的言説)も登場し,問題となっている.なかには「新型コロナワクチンを接種すると不妊になる」といった,それが蔓延することでより深刻な問題を引き起こしかねない説もあり,そうした説に傾倒する背景要因の究明は社会的な喫緊の課題であるといえる.本研究では,こうした新型コロナに関連する疑似科学的言説への態度に関わる背景要因の分析を行った.具体的には,新型コロナに関して科学的根拠に乏しいと思われる個別の説を収集,質問項目を作成したうえで,「科学に対する認識」や「新型コロナ以外の疑似科学的言説への態度」「科学知識」などとの関連性を検討した.クラウドソーシングを用いた調査を行った結果,新型コロナに関する疑似科学的言説への態度に対して,従来の疑似科学への態度や科学に対する認識,科学知識との一定の関連性が示された.これらの結果に基づき,科学に対する認識の次元にまで踏み込んだ教材開発およびその教育実践の重要性について提案したい.
- 著者
- 中川 毅
- 出版者
- 日本第四紀学会
- 雑誌
- 第四紀研究 (ISSN:04182642)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.1, pp.1-31, 2023-02-01 (Released:2023-02-21)
- 参考文献数
- 119
気候変動の地域による先行,遅延,あるいは同時性は,気候変動の因果関係を理解する上で,しばしばカギとなる情報を提供する.とくに,16〜10 cal. kyr BP頃に起こった晩氷期から完新世初期にかけての移行は,いくつかの急激な気候変動を含む上に情報も多いことから,気候変動の時空間構造を調べるためのターゲットとして理想的である.だが現実には,異なる地域の間で年代軸を精密に同期 (synchronise) させることは容易ではなく,気候変動のタイミング比較はほとんどの場合,仮説的な議論にとどまってきた.このことを踏まえ,本研究では福井県水月湖から新たに得られた花粉データ (n=510) および気候復元の結果について報告する.水月湖の放射性炭素データはIntCal20の主要構成要素であり,絶対年代はU/Th年代と互換性がある.水月湖のきわめて精密な年代軸,およびグリーンランドのアイスコアに含まれる宇宙線生成核種の研究の進歩により,水月湖とグリーンランド,またその他の多くの地域の精密な対比が可能になった.それによると,完新世および晩氷期亜氷期 (ヤンガー・ドリアス期に相当) の開始は,いずれも水月湖とグリーンランドの間で同時だった.ただし晩氷期亜間氷期 (ベーリング・アレレード期に相当) の開始については,水月湖がグリーンランドに200年ほど先行した.偏西風の双峰的 (bimodal) な移動は,東および南アジア (ひょっとすると西アジアも) において急激な変動を産み出す,「しきい値」 を含んだメカニズムとして重要だったかもしれない.大西洋においては,緯度方向の鉛直循環 (Antarctic Meridional Overturning Circulation: AMOC) のオン・オフの切り替わりが,より強力な 「しきい値」 メカニズムとして存在していた.アジアと大西洋のしきい値の高さが異なることで,両者の気候応答に数十年〜数百年規模の遅延が生じた.また,どちらか一方だけが応答した場合には東西で気候モードの不均衡が発生し,気候は不安定化した.気候が安定な時代は,人類が農耕と定住を開始した時期に対して良い一致を示した.これらの新しい生活技術は気候が安定した時代,すなわち短期的な予測が可能な時代でないと,必ずしも生存にとって有利に働かなかったのかもしれない.
1 0 0 0 OA ニュータウンの記憶のゆくえ
- 著者
- 西川 祐子
- 出版者
- Japan Association for Urban Sociology
- 雑誌
- 日本都市社会学会年報 (ISSN:13414585)
- 巻号頁・発行日
- vol.2009, no.27, pp.21-36, 2009 (Released:2011-10-07)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 1
In Kozoji New Town, Kasugai City, there is a community medium that is continuing the conveyance of information and the formation of a residential network while transforming the medium in three stages, from a hard copy-based community publication to an information exchange through the electronic medium of a website and then on to the establishment of a town-development NPO corporation and administration of a space for residents' communal exchange. The collective memory of the new town is built by this community medium and has the characteristics of being open to the external world and formed by the spontaneous contribution of the vague and faded memories of individuals. This essay discusses the relationship between the collective memory of a new town and the town development movement.
1 0 0 0 OA 船舶建造工程シミュレーションを用いた生産計画立案手法の現場適用に関する研究
- 著者
- 大久保 友結 満行 泰河
- 出版者
- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会
- 雑誌
- 日本船舶海洋工学会論文集 (ISSN:18803717)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.115-123, 2023 (Released:2023-08-03)
- 参考文献数
- 18
Shipbuilding is one of the most complex production systems in the manufacturing industry because of the incredible variety of parts and highly complex processes. However, production plans are currently prepared manually depending on the experience of expert workers. In this paper, a production planning method based on shipbuilding process simulation is proposed for use in actual shipyards, which simultaneously satisfies the needs of both production managers, who require on-time delivery plans, and field workers, who aim to minimize waiting time and improve operating rates. Specifically, the authors developed a hybrid method that combines backward and forward simulation for planning front-loading to meet deadlines and reduce waiting time. In the case study, the method was applied to a sub assembly conveyor line in an actual shipyard to demonstrate the validity and feasibility of the simulation results.
1 0 0 0 OA 高校無償化の憲法・学校法学的評価 : 私立高校無償化の法的可能性も視野に含めて
- 著者
- 結城 忠
- 雑誌
- 白鴎大学論集 = Hakuoh Daigaku ronshu : the Hakuoh University journal (ISSN:09137661)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.203-242, 2012-09-01
1 0 0 0 OA 義務教育を受ける権利と義務教育の無償性
- 著者
- 結城 忠
- 雑誌
- 白鴎大学教育学部論集 = Hakuoh Journal of the Faculty of Education (ISSN:18824145)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.1, pp.51-65, 2012-04-01
1 0 0 0 OA 世界最大船型のRO/RO船"TONSBERG"(<シリーズ>新造船紹介SOY2011)
- 著者
- 江熊 寿典
- 出版者
- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会
- 雑誌
- 日本船舶海洋工学会誌 KANRIN(咸臨) (ISSN:18803725)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, pp.47-49, 2012-07-10 (Released:2018-02-24)
1 0 0 0 OA 天蚕(ヤママユ)の食性と適性飼料樹
- 著者
- 寺本 憲之
- 出版者
- 社団法人 日本蚕糸学会
- 雑誌
- 蚕糸・昆虫バイオテック (ISSN:18810551)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.3, pp.3_159-3_166, 2011 (Released:2016-04-21)
- 参考文献数
- 22
1 0 0 0 OA 食品における結合態D-アミノ酸の分布と異性化を促進させる要因の解析
食品における結合態D-アミノ酸の存在と異性化を促進する要因について解析を行った。サプリメントとして販売されているコラーゲンペプチドには、結合態D-ValがD/D+L比20%程度の非常に高い割合で存在することを見出した。一方でダイズやホエー由来ペプチドでは結合態D-Valは検出されなかった。またAspジペプチドをモデルとして異性化を促進する加工処理を検討した。電子レンジでの加熱において、アルカリ条件では700 W、30秒で異性化が進行することを見出した。既知の条件よりもかなり低い温度と短時間で進行することが明らかになり、マイクロウェーブが結合態アミノ酸の異性化を促進することが示唆された。
1 0 0 0 レクチャー : 第一次世界大戦を考える
- 出版者
- 人文書院
1 0 0 0 OA 救急救命士の気管挿管指導
- 著者
- 寺井 岳三
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.7, pp.627-636, 2006 (Released:2006-12-22)
- 参考文献数
- 9
救急救命士の気管挿管が認められ, 病院での気管挿管実習が始まった. 大阪労災病院で実習を修了した救急救命士12名の問題点として, 麻酔器を用いたマスク換気が十分にできず, 人形を用いた事前訓練による悪い癖がついているため喉頭鏡操作がうまくできないことがある. 気管挿管成功率は92±6%であり, 個人間で技術にばらつきがみられるが, 年齢と成功率には有意な相関はなかった. 合併症は咽頭痛が12.5%, 嗄声が19.1%にみられた. 指導医は, 救急救命士が気管挿管を行うことの意義をよく理解し, 気管挿管実習とは総合的な気道管理実習の一部であると認識しなければならない. まずマスク換気がしっかりできること, そして確実かつ合併症を起こさない挿管技術を指導することが重要である.
1 0 0 0 OA 上肢のリーチ動作の評価と運動療法
- 著者
- 楠 貴光 鈴木 俊明
- 出版者
- 関西理学療法学会
- 雑誌
- 関西理学療法 (ISSN:13469606)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.39-46, 2018 (Released:2018-12-20)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 2
Manual muscle testing is used to assess movement during arm elevation. Prior studies of movement during arm elevation have not assessed concurrent elbow joint motion. However, arm elevation in activities of daily living is performed not only with movement of the shoulder joint and shoulder blades, but also with elbow joint movement. Therefore, arm reach movement and arm elevation are different actions. This paper discusses research to date on arm reach movement and describes assessment and exercise therapy methods.
- 著者
- 落合莞爾 斎藤充功著
- 出版者
- 学研マーケティング(発売)
- 巻号頁・発行日
- 2014
1 0 0 0 日本語オノマトペにおけるインアウト効果の検討
- 著者
- 大竹 裕香 山本 健太郎 山田 祐樹
- 雑誌
- 日本心理学会第87回大会
- 巻号頁・発行日
- 2023-08-03
1 0 0 0 当たり外れのわかりにくさは不正行為を誘発する
- 著者
- 劉 歓緒 山田 祐樹
- 雑誌
- 日本心理学会第87回大会
- 巻号頁・発行日
- 2023-08-03
- 著者
- Kana Kurokawa Munechika Hara Shin-ichiro Iwakami Takuya Genda Naoko Iwakami Yosuke Miyashita Masahiro Fujioka Shinichi Sasaki Kazuhisa Takahashi
- 出版者
- The Japanese Society of Internal Medicine
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.22, pp.3283-3287, 2019-11-15 (Released:2019-11-15)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 13 15
The anti-programmed cell death-1 protein monoclonal antibody, pembrolizumab is an immune checkpoint inhibitor. While it improves the prognoses of patients with advanced non-small-cell lung cancer, it has been reported to induce various kinds of immune-related adverse events, including hepatotoxicity. Despite the frequency of hepatotoxicity, there is only limited information available regarding the pathophysiology and treatment. We herein report a 48-year-old man with lung adenocarcinoma who was treated with pembrolizumab and developed cholestatic liver injury. In this case, the importance of evaluating the histology of hepatotoxicity and the effectiveness of ursodeoxycholic acid for cholestatic liver injury is indicated.
1 0 0 0 重量挙げ習慣は垂直空間感情メタファを破壊するか?
1 0 0 0 注意の舞踏会
- 著者
- 張 倫博 山田 祐樹
- 雑誌
- 日本心理学会第87回大会
- 巻号頁・発行日
- 2023-08-03
- 著者
- Yuki TAKAMI Miyuu TANAKA Masahiro MORITA Takaya MARUNO Naohiro ANAI Tsubasa SUDO Chiho KEZUKA Takeshi IZAWA Jyoji YAMATE Mitsuru KUWAMURA
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- pp.22-0457, (Released:2023-08-03)
A 25-year-old female California sea lion (Zalophus californianus) reared in an aquarium died following a history of anorexia, lethargy, abnormal protrusion of the skin, and oral respiration. At necropsy, multiple yellowish-white nodules with diameters of 0.1–0.5 cm were disseminated in the thoracic cavity and lungs. Histopathologically, the nodules were continuous with normal mesothelium and were characterized by the proliferation of spindle-shaped to polygonal neoplastic cells with prominent atypia. The neoplastic cells exhibited diffuse, strong staining for vimentin and partial, weak to moderate staining for cytokeratin AE1/AE3. Based on these findings, the lesions were diagnosed as pleural mesothelioma. This study reports the first case of pleural mesothelioma in California sea lion.
- 著者
- 水川 展吉 冨永 進 木股 敬裕 小野田 友男 野宮 重信 杉山 成史 川本 知明 山近 英樹 植野 高章 高木 慎
- 出版者
- 岡山医学会
- 雑誌
- 岡山医学会雑誌 (ISSN:00301558)
- 巻号頁・発行日
- vol.119, no.3, pp.267-272, 2008-01-04 (Released:2008-07-04)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 2 2
There is a medical team approach used in many hospitals for oral cancer patients. The members are head & neck surgeons and plastic surgeons, or oral surgeons and plastic surgeons. However, in Japan, it is very difficult for oral surgeons to cooperate with head & neck surgeons, except in the case of extractions and oral health care, because both surgeons treat oral carcinomas and there is therefore a conflict in their scope of practice. We believe it desirable for head & neck surgeons to treat oral cancer patients with tumors extending to other regions, and oral surgeons should be in charge of occlusion in head and neck carcinomas. We treated two patients with oral carcinomas in collaboration with head and neck surgeons and plastic surgeons, with head & neck surgeons resecting the tumors, plastic surgeons reconstructing, and oral surgeons (dentists) taking charge of the occlusion for patients in the operating room. This collaboration resulted in patients having good position of the temporomandibular joint and occlusions after the operation. We therefore conclude that this collaborative team approach may be of benefit to the patients.