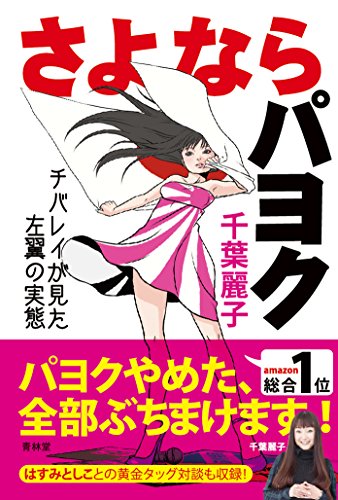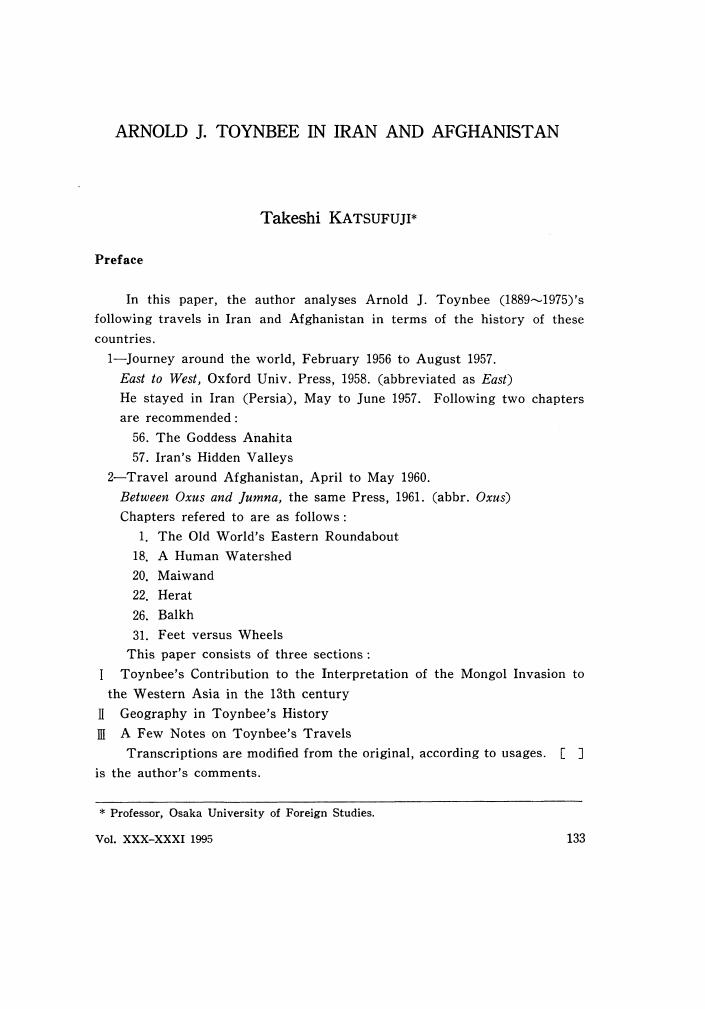1 0 0 0 テキストマイニングによるHSPに関する書籍のタイトルの特徴の抽出
- 著者
- 水野 雅之 水野 裕子
- 雑誌
- 日本心理学会第87回大会
- 巻号頁・発行日
- 2023-08-03
1 0 0 0 OA 被子植物における性の成立と進化 性の多様性を駆動する「植物らしさ」とは?
- 著者
- 増田 佳苗 赤木 剛士
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.23-29, 2021-01-01 (Released:2022-01-01)
- 参考文献数
- 26
「性」は動植物を問わず,遺伝的多様性を維持するための根幹機構である.しかし,動物に代表されるような画一的な性決定システムとは対照的に,植物は,祖先型である両全性から系統独立的に何度も性の成立・逸脱を繰り返してきた.植物の遺伝的な性に関する研究は100年以上に及ぶが,性別決定因子はまだ数えるほどしか発見されておらず,その制御機構や進化過程も多くが謎に包まれている.いまだ黎明期にある植物の性決定研究であるが,そのシステムの多様性のなかにあって,植物特異的な性質や歴史から垣間見える「一般性」も確かに存在するようであり,本稿では,植物性決定因子の発見に関する最新の知見の中から,その多様性を駆動する仕組みについて考える.
- 著者
- Ryuichi NODA Atsuya AKABANE Mariko KAWASHIMA Masafumi SEGAWA Sho TSUNODA Tomohiro INOUE
- 出版者
- The Japan Neurosurgical Society
- 雑誌
- NMC Case Report Journal (ISSN:21884226)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.221-226, 2023-12-31 (Released:2023-08-03)
- 参考文献数
- 20
Spontaneous regression of an arteriovenous malformation (AVM) is a rare condition observed in 0.3%-1.3% of patients with AVMs and is most likely caused by hemorrhagic events. The regression of an unruptured AVM is rarer than that of a ruptured AVM. Moreover, due to its low frequency of occurrence, the etiology and natural course of spontaneous regression of an AVM is still unclear. This is the first report presenting a case of a spontaneous regression of an unruptured AVM caused by a gradual drainer vein thrombosis that was suspected to result from hypercoagulability due to protein S deficiency.
1 0 0 0 OA 火落菌について
- 著者
- 野白 喜久雄 百瀬 洋夫
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.2, pp.88-91, 1970-02-15 (Released:2011-11-04)
- 被引用文献数
- 5 5
火落ちを防止するためには, その根本原因である火落菌の性質を熟知する必要がある。そこで清酒に関係する乳酸菌について研究されている筆者に, 火落菌の種類と清酒中の挙動について解説していただくと同時に, 火落防止に対する基本的考え方を示していただいた。
- 著者
- 市川 玲子 鈴木 美穂 秋冨 穣
- 雑誌
- 日本心理学会第87回大会
- 巻号頁・発行日
- 2023-08-03
1 0 0 0 さよならパヨク : チバレイが見た左翼の実態
1 0 0 0 OA 『文化情報学』刊行にあたって
- 著者
- 村上 征勝 Masakatsu Murakami
- 出版者
- 同志社大学文化情報学会
- 雑誌
- 文化情報学 = Journal of culture and information science
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.1, 2006-03-20
巻頭言
1 0 0 0 OA 人間はなぜ,スポーツをするのか(2/2)─スポーツとは何か:本質・構造・機能─
- 著者
- 内海 和雄
- 出版者
- 広島経済大学経済学会
- 雑誌
- 広島経済大学研究論集 = HUE Journal of Humanities, Social and Natural Science (ISSN:03871444)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.2, pp.3-18, 2022-11-30
1 0 0 0 OA ポストフェミニスト的言説パターンの登場とその特徴
- 著者
- 高橋 幸
- 出版者
- 日本女性学会
- 雑誌
- 女性学 (ISSN:1343697X)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.23-37, 2022-03-31 (Released:2023-04-01)
- 参考文献数
- 22
ネオリベラリズム政権によってフェミニズムが簒奪され、「官製フェミニズム」が進む社会状況のなかで見られるようになった、メディア上のポストフェミニスト的言説パターンについて報告する。 英米では、バックラッシュ後の1990年代から、現代を「フェミニズム」以後の時代と捉えるポストフェミニスト的言説パターンが登場した。それは、大きく次の二つの特徴を持つ。第一に、「現代では性別にかかわらず実力次第で誰でも活躍できる」というネオリベラリズム的・個人主義的主張。第二に、恋愛や結婚、性の場面をおもに念頭に置きつつ、性別らしさを重視する主張である。また、「ポストフェミニスト」という語が人口に膾炙するようになった90年代のアメリカでは、マクロレベルで見ても、性別役割意識の低下が停滞するという動向の変化が起こっている。日本でも、2000年代のバックラッシュと、その後の政府主導の女性労働力化の促進のなかで、ポストフェミニスト的な言説パターンが見られるようになっており、性別役割意識の低下の停滞も見られる。2000年代日本の「めちゃ♥モテ」ブームを分析すると、「モテ」を目指して性的魅力を向上させようとする営みやコミュニケーションのなかで、性別二元論的な性別役割が再生産されていることがわかる。 このようなポストフェミニスト的言説パターンは、アンチフェミニズムとは異なる形でフェミニズムを無効化するように働く可能性がある。そのため、これに対する新たな対抗言説を構築していくことがフェミニズムの喫緊の課題となっている。
1 0 0 0 OA 『水俣病と医学の責任』を読んで
- 著者
- 二塚 信 衛藤 光明 内野 誠
- 出版者
- 一般社団法人日本衛生学会
- 雑誌
- 日本衛生学雑誌 (ISSN:00215082)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, pp.23002, 2023 (Released:2023-07-14)
- 参考文献数
- 21
Even today, more than 60 years after the discovery of Minamata disease, many controversies continue to arise from various viewpoints. Recently, Dr. Shigeru Takaoka has published a book entitled “Minamata Disease and the Responsibility of Medical authorities” as a summary of his and colleagues’ previous works in which he presented their objections to past academic theories. We, who were also engaged in this research at Kumamoto University, would like to address some substantial viewpoints. Drs. Nishimura and Okamoto clarified why a series of cases that were clearly Minamata disease were found only in the Minamata plant from late 1950 to 1975, even though many acetaldehyde plants have been operating in Japan for many years. Dr. Takaoka ignored this very important issue and we point out the lack of reliability of his data from their health examination of “10,000” people. From the pathology perspective, Dr. Takaoka misunderstood the location and plasticity of neurons. From a clinical viewpoint, he mentioned the poor evidence for the characteristics and courses of the patients’ clinical symptoms.
1 0 0 0 OA 旧佐倉藩同協社趣意書並諸規則 [書写資料] / 同協社中倉次亨
- 巻号頁・発行日
- 1872
経済-会社(附・新聞社) / 和装 / 明治5年6月
1 0 0 0 OA プラズマコンタクタ
- 著者
- 竹ヶ原 春貴 小境 正也 山極 芳樹 大西 健夫 田原 弘ー
- 出版者
- 一般社団法人 日本航空宇宙学会
- 雑誌
- 日本航空宇宙学会誌 (ISSN:00214663)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.602, pp.79-85, 2004-03-05 (Released:2019-04-17)
- 参考文献数
- 29
1 0 0 0 OA 人工衛星の軌道変化から求めた超高層大気の密度その他の特性
- 著者
- 佐貫 亦男
- 出版者
- 一般社団法人 日本航空宇宙学会
- 雑誌
- 日本航空学会誌 (ISSN:00214663)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.105, pp.334-338, 1962 (Released:2009-05-25)
- 参考文献数
- 5
1 0 0 0 OA 栄養低下時における感染の併発
- 著者
- 原 耕平 塩澤 恒雄 河野 茂 門田 淳一 白井 亮 川上 かおる 飯田 桂子
- 出版者
- 一般社団法人 日本感染症学会
- 雑誌
- 感染症学雑誌 (ISSN:03875911)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.6, pp.569-574, 1998-06-20 (Released:2011-09-07)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 4 2
近年compromisedhostにおける日和見感染の実態が次第に明らかにされ, それらの感染症に対する治療の指針が述べられている.これらcompromisedhostにおける感染症の研究については数多くの成績が発表されているが, これらの病態における感染の発症が, 宿主の免疫能や栄養状態とどのようにかかわり合っているかを追求したものは極めて少ない.私達が行った成績では, 肺癌, 肝癌, 腎不全などの患者において, これら患者の免疫能は栄養状態によって影響をうけ, 栄養が不良になると免疫能の低下も著明になることが確かめられた.すでに手術を施行した患者においては, 術前に栄養の評価が行われ, その改善のための対策を講ずることによって予後を改善せしめようとの努力がなされているが, 多くの疾患においても, 宿主の栄養状態の管理は極めて重要で, その対策が感染の併発や疾病の予後を左右する要因であることを強調したい.
1 0 0 0 OA 抗体-薬物複合体開発の発展と現状
- 著者
- 眞鍋 史乃
- 出版者
- 日本DDS学会
- 雑誌
- Drug Delivery System (ISSN:09135006)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.1, pp.10-21, 2019-01-25 (Released:2019-04-25)
- 参考文献数
- 47
抗体-薬物複合体(antibody-drug conjugate:ADC)は、抗体をデリバリーツールとして活性の強い低分子化合物を病変部位へと送達し、安全域を広げるので、次世代抗体医薬として期待されている。本稿においては、より効果的なADCを作製するために各構成分子である抗体、低分子化合物、リンカーそれぞれに求められる事項と最近の話題について概説する。
- 著者
- Thein LIN Shizuka NOMURA Suzuka SOMENO Takahiro ABE Miyuki NISHIYAMA Shunya SHIKI Hayato HARIMA Kanako ISHIHARA
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- vol.85, no.8, pp.832-836, 2023 (Released:2023-08-01)
- 参考文献数
- 25
We focused on streptomycin resistance because of the high percentage of streptomycin-resistant Escherichia coli concerning the amount used of streptomycin. Antimicrobial resistance and horizontal transfer were identified in 117 isolates of coliform bacteria from chicken meat to identify the factors that increase streptomycin resistance. Escherichia (45 isolates) was the predominant genus. Most streptomycin-resistant Escherichia isolates were resistant to other antimicrobials (17/18), suggesting that using various antimicrobials could select streptomycin-resistant Escherichia isolates. Resistance was transferred from 7 out of the 18 streptomycin-resistant isolates. The transconjugants acquired strA/strB (7/7), blaTEM (5/7), aphA1 (5/7), tetB (3/7), dfrA14 (1/7) and/or dfrA17 (1/7). The co-resistance of streptomycin resistance with other resistances would also increase streptomycin resistance.
- 著者
- 松田 兼一
- 出版者
- 一般社団法人 日本人工臓器学会
- 雑誌
- 人工臓器 (ISSN:03000818)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.1, pp.71-74, 2017-06-15 (Released:2017-09-15)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 2
1 0 0 0 OA 嘘を発見する対話システム
- 著者
- 角森 唯子 Graham Neubig Sakriani Sakti 平岡 拓也 水上 雅博 戸田 智基 中村 哲
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会研究会資料 言語・音声理解と対話処理研究会 75回 (2015/10) (ISSN:09185682)
- 巻号頁・発行日
- pp.04, 2015-10-26 (Released:2021-06-28)
When humans attempt to detect deception, they perform two actions: looking for telltale signs of deception, and asking questions to attempt to unveil a deceptive conversational partner. There has been a significant amount of prior work on automatic deception detection, which focuses on the former. On the other hand, we focus on the latter, constructing a dialog system for an interview task that acts as an interviewer asking questions to attempt to catch a potentially deceptive interviewee. We propose several dialog strategies for this system, and measure the utterance-level deception detection accuracy of each, finding that a more intelligent dialog strategy results in slightly better deception detection accuracy.
1 0 0 0 OA ARNOLD J. TOYNBEE IN IRAN AND AFGHANISTAN
- 著者
- Takeshi KATSUFUJI
- 出版者
- The Society for Near Eastern Studies in Japan
- 雑誌
- Orient (ISSN:04733851)
- 巻号頁・発行日
- vol.30and31, pp.133-141, 1995 (Released:2009-02-12)