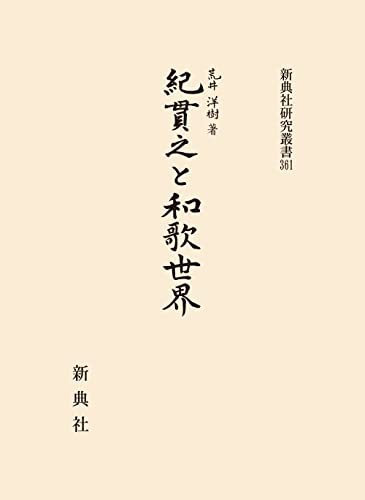- 著者
- Saki Teramura Kazumasa Yamagishi Mitsumasa Umesawa Mina Hayama-Terada Isao Muraki Koutatsu Maruyama Mari Tanaka Rie Kishida Tomomi Kihara Midori Takada Tetsuya Ohira Hironori Imano Yuji Shimizu Tomoko Sankai Takeo Okada Akihiko Kitamura Masahiko Kiyama Hiroyasu Iso
- 出版者
- Japan Atherosclerosis Society
- 雑誌
- Journal of Atherosclerosis and Thrombosis (ISSN:13403478)
- 巻号頁・発行日
- pp.63907, (Released:2023-03-03)
- 参考文献数
- 40
- 被引用文献数
- 6
Aim: We aimed to examine sex-specific risk factors for hyperuricemia or gout in Japanese cohorts. Methods: We followed up 3,188 men (mean age, 55.6 years) and 6,346 women (mean age, 54.1 years) without hyperuricemia, gout, or elevated liver enzymes at baseline from 1986 to 1990 for a median of 14.6 years. The participants were considered as having hyperuricemia or gout if their serum uric acid levels were ≥ 7.0 mg/dL or they were receiving treatment for hyperuricemia or gout during annual health checkups. The sex-specific multivariable hazard ratios (HRs) of hyperuricemia or gout incidence were calculated after adjustment for smoking and drinking status, body mass index, hypertension, diabetes, hypercholesterolemia, and hypertriglyceridemia using the Cox proportional-hazard model. Results: During follow-up, 733 men and 355 women had hyperuricemia or gout. Among men, the multivariable HRs (95% confidence intervals) of hyperuricemia or gout were 1.23 (1.00–1.52) and 1.41 (1.13–1.75) for drinkers of <46 and ≥ 46 g ethanol/day, respectively, compared with non-drinkers; 1.00 (0.81–1.24) and 1.18 (0.93–1.50) for smokers of 1–19 and ≥ 20 cigarettes/day, respectively, compared with never smokers; and 1.41 (1.20–1.65) for hypertensive compared with non-hypertensive participants. The HRs for women were 1.02 (0.70–1.48), 1.66 (1.05–2.63), and 1.12 (0.88–1.42) for current drinkers, current smokers, and hypertensive participants, respectively. For both men and women, body mass index, diabetes, hypercholesterolemia, and hypertriglyceridemia were not associated with hyperuricemia or gout incidence. Conclusions: Hypertension and alcohol drinking are risk factors for hyperuricemia or gout among men and smoking among women.
1 0 0 0 OA スマート育種ツールの利用に関するワークショップ
- 著者
- 杉本 和彦 米丸 淳一 坂井 寛章 川原 善浩 鐘ケ江 弘美
- 出版者
- 日本育種学会
- 雑誌
- 育種学研究 (ISSN:13447629)
- 巻号頁・発行日
- pp.25.W05, (Released:2023-03-25)
気候変動及び様々なニーズに対応した育種を効率化・加速化するために,データに基づいたスマート育種の育種現場への実装が期待されている.現在,スマート育種を育種現場に実装するための取組みとして,農林水産省においてスマート育種に関する委託プロジェクト(「次世代育種・健康増進プロジェクト」のうち民間事業者等の種苗開発を支える「スマート育種システム」の開発,平成30年~令和5年)が実施されている.本ワークショップでは,当該プロジェクトを構成する2つの研究課題である「育種ビッグデータの整備及び情報解析技術を活用した高度育種システムの開発」(略称:BAC)及び「民間事業者,地方公設試等の種苗開発を支える育種基盤技術の開発」(略称:DIT)について概要を紹介し,当該プロジェクトの予算で開発を行っている3種の育種ツール,育種情報の集約・解析支援を行う育種情報管理支援システム「BRIMASS」,育種の家系図情報を表示する系譜情報グラフデータベース「Pedigree Finder」及び有用遺伝子の品種間多型情報を整理した有用遺伝子カタログと可視化ツール「アリルグラフ」について説明する.また,3種の育種ツールについてはPCを使った実習も合わせて行う.
1 0 0 0 OA 1molの量を可視化する立方体教材の開発
- 著者
- 石田 良仁 弘田 柊
- 雑誌
- 帝京科学大学紀要 = Bulletin of Teikyo University of Science (ISSN:18800580)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.31-39, 2023-03-31
1 0 0 0 OA 夜間定時制高校数学科における反転授業の有効性の検証
- 著者
- 原 健太郎 渡辺 雄貴 清水 克彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.3, pp.239-252, 2019-12-31 (Released:2020-02-14)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 1
夜間定時制高校は,算数・数学の基礎学力に課題を抱える生徒が多く在籍している.本研究では,夜間定時制高校でのアクティブ・ラーニング型の授業設計の検討を見据え,数学科での反転授業の有効性について検証することを目的とした.そのためにADDIE モデルに従って開発した授業に対し,ID の目指す価値としての効果・効率・魅力の観点から検証し,以下の結果を得た.授業前に動画を視聴しない状況,動画を視聴していてもそれを前提とした授業展開は厳しい状況が見られた.学習形態の変容により学習に困難を抱える生徒は取り組みやすくなり,教え合いの対話的活動での動画活用や,復習として主体的な動画利用の状況が見られた.定期考査等の得点が低かった生徒でも得点が増加し,効果的な習得が確認された.学習場面での必要時間が短縮され,効率的な学習が行われた.反転授業によって,基礎学力に課題を抱える生徒において大きな効果が得られる可能性が示唆された.
- 著者
- 樋口 靖
- 出版者
- 文教大学
- 雑誌
- 文学部紀要 = Bulletin of the Faculty of Language and Literature (ISSN:09145729)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.1, pp.1-14, 1997-10-01
日本統治台灣時期出現了許多有關台語的著作。這期間被使用的台語漢字有些獨特之處;使用訓讀漢字用得比較多,而且它的用法相當不統一。其原因何在?大部分作品的作者是日本人,讀者也是日本人,是用於日本人學台語所編的語言敎材和辭典之類。日語的漢字用法多用訓讀法來表示「大和言葉」。當時,日文的漢字用法比較隨便;對同一個單字,有時候用這個漢字充當,又有時候用那個漢字充當。或是,以同一個漢字表示兩個不同日語單字。日本作者可能把這種日文的習慣帶進台語著作裡面。例如:對台語【khùn睏】出現有「睡,眠」兩種寫法;又,對台語【khng,hē】兩個字使用一個「置」(おく)字來表示,等等。台語有很多單字無法以恰當的漢字表出,有時候關於一個字的寫法眾説紛紜,是叫我們初學台語的外國人實在傷腦筋的事。如要解決這種問題,採用訓讀法可能是比較妥當的解決方式。然則,個人以爲日本時代的漢字用法也有一定的參考價値。
1 0 0 0 OA 岡山県に於けるイタドリ方言の分布
- 著者
- 佐藤清明
- 出版者
- 植物研究雑誌編集委員会
- 雑誌
- 植物研究雑誌 (ISSN:00222062)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.6, pp.208-218, 1931-04-30 (Released:2023-03-31)
- 著者
- 横山 友里 清野 諭 光武 誠吾 西 真理子 村山 洋史 成田 美紀 石崎 達郎 野藤 悠 北村 明彦 新開 省二
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.10, pp.752-762, 2020-10-15 (Released:2020-12-23)
- 参考文献数
- 38
- 被引用文献数
- 1
目的 「運動」「栄養」「心理・社会参加」を柱としたフレイル改善のための複合プログラムへの参加がその後の要介護・死亡発生リスクや介護費に及ぼす影響を,傾向スコアマッチングを用いた疑似実験的デザインにより検証した。方法 鳩山コホート研究参加者742人のうち,2011年度(47人)と2013年度(30人)に開催した3か月間のフレイル改善教室のいずれかの年度に参加したフレイルまたはプレフレイルの計77人を介入群とした。不参加群は,鳩山コホート研究参加者の中から,介入不参加者(介入対象外であった者のほか,介入対象であったものの,教室参加を拒否した者を含む)を対象に,傾向スコアを算出し,介入群との比を1:2としてマッチングすることにより,設定した。傾向スコアで完全にマッチングできた対象者は介入群70人,不参加群140人,計210人であった。住民異動情報・介護保険情報を突合し,32か月間(教室終了後24か月)の追跡による要介護(要支援含む)・死亡発生リスクをCoxの比例ハザードモデルを用いて算出した。また,ガンマ回帰モデルを用いて介護費の比較を行った。結果 要介護の発生率(対千人年)は介入群が不参加群に比し,有意ではないものの低い傾向を示し(介入群:1.8 vs.不参加群:3.6),不参加群に対する介入群の要介護認定のハザード比と95%信頼区間(95%CI)は0.51(0.17-1.54)であった。また,介入群と不参加群の間で介護費発生の有無に有意な差はみられなかったものの,介護費については,受給者1人あたりの追跡期間中の累積の費用,1か月あたりの費用の平均値はそれぞれ,介入群で375,308円,11,906円/月,不参加群で1,040,727円,33,460円/月と介入群では約1/3の低額を示し,累積の費用(コスト比=0.36, 95%CI=0.11-1.21, P=0.099),1か月あたりの費用(コスト比=0.36, 95%CI=0.11-1.12, P=0.076)ともに,不参加群に比べて介入群で低い傾向がみられた。結論 本研究では統計的な有意差は認められなかったものの,フレイル改善のための複合プログラムの実施により,その後の要介護発生リスクおよび介護費を抑制できる可能性が示された。今後,より厳密な研究デザインによるさらなる検証が必要である。
1 0 0 0 OA 富山湾におけるブリ,スルメイカ,ホタルイカの 漁況と日本海の海洋環境との関係
- 著者
- 小塚 晃 北川 慎介 南條 暢聡 辻本 良
- 出版者
- 日本海洋学会 沿岸海洋研究会
- 雑誌
- 沿岸海洋研究 (ISSN:13422758)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.1, pp.81-86, 2020 (Released:2020-09-12)
- 参考文献数
- 20
富山湾では400年以上も前から定置漁業が盛んであり,暖水性の回遊魚を中心に漁獲してきた.主要漁獲物であるブリ, スルメイカおよびホタルイカについて,漁獲変動と海洋環境との関係を調べた.ブリでは,日本周辺海域の海水温の上昇 に伴い分布域がオホーツク海まで拡大し,2000年代後半以降に北海道の漁獲量が急増した.また,南下期である冬季の富 山湾への来遊状況は,12月に山形県沖が暖かく能登半島北西沖が冷たい水塊配置のときに好漁となる傾向が認められた. 富山県沿岸で1月~3月に漁獲されるスルメイカは,日本海北部海域の1月期における水温が低い年に南下経路が沿岸よ りとなり,漁獲量が多くなる傾向があった.日本海北部海域の水温上昇は,冬季の富山湾へのスルメイカの来遊量を減少 させる要因となると考えられる.ホタルイカでは,2008年まで,日本海における主産卵場である山陰沖の5月の水温が高 いと,翌年の富山湾漁獲量が多くなる傾向が認められた.しかし,2009年以降,山陰沖水温環境指標と富山湾漁獲量との 間の関係性が悪くなり,その要因の解明が必要となっている.これらの種は,東シナ海や日本海を産卵場とし,日本海を 広く回遊する.対馬暖流の勢力は,加入量や仔稚魚の分散にも関与し,富山湾への来遊は,日本海の水温や水塊配置に大 きく依存している.地球温暖化やレジームシフトによる海洋環境の変化により,日本海や東シナ海において産卵場や回遊 状況が変化し,長期的に富山湾の漁況が変化していくことが懸念される.
1 0 0 0 OA 看護における「ニード論」「ストレス-コーピング理論」
- 著者
- 茶園 美香
- 出版者
- The Japanese Society of Intensive Care Medicine
- 雑誌
- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.4, pp.431-435, 2006-10-01 (Released:2009-03-27)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 1
心理学における「ニード論」,「ストレス-コーピング理論」について紹介し,看護での捉え方や使い方について述べる。患者は,病気によるさまざまな制約により自分でニードを充足することが困難で,人間としての営みを続けることが妨げられている。看護では,病気を持った患者のニードに焦点を当て,基本的なニードが充足するための援助を行なっている。今回は,ニードに焦点を当てた看護論の中から,ヘンダーソンのニード論を紹介し,ニードに対する看護の進め方を論述する。また,患者は病気によって,さまざまなストレスに遭遇している。ストレスの持続は,身体的・心理的に患者を脅かし,病気の回復を遅らせるだけではなく,身体的・心理的に危機的な状況を引き起こす。看護では,患者がストレスに対して効果的なコーピングができるように援助している。今回は,ラザルスらのストレス-コーピング理論を紹介し,看護の進め方を論述する。
1 0 0 0 OA <論文>百済王子豊璋と倭国
- 著者
- 高 寛敏
- 出版者
- 大阪経済法科大学アジア研究所
- 雑誌
- 東アジア研究 = East Asian Studies (ISSN:13404717)
- 巻号頁・発行日
- no.10, pp.53-71, 1995-11-01
1 0 0 0 OA 檀一雄の病跡学的研究 : 躁的防衛,抑うつポジション,移行対象の視点から
- 著者
- 真鍋 守栄 Morie Manabe 茨城キリスト教大学社会・自然科学 Ibaraki Christian University Social and Natural Sciences
- 雑誌
- 茨城キリスト教大学紀要. II, 社会・自然科学 = Journal of Ibaraki Christian University. II, Social and natural sciences (ISSN:13426370)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, pp.23-35, 2002-02-25
Kazuo Dan is considered as a ruinous type of writer. He had difficulties in his background, for instance, his mother left home when he was 9 years old. I can see a vitality and will to live behind his dissapation for destruction. It seems like a home environment had a deep effect on his behavior later on. In this paper, I have tried to understand his life through the psychoanalytic viewpoints of Manic Defences, Depressive Position and Transitional Object.
1 0 0 0 OA 水痘・帯状疱疹におけるウィルス特異抗原の検出とウイルス分離の比較
- 著者
- 吉田 正己 手塚 正
- 出版者
- Meeting of Osaka Dermatological Association
- 雑誌
- 皮膚 (ISSN:00181390)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.2, pp.177-181, 1989 (Released:2010-08-25)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1
水痘・帯状疱疹患者40例を対象として, ウイルス特異抗原の検出とウイルスの分離を試み, 両方法のウイルス学的診断法としての有用性を比較検討した。ウイルス特異抗原の検出率は95%で, ウイルスの分離率は70%であった。塗抹標本でのウイルス特異抗原の検出は迅速かつ簡便であり, 検出率も高いことから, 水痘・帯状疱疹におけるウイルス学的診断法として臨床的に非常に有用な方法と考える。
1 0 0 0 OA Chopart amputation with tendon balancing
- 著者
- Kazuo Ouchi Naoyuki Oi Mari Sato Shoji Yabuki Shin-ichi Konno
- 出版者
- THE FUKUSHIMA SOCIETY OF MEDICAL SCIENCE
- 雑誌
- FUKUSHIMA JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE (ISSN:00162590)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.1, pp.67-71, 2023 (Released:2023-04-05)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 2
Background: When foot necrosis occurs due to lower limb blood flow disorder caused by diabetes or peripheral arterial occlusion, many patients require lower limb amputation. The functional prognosis after lower limb amputation largely depends on whether the heel can be preserved. However, there are many reports that Chopart amputation causes varus and equinus deformity, and is functionally unfavorable. We herein report a case of Chopart amputation performed with muscle balancing. Postoperatively, the foot was not deformed and the patient was able to walk independently with a foot prosthesis. Case: A 78-year-old man presented with ischemic necrosis of his right forefoot. The range of necrosis extended to the central part of the sole, so Chopart amputation was performed. In the operation, to prevent varus and equinus deformity, the Achilles tendon was lengthened, the tibialis anterior tendon was transferred through a tunnel created in the neck of talus, and the peroneus brevis tendon was transferred through a tunnel created in the anterior part of the calcaneus. At the final follow-up 7 years after the operation, no varus or equinus deformity was observed. The patient became able to stand up and walk on his heel without a prosthesis. In addition, step motion was possible by wearing a foot prosthesis.
1 0 0 0 原色滿洲有用淡水魚類圖説
- 著者
- Yu GUO Mohamed Mahdi ALSHAHNI Kazuo SATOH Takashi TAMURA Rima Zakzuk ALSHAHNI Koichi MAKIMURA
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- vol.85, no.3, pp.271-278, 2023 (Released:2023-03-01)
- 参考文献数
- 29
Koalas are iconic mammals indigenous to Australia. These rare animals and their habitats are occasionally associated with pathogenic fungi, including species of Cryptococcus, and consequently, monitoring the mycobiota of areas inhabited by koalas is of considerable importance. In this report, we describe a novel basidiomycetous yeast isolated from a site in Kanazawa Zoo, Japan, associated with captive koalas. Swab samples were collected from koala breeding environments, from which we isolated a novel unencapsulated yeast characterized by ovoid to ellipsoidal cells (3.2–4.9 × 3.5–5 μm). These cells were observed to undergo polar budding and grow as parent bud pairs, with an optimal growth temperature of 28°C. Colonies grown on yeast extract peptone dextrose agar at 28°C have a characteristic coral pink color. On the basis of physiological, morphological, and molecular characters, the new species was placed in the genus Begerowomyces, and the name Begerowomyces aurantius JCM33898T(LSEM1333T=CBS16241T) is proposed.
1 0 0 0 OA 『一代五時継図』と『注法華経』 : 女人成仏を端緒として (特集 女人成仏)
- 著者
- 関戸 堯海
- 出版者
- 身延山大学東洋文化研究所
- 雑誌
- 東洋文化研究所 所報 = Journal, Research Institute of Eastern Culture (ISSN:13426605)
- 巻号頁・発行日
- no.2, pp.19-27, 1998-03-25
1 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1911年02月27日, 1911-02-27
1 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1914年09月08日, 1914-09-08