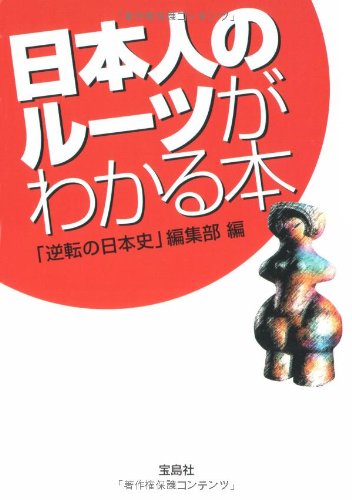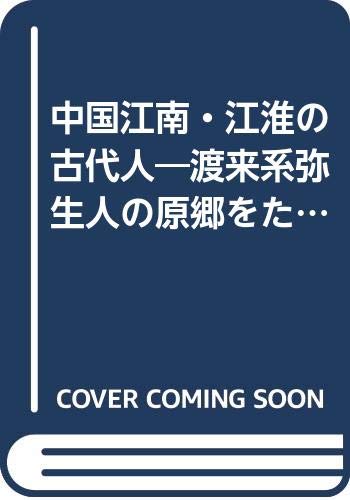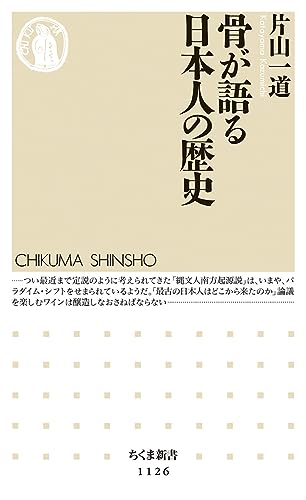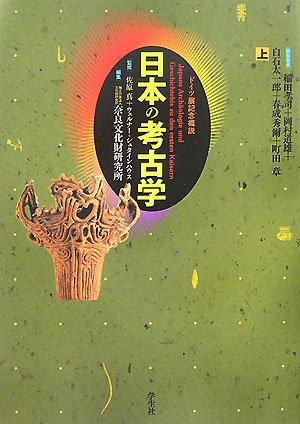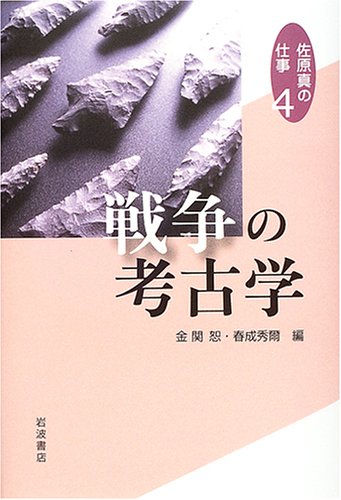1 0 0 0 OA 胆道出血で発症した肝細胞癌の1例
- 著者
- 井上 明星 濱中 訓生 板橋 健太郎 井本 勝治 山﨑 道夫 坂本 力 八木 勇紀
- 出版者
- 一般社団法人 日本救急医学会
- 雑誌
- 日本救急医学会雑誌 (ISSN:0915924X)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.9, pp.793-798, 2013-09-15 (Released:2013-12-30)
- 参考文献数
- 10
症例は54歳の男性。30歳時にC型肝炎を指摘されたが放置していた。2時間前から徐々に増強する心窩部痛を主訴に来院した。血圧88/58mmHg,脈拍57/分であった。身体診察にて,心窩部に圧痛を認めた。血液検査では肝臓逸脱酵素および胆道系酵素の上昇と軽度のビリルビン上昇を認めた。腹部単純CTでは右肝管から総胆管内の出血を,造影後は肝右葉優位に多発する濃染腫瘤を認め,肝細胞癌破裂により生じた胆道出血と診断した。内視鏡的胆道内血腫除去を行い,心窩部痛の改善を認めた。さらに入院3日目に再出血予防および肝細胞癌の治療を目的として肝動脈化学塞栓術(transcatheter arterial chemoembolization: TACE)を施行した。症状は改善し入院24日目に退院となった。2か月後,5か月後に残存腫瘍に対してTACEを行ったが,7か月後に肝不全で永眠された。胆道出血の治療方針の柱は止血と胆道閉塞解除であり,出血速度に応じていずれを優先させるかを判断する必要がある。
1 0 0 0 OA 慢性腰痛に対する運動療法の効果
- 著者
- 宮本 雅史 伊藤 博元
- 出版者
- 日本腰痛学会
- 雑誌
- 日本腰痛学会雑誌 (ISSN:13459074)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.1, pp.92-96, 2005 (Released:2007-12-14)
- 参考文献数
- 9
慢性腰痛に対する運動療法は重要な保存的治療法である.しかし現在の医療制度の中では,その治療効果についての科学的根拠が確立されていないという理由から,診療報酬を削減される危機に陥っている.従来のシステマテックレビューには個々の論文の間で慢性腰痛の定義や治療効果を判定するためのアウトカム指標が統一されていないことや,運動療法の種類や対照群の治療法がさまざまであるなどの問題点が指摘されている.近年,Liddle SDらはこれらの点に改善を加えた新しいシステマテックレビューを行い,運動療法は慢性腰痛患者に対し特に腰痛の特異的機能評価の観点から効果的に作用すると報告した.国内でも現在,慢性腰痛に対する運動療法に関する質の高いRCTが進行中であり,運動療法の有効性に対する評価を見直すべき時期にきているといえるであろう.
1 0 0 0 OA 相模愛甲郡の道祖神と小正月の行事
- 著者
- 藤江 慎二 松永 千惠子
- 出版者
- 一般社団法人 日本社会福祉学会
- 雑誌
- 社会福祉学 (ISSN:09110232)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.2, pp.91-102, 2021-08-31 (Released:2021-10-29)
- 参考文献数
- 19
本研究では,障害者支援施設で発生した施設内虐待の要因を明らかにし,虐待予防について考察することを目的とした.方法としては,施設内虐待の事件の裁判調書を法律に基づき入手し,事件を詳細に把握・分析した.その結果,施設内虐待の事件には,①施設の人材育成の問題が虐待行為と関連していること,②職員間コミュニケーションの不足が虐待行為の慢性化に影響していたこと,③施設・法人の虐待問題を隠蔽しようとする考え方は職員間に広がり,職員の退職にも影響を及ぼしていたことが明らかになった.施設内虐待は構造的な問題であり,職員間コミュニケーションの改善や虐待予防のシステム構築をしていくことが今後の課題であることを指摘した.
1 0 0 0 OA 半導体産業における垂直分業の変容
- 著者
- 中原 裕美子
- 出版者
- アジア経営学会
- 雑誌
- アジア経営研究 (ISSN:24242284)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, pp.39-51, 2022 (Released:2023-04-08)
- 参考文献数
- 42
In this paper, we analyze the transformation of vertical division of labor in the semiconductor industry. In the semiconductor industry, the vertical division of labor has progressed due to the emergence of a business model called foundries which specializes in contract production that could be described as “disruptive innovation” in the 1980s. Then, under the COVID-19, as the demand for semiconductors has increased and the semiconductors became in short, TSMC has attracted increasing attention as a key player in the supply of semiconductors in the world. This situation is no longer something like “suppliers from late industrialized countries grow up in the vertical division of labor governed by companies in developed countries,” as the Global Value Chain theory or the Global Production Network theory described. In the divides, the form of vertical division of labor is shifting to a new phase where the supplier holds the casting boat. This is the first aspect of the transformation of the vertical division of labor in the semiconductor industry. Moreover, developed countries such as the United States and Japan, where vertically integrated semiconductor companies once prospered, are eager to attract TSMC factories in order to incorporate semiconductor production bases into their own countries. That is, the vertical division of labor, which was in the form of “a company in a developed country consigns production to a supplier located in a low-cost late developed country,” has changed to a phenomenon in which a supplier in the late developed country has a production base in a developed country at the request of a developed country. This is the second aspect of the transformation of the vertical division of labor in the semiconductor industry.
1 0 0 0 OA 社会的相互作用における排除
- 著者
- 水津 嘉克
- 出版者
- The Japan Sociological Society
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.3, pp.335-349, 1996-12-30 (Released:2010-05-07)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 1
今日「差別や偏見は正しいことですか」と尋ねられて, 肯定的な答をする人はむしろ少数であるにもかかわらず, 身体や精神に障害を持つ人に対する偏見は相変わらず根強く残存しているように思われる。これまで多くの議論が, 社会的な場面におけるこれら差別や偏見を, 相互作用の断絶という文脈で語ってきた。しかし, 「排除」は必ずしもその直接的な形をとってのみあらわれるとは限らない。本論稿で問題とするのは社会的相互作用が拒絶される形で現出する差別・偏見ではない。一見社会的相互作用が維持されている場面のなかに〈方法〉として維持されている「排除する-される」という関係である。それは「私的局域の侵害」「現実構築作業への参加拒否」「主体的人間像の否定」という形で現れてくる。以下, 前提となる議論を若干試みた後, それぞれの「排除」について議論を行う。
1 0 0 0 OA 機関投資と経営者支配(1)
- 著者
- 佐賀 卓雄
- 出版者
- 小樽商科大学
- 雑誌
- 商学討究 (ISSN:04748638)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.2, pp.52-64, 1976-10-30
論説
- 著者
- Wentao ZHANG Chen MIAO Wen WU
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- IEICE TRANSACTIONS on Communications (ISSN:09168516)
- 巻号頁・発行日
- vol.E106-B, no.4, pp.307-316, 2023-04-01
Direction of arrival (DOA) estimation has been a primary focus of research for many years. Research on DOA estimation continues to be immensely popular in the fields of the internet of things, radar, and smart driving. In this paper, a simple new two-dimensional DOA framework is proposed in which a triangular array is used to receive wideband linear frequency modulated continuous wave signals. The mixed echo signals from various targets are separated into a series of single-tone signals. The unwrapping algorithm is applied to the phase difference function of the single-tone signals. By using the least-squares method to fit the unwrapped phase difference function, the DOA information of each target is obtained. Theoretical analysis and simulation demonstrate that the framework has the following advantages. Unlike traditional phase goniometry, the framework can resolve the trade-off between antenna spacing and goniometric accuracy. The number of detected targets is not limited by the number of antennas. Moreover, the framework can obtain highly accurate DOA estimation results.
1 0 0 0 東アジアと『半島空間』 : 山東半島と遼東半島
- 著者
- 千田稔 宇野隆夫共編
- 出版者
- 思文閣出版
- 巻号頁・発行日
- 2003
1 0 0 0 日本人のルーツがわかる本
- 著者
- 「逆転の日本史」編集部編
- 出版者
- 宝島社
- 巻号頁・発行日
- 2008
1 0 0 0 異人その他 : 日本民族=文化の源流と日本国家の形成
1 0 0 0 中国江南・江淮の古代人 : 渡来系弥生人の原郷をたずねる
1 0 0 0 骨が語る日本人の歴史
1 0 0 0 日本の考古学 : ドイツ展記念概説
- 著者
- 文化財研究所奈良文化財研究所編集
- 出版者
- 学生社
- 巻号頁・発行日
- 2007
- 著者
- 中村 俊夫
- 出版者
- 名古屋大学年代測定資料研究センター
- 雑誌
- 名古屋大学加速器質量分析計業績報告書
- 巻号頁・発行日
- no.15, pp.103-112, 2004-03
第16回名古屋大学タンデトロン加速器質量分析計シンポジウム(平成15年(2003年度)報告 Proceedings of the 16th Symposium on Researches Using the Tandetron AMS System at Nagoya University in 2003 日時:平成16(2004)年1月22日(木)、23日(金) 会場:名古屋大学シンポジオン Date:January 22nd and 23rd,2004 Place:Nagoya University Symposion Hall
- 著者
- 篠田 謙一 神澤 秀明 角田 恒雄 安達 登
- 出版者
- 日本人類学会
- 雑誌
- Anthropological Science (Japanese Series) (ISSN:13443992)
- 巻号頁・発行日
- vol.127, no.1, pp.25-43, 2019
- 被引用文献数
- 5
<p>佐世保市下本山岩陰遺跡から出土した2体の弥生人骨の核ゲノム解析を行った。これらの人骨は,遺跡の地理的な位置と形態学的な研究から縄文人の系統を引く西北九州弥生人集団の一員であると判断されている。しかし,次世代シークエンサを用いたDNA解析の結果,共に縄文系と渡来系弥生人の双方のゲノムを併せ持つことが明らかとなった。これらの人骨の帰属年代は弥生時代の末期にあたる。本研究結果から,この時期には九州の沿岸地域でも,在来集団と渡来した人々との間で混血がかなり進んでいたことが明らかとなった。このことは,これまで固定的に捉えられていた渡来系弥生人と西北九州弥生人の関係を捉え直す必要があることを示している。また本研究によって,古人骨の核ゲノムの解析で得られたデータは,このような混血の状況を捉えるのに有効であることも示された。今後,北部九州の弥生人骨のゲノム解析を進めていけば,日本人の成立のシナリオは更に精緻なものになることが期待される。</p>
1 0 0 0 HLAと人類の移動 (特集 日本列島の人類学的多様性)
- 著者
- 徳永 勝士
- 出版者
- 勉誠出版
- 雑誌
- Science of humanity Bensei
- 巻号頁・発行日
- no.42, pp.4-9, 2003-04