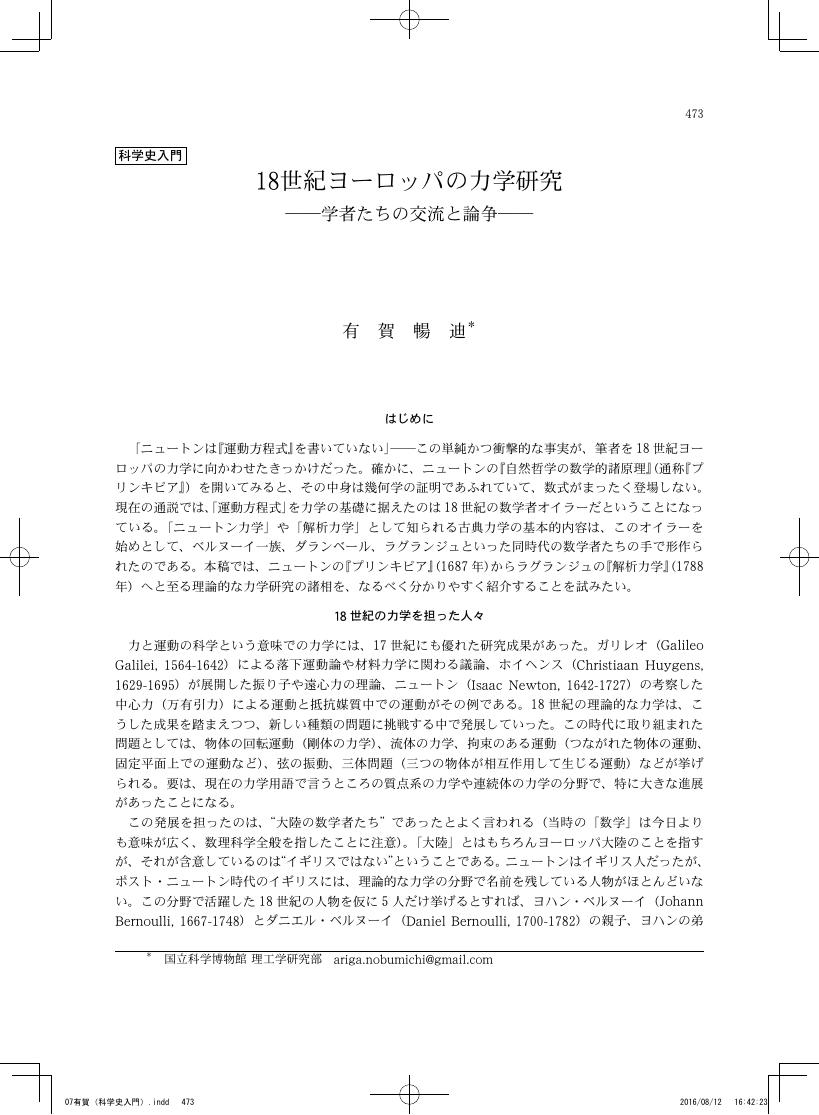1 0 0 0 OA 制御用2進-2進化10進符号変換器の集積回路化
- 著者
- 小西 務
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電氣學會雜誌 (ISSN:00202878)
- 巻号頁・発行日
- vol.91, no.1, pp.123-130, 1971-01-20 (Released:2008-04-17)
- 参考文献数
- 10
1 0 0 0 長野市権堂町史
- 著者
- 権堂町史編集委員会編
- 出版者
- 権堂町公民館
- 巻号頁・発行日
- 1993
1 0 0 0 OA 衛星データプラットフォームを用いた遠隔方式によるデータサイエンス教育
- 著者
- 鈴木 静男 田中 康平 大沼 巧 玉置 慎吾 大庭 勝久 酒井 基至 竹口 昌之 白井 秀範 芳野 恭士
- 出版者
- 公益社団法人 日本工学教育協会
- 雑誌
- 工学教育 (ISSN:13412167)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.4, pp.4_80-4_85, 2021 (Released:2021-08-01)
- 参考文献数
- 11
In the experiments performed in the advanced course of the National Institute of Technology, Numazu College, data science education was conducted remotely by using asynchronous and synchronous interactive methods. The Tellus platform with satellite and terrestrial data was used to analyze data in a cloud environment. We adopted the development of data engineering, data analysis, and value creation skills as basic educational guidelines. From the answers to the questionnaire, we conclude that 1) the asynchronous interactive method made us aware of many benefits, 2) the synchronous interactive methods gave us some issues to be solved, and 3) the three guidelines were successfully achieved.
1 0 0 0 OA 科学史入門 18世紀ヨーロッパの力学研究 : 学者たちの交流と論争
- 著者
- 有賀 暢迪
- 出版者
- 日本科学史学会
- 雑誌
- 科学史研究 (ISSN:21887535)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.272, pp.473, 2015 (Released:2020-12-14)
1 0 0 0 OA ガーデニングと明治期の家庭園芸
- 著者
- 水島 かな江
- 出版者
- 恵泉女学園大学園芸文化研究所
- 雑誌
- 恵泉女学園大学園芸文化研究所報告:園芸文化 = Bulletin of Keisen Institute of Horticulture (ISSN:18825044)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.12-23, 2010-07
1 0 0 0 OA 日本語-セブアノ語(ビサヤ語)-英語 対照基礎語彙集5000
- 著者
- 安部 清哉 Seiya Abe
- 出版者
- フェリス女学院大学
- 雑誌
- フェリス女学院大学文学部紀要 (ISSN:09165959)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, pp.A1-A105, 2002-03
1 0 0 0 OA 「ちびっ子食農教育」実践報告
- 著者
- 杉山 道雄 石原 加代子 内田 美佐子 尾木 千恵美 古賀 裕子 鷲見 孝子 平光 美津子 山澤 和子 Michio SUGIYAMA Kayoko ISHIHARA Misako UCHIDA Chiemi OGI Yuko KOGA Takako SUMI Mitsuko HIRAMITSU Kazuko YAMAZAWA 東海学院大学 東海女子短期大学食物栄養学科 東海女子短期大学食物栄養学科 東海女子短期大学食物栄養学科 東海女子短期大学食物栄養学科 東海女子短期大学食物栄養学科 東海女子短期大学食物栄養学科 東海女子短期大学食物栄養学科 / TOKAI Women's Junior College TOKAI Women's Junior College TOKAI Women's Junior College TOKAI Women's Junior College TOKAI Women's Junior College TOKAI Women's Junior College TOKAI Women's Junior College
- 雑誌
- 東海女子短期大学紀要 = The journal of Tokai Women's Junior College (ISSN:02863170)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, pp.89-100, 2008-01-01
1 0 0 0 OA アメリカの中学生の日常あいさつ言葉について
- 著者
- 近藤 富英
- 出版者
- 信州豊南短期大学
- 雑誌
- 信州豊南短期大学紀要 = Bulletin of Shinshu Honan Junior College (ISSN:1346034X)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.1-14, 2009-03-01
1 0 0 0 OA 尼門跡の言語環境について : 尼門跡の言語生活の調査研究 (II)
- 著者
- 井之口 有一 堀井 令以知 中井 和子 Y. Inokuti R. Horii K. Nakai
- 雑誌
- 西京大學學術報告. 人文 = The scientific reports of Saikyo University. Humanistic science
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.22_a-1_a, 1958-10-25
In Part I, we touched on the ancient court-lady speechs which have persisted in Daisyozi Amamonzeki nunnery. The present paper is an attempt to explain some linguistic circumstances in this nunnery. It is difficult to classify the extremely varied assertions which have been made connecting lingustic and nonlinguistic behavior. Therefore, in this paper, we will primarily ask three kinds of nonlinguistic questions : 1) What are the natures of human relation connected with Daisyozi and Imperial palace, of social circles and their manners and customs? 2) What are the year's regular functions in Daisyozi? (the Feast of the Seven Herbs of Health, Kazyo, the moonlight party and ancient customs etc.) 3) What kinds of education and recreation were done for the nuns? (the distinctive perception of public and private affairs, Kiyo and Otugi, Genzimonogatari cards and others) Thus, we intend to treat in next Parts on the correlation between some aspects of language and non-linguistic phenomena in this nunnery.
1 0 0 0 OA 類似と相違 : 中日文化の相違を考える
- 著者
- 肖 爽
- 雑誌
- 北星学園大学大学院文学研究科北星学園大学大学院論集 = Hokusei Gakuen University Graduate School Literature Review (ISSN:18804179)
- 巻号頁・発行日
- no.4, pp.15-24, 2008-03
1 0 0 0 OA 辞儀と魅力行動 : 教育現場への提言
- 著者
- 古閑 博美 コガ ヒロミ Hiromi KOGA
- 雑誌
- 嘉悦大学研究論集
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.2, pp.63-73, 2005-10-31
学生の授業中の私語、着帽、睡眠、携帯電話の操作、飲食、化粧、教科書・ノート・筆記具の不携帯のほか、トイレや電話のための途中退室などが問題となっている。そういった態度に接し、教師はどのように対すればよいのであろうか。教育現場で、このことに悩む教師の姿がある。社会で礼儀・作法は不可欠であり、教育現場で、無作法な態度や傍若無人な振舞いが看過されてよいわけはないのである。大学は躾教育まで担っていない、との考えは排除したいものとなる。知識の教養と行動の教養を身につけた学生を育成するのは、社会のニーズでもある。教師は、教育現場にふさわしい辞儀と魅力行動を実践したい。授業中、飲食、私語、着帽などの学生がいても、注意もせず放置する教師を、心ある学生は評価していない。学生が、知的教養以外にマナーなど行動の教養を身につけることは、彼らの将来にとって重要というだけでなく、わが国の将来と直結する課題となる。魅力行動学という研究分野を、あえて唱える所以である。
1 0 0 0 OA 中国貴州省西南部の苗(ミャオ)族と布依(プイ)族の食文化(第4報) : 日常の食事状況
- 著者
- 酒井 映子 末田 香里 内島 幸江 サカイ エイコ スエダ カオリ ウチジマ ユキエ Eiko SAKAI Kaori SUEDA Yukie UCHIJIMA
- 雑誌
- 名古屋女子大学紀要. 家政・自然編 = Journal of Nagoya Women's University. Home economics・natural science
- 巻号頁・発行日
- vol.40, pp.145-153, 1994-03-05
"中国貴州省吾南部の苗族と布依族の食文化の特徴の一端を栄養的側面から明らかにすることを目的として,日常の食事状況について調査研究を行った.中国における栽培作物の事情は,1980年の「包産到戸」,すなわち農家の個人販売許可によって,食料作物から経済作物へと変化している.このような状況の中で,少数民族である苗族や布依族においても食料事情には変化が生じているものと考えられる.そこで,主として日常の食物摂取状況から両民族間の比較検討を行い,さらに,現状の栄養的問題についても若干の検討を行ったので報告する."
1 0 0 0 OA <フィールドワーク便り> ベトナム人の家への招待
- 著者
- 山川 篤子
- 出版者
- 京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科
- 雑誌
- アジア・アフリカ地域研究 (ISSN:13462466)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.2, pp.229-233, 2012-03
1 0 0 0 OA ホームステイ・ガイドブック(ホストファミリー用)
- 著者
- 南 満幸 ミナミ ミチユキ Michiyuki Minami
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.87-97, 1996-12
1 0 0 0 OA 東北各県の食育推進計画について
- 著者
- 中村 恵子 大森 桂 菅原 悦子 高木 直 長沼 誠子
- 出版者
- 日本家庭科教育学会東北地区会
- 雑誌
- 東北家庭科教育研究 (ISSN:1347331X)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.53-61, 2011-05-01
- 著者
- 下窪 拓也
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育・スポーツ・健康学会
- 雑誌
- 体育学研究 (ISSN:04846710)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, pp.87-102, 2023 (Released:2023-02-25)
- 参考文献数
- 64
The present study examined the relationship between family background and exercise habits in adulthood. Although previous studies have examined the relationship between socio-economic status (SES) and exercise habits, few have focused on the relationship between exercise habits in adulthood and SES of the family of origin. It has been suggested that the family's SES is correlated with exercise habits in childhood, and that such habits may be linked to those in adulthood. Furthermore, an individual's SES, including education and occupation, may be influenced by his/her family's SES. Thus, it is expected that a family's SES may affect an individual's exercise habits in adulthood directly or indirectly. In order to test this hypothesis, the present study examined the relationship between a family's SES and individual exercise habits in adulthood. The study was conducted at 2 different time points, as it has been found that the association between SES and exercise habits changed from the early 2000s to 2010s. Quantitative analysis of a Japanese General Social Survey performed in 2002 and 2018 was conducted. The sample was divided into 4 subgroups (according to sex and year). Multiple group structural equation modeling was employed. The dependent variable was the number of exercise days per month. The independent variables were family SES, particularly the economic condition at 15 years of age, educational attainment of the parents and the father's occupational prestige score, and the SES of the respondents, particularly their equivalent household income, educational attainment, and occupational prestige score. The results indicated that each variable in the family SES had an indirect positive effect on exercise habits in adulthood via the respondents' educational attainment. This means that those who grew up in families with a high SES tended to be more highly educated and thus more likely to exercise. Therefore, in order to reduce inequalities in exercise habits attributable to family SES, it is necessary to promote exercise habits among those with lower levels of education. Furthermore, although the father's occupational prestige score had a negative direct effect on women's exercise habits in 2002, this association was no longer statistically significant in 2018. This may be explained by changes in attitudes to gender roles and increases in sports participation between 2002 and 2018. Finally, the limitations of this research were discussed.
高年齢に達した一卵性双生児は、遺伝要因が全く同一でありながらペアの1方が認知症や糖尿病などを発症しても他方は健常なペアが多く見られることから、このペア内の差異の原因となる環境因子を解明することは予防医学の面で学術的にも社会的にも極めて重要である。本研究では、既に把握して研究協力を得ている60歳以上の高齢双生児を対象に各種臨床検査を含む総合的な健康調査を実施している。特に、生活環境因子の影響については、ライフヒストリーを中心に食品摂取、身体的運動、職業内容、家族環境等を詳細に調査している。また同時に、性格検査、人生満足度テスト、知能検査等の検査データを収集してきた。これらデータは、国際的にも稀有なデータベースとなることから予防医学の面で極めてユニークで貴重な研究となることが期待されている。平成28年度の研究計画では、エピジェネチックな遺伝子発現に関与する環境因子について前年度と同様にライフスタイル因子や性格環境因子についてはブレスローのライフスタイル指標を含めた詳細なデータを収集し遺伝疫学的分析を実施している。また、これらの分析研究については従来より共同研究を実施している大阪大学大学院異学系研究科附属ツインリサーチセンター(センター長:岩谷良則教授)との共同研究として実施している。また尾形宗士朗(日本学術振興会特別研究員)には、ライフスタイルや生活環境因子の遺伝疫学的解析に参画いただいた。これらの研究成果については、多面的な複数の学術的な国際雑誌への論文および学会発表として公表することができた。