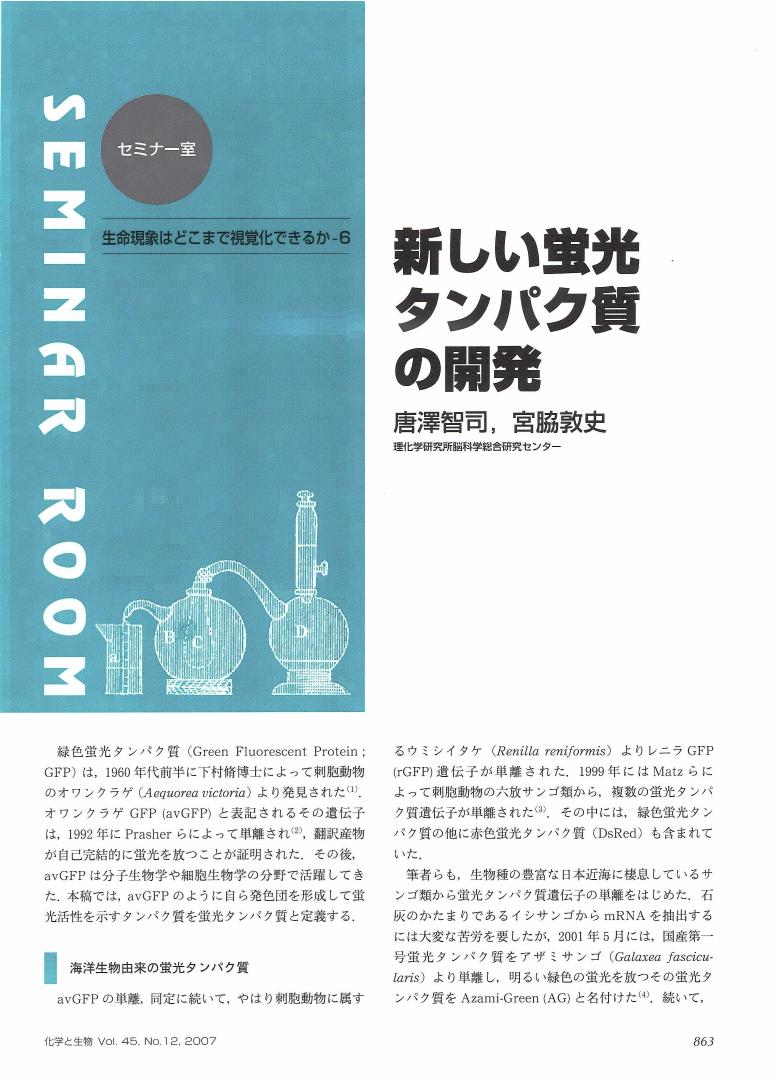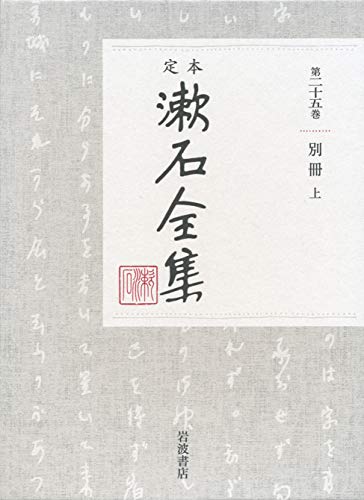1 0 0 0 OA 実験的AAアミロイドーシスにおけるFK506のアミロイド抑制効果とT細胞の関与
- 著者
- 植田 光晴 孟 薇 大林 光念 堀端 洋子 安東 由喜雄
- 出版者
- 日本臨床免疫学会
- 雑誌
- 日本臨床免疫学会総会抄録集 第35回日本臨床免疫学会総会抄録集 (ISSN:18803296)
- 巻号頁・発行日
- pp.121, 2007 (Released:2007-10-12)
【目的】 関節リウマチなどに併発するAAアミロイドーシスの発症機構は不明な点が多く確立された治療法もない。本研究ではT細胞とアミロイド沈着機構の関連に注目し、実験的AAアミロイドーシス惹起マウスに対しT細胞の活性化を抑制する免疫抑制剤であるFK506を用いアミロイド沈着抑制効果をはじめとする病態変化を解析した。 【方法】2種類の方法(急性アミロイド惹起と慢性アミロイド惹起)でマウスにAAアミロイドーシスを惹起しFK506を連日投与した。組織学的にアミロイド沈着量の変化を検討した。同時に血清中のSAA、IL-1β、IL-6、TNF-α濃度の変化をELISA法で測定した。また、肝臓でのSAAのmRNAレベルをリアルタイムRT-PCR法で検討した。更に、SCIDマウスとヌードマウスのアミロイド形成性を検討した。 【結果】FK506は用量依存性を持ってアミロイドーシス抑制効果を示した。FK506投与でアミロイド前駆蛋白質であるSAAの血清濃度とそのmRNAレベル、SAAの産生を刺激するIL-1β、IL-6は抑制されなかった。また、SCIDマウスとヌードマウスはAAアミロイドーシス惹起に対して抵抗性を示した。 【結語】 AAアミロイドーシス形成機構にT細胞の動態が関与していると考えられる。T細胞の活性化抑制をターゲットとする治療戦略はAAアミロイドーシスの新たな治療法となる可能性がある。
1 0 0 0 90年代のアダムとイヴ
- 著者
- 上野千鶴子 NHK取材班著
- 出版者
- 日本放送出版協会
- 巻号頁・発行日
- 1991
- 著者
- Laurence Picken
- 出版者
- Oxford University Press
- 巻号頁・発行日
- 1975
1 0 0 0 OA 在胎37週,38週の早期正期産児(Early term児)の臨床的検討
- 著者
- 藤中 義史 松永 麻美 高橋 恵 瀬谷 恵 小野山 陽祐 岡田 真衣子 高下 敦子 大橋 祥子 増永 健 岩田 みさ子 瀧川 逸朗
- 出版者
- 一般社団法人 日本周産期・新生児医学会
- 雑誌
- 日本周産期・新生児医学会雑誌 (ISSN:1348964X)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.1, pp.37-43, 2022 (Released:2022-05-10)
- 参考文献数
- 22
在胎37,38週のEarly term児における母体患者背景,新生児期合併症,入院率について後方視的に検討した.2014年から2017年に当院で出生した正期産児(4,013例)のうち,多胎,先天異常等を除外したEary term児894例,Full term児1,695例を対象とした.結果は,Early term群で母体合併症,帝王切開(特に予定帝王切開)症例が多く,新生児期合併症は,単変量解析ではEarly term群に新生児仮死と低血糖(< 50mg/dL)が多かったが,多変量解析では低血糖のみ有意差がみられた.新生児科入院率および再入院率は“Early term”が独立したリスク因子であった.当院では予定帝王切開を主に38週台で行っているが緊急帝王切開増加リスクは許容範囲内であり(約8%),欧米の推奨するFull termよりもやや早めに設定することは妥当と考える.
- 著者
- 沼田 知加 Chika Numata
- 雑誌
- 共立女子大学文芸学部紀要 = The Kyoritsu journal of arts and letters
- 巻号頁・発行日
- vol.66, pp.1-13, 2020-02
1 0 0 0 夏目漱石『それから』試論 -〈自然〉の実現と堕落-
1 0 0 0 OA 安倍政権の雇用・労働改革 ―解雇規制の緩和について―
- 著者
- 京谷 栄二
- 出版者
- 長野大学
- 雑誌
- 長野大学紀要 = BULLETIN OF NAGANO UNIVERSITY (ISSN:02875438)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.1, pp.1-10, 2015-07-31
1 0 0 0 OA 新しい蛍光タンパク質の開発
- 著者
- 唐澤 智司 宮脇 敦史
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.12, pp.863-868, 2007-12-01 (Released:2009-05-25)
- 参考文献数
- 12
1 0 0 0 OA 球状コンクリーションの理解と応用
- 著者
- 吉田 英一
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.129, no.1, pp.1-16, 2023-01-26 (Released:2023-01-26)
- 参考文献数
- 101
- 被引用文献数
- 1
‘コンクリーション’とは,堆積岩中に産出する塊状(主に球状をなす)岩塊のことを指し,炭酸塩,シリカや酸化鉄を主成分とするものが多い.その中でもとくに炭酸塩を主成分とするコンクリーションは,保存良好の生物の化石を内包することが多く,古くは一世紀以上も前から記載・研究がなされてきた.これまでの研究から,炭酸カルシウム球状コンクリーションの形成は,有機炭素のまとまった供給が可能となる大型の生物が出現して以降の海性堆積層中で生じる現象であり,大型の生物が出現して以降の地質時代を通しての普遍的なプロセスと言うことができる.本論では,これらの産状や成因,形成プロセスについてこれまでの研究成果をもとに述べるとともに,コンクリーション化プロセスを応用・開発した‘シーリング素材’及び,その素材を用いた実地下環境でのシーリング実証試験の現状・結果について紹介する.
1 0 0 0 ブロブ解析によるオーク材まさ目面の広放射組織模様の分類
- 著者
- 山口 穂高 仲村 匡司
- 雑誌
- 第73回日本木材学会大会
- 巻号頁・発行日
- 2023-02-03
1 0 0 0 OA 原発性ALアミロイドーシスの1例における身体表現性障害の合併
- 著者
- 谷口 豪 當山 陽介 藤田 宗久 光定 博生 諏訪 浩
- 出版者
- 一般社団法人 日本総合病院精神医学会
- 雑誌
- 総合病院精神医学 (ISSN:09155872)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.4, pp.397-402, 2011-10-15 (Released:2015-06-24)
- 参考文献数
- 11
アミロイドーシスは,線維状の異常蛋白であるアミロイドが全身諸臓器の細胞外に沈着することによって機能障害を引き起こす一連の疾患群である。われわれは,多彩な身体症状を「身体表現性障害」として精神科クリニックにて加療されていた37歳男性に対して入院精査を行い,原発性ALアミロイドーシスとの確定診断に至った。本症例は原発性ALアミロイドーシスが特異的な症状所見に乏しく早期診断が困難であるという特徴と医療者の行き過ぎた「了解」が重なり,身体疾患を見逃した結果「身体表現性障害」と診断されていたと考えた。身体科から紹介されて受診する身体表現性障害疑いの患者のなかには,今回のように確定診断の難しい身体疾患が紛れている可能性がある。身体疾患を見落とし,すべての症状を身体表現性障害による表出と誤解しないために,本疾患のように身体科専門医をしても診断が容易でない場合があることを念頭に置くことが,リエゾン精神医学の実践に不可欠である。本症例は一方でヒステリー的な性格特性と行動様式も有しており,これにアミロイドーシスの身体諸症状が取り込まれる形をとっていた。当院における診断はアミロイドーシスと身体表現性障害の併存とした。われわれは,本人の性格や葛藤状況を適切に「了解」し,それに基づく治療的配慮を施しながら慎重に診断作業を継続したことにより,身体疾患の確定診断を得た。精神科診療における「了解可能性」の判断の確かさが問われていることに気づかされた症例であった。
1 0 0 0 OA 日本におけるオピオイド鎮痛薬の依存と嗜癖の状況
- 著者
- 佐藤 史弥 廣瀬 宗孝
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.3, pp.330-334, 2018-05-15 (Released:2018-06-23)
近年,欧米を中心にオピオイド使用量は増加し続けているが,日本においても例外ではない.高齢化に伴うがんサバイバーの増加により,慢性非がん性疼痛を抱えたがん患者が増加し,オピオイドの使用の判断が難しくなる症例も多くみられる.慢性非がん性疼痛で適応のあるオピオイドも増えてきているが,どのように使用すればよいだろうか.臨床の場において,多くのペインクリニシャンが乱用や嗜癖につながるケースを経験し始めているが,実際どの程度のリスクがあり,どのようなことに注意すればよいだろうか.日本におけるオピオイド使用と乱用・嗜癖の現状について整理する.
1 0 0 0 液体金属と共存するFeCrAl合金のクラッド技術開発
- 著者
- 大野 直子 長野 太郎
- 雑誌
- 日本金属学会2023年春期(第172回)講演大会
- 巻号頁・発行日
- 2023-01-31
1 0 0 0 ロボットと倫理のこれからの展開に向けて
- 著者
- 松浦 和也
- 出版者
- 一般社団法人 日本ロボット学会
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.1, pp.23-26, 2023 (Released:2023-01-21)
- 参考文献数
- 22
- 著者
- Yoshimasa SASAKI Tsutomu NOZAWA-TAKEDA Kenzo YONEMITSU Tetsuo ASAI Hiroshi ASAKURA Hidetaka NAGAI
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.7, pp.1029-1033, 2022 (Released:2022-07-25)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 1
As free-living crows are a potential source of Campylobacter infections in broilers and cattle, we characterized Campylobacter spp. isolated from crows using multilocus sequence typing and antimicrobial susceptibility testing. We obtained 82 samples from 27 birds captured at seven different times using a trap set in Tochigi prefecture, Japan. Campylobacter jejuni was isolated from 55 (67.1%) of the 82 samples and classified into 29 sequence types, of which 21 were novel. Tetracycline and streptomycin resistance rates were 18.2% and 3.6%, respectively. These results show that most types of C. jejuni infecting crows differ from those isolated from humans, broilers, and cattle. Thus, the importance of free-living crows as reservoirs of Campylobacter infections in broilers and cattle may be limited.
1 0 0 0 OA 精神疾患を有する頭頸部癌症例の検討
- 著者
- 橋本 和樹 中島 寅彦 藤 賢史 安松 隆治 小宗 静男
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本頭頸部外科学会
- 雑誌
- 頭頸部外科 (ISSN:1349581X)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.2, pp.195-199, 2014 (Released:2015-02-11)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1 1
精神疾患を有する頭頸部癌症例においては,しばしば標準治療の遂行が困難となる。今回2008年1月から2013年6月の間に当院にて入院加療を行った精神疾患を合併する頭頸部癌症例27例について,治療経過や合併症に関する検討を行った。高度の認知障害を有する6例では治療を開始できなかった。放射線治療症例においては,治療の長期化に伴い精神疾患の増悪や身体合併症の出現がみられ,治療中断となる症例もみられた。手術を施行した症例では術後せん妄が多く,再建症例では皮弁に関連した合併症率が高い傾向を認めた。精神疾患合併頭頸部癌症例においては,進行度や全身状態,また精神社会的背景を十分に考慮した上での治療適応検討が重要と考える。
1 0 0 0 OA 冷凍血の凍結保存期間および有効期間の延長について
- 著者
- 堀江 真理子 堀木 ちさと 飯田 俊二 大谷 智司 岡田 基文 平井 健策 大久保 康人
- 出版者
- 一般社団法人 日本輸血・細胞治療学会
- 雑誌
- 日本輸血学会雑誌 (ISSN:05461448)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.5, pp.651-655, 1991-11-15 (Released:2010-03-12)
- 参考文献数
- 4
In the United States, the FDA licenses Red Blood Cells Frozen (RBCF) up to 10 years and the AABB (AMERICAN ASSOCIATION OF BLOOD BANKS)'s Standards allow frozen storage of blood for routine transfusion up to 10 years.But in Japan, the storage period of RBCF for routine transfusion allowed is 5 years and that of the thawed, deglycerolized red blood cells (DRBC) is only 12 hours at 4-6°.The quality of RBCF stored for 5 years or 10 years was investigated to extend the storage period of RBCF and DRBC.ATP levels and morphology scores of DRBC stored for 10 years were high as those of DRBC stored for 5 years but 2, 3-DPG levels were slightly low.The hemolysis of DRBC immediately after deglycerolization was low, but increased rapidly with the storage. The result obtained indicated that the quality of the DRBC was maintained in good conditions. We would like to propose to extend the storage period of the RBCF up to 10 years.
1 0 0 0 OA あぶみ骨手術が著効を示したあぶみ骨脱臼症例
- 著者
- 中野 淳 稲福 繁 呉 孟達 中山 明峰 石神 寛通
- 出版者
- 耳鼻咽喉科臨床学会
- 雑誌
- 耳鼻咽喉科臨床 補冊 (ISSN:09121870)
- 巻号頁・発行日
- vol.2000, no.Supplement104, pp.37-41, 2000-10-31 (Released:2012-11-27)
- 参考文献数
- 11
We report a patient with traumatic perilymphatic fistula caused by an earpick. Exploratory tympanotomy was performed via endoaural incision. The patient was found to have a dislocated stapes in the vestibule. The stapes was removed, and no perilymphatic leakage from the oval window was seen. Jugular pressure was also performed with no lymphatic leakage. We then injected physiological salt solution at 37°C into the oval window. Lastly, stapes surgery was perfomed and a piece of fascia was placed over the perforation in the tympanic membrane using fibrin glue. The patient's operation was performed 3 days after trauma and improvement of vertigo and hearing (sensory and air-bone gap) was obtained after surgery.