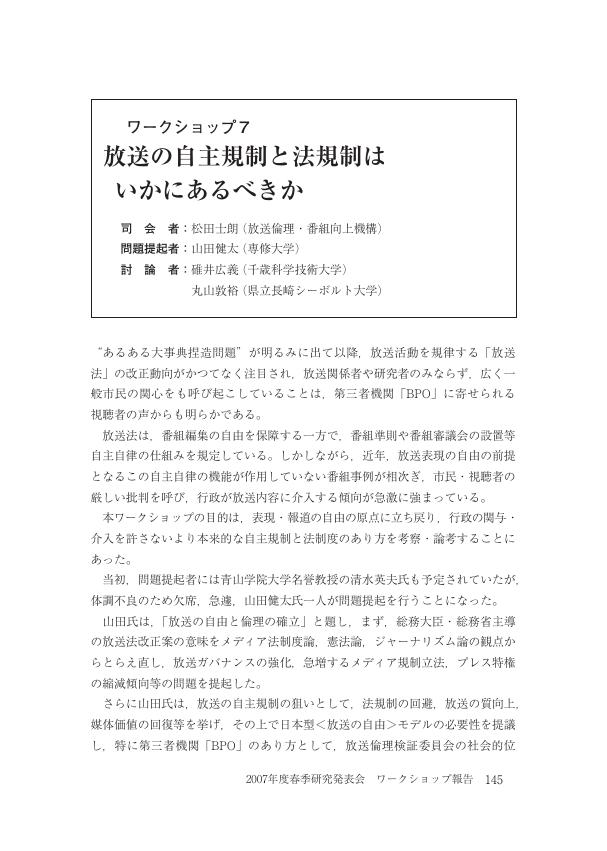- 著者
- 松田 士朗
- 出版者
- 日本メディア学会
- 雑誌
- マス・コミュニケーション研究 (ISSN:13411306)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, pp.145-146, 2008-01-31 (Released:2017-10-06)
- 著者
- Yoshino Ishizaki Masaya Ogura Chihiro Takahashi Maya Kaneko Akari Imura Yuta Shiino
- 出版者
- The Plankton Society of Japan, The Japanese Association of Benthology
- 雑誌
- Plankton and Benthos Research (ISSN:18808247)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.1-12, 2023-02-28 (Released:2023-03-02)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 1
Lack of evidence prevents an understanding of how ghost crabs create burrows underground. For the reconstruction of ichnogenetic stages in the burrows of ghost crabs, we report on how the burrows of the ghost crab Ocypode stimpsoni from the foreshore and backshore on Ikarashi beach, Niigata, Japan are created. Plaster casting of the burrows reveals detailed morphology with bioglyphs on the burrow wall. The casts of burrows show a variety of morphologies, such as J- and Y-shapes. Based on the burrow ichnogeny, J-shaped burrows were well constructed at a shallower level of the waterline underneath the beach, occasionally creating a second opening of the burrow. In turn, Y-shaped burrows were constructed at a deeper waterline, thereby recycling and reburrowing the deepest part of the J-shaped burrow. As a result, the total depth of Y-shaped burrows tends to be larger than that of J-shaped burrows. The depth and mean diameter of the burrows range from 3.3–37.6 cm and 9.28–31.54 mm, respectively, and the depths are apparently shorter than those on a Pacific beach. The lines of evidence suggest that the morphological features of burrows in Ikarashi beach are attributed to a smaller difference in tidal level in the Sea of Japan, where the available space for burrows ought to be limited by the waterline under the ground.
- 著者
- 大橋 きょう子 Kyoko Ohashi
- 雑誌
- 學苑 = GAKUEN (ISSN:13480103)
- 巻号頁・発行日
- vol.815, pp.84-97, 2008-09-01
食用油脂が日常の食生活に普及し始め,油脂調理が家庭に定着する兆しが見えたと考えられる明治時代末期から大正時代末期までの19年間における食用油脂を用いた調理について,当時の婦人雑誌のひとつである『婦人之友』を調査対象として,食用油脂の種類および油脂調理の実態を調査し,特徴を明らかにした。日本料理は胡麻油を用いて揚げる調理が,支那料理では胡麻油およびラードを用いて妙める調理が多かった。日本料理および支那料理は,油脂を単独で使用する場合が多く,油脂の種類および油脂を用いた調理法としては,炒める,揚げる,焼く調理に限られていた。これに対して西洋料理は,炒める,揚げる,焼く(焼き付ける),煮る(煮込む),加熱用ソース,製菓材料,非加熱ソース,風味付けなどにバターをはじめとした食用油脂を使用し,しかもひとつの料理に複数の油脂を用いていた。特に西洋料理におけるバターの使用頻度は他の食用油脂に比べて最も多く,その調理方法および利用範囲も他の油脂類に比べて広いことが認められた。西洋料理同様に和洋折衷料理においても油脂を複数用いた調理が多く,調理法も多種多様であった。西洋料理の普及とともに,和洋折衷料理が誕生し定着した経緯の中で,油脂を用いた調理は増加傾向を示し,油脂の調理法は多様化したことが明らかとなった。明治時代以来,ひたすら西洋料理に目を向けその普及に努めてきた社会の風潮は,婦人雑誌の料理記事にも表れていたことを認めた。明治から大正時代にかけての油脂調理の大半は,西洋料理および和洋折衷料理であり,油脂を多量に使用する支那料理が一般家庭で日常的に調理できるには至っていなかったことが分かった。
1 0 0 0 OA 料理習得に対する高校までの調理実習の影響
- 著者
- 堀 光代 平島 円 磯部 由香 長野 宏子
- 出版者
- 岐阜市立女子短期大学
- 雑誌
- 岐阜市立女子短期大学研究紀要 = Bulletin of Gifu City Women's College (ISSN:09163174)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, pp.55-59, 2010
A survey was conducted among 534 college freshmen (2008-2009, age:18-20) to investigate effects of cooking practices in home economics classes at junior high school and high school on students' cooking skills. With increasing the number of times they have experienced cooking practices, the number of students, who liked cooking and had a specialty dish, increased. Students with experiences in cooking have acquired cooking skills compared with students without experiences in cooking at junior high and high schools. We found that cooking practices at schools were quite effective on learning cooking skills for students, especially for students, who did not cook home.
1 0 0 0 OA 昭和時代における食用油脂及び油脂調理について(1)(1926年~1935年)
- 著者
- 大橋 きょう子 Ohashi Kyoko
- 雑誌
- 學苑 = GAKUEN (ISSN:13480103)
- 巻号頁・発行日
- vol.851, pp.26-38, 2011-09-01
1 0 0 0 OA アリストテレスから学ぶ貨幣とマクロ経済学
- 著者
- 山﨑 弘之
- 出版者
- 国士舘大学政経学会
- 雑誌
- 國士舘大學政經論叢 = SEIKEI-RONSO = THE REVIEW OF POLITICS AND ECONOMICS (ISSN:05869749)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.1, pp.21-52, 2018-06-25
目次1.はじめに2.演繹論:プラトンからアリストテレスへ3.比例論:アリストテレスから現代へ4.社会は常に非通約性と通約性が共存する5.貨幣とはノミスマ (νóμισμα) である6.メンガーに見られるアリストテレスの思想7.アリストテレスから見える現代マクロ経済学への警鐘
1 0 0 0 OA 日本人学生のレポートに見られる「のだ」の使用実態 : レポートで使用しないほうがいい用法
- 著者
- 苗田 敏美
- 出版者
- 姫路獨協大学大学院言語教育研究科日本語コース
- 雑誌
- 日本語教育論集 = Working papers in teaching Japanese as a foreign language = Working papers in teaching Japanese as a foreign language (ISSN:18818552)
- 巻号頁・発行日
- no.28, pp.23-30, 2019-03
1 0 0 0 日本人工関節学会誌
- 著者
- 日本人工関節学会事務局編
- 出版者
- 日本人工関節学会
- 巻号頁・発行日
- 1996
1 0 0 0 OA 下顎骨切除後に神経再生誘導チューブによる下歯槽神経再建を行った1例
- 著者
- 藤城 建樹 荘司 洋文 北詰 栄里 岡村 尚 吉田 和正 辺見 卓男
- 出版者
- 公益社団法人 日本口腔外科学会
- 雑誌
- 日本口腔外科学会雑誌 (ISSN:00215163)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.8, pp.486-491, 2018-08-20 (Released:2018-10-22)
- 参考文献数
- 15
If the inferior alveolar nerve is resected by surgery for a mandibular tumor, the perception of its dominant area will be permanently lost. When we perform nerve reconstruction, autologous nerve grafting is usually performed, but there is a fault that we produce new neuropathy in the nerve-donor site. The nerve conduit, which is an artificial material, begins to be used for nerve amputation and deficiency, but there is no report about mandibular tumors. The patient was a 20-year-old man with mandibular ameloblastoma. We performed hemimandibulectomy, mandibular reconstruction with a free iliac bone graft, and inferior alveolar nerve reconstruction with a nerve conduit. The postoperative course was uneventful. Neurosensory disturbance of the mental nerve improved 5 months after surgery, and approximately normally status was recovered after 10 months. Currently, 2 years have passed since the operation, and there are no obvious abnormalities.
1 0 0 0 OA 転移性皮膚癌32症例の統計学的観察
- 著者
- 福井 佳子 徐 信夫 前島 精治 酒谷 省子 草壁 秀成 清金 公裕
- 出版者
- Meeting of Osaka Dermatological Association
- 雑誌
- 皮膚 (ISSN:00181390)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.5, pp.534-543, 1995 (Released:2010-08-25)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 9
昭和52年4月から平成7年3月までの18年間の転移性皮膚癌32症例を集計した。同期間内に当科外来を受診した新患総数に対する転移性皮膚癌患者の頻度は0.04%であった。年齢構成は平均58.9歳 (男: 59.2, 女: 58.6), 原発巣分類では胃癌 (9例)・乳癌 (8例)・肺癌 (7例) が多く, 全体の75%を占めていた。転移部位は胸腹部に多くみられ, 多発型が多かった。臨床像は結節型, 組織像は腺癌が圧倒的に多かった。原発巣発見後皮膚転移までの平均期間は36カ月で, 乳癌は長い傾向にあった。皮膚転移後死亡までの平均期間は5カ月で, 6カ月以内に死亡する例が全体の75%を占めていた。
1 0 0 0 OA イヌ回虫性脊髄炎の1例
- 著者
- 石原 智彦 小澤 鉄太郎 根本 麻知子 新保 淳輔 五十嵐 修一 田中 惠子 西澤 正豊
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.96, no.1, pp.141-143, 2007 (Released:2009-12-01)
- 参考文献数
- 8
イヌ回虫性脊髄炎は幼虫移行症の一つであり,まれな神経感染症である.症例は左半身のしびれ感にて発症した21歳女性で,頻回に生の牛レバー食歴があった.脊髄MRIで第4~8胸椎レベルに病変を認め,脳脊髄液中の好酸球出現と血清IgE上昇を認めた.血清,脳脊髄液中のイヌ回虫抗体価上昇を認め,イヌ回虫性脊髄炎と診断した.アルベンダゾールの内服で臨床症状は改善し,抗体価も低下した.脊髄炎の鑑別診断の一つにイヌ回虫性脊髄炎も考慮すべきと考え,報告する.
1 0 0 0 OA 農業用移動ロボットの自動充電システム
- 著者
- 井小萩 湧 高橋 庸平 北澤 椋太 鳥山 渓太 小林 稜平 小山内 太郎 ミヤグスク レナート 尾崎 功一
- 出版者
- 自動制御連合講演会
- 雑誌
- 自動制御連合講演会講演論文集 第65回自動制御連合講演会
- 巻号頁・発行日
- pp.530-532, 2022 (Released:2022-12-15)
1 0 0 0 OA 綺麗な娘(夢幻歌劇「クリスピーノ」より)
1 0 0 0 OA 金属塩および酵素反応を用いた一液型タンニン複合化天然系凝集剤の創出
海藻凝集剤と植物凝集剤は助剤を必要とする二液型の凝集剤であり、その性能は合成系高分子凝集剤に比べて劣るものである。本研究では、酵素によるタンニンの複合化反応、または金属塩を用いて、海藻凝集剤および植物凝集剤を一液型とすること、および、タンパク質吸着能の付与などの高性能化を目指した。金属塩の試験ではマグネシウム塩とカルシウム塩について検討し、いずれの場合も一液型化が可能であったが、比較的低濃度のカルシウム塩を所定の方法で加えることで、海藻の凝集作用成分であるアルギン酸を効果的に一液型とすることができた。また、得られる一液型凝集剤は高い凝集性能を示すことがわかった。
1 0 0 0 IR 三星堆出土遺物の文化史的意義について--私的備忘録として
- 著者
- 稲畑 耕一郎
- 出版者
- 早稻田大學中國文學會
- 雑誌
- 中国文学研究 (ISSN:03850919)
- 巻号頁・発行日
- no.22, pp.124-128, 1996-12
1 0 0 0 OA ぼかし表現「とか」についての考察
- 著者
- 劉 暁傑
- 出版者
- 相愛大学人文科学研究所
- 雑誌
- 相愛大学人文科学研究所研究年報 (ISSN:18817483)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.48-35, 2011-03
1 0 0 0 OA 絵本を介した親子のコミュニケーションの発達
- 著者
- 吉田 佐治子 Sachiko YOSHIDA
- 雑誌
- 摂南大学教育学研究
- 巻号頁・発行日
- vol.7, 2011-01
"絵本の読み聞かせ場面における親子のやりとりを長期にわたり追跡し,横断的・縦断的に検討したものを概括した.追跡調査は継続中であるが,0歳から4歳までの経過からは,各親子で独自の読み聞かせスタイルがあること,そのスタイルは,こどもが発達しても大きくは変わらないことが示された"
- 著者
- 澤田 康徳 鈴木 享子 小柳 知代 吉冨 友恭 原子 栄一郎 椿 真智子
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- E-journal GEO (ISSN:18808107)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.40-53, 2023 (Released:2023-03-08)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 1
本研究ではGLOBEプログラムを例に,身近な自然環境調査成果の全国発表会に関する感想文から,生徒と教員の発表会のとらえ方および生徒の調査の継続志向の特徴を示した.発表会のとらえ方には,生徒の参加や発表,調査に関する観点が生徒と教員に認められた.発表会の多様性は生徒に特徴的な観点で,日本各地や他の学校の環境およびその認識などを含む.すなわち生徒において全国発表会は,自然環境の認識や理解を日本規模で深める場の機能を有する.また,異学年間の活動の継続を考え今後の活動意欲につながっている.教員において全国発表会は,充実した調査の継続に重要な自校の測定環境をとらえなおす場として機能している.生徒の調査の継続志向は,科学的思考より調査結果や探究活動過程全体,生徒をとりまく人と関連することから,継続的調査に,発表会においてとりまく人などと連関させた生徒の振り返りや教員の測定環境のとらえなおしが重要である.