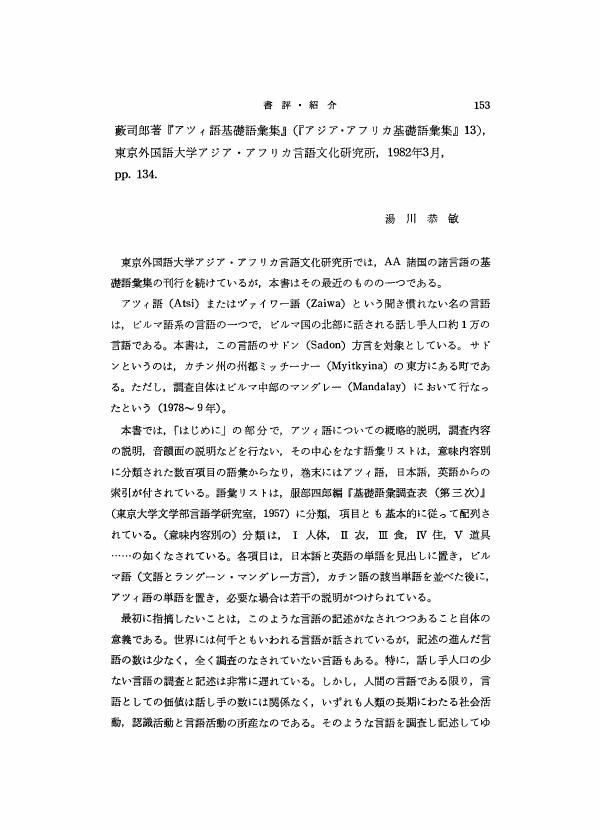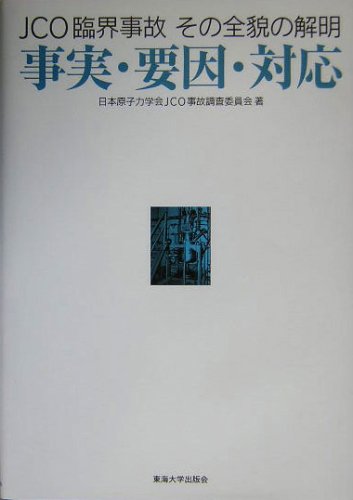1 0 0 0 OA 老年者の栄養
- 著者
- 小柳 達男
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1Supplement, pp.105-108, 1966-03-31 (Released:2009-11-24)
1 0 0 0 OA 遺伝性疾患の原因遺伝子単離と ゲノム異常発生分子機構に関する研究
- 著者
- 水口 剛
- 出版者
- 横浜市立大学医学会
- 雑誌
- 横浜医学 = Yokohama Medical Journal (ISSN:03727726)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.4, pp.635-643, 2019-10-30
希少遺伝性疾患の原因は,現在でも全体の40-60%程度の疾患について未解明のままである. 疾患を引き起こす遺伝子変異の種類やサイズは多様で全てを網羅的にカバーするゲノム解析技術は存 在しない.従って未解明の疾患については既存の解析技術の穴をうめるような新規解析技術の適用が 有用である.実際,染色体核型分析,FISH法,キャピラリーシーケンサー,マイクロアレイ,次世 代ショートリードシーケンサーに代表される染色体・ゲノム解析法はそれぞれ異なる解像度を有し, 新規解析技術の登場が新たな種類・サイズの病的変化を明らかにしてきた.本稿ではこれらの解析技 術を駆使して筆者が行ってきた遺伝性疾患の原因・病態解明を目的とした多角的取り組みについて紹 介する.
1 0 0 0 日本の汽車 : ドラフトのひびきを追って
1 0 0 0 さよなら蒸気機関車 : 植松宏嘉鉄道写真集
1 0 0 0 OA 書評・紹介 藪司郎 著 『アツィ語基礎語彙集』
- 著者
- 湯川 恭敏
- 出版者
- 日本言語学会
- 雑誌
- 言語研究 (ISSN:00243914)
- 巻号頁・発行日
- vol.1983, no.84, pp.153-155, 1983-11-15 (Released:2013-05-23)
- 著者
- 床井 啓太郎
- 出版者
- 北海道大学文学部西洋史研究室
- 雑誌
- 西洋史論集
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.76-84, 2000-03-08
1 0 0 0 OA 授乳方法がその後の口腔機能発達に及ぼす影響 アンケート調査による食行動の検討
- 著者
- 中西 正尚 山田 賢 中原 弘美 田村 康夫
- 出版者
- 一般財団法人 日本小児歯科学会
- 雑誌
- 小児歯科学雑誌 (ISSN:05831199)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.5, pp.669-679, 2005-12-25 (Released:2013-01-18)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 2
本研究は,授乳方法と口腔機能発達との関連を検討する目的で,2歳児から5歳児の1357名(平均年齢3歳7か月)の保護者を対象にアンケートによる調査を行いその結果を分析,検討した.出生後3か月までの授乳方法から母乳哺育群(Br群),混合乳哺育群(Mix群),人工乳哺育群(Bo群)の3群に分類すると,Br群が399名(29.4%),Mix群が811名(59.8%)で,Bo群が147名(10.8%)であった.離乳に関して,離乳食開始時期,離乳食終了時期,断乳時期ともに授乳方法問に差は認められなかった.現在の食べ方について,18項目中,咀嚼の上手下手,前歯で噛みきる食べ物,食べ物の吐き出し,食べこぼし,食生活のリズム,食事の自立の6項目において群間の有意差が認められ,いずれもBr群が良好な発達を示していた.その他の関連項目で,吸指癖,おしゃぶり,言語発達の遅れ,性格面に有意差が認められた.以上より,アンケートではBr群が全体的に良好な咀嚼発達を示し,Bo群の食行動に一部問題がみられたことから,授乳方法はその後の咀嚼の発達に少なからず影響を及ぼしていることが示唆された.
1 0 0 0 JCO臨界事故その全貌の解明 : 事実・要因・対応
- 著者
- 日本原子力学会JCO事故調査委員会著
- 出版者
- 東海大学出版会
- 巻号頁・発行日
- 2005
1 0 0 0 OA 文科大学史誌叢書
- 著者
- 坪井九馬三, 日下寛 校訂
- 出版者
- 吉川半七等
- 巻号頁・発行日
- vol.家忠日記 二, 1897
1 0 0 0 OA 一過疎農山村における家族介護者の老人介護と農業両立の意味に関する記述的研究
- 著者
- 麻原 きよみ
- 出版者
- 公益社団法人 日本看護科学学会
- 雑誌
- 日本看護科学会誌 (ISSN:02875330)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.1, pp.1-12, 1999-03-25 (Released:2012-10-29)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 6 1
本研究は, 過疎農山村における家族介護者の老人介護と農業両立の意味を探求することを目的とした. 方法論としてエスノグラフィを用いた. データ収集は27名の要介護老人の介護者, 住民および保健医療福祉関係者に対するインタビュー, 参加観察, 村の書類, 資料等の検討であった. 得られたデータを方法と動機の観点から分析した結果, 以下のことが明らかとなった.(1) 農村介護者は介護と農業両立の仕事の調整方法として, 1日の生活時間に両者を組み込でいく <介護と農業の組み込み戦略> を用いていた.(2) 介護と農業両立の動機づけには, <伝統的価値規範の内面化>, <村落共同体的集団原理に従う>, <農業継続困難な現状の受け入れ>といった消極的動機づけ, <老人に対する愛情>, <生き甲斐としての農業>, <行為へ価値づける> 積極的動機づけがみられ, これは介護と農業を調整する自己認識の調整であった.(3) 農村介護者の消極的動機づけによる介護と農業継続の内面化, および自らの主体性に意味づける積極的動機づけから, <農村介護者は介護と農業を両立できることに自己存在の意味を見出す> をテーマとして抽出した. このテーマは, 農村介護者の現実への対処行動だけでなく, 自己を積極的に意味づけて生き抜く, 農村介護者の生き方をも示していた.以上のことから, 農村介護者の伝統的価値規範を問題意識化することなく受容する認識面, およびそれを支持する社会的環境面の問題を提示するとともに, 介護と農業継続に関する農業の重要性について述べ, 地域看護実践のあり方を考察した.
1 0 0 0 OA 南大東島へのニューギニアヤリガタリクウズムシの侵入
- 著者
- 松井 晋 赤谷 加奈 松尾 太郎 杉浦 真治
- 出版者
- 日本応用動物昆虫学会
- 雑誌
- 日本応用動物昆虫学会誌 (ISSN:00214914)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.3, pp.143-146, 2010-08-25 (Released:2010-08-28)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 1 1
Introduction of the snail-eating flatworm Platydemus manokwari has caused the extinction and decline of native land snails on tropical and subtropical islands. Here we report the first record of P. manokwari from Minami-daito Island in the oceanic Daito Islands (western Pacific) which support an endemic land snail fauna. Platydemus manokwari was found in July 2004, July 2008, and June 2009 on Minami-daito Island. To clarify the effect of P. manokwari on land snail survival in the field, we examined survival rates of snails experimentally placed in the areas where P. manokwari were found in June 2009. Despite the presence of P. manokwari, we found little evidence of predation, suggesting that the density of P. manokwari was not high enough to impact snails on Minami-daito Island.
1 0 0 0 OA グループでのデザイン活動の為の発想支援ツールの提案
- 著者
- 高野 悠人 齋藤 共永
- 出版者
- 一般社団法人 日本デザイン学会
- 雑誌
- 日本デザイン学会研究発表大会概要集 日本デザイン学会 第58回研究発表大会
- 巻号頁・発行日
- pp.130, 2011 (Released:2011-06-15)
本研究ではグループでのデザイン活動における発想を支援するツールを研究し提案することを目的とする。グループメンバー同士のコミュニケーションを促進し、メンバー間の情報共有を効果的にサポートするツールを目指す。デザインにおけるコミュニケーション・情報共有で重要なことは各個人のアイデアを単に集めて見せ合うだけではなく、それらのアイデアを関連づけ、統合して、より高度の『集合知』にまとめることである。ブレインストーミングやマインドマップでの考え方を応用しつつ、概念しか扱えないそれらの方法をビジュアルイメージを扱うことができ、デザインに応用することができるものを活動する。文献調査や観察実験をとおしてグループでの発表を支援する為に何が必要かを抽出し、それをもとに仮説をたて、プロトタイプを制作し、使用実験により有効性を検証していく。
1 0 0 0 OA 世界トップレベルで活躍するケニア人長距離ランナーの体力・形態特性
- 著者
- 吉岡 利貢 中垣 浩平 中村 和照 向井 直樹 鍋倉 賢治
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育・スポーツ・健康学会
- 雑誌
- 体育学研究 (ISSN:04846710)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.1, pp.237-248, 2012 (Released:2012-06-02)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 4 2
The purpose of this study was to compare the physiological and morphological characteristics of J. Ndambiri, a Kenyan world-class long-distance runner (10,000 m personal best: 27:04.79), with runners belonging to the national corporate team (29:32.18±0:30.35). Oxygen uptake (VO2), heart rate, blood lactate concentration and stride frequency were measured during submaximal exercise on a treadmill (270, 290, 310, 330, 350 and 370 m/min velocities with 1% inclination). Peak oxygen uptake (VO2peak) was determined during the maximal exercise test. In addition, morphological parameters (length of thigh and shank, maximum circumference of thigh and shank, and cross-sectional area of the trunk, thigh and shank muscles) were determined using a tape measure and magnetic resonance imaging (MRI). Ndambiri was superior to Japanese runners in terms of not only running economy (65.0 vs 69.8±1.9 ml/kg/min at 330 m/min), but also blood lactate concentration (1.50 vs 2.59±0.74 mmol/l at 330 m/min), heart rate (159.8 vs 170.8±4.0 bpm at 330 m/min) during the submaximal running test and VO2peak (80.8 vs 76.3±2.4 ml/kg/min). In addition, the morphological characteristics of Ndambiri were also quite different from those of Japanese runners. In particular, Ndambiri's maximum shank circumference was much smaller than that of Japanese runners (32.0 vs 35.8±1.8 cm). Furthermore, the cross-sectional area of the gastrocnemius muscle, which composes the shank, was significantly correlated with the oxygen cost of running at 330 m/min (r=0.700). These findings indicate that the superior performance of Ndambiri is attributable to various factors such as a higher VO2peak, lower blood lactate concentration and heart rate, as well as running economy. In the future, it will be necessary to clarify the factors supporting these relationships between physiological variables and morphological characteristics.
- 著者
- Anne Marit VIK Sayaka TSUCHIDA Atsushi KOBAYASHI Yuki AKIBA Mei HARAFUJI Kazunari USHIDA
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.9, pp.1221-1224, 2022 (Released:2022-09-01)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1
Egg yolk from captive and wild Japanese rock ptarmigan were analyzed for fatty acid composition. Compared to commercially reared poultry species, the ptarmigan yolk samples displayed higher level of polyunsaturated fatty acids as opposed to monounsaturated fatty acids. The difference between the commercial controls and ptarmigan were larger than the difference between groups of ptarmigan, indicating that the fatty acid profile of Japanese rock ptarmigan might be partly attributed to genetic factors rather than feed, despite wild and captive birds having vastly different diets, and captive birds having been artificially bred for several generations.
1 0 0 0 OA 治るか治らないかという議論はしない耳鳴り治療(押さえておきたい!心身医学の臨床の知30)
- 著者
- 五島 史行
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.7, pp.659-662, 2011-07-01 (Released:2017-08-01)
- 参考文献数
- 10
1 0 0 0 OA 電気通信施設
- 著者
- 日本電信電話公社施設局 編
- 出版者
- 電気通信協会
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.4, 1982-04
1 0 0 0 OA NTT施設
- 著者
- 日本電信電話株式会社研究開発技術本部技術情報センタ 編
- 出版者
- 電気通信協会
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.4, 1988-04
1 0 0 0 OA IT企業の新入社員を対象としたストレスマネジメント行動促進プログラムの評価
- 著者
- 長井 麻希江 森河 裕子
- 出版者
- 日本産業看護学会
- 雑誌
- 日本産業看護学会誌 (ISSN:21886377)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.1, pp.24-30, 2019-10-02 (Released:2019-11-21)
- 参考文献数
- 18
【目的】本研究の目的は,集団認知行動療法を基盤としたストレスマネジメント行動促進プログラムを立案し,IT 企業の新入社員を対象に介入,評価することである.【方法】ストレスに関する講義とグループ討議により各自のストレス状況改善アクションプランを立案し,その後日記をつけるというプログラムを立案した.新入社員56 名を対象に実施し,介入前後の職業性ストレス,ストレス反応,コーピングを調査した.【結果】全プログラム参加者は22 名(39.3%,男性18 名,女性4 名)だった.①全対象者の介入前後における各指標の有意な変化はなかった.②アクションプランに取り組んでいた群とアクションプランに関する記載がなかった群に分けて比較したところ,取り組んでいた群の感情表出コーピングが有意に高まっていた.【結論】講義,グループ討議,セルフモニタリングというストレスマネジメントプログラムは,感情表出の行動変容が起こる可能性がある.