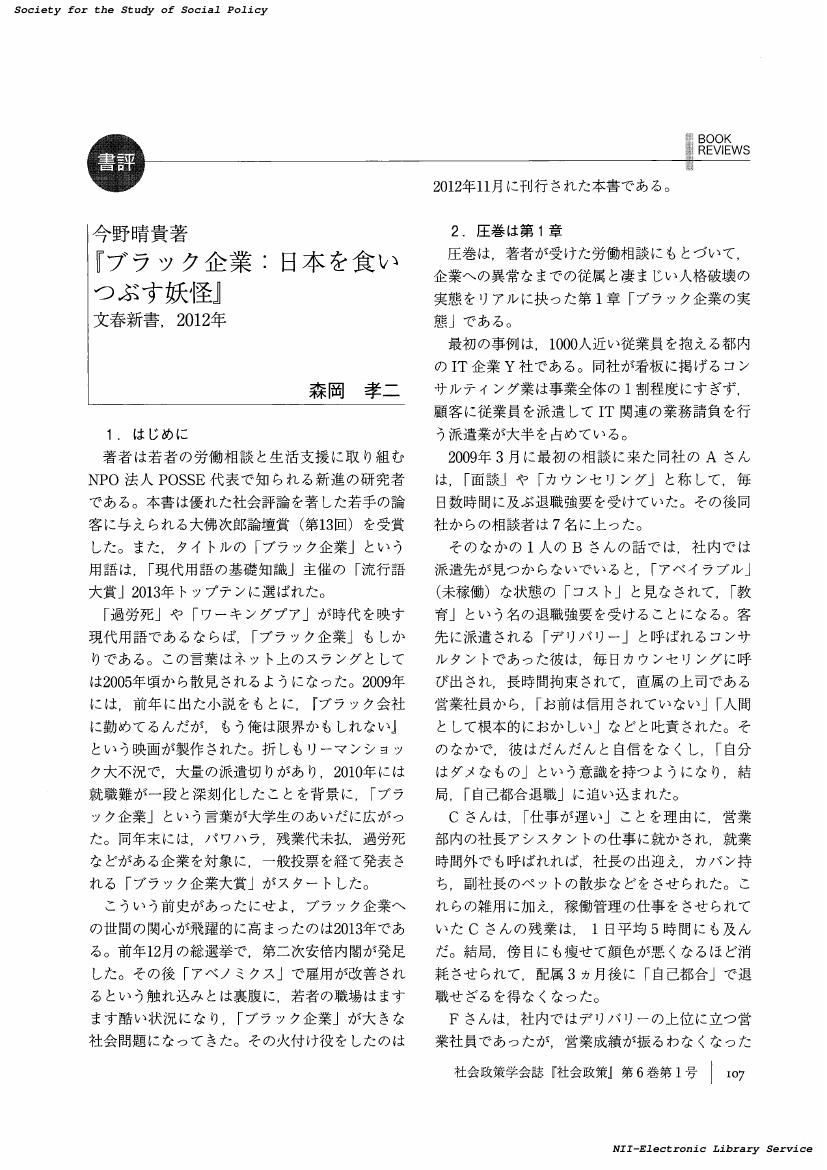1 0 0 0 OA 作曲家としての幸田延
- 著者
- 平高 典子
- 雑誌
- 芸術研究:玉川大学芸術学部研究紀要 (ISSN:18816517)
- 巻号頁・発行日
- no.9, pp.1-14, 2018-03-31
幸田延(1870明治3―1946昭和21)は音楽教育家として知られているが、ウィーン留学時以来、作曲活動も鋭意行っていた。本稿では、演奏や印刷されていないと考えられるものも含め、残された作品を紹介・解説したうえで、幸田の作風や作曲活動の意義と限界について考察する。
1 0 0 0 OA 自衛隊災害派遣法制の一考察
- 著者
- 田村 達久
- 出版者
- 早稲田大学法学会
- 雑誌
- 早稻田法學 (ISSN:03890546)
- 巻号頁・発行日
- vol.95, no.3, pp.525-550, 2020-03-30
1 0 0 0 OA SR11000モデルH1におけるバリア同期の高速化手法
- 著者
- 中村 友洋 高山 恒一 青木 秀貴 松居 昭宏 助川 直伸
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告計算機アーキテクチャ(ARC)
- 巻号頁・発行日
- vol.2003, no.119(2003-ARC-155), pp.69-74, 2003-11-27
共有メモリ型計算機において高い並列実効性能を実現するには,並列処理の起動終結時のバリア同期オーバーヘッドを低減することが重要である。ノードを構成する複数のマイクロプロセッサを一斉にしかも高速に起動させる協調型マイクロプロセッサ機構により高い並列実効性能を達成したスーパーテクニカルサーバSR8000の後継シリーズの初代モデルであるSR11000モデルH1は,キャッシュシステムを利用したソフトウェアによるバリア同期方式により,高速なバリア同期処理を実現することで,高い並列実効性能を達成する。本稿では高速バリア同期方式の概要とその高速化手法について述べ,SR11000モデルH1による性能評価結果を紹介する。
1 0 0 0 OA SR11000におけるソフトウェアプリフェッチ手法の評価
- 著者
- 青木 秀貴 處 雅尋 本川 敬子 五百木 伸洋 齋藤 拡二
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告計算機アーキテクチャ(ARC)
- 巻号頁・発行日
- vol.2004, no.80(2004-ARC-159), pp.109-114, 2004-07-31
SR11000モデルH1が採用するPOWER4+はハードウェアによるデータプリフェッチをサポートするが,多数のロードストリームを含むループでは,ハードウェアですべてのストリームをプリフェッチすることができず,性能が低下する。本稿では,この問題を解消するソフトウェアプリフェッチ手法について紹介する。評価の結果,本手法の適用により,ストリーム数が増えた場合にも安定して高い性能を実現できることを確認し,ストリーム数を考慮したループ分割が不要なことを明らかにした。SR11000モデルH1向けの日立最適化FORTRAN90コンパイラは,本手法によるコード生成が可能である。
1 0 0 0 OA SR11000モデルH1における高精度性能分析手法
- 著者
- 松居 昭宏 助川 直伸 高山 恒一 青木 秀貴 中村 友洋
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告計算機アーキテクチャ(ARC)
- 巻号頁・発行日
- vol.2003, no.119(2003-ARC-155), pp.81-86, 2003-11-27
大規模な科学技術計算アプリケーションは,一般に高いメモリ性能を要求する。これに対し,スーパーテクニカルサーバSR11000モデルH1では,高性能なメモリシステムの設計を行った。新しい設計における同機のアプリケーション特性を知るため,メモリに対する負荷を定量化する性能分析手法を開発した。SR11000モデルH1における評価の結果,本手法によりアプリケーション特性を高精度に定量化することが可能であり、また、得られた特性がアプリケーションのチューニング指標としても有効であることを確認した。
1 0 0 0 OA SR11000モデルH1のノード構成とスケーラビリティ評価
- 著者
- 青木 秀貴 高山 恒一 中村 友洋 松居 昭宏 助川 直伸
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告計算機アーキテクチャ(ARC)
- 巻号頁・発行日
- vol.2003, no.119(2003-ARC-155), pp.75-80, 2003-11-27
POWER4+プロセッサによる8CPU超のSMPノードでは,各CPUがL2キャッシュミスを起こした際に発行するスヌープ要求同士の競合により,性能低下が発生する。このスヌープ競合の影響を評価した結果,スヌープ競合の発生しない8CPU構成と比べ,24CPU構成/32CPU構成ではアプリケーション実行時にそれぞれ平均20%/27%の性能低下を起こすのに対し,16CPU構成では平均10%の性能低下にとどまり,CPU数に対する高い性能スケーラビリティを実現できることがわかった。この結果に基づき,SR11000モデルH1のノードを16CPU構成とした。
1 0 0 0 OA 大学生男女におけるボディイメージと関連要因についての研究
- 著者
- 横山 洋子 Yoko YOKOYAMA
- 出版者
- 名鉄局印刷株式会社
- 雑誌
- 瀬木学園紀要 = Segigakuen Kiyo
- 巻号頁・発行日
- no.12, pp.168-169, 2018
- 著者
- 呉 哲男
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.1, pp.10-17, 1997-01-10 (Released:2017-08-01)
戦後いちはやく国文学に実証的な批評を導入し、古代文学研究の先端を切り開いた存在として西郷信綱がいる。西郷は本居宣長の国学批判から出発し、その負の遺産を構造主義で乗り越えようとした。現在の自己完結的な古事記研究もそれを基本的に継承している。
1 0 0 0 OA 梵網經戒相の批判研究
- 著者
- 西本 龍山
- 出版者
- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.2, pp.433-439, 1960-03-30 (Released:2010-03-09)
1 0 0 0 ヴァイマル期ドイツにおける産業合理化と労働者文化
本研究は,第一に,ヴァイマル期における産業合理化と労働者・労働組合との関係,第二に,労働者生活圏の変容と労働者文化・大衆文化との関係をテーマとした。1.相対的安定期に始まる産業合理化は,ルール炭鉱では,坑内労働の機械化と労働組織の再編成によって,電機・機械工業では,フォード・システムに倣う大量生産方式の端緒的導入によって,労働者の伝統的な労働の世界を変えた。それは,労働運動の基礎となっていた旧来の熟練を掘り崩し,労働者の連帯の構造を破壊した。産業合理化に対して,ドイツ労働総同盟(ADGB)は,生産性の上昇による生活水準の改善という方向で積極的に対応し,これまでの社会主義的な大衆窮乏化論に代えて大衆購買力論を打ち出した。しかし,ADGBの経済民主主義論では経営民主主義は軽視されており,合理化による生産点での労働者文化の変質についての認識は乏しかった。2.1920年代における労働者生活圏については,労働者街の変容と労働者文化,青年労働者層と大衆文化という点について検討した。大都市ベルリンでは,都市計画により中心部の再開発が緒につくとともに,郊外には集合住宅団地が建設され,これによって従来の労働者街は変容していった。一方,ルールの炭鉱住宅にも社会的変容の波は押し寄せていたが,労働者文化と生活圏の一体性はなお比較的よく保たれており,生活の場での労働者の連帯感はかえって強まった。このような社会的変容のなかで青年労働者層は,世界恐慌期に不安定な生活を送っており,両親の世代とは異なる生活観と政治意識を有していた。彼らこそ,労働者文化と大衆文化との間で方向を見定められないこの時期の労働運動文化のディレンマを体現していたといえる。
1 0 0 0 OA 第7回 スウェーデン
- 著者
- 兼子 利夫
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.9, pp.610-618, 2005 (Released:2005-12-01)
- 参考文献数
- 7
世界的に1990年代からインターネットとPCが急速に普及し始め,産業活動はもちろんのこと一般社会にもその活用が広がりつつある。そのひとつのビジネス形態が,電子商取引である。各国の政府機関等では,これらの情報技術(Information Technology: IT)を積極的に政策に取り込み,自国のIT政策として展開している。本稿では,最初にスウェーデンのIT政策の経緯を述べ,そして,同国のIT政策の基本である「全国民のための情報社会」の概要について述べる。次に,情報技術クラスターの現状について,最後に,IT産業の一分野としてデジタル・ゲーム産業とIT政策戦略グループについて記述する。
1 0 0 0 OA 小型ロボットを用いた自己客体視システムによる思考変容の誘発
- 著者
- 高橋 英之 島谷 二郎 小山 虎 吉川 雄一郎 石黒 浩
- 雑誌
- 研究報告ヒューマンコンピュータインタラクション(HCI) (ISSN:21888760)
- 巻号頁・発行日
- vol.2018-HCI-176, no.21, pp.1-4, 2018-01-15
自分があらかじめ記述した考えをロボットが代わりに述べ,それを論破するという自己客観視システムを構築した.このシステムを用いた予備実験から,一定数の被験者がロボットを通じた自分自身との対話を通じて考え方や価値観を変化させることが示された.本研究ではこのようなシステムが持つ意義について考察したい.
1 0 0 0 OA 明治初年の政情と地方支配 : 「民蔵分離」問題前後
- 著者
- 松尾 正人
- 出版者
- 土地制度史学会(現 政治経済学・経済史学会)
- 雑誌
- 土地制度史学 (ISSN:04933567)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.3, pp.42-57, 1981-04-20 (Released:2017-11-30)
Problems of local control by the central government in the early stage of the Meiji Period still remain unclear. This paper discusses a period from the establishment of the Meiji government to the abolition of feudal domains and establishment of prefectures to elucidate details of local government and relations between problems of local rule and the political process of the new government. Firstly, this paper specifically covers matters which have been rarely discussed, such as functions of the Ministry of Home Affairs (民部官) and the role of the Deputy Minister for Home Affairs, Saneomi Hirosawa (広沢真臣), and describes how government agencies for local rule were set up in the initial stage of the Meiji Period, and other particular aspects of the agencies. The ministry's measures for ruling prefectures derived from an idea of Saneomi Hirosawa, who strove to establish a prefectural government in Kyoto. In explaining the character of these measures, this paper makes it clear that the measures included enlightened spects while promoting centralized rule. As examples, the ministry's establishment of prefectural assemblies and its administrative inspectors sent to local governments are cited. Secondly, this paper describes difficulties in local rule by the new government under pressure from Europe and the United States and intra-government conflicts over local rule. It is pointed out that Saneomi Hirosawa's idea played an important role in the separation, especially the separation of the Home Affairs Ministry from the Finance Ministry in July 1870. Furthermore, it is explain that behind separation there were intra-governmental conflicts over local rule and criticism by local administrators against the two ministries. Thirdly, this paper touches upon the role that problems of local rule played in the abolition of feudal domains and establishment of prefectures in 1871, and other reforms before and after that. It explains that Toshimichi Okubo (大久保利通), who took the initiative in the 1871 reforms, intended to curb the considerable influence of the Finance Ministry for a stable Government while strengthening the authority of the Imperial Court. The basic political course of the new Meiji government was centralization under financial pressure. Based on the analysis in this paper, however, I believe the government's internal confusion, caused by problems of local rule and subsequent reforms of government agencies, characterize the new Meiji regime during its process of establishment.
1 0 0 0 OA 今野晴貴著, 『ブラック企業 : 日本を食いつぶす妖怪』, 文春新書, 2012年
- 著者
- 森岡 孝二
- 出版者
- 社会政策学会
- 雑誌
- 社会政策 (ISSN:18831850)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.1, pp.107-109, 2014-09-10 (Released:2018-02-01)
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 北海道におけるハマゴウ属(シソ科)の初記録
1 0 0 0 OA メタンハイドレート
- 著者
- 松本 良 青木 豊 渡部 芳夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, no.11, pp.931, 1996-11-15 (Released:2008-04-11)
- 被引用文献数
- 1 1
1 0 0 0 OA 給水車運転職員の減少に伴う準中型自動車免許取得制度の新設
- 著者
- 細沼 茉由 多田 広晃 井手 歩美
- 出版者
- 公益社団法人 日本水道協会
- 雑誌
- 全国会議(水道研究発表会)講演集 令和2年度水道研究発表会講演集 (ISSN:24361496)
- 巻号頁・発行日
- pp.682-683, 2020 (Released:2021-10-31)
1 0 0 0 OA テキスト分析に基づくソーシャルメディア上でのニュースの影響度予測に関する研究
- 著者
- 上子 優香 榊 剛史 原 忠義 森 純一郎 坂田 一郎
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第29回 (2015)
- 巻号頁・発行日
- pp.4I13, 2015 (Released:2018-07-30)
これまでニュース記事の一読者に過ぎなかった人々が、ソーシャルメディアを通じて意見を発信することで社会的影響力を持つようになってきた。本研究ではYahoo!ニュース内のコメントとTwitterでのコメントを対象として、ニュース記事のもつ言語的特徴が、ニュース記事の読者がソーシャルメディア上で発信するコメントの数や感情度に与える影響と、プラットフォームによるコメントの性質の違いを明らかにした。
1 0 0 0 OA 今後の入会林野管理に求められるもの 近年の紛争例、英国の立法を参考に
- 著者
- 鈴木 龍也
- 出版者
- 中日本入会林野研究会
- 雑誌
- 入会林野研究 (ISSN:2186036X)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, pp.23-34, 2020 (Released:2020-05-01)
本報告は、近年の入会訴訟(財産区に関する訴訟も含む)およびイギリス(基本的にイングランドのみに対象を絞る)のコモンズに関する立法の分析から示唆を得て、日本の入会林野のガバナンスに今何が必要とされているか考察するものである。近年においても入会や財産区がかかわる訴訟のうちのかなりの部分を「開発」に起因する訴訟が占めている。また、最近は財産区の適切な管理を求める市民からの請求が、住民訴訟という形で行われるようになってきている。これらは入会団体内部の構成員および外部の市民からの現状の入会財産管理に関する異議申立である。イギリスでは、コモンズの管理不全に対応すべく立法へ向けた努力が継続されてきた。その過程では、コモンズの所有者やコモナーの利害に加えてコモンズへの市民のアクセスや動植物の保護、農地や林地としての利用など様々な利害をどのように調整するかが問われてきた。これら2つの対象に関する検討から示唆されるのは、今後の入会地の管理にとって、入会地にかかわる様々な公益の内容および優先順序に関する社会的な合意を形成すること、そして具体的な場でそれら様々な公益を調整しうる有効な枠組みを作り上げていくことが喫緊の課題となっているということである。