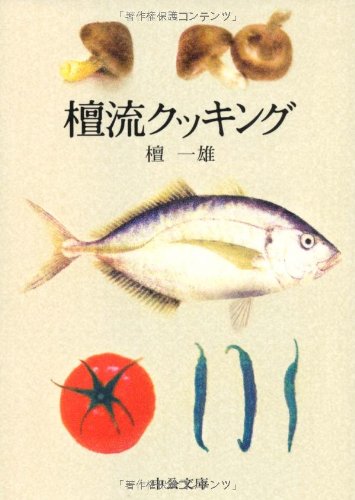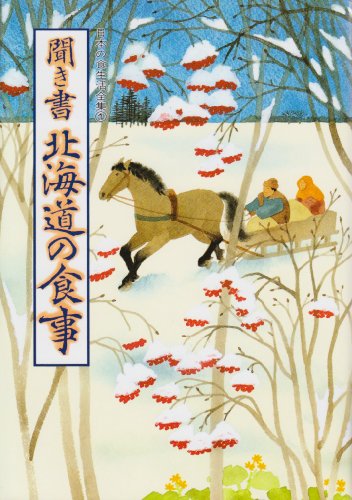1 0 0 0 聞き書北海道の食事
- 著者
- 「日本の食生活全集北海道」編集委員会編
- 出版者
- 農山漁村文化協会
- 巻号頁・発行日
- 1986
1 0 0 0 コロラドプロジェクトのUFO研究, その結論と勧告
- 著者
- エドワード・U.コンドン監修 中山光正訳
- 出版者
- ブッキング(発売)
- 巻号頁・発行日
- 2003
- 出版者
- 法政大学大原社会問題研究所
- 雑誌
- 大原社会問題研究所雑誌
- 巻号頁・発行日
- vol.2013年(12月), no.662, 2013-12-25
1 0 0 0 OA 日本人青年の罪悪感喚起状況の構造
- 著者
- 有光 興記
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.2, pp.148-156, 2002-06-25 (Released:2010-07-16)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 12 9
The aim of the present study was to specify guilt eliciting situations for Japanese adolescents, and examine the relationship between guilt-proneness in the situations and personality traits. With an open-ended questionnaire, 315 guilt experiences were collected and categorized into 37 situations. Situational Guilt Inventory (SGI) for the 37 was developed and administered to 500 Japanese adolescents. Factor analysis found four factors: hurting others, inconsiderate to others, acting selfishly, and debt feeling toward others. SGI scores had positive correlations with private and public self-consciousness and depression. However, correlations with the Big Five were low, none higher than. 2, except those with conscientiousness. The factors were similar to those of Dimension of Conscience Questionnaire (DCQ; Gore & Harvey, 1995) and Situational Guilt Scale (SGS; Klass, 1987), except that they do not have the fourth: debt feeling. These results showed some characteristics of guilt among Japanese people, as well as reliability of the inventory.
1 0 0 0 OA 予防薬として五苓散を用いた片頭痛の1症例
- 著者
- 緒方 裕一 濵田 高太郎 平井 慎理
- 出版者
- 一般社団法人 日本ペインクリニック学会
- 雑誌
- 日本ペインクリニック学会誌 (ISSN:13404903)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.4, pp.345-346, 2020-10-25 (Released:2020-10-28)
- 参考文献数
- 5
1 0 0 0 OA がん緩和医療におけるミルタザピンの有用性についての検討
- 著者
- 植松 夏子 柴原 弘明 今井 絵理 吉田 厚志 西村 大作
- 出版者
- 一般社団法人 日本農村医学会
- 雑誌
- 日本農村医学会学術総会抄録集 第60回日本農村医学会学術総会 (ISSN:18801749)
- 巻号頁・発行日
- pp.343, 2011 (Released:2012-02-13)
【背景】がん患者には様々な苦痛症状が出現する。原発部位や基礎疾患により投与できる薬剤が限られ、副作用により投与中止となる場合もみられる。また各症状に対し個々に薬剤を使用することは薬剤の相互作用や内服負担増の面で患者に苦痛を与えることもある。ミルタザピンはノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬(NaSSA)に分類されH1受容体拮抗作用、5-HT3拮抗作用を有するため、緩和医療領域では抗うつ作用以外の効果も期待されている。 【目的】がん緩和医療における苦痛症状へのミルタザピンの有用性を明らかにすること。 【対象と方法】2010年10月から2011年5月までに緩和ケア科でミルタザピンが処方された24例。自覚症状の変化を「著効(症状の消失)」「有効(症状の軽快)」「無効」「中止」の4段階に分けretrospectiveに評価した。なお当研究調査には十分な倫理的配慮を行った。 【結果】性別は男性11例 女性13例、原疾患は膵癌7例、胃癌5例、乳癌3例、胆管癌2例、大腸癌2例、肺癌1例、肝癌1例、前立腺癌1例、リンパ腫1例、GIST1例であった。ミルタザピンは不安・吐き気・食欲不振・掻痒感・疼痛・せん妄のいずれかまたは複数の症状がみられた患者に処方されていた。全24例のうち著効11例、有効6例、無効3例、中止4例で、中止理由は4例とも眠気であった。至適投与量は15mg 2例、7.5mg 9例、3.75mg 10例、1.875mg 3例であり、7.5mg以下の低用量投与が92%であった。 【考察】ミルタザピンはがん患者の苦痛症状に対し有効で、低用量で十分な効果がえられていた。本研究は少数例であり,さらなる症例を蓄積したうえでの検討が今後必要であろう。 【結語】ミルタザピンは低用量で各苦痛症状の緩和をもたらす。
1 0 0 0 OA 化粧行動を規定する個人差要因の日タイ比較
- 著者
- 平松 隆円
- 出版者
- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会
- 雑誌
- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.6, pp.456-461, 2018-06-28 (Released:2018-06-28)
- 参考文献数
- 11
本研究は,化粧行動を自意識や他者意識がどのように規定するのかについて,日本人とタイ人で比較検討をおこなうことが目的である.タイ人男子61 名,タイ人女子239 名,日本人男子89 名,日本人女子112 名を対象に質問紙調査をおこなったところ,おおむねタイ人男女の化粧行動は公的自意識が規定し,部分的ではあるものの空想的他者意識がタイ人男子の化粧行動を規定していた.また,日本人男子の化粧行動は私的自意識,外的他者意識,空想的他者意識が部分的ではあるが規定し,日本人女子の化粧行動は部分的に内的他者意識が規定していた.
1 0 0 0 OA 感謝介入による死の不安軽減効果に関する研究
- 著者
- 廣瀬 悠貴 本多 明生
- 出版者
- 日本感情心理学会
- 雑誌
- 感情心理学研究 (ISSN:18828817)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.1, pp.16-24, 2022-05-30 (Released:2022-06-07)
- 参考文献数
- 37
Lau and Cheng (2011, 2013) reported that a gratitude induction procedure reduced death anxiety but that it did not promote emotional well-being. The present study was aimed at replication of their reported findings. Experiment 1 assessed single gratitude intervention effects on death anxiety, feeling, and mental health among college students. Results showed death anxiety was not reduced by the intervention but positive feeling and mental health were improved. Experiment 2 examined effects of one-month gratitude intervention on death-related anxiety, feeling, and mental health. We also examined effects of trait gratitude. Results showed no significant effect of gratitude intervention on death anxiety reduction, but participants with higher gratitude traits exhibited better mental health. These results suggest that trait gratitude is associated with mental health, although the results did not confirm a death anxiety reduction effect of gratitude intervention, as reported by Lau and Cheng (2011, 2013).
1 0 0 0 OA 読むことと書くことの関係
- 著者
- ティモシー シャナハン
- 出版者
- 全国大学国語教育学会
- 雑誌
- 全国大学国語教育学会国語科教育研究:大会研究発表要旨集 142 (ISSN:24321753)
- 巻号頁・発行日
- pp.125-128, 2022-05-28 (Released:2022-08-11)
1 0 0 0 OA 続・黄泉無著の「参府記」の訳註研究
- 著者
- 川口 高裕
- 出版者
- 愛知学院大学禅研究所
- 雑誌
- 禅研究所紀要 = Journal of the Institute for Zen Studies Aichigakuin University (ISSN:02859068)
- 巻号頁・発行日
- no.41, pp.75-102, 2013-03-31
1 0 0 0 OA 完全主義が抑うつに及ぼす影響 —不安の影響を統制した再検討
- 著者
- 高山 智史 佐藤 寛
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 認知行動療法研究 (ISSN:24339075)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.2, pp.183-191, 2022-05-31 (Released:2022-07-28)
- 参考文献数
- 31
本研究の目的は、小堀・丹野(2002)で確認された完全主義が抑うつに至るプロセスを、不安の影響を考慮して再検討することであった。大学生346名を対象として、完全主義、抑うつ、不安をそれぞれ測定した。その結果、小堀・丹野(2002)と一致する知見として、(1)完全性欲求は高目標設置と失敗恐怖を促進する、(2)高目標設置は抑うつを抑制する可能性がわずかながらある、といった点が示唆された。一方で新たな知見として、(3)失敗恐怖は抑うつと直接的な関係は示されず、不安を媒介して間接的に抑うつを促進する関係性のみを示す、(4)高目標設置は不安を抑制する、といった点が示唆された。これらの結果から、抑うつと不安の改善を目的とした心理学的支援に完全主義を応用する意義について議論した。
1 0 0 0 OA 適応回復プロセスに対応したレジリエンス要因の抽出
- 著者
- 徳田 文美 杉若 弘子
- 出版者
- 日本パーソナリティ心理学会
- 雑誌
- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.35-38, 2022-06-17 (Released:2022-06-17)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 1
This study identifies the resilience factors and their contributions to each phase of the stress-related recovery process, and examines their effects on subjective adjustment as well as physical and mental health. The data obtained from 263 Japanese undergraduates showed that (1) resilience factors contributing to the stages before exposure to the stressor and after recovering from stressful situations included interpersonal items affecting subjective adjustment; and (2) the factors related to the stressor-exposure period included cognitive coping strategies that influenced physical and mental health during such adversities. These results suggest that developing interventions in accordance with the individual’s recovery process may be effective in increasing resilience.
1 0 0 0 OA 読み書き障害
- 著者
- 櫻井 靖久
- 出版者
- 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会
- 雑誌
- 高次脳機能研究 (旧 失語症研究) (ISSN:13484818)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.2, pp.197-201, 2022-06-30 (Released:2022-08-30)
- 参考文献数
- 23
後天性読み書き障害について, 認知心理学的な分類と病巣研究に基づいた神経解剖学的な分類を整理して紹介した。認知心理学では, 失読を中心性 (視覚認知から意味, 音声にアクセスする段階での障害) と周辺性 (単語の視覚認知レベルの障害) に分け, 中心性失読はさらに音韻性失読, 表層性失読, 深層性失読に分けられる。失書も同様に, 中心性 (語彙, 音韻処理にかかわる過程での障害) と周辺性 (視覚・運動覚イメージを書字運動に変換する段階での障害) に分けられ, 中心性 (言語性ともいわれる) 失書は音韻性失書, 語彙性失書, 深層性失書に, 周辺性 (運動性ともいわれる) 失書は失行性失書, 異書性失書にそれぞれ分けられる。神経解剖学的分類では, まず純粋失読, 失読失書, 純粋失書に分け, それぞれが細分類されている。 さらに選択的音読み障害と意味性認知症にみられる訓読みに顕著な読み障害に関する筆者らの最近の研究を紹介した。これらの事実は, 音読みにかかわる経路と訓読みにかかわる経路が独立した二重回路をなすことを示唆している。
1 0 0 0 OA 公正感受性とバッシング許容度の関連――怒り感情を媒介したモデルの検討
- 著者
- 篠原 千春 西口 雄基 石垣 琢麿
- 出版者
- 日本パーソナリティ心理学会
- 雑誌
- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.65-68, 2022-07-06 (Released:2022-07-06)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1
During the novel coronavirus pandemic, people who defied the call for isolation and the government’s requirement for self-quarantine have encountered frequent condemnation. There was a prevailing acceptance of such bashing behavior. Given this context, this study focused on justice sensitivity as a key factor in the acceptance of bashing. Participants (N=1,000) read a short scenario that involved a person who goes out despite the self-quarantine requirement. The results showed a moderated mediation in which individuals with higher justice sensitivity showed a greater degree of anger, which in turn led to higher bashing acceptance when the scenario was judged as an injustice.
1 0 0 0 OA 親鸞教学における弾圧の意味-下-
- 著者
- 廣瀬 杲
- 出版者
- 大谷大学真宗学会
- 雑誌
- 親鸞教学 = SHINRAN KYOGAKU The Otani Journal of Shin Buddhism (ISSN:05830567)
- 巻号頁・発行日
- no.58, pp.1-18, 1991-09-30
1 0 0 0 OA 生後1年間の抱き時間とその変化:身体発達と養育者の役割
- 著者
- 園田 正世 工藤 和俊 野澤 光 金子 龍太郎
- 出版者
- 日本生態心理学会
- 雑誌
- 生態心理学研究 (ISSN:13490443)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, pp.183-187, 2022-05-01 (Released:2022-06-27)
- 参考文献数
- 13
ヒトの乳児は出生後すぐには自ら移動できないため,しばらくは養育者による移動に委ね,身体の発達とともに能動的で探索的な移動に変化していく.抱くことは移動を可能にするだけでなく,授乳やあやし,コミュニケーションの基底的手段である.本研究では,家庭内での抱きの生起と継続の様相を明らかにし,成長発達と日常生活のなかで抱きの意味を検討するために,出産から独立歩行までの発達が著しい生後1年間(各月1回24 時間連続)の2組の抱き時間を計測した.新生児期から計測をスタートし,A 参加者は7 時間29 分, B 参加者6 時間48 分だったが,A 参加者は12 ヶ月後に3 時間56 分まで減少し,B 参加者は7 時間33 分に増加した.抱きは移動やあやしのための行為から,家事と平行するためのおんぶや授乳中心に変化し,子の受動的な移動が減少する様子がみられた.
1 0 0 0 OA 文官軍人教員恩給法解説
1 0 0 0 OA エコロジカル・アプローチ:はじまりの動機と展開
- 著者
- 佐々木 正人
- 出版者
- 日本生態心理学会
- 雑誌
- 生態心理学研究 (ISSN:13490443)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, pp.113-141, 2022-05-01 (Released:2022-06-27)
- 参考文献数
- 41
こんにちは,佐々木です.日本生態心理学会20 周年おめでとうございます.この機会を記念して何か話すようにご依頼いただきました.パワポを用意しました.はじめに本会創設の頃を短く振り返ります.次にエコロジカル・アプローチについて,自分のフィールドでの経験も紹介しながら,身体,場所,モノの3 つをテーマに話します.