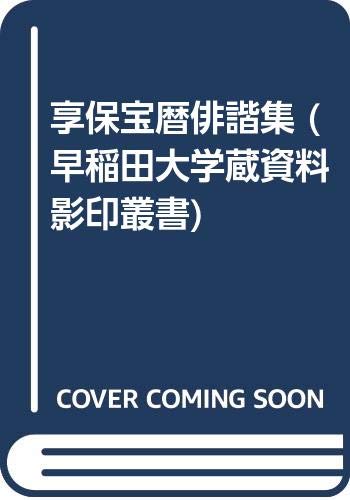1 0 0 0 OA 腎移植後内科・小児科系合併症ガイドライン
- 著者
- 西 慎一
- 出版者
- 一般社団法人 日本移植学会
- 雑誌
- 移植 (ISSN:05787947)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.6, pp.417-422, 2014-12-10 (Released:2014-12-26)
- 参考文献数
- 17
Many medical complications, including hypertension, diabetes, and dyslipidemia, appear after kidney transplantation. These complications significantly affect the grafts and the patient survivals; thus the control of posttransplant medical complications is absolutely essential. Unfortunately, steroid and immunosuppressive agents induce or impair the medical complications, which are a special condition after kidney transplantation.The Japanese Society of Clinical Renal Transplantation (JSCRT) has already published "Guidelines for medical and pediatric complications after kidney transplantation" in 2011. Earlier, in 2009, "KDIGO Clinical Practice Guidelines for Kidney Disease" for the care of kidney transplant patients was published in the American Journal of Transplantation. The contents of recommendations are not always the same between two guidelines. Referring to these two guidelines, the author summarized the points and problems and posttransplant hypertension, posttransplant diabetes, and post transplant dyslipidemia.
- 著者
- 林 伸和 小島 愛 内方 由美子 舛永 安繁 中村 圭吾
- 出版者
- 日本臨床皮膚科医会
- 雑誌
- 日本臨床皮膚科医会雑誌 (ISSN:13497758)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.5, pp.564-573, 2017 (Released:2018-08-17)
- 参考文献数
- 9
尋常性痤瘡患者に対する過酸化ベンゾイルゲル(ベピオ(R)ゲル 2.5 %,以下,本剤)の日常診療下における安全性及び有効性について,本剤使用3ヵ月後までの中間集計結果をもとに検討した. 解析対象症例378例中57例(15.1%)に副作用を認めたが,重篤なものはなかった.適用部位の皮膚刺激症状(紅斑,刺激感,乾燥,瘙痒感,皮膚剥脱,疼痛)のほとんどは本剤使用開始後1ヵ月以内に発現していた.皮膚刺激症状の発現率について,性別,年齢,尋常性痤瘡の重症度による一定の傾向はなかったが,敏感肌では有意に高かった.接触皮膚炎は5例(1.3%)に認められ,その発現時期は本剤使用開始後5〜20日であった. 全顔の皮疹数の減少率(中央値)は,本剤使用3ヵ月後において,炎症性皮疹が75.0%,非炎症性皮疹が61.3%,総皮疹が67.7%であった.12歳未満の小児患者においても良好な結果が得られ,特に炎症性皮疹数は12歳以上と比較して有意に高い減少率であった.全般改善度で「著明改善」または「改善」と判定された症例は、顔面で377例中271例(73.4%),顔面以外で32例中18例(58.1%)であった.Skindex-16日本語版を用いたquality of life評価では、症状,感情,機能および総合スコアの全てが本剤使用3ヵ月後に改善していた. 以上より,本剤は尋常性痤瘡の急性炎症期における有用な治療選択肢の一つであり,小児患者に対しても有用な薬剤となり得ることが示唆された.
1 0 0 0 支那事変画報
- 著者
- 大阪毎日新聞社, 東京日日新聞社 編
- 出版者
- 大阪毎日新聞社[ほか]
- 巻号頁・発行日
- vol.第4,5輯, 1937
- 著者
- 落合 知美 綿貫 宏史朗 鵜殿 俊史 森村 成樹 平田 聡 友永 雅己 伊谷 原一 松沢 哲郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本霊長類学会
- 雑誌
- 霊長類研究 (ISSN:09124047)
- 巻号頁・発行日
- pp.31.001, (Released:2015-03-20)
- 参考文献数
- 70
- 被引用文献数
- 2 2
The Great Ape Information Network has collated and archived information on captive chimpanzees within Japan since 2002. As of July 1st, 2014, a total of 323 chimpanzees were housed within 52 facilities across Japan, all registered in the Japanese Association of Zoos and Aquariums (JAZA) studbook. JAZA has recorded information on captive chimpanzees within Japan since the 1980s. However, for individuals unregistered and/or deceased prior to this period, JAZA holds scant information. There are very few surviving reports on living conditions and husbandry of such individuals, particularly for the years preceding the Second World War (WWII) (up to 1945). Here we present the first detailed history of captive chimpanzees in Japan before WWII, following a systematic investigation of disparate records. The first record of any live chimpanzee within Japan was a chimpanzee accompanying an Italian travelling circus in 1921. The history of resident captive chimpanzees in Japan began in 1927 when a chimpanzee, imported into Japan by a visitor, was exhibited in Osaka zoo. In the 1930s, many chimpanzee infants were imported to Japanese zoos until in 1941 imports were halted because of WWII. By the end of WWII, there was only one single chimpanzee still alive within Japan, “Bamboo”, housed in Nagoya. In 1951, importation of wild chimpanzees into Japan resumed. In total, we identified 28 individuals housed within Japan before 1945, none listed previously in the JAZA studbook. Of these 28 individuals: 6 entered Japan as pets and/or circus animals, 21 were imported to zoos, and one was stillborn in zoo. Of the 21 zoo-housed individuals, 7 died within one year and 9 of the remaining 14 were dead within 5 years of arriving in Japan. Four individuals are recorded to have lived 7-8 years. Only one male individual, the aforementioned “Bamboo”, lived notably longer, to about 14 years.
1 0 0 0 OA 呼吸筋力と増強
- 著者
- 解良 武士
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.1-6, 2003 (Released:2003-05-01)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 10 1
呼吸筋力の測定には,最大口腔内圧を用いることが一般的である。最大口腔内圧は様々な因子で変化するが,肺気量の変化が最も大きな影響を及ぼす。この呼吸筋力の低下は肺胞低換気による高炭酸ガス血症を伴う低酸素血症の原因となるため,呼吸器疾患を持つ患者には重要である。呼吸筋力はいくつかの原因で低下するが,閉塞性換気障害と拘束性換気障害を例に取り解説する。呼吸筋力低下がもたらす症状を持つ患者にとってその改善は重要であるが,そのトレーニング方法についても紹介する。
1 0 0 0 OA 肢節間協調の制御機構
- 著者
- 平岡 浩一
- 出版者
- 日本理学療法士協会(現 一般社団法人日本理学療法学会連合)
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.46 Suppl. No.1 (第53回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.I-15-1, 2019 (Released:2019-08-20)
歩行などのリズミカル運動では中枢パターン発生器(central pattern generator; CPG)が駆動される。左右異なる速度で動くトレッドミル上で乳児を歩行させると左右異なるリズムのステップで対応するという知見などから,CPGは左右独立して存在すると考えられている。また,胸髄レベルで離断した除脳動物において,上・下肢のリズミカルな筋収縮をそれぞれ個別に誘発できるという知見から,上肢と下肢のCPGもそれぞれ独立しているとされる。各肢の制御を目的に独立して存在するCPGであるが,それらは固有脊髄路を介して互いに協調している。除脳動物において薬物を投与すると上下肢の協調したリズミカル運動が生じるが,その後胸髄レベルでも脊髄を離断するとこの協調は消失することから,固有脊髄路が上下肢のCPGを協調させていることがうかがえる。ヒトにおいても上肢の歩行様の腕振りにより,歩行時のパターンに合致したヒラメ筋H反射の相依存的な変調が同側と対側双方に出現する。これは,ヒト歩行時における上下肢CPG間の協調を裏付ける知見である。固有脊髄路は対側へ分岐した経路を介して左右肢の協調にも関与する。たとえばヒトにおいて,片側足関節のリズミカル運動をすると,安静している側のヒラメ筋H反射がtonicに抑制される。つまり,片側CPGの駆動は安静にある対側伸筋に対して持続性の強い交差性抑制をもたらす。これに対して両側足関節の交互運動をしている時には反対側に対しては位相依存的な抑制が生じるが,両側足関節の同位相性運動をするとその抑制は生じない。これは,両側を交互にリズミカルに活動させる歩行などに特化して位相依存的な抑制が生じることを示唆する。さらに重要なのは,リズミカルでない運動中は固有脊髄路を介した上下肢の協調を示唆する皮膚反射が消失することから,固有脊髄路を介した四肢運動協調は課題依存的に柔軟に回路を開閉できるという知見である。
1 0 0 0 OA Göbelの第2不完全性定理
- 著者
- 山岡 悦郎 Yamaoka Etsuro
- 出版者
- 三重大学人文学部
- 雑誌
- 人文論叢 : 三重大学人文学部文化学科研究紀要 (ISSN:02897253)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.81-94, 1988-03-25
1 0 0 0 OA 煙型雪崩に対する二層火砕流数値モデルの応用可能性:雪崩・火砕流の統一モデル構築に向けて
- 著者
- 志水 宏行
- 出版者
- 公益社団法人 日本雪氷学会
- 雑誌
- 雪氷 (ISSN:03731006)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.4, pp.323-340, 2022-07-15 (Released:2022-08-04)
- 参考文献数
- 87
煙型雪崩と火砕流は,粒子濃度の成層構造をもつ固気混相重力流である.本論文では,既存の二層火砕流モデルについてレビューし,二層火砕流モデルの雪崩への応用可能性について議論する.二層火砕流モデルは,成層化した流れの上部を低濃度乱流サスペンション流として,下部を高濃度粒子流としてモデル化し,それらの相互作用(粒子のやりとりなど)を考慮することによって,火砕流の流動・停止を評価する.特に,高温である火砕流の上部低濃度流の停止プロセス(低濃度流が周囲大気より軽くなり離陸するプロセス)を評価するために,低濃度流上面から取り込まれた周囲大気の熱膨張の効果が評価される.煙型雪崩の流動・停止における多くの物理プロセスは火砕流と共通する.しかし,煙型雪崩の上部低濃度流(雪煙り層)の停止プロセスは,火砕流とは異なり,低濃度流内部の乱れ速度の減少によって流れ内部の全粒子が沈降するという物理プロセスによって説明される.このプロセスを二層火砕流モデルに組み込むことにより,雪崩・火砕流の統一モデルを構築できることが期待される.
1 0 0 0 OA 球後麻酔後に意識消失し呼吸停止が生じた1症例
- 著者
- 中村 里依子 行木 香寿代 小西 純平 寺門 瞳 前田 剛 鈴木 孝浩
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.4, pp.430-433, 2015-07-15 (Released:2015-09-18)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 1 1
症例は局所麻酔下に白内障手術予定の74歳の女性.眼科医によって施行された2%リドカイン3.5mLを用いた球後麻酔の数分後に意識消失と呼吸停止が生じ,その原因として局所麻酔薬の視神経鞘を介したくも膜下注入による脳幹麻酔が疑われた.マスクを用いた人工呼吸を継続した結果,球後麻酔から約30分後には呼吸努力が認められ,約65分後には意識清明となり,呼吸およびその他の運動機能も完全に回復した.球後麻酔といえども危機的合併症が発現し得ることを認識し,呼吸や意識の経時的観察,そして合併症が生じた際に迅速対応できる体制が重要と考えられた.
- 著者
- 安本 慎也 大槻 伸吾 柳田 育久 相原 望 大久保 衞
- 出版者
- 一般社団法人 日本整形外科スポーツ医学会
- 雑誌
- 日本整形外科スポーツ医学会雑誌 (ISSN:13408577)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.2, pp.100-104, 2022 (Released:2022-05-31)
- 参考文献数
- 18
メディカルチェックは選手の身体特性を把握するための有益な情報となる.本研究では大学野球部新入生を対象としたメディカルチェックを実施し,投球肩肘障害を有する選手の身体機能を比較検討した.身体機能検査では下肢・体幹可動性テスト,肩・肩甲骨可動性テスト,肩甲骨周囲筋・腱板機能の測定を実施した.肩痛群(PS群)では疼痛なし群(N群)と比較して,Elbow Push Test(EPT)の陽性者が有意に多かった.投球肩障害には,今回測定した身体機能のうち,肩甲骨動的安定性の低下が関与している可能性が示唆された.
- 著者
- 日本箱庭療法学会
- 出版者
- 誠信書房 (製作・発売)
- 巻号頁・発行日
- 1988