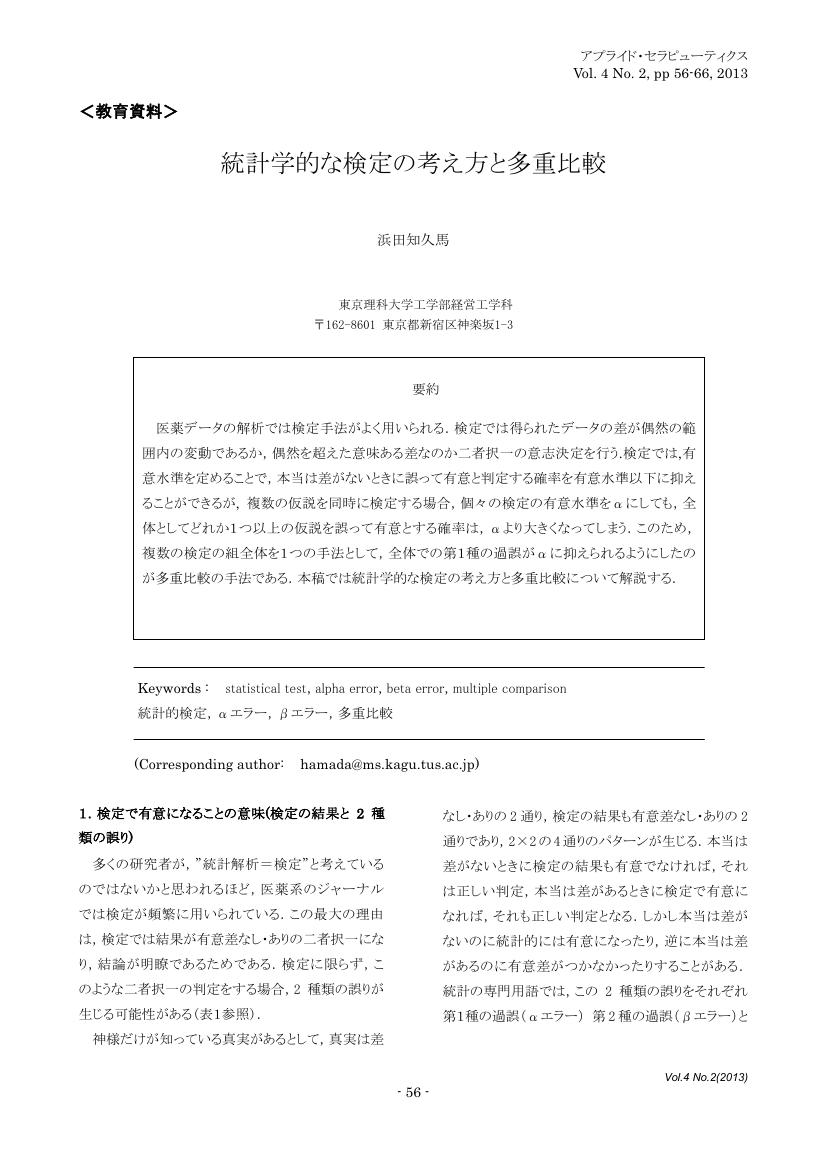1 0 0 0 親鸞による阿弥陀の慈悲とトマス・アクィナスによる神の愛-比較研究
- 著者
- Valles J.G. 堀内 紀子
- 出版者
- 清泉女子大学
- 雑誌
- 清泉女子大学紀要 (ISSN:05824435)
- 巻号頁・発行日
- no.21, pp.81-90, 1973-12
1 0 0 0 OA 統計学的な検定の考え方と多重比較
- 出版者
- 日本アプライド・セラピューティクス(実践薬物治療)学会
- 雑誌
- アプライド・セラピューティクス (ISSN:18844278)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.2, pp.56-66, 2013 (Released:2021-02-28)
1 0 0 0 流通在庫の3割が偽物? 半導体不足で模倣品リスク上昇
- 出版者
- 日経BP
- 雑誌
- 日経エレクトロニクス = Nikkei electronics : sources of innovation (ISSN:03851680)
- 巻号頁・発行日
- no.1235, pp.78-83, 2022-01
では、流通在庫品にはどの程度の模倣半導体が紛れ込んでいるのか。当然のことながら、中国などの闇市場でつくられるものなので、実態を正確に把握するのは非常に難しく、信頼できる調査報告も数少ない。 例えば、ERAIには会員企業から20年に463件の報告があっ…
1 0 0 0 OA 東京圏における新都心の業務集積に関する実証的研究
- 著者
- 小川 剛志 石川 允
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.685-690, 1991-10-25 (Released:2020-05-01)
- 参考文献数
- 3
THIS PAPER ANALYSED THE RECENT TENDENCY OF THE LOCATION OF THE BUSINESS FUNCTION IN THE NEW CENTRAL BUSINESS DISTRICT, MAKUHARI, KAWASAKI AND OMIYA THE SUBURBAN CORE CITIES IN TOKYO METOROPOLITAN AREA. AND COMPARED WITH THE QUALITIES OF BUSINESS FUNCTION, THE FACTORS OF THE LOCATION AND FACTORS OF RELOCATION OF THE REMOVING INDUSTRY IN THAT EACH PLACE, AND EXAMIND ON THE FORM OF ACCUMULATION OF THE BUSINESS FUNCTION IN THE NEW CENTRAL BUSINESS DISTRICT.
- 著者
- 金井 潤一
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.583-588, 1991-10-25 (Released:2020-05-01)
- 参考文献数
- 3
THE PURPOSE OF THIS STUDY IS TO GRASP 1)PHYSICAL CHANGES OF THE AREAS 2)RESIDENTS' VIEWS ON THEIR HOUSES AND FUTURE PROSPECTS OF THE AREAS. AND THESE POINTS ARE STUDIED AS A CASE STUDY IN NEIGHBORING AREA OF SHINJUKU SUBCENTER. THE RESULTS OF THIS STUDY ARE AS FOLLOWS: 1) THE CHANGES OF LAND USE APPEAR NOT AS DIRECT LOCATIONS OF BUSINESS BUILDINGS, BUT AS PUTTING BUSINESS FUNCTIONS WITH CONDOMINIUMS OR DEVERSION FOR BUSINESS AFFAIR IN DWELLING UNITS. 2) CONSCIOUSNESS OF BEING SETTLED IN THE AREA IS DECLINING, AND THERE EXIST CONSIDERABLE RESIDENTS OF HAVING THE CONSCIOUSNESS OF MOVING FROM THE AREA.
- 出版者
- 日経BP
- 雑誌
- 日経ビジネス = Nikkei business (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.2094, pp.26-31, 2021-06-07
「中国でビジネスを広げたいなら西側諸国には向いていない別の窓を持った方がいいですよ」。米国のトランプ前大統領が中国企業排除の動きを強めていた19年、訪中した当時のルネサス経営幹部は中国政府関係者からこうした「助言」を受け、驚いた。「米中緊張…
1 0 0 0 OA 宮崎市の公園緑地における半寄生植物オオバヤドリギの繁茂と樹木衰退
- 著者
- 石田 弘明 黒田 有寿茂 岩切 康二
- 出版者
- 植生学会
- 雑誌
- 植生学会誌 (ISSN:13422448)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.1, pp.15-32, 2016 (Released:2016-07-01)
- 参考文献数
- 37
1. オオバヤドリギは樹上に生育する半寄生の常緑低木である.オオバヤドリギは比較的希少な種であるが,宮崎県立平和台公園の敷地内には本種の寄生を受けている樹木(以下,宿主木)が数多く分布している.また,これらの多くではシュートの枯死が認められる.このような樹木の衰退はオオバヤドリギの寄生に起因していると推察されるが,オオバヤドリギの寄生と樹木衰退の関係について詳しく検討した例はみられない.2. 本研究では,オオバヤドリギの宿主選択特性とその寄生が樹木に与える影響を明らかにするために,平和台公園においてオオバヤドリギの寄生状況と宿主木の衰退状況ならびにこれらの状況の経年変化を調査した.3. 今回の調査では27種,422本の宿主木が確認された.宿主木の樹高の範囲は1.4-27.0 mで,その96.9%は林冠木であった.種別の幹数はマテバシイが最も多く,総幹数の62.8%を占めていた.4. 本研究と既往研究の間でオオバヤドリギの宿主木を比較した結果,総種数および総科数はそれぞれ67種,29科であった.このことから,オオバヤドリギは少なくとも67種29科の樹木に寄生しうることが明らかとなった.5. マテバシイの寄生率は樹高と共に増加する傾向にあり,樹高が寄生率の高低に関係していることが示唆された.また,マテバシイとアラカシの寄生率は林冠木の方が下層木よりも有意に高く,林冠木がオオバヤドリギの寄生を受けやすいことが示唆された.6. 樹種に対するオオバヤドリギの選好性について検討した結果,マテバシイ,コナラ,スギ,ヒサカキはオオバヤドリギの寄生を受けやすく,逆にシイ類,クスノキ,ハゼノキ,コバンモチ,ナンキンハゼ,アカメガシワなどは寄生を受けにくいことが示唆された.7. 宿主木の衰退の程度を5段階で評価した(衰退度1-5;衰退度5は衰退の程度が最も大きい).その結果,全宿主木の86.7%は衰退度2以上であった.また,これらの中には衰退度5の宿主木も複数含まれており,その幹数は全宿主木の19.7%を占めていた.さらに,マテバシイの衰退度とオオバヤドリギの被覆面積との間には強い正の有意な相関が認められた.これらのことから,調査地における宿主木の衰退の主な要因はオオバヤドリギの寄生であると考えられた.8. 宿主木の中には追跡調査時に枯死が確認されたものが数多く含まれていた.このことから,オオバヤドリギの寄生は宿主木の枯死を引き起こすことが明らかとなった.9. 衰退度5の総幹数は83本で,このうちの89.2%はマテバシイであった.また,追跡調査時に枯死が認められた宿主木の85.4%はマテバシイであった.これらのことから,マテバシイはオオバヤドリギの寄生によって著しく衰退し,場合によっては枯死に至る種であると考えられた.10. 平和台公園にはマテバシイが優占する「放置状態の照葉二次林」がまとまった面積で分布しているので,このことが本公園におけるオオバヤドリギの繁茂に強く関係していると考えられた.
1 0 0 0 OA バスケットボール大要 : 附・競技規定
1 0 0 0 アマチュア写真家の興味の深まりにおける実践ネットワークの関与
- 著者
- 杉山 昂平 森 玲奈 山内 祐平
- 出版者
- 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.4, pp.381-396, 2020
<p>人々が興味を深めるとき,ゆるやかな社会関係はいかに関与するのだろうか.本研究の目的は,興味追求としての趣味に着目し,強固な実践共同体に対比されるゆるやかな実践ネットワークが,趣味人の興味の深まりにいかに関与するのかを明らかにすることである.事例としてデジタル時代のアマチュア写真を取り上げ,アマチュア写真家14名に対してインタビュー調査を行った.その結果,興味の深まりに関与する実践ネットワークとして「刺激的な隣人」と「不特定の観衆」の存在が明らかになった.「刺激的な隣人」は自立的に興味を追求する多様な趣味人の姿を可視化し,「不特定の観衆」は作品に対してフィードバックを与え,それ自体が深い興味の対象になったり,興味を深めるさらなる行動を促したりする.こうした実践ネットワークはSNS によって形成されることもある一方,展覧会や撮り歩き会のような,趣味の世界における対面的な活動によっても形成されていた.</p>
1 0 0 0 国際木材保存会議(IRG)から見た世界の木材保存研究の動向推移 Ⅱ.IRG38(2007)~IRG40(2009)とIRG Americas Regional Meeting(2008)を対象に
- 著者
- 松永 浩史
- 出版者
- 日本木材保存協会
- 雑誌
- 木材保存 (ISSN:02879255)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.2, pp.66-70, 2020
- 被引用文献数
- 2
2021年の5月9日~13日にかけて,国際木材保存会議(IRG52)日本大会が沼津で開催される。2001年の奈良大会(IRG32)以来,20年ぶりの日本開催となる。日本木材保存協会は,IRG52大会組織委員会とIRG52大会実行委員会を立ち上げ,久方ぶりの日本開催を円滑に進める観点から,ここ数年のIRG大会参加への渡航助成や大会参加ツアー,発表プロシーディングの文献抄録紹介(当協会発行の木材保存に掲載)といった機運を高める取組を進めている。この総説もこういった取組の一つである。奈良大会以降のIRG大会を幾つかの期間に分け,各大会の概要を学術的な面や技術開発の側面からおさらいして,世界の木材保存研究の潮流を見渡すことを目的としている。今回は,前報(IRG33(2002年)~IRG37(2006年))に続いて,IRG38(2007年)~IRG40(2009年)を整理する。なお,2008年は本大会とは別にアメリカ地域大会が別途開催されたので,これについても整理する。
1 0 0 0 OA Epidemiological study of amateur soccer players: a 17-month study to determine injury and pain
- 著者
- Maya Hagiwara Sonoko Mashimo Hitoshi Shiraki
- 出版者
- The Japanese Society of Physical Fitness and Sports Medicine
- 雑誌
- The Journal of Physical Fitness and Sports Medicine (ISSN:21868131)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.2, pp.79-86, 2022-03-25 (Released:2022-03-14)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 2
Injury can possibly change an athlete’s career. To date, few epidemiological studies have been made of amateur soccer players. More data is needed to allow medical professionals to develop realistic injury prevention and conditioning programs for the amateur level. The purpose of this study was to determine injury incidence, common injury types and body regions, and pain in amateur soccer players. Soccer-related injury and pain data were collected daily in June 2016 thorough October 2017 involving 76 amateur soccer players from two teams. Overall injury incidence was 69 injuries and 2.72/1000 player hours. Acute injuries were 52 (2.05/1000 player hours) and chronic injuries were 17 (0.67/1000 player hours). Most acute injuries occurred during a game (1.99/1000 player hours). In terms of body regions, ankle injury (27.5%) was the most common, followed by knee (15.9%), and thigh (9.0%). Pain incidence was reported 1042 (41.10/1000 player hours). The highest pain incidence was reported during a game (36.9/1000 player hours). The most common location of pain was foot/toe (5.80/1000 player hours), followed by lateral ankle (5.21/1000 player hours), anterior thigh (3.98/1000 player hours), and groin (3.27/1000 player hours). Type of injury, location of injury, and the higher incidence of injury during a game, as opposed to training, were the same as other studies. The pain incidence rate was higher than injury incidence. More epidemiological studies are needed in amateur sports to better understand athletes’ injuries and pain and be able to develop an appropriate injury prevention strategy.
- 著者
- 執行 治平
- 出版者
- 日本レジャー・レクリエーション学会
- 雑誌
- レジャー・レクリエーション研究 (ISSN:09198458)
- 巻号頁・発行日
- no.94, pp.39-49, 2021-10
1 0 0 0 OA 日韓社会の「記念日」(柳原初樹准教授追悼号)
- 著者
- 金 泰虎
- 出版者
- 甲南大学
- 雑誌
- 言語と文化 (ISSN:13476610)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.131-156, 2014
1 0 0 0 IR 佐藤信淵と河上肇 : 帝国主義思想と社会主義思想
- 著者
- 碓井 隆次
- 出版者
- 大阪社会事業短期大学社会問題研究会
- 雑誌
- 社會問題研究 (ISSN:09124640)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.1-20, 1971-10-01
1 0 0 0 OA 思春期年代の発達障害の多様性とその介入-Irritabilityを中心に-
- 著者
- 宇佐美 政英
- 出版者
- 日本精神保健・予防学会
- 雑誌
- 予防精神医学 (ISSN:24334499)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.1, pp.16-24, 2019 (Released:2020-12-01)
- 参考文献数
- 29
本シンポジウムでは、思春期の発達障害の多様性について、Irritabilityを中心に総括した。思春期における自閉スペクトラム症や注意欠如・多動症を代表とする発達障害を抱えた子どもたちが、思春期になって初めて医療機関に登場することがある。思春期になった発達障害児たちは、その固有な症状よりも不登校・家庭内暴力などの多彩な問題に直面していることがある。これらの症状の背景に幼少期から抱えてきた不全感や、Irritabilityとして表出される抑うつ感が潜んでいることがあり、臨床医たちはこの不全感やIrritability共感的に接することを忘れてはならない。特に思春期の発達障害おけるIrritabilityは周囲との軋轢や問題行動と関連するなど、低い自己肯定感を強化しさまざまな精神症状を誘発するKey症状として理解しなくてはならない。
1 0 0 0 OA 佐藤信淵の国土計画思想に関する研究
- 著者
- 川上 征雄
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, pp.379-384, 1995-10-25 (Released:2018-12-01)
- 参考文献数
- 8
THIS STUDY DEALS WITH A SCHOLAR NAMED NOBUHIRO SATO (1769?-1850) WHO LIVED IN EDO PERIOD. HE WROTE MANY THESISSES IN POLITICS, ECONOMICS, AND NATIONAL MANAGEMENT ETC. I EXAMINE HIS THOUGHT IN THE NATIONAL PLANNING FIELD. BECAUSE PREWAR SHOWA ADMINISTRATION USED TO REFER SATO'S THESISSES, ESPECIALLY WHEN THE FIRST NATIONAL PLAN WAS TRIED. SATO'S THOUGHT ON THE NATIONAL PLANNING POLICY WAS RATHER FUNCTION-ORIENTED AND CENTRALIZED INTENTION WITH HIERARCHIC STRUCTURE. A FEW OF HIS IDEAS MIGHT BE STILL COMMON IN THE NATIONAL PLANNING POLICY NOW.
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.1981, pp.78-80, 2019-03-04
15年の初夏。同社の倉庫には秋冬の主力商品である機能性肌着「ヒートテック」が山積みされていた。本格的に売れ始める時期までまだ半年ほどある。明らかな過剰在庫だった。
- 著者
- 錦野 将元 越智 義浩 長谷川 登 河内 哲哉 大場 俊幸 海堀 岳史 永島 圭介
- 出版者
- 一般社団法人日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会講演概要集 (ISSN:13428349)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.2, 2010-08-18
1 0 0 0 OA Shakespeare newsletter
- 著者
- 日本シェイクスピア協会
- 出版者
- 日本シェイクスピア協会
- 巻号頁・発行日
- vol.2020, no.(1), 2020-10-01
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.1763, pp.28-33, 2014-10-27
我々と東レの関係は、未来の産業の教科書に載るんじゃないか。売り手と買い手が一心同体になり、お互いの技術と知見をオープンにして、全く新しい商品を生み出していく。原材料の特性を知っている東レと組めたからこそ、当社は「ヒートテック」のようなヒッ…