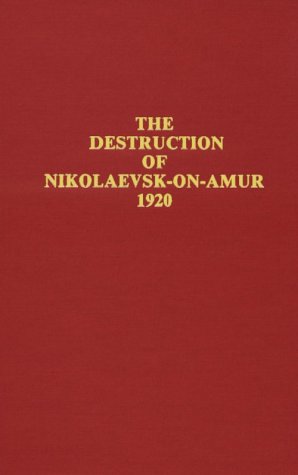1 0 0 0 OA 選択性緘黙の理解と治療 : わが国の最近10年間の個別事例研究を中心に
- 著者
- 相馬 壽明
- 出版者
- 一般社団法人 日本特殊教育学会
- 雑誌
- 特殊教育学研究 (ISSN:03873374)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.1, pp.53-59, 1991-06-30 (Released:2017-07-28)
1 0 0 0 IR <悪魔と天使の法学入門第45話>事業仕分けと国立大学予算
- 著者
- 星野 豊 Hoshino Yutaka
- 出版者
- 学事出版
- 雑誌
- 月刊高校教育
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.15, pp.86-87, 2010-12
1 0 0 0 OA 2型糖尿病患者における安静時エネルギー消費量に及ぼすSGLT2阻害薬の影響
- 著者
- 藤山 友紀 立花 詠子 塚原 丘美 草間 実 今峰 ルイ 溝口 麻子 間瀬 創 佐藤 愛 関口 まゆみ 渡会 敦子 中島 英太郎
- 出版者
- 名古屋学芸大学管理栄養学部
- 雑誌
- 名古屋栄養科学雑誌 = Nagoya Journal of Nutritional Sciences (ISSN:21892121)
- 巻号頁・発行日
- no.4, pp.9-16, 0208-12-25
糖尿病治療では、良好な血糖コントロールを行う上でエネルギー摂取量の遵守は重要である。しかし、糖尿病治療薬によっては安静時エネルギー消費量(REE)に影響を及ぼすことが報告されている。そこで、sodium glucose cotransporter 2(SGLT 2)阻害薬のREEに及ぼす影響を検討した。外来受診中の2 型糖尿病患者20名を対象に、SGLT 2 阻害薬服用前と3か月後でREE 測定、体組成測定、血液検査、食物摂取頻度調査を行い比較した。結果、REE は服用前後で1554±257kcal/ 日から1491±313kcal/日と低下傾向を示したものの有意差は認められなかった。また、体重当たりのREEも有意差は見られなかった。体重や体脂肪量が有意に低下したが、骨格筋量は有意な変化は見られなかった。以上の結果より、3ヶ月間のSGLT 2阻害薬服用ではREEに影響を及ぼさない可能性が示唆された。今後は症例数を増やした検討が必要である。
1 0 0 0 OA 歯牙のピンク色着染現象に関するキャピラリーを象牙細管モデルとした実験的研究
- 著者
- 高野 恵 佐藤 啓造 藤城 雅也 新免 奈津子 梅澤 宏亘 李 暁鵬 加藤 芳樹 堤 肇 伊澤 光 小室 歳信 勝又 義直
- 出版者
- 昭和大学学士会
- 雑誌
- 昭和医学会雑誌 (ISSN:00374342)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.5, pp.387-394, 2009-10-28 (Released:2011-05-20)
- 参考文献数
- 24
死後変化が進んだ死体において時に歯が長期にわたりピンク色に着染する現象が知られており,ピンク歯と呼ばれ,溺死や絞死でよく見られる.ピンク歯発現の成因として歯髄腔内での溶血により,ヘモグロビン(Hb)が象牙細管内に浸潤していくことが推測されているが,生成機序も退色機序も十分明らかになっていない.先行研究において実験的に作製したピンク歯では一酸化炭素ヘモグロビン(COHb)や還元ヘモグロビン(HHb)によるピンク歯は6か月以上,色調が安定であったのに対し,酸素ヘモグロビン(O2Hb)によるピンク歯は2週間で褐色調を呈し,3週間で退色することを既に報告している.ピンク歯の生成・退色機序を解明するうえで,O2Hbによるピンク歯が早期に退色する現象を詳細に検討することは意義のあることと考えられる.う歯がなく,象牙細管がよく保たれた歯の多数入手が不可能であるため,本研究では象牙細管のモデルとして内径1mmのキャピラリーを用い,O2Hbによるピンク歯の退色について詳細に検討した.実際の歯とキャピラリーを用いてO2HbとCOHbの退色を比較したところ,キャピラリーはピンク歯のよいモデルとなることが分かった.キャピラリーを用いた詳細な実験で,O2Hbは酸素が十分存在し,赤血球膜も十分存在するという限られた条件において早期に退色することが明らかになった.このことはO2Hbに含まれる酸素が赤血球膜脂質と反応してHbの変性を来し,Hbの退色をもたらすことを示唆している.この退色は温度の影響をほとんど受けず,防腐剤の有無にも影響を受けなかった.死体では死後に組織で酸素が消費され,新たに供給されないので,極めて嫌気的な環境にあり,死後産生されたCOHbを少量含む主としてHHbによる長期的なピンク歯を生じやすいといえる.溺死体のような湿潤な環境で象牙細管へのHHbやCOHbの侵入と滞留があれば,ピンク歯はむしろ生じやすい現象といえるであろう.
- 著者
- 石井 明
- 出版者
- 上武大学ビジネス情報学部
- 雑誌
- 上武大学ビジネス情報学部紀要 (ISSN:13476653)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.1, pp.1-24, 2010-09-30
本論文では、アメリカの20世紀初頭における鉄道会社の設備金融の特質および問題、リース方式―フィラデルフィア方式―による設備金融の歴史、設備信託スキームおよび法律上の問題点、リースの会計実務および会計報告の基準等を検討する。そして、20世紀初頭、州際商業委員会(ICC)の設定した規定によって、アメリカの鉄道会社が使用するリース設備が所有設備と合算されて「設備」として資産計上されており、さらに、今日の企業会計の経済的実質に基づくリースの資本化論とは異質の考え方である「法的実質」の理論があったことを明らかにする。
1 0 0 0 簡易成形法による自転車部品への炭素繊維の応用
- 著者
- 木村 南
- 出版者
- 日本デザイン学会
- 雑誌
- 日本デザイン学会研究発表大会概要集
- 巻号頁・発行日
- vol.50, pp.36, 2003
自転車の軽量化のために1985年以降、日本の東レで開発された炭素繊維が自転車フレームとして採用され、オリンピックで東ドイツチームが金メダルを取り、その後ツールドフランスでの活躍もあり、自転車用素材として炭素繊維は広く受け入れられてきた。また、チタン合金もTig溶接の進歩に伴って徐々に拡大されている。またAlパイプも大径化により、ヤング率の低さをカバーして広く用いられるようになってきた。当初は接着構造が主体であったが、Tig溶接に置き換わってきている。これらの自転車における新素材の応用について過去30年間の日本で入手できる自転車、自転車部品を雑誌広告の中から抽出し、材料開発、接合技術開発の観点から整理した。結論として材料開発から約3_から_10年後に実用化がなされ、コスト的に従来材のCr-Mo鋼パイプのろう付け構造と同一コストになるまでにはさらに5_から_10年を要した。そこで著者が開発したオートクレーブを使用しないゴム型を利用する簡易成形法により、炭素繊維の応用例が少ない自転車ペダル等(Vf=25_から_40%)への応用を試みた。この技術を将来的には車椅子の軽量化に応用することを目的としている。
1 0 0 0 OA 4 医療への接着剤の応用
- 著者
- 林 壽郎
- 出版者
- 一般社団法人 溶接学会
- 雑誌
- 溶接学会誌 (ISSN:00214787)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.2, pp.257-261, 2001-03-05 (Released:2011-08-05)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 サッカーにおけるデータ分析とチーム強化
- 著者
- 加藤 健太
- 出版者
- 一般社団法人 電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会 通信ソサイエティマガジン (ISSN:18844863)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.1, pp.29-34, 2016
1 0 0 0 OA 体表面微細振動研究の諸問題
- 著者
- ロールアツヘル フーベルト
- 出版者
- 耳鼻と臨床会
- 雑誌
- 耳鼻と臨床 (ISSN:04477227)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.4, pp.209-217, 1966-12-20 (Released:2013-05-10)
- 参考文献数
- 22
Mikrovibration (体表面微細振動) の研究が日本ほど盛んに行なわれている国は他になく, その日本の科学雑誌に寄稿するのは喜びにたえない. さて, こゝでは生理学的および技術的問題点を取り上げてみたい.Mikrovibration (以下MVと略す) は温血動物のみにみられる全身的の不断の微細振動であると定義することができよう. これは肉眼的な振動と比較され, Miner Tremor (稲永, 1959) とかphysiologischer Tremor (Stuart, et al. 1963) と呼称された. だが Tremorというのは一定条件 (寒さ, 興奮) で起こる生体の反応や脳疾患 (パーキンソン氏病) で起こるものであり, MVは生涯間断なく続くものである. しかもこれは生体の反応でなく, 永続的な筋活動である. 従つてTremorというよりMVと命名する方が妥当である. それで私は「MVとは温血動物のみにみられ, 全身に存在する永続的な振動で, 健康成人は7~14cpsの周波数をもつものである」と定義する.生物学的問題: MVの生物学的機能はまだ不明である. しかし体温保持と筋緊張が問題となる. 運動神経を切断された四肢ではMVが消失する (菅野, 1957) ことから, これは筋線維の収縮によつて生ずるといえる. またMVは温血動物のみに存在することから, 永続的筋収縮によつて体温を保持するに必要な熱量が生産されていることと関係があると思われる. 身体の弛緩状態および睡眠中は筋肉の活動電流は認められない (Buchthal, 1958). だがその場合でも存在する収縮性筋トーヌスはいかなる機構でなされているかという問題が生ずる. 冷血動物の筋トーヌスはいわゆる遅速線維-温血動物にはみられない-の収縮によつて生ずるようである (Reichel, 1960). また組織と体液のリズミカルな振動が生体の化学的作用に無関係とは思われない. これらの点に大きな意義を有すると考えられるMVの力学的力は, 鉛板による測定実験で, 意外に大きいことが判明した.MVのもう一つの生物学的作用は迷路の受容器の刺激にある. 三半規管の内リンパ液がMVによつて一定の振動をなしていて, そこに存在する受容器は常に刺激されていると考えられる. その刺激が中枢へ伝えられることによつて, 人間は安静時でも方向知覚を保持するのであろう. この仮説の証明のために, 平衡障害患者と正常人で比較実験が行なわれ, 前者では周波数は高く, 振幅は小さいことが実証された (永淵, 1966). この仮説から次のことが考えられる. すなわちMVを欠く冷血動物は温血動物に比較して, 迷路から体位についての情報が少なく, そのため平衡維持が困難であろう. このように考えると, MVは系統発生学にも意義をもつてくる. 温血であることもMVによつて初めて生ずることから, 哺乳動物や鳥類に重要な二つの器官-体温と平衡調節-は系統発生史上ほぼ同時期に現れたといえる.MVの発生に二つの仮説-心搏説と筋原説-がある. 心搏説 (Brumlik, 1962, Buskirk & Fink, 1962) によると, MVは心搏動による身体の共振であると述べている. だがMVは死後数分間認められる (Rohracher, 1954, 菅野, 1957, 吉井, 1965). 実際には心搏の影響をMVから完全に分離することは出来ない. MVの機構は筋原説でうまく説明出来る. 各運動神経線維は多くの筋線維を支配しており, 個々の筋線維が, それぞれ収縮を行なうと周囲に振動を及ぼし, それが綜合されて一つの持続的な微細運動を形成する. 菅野 (1957) と吉井 (1963) は動物実験で頸部脊髄を切断してもMVは存続することを証明した. 脊髄反射が筋線維の収縮に大きな役割を果していることは明らかである. 菅野は脊髄後根を切断すると, その領域の MVは一時増大したあと消失することを証明した. このことから菅野と福永 (1960) はMVの発生に脊髄反射が関与していると述べている. MVの発生機序には脊髄反射以外に中枢支配も考えねばならない. 温度が低下すると, MVの周波数は増加し, それによつて筋肉内の熱量が産生される. この調節は非常に正確に行なわれており, その中枢は視床下部にある. この中枢と筋収縮との間には, 脊髄の運動細胞, ガンマ運動神経, 筋紡錘が関与している.低温ではMVの周波数は高い成分が優位となり, 振幅は減少する (Rohracher, 1954, 1958). だがこの逆の事実が発見された. すなわち人体のMVは冬でその周波数が高く夏で低いという実験結果である. また温帯地方の住民は寒帯地方の住民よりMV周波数は高い (日本人とオーストリア人の比較実験). この説明はまだなされていない.技術的問題: 技術的に最も困難なことはMVの正確な測定である. Marko (1959) は光学的にMVを可視出来るように試みた. 他には電気力学的にこれを把握しようと工夫されている. MVが正絃波振動であれば正確に測定出来るが, 実際は複雑なので正確な測定は困難である. MV測定の理想は, ピツクアツプが小さくて軽いこと, そして振幅と周波数を積分せずに正確に記録出来ることである. 現在はまだこれがないので, 加速度型ピツクアツプと積分装置で測定しなければならない. MVはこの他, 筋活動の本体, 臨床医学的応用, 更に筋活動に必要なエネルギーと体温との関係等の問題をもつている.
1 0 0 0 実践編 会員制からオークションまで 火花散る年末商戦の舞台裏 (特集 3兆円市場が動き出す!ネット商戦「冬の陣」--e-歳暮、e-クリスマス、e-ボーナス 99年末、日本のECがついにブレーク)
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ネットビジネス (ISSN:13450328)
- 巻号頁・発行日
- no.54, pp.82-89, 2000-01
「今年の売れ方は今までとはまるで違う。一度に10件もまとめて注文するユーザーが出てきた。中元商戦のときは試し買いのユーザーが多かったが、勢いが全く違ってきた」(東急百貨店の営業推進室営業政策部EC推進の田渕也寸志統括マネジャー)。 「11月27、28日の最初のピークを過ぎて、1日に70から80件の注文が入るようになった。
1 0 0 0 言論自由論・勃爾咢ヲ殺ス
1 0 0 0 IR メルボルン事件の通訳に関する研究
1 0 0 0 IR 景清伝承の起源と展開--口承文芸と記載文芸のはざまから見た
- 著者
- 松前 健
- 出版者
- 奈良大学
- 雑誌
- 奈良大学紀要 (ISSN:03892204)
- 巻号頁・発行日
- no.23, pp.p75-96, 1995-03
鎌倉時代の軍記物、室町時代の謡曲、舞の本、それから江戸時代の浄瑠璃、歌舞伎に至るまで、民衆の英雄として、人気の的であった人物の一人は、悪七兵衛景清であった。景清の史実性についての確実な資料は乏しく、『吾妻鏡』などにも、その名は現れない。ただ十二巻本の『平家物語』では、八島合戦のとき、美尾谷十郎との一騎打ちの中で、豪快なシコロ引きの話が語られる位で、そのほかは、大勢の平氏の武者の中に、その名をつらねるだけで、それほどの武将とも思われない。
1 0 0 0 選鑛研究會開催の發議
- 出版者
- 一般社団法人 資源・素材学会
- 雑誌
- 日本鑛業會誌 (ISSN:03694194)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.513, pp.82, 1928
- 著者
- 中須 晴南 湯川 夏子 中西 洋子
- 出版者
- 日本家庭科教育学会
- 雑誌
- 日本家庭科教育学会大会・例会・セミナー研究発表要旨集 第57回大会・2014例会
- 巻号頁・発行日
- pp.62, 2014 (Released:2015-01-10)
【目的】中学校技術・家庭科の技術分野において、新学習指導要領より「生物育成」が必修となった。「生物育成」の中には、野菜の栽培も含まれる。また、家庭分野の調理実習においては、野菜を使った料理を取り上げることもできる。したがって自分たちで食材を栽培し、調理して食べるという技術科と家庭科の連携の授業ができると考えた。しかし、どの野菜が栽培と調理実習の連携の教材として適しているのか、またどのように連携授業を行えばよいのか明らかではない。そこで本研究では、「生物育成」で栽培する野菜の検討及び連携授業の提案と実践を行い、その教材の教育的効果を検証することを目的とした。【方法】2012年5月~2013年8月に、中学校技術科の教科書に記載されている野菜を中心に、16種類の野菜を栽培し、評価を行った。評価の結果、適していると考えられた野菜の一つである万願寺とうがらしを用いた教材を提案し、授業実践を行った。授業実践は2013年10月に、京都府内のA中学校の第1学年(124名、4クラス)を対象とし、講義と調理実習の授業実践と、授業実践前後にアンケート調査を行った。調査内容は、万願寺とうがらしの知名度や好き嫌い、イメージ等、である。【結果】栽培と調理実習の連携授業を行うにあたっては、「収穫しやすく、かつ一度に多く収穫できる」野菜であり、「50分間という短い時間でも可能な調理実習内容」という課題を解決する必要があることを我々は明らかにした1)。そこで、栽培をした野菜について1.簡単さ、2.面白さ、3.時季、4.関係性、5.調理への応用、という5つの観点から評価した結果、ピーマン、万願寺トウガラシ、シシトウ、ミズナ、コマツナ、ホウレンソウ、ジャガイモがその条件を満たしており、かつ総合的にも栽培と調理実習の連携に適した教材であることが分かった。 これらの野菜の中から、京野菜でもある、万願寺とうがらしを選び、育ち方や旬、京野菜についての講義と、短い時間でもできる「万願寺とうがらしと厚揚げの炒め煮」の調理実習を提案し、授業実践を行った。授業後にアンケート調査を行った結果、万願寺とうがらしに対するイメージの変化や好みの変化が見られ、講義や調理実習を通して生徒の意識を変え、可能性を広げることができた。また、京野菜の一つである万願寺とうがらしの学習をしたことで、他の京野菜にも関心をもつきっかけにもすることができた。本授業の目標は、「万願寺とうがらしについて理解を深め、万願寺とうがらしを使った料理を作ることができる。」であったが、調理実習に意欲的に取り組んでいたことからも授業の目標は達成できたといえる。調理実習は、4クラスとも50分間で片付けまで終わらせることができていたことも含め、「万願寺とうがらしと厚揚げの炒め煮」は教材として適しているといえるだろう。 以上のことから、万願寺とうがらしを用いたこの教材の教育的効果は認められ、栽培と調理実習の連携の授業として有効であるといえる。今後は、栽培と調理実習の連携の授業を推進していくために、「収穫しやすく、かつ一度に多く収穫できる」野菜を用いた、「50分間という短い時間でも可能な調理実習内容」等の調理実習教材を開発することが必要である。また、京都府以外でも実践できる「地域の食文化」の内容と関連づけた、各地域の特産物や郷土料理を用いた教材を開発することも必要であろう。そして、教員自身の意識を高め、「生物育成」と調理実習の連携を推進していきたい。 引用文献1)中須晴南ら;教育実践研究紀要 Vol.14,印刷中(2014)
- 著者
- 高橋 ゆう子
- 出版者
- 一般社団法人 日本特殊教育学会
- 雑誌
- 特殊教育学研究 (ISSN:03873374)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.4, pp.231-240, 2008
- 被引用文献数
- 1
本研究では、歩行が安定しない重度の知的障害児2名に動作法を適用し、身体への気づきが促され、過度な緊張の弛緩や適度な緊張が獲得されるプロセスにおいて、日常行為がどのように変容するか、特に母親との関係の中でとらえられる子どもの変容に着目して検討を行った。分析にあたっては、動作法適用の経過、日常生活での様子、さらに発達検査の項目に関する母親の自由記述を資料とした。その結果、日常行為の変容過程における特徴として、(1)日常行為での身体の気づきが高まる、(2)周囲への注意が変化する、(3)試行的な動きが生じる、(4)情緒不安定さが軽減する、というプロセスがとらえられた。そこから身体の操作性と日常行為との関連、日常行為の変容に関する母親の気づきについて考察を行った。