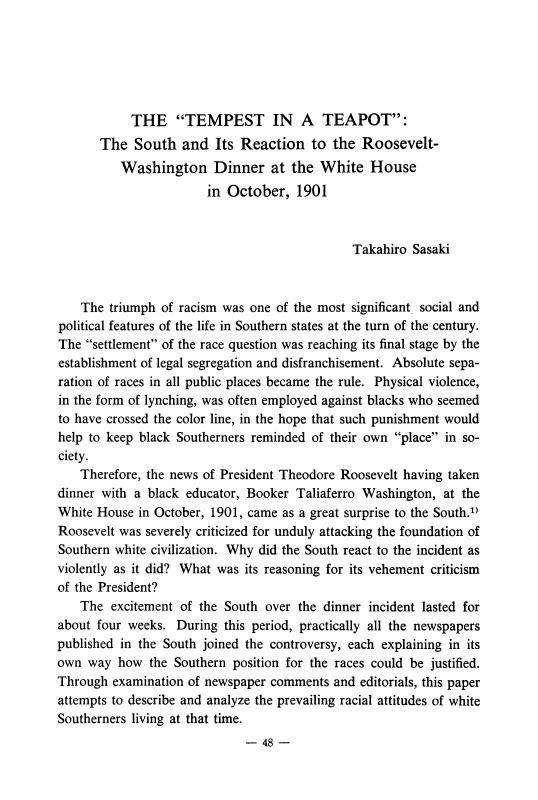1 0 0 0 OA 他者と如何に関係すべきか
- 著者
- 青木 克仁 Katsuhito Aoki
- 出版者
- 安田女子大学大学院
- 雑誌
- 安田女子大学大学院紀要 = The journal of the Graduate School, Yasuda Women's University (ISSN:24323772)
- 巻号頁・発行日
- no.26, pp.41-51, 2021-03-31
ハラリが指摘している通り,人間は「フィクション」を操ることでこの世に君臨する生き物になった。「フィクション」という夾雑物なしでは,生きることのできない,実に不可思議な生き物となったのだ。それゆえ,個人の問題に関しても,人間は自分の「自己イメージ」という,自己にまつわるフィクションを介して自分自身と関係する生き物になった。フロイト経由で,ラカンが指摘しているように,人間関係はどうしても4者関係になってしまう。私とあなたの間に私の「自己イメージ」とあなたの「自己イメージ」が介在してしまうからだ。本論考は,「イメージ」を介在させずに,人間関係を築くことは可能なのだろうか,という問いを立て,その答えを見出すべく議論を展開している。
- 著者
- Takahiro Sasaki
- 出版者
- THE JAPANESE ASSOCIATION FOR AMERICAN STUDIES
- 雑誌
- アメリカ研究 (ISSN:03872815)
- 巻号頁・発行日
- vol.1986, no.20, pp.48-67, 1986-03-25 (Released:2010-10-28)
- 参考文献数
- 81
1 0 0 0 7.転移性肺腫瘍の切除経験 : 第21回肺癌学会関関西支部会
- 著者
- 加来 耕三
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ベンチャ- (ISSN:02896516)
- 巻号頁・発行日
- no.231, pp.122-125, 2003-12
中上川(彦次郎)さんはじめ、益田(孝)さん、團だん(琢磨)さん、池田(成彬)さん、向井(忠晴)さん。あるいは中上川さんの前に活躍した三野村利左衛門さんと三井を主宰された方は、それぞれいろいろな業績を残されていますが、なんといっても中上川さんが一番でしょう。それをわずか十年間でやられたんだからたいへんな人だったんですね。
- 著者
- 佐々木 博明 寺田 浩一 柳谷 聡
- 出版者
- 公益社団法人 空気調和・衛生工学会
- 雑誌
- 空気調和・衛生工学会大会 学術講演論文集 (ISSN:18803806)
- 巻号頁・発行日
- vol.1998, pp.1441-1444, 1998
- 著者
- 鶴 宏史
- 出版者
- 大阪府立大学
- 雑誌
- 社會問題研究 (ISSN:09124640)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.1, pp.179-197, 2007-12
1 0 0 0 腎盂腫瘍を疑わしめたグラビッツ腫瘍の1例 : 第65回東海地方会
- 著者
- 加治 安彦 内山 記世之 福島 賢秀
- 出版者
- 社団法人日本泌尿器科学会
- 雑誌
- 日本泌尿器科學會雜誌 (ISSN:00215287)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.3, 1965
1 0 0 0 IR 新しい「帝国」概念の有効性 : ハートとネグリの『帝国』をめぐって
- 著者
- 植村 邦彦
- 出版者
- 関西大学経済・政治研究所
- 雑誌
- 多元的経済社会の展開
- 巻号頁・発行日
- pp.19-48, 2003-03-31
一つの妖怪が世界をうろついている。「帝国」という妖怪が。すでに1997年には、極東の片隅でもこう言われていた。「帝国の到来をめぐる予言が今日ほどさかんだったことはない。しかもそれは、一地域における帝国の誕生ではなく、世界帝国とも言うべきものの出現である(1)」。この「世界帝国」の表象について、『帝国とは何か』の編者の一人である増田一夫は、次のように説明している。「われわれの目前で成立しつつあるかもしれないとされる帝国は、武力制覇によって成立するのでもなく、中心的な核もなく、あくまで匿名であり続けると言われている。このイメージは政治よりも経済、経済よりもコミュニケーションの分野で実際に起こっている事態を想起させる。ピラミッドや樹[ツリー]状の組織ではなく、無限に接続し合い絡み合うウェブもしくはネットワーク。あらゆる地点からのランダム・アクセスの可能性を備えた開かれたシステム。根茎[リゾーム]状の組織。これはドゥルーズとガタリの著作『資本主義と分裂症』において提示されたイメージにほかならない(2)」。そのように述べたうえで、増田は次のように結論を保留している。「そして『帝国』。その到来の予感は、一部の人々の期待を代弁しているにすぎないのかもしれない。……しかし『帝国』は、たんに、国民国家が弱体化してゆくなか、その崩壊の後に来る事態を『混沌』と呼ぶのを忌避して用いられる名にすぎないのかもしれない(3)」。このような叙述からわかるように、最近現れた「帝国」という言説は、イマニュエル・ウォーラーステインによって提起された資本主義「世界システム」論やその上部構造としての「インターステイト・システム」論に取って代わる、新しい世界認識の概念として論じられているのであって、従来の「帝国主義」論や「帝国主義の問題を『意識』に即して見ること(4)」をテーマとする「帝国意識」論とは問題関心が基本的に異なると考えるべきであろう。本論文は、このような意味での「帝国」論の最新の成果であり、2000年にアメリカで出版されるとすぐに大きな話題を呼んだマイケル・ハートとアントニオ・ネグリの共著『帝国(5)』を取り上げ、その内容を紹介したうえで、その理論的な有効性について考えようとするものである。
1 0 0 0 グラビッツ腫瘍の皮膚転移例
- 著者
- 野村 房江
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 臨床皮膚科 (ISSN:00214973)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.11, pp.1161-1166, 1969-11
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 冬營地における御崎馬:御崎馬の社会調査・報告第2
- 著者
- 今西 錦司
- 出版者
- 日本動物心理学会
- 雑誌
- 動物心理学年報 (ISSN:00035130)
- 巻号頁・発行日
- no.3, pp.11-31, 1953
- 被引用文献数
- 3
i) 冬季における御崎馬の社会では, 1 頭または 2 頭からなる小世帶を, 形成しているものが多い。<BR>ii) これらの小世帶の中には, お互いにその行動圏の overlap しているものがあつて, その間には neighborhood 関係の認められるものもある。<BR>iii) 大世帶で生活しているものは, グループとして独立している;すなわち他の世帶と, neighborhood 関係で結ばれていない。交尾期になつても, 交尾集団の成立のために, グループを解散するようなごとはない。<BR>iv) 大世帶グループには, nelghborhood 関係というよりも, 知己関係といつた方がよいような馬が, 客員としてはいつてきている。<BR>v) 大世帶グループでは, その中にいるリーダー格の馬が, アトラクションの中心となつている。その馬を中心に, 血縁的な結びつきの存在することも考えられるが, 必らずしもそれだけでにないらしい。客員は, このリーダーにひかれて, グループに入つてきているように見える。<BR>vi) 〓の行動圏は一般にひろい。その中には大世帶の行動圏も, 小世帶の行動圏もふくまれる。そこに〓を介した community 関係ともいうべき, 一つの社会関係が認められる。<BR>vii) しかし, 大世帶と小世帶とで, 〓に対する関係がちがう。〓は小世帶をリードできても, 大世帶をリードすることはできない。ゆえに大世帶に対しては, 〓も客員となつてそのリードにまかすか, あういはその中かち結合の弱いものを, とりこにするの他はない。<BR>viii) 以上から, この馬の社会では, 〓の地位と, 大世帶グループのリーダーとなつている〓の地位とが, social organization の key point をなすものである, といえよう。<BR>ix) われわれはこれで, 春の交尾期と冬の疎開期との, 概況を知つたから, つぎには, イワクラと小松が辻の草地に, ほどんどすべての馬が出そろうという, 夏の集中期をえらんで調査してみたいのである
1 0 0 0 IR 社会問題の解決に向けた市場創造アプローチの検討 : 犬の譲渡普及促進に向けて
- 著者
- 岩倉 由貴 イワクラ ユキ Yuki Iwakura
- 雑誌
- 経済と経営
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.2, pp.63-72, 2013-03
1 0 0 0 IR 動物と暮らす : 動物愛護管理行政における協働 (平成24年度共同プロジェクト成果報告)
- 著者
- 岩倉 由貴 イワクラ ユキ Yuki Iwakura
- 出版者
- 札幌大学附属総合研究所
- 雑誌
- 札幌大学総合研究 = Sapporo University Research Institute journal (ISSN:18848982)
- 巻号頁・発行日
- no.7, pp.59-74, 2015-12
- 著者
- 榎木 英介
- 出版者
- 近畿大学医学会
- 雑誌
- 近畿大学医学雑誌 = Medical Journal of Kindai University (ISSN:03858367)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.3-4, pp.9A-17A, 2017-12-20
1 0 0 0 ビデオ文脈依存再認におよぼすアウトシャイン原理の影響
中島・漁田・漁田(2015)は,再認弁別におけるビデオ文脈依存効果が手がかり負荷の増大にともなって消失することを示し,手がかり負荷の増大にともなう手がかり強度の低下をアウトシャイン原理の影響と推測した。本研究は,この推測の妥当性を検証することを目的とし,同じ手がかり負荷のもとでも,項目手がかり強度を下げることでビデオ文脈依存効果が生じるかを調べた。実験は,中島ら(2015)の手がかり負荷18条件の材料および手続きを踏襲したが,項目の提示時間のみ,中島ら(2015)の4秒/項目から1.3秒/項目に変更した。実験の結果,手がかり負荷が同じであっても,項目の提示時間が短い場合には再認弁別においてビデオ文脈依存効果が生じた。この結果は,中島ら(2015)の推測の妥当性を高めるとともに,ビデオ文脈依存再認がアウトシャイニングを支持することを意味している。