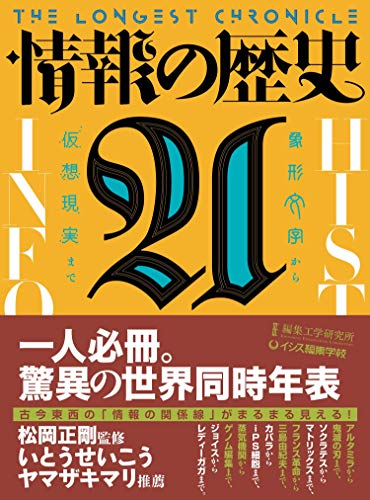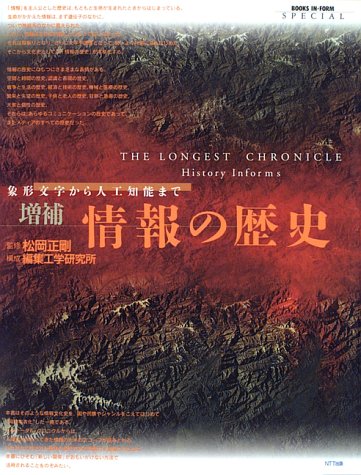- 著者
- 井出 剛 小崎 丈太郎
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経バイオビジネス (ISSN:13464426)
- 巻号頁・発行日
- no.20, pp.96-101, 2003-01
創薬の基盤技術として製薬会社に提供しようというベンチャー企業がトランスジェニックだ。12月10日にマザーズ上場を準備中の井出社長に勝算を聞いた。(聞き手は本誌編集長:小崎丈太郎)—— 投資家向けの事業説明をやられていますね。いわゆるロードショーの真っ最中なわけですね。一番よく出る質問とは何ですか?井出 収益モデルについて質問がよく出ますね。
1 0 0 0 IR 日本におけるロボットの変遷と表現との関係
- 著者
- 西山 禎泰
- 出版者
- 名古屋造形大学
- 雑誌
- 名古屋造形大学紀要 (ISSN:21850208)
- 巻号頁・発行日
- no.17, pp.151-166, 2011
1 0 0 0 IR 生存権をめぐる対立と社会保障: 憲法25条と生活保護法(旧法)の関連を中心に
- 著者
- 村田 隆史
- 出版者
- 金沢大学大学院人間社会環境研究科 = Graduate School of Human and Socio-Enviromental Studies Kanazawa University
- 雑誌
- 人間社会環境研究 = Human and socio-environmental studies (ISSN:18815545)
- 巻号頁・発行日
- no.28, pp.93-108, 2014-09-26
1 0 0 0 IR アルメニアにおける日本研究
- 著者
- ホワニシャン アストギク
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 世界の日本研究 = JAPANESE STUDIES AROUND THE WORLD (ISSN:24361771)
- 巻号頁・発行日
- no.2020, pp.37-47, 2021-03-31
アルメニア共和国の教育機関において日本研究コースが初めて開かれたのは2009年であるため、同国における日本研究の歴史は決して長くない。しかし、20 世紀初頭から日本に関する著書が出版され、また日本の文学作品が、ロシア語などの言語を媒介して翻訳されている。本稿では、アルメニア国立図書館で保管されている日本に関する著書や、アルメニア語に翻訳された文学作品を紹介し、アルメニアにおける日本研究の現状や課題について述べる。
1 0 0 0 「造り物」の観点から見た箱庭と箱庭療法
- 著者
- 菱田 一仁
- 出版者
- 日本箱庭療法学会
- 雑誌
- 箱庭療法学研究 (ISSN:09163662)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.3, pp.27-38, 2019 (Released:2019-06-14)
- 参考文献数
- 39
河合(1975)の言うように,箱庭療法は古来行われてきた箱庭遊びとの関連を持っている。そして,箱庭が生まれてきた経緯について歴史的に見ていくと,それが大嘗祭における標の山のような造り物の系譜の中に生まれてきたものであることが分かる。造り物はのちの世には次第に洲浜や灯籠,盆景といった様々な形で作られるようになった。造り物は,見立てという技法を持つことによって,その置かれる場所を超越的な経験の起こる場所へと変える力を持っているといえる。見立てとはある種の隠喩であり,それによって造り物は,見たままの意味とそれの暗示する内的な真実という二つのものを同時に表すことができるようになると考えられる。つまり,造り物という観点から改めて見るとき,同様に見立てという技法によって作られたり見られたりする箱庭も同じような特徴を持っており,だからこそそこに投影された隠れたクライエントの本質を明らかにすることができるようになると考えられる。
1 0 0 0 OA 長崎県立長崎北陽台高校理数科 課題研究化学班(化学クラブただ今実験中!,実験の広場)
- 著者
- 野口 大介
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 化学と教育 (ISSN:03862151)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.3, pp.113, 2012-03-20 (Released:2017-06-30)
- 参考文献数
- 2
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 強磁場下における銅樹析出反応の実験条件:ローレンツ力を可視化する教材としての検討
- 著者
- 野口 大介 島田 旭
- 出版者
- 一般社団法人 日本科学教育学会
- 雑誌
- 科学教育研究 (ISSN:03864553)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.4, pp.321-327, 2020 (Released:2021-02-05)
- 参考文献数
- 29
Metal dendrites can be valuable learning materials for the visualization of the Lorentz force in chemical reactions; however, the appropriate experimental conditions for this purpose such as the voltage, reaction time, magnitude of magnetic field, and electrolyte solution concentration are not known. Hence, we conducted experiments to effectively visualize metal dendrite precipitation in a swirling shape due to the Lorentz force generated by the magnetic field and for use as practical teaching materials. The electrolysis was carried out at a voltage of 20 V, 15 V or 10 V for 1 or 2 min with 3 or 5 rare-earth magnets in piles and a CuSO4 aqueous solution with the concentrations of 0.050, 0.10, and 0.15 mol L–1. It was found that the magnetic field was increased using the magnets stacked, even though the effect decreased with increasing numbers of layers. To observe the shape of the metal dendrites under a magnetic field effectively in a short time, the concentration of the aqueous CuSO4 was determined to be 0.10 mol L–1. The magnetic field was increased using magnets in piles, even though the effect decreased with increasing numbers of layers. A copper wire was used repeatedly as the anode, and the mass of the copper participating in the reaction gradually decreased. The magnitude of the applied voltage was not sufficiently studied in this work, and will be investigated in future studies.
1 0 0 0 OA 表面張力で油滴を動かす条件 薬よ届け!!
- 著者
- 濵﨑 桃香 末永 遥香 磯田 童奈
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.7, pp.483-485, 2015-06-20 (Released:2016-06-20)
- 参考文献数
- 2
- 被引用文献数
- 1
本研究は,日本農芸化学会2014年度大会(開催地: 明治大学)での「ジュニア農芸化学会」において発表された.界面活性剤を放出する油滴が,低いpH領域に向かって自ら進むという現象をドラッグデリバリーシステム(DDS)に応用することを目指した興味深い内容であり,本誌編集委員から高い評価を受けた
1 0 0 0 OA 磁力を金属樹の形状で可視化する探究型学習教材の開発
- 著者
- 野口 大介
- 出版者
- 一般社団法人 日本科学教育学会
- 雑誌
- 日本科学教育学会研究会研究報告 (ISSN:18824684)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.3, pp.47-52, 2019-12-21 (Released:2019-12-18)
- 参考文献数
- 81
Copper dendrites exposed to a magnetic field of rare earth magnets in an electrolyzing aqueous solution of CuSO4 resulted in two things. Firstly, a precipitation around the cathode with swirling, and secondly, a growth while spinning around the cathode during the electrolyzing process if a vibration by hand was gently added to the cathode. If these phenomena become inquiring learning materials, it seems to be of significant value in secondary educational practice. In this report, it is shown that the different concentrations of solution change the form of copper dendrites. The lower one needs waiting for enough changing the form, on the other hand, the higher one causes collapse with too strong flow by the Lorentz force acting ions in the solution.
1 0 0 0 OA 探究的な授業実践と金属樹を題材とした課題研究
- 著者
- 野口 大介
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 化学と教育 (ISSN:03862151)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.6, pp.254-257, 2019-06-20 (Released:2020-06-01)
- 参考文献数
- 10
授業実践の探究的な試みとして,マグネシウムと塩酸の反応で水素を発生させ,水素の物質量をどれだけ正確に求められるかを,ドルトンの分圧の法則を用いて実践した。金属樹を題材とした課題研究では,金属樹が回転運動する現象,次々にちぎれる現象について新規に見いだし,研究指導を通じて一定の成果を上げた。
1 0 0 0 OA 分子構造ICT教材開発を志向したナトリウムフェノキシド類結晶構造の文献調査
- 著者
- 野口 大介
- 出版者
- 一般社団法人 日本科学教育学会
- 雑誌
- 日本科学教育学会研究会研究報告 (ISSN:18824684)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.10, pp.23-28, 2020-06-20 (Released:2020-06-17)
- 参考文献数
- 15
高等学校化学においてよく取り上げられるナトリウムフェノキシド(NaOPh)の結晶構造データを取得し,その単分子および結晶中三次元構造を調査した。NaOPhのみからなる純結晶はNa2O2四角形単位を含む(Na2O2)nラダー型ポリマー構造を有しており,ユニークな三次元構造を形成している.一方,水和物結晶であるNaOPh・H2Oでは対イオンであるナトリウムイオンとともに水和されている様子が,さらにNaOPh・3H2Oでは結晶水によりナトリウムイオン対が解離して水に溶解したかのような状態が,それぞれ確認できる.その他の溶媒和結晶の構造からも,溶媒和に伴う(Na2O2)n構造の解離の様子が見られた.これら一連の流れを授業で効果的に展開することで,化学物質の構造や溶解現象を分子間相互作用と結び付けて生徒に理解させることが期待できる.
- 著者
- 野口 大介
- 出版者
- 一般社団法人 日本科学教育学会
- 雑誌
- 日本科学教育学会研究会研究報告 (ISSN:18824684)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.7, pp.33-38, 2020-05-16 (Released:2020-05-13)
- 参考文献数
- 32
Some spiders were easily observed on the campus of Nagasaki University from autumn to winter such as Argiope bruennichi, Thomisus labefactus, Cyclosa confuse, Hasarius adansoni, Argyrodes bonadea, and Leucauge blanda. The spiders that could be found in the field even in winter, outside of the period in which adults are expected to appear by literature, had white, silver, and golden parts of the body surface. The case that the crab spider T. labefactus preyed A. bruennichi in its center of the web is considered to be unique. UV-vis spectrum of L. blanda was measured and shown that the body had gold and yellow parts.
1 0 0 0 IR 全米IR協会(NIRI)年次大会2016にみる「IRの最新動向」
- 著者
- 米山 徹幸 Tetsuyuki YONEYAMA
- 出版者
- 埼玉学園大学
- 雑誌
- 埼玉学園大学紀要. 経済経営学部篇 = Bulletin of Saitama Gakuen University (ISSN:21884803)
- 巻号頁・発行日
- no.16, pp.119-127, 2016-12
- 著者
- Koichiro YAMANAKA Keita TAKAHASHI Toshiaki FUJII Ryuraroh MATSUMOTO
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- IEICE Transactions on Information and Systems (ISSN:09168532)
- 巻号頁・発行日
- vol.E104.D, no.5, pp.785-788, 2021-05-01 (Released:2021-05-01)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 4
Thanks to the excellent learning capability of deep convolutional neural networks (CNNs), CNN-based methods have achieved great success in computer vision and image recognition tasks. However, it has turned out that these methods often have inherent vulnerabilities, which makes us cautious of the potential risks of using them for real-world applications such as autonomous driving. To reveal such vulnerabilities, we propose a method of simultaneously attacking monocular depth estimation and optical flow estimation, both of which are common artificial-intelligence-based tasks that are intensively investigated for autonomous driving scenarios. Our method can generate an adversarial patch that can fool CNN-based monocular depth estimation and optical flow estimation methods simultaneously by simply placing the patch in the input images. To the best of our knowledge, this is the first work to achieve simultaneous patch attacks on two or more CNNs developed for different tasks.
1 0 0 0 IR 子ども自身、保護者、観察者による、発達障害児のレジリエンス評定
- 著者
- 樋口 隆弘 湯浅 龍 石田 陽彦
- 出版者
- 関西大学臨床心理専門職大学院 心理臨床センター
- 雑誌
- 関西大学心理臨床センター紀要
- 巻号頁・発行日
- no.10, pp.21-25, 2019-03
私たちは、発達障害児のレジリエンスの向上を目指したキャンプを実施し、レジリエンスの構成要素である社会性などを下位尺度に含む、The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) を用いて、キャンプ前後の子どものレジリエンスの変化を、子ども自身、保護者、観察者がそれぞれ評定した。その結果、向社会性得点の平均値は、子ども自身、保護者、観察者それぞれの評定で変化は見られなかったが、保護者と観察者から見た子どもの困難さ得点の平均値が有意に低下した。ただし、三者間において、子どもの困難さと向社会性得点の平均値に差が見られた。困難さにおいては、保護者と観察者を比較して、保護者は子どもの困難さを強く捉えていた。向社会性においては、保護者と観察者の他者評価と比較して、子ども自身の自己評価が高かった。つまり、子ども自身は、他人の気持ちを考えて行動しているつもりでも、実際はそのような行動を取れていない場合があるなど、発達障害特性の一面が出ていると考える。子どもの困難さや向社会性を多角的に評価し、三者間の評定の違いを明らかにすることで、その後の子どもや保護者への支援に活かすことができる可能性が示唆された。
1 0 0 0 トンネル栽培による保温の影響を題材とした農業教育の実践
- 著者
- 渡邊 司 皆川 泰臣 中澤 有紗
- 出版者
- 日本農業教育学会
- 雑誌
- 日本農業教育学会誌 = The Japanese journal of agricultural education (ISSN:09159320)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.2, pp.33-44, 2020-11
- 著者
- 許 挺傑 林 満理子
- 雑誌
- 大分県立芸術文化短期大学研究紀要 = Bulletin of Oita prefectural College of Arts and Culture (ISSN:13466437)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, pp.157-178, 2021-03-23
1 0 0 0 IR 産業組合製糸の成立・第1の波--戦間期岩手の蚕糸業研究-2-(a)
- 著者
- 早坂 啓造
- 出版者
- 岩手大学人文社会科学部
- 雑誌
- アルテスリベラレス (ISSN:03854183)
- 巻号頁・発行日
- no.55, pp.p153-222, 1994-12
1 0 0 0 情報の歴史21 : 象形文字から仮想現実まで
- 著者
- 編集工学研究所 イシス編集学校構成
- 出版者
- 編集工学研究所
- 巻号頁・発行日
- 2021