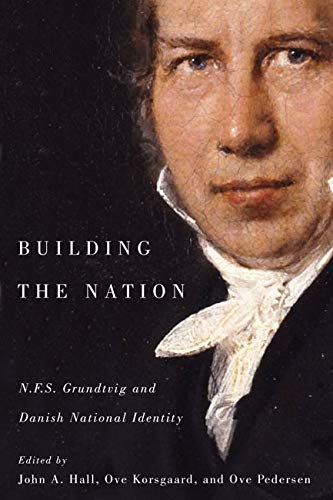1 0 0 0 OA 高齢者における体格・体力の加齢に伴う変化及びその性差
- 著者
- 中 比呂志 出村 慎一 松沢 甚三郎
- 出版者
- 日本体育学会 = Japan Society of Physical Eduction, Health and Sports Science
- 雑誌
- 体育学研究 = Japanese journal of physical education (ISSN:04846710)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.2, pp.84-96, 1997-07-10
The purpose of this study were to investigate factorial structures of physique and physical fitness, and to determine the change of physique and physical fitness with age and its sex difference in the elderly. Nineteen test items were selected from 5 domains of physique, muscle function, joint function (flexibility), neuromuscular function and lung function, considering the validity, safety and convenience of tests. The subjects were 207 males and 226 females aged 65 to 89 years. Factor analysis was applied to each correlation matrixes consisting of 8 physique variables and 11 physical fitness variables. In physique domain, three extracted factors were interpreted as body fat, body linearity and body bulk. Body bulk and body linearity in both sexes and body fat in females decrease significantly with age. Body linearity was found significantly larger in males than females. Body fat was significantly greater in females. In physical fitness domain, four factors were extracted and interpreted as muscular strength, balance, agility of upper and lower limbs, and flexibility. A significant declining trend with age was found in the above-mentioned physical fitness elements both sexes. Also, significant sex differences in muscular strength, balance, and flexibility were found, and males were superior to females except for flexibility. It was inferred that the influence of aging in muscular strength and balance is greater flexibility and agility of upper and lower limbs in the elderly. Further, the decrease of muscular strength seems to facilitate the decline of balance with age.
1 0 0 0 関数型記号処理言語の分散システムに適した評価法
- 著者
- 沼尾 正行 志村 正道
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.247-256, 1985-03-15
分散処理システムで グラフリタクション方式により関数型言語を評価するためには システムを構成する各プロセッサにグラフを分散して配置する必要がある.グラフが各プロセッサに分散していると リタクションを行うために他のプロセッサ内の記憶装置を参照したり 書き換えたりすることが必要となる.また 複数のプロセッサで一つのグラフを書き換えるため グラフのアクセスに対して危険領域を設定しなければならない.本論文では これらの煩雑な問題を解消するため ノード単位でリダクションを行う方法を述べる.この方法では プロセスがグラフの各ノードに割り当てられており アークを通して互いに通信し合う.これらのプロセスにより リタクションがノード単位で行われるので グラフを分割して各プロセッサに割り当てることが容易である.リタクションの基本操作はノードの消去とノードのコピーであり これらの二つの操作を組み合わせることにより リダクションが行われる.ノード単位でリダクションを行うことにより グラフを各プロセッサの共用データとする必要がなくなるため 共用データにアドレスを割りふったり アクセスを行うプログラムに危険領域を設けたりする必要がなくなる.このため 大規模で拡張性の高い分散リタクションシステムを構築することが可能となる.
1 0 0 0 OA コロナ禍における聴覚障害者の防災意識調査 : 滋賀県草津市におけるアンケートから
- 著者
- 近藤 誠司 中野 充博
- 出版者
- 関西大学 社会安全研究センター
- 雑誌
- 社会安全学研究 = Journal of societal safety sciences (ISSN:21860815)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.109-123, 2021-03-31
In this study, we conducted a questionnaire survey on communication issues among all hearing-impaired person in Kusatsu city, in order to consider the natural disaster countermeasures for support needing people under COVID-19 crisis. Consequently, we found that their commitments to disaster risk reduction (DRR) activities had not made much progress, although 69.8% of them had interests in DRR measures. Furthermore, they would have to grapple with the problem of an aging population. In consideration of this situation, we insisted that it was necessary to improve the intergenerational social exchange based on the mutually helping.
1 0 0 0 類推要素間の関連性に関する論理的分析
- 著者
- 有馬 淳
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.7, pp.887-896, 1992-07-15
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 7
2つの事柄がある共通の性質(S:類似性)を有している時 一方(B:ベース)の持つ性質(P:投射性)を他方(T:ターゲット)も持つと推定する類推について考察する本研究では類推の論理的な分析が行われ その結果に基づき 与えられた公理Aのもとで類推要素T B S P が満たすべき例証的基準と呼ぶ論理的関係が示される.ここで例証的基準は以下の2つの前提から得られる:"類推はベースが満たす何らかの性質をターゲットに対し投射することによってその推論が行われる一般的に非演繹的な推論である" "ターゲットは特殊な個体ではない"類推研究では 1)"あるターゲットに対し何をベースとするか"2)"どの性質をもって類似性というか"3)"ある類似性に対してどのような性質が投射されうるか"が長い間 本質的な問いであり続けている例証的基準は これら1) 2) 3)の問題に対する1つの解答になっており 類推研究の1つの一般的な足掛りとなることが期待されるまた この基準に関して これまでの研究のいくつかが実際にこの基準を満たしていることが示されるとともに 従来類推と独立に研究されてきた仮説推論 アブタクション EBG とも密接な関連があることが記される
1 0 0 0 金融実務者による知識創造と人工知能実装
- 著者
- 加藤 惇雄 長尾 慎太郎
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能 (ISSN:21882266)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.3, pp.294-301, 2021-05-01 (Released:2021-05-01)
1 0 0 0 OA 離散的数量調整過程の代数構造
- 著者
- 八木 直人
- 出版者
- 新潟産業大学附属東アジア経済文化研究所
- 雑誌
- 新潟産業大学経済学部紀要
- 巻号頁・発行日
- no.46, pp.19-31, 2016-02
本論文では,(S, s) 在庫政策を伴う一般的な投入産出構造と時間構造を持つマクロ経済モデルを提示し,経済変動における離散的数量調整過程の特性を分析する。とくに個々の企業の生産および派生需要の伝播によるマクロ的在庫調整過程をそれぞれ演算として定義し,在庫調整過程の安定性に関する条件を示す。また演算の集合としての群を定義し,外生需要によって引き起こされる在庫調整過程を代数的に分析するアプローチを示すとともに,在庫調整過程とマクロ動学における安定集合の代数構造を分析する。最後に,マクロ経済の在庫水準の長期的な定常状態について分析する。
1 0 0 0 OA 『鼠の草子』に見える小歌
- 著者
- 真鍋 昌弘
- 出版者
- 奈良教育大学国文学会
- 雑誌
- 奈良教育大学国文 : 研究と教育 (ISSN:03863824)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.28-35, 1979-03-30
1 0 0 0 OA 簡易な開口力測定器の開発 ―第2報:開口力と嚥下障害の関係について―
- 著者
- 原 豪志 戸原 玄 和田 聡子 熊倉 彩乃 大野 慎也 若狭 宏嗣 合羅 佳奈子 石山 寿子 平井 皓之 植田 耕一郎 安細 敏弘
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年歯科医学会
- 雑誌
- 老年歯科医学 (ISSN:09143866)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.3, pp.289-295, 2014-01-14 (Released:2014-01-24)
- 参考文献数
- 35
過去に,喉頭挙上筋が開口筋であるため嚥下機能の評価を目的として開口力測定器を開発し,健常者の開口力を測定した。本研究では開口力が嚥下障害のどのような要素を反映しているかを調べるために,開口力と誤嚥,咽頭残留の有無との関係を調べた。 対象者は慢性期嚥下障害の患者95名 (男性49 名,女性46 名) で平均年齢は男性75.4±9.7 歳,女性 79.3±9.6 歳である。 誤嚥あり群 (男性:4.1±2.8 kg,女性:3.4±1.7 kg) と誤嚥なし群 (男性:5.6±2.9 kg,女性:4.4±1.8 kg) では,男女別で開口力に有意差を認めた。喉頭蓋谷に残留あり群 (男性:4.2±2.3 kg,女性:3.6±1.4 kg) となし群 (男性:8.5±3.4 kg,女性:5.0±2.0 kg) では,男女別でともに有意差を認めた。梨状窩に残留あり群 (男性:4.1±2.1 kg,女性:3.5±1.5 kg) となし群 (男性:6.7±3.6 kg,女性:4.7± 1.9 kg) においても,男女別でともに有意差を認めた。 誤嚥は口腔期の問題でも生じるが不十分な咽頭収縮や喉頭挙上により起こり,咽頭残留は不十分な喉頭蓋の翻転や咽頭短縮が主な成因である。これらはいずれも不十分な舌骨,喉頭の挙上に起因する。以上より開口力は,嚥下時の機能評価において誤嚥と咽頭残留の有無を反映していることが示唆された。
1 0 0 0 紫上と和琴--言語空間としての六条院の女楽攷
- 著者
- 森野 正弘
- 出版者
- 国学院大学出版部
- 雑誌
- 国学院雑誌 (ISSN:02882051)
- 巻号頁・発行日
- vol.94, no.8, pp.p21-36, 1993-08
- 著者
- 松山 隆司 尾崎 正治
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.2, pp.191-204, 1986-02-15
- 被引用文献数
- 26
本論文では 画像処理に関する知識を利用して画像のセグメンテーションを自動的に行うエキスパートシステムについて述べる.システムに対する要求は 画像から抽出すべき画像特徴(長方形 線など)とその属性(面積 長さなど)に対する制約条件によって表される.システムは 要求された画像特徴を検出するための最も有効な処理方針を推論し それに従って実際の画像処理を実行する.また 処理が途中で失敗した場合には 処理方針 処理アルゴリズム 処理パラメータを適宜変更し 処理をやりなおす.こうした推論 処理の過程は 画像処理に関するヒューリスティックスを表すプロタクション・ルールによって制御されており 試行錯誤的な解析など柔軟な解析が実現できる.
- 著者
- 西田 美香
- 雑誌
- 九州保健福祉大学研究紀要 = Journal of Kyushu University of Health and Welfare
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.13-23, 2021-03-25
1 0 0 0 OA Time-restricted feeding in rest phase alters IgE/mast cell-mediated allergic reaction in mice
- 著者
- Yuki Nakamura Kayoko Ishimaru Atsuhito Nakao
- 出版者
- Japanese Society of Allergology
- 雑誌
- Allergology International (ISSN:13238930)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.2, pp.296-299, 2020 (Released:2020-04-17)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 5
1 0 0 0 OA 「ニューノーマル」時代の外国語語教育 : 授業・学習の「サイクル」をめぐって
- 著者
- 山内 真理
- 出版者
- 千葉商科大学国府台学会
- 雑誌
- 千葉商大紀要 (ISSN:03854566)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.3, pp.51-86, 2021-03-31
- 著者
- 陳 志勤
- 出版者
- 東京大学東洋文化研究所
- 雑誌
- 東洋文化研究所紀要 (ISSN:05638089)
- 巻号頁・発行日
- vol.152, pp.141-170, 2007-12
紹興是具有二千五百年悠久歷史的著名水鄉,但是,紹興的美麗風光並不是依賴自然界的變化而形成的。不用說紹興的自然環境變化得益於歷代統治者的治水和利水,但是我們也不應忘卻生活在這一方土地的人民對自然的利用以及管理。現在,因為急劇的經濟發展和地方開發,環境問題特別是水污染問題不斷加劇。對於自然的管理和環境問題,無論日本和中國已在很多領域展開深入的研究,為了探求自然的利用和管理,"自下而上"的以社區為基礎的管理模式(community based management)已引起極大關注。因此,對於長期以來與山林河川共生共存的當地人民是如何進行自然的利用和管理的這一問題,當然就成為一個必須探討和研究的重要課題。作為本文研究對象的紹興南部山區王壇鎮舜王廟周圍,傳承著魚類敬仰舜王的民俗,為了保護這些魚類,很早以來就有把舜王廟下雙江溪中的舜皇潭作為禁漁區的習慣。並且,對於那些違反禁漁規約的人,作為懲罰要讓他們負擔請戲班演戲或者置辦酒席的費用,也就是說曾經存在過"罰戲"、"罰宴"這種適應當地人文環境的懲罰方式。從這樣的傳統民俗中,我們可以看到因為信仰、祭祀而結成的地域共同體在自然管理中所發揮的作用,很明顯,這和日本的村落共同體在自然管理中發揮作用的情形是不相同的。本文的研究目的是,首先闡明因舜王信仰、舜王廟會而形成的共同體和自然管理的關係,然後探究把罰戲、罰宴作為懲罰手段的這種類型的共同體,在自然管理中所發揮的作用。
1 0 0 0 OA <論文>ジョブエンリッチメントからシンボリックマネジメントヘ
- 著者
- 斎藤 弘行
- 出版者
- 東洋大学
- 雑誌
- 経営論集 = Journal of business administration (ISSN:02866439)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, pp.71-87, 1998-03-24
1 0 0 0 OA エリートサッカーゴールキーパーにおける異なるシュートパタンに対する事前動作の特性
- 著者
- 松倉 啓太 平嶋 裕輔
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育・スポーツ・健康学会
- 雑誌
- 体育学研究 (ISSN:04846710)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, pp.1049-1067, 2020 (Released:2020-12-24)
- 参考文献数
- 21
The aim of this study was to shed light on preparatory sequences performed by elite goalkeepers for defense against shots in response to variations in the position from where a shot at goal is taken, and in the number of touches ahead of the shot. The samples were extracted from videos of shots in all 64 matches of the 2018 FIFA World Cup in Russia. First, to analyze the characteristics of shots in elite games, data on shots from different areas and after various numbers of touches were studied. Then, to analyze the preparatory sequences taken by goalkeepers to defend against those shots, the shots were classified into 6 groups based on ‘the presence or absence of a specific prejump’, ‘a change in the distance between the feet during the preparation period’, and ‘whether the goalkeeper was still in a moving position or had completed the move’. The results of this analysis of the characteristics of the elite game made it possible to divide the positions from where shots were taken in 2 types, based on the probability of the shot being on target and the probability that a goal would be scored. In addition, it was shown that when one-touch shots were on target, it was difficult for goalkeepers to defend against them. Next, as an overall trend, the most frequent preparatory sequence performed by goalkeepers was to prepare for a shot with a slight jump in order to widen the distance between the feet after they had finished moving into position. In addition, a breakdown of the preparatory sequences for various numbers of touches ahead of the shot revealed that – for onetouch shots – a proportion of goalkeepers moved into position until immediately before the shot was taken. Overall, from these analyses, it was concluded that elite goalkeepers must engage in different preparatory sequences depending on the circumstances of the shot.
1 0 0 0 IR 2020年に新型コロナウイルス感染症の影響で中止になった半自然草原の火入れの記録
- 著者
- 横川 昌史
- 出版者
- 大阪市立自然史博物館
- 雑誌
- 大阪市立自然史博物館研究報告 = Bulletin of the Osaka Museum of Natural History (ISSN:00786675)
- 巻号頁・発行日
- no.75, pp.107-111, 2021-03-31
2020年に入ってから,全世界的に新型コロナウイルス感染症が猛威を振るっている.日本国内 において,新型コロナウイルス感染症拡大防止のために,春の半自然草原の火入れを中止した地域が 多数見られた.感染症が草原の管理に影響を与えた記録は重要だと考えられるため,インターネット 上で見つけられた新型コロナウイルス感染症に関連した火入れの中止について記録した.2020年2月下 旬から5月中旬にかけて,Google や Twitter・Facebook などの SNS で,「火入れ」「野焼き」「山焼き」「ヨ シ焼き」「コロナ」「中止」などのキーワードを任意に組み合わせて検索し,新型コロナウイルス感染 症の影響で中止になった日本国内の火入れを記録した.その結果,14道府県18ヵ所の草原で火入れが 中止になっており,4県4ヵ所の草原で制限付きで火入れが実施されていた.これら,新型コロナウイ ルス感染症による半自然草原の火入れの中止は,草原の生物多様性や翌年以降の安全な火入れに影響 を及ぼす可能性がある.
1 0 0 0 OA 交通電気博ポスター選集 : 大礼奉祝
- 著者
- 交通電気博覧会事務局 編
- 出版者
- 日本広告学会
- 巻号頁・発行日
- 1928
- 著者
- 長谷川 利拡 高野 順也 崎原 健 三橋 民和 大嶋 和則 片野 学 仲里 長浩
- 出版者
- 日本作物学会九州支部
- 雑誌
- 日本作物学会九州支部会報
- 巻号頁・発行日
- no.60, pp.9-12, 1994
九州の主要良食味品種のミネアサヒ,ヒノヒカリ,ユメヒカリおよび沖縄の主要品種のチヨニシキの出芽期~二次枝便分化期までの発育特性を,堀江・中川の発育動態モデルを用いて解析した。データベースは,阿蘇と西表における作期移動試験である(n=13)。本モデルは,37~114日にわたる発育日数の変動を3,7~5,2日の精度で推定した。ミネアサヒとヒノヒカリの発育速度は気温に対してほぼ直線的な増加を示し,日長の影響は14時間以上においてのみ認められた。一方,チヨニシキおよびユメヒカリの発育速度は,気温に対して23℃あたりから頭打ちを示し,広い範囲の日長に反応することがわかった。