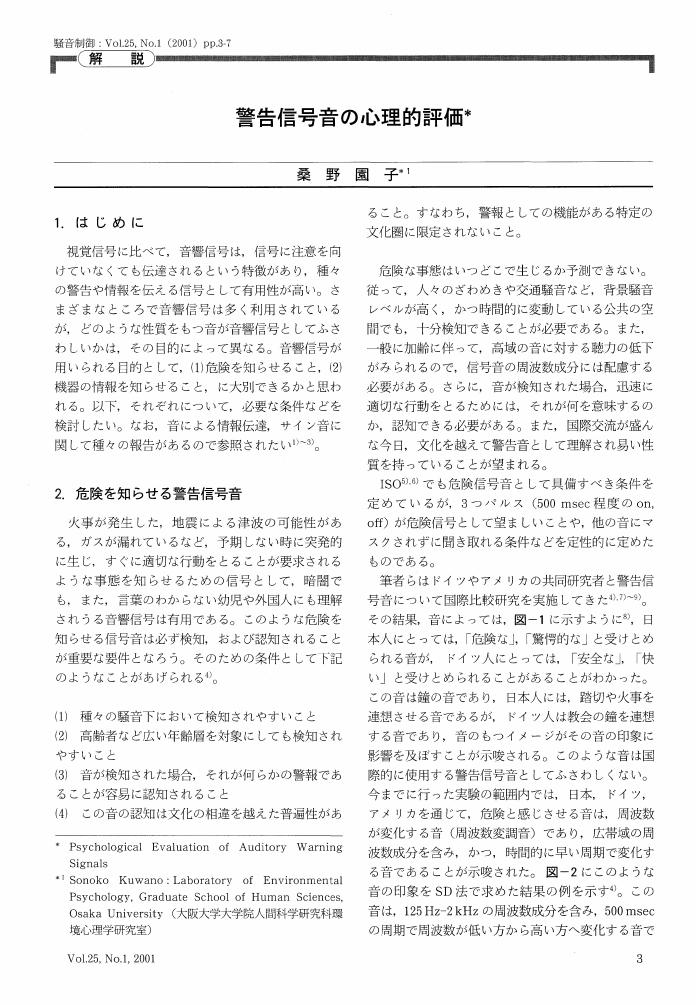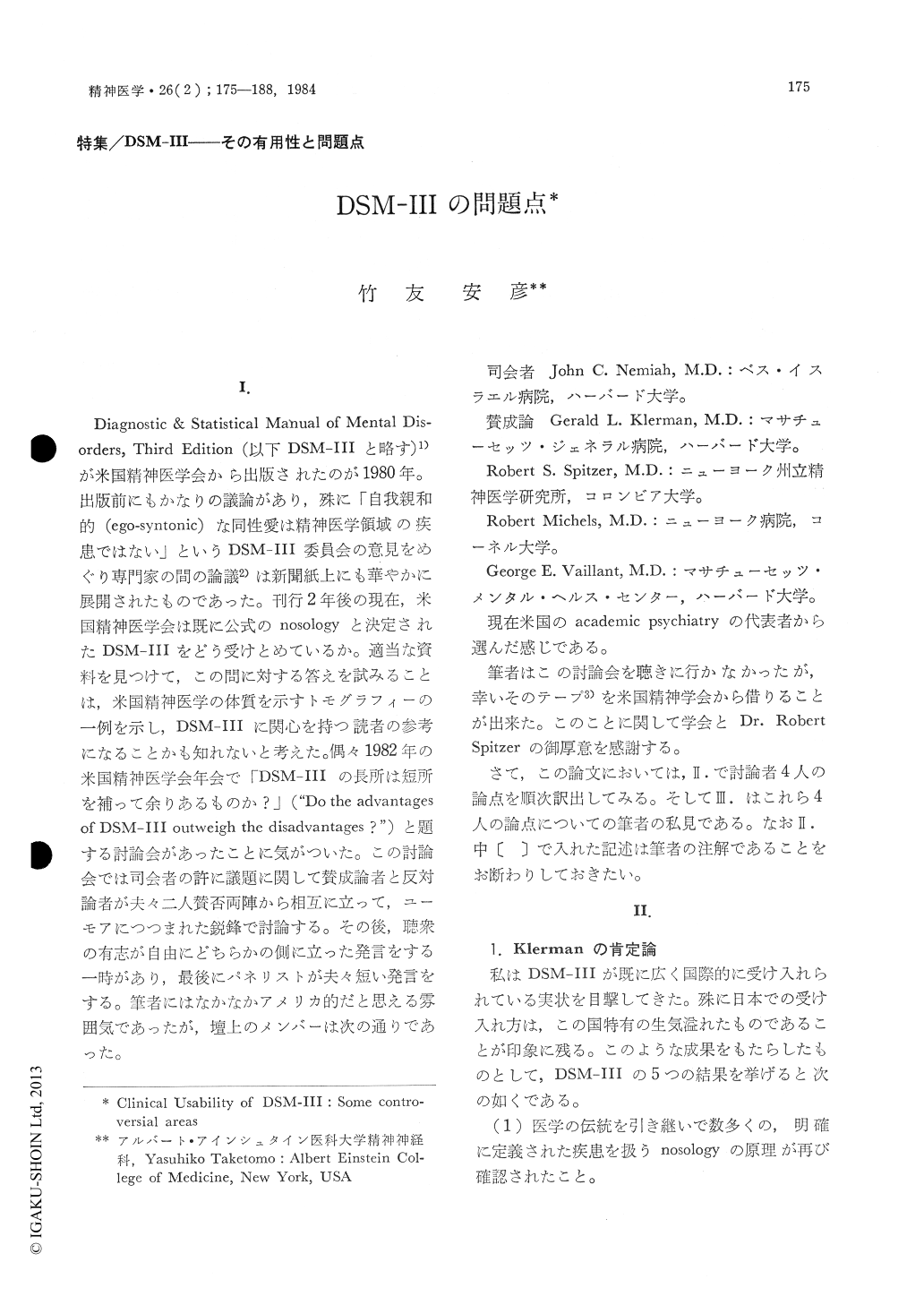1 0 0 0 OA 警告信号音の心理的評価
- 著者
- 桑野 園子
- 出版者
- The Institutew of Noise Control Engineering of Japan
- 雑誌
- 騒音制御 (ISSN:03868761)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.3-7, 2001-02-01 (Released:2009-10-06)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 5
1 0 0 0 OA 精度管理研修記録 個人データの変動要因 ―健診結果の解釈―
- 著者
- 田内 一民
- 出版者
- 一般社団法人 日本総合健診医学会
- 雑誌
- 日本総合健診医学会誌 (ISSN:09111840)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.3, pp.384-390, 2001-09-30 (Released:2010-09-09)
- 参考文献数
- 5
検体検査の健診結果の判定は基準範囲から設定した判定基準に照らし合わせ, 受診者の臨床症状を考慮し受診者に報告する。しかし, 個人データを経時的に観察し, 個人差を考慮すればより細かい判定が可能である。検査データの変動は生活習慣の変化が要因になっている場合が多い。予防医学的な見地からは基準範囲内の変化であっても生活習慣を改善することが必要な場合も出てくる。
1 0 0 0 OA 悪性脳腫瘍に対する当院のケトン食療法の取り組み
- 著者
- 篠島 直樹 前中 あおい 牧野 敬史 中村 英夫 黒田 順一郎 上田 郁美 松田 智子 岩崎田 鶴子 三島 裕子 猪原 淑子 山田 和慶 小林 修 斎藤 義樹 三原 洋祐 倉津 純一 矢野 茂敏 武笠 晃丈
- 出版者
- 日本外科代謝栄養学会
- 雑誌
- 外科と代謝・栄養 (ISSN:03895564)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.5, pp.235-242, 2019 (Released:2019-11-15)
- 参考文献数
- 14
【背景・目的】当院では難治性てんかんの患児に「ケトン食」を40年以上提供してきた.その経験に基づきIRB承認の下,悪性脳腫瘍患者を対象にケトン食の安全性,実行可能性,抗腫瘍効果について検討を行った. 【対象・方法】2012年11月から2018年10月までの悪性脳腫瘍患者14例(成人10例,小児4例).栄養組成はエネルギー30~40kcal/kg/日,たんぱく質1.0g/kg/日,ケトン比3:1のケトン食を後療法中ないし緩和ケア中に開始し,自宅のほか転院先でもケトン食が継続できるよう支援を行った. 【結果】ケトン食摂取期間の平均値は222.5日(5‐498日),空腹時血糖値および血中脂質値はケトン食摂取前後で著変なかった.有害事象は導入初期にgrade1の下痢が2例,脳脊髄放射線照射に起因するgrade 4の単球減少が1例でみられた他,特に重篤なものはなかった.後療法中に開始した10例中9例が中断(3例は病期進行,6例は食思不振など),緩和ケア中に開始した4例中3例は継続し,うち2例は経管投与でケトン食開始後1年以上生存した. 【考察】後療法中にケトン食を併用しても重篤な有害事象はなく安全と考えられた.長期間ケトン食を継続できれば生存期間の延長が期待できる可能性が示唆された.中断の主な理由として味の問題が大きく,抗腫瘍効果の評価には長期間継続可能な美味しいケトン食の開発が必要と考えられた.
1 0 0 0 OA スエズ戦争(1956年)と米国・エジプト関係
- 著者
- 鹿島 正裕
- 出版者
- 金沢大学法学部 = The Faculty of Law, University of Kanazawa
- 雑誌
- 金沢法学 = Kanazawa law review (ISSN:0451324X)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.1, pp.37-68, 1995-01-27
1 0 0 0 OA ミツバチの配偶行動
- 著者
- 吉田 忠晴
- 出版者
- Pesticide Science Society of Japan
- 雑誌
- Journal of Pesticide Science (ISSN:1348589X)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.4, pp.497-502, 2011-11-25 (Released:2012-11-10)
- 参考文献数
- 30
1 0 0 0 OA 0.3%ロメフロキサシンのイヌ細菌性外耳炎に対する有効性と安全性に関する調査
- 著者
- 貞本 和代 坂本 祐一郎 門屋 美知代 末信 敏秀
- 出版者
- 日本獣医皮膚科学会
- 雑誌
- 獣医臨床皮膚科 (ISSN:13476416)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.11-19, 2020 (Released:2021-03-30)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1
0.3%ロメフロキサシンの点耳薬であるロメワン®のイヌ細菌性外耳炎への使用時における安全性および有効性を確認することを目的として,使用成績調査を実施した。本調査では,副作用発現状況の把握を目的とした安全性調査および,有効性および細菌学的効果を承認前に実施した治験成績と比較することを目的とした有効性調査を実施した。安全性評価の対象となった613症例のうち,3症例に副作用(嘔吐,耳擦過傷および外耳障害)が認められ,副作用発現率は0.49%であった。有効性評価の対象となった103症例における有効率は66.0%(68/103)であった。また,有効菌種であるS. intermedius,S. canisおよびP. aeruginosaの消失率はそれぞれ77.1%,79.0%および92.3%であり,ロメワン®は有効菌種に対して高い細菌学的効果を示した。以上の結果より,ロメワン®は副作用発現率が低く,有用な薬剤であることが示された。
1 0 0 0 OA ポディフォーム・クロミタイトはマントル内を循環するか?:超高圧クロミタイトの謎
- 著者
- 荒井 章司
- 出版者
- 一般社団法人 日本鉱物科学会
- 雑誌
- 岩石鉱物科学 (ISSN:1345630X)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.6, pp.247-256, 2012 (Released:2012-12-29)
- 参考文献数
- 56
- 被引用文献数
- 4 4
Podiform chromitites have been interpreted as cumulates formed via melt/harzburgite reaction and subsequent melt mixing within the upper mantle. Recent finding of ultrahigh-pressure (UHP) minerals such as diamond from some podiform chromitites has, however, seriously required us to reconsider the whole framework of podifrom chromitite genesis. The UHP podiform chromitites are characterized by presence of frequent silicate lamellae in chromian spinel and only PGE (platinum-group elements) alloys as platinum-group minerals. The UHP chromitites were possibly formed by deep recycling of the ordinary low-pressure podiform chromitites. Diamonds could be formed by reduction of CO2 metasomatically supplied to chromian spinel in advance. Silicate lamellae in chromian spinel of UHP chromitites were possibly derived from primary silicate inclusions (pyroxenes, pargasite and Na phlogopite), commonly found in the low-pressure chromitite. They were decomposed/partially melted and resolved in high-pressure chromian spinel during compression/heating during downward transportation, and were exsolved as silicate lamellae on decompression/cooling during uprising. PGE sulfides commonly found in the low-pressure chromitite may have been decomposed to PGE alloys and sulfur-rich melt/fluid that were removed outside. We should systematically re-examine all podiform chromitites that have been ever documented, but our preliminary examination indicates that both concordant and discordant chromitites from Oman ophiolite are of low-pressure origin, containing primary pargasite inclusions in chromian spinel. More thorough characterization of the UHP chromitite may enable us to place constraints on the style of mantle convection that provided the MORB source possibly comprising the UHP chromitite. Possible presence of ringwoodite as one of UHP minerals in chromitite may favor the two-layer mantle convection for supplying the source mantle that formed the oceanic lithosphere.
- 著者
- 游 舒婷 Yu Shuting
- 出版者
- 神奈川大学日本常民文化研究所 非文字資料研究センター
- 雑誌
- 非文字資料研究 = The study of nonwritten cultural materials (ISSN:24325481)
- 巻号頁・発行日
- no.14, pp.321-347, 2017-03-20
台湾で流通していた暦には、清国、日本、国民党それぞれの統治の正統性を象徴する公式の暦(官暦)と、それを底本にして編纂されていた民間暦がある。清国の時間規範である旧暦、特にその中の吉凶日は、宇宙論的王権のイメージを表象するものである。民間暦に記されている吉凶的意味づけに官暦と違う解釈がみられると同時に、宇宙論という前提を共有する上で、宇宙論的王権のイメージが、福建や広東から輸入された民間暦の流通や吉凶的意味を読み取れる人を通して台湾に拡がっていった。 それに対して、近代文明を表象する時間規範である新暦は、清末を端緒としてキリスト教の宣教師によって台湾に伝わった。それから、日本統治下に入ると、天皇を頂点とする時間秩序と新暦を文明開化とする二重のイメージが表現されている日本暦(明治政府が1872年に下した改暦詔書を基にして頒布した官暦)は、神宮教によって普及されたが、台湾総督府がその普及に積極的な姿勢を示さなかった。それに替わって、1913年に総督府は「日本暦」と「中華暦」の折衷ともいわれるような体裁をとっている「台湾民暦」を頒布した。台湾民暦は行政システムを通して上から下へと普及されていく過程で、地方行政レベルの社会に侵入し、記憶された。それが原因であるようで、戦後、台湾民暦と似たような構成をとっている民間暦(「農民暦」という)が刊行された。国民党統治下で中華文化が推進されていることが背景にあると考えられるが、そのような民間暦に記されている吉凶日は段々と増えて、60、70年代の高度経済成長と共に、台湾の家々に浸透していった。 本稿は、暦に記されている吉凶日の変容、さらに暦の流通、暦と関わっている人々の実態について考察したものである。それによって、宇宙論的王権のイメージが日本そして国民党統治時代にわたってどのように再編されたか、どのように継続していたか、その消長を明らかにし、それを通して台湾における近代化の様相の一端をみることを目的とする。Taiwan has adopted an official calendar that represents the orthodoxy of the Qing Dynasty, Japanese rule and the Nationalist government, and a folk calendar developed based on the official one. The old calendar that the dynasty used as a dating system―the notion of days of fortune and misfortune in particular―symbolizes cosmological sovereignty. The interpretations of those days differ between the two types of calendars. Moreover, along with cosmology itself, the concept and image of cosmological sovereignty spread to Taiwan through the circulation of the folk calendar imported from Fujian and Guangdong and interpreters of the days of fortune and misfortune. The new calendar signifying modern civilization was introduced at the end of the Qing Dynasty and brought into Taiwan by Christian missionaries. Under Japanese rule, the Japanese calendar that incorporated a date system based on the period of the reign of the emperor and Japanese cultural enlightenment was adopted and promoted by a sect of Shinto called Jingu-kyo. It was an official calendar proposed by the Meiji government, but the Taiwan Governor-Generalʼs Office was not willing to circulate it. Instead, the office adopted the Taiwanese folk calendar that combined the Japanese and Chinese chronological systems in 1913. It was introduced to the public in a top-down manner through the government administration system and came to be commonly used at a local government level and downward. After World War II, an agricultural calendar similar to the Taiwanese calendar was launched in the wake of the promotion of Chinese culture under the Nationalist government. The number of days of fortune and misfortune in this calendar gradually increased and started to be widely used in Taiwanese households during the period of high economic growth in the 1960s and 1970s. This paper will examine changes in the days of fortune and misfortune in these calendars, the circulation of each calendar system, and people involved in the process. In doing so, the rise and fall of the concept of cosmological sovereignty, such as how it was reconstructed and preserved under Japanese rule and the Nationalist regime, will also be discussed, thereby revealing aspects of Taiwanʼs modernization.2015年度奨励研究 成果論文
1 0 0 0 OA 永久磁石界磁同期電動機の回転子位置と速度のセンサレス検出の一方法
- 著者
- 渡辺 博巳 宮崎 聖 藤井 知生
- 出版者
- The Institute of Electrical Engineers of Japan
- 雑誌
- 電気学会論文誌D(産業応用部門誌) (ISSN:09136339)
- 巻号頁・発行日
- vol.110, no.11, pp.1193-1200, 1990-11-20 (Released:2008-12-19)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 5 14
A inverter-fed permanent magnet synchronous motor with a rotor position sensor and a speed sensor is used in many industrial applications as a DC-brushless motor. In this paper, a strategy which determines the rotor position and the speed of the permanent magnet synchronous motor by using the instantaneous values of phase voltage and phase current sensing is explained.In a permanent magnet synchronous motor, the permeance of the stater magnetic circuit is altered by rotating the rotor position; the inductance of a phase winding changes according to rotor positions. Hence, the phase voltages and currents of the motor have close relations with the rotor positions. Measured values of phase voltages and currents and the values of the equivalent circuit parameters are substituted to the voltage equation of the synchronous motor. Then, we can calculate the value of the rotor position angle by that voltage equation. The rotating speed of the rotor can be calculated from the voltage equation by substituting the rotor position angle. In these calculations, we used a 16-bit micro-computer and a DSP, and for sensing phase voltages and currents, 12-bit high quality A/D converters are used.Experimental results obtained by using the prototype system were congruous values of the rotor position angles and the rotating speed.
1 0 0 0 松本清張『砂の器』における「方言」と「方言学」
- 著者
- 小西 いずみ
- 出版者
- 東京都立大学国語国文学会
- 雑誌
- 都大論究 (ISSN:03875393)
- 巻号頁・発行日
- no.42, pp.74-86, 2005-04
1 0 0 0 OA マウス胚および配偶子の凍結保存
- 著者
- 中潟 直己
- 出版者
- Japanese Association for Laboratory Animal Science
- 雑誌
- Experimental Animals (ISSN:00075124)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.1, pp.11-18, 1994-01-01 (Released:2010-08-25)
- 参考文献数
- 44
- 被引用文献数
- 4 6
Embryos, oocytes and spermatozoa of mice could be successfully preserved at -1961 by simple freezing methods. The survival rate of frozen embryos was very high at thawing and they developed into normal young after embryo transfer. In gametes, the cryopreserved oocytes could be fertilized in vitro by fresh spermatozoa and the cryopreserved spermatozoa could fertilize fresh oocytes. Moreover, the cryopreserved oocytes could be fertilized by the cryopreserved spermatozoa and the embryos obtained by in vitro fertilization between cryopreserved gametes could develop into normal, live young after embryo transfer. In the future, if not only the embryos but also the oocytes and spermatozoa of many mouse strains are frozen, normal young can be produced from cryopreserved embryos and gametes.
1 0 0 0 OA 古典的ハリウッド映画の中の美術と美術館 : プリミティヴィズムの馴致
1 0 0 0 レジ袋有料化は天下の愚策
- 著者
- 内藤 陽介
- 出版者
- ワック
- 雑誌
- Will : マンスリーウイル
- 巻号頁・発行日
- no.189, pp.326-331, 2020-09
1 0 0 0 OA 支那事変と其の背後に迫るもの
1 0 0 0 IR 小児病棟における入院児の遊びと学習環境の実態について
- 著者
- 金城 やす子
- 出版者
- 名桜大学
- 雑誌
- 名桜大学紀要 (ISSN:18824412)
- 巻号頁・発行日
- no.13, pp.29-38, 2007
入院児の療養環境について、看護師長を対象に調査を行った。その結果、小児病棟の混合病棟化が進み、混合病棟では子どもにとっての遊びや教育環境が十分な状況にないことが明らかになった。入院している子どもにとって子どもとしての生活、遊びや教育は重要である。そのため、入院児の生活について検討することは、今後の小児看護を検討するうえの重要な視点となる。
1 0 0 0 DSM-IIIの問題点
I. Diagnostic & Statistical Manual of Mental Disorders, Third Edition(以下DSM-IIIと略す)1)が米国精神医学会から出版されたのが1980年。出版前にもかなりの議論があり,殊に「自我親和的(ego-syntonic)な同性愛は精神医学領域の疾患ではない」というDSM-III委員会の意見をめぐり専門家の間の論議2)は新聞紙上にも華やかに展開されたものであった。刊行2年後の現在,米国精神医学会は既に公式のnosologyと決定されたDSM-IIIをどう受けとめているか。適当な資料を見つけて,この間に対する答えを試みることは,米国精神医学の体質を示すトモグラフィーの一例を示し,DSM-IIIに関心を持つ読者の参考になることかも知れないと考えた。偶々1982年の米国精神医学会年会で「DSM-IIIの長所は短所を補って余りあるものか?」(“Do the advantagesof DSM-III outweigh the disadvantages?”)と題する討論会があったことに気がついた。この討論会では司会者の許に議題に関して賛成論者と反対論者が夫々二人賛否両陣から相互に立って,ユーモアにつつまれた鋭鋒で討論する。その後,聴衆の有志が自由にどちらかの側に立った発言をする一時があり,最後にパネリストが夫々短い発言をする。筆者にはなかなかアメリカ的だと思える雰囲気であったが,壇上のメンバーは次の通りであった。