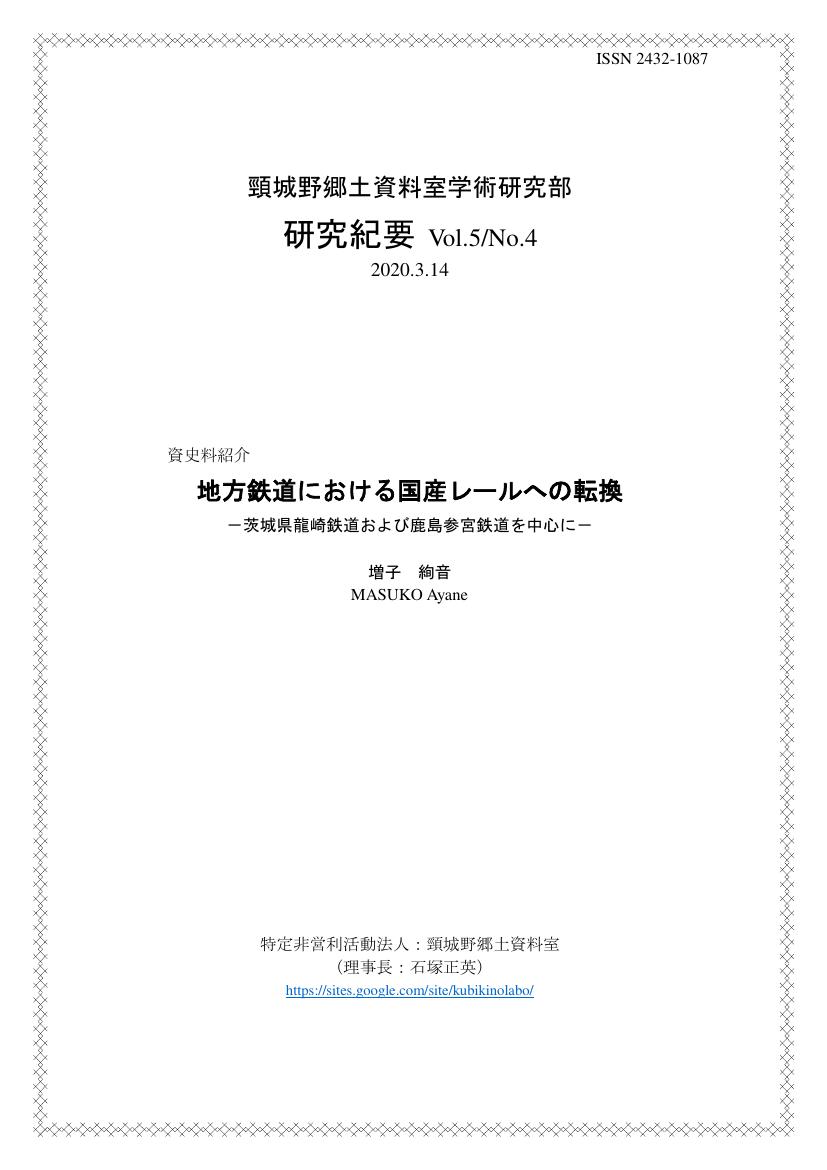1 0 0 0 OA 市販しらす干しの品質調査
- 著者
- 坂田 由紀子
- 出版者
- The Japan Society of Home Economics
- 雑誌
- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.5, pp.335-339, 1989-05-05 (Released:2010-03-10)
- 参考文献数
- 9
市販のしらす干しについて, 衛生学的見地から品質調査を行った.鮮度の判定はpH, 水分, 水分活性, 塩分濃度, トリメチルアミン-窒素, 揮発性塩基窒素, ヒスタミンについてであり, 微生物学的検査では, 大腸菌群, 一般生菌, 腸炎ビブリオについて検査した.1) 水分は, 平均約40%で半乾燥品であるため, 生魚より低かったが, 含有量のばらつきが大きかった.これは, 生産地で出荷先にあわせて, いろいろな乾燥度の製品を製造しているためであると考えられる.ヒスタミン量は平均して新鮮な魚肉の含有量と同等であり, 最高でも3.57mg/100gで中毒量を超えるものはみられなかったが, 2期には含有量が1期に比べて有意に増加した.2) 微生物学的検査では, 一般生菌数は, 魚の干物と生魚の付着菌数より多い結果となったが, 106/g数を示したものが全体の32%あり, 大腸菌群数も干物に比較して検出率が高い結果となった.一般生菌数, 大腸菌群数ともに, 時期的な差はなかった。腸炎ビブリオは1例も検出されなかった.3) しらす干しの塩分濃度は市販の魚の干物より高く, 平均6.3%であり, 含有量は1期に有意に増加した.最近は魚の干物でも, 水分量が多く生魚に近い値になってきている事実に注目すれば7), しらす干しも生魚と同じように低温保持に十分な注意を払われなければならないし, また, それを購入した消費者も同様に取り扱う必要があると考えられる.
1 0 0 0 OA 用宗のシラス加工 : 加工会社のこだわり
- 著者
- 海野 未樹
- 出版者
- 静岡大学人文社会科学部社会学科文化人類学コース
- 雑誌
- 静岡市・用宗地区. - (フィールドワーク実習調査報告書 ; 平成26年度)
- 巻号頁・発行日
- pp.20-28, 2014-12
- 著者
- 井野 朋也 迫川 尚子
- 出版者
- 太田出版
- 雑誌
- Atプラス : 思想と活動
- 巻号頁・発行日
- no.23, pp.102-114, 2015-02
1 0 0 0 OA 「プラーティナのタルシア(一四七七-一四九〇)」(下)-アペンディクス(一)(二)-
- 著者
- アルフレード プエラーリ 上田 恒夫
- 出版者
- 五浦美術文化研究所
- 巻号頁・発行日
- no.26, pp.101-136, 2020-12-15
- 著者
- 山﨑 洋史
- 出版者
- 国学院大学大学院
- 雑誌
- 国学院大学大学院紀要. 文学研究科 = Journal of the Graduate School, Kokugakuin University (ISSN:03889629)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, pp.25-44, 2019
- 著者
- 松田 輝美 津田 彰 Terumi Matsuda
- 出版者
- 久留米大学大学院心理学研究科
- 雑誌
- 久留米大学心理学研究 : 久留米大学文学部心理学科・大学院心理学研究科紀要 (ISSN:13481029)
- 巻号頁・発行日
- no.12, pp.34-43, 2013
本研究の目的はジャーナル・アプローチが在日中国人留学生の精神的健康に及ぼす効果の検討とプログラムの評価を量的な質問紙調査と質的な面接を用いて行うことである。研究1では,中国人留学生19名を無作為にジャーナル・アプローチ介入群と待機群に分けた。3か月の介入前後にGeneralHealthQuestionnaire-28(GHQ-28)中国語版で精神的健康を測定した。2要因分散分析の結果,両群に有意差は認められなかった。介入群のうち半数が中断したが,彼らは受験が気がかり,あるいは周りの目が気になっていたことが明確になった。研究2では,プログラムの評価と介入中断の原因を特定するために,介入群の中国人留学生6名を対象に半構造化面接を行った。その結果,プログラムに参加した一部の留学生にストレスの緩和や気持ちの変化があることが示された。
1 0 0 0 OA 高齢化の進行する地域における要介護原因疾病の変化
- 著者
- 高橋 恭子 築島 恵理
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.3, pp.195-203, 2021-03-15 (Released:2021-03-30)
- 参考文献数
- 23
目的 高齢化が急速に進行している地域において,高齢者人口の増加に伴う要介護原因疾病の変化を明らかにすることを目的に,5年前の要介護原因疾病との比較検討を行った。方法 札幌市南区において2018年度に新規要介護認定を受けた第1号被保険者2,538人および2013~2014年度に認定を受けた第1号被保険者4,089人が対象となった。 主治医意見書に記載された疾患名を国民生活基礎調査の介護票の疾病分類に基づいて分類して原因疾病として用いた。調査年度間の原因疾病の割合をχ2検定を用いて解析を実施した。結果 5年間の比較では男性は原因疾病の比率に統計学的有意な変化を認めなかった。女性は脳血管疾患の比率が7.8%から5.6%に減少し(P=0.008),骨折・転倒の比率が9.5%から13.8%に増加し(P<0.001),いずれも統計学的有意であった。 介護度が重度になる疾患について男性は5年間では変化がなく,悪性新生物が最も多く,次いで脳血管疾患であった。女性は骨折・転倒が10.5%から17.7%に統計学的有意に増加し(P=0.002),原因として最も多くなった。女性の骨折・転倒に関しては介護度が軽度の群でも9.2%から12.5%と統計学的有意に増加していた(P=0.004)。結論 5年間の経過で女性の骨折・転倒が増加し,予防対策を早期から開始することの必要性が示された。健康寿命短縮の要因となる原因疾病には悪性新生物,脳血管疾患の生活習慣病の関与が大きく,健康寿命延伸において生活習慣病予防の重要性が改めて示された。
1 0 0 0 OA ヤングケアラーの生活満足感および主観的健康感:大阪府立高校の生徒を対象とした質問紙調査
- 著者
- 宮川 雅充 濱島 淑恵
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.3, pp.157-166, 2021-03-15 (Released:2021-03-30)
- 参考文献数
- 28
目的 日本においても,家族のケアを担っている子ども(ヤングケアラー)が相当数存在することが指摘されている。しかしながら,ケア役割の状況が彼らの生活満足感や健康に与える影響に関する調査研究はほとんど行われていない。本研究では,高校生を対象に,生活満足感および主観的健康感についてケア役割の状況との関連を分析し,ケア役割がヤングケアラーの生活満足感や主観的健康感に与える影響について検討した。方法 大阪府の府立高校(10校)の生徒6,160人を対象に質問紙調査を行った。調査では,家族の状況とともに,彼らの担うケア役割の状況を尋ねた。また,生活満足感に関する質問(1問),主観的健康感(全体的な健康感)に関する質問(1問)を尋ねた。さらに,各種自覚症状に関する質問(7問)を尋ね,主成分分析を適用し主観的健康感を評価した。生活満足感および主観的健康感について,ケア役割の状況との関連を,交絡因子の影響を調整して分析した。結果 5,246人(85.2%)から有効回答を得た。本稿では,分析で使用する変数に欠損値がなかった4,509人を分析対象とした。そのうち47人(1.0%)が幼いきょうだい(障がいや疾病等はない)のケアを担っていた(ヤングケアラーA)。また,233人(5.2%)が,障がいや疾病等のある家族のケアを担っていた(ヤングケアラーB)。残りの4,229人(93.8%)は,家族のケアを行っていなかった(対照群)。生活満足感に関するロジスティック回帰分析では,ケア役割の状況との間に有意な関連が認められた(P<0.001)。ヤングケアラーAとBの不満足感のオッズ比は,対照群と比較した場合,それぞれ2.742(P<0.001),1.546(P=0.003)であり,いずれも有意に高かった。全体的な健康感については,ケア役割の状況との間に有意な関連は認められなかった(P=0.109)が,各種自覚症状の主成分得点に関する重回帰分析では,ケア役割の状況との間に有意な関連が認められた(P<0.001)。ヤングケアラーAとBの不健康感の係数は,対照群と比較した場合,それぞれ0.362(P=0.012),0.330(P<0.001)であり,いずれも有意に高かった。結論 ケア役割の状況が過度になった場合,ヤングケアラーの生活満足感や主観的健康感に悪影響が生じることが示唆された。
1 0 0 0 OA 地域在住高齢者のサロンで実施したロコモーショントレーニングの効果
- 著者
- 柴田 陽介 岡田 栄作 中村 美詠子 尾島 俊之
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.3, pp.180-185, 2021-03-15 (Released:2021-03-30)
- 参考文献数
- 15
目的 本邦ではロコモティブシンドローム(ロコモ)の予防としてロコモーショントレーニング(ロコトレ)が注目されてる。ロコトレの効果を検証した報告は,虚弱な高齢者を対象にした研究が多く,健康な者が多い地域在住高齢者を対象にした報告は少ない。そこで本研究の目的は,地域在住高齢者を対象に行われたロコトレの効果を報告することとした。方法 浜松市ではサロンの場でロコトレ事業(サロン型ロコトレ事業)を行っている。この事業は,一人以上のサロンメンバーがロコトレの講習会を受け,その者が各サロンの場で他のメンバーにロコトレを指導する形式の事業である。定期的な評価として,ロコトレ開始前と3か月ごとにロコモ5を用いてロコモの度合いを評価している。ロコモ5とは0~20点のスコア化ができる自記式調査票であり,高得点なほどロコモの重症度が高く,6点以上ではロコモ陽性と判定される。本研究では,2017年度に初めてサロン型ロコトレ事業に参加した地域在住高齢者2,855人のうち,欠損データがない者1,211人を解析対象とした。解析は,ロコトレ開始前の状態によってロコモ群(ロコモ5の得点:6点以上)と非ロコモ群(5点以下)に分類し,開始前,3か月後と6か月後のロコモ5の得点およびロコモ陽性者の割合を算出した。活動内容 対象者の平均年齢は77.5歳,男性は301人(24.9%),ロコモ群は237人(19.6%)であった。ロコモ5の平均得点±標準偏差は,非ロコモ群では開始前1.39±1.67点,3か月後1.62±2.35点,6か月後1.59±2.26点,ロコモ群では開始前9.47±3.50点,3か月後8.35±4.82点,6か月後8.22±4.66点であった。ロコモ陽性者の割合は,非ロコモ群では3か月後54人(5.5%),6か月後57人(5.9%),ロコモ群では3か月後165人(69.6%),6か月後167人(70.5%)であった。サロン型ロコトレ事業の特徴としては,多くのロコモ陽性者をリクルートできたこと,ロコトレ事業の運営側の労力が少なかったことが挙げられた。結論 ロコモだった者は3か月でロコモ5の得点が低下し,ロコモ陽性者の割合も減少したが,6か月後は横ばい傾向であった。一方でロコモでなかった者は,良い状態が維持されていた。
1 0 0 0 諸先生のあまのじゃく 鼻息荒い原子核屋への対抗(わが師わが友)
- 著者
- 台 弘
- 出版者
- 中央公論社
- 雑誌
- 自然 (ISSN:03870014)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.11, pp.26-29, 1966-11
1 0 0 0 IR 近年における昭和創業喫茶店の受容
- 著者
- 大井 佐和乃 Sawano Ohi
- 出版者
- 武庫川女子大学大学院生活環境学専攻 ; 2013-
- 雑誌
- 生活環境学研究 = Mukogawa journal of human environmental sciences : 教育・研究誌 (ISSN:21883335)
- 巻号頁・発行日
- no.5, pp.46-49, 2017
現代日本の都市ではカフェや喫茶店が街中にある風景はありふれたものとなっている。多くの駅前にはチェーン店のカフェが出店しており,駅構内で営業している場合もある。カフェと喫茶店はどちらもコーヒー,お茶,ジュース,軽食などの飲食物を提供する店舗に変わりはなく,カフェと喫茶店の違いは明確には存在しないようだ1)。読売新聞のキーワードによる記事検索では「カフェ」を含む記事数は増加し続けている(図1)。一方「喫茶」を含む記事数は減り続け,2005年に「カフェ」の数が「喫茶」を超えた。時代によって変化してきた提供物の趣向やサービスの傾向などによって喫茶という言葉の代わりにカフェが使われ始め,今ではカフェの方が広く浸透した呼び名となっている。カフェ,喫茶店の客は飲食以外で何の行為をしているのだろうか。一人で来る客は時間つぶしでスマホ操作,読書,あるいは何もせずにもの思いにふける場合もあるだろう。また勉強をしている学生や仕事をする社会人もいる。ノートパソコンで仕事や何かしらの作業をしている人もいるが,その需要に応えコンセントや無線LANを設置している店も多い。複数人でいる場合はおしゃべりを楽しんだりするだけでなく,仕事の打ち合わせなど会議室代わりとしても使われる。早朝にはモーニングを提供し,夜は遅くまで営業している店もあり,時間帯によって客層の世代や社会的立場が変化しつつ存在している場所である。レストランでは食事と会話以外の行為をすることを憚られるが,カフェや喫茶店は飲食店ではあるものの,食欲を満たすためという側面が薄いことから,仮設の私室としての感覚で気軽に利用できる。しかし周囲に他人がいる公共の場所であり,特にフルサービスの店では常に店員が客席に気を配っているため,場合によっては周りの目を気にすることもあるだろう。また,周りからどのように見られるかを気にするという側面から考えると,どのようなタイプのカフェや喫茶店に行くかによって自分らしさを表現しているというパターンもあるだろう。本稿ではカフェという言葉に押され気味の喫茶店と呼ばれる存在に着目し,主に昭和創業で現在も営業し続けており当時の面影を残す喫茶店を純喫茶と呼ぶこととする。総務省がおこなう事業所調査では喫茶店の店舗数は1981年のピーク以降減少し続けている。しかし近年純喫茶の全盛期を経験していない世代が純喫茶に価値を感じている現象があることを様々なメディアから見ることができる。また若年層が中心となっているSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の一つであるインスタグラムでも純喫茶に関する投稿が見られる。若い世代が経験していないにもかかわらず純喫茶に対して郷愁を感じているのはなぜなのか,そして純喫茶の今後を考える。
- 著者
- 情報処理学会 [編] = Information Processing Society of Japan
- 出版者
- 情報処理学会
- 巻号頁・発行日
- 1979
1 0 0 0 ヴォーカルマイノリティ現象を説明する意見発信モデルの提案
- 著者
- 鳥海 不二夫 松澤 有 鈴村 豊太郎
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.6, pp.1277-1286, 2017-06-15
ソーシャルメディア上で頻繁に見られる意見と,世間一般における多数派の意見とは必ずしも一致しない.このような現象が発生する原因の1つにヴォーカル・マイノリティがあると考えられる.本研究では,ヴォーカル・マイノリティ現象が発生する要因を明らかにするために,ソーシャルメディア上でのユーザ行動のマルチエージェントモデルを提案した.提案モデルを用いたシミュレーションによってハブエージェントの影響がヴォーカル・マイノリティが発生する要因の1つであると考えられることを明らかにした.さらに,ソーシャルメディアの実データを用いて分析を行い,本シミュレーション結果が実データでも支持されることを確認した.
1 0 0 0 OA 新生児聴覚スクリーニング一側リファーから診断された両側難聴児の検討
- 著者
- 増田 佐和子 鶴岡 弘美 須川 愛弓 臼井 智子
- 出版者
- 一般社団法人 日本聴覚医学会
- 雑誌
- AUDIOLOGY JAPAN (ISSN:03038106)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.1, pp.54-60, 2021-02-28 (Released:2021-03-20)
- 参考文献数
- 15
要旨: 自動 ABR による新生児聴覚スクリーニング (NHS) で一側リファーとなり両側難聴と診断した19例を検討した。5例に難聴の家族歴を認め, 7例は複数回のスクリーニングで両側リファーとなったことがあった。パス側で判明した難聴の程度は軽度7例, 中等度11例, 高度1例, 聴力型は水平型9例, 低音障害型4例, 高音漸傾型3例, 高音急墜型2例, 不明1例であり, リファー側とパス側の難聴の程度は17例で, 聴力型は13例で一致した。パス側の偽陰性の理由は, 11例が境界域の聴力レベル, 6例が高音域の閾値が正常範囲内の聴力型, 1例が進行性難聴によると推定され, 1例は不明であった。18例が補聴器の適応とされたが4例は装用を拒否または受診を中断した。一側リファー例でも慎重に対応し, 難聴の家族歴をもつ場合, 複数回のスクリーニングで両側リファーがあった場合, リファー側が軽・中等度難聴や特殊な聴力型である場合などは特に注意すべきであると考えられた。
- 著者
- 廣瀬 正雄 北島 三郎
- 出版者
- 社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 工業化学雑誌 (ISSN:00232734)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.9, pp.994-996, 1930
1 0 0 0 OA 地方鉄道における国産レールへの転換 茨城県龍崎鉄道および鹿島参宮鉄道を中心に
- 著者
- 増子 絢音
- 出版者
- 特定非営利活動法人 頸城野郷土資料室
- 雑誌
- 頸城野郷土資料室学術研究部研究紀要 (ISSN:24321087)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.4, pp.1-17, 2020 (Released:2020-04-07)
- 参考文献数
- 12
1 0 0 0 OA 角運動量制御による2足歩行ロボットの3次元動歩行
- 著者
- 佐野 明人 古荘 純次
- 出版者
- The Society of Instrument and Control Engineers
- 雑誌
- 計測自動制御学会論文集 (ISSN:04534654)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.4, pp.459-466, 1990-04-30 (Released:2009-03-27)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 9 18
A biped locomotion robot is expected to be very useful in indoor space designed for human locomotion. In order to achieve a smooth dynamic walking like a human being, it is very important to control a quantity which can represent the state of the biped system as a whole. In regard to biped locomotion systems, an angular momentum of the whole system can be considered as a good index, since it is a stable quantity, as seen from ‘the law of the conservation of angular momentum.’ A control method divided the walking into motions in the sagittal plane and in the lateral plane is adopted. For motion in the sagittal plane, we put the angular momentum close to the smooth reference function given in advance by controlling the ankle torque of supporting leg. For motion in the lateral plane, we treated the motion control as a regulator problem with two equilibrium states. The effectiveness of the proposed control method was examined by the experiments with our walking robot BLR-G2. The BLR-G2 achieved three-dimensional walking where the walking speed is 0.35m/s with stride length 35cm.