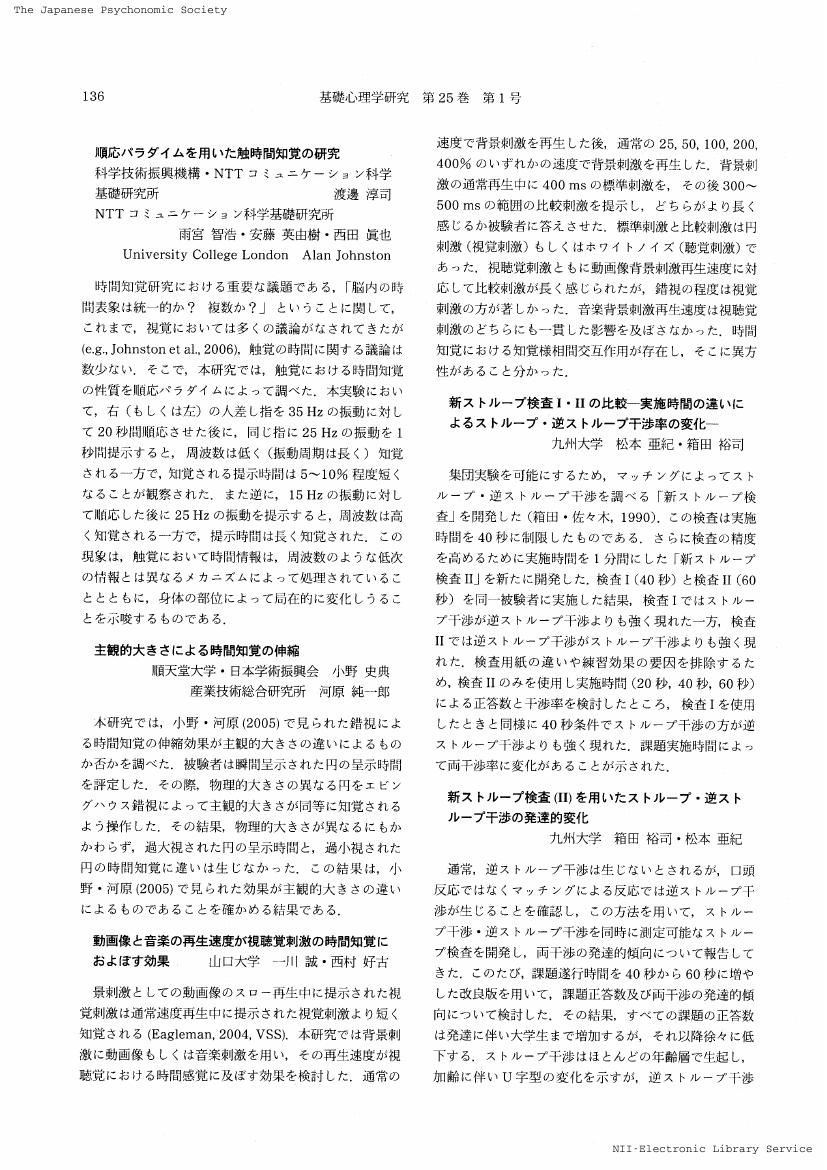- 著者
- 所 吉彦 徳永 彩子
- 出版者
- 学校法人 尚絅学園 尚絅大学研究紀要編集部会
- 雑誌
- 尚絅大学研究紀要 A.人文・社会科学編 (ISSN:21875235)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, pp.113-120, 2020
ILO によれば我が国の女性管理職比率は12%とG7最下位である。そこで本研究は女性が管理職に至るまでの「鍵となる出来事」を探ること,今後の調査への示唆を目的とした。東証1部上場企業女性管理職10名を対象とした半構造化面接を実施した。分析は前回研究と異なるM-GTA 法を用いた。その結果,「鍵」には5カテゴリーが存在することが再度確認された。また,「鍵」カテゴリーの継続修正,初級管理職の「鍵」データ蓄積が必要であることが分かった。
1 0 0 0 OA 支部だより ~中部支部の研究室紹介~
- 著者
- 飯野 亮太 奥田 覚 島本 勇太
- 出版者
- 一般社団法人 日本生物物理学会
- 雑誌
- 生物物理 (ISSN:05824052)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.2, pp.128-129, 2021 (Released:2021-03-25)
1 0 0 0 IR イタリア・アグリツーリズモ・研修報告 : 「食」と「生活の質」を中心に
- 著者
- 松木 宏美
- 出版者
- 同志社大学
- 雑誌
- 同志社政策科学研究 (ISSN:18808336)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.2, pp.195-200, 2009-12
研究活動報告(Research and Activity Report)古来、イタリアは食文化の中心地の一つであり、近年においてはスローフード運動の発祥の地としても知られる。筆者は2008年10月「テッラ・マードレ」参加のため、イタリア北部の古都トリノを訪れた。その際、それぞれの社会の進化において共通の問題が帯のように横たわっているのではないかと考えた。併せて、スローフード運動の発祥はなぜイタリアだったのか、イタリアと日本との差異の要因は何なのかという疑問を持つようになった。その後、中央大学法学部の工藤裕子教授(政治学)の地域・公共マネジメント・プログラムの海外現地調査の一環である『イタリア・アグリツーリズモ・ワークショップ』に参加し、中部イタリアの農家民宿に宿泊しながら、地域の農家や自治体関係者の話を聴くことができた。ここでは、この体験をもとに、人間やその共同体にとっての「食べること」の意味、生活の質、よりよい生活に向けての活動の要点、よりよい生活の実践に際しての日本との差異等について、調査し考察した結果を報告する。
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経コンピュータ (ISSN:02854619)
- 巻号頁・発行日
- no.810, pp.96-98, 2012-06-07
なぜ10対0なのか―。実質的に日本IBMの全面敗訴となった「スルガ銀―IBM裁判」第一審判決の判決理由が明らかになった。東京地方裁判所の判断を左右したのは、両社幹部によるステアリングコミッティーの議事録だった。書面として残された証拠の重要性が改めて浮き彫りになった。 勘定系システムの開発が失敗した責任を巡り、スルガ銀行と日本IBMが互いを訴えたスルガ銀―IBM裁判。
1 0 0 0 OA 映像再生速度とそのリラクゼーション効果について:心拍変動解析による評価
- 著者
- 杉浦 友紀 奥平 裕 中村 剛士 伊藤 英則
- 出版者
- 日本感性工学会
- 雑誌
- 日本感性工学会論文誌 (ISSN:18845258)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.3, pp.595-602, 2009-02-28 (Released:2016-01-25)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1 2
Healing music and Musicotherapy attract attentions recently. They are beginning to be used in the medical treatment. On the other hand there are little practical utilization to relax with video images compared with music. Visual information is said to occupy about the whole of 80% humans receive from five senses. Therefore it has some potential that visual information affects human's mental and physical state as well as aural information does. This paper attempts to investigate the relation between characteristics of video images and mental relaxation. The one of characteristics we focus is motion speed of video images. It is considered that it might correspond to tempo of music. This paper investigates the relaxation effect by using the index calculated by heart rate variability analysis. The experimental results and analysis confirmed that viewing video images might have higher effect of reducing stress than eyes closed state and the relaxation effect might depend on motion speed.
- 著者
- 一川 誠 西村 好古
- 出版者
- 日本基礎心理学会
- 雑誌
- 基礎心理学研究 (ISSN:02877651)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.136, 2006-09-30 (Released:2016-12-01)
1 0 0 0 IR W.G.ゼーバルトと写真 : 『アウステルリッツ』読解のための覚書
- 著者
- 大河内 朋子 OKOCHI Tomoko
- 出版者
- 三重大学人文学部文化学科
- 雑誌
- 人文論叢 = Bulletin of the Faculty of Humanities and Social Sciences,Department of Humanities (ISSN:02897253)
- 巻号頁・発行日
- no.34, pp.109-114, 2017
W.G.ゼーバルト(1944-2001)は、発表した文学作品のすべてに図像を挿入している。拙稿では、図像の中でもゼーバルトによる利用度の高いメディアである写真を取り上げて、次の3点から考察した。まず、ゼーバルトが写真という媒体をどのように捉えているのかについて、ゼーバルト自身の言説を手がかりに考察した。ゼーバルトは、写真には被写体という「現実的な細胞核」があり、この細胞核の周りを取り巻いて「無の巨大な中庭」があると述べている。写真を観る者は、写真から聞こえてくる「物語りなさいという途轍もない呼びかけ」に応えて、この「無の中庭」を想像上の物語で埋めることになる。つまりゼーバルトにとって写真とは、過去を物語るための原動力であった。次に、言語テクストと写真の「開かれた」関係について考察した。写真に内包された「無の中庭」を埋める物語は、写真を観る者の想像力次第で、さまざまな内容の物語として紡ぎ出されてくる。この意味において、写真は多様な言語テクストの産出に対して「開かれて」いる。言語テクストと写真の間には、もう一つの「開かれた」関係がある。両者が交わす間メディア的な「対話」は、紡ぎ出された物語の信憑性や事実性を高めているようにも、また逆に物語の虚構性を暴露しているようにも見える。つまり、ゼーバルトの間メディア的テクストは、「事実性と虚構性の緊張関係」の中に「開かれた」対話を交わしているのである。3点目として、挿入された白黒写真の不鮮明な画質に着目した。画像の不明瞭さや暗さは、人の記憶の中の像にも似ていて、無常や忘却のアレゴリーである。ゼーバルトは、ぼんやりと写っている被写体を暗やみの地下世界に永遠に葬ってしまうのではなく、闇を追い払う光(過去を観察し思索する眼差し)の力と、その力で紡ぎ出された物語によって、読者に対して過去を想起せよと警告しているのである。
1 0 0 0 OA 甲状腺全摘後の血清マーカー値の経時的変動分析に基づく甲状腺乳頭癌の予後の動的予測
- 著者
- 宮内 昭 工藤 工 都島 由希子 宮 章博 小林 薫 伊藤 康弘 高村 勇貴 木原 実 東山 卓也 福島 光浩 藪田 智範 舛岡 裕雄 進藤 久和 山田 理 中山 彩子
- 出版者
- 日本内分泌外科学会・日本甲状腺外科学会
- 雑誌
- 日本内分泌・甲状腺外科学会雑誌 (ISSN:21869545)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.1, pp.13-17, 2013 (Released:2013-05-31)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1
現在,甲状腺乳頭癌に対しては,腫瘍径,Ex,N,Mの評価に基づいて手術術式が選択され,術後は病理学的所見や術後の血清サイログロブリン(Tg)値に基づき,術後療法が選択されている。本論文では,Tg抗体(TgAb)陰性の乳頭癌においては甲状腺全摘後のTSH抑制下のTg値の変動から求めたTgダブリングタイム(TgDT)が多変量解析において最強の予後因子であることを紹介する。Tg値の変動が重要である。しかし,TgAb陽性患者においてはTg値の信頼性は低い。そこで,TgAb陽性の乳頭癌225症例の甲状腺全摘後のTgAb値の変動と予後との関係を調べると,術後2年以内に50%以上低下した症例は非低下症例より有意に良好であり,多変量解析において優れた予後因子であることが判明した。今後は,旧来のTNM,病理学的分化度による予後予測の時代から,血清Tg,TgAb値の経時的変動分析に基づく動的予後予測の時代へとパラダイムシフトが起こるものと予想される。
1 0 0 0 故理學博士矢田部良吉君ノ略傳
- 著者
- 松村 任三
- 出版者
- 公益社団法人 日本植物学会
- 雑誌
- 植物学雑誌 (ISSN:0006808X)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.155, pp.1-4, 1900
1 0 0 0 OA 東海地方の自治体における小中学校教員の人事異動の傾向
- 著者
- 深谷 和義
- 雑誌
- 教育学部紀要 (ISSN:18838626)
- 巻号頁・発行日
- no.8, pp.207-216, 2015
1 0 0 0 OA 語学教育と文法
- 著者
- 朝倉 季雄
- 出版者
- 日本フランス語教育学会
- 雑誌
- フランス語教育 (ISSN:09102353)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.19-25, 1981-05-28 (Released:2017-10-14)
1 0 0 0 OA 幼児の睡眠・生活リズムと親子の生活習慣等の関連
- 著者
- 藤井 千惠
- 出版者
- 愛知教育大学
- 雑誌
- 愛知教育大学研究報告. 教育科学編 (ISSN:18845142)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, pp.43-51, 2016-03-01
1 0 0 0 IR ヴァレンティノス派教師プトレマイオスのフローラ宛書簡の再評価
- 著者
- 新免 貢 Mitsugu Shinmen
- 出版者
- 宮城学院女子大学キリスト教文化研究所
- 雑誌
- キリスト教文化研究所研究年報 (ISSN:0386751X)
- 巻号頁・発行日
- no.44, pp.1-39, 2010
1 0 0 0 DNAマーカーを利用した日本に現存するウルシ林の遺伝的多様性評価
- 著者
- 渡辺 敦史 田村 美帆 泉 湧一郎 山口 莉未 井城 泰一 田端 雅進
- 出版者
- 日本森林学会
- 雑誌
- 日本森林学会誌 (ISSN:13498509)
- 巻号頁・発行日
- vol.101, no.6, pp.298-304, 2019
- 被引用文献数
- 1
<p>二つのDNAマーカー,EST-SSRマーカーとgenomic SSRマーカーを利用してウルシ林の多様性評価を行った。EST-SSRマーカーは次世代シーケンサーを利用して新たに開発した。得られたEST情報から2塩基または3塩基モチーフの一定繰り返し数以上を示した21領域にプライマーを設計した結果,最終的に8マーカーが利用可能であった。8 EST-SSRマーカーおよび7 genomic SSRマーカーを利用して,全国各地のウルシ林9集団から採取した377個体を対象として分析した。ウルシは,渡来種であり,クローン増殖が容易であることから遺伝的多様性の喪失が懸念されたが,遺伝的多様性は近縁種であるハゼノキよりもやや高く,著しい喪失は認められなかった。クラスター分析・主座標分析・STRUCTURE分析の結果は,集団によっては特異性が維持されていることを示す一方で,種苗が移動したことによる集団内の遺伝構造の存在を示していた。クローンの存在や小集団化に伴うボトルネックは限定的であり,現在のウルシ林を適切に保存すれば,ウルシ遺伝資源は維持できると考えられる。</p>
- 著者
- 井手 幸恵 風間 健
- 出版者
- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会
- 雑誌
- 繊維製品消費科学
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.5, pp.265-270, 1997
本報の目的は女子就労者がブランドの鞄を所持する状態と希望する要因を明らかにすることである.分析手法として因子分析を用いた.結果は以下のとおりであった.<BR>1) 女子就労者が所持している鞄はユリエニタニ, エルメス, フェンディ, マリクレール等が多かった.<BR>2) 女子就労者が希望する鞄はシャネル, ルイ・ヴィトン, プラダ, フェラガモ, フェンディ等が多かった.<BR>3) 因子得点の符号の正負と勤務先, 所持ブランド, 希望ブランドとのそれぞれの間にはχ<SUP>2</SUP>検定を行なった結果, 有意な差があると認められた.<BR>4) 希望するブランドの鞄には3つの要因があることが明らかになった.「ゴージャス-シンプル」, 「話題性-実用性」, 「自己志向-他者志向」の要因と考えた.これらの要因と勤務先や希望ブランドの関連性を追究した.<BR>5) 各ブランド側のアピールが女子就労者によく伝わっていることがわかった.<BR>6) 所持している鞄と希望する鞄とは共通の要因があった.
1 0 0 0 IR ココ・シャネルによるCHANELのブランド・ビルディング
- 著者
- 塚田 朋子
- 出版者
- 東洋大学経営学部
- 雑誌
- 経営論集 (ISSN:02866439)
- 巻号頁・発行日
- no.67, pp.83-99, 2006-03
1 0 0 0 IR アール・デコの服飾
- 著者
- 川中 美津子
- 出版者
- 関西意匠学会
- 雑誌
- デザイン理論 (ISSN:09101578)
- 巻号頁・発行日
- no.34, pp.136-137, 1995-11-18
- 著者
- 飯塚 由美 Yumi Iitsuka
- 雑誌
- 島根県立大学短期大学部松江キャンパス研究紀要 (ISSN:18826768)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, pp.21-29, 2014-03-31