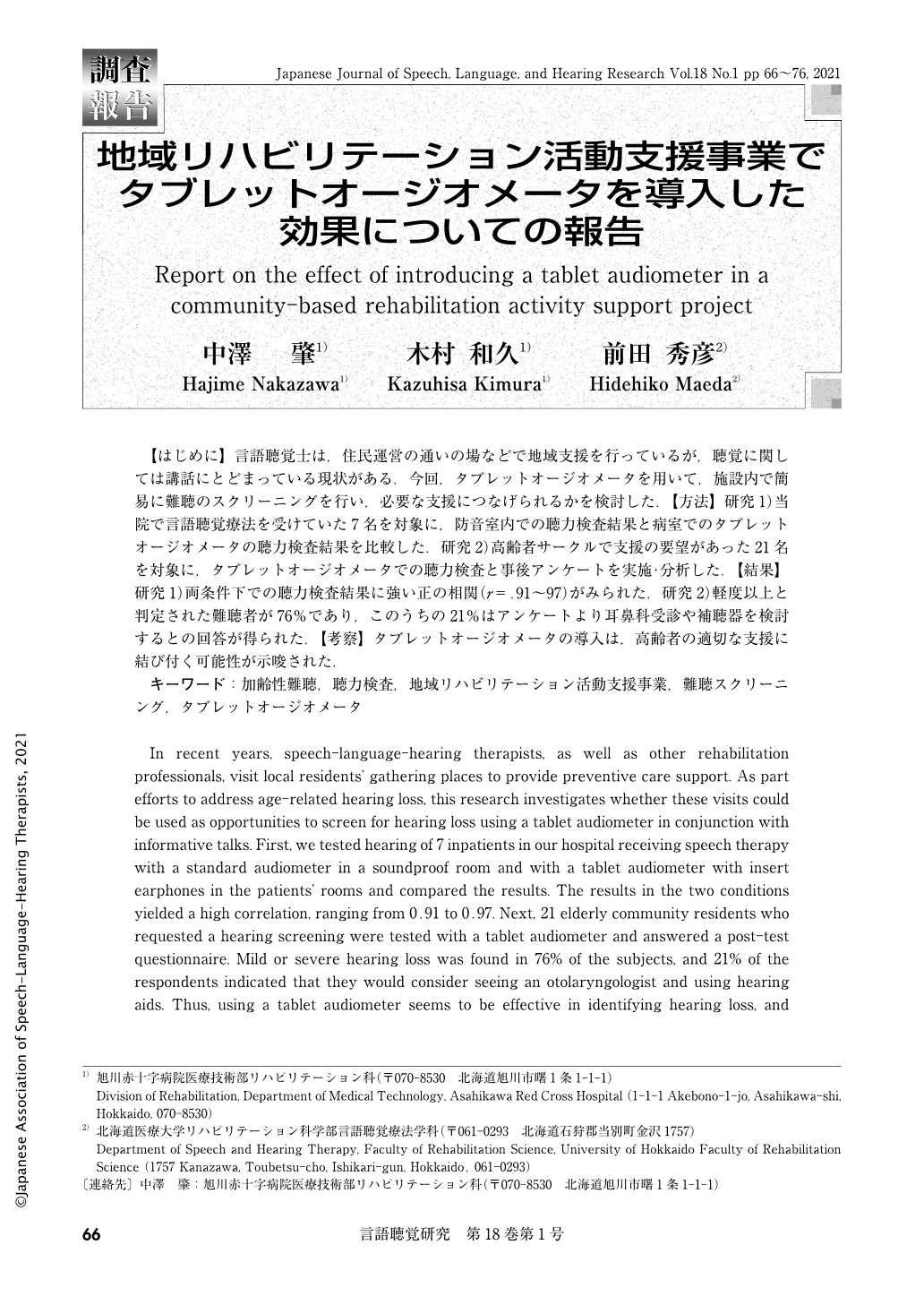1 0 0 0 IR 〝説得〟コミュニケーションの研究 : Self Persuasion『自主説得』の考察
- 著者
- 中村 克洋
- 出版者
- 広島経済大学
- 雑誌
- 広島経済大学創立五十周年記念論文集
- 巻号頁・発行日
- pp.733-768, 2017-07-31
説得(的)コミュニケーションとは,受け手(コミュニケーションの相手)の意見を特定の方向に変化させ,それによって相手の行動を変化させることをねらった(意図的)コミュニケーションである。古来,受け手(コミュニケーションの相手)の行動を自分の都合のいい方向に変化させることを目的にした『説得行為』が,様々に工夫されて行われてきた。また,成功効率の高い「説得テクニック」が模索されてきた。しかし,相手の意見や行動を特定の方向に変化させるというコミュニケーション行為には,必然的に,ある「作為」がともなう。この「作為」が,ややもするとリアクタンス(心理的な反発)を引き起こす。いわゆる「不本意な感情」である。「だまされた」「のせられた」「してやられた」といった負の感情を引き起こしてきたのである。従来の説得コミュニケーションのテクニックは,すべてこういったリスクを伴っている。この従来型の説得テクニックを本論では『古典的説得技法』と名づけておく。その『古典的説得技法』に対して,本論の主題である『Self-Persuasion』(『自己説得』と邦語訳するケースが多いが,宗教的な意味合いを持って使われる場合が多いので,本論では『自主説得』として論述する)は,リアクタンスが全く起きないという意味で画期的であり,両者(説得者と被説得者)が,お互いウィンウィンの関係が保てるというメリットまである。この『自主説得』を効率よく使うことによって,人間関係は良好に保たれ,ビジネスの現場での様々な説得行為における説得(的)コミュニケーションを理想的な形で行うことができる。本論では,説得行為そのものの考察を行うことで,古典的説得技法における説得コミュニケーションの理論を確認し,その発展的段階として『自主説得』というリアクタンスを生まない最先端の説得技法に言及する。人生やビジネスの現場の「説得シーン」において,もっとも理想的な『自主説得』を使いこなし,より良い人間関係や目覚ましいビジネス実績を残せる「説得のエキスパート」となることに資するべく,本論を起稿する。1.〝何が〟『人を動かす』のか〝説得心理〟の分析 1.1 古典的説得法で説得の基礎を知る 1.2 説得は『二つの原理』が支配 1.2.1 『返報性の原理』と『一貫性の原理』 1.3 〝フット・イン・ザ・ドア〟『一貫性の原理』 1.3.1 【小さなイエス】から【『一貫性』の(大きな)イエス】 1.3.2 「フット・イン・ザ・マウス」 1.4 〝ドア・イン・ザ・フェイス〟『返報性の原理』 1.4.1 【大きなノー】から【『返報性』の(小さな)イエス】 2. 新原理を理解する その名は『自主説得』 2.1 これぞ究極の説得だ 2.1.1 『自主説得』は〝ウィンウィン〟 2.1.2 非常に興味深い〝ある実験〟(アメリカ国民に〝虫〟を食べさせる) 2.1.3 実験結果から見えた『自主説得』の〝心理的背景〟 2.2 最先端の説得技法『自主説得』 2.2.1 吉本さんに〝マツダ〟の車を買ってもらう 2.2.2 これまでとは〝全然ちがう〟(「心理的反発」がまるでない) 2.2.3 古典的説得では〝あまのじゃく心理〟がジャマをする(説得するほど反発をかう) 2.2.4 こんな説得〝なかった〟(〝反発〟がまるでない) 2.3 〝メリット〟を自主的に認識する『自主説得』 2.3.1 〝生命保険〟の勧誘 3.最新理論『自主説得』を〝実践〟する 3.1 『自主説得』のノウハウ 3.1.1 〝相手に言わせる〟ための「質問」がほしい 3.1.2 「言わせる」ための〝聞き出し〟 3.1.3 〝逆〟効果の〝聞き出し〟質問 3.2 〝聞き出し〟のコツ『イイとこ掘り』 3.2.1 答えの〝正しい誘導〟と〝会話の支配〟 3.2.2 「イイとこ」のバリエーション(言いかえ) 3.3 『イイとこ掘り』を繰り返しているうちに 3.3.1 『自主説得』効果は〝持続〟する 3.3.2 『自主説得』はアトからでも〝発現〟する 4.『自主説得』のバックアップ技法(『一般的会話技法』より) 4.1 火縄銃よりマシンガン 4.1.1 ねらった答えを次々に誘発するには? 4.1.2 『イイとこ掘り』は会話を支配する 4.1.3 『イイとこ掘り』の連発撃ちは〝5W1Hを聞け!〟 4.2 主語を『私(たち)』に変える 4.2.1 主語を『私』に変えると……(『返報性の原理』が使える!) 4.3 「教えてください」で〝教えたがる〟相手を利用 4.3.1 『自主説得』への〝くすぐり効果〟 4.4 相手を〝いい気分〟にさせて『自主説得』効果を上げる 4.4.1 『ラべリング』 4.4.2 〝ほめて〟『返報性の原理』『一貫性の原理』をうながす あとがきにかえて 参考文献
1 0 0 0 OA ヒノキ両性不稔個体の発見
- 著者
- 齋藤 央嗣
- 出版者
- 日本森林学会
- 雑誌
- 日本森林学会誌 (ISSN:13498509)
- 巻号頁・発行日
- vol.99, no.4, pp.150-155, 2017-08-01 (Released:2017-10-01)
- 参考文献数
- 43
- 被引用文献数
- 2
ヒノキの花粉症対策のため,雄性不稔個体の探索を行った。神奈川県内のヒノキ林を探索した結果,雄花から花粉が飛散しない個体が発見された。花粉の飛散を調べるため,雄花がついた枝を袋に入れ水差ししたところ,飛散期を過ぎても花粉嚢が開かず,全く花粉を飛散しなかった。花粉嚢内の状況を光学顕微鏡で観察したところ,正常花粉と異なる大小の粒子が観察された。電子顕微鏡で花粉嚢内を観察したところ,正常花粉同様に花粉の表面に形成されるオービクルは観察されたものの,正常な花粉は形成されていなかった。種子の稔性を調査したところ,結実した球果は小型で,正常な種子は形成されなかった。さし木の活着率は70%であり,クローン増殖が可能であった。増殖したさし木クローンに着花した雄花も花粉を飛散せず,雄性不稔形質は増殖個体でも再現性があった。染色体数を確認したところ 2n= 22 本で2倍体であり,染色体数の異常は認められなかった。花粉四分子期の観察により,雄性不稔形質は,減数分裂時の不等分裂が原因であると推定された。雄花および球果の状況から,両性不稔個体であると判断された。
1 0 0 0 OA 137.ヒメスイバ, ギシギシ花粉症(花粉症)
- 著者
- 我妻 義則 松山 隆治 佐藤 幹弥 伊藤 浩司 水谷 民子 藤崎 洋子
- 出版者
- 一般社団法人 日本アレルギー学会
- 雑誌
- アレルギー (ISSN:00214884)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.3, pp.245-246, 1974-03-30 (Released:2017-02-10)
1 0 0 0 IR コメにおける4-アミノ酪酸(GABA)増量法の開発ならびにその利用
- 著者
- 三枝 貴代
- 出版者
- 筑波大学 (University of Tsukuba)
- 巻号頁・発行日
- 2016
2015
1 0 0 0 IR 二人の機織女 : 瓜子姫とあまのじゃく
- 著者
- 荒川 理恵
- 出版者
- 学習院大学
- 雑誌
- 学習院大学上代文学研究 (ISSN:09162453)
- 巻号頁・発行日
- no.29, pp.18-34, 2004-03-31
1 0 0 0 IR 「言いさし文」における「という」の諸用法 : 終助詞的用法に関する一考察
- 著者
- 上村 昂史
- 出版者
- 京都大学大学院人間・環境学研究科言語科学講座
- 雑誌
- 言語科学論集
- 巻号頁・発行日
- no.20, pp.31-48, 2014
In this paper I focus on the functions of ~toiu (~teiu as one of the colloquial variants) in discourse and take an empirical study on it. Based on data which is recorded from discourse, I analyze, although ~toiu is regarded originally as "suspended-sentence" type element, it can actually be used by speakers to combine their statement with preceding ones, or to mark the end of their utterance. I apply the theoretical framework of Shirakawa (2009), who proposes alternative view against traditional grammar. A comprehensive study by Shirakawa (2009) proposes that conjunctive subordinate clauses utilizing i.e. ~kedo, ~kara or ~shi can be used without main clauses in discourse level. He argues that it reveals the fact that they show a certain attitude of a speaker during a discourse. Firstly I argue that this function does not match with any traditonal categories of ~toiu which traditional grammar of the Japanese language presents. Secondly, I categorize this usage into two categories, according to Shirakawa (2009). Then, I point out that the usage as "terminated-sentence" has a similar function to sentence-final particles, which show a certain behavior of a speaker, i.e. taking a cynical attitude towards state of affairs. Then I make an explanation on these "~toiu"-constructions by taking into account the metalinguistic function of "~to (as a quotation marker)". I assume that ~toiu works as a marker of "meta-description" and draw the conclusion that it enables a speaker to express a state of affair as if one would not have been present in order to make an ironical nuance. Lastly, I show the process how ~toiu obtain the new function in discourse level, referring to the previous description by the traditional grammarians.
1 0 0 0 多数状況における内閣総辞職:政策決定の集権性と党内支持
- 著者
- 上條 諒貴
- 出版者
- 日本選挙学会
- 雑誌
- 選挙研究 (ISSN:09123512)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.1, pp.57-70, 2017
議会の過半数を占める政党が存在する「多数状況(majority situation)」における内閣総辞職は,議院内閣制における内閣の終了を扱った研究が拠って立つ政党間交渉の理論からでは説明困難な現象である。本稿では,数理モデルを用いて執行部への党内支持の観点から総辞職を理論的に分析する。モデルの含意として,党への支持が低下している場合に,現在の世論により合致した政策選好を持った政治家に党首を交代させることで支持を回復するという戦略の有効性が増すため,多数状況においては政党が集権的な場合の方がより総辞職が起こりやすいという仮説が提示される。理論的検討の後,この仮説を1960年から2012年の日本の内閣データを用いて実証する。分析の結果,内閣支持率などの変数を統制してもなお,党内の集権性が高まった政治制度改革後の方が内閣総辞職のリスクが高いことが示される。
- 著者
- 松井 千鶴子 Chizuko Matsui
- 出版者
- 上越教育大学
- 雑誌
- 上越教育大学教職大学院研究紀要 (ISSN:2187882X)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.159-169, 2014-02
【はじめに】言語聴覚士は,住民運営の通いの場などで地域支援を行っているが,聴覚に関しては講話にとどまっている現状がある.今回,タブレットオージオメータを用いて,施設内で簡易に難聴のスクリーニングを行い,必要な支援につなげられるかを検討した.【方法】研究1)当院で言語聴覚療法を受けていた7名を対象に,防音室内での聴力検査結果と病室でのタブレットオージオメータの聴力検査結果を比較した.研究2)高齢者サークルで支援の要望があった21名を対象に,タブレットオージオメータでの聴力検査と事後アンケートを実施・分析した.【結果】研究1)両条件下での聴力検査結果に強い正の相関(r=.91〜97)がみられた.研究2)軽度以上と判定された難聴者が76%であり,このうちの21%はアンケートより耳鼻科受診や補聴器を検討するとの回答が得られた.【考察】タブレットオージオメータの導入は,高齢者の適切な支援に結び付く可能性が示唆された.
1 0 0 0 IR 国際寡占市場・最適課税 : 補助金政策・新ベルトラン均衡
- 著者
- 下村 耕嗣
- 出版者
- 慶應義塾経済学会
- 雑誌
- 三田学会雑誌 (ISSN:00266760)
- 巻号頁・発行日
- vol.89, no.2, pp.163(23)-174(34), 1996-07
小特集 : 国際貿易と経済成長
- 著者
- Teiichiro ITO Akira TAKATSUKI Kenji KAWAMURA Katsuki SATO Gakuzo TAMURA
- 出版者
- Japan Society for Bioscience, Biotechnology, and Agrochemistry
- 雑誌
- Agricultural and Biological Chemistry (ISSN:00021369)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.3, pp.695-698, 1980 (Released:2008-11-27)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 44
- 著者
- 田島 宏一
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会論文誌. D, 産業応用部門誌 (ISSN:09136339)
- 巻号頁・発行日
- vol.133, no.6, pp.NL6_3, 2013
1 0 0 0 OA 伊曽乃神社志
- 著者
- 伊曽乃神社奉賛会 編
- 出版者
- 伊曽乃神社奉賛会
- 巻号頁・発行日
- 1937
1 0 0 0 OA The Structure of Kanamycin B
- 著者
- Teiichirō Itō Motohiro Nishio Hiroshi Ogawa
- 出版者
- Japan Antibiotics Research Association
- 雑誌
- The Journal of Antibiotics, Series A (ISSN:03681173)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.5, pp.189-193, 1964 (Released:2020-07-07)
- 参考文献数
- 14
In the course of a research for kanamycin (kanamycin A)1) purification, kanamycin B1) and kanamycin C2) were isolated from the culture broth of Streptomyces kanamyceticus1). Kanamycin B was obtained in pure form by Schmitz, Fardig, O’Herron, Rousche and Hooper8), who isolated deoxystreptamine and 3-amino-3-deoxy-D-glucose after acid hydrolysis of N-acetyl-kanamycin B. Wakazawa, Sugano, Abe, Fukatsu and Kawaji4) reported that partial hydrolysis mixture of kanamycin B still retained some biological activity against B. subtilis, and later they5) isolated a crystalline degradation product which had antibacterial properties.It has been determined that in kanamycins A6,7,8,9) and C10) two aminosugars link to 4- and 6-positions of deoxystreptamine, while in neomycin-group (neomycins B C11,12d) and paromomycin13) the 4,5 hydroxyls of deoxystreptamine are substituted. It should be noted that neomycins are more toxic than kanamycins A and C. As compared with kanamycin A and neomycin S, kanamycin B has more than twice less toxicity than neomycins and has more than five times toxicity than kanamycin A. As reported by Wakazawa et. al.4), kanamycin B can be determined separately from A.In the present paper, our experiments on the structure of kanamycin B are described. Kanamycin B base, which was prepared by the process of Wakazawa et al4) and was recrystallized from ethanol-water, showed [α]24D+ 126° (c, 0.7 in water) and decomposed over the range of 170~190°C. It was soluble in water, but hardly soluble in organic solvent. Its molecular weight was reported to be 1,170 (Rast method, urea as solvent) by Schmitz et al.3) and 385~560 (Barger method, water as solvent) by Wakazawa et al.4) The crystals obtained in our laboratory showed molecular weight of 430~590 by the Rast method (urea as solvent, kanamycin A as standard).N-Acetylkanamycin B3,4) was prepared and, from its hydrolyzates, deoxystreptamine hydrochloride (molecular weight 235) was isolated in the yield of about 30% by weight. The elemental analyses of kanamycin B base and its N-acetyl derivative, together with the above data, suggested the molecular formula C18H37N5O10 for kanamycin B base.
1 0 0 0 IR 作田啓一の社会学的想像力
- 著者
- 真鍋 公希
- 出版者
- 京都大学大学院人間・環境学研究科
- 雑誌
- 人間・環境学 (ISSN:09182829)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, pp.39-51, 2019
作田啓一は, 生の経験の中にあらわれる非合理性を捉えるための理論体系の構築に一貫して取り組んだ社会学者である. 先行研究では, 彼の生の経験への関心が中心的に論じられてきた. しかし, 作田の特徴は, 生の経験への関心だけでなく, それとは矛盾するように思われがちな体系化への志向性をも兼ね備えている点にあるように思われる. この問題意識に基づき, 本稿では作田の思想における理論の位置づけについて検討する. 本稿では, まず, 『命題コレクション社会学』の付論に注目し, 水平的関係と垂直的関係という二つの関係性を抽出する. 続いて, 現代社会学と小林秀雄に向けた作田の批判を検討し, 批判の要点が, 両者がともに, 現実を水平的/垂直的関係に還元して論じようとする点にあることを明らかにする. 最後に, 作田の犯罪分析を取り上げ, 彼が水平的関係と垂直的関係の両方を論じようとしていたことを指摘する. 以上から, 作田は社会学的な説明(水平的関係)と生の経験(垂直的関係)の二つを結びつけた理論的視座の構築を試みていたことを指摘し, その理論によって一つの「全体」を仮構していたと結論づける.
1 0 0 0 OA 他人を「下げる」が妬みにつながる人々 ―実体的知能観による調整効果―
- 著者
- 服部 陽介
- 出版者
- 日本感情心理学会
- 雑誌
- 感情心理学研究 (ISSN:18828817)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.Supplement, pp.ps41, 2020 (Released:2020-12-24)
1 0 0 0 OA 建屋間ネットワークのデータ転送性能評価
- 著者
- 宇野 篤也 岩本 光夫 八木 学 横川 三津夫
- 雑誌
- 研究報告ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC) (ISSN:21888841)
- 巻号頁・発行日
- vol.2017-HPC-158, no.14, pp.1-5, 2017-03-01
近年,HPC システムの大規模化にともない,シミュレーション結果も膨大な量となっている.この膨大な計算結果を効率よく分析するための手段として,可視化等が用いられることが多く,可視化専用のハードウェアを搭載したシステムを利用することがよくある.この場合,シミュレーションを行ったシステムとのデータ連携が必要となる.これらのサーバが同一のサイトに設置されている場合は,ストレージ共有で対応できるが,異なるサイトに設置されているシステムを利用する場合には,ネットワーク経由でデータの転送を行うことになり,高速なデータ転送が求められる.今回,スーパーコンピュータ 「京」 と隣接する神戸大学統合研究拠点の計算科学教育センターに設置された可視化用計算サーバ 「π-VizStudio」 を直接ネットワークで接続し,データ転送性能評価を行ったので報告する.
1 0 0 0 OA 2台の車両型移動ロボットから構成される協調搬送システムのベジェ曲線による経路計画
- 著者
- 山口 博明 新井 民夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学会論文集 C編 (ISSN:03875024)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.691, pp.774-781, 2004-03-25 (Released:2011-03-04)
- 参考文献数
- 6
This paper presents a novel path planning methodology using Bezier curves for a cooperative transportation system with two car-like mobile robots. We first transform the kinematical equation of this transportation system into two-chain, single-generator chained form in a coordinate system where a path is a curved line axis and a straight line perpendicular to the tangent of the path is another axis. The carrier of the transportation system can follow any path as long as its curvature is two times differentiable. The orientation of the carrier is uniquely determined according to the orientation of the tangent of the path. We secondly set the path to be a Bezier curve and we arrange the controlling points of the Bezier curve based on the working environment of the transportation system, e. g., in order for it to avoid collisions wit obstacles. The validity of this path planning methodology is supported by computer simulations.
1 0 0 0 OA 消費者評価から見たコーヒー関連企業の位置付け
- 著者
- 木村 雅敏 岩坪 友義
- 出版者
- 日本経営診断学会
- 雑誌
- 日本経営診断学会論集 (ISSN:18824544)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.49-55, 2010 (Released:2011-02-04)
- 参考文献数
- 22
コーヒーは,各々の特性によりレギュラーコーヒー,インスタントコーヒーならびに缶コーヒーの3タイプに分類され,さまざまなシチュエーションで飲用されている。本論文では,生産販売の実績データや財務諸表を基にした業界および企業の分析を行うとともに,消費者評価がコーヒー製造企業の経営行動に与える影響について,アンケート調査により主要企業の当該市場における位置付けを行った。それらの結果,主要企業をそれぞれ「ガリバー型」,「製品品質重視型」,「コアブランド重視型」,「自動販売機偏重型」等に分類・位置付けし,企業実績等により各社の優劣を考察した。
- 著者
- 林 和憲 伊藤 裕久
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 研究報告集 II, 建築計画・都市計画・農村計画・建築経済・建築歴史・意匠 (ISSN:13464361)
- 巻号頁・発行日
- no.74, pp.465-468, 2004-02