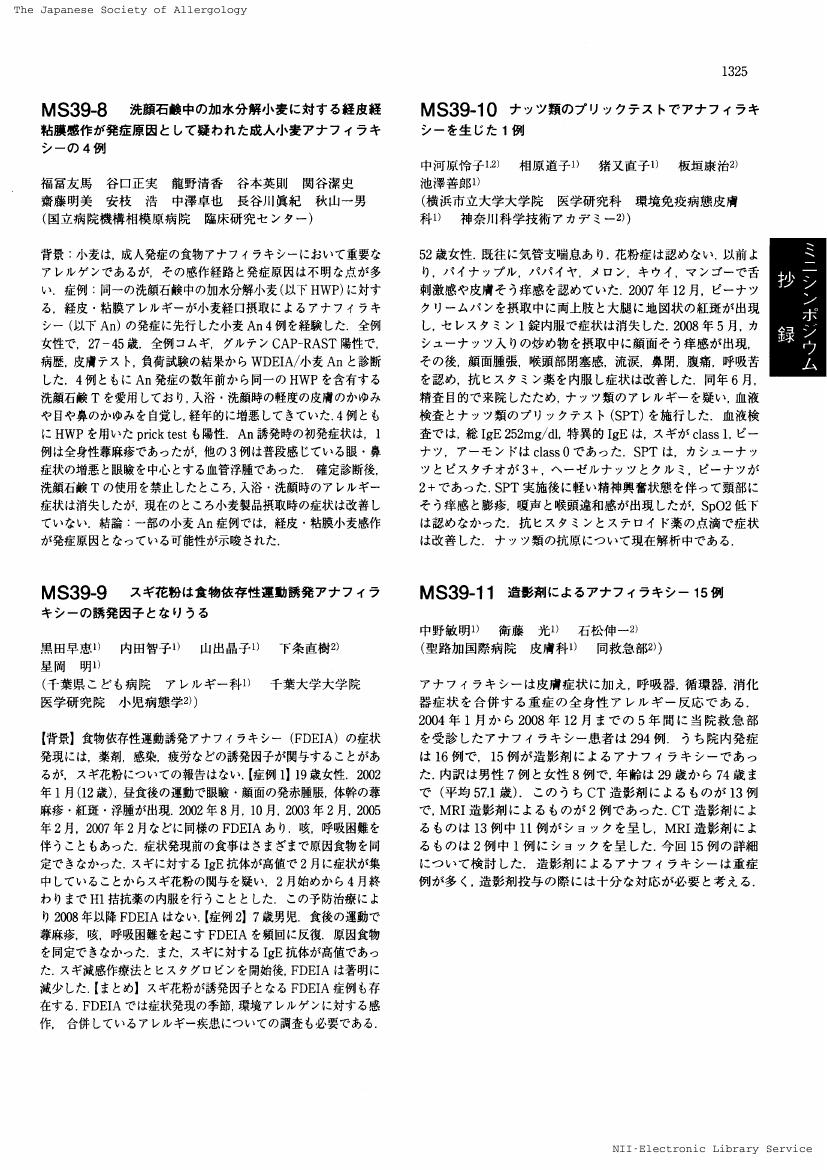1 0 0 0 伊豆の最南端で伊勢海老とシーカヤック
- 著者
- 南伊豆町 企画課
- 出版者
- 一般社団法人 日本風力エネルギー学会
- 雑誌
- 風力エネルギー (ISSN:03876217)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.3, pp.398-400, 2018
1 0 0 0 OA 歴史家としての吉田裕先生
- 著者
- 原田 俊彦
- 出版者
- 早稲田大学法学会
- 雑誌
- 人文論集 (ISSN:04414225)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, pp.ix-xiii, 2020-02-20
1 0 0 0 幕末から明治期における主婦の日記にみる食生活:―贈答品を中心に―
- 著者
- 櫻井 美代子
- 出版者
- 一般社団法人 日本家政学会
- 雑誌
- 一般社団法人日本家政学会研究発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.55, pp.126, 2003
【目的】近世・近代の家庭における食生活の実態を知るため、主婦の日記を資料としてそこに記載されている食品・食物を調査・検討行うことでその時代の食生活の一端を考察してきた。今回は地域の異なる二つの日記を比較することで、その食生活の特徴の違いを検討することを目的とする。【目的】『小梅日記』を中心にし、これとほぼ同時期に書かれた江戸近郊の日記である『大場美佐の日記』を比較することで地域的特徴などの違いを検討した。【結果】『小梅日記』・『大場美佐の日記』には日常の細々とした事柄が記載され、その中でも共に贈答品が多く登場し、食品・食物の割合は約80%であった。『小梅日記』では魚介・海藻類が最も多く、その内容は鯛・かつお・いな・ちぬ・さば・あじ・伊勢海老など多種類の記載があり、野菜・果物類では竹の子・松たけ、柿・梨・西瓜・郁李・仏手柑・利夫人橘などがみられ、穀類ではすし・餅類などで、嗜好品では酒・酒券・菓子などの記載がみられた。一方『大場美佐の日記』では魚介・海藻類鮎・肴・かつぶしが多く、野菜・果物類では柿・里芋・竹の子・さつま芋・真桑瓜などで、穀類ではそば・そば粉・赤飯・すし・うどん・うどん粉・餅類などがみられ、嗜好品の酒・にごり酒・菓子は多く用いられていた。どちらの日記も穀類,魚介・海藻類,野菜・果物,嗜好品類が多く記載されており、その中で江戸近郊の大場家ではみられなかった魚券・酒券が紀州川合家では使用されていた。また記載はすくない獣鳥肉類の中で大場家では記載がなかった牛肉は、川合家では寒中見舞いなどの贈答品として使用されていた。
1 0 0 0 OA エアトラック実験における水平調整と空気抵抗の影響
- 著者
- 新井 洋二 安達 健
- 出版者
- 日本物理教育学会
- 雑誌
- 物理教育 (ISSN:03856992)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.3, pp.185-187, 1974-09-20 (Released:2017-02-10)
1 0 0 0 OA 朱仁聰と周文裔・周良史 : 来日宋商人の様態と藤原道長の対外政策
- 著者
- 森 公章
- 出版者
- 東洋大学
- 雑誌
- 東洋大学文学部紀要. 史学科篇 = Bulletin of Toyo University, Department of History, the Faculty of Literature (ISSN:03859495)
- 巻号頁・発行日
- no.40, pp.1-69, 2014
- 著者
- 八坂 茂 宮原 昭二郎 田端 義明
- 出版者
- 長崎大学水産学部
- 雑誌
- 長崎大学水産学部研究報告 (ISSN:05471427)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.29-38, 1955-05-31
We already reported a prawn secreted an agaragarlike substance in the first report "Studies on the muscle-protein of Penaeus japonicus BATE". Now we intend to entitle a series of agaragarlike protein as a crustacean proteid. A crustacean proteid of crayfish contains fifteen substances―serine, lysine, glycine, arginine, histidine, threonine, alanine, tyrosine, methionine, phenyl-alanine, leucine, trace of proline and three unknown matters. The another crustacean proteid has an almost similiar constitution.
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.1240, pp.38-40, 2004-05-03
秋田県能代市の中心街にある、一見何の変哲もない公立学校。それが、高校バスケットボール界で、55度の日本一を獲得した能代工業高校だった。 校舎の横に隣接する体育館はバスケ部専用のものだ。米プロバスケットボール(NBA)のテレビ中継でよく見る、透明のバックボードが設置されている。総工費は4億円。
1 0 0 0 IR 音大生にふさわしい音響学の授業について ―コンサートホールを使った体験授業の報告―
- 著者
- 積田 勝
- 雑誌
- 武蔵野音楽大学研究紀要 = Bulletin of Musashino Academia Musicae (ISSN:05802466)
- 巻号頁・発行日
- no.49, pp.89-118, 2018-03-31
- 著者
- 飯村 伊智郎 池端 伸哉 中山 茂
- 出版者
- 情報知識学会
- 雑誌
- 情報知識学会誌 (ISSN:09171436)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.2, pp.1-17, 2003
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 8 3
遺伝的アルゴリズム(genetic algorithm : GA)には,集団内で同じ個体が急増するなどして,集団の多様性が失われてしまう過剰収束という好ましくない現象が生じ得る.一旦過剰収束が起こると交叉はその機能を失い,GAによる探索が殆ど意味のないものになってしまう.この過剰収束を回避して多様性を維持することが,GAを適用する際の重要なポイントとなる.本論文では,まず,並列GAの実装形態として,柔軟な分散並列処理の構築を提供し得るオブジェクト共有空間を用いた実装を提案する.次に,できる限り単純な仕組みで過剰収束を回避する手法として,並列GAにおけるノアの箱舟戦略を提案し実験によりその有用性を明らかにする.この手法は,進化の停滞した部分集団の個体の殆どを探索解空間から新たに迎え入れた個体群と入れ換えるものであり,非同期に均質個体を淘汰し集団の多様性減少に制限をかけることで過剰収束を回避する.
1 0 0 0 OA 人型ロボットの歩行制御
- 著者
- 山本 江
- 出版者
- 一般社団法人 日本ロボット学会
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.2, pp.103-109, 2018 (Released:2018-04-15)
- 参考文献数
- 38
1 0 0 0 OA MS39-9 スギ花粉は食物依存性運動誘発アナフィラキシーの誘発因子となりうる(食物アレルギー・薬物アレルギー-病態生理と治療4-アナフィラキシーを中心に-,第59回日本アレルギー学会秋季学術大会)
- 著者
- 黒田 早恵 内田 智子 山出 晶子 下条 直樹 星岡 明
- 出版者
- 一般社団法人 日本アレルギー学会
- 雑誌
- アレルギー (ISSN:00214884)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.8-9, pp.1325, 2009-09-30 (Released:2017-02-10)
1 0 0 0 OA 藤澤東畡と七絃の琴 -その琴系及び弾琴、琴学、琴事の実像について
- 著者
- 山寺 美紀子
- 出版者
- 関西大学東西学術研究所
- 雑誌
- 関西大学東西学術研究所紀要 (ISSN:02878151)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, pp.139-165, 2016-04-01
Fujisawa Togai (1794‒1864) -founder of the Chinese studies academy Hakuen Shoin and responsible for the revival of the Confucian school of Ogyu Sorai-loved the music of the seven-stringed Chinese qin, as Sorai had before him, and was also known during his day as a master of playing the instrument. This paper reports the following research and analysis in an effort to clarify the historical facts surrounding Togai’s relationship with the qin. In the first section, there is a brief discussion of the lineage of qin-playing to which Togai belonged, and of Sorai’s study of the qin, which probably influenced Togai. The second section traces Togai’s connections, through the qin, with contemporaries such as Chokai Setsudo, Abe Kenshu, Sogo Setsudo, Nomura Kosetsu, Kogaku Yushin, and Mega Yusho. The third section uses qin scores and books on the qin in the collection of Hakuen Shoin to specify the pieces that Togai probably studied and played (about thirty in all) and to speculate on what he might have learned from the literature on the qin that he read and consulted (including Ogyu Sorai’s writings on the qin). Finally, in the fourth section, Togai’s essays, “Kogetsu kinki” and “Kinkai ki”, are scrutinized for what they reveal about the events and gatherings related to the qin that Togai engaged in with his teacher and fellow players, giving us a glimpse of Togai’s frame of mind and the nature of his friendships mediated through his musical activity.
1 0 0 0 OA メディア・リテラシー尺度の作成に関する研究
- 著者
- 後藤 康志
- 出版者
- 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.Suppl, pp.77-80, 2006-03-20 (Released:2016-08-02)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 1
メディア・リテラシー教育におけるカリキュラム開発の基礎的データを提供するためのメディア・リテラシー尺度を,メディア操作スキル,批判的思考,主体的態度の3つを下位尺度として作成している.本研究では批判的思考,主体的態度についての項目を作成し,信頼性と妥当性を検討した.結果として次の2点が明らかになった.(1)IT相関分析,GP分析,信頼性係数の分析から,作成した尺度は一定の信頼性をもつ.(2)主体的態度が高い者はインターネットを「速報性があり,正確で,簡便で,好む」のに対し,そうでない者はテレビに依存する傾向があるなど,先行研究の知見と合致する結果が得られ,尺度の妥当性が示唆された.さらに,今後尺度の信頼性・妥当性を高めるための課題についても検討する.
1 0 0 0 OA PH073 解離的対処行動尺度の作成 : 信頼性と妥当性の検討(臨床,ポスター発表H)
- 著者
- 廣澤 愛子 大西 将史 岸 俊行
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 日本教育心理学会総会発表論文集 第57回総会発表論文集 (ISSN:21895538)
- 巻号頁・発行日
- pp.727, 2015-08-19 (Released:2017-03-30)
- 著者
- 角山 朋子
- 出版者
- 埼玉大学大学院文化科学研究科
- 雑誌
- 博士論文(埼玉大学大学院文化科学研究科(博士後期課程)
- 巻号頁・発行日
- 2016
【序論】1. 研究の目的と背景 1.1. 研究目的・・・・・1 1.2. 研究背景・・・・・22. 研究の意義・・・・・33. 先行研究の問題点 3.1. ウィーン工房研究・・・・・4 3.2. オーストリア工作連盟研究・・・・・6 3.3. 「世紀末ウィーン」後の研究・・・・・7 3.4. 日本におけるオーストリア・デザイン史研究・・・・・7 3.5. 先行研究の課題・・・・・84. 研究の方法、構成 4.1. 研究の方法・・・・・9 4.2. 考察対象 4.2.1. 用語について・・・・・9 4.2.2. 考察対象・・・・・10 4.3. 研究の構成・・・・・13【本論】1. オーストリア近代デザイン運動の胎動 1.1. 英国アーツ・アンド・クラフツ運動:20世紀初頭までの変遷・・・・・16 1.2. ウィーンへのアーツ・アンド・クラフツ運動の伝播 1.2.1. ヨーロッパ対六の装飾芸術運動:アール・ヌーヴォー、ユーゲントシュティール・・・・・24 1.2.2. ウィーンのける諸外国の動向の欠落・・・・・26 1.2.3. アルトゥール・スカラによるイギリス工芸の導入・・・・・28 1.2.4. ウィーン美術工芸協会の反発・・・・・32 1.3 第一期デザイン改革:アイテルベルガ―と帝国立オーストリア芸術産業博物館 1.3.1. ハプスブルク君主国の工業化と経済成長・・・・・36 1.3.2. アイデルベルガ―による芸術産業博物館設立の献言・・・・・38 1.3.3. 帝国立オーストリア芸術産業博物館の開館・・・・・40 1.4 第二期デザイン改革:ウィーン分離派による芸術刷新 1.4.1. 「7人クラブ」:近代芸術運動の萌芽・・・・・48 1.4.2. ウィーン造形芸術家協会の内部抗争:ウィーン分離派結成の経緯・・・・・51 1.4.3. ウィーン分離派の芸術理念・・・・・56 1.4.4. 「一つのオーストリア」を目指して・・・・・592. ウィーン工房誕生の布石:ウィーン分離派によるクンストゲヴェルベシューレ改革・・・・・67 2.1. 1900年以前のクンストゲヴェルベシューレにおける工芸教育の変遷 2.1.1. 1867年制定の学校規則・・・・・68 2.1.2. 1872年の改訂版学校規程及び教育計画:予備課程の強化・・・・・69 2.1.3. 1877年の再改定版学校規程及び教育計画:芸術教育の重視・・・・・71 2.1.4. 1888年の改訂版学校規則:模写と様式学習の継続・・・・・73 2.2. 芸術産業博物館の近代化:クンストゲヴェルベシューレ改革の素地 2.2.1. スカラとウィーン美術工芸協会の主導権争い・・・・・75 2.2.2. 1898年制定の芸術産業博物館規約:創造的工芸家の養成・・・・・76 2.2.3. 文化教育省の文化政策:「芸術評議会」の開設・・・・・78 2.2.4. 博物館理事会でのオットー・ヴァグナーの学校改革に関わる提言・・・・・79 2.2.5. スカラの現実的構想・・・・・82 2.3. ウィーン分離派によるクンストゲヴェルベシューレ改革 2.3.1. 教師陣の交替・・・・・85 2.3.2. 授業の課題と改善・・・・・863. ウィーン工房の設立構想とその初期理念:1990-1906年 3.1. 設立までの出来事 3.1.1. ヘルマン・バールによる「芸術と工芸を結ぶ組織」の提案・・・・・89 3.1.2. 第8回ウィーン分離派展(1990)の成果 3.1.2.1. 幾何学的ユーゲントシュティールの確立と成功・・・・・90 3.1.2.2. アシュビーとギルド・オブ・ハンディクラフトからの影響・・・・・94 3.1.2.3. マッキントッシュとの関係・・・・・96 3.1.3. 設立前年の動き:ヴェルンドルファーの貢献・・・・・99 3.2. 組織形態 3.2.1. 1903年5月の設立規約、登記簿登録、及び最初の営業許可書・・・・・104 3.2.2. 『ウィーン工房作業綱領』(1905)に書かれた理念と理想・・・・・105 3.2.3. 「協同組合」という選択・・・・・108 3.3. 幾何学的ユーゲントシュティール 3.3.1. 装飾の抑制・・・・・112 3.3.2. ビーダマイヤー・・・・・115 3.3.3. 高級工芸品としてのウィーン工房製品・・・・・1164. 理想と経営のはざまで:1907年以降とウィーン工房の企業化とデザイン特性の変化 4.1. ウィーン工房の経営体質(1903-1932) 4.1.1. アーツ・アンド・クラフツ運動と経済性:イギリス、ドイツにおける実践・・・・・118 4.1.2. 資金提供者兼経営責任者の変遷・・・・・120 4.1.3. 企業形態の変遷 4.1.3.1. 子会社、合名会社の設立・・・・・121 4.1.3.2. 「有限会社ウィーン工房」への移行(1914):有限会社化とヴェルンドルファーの離脱・・・・・122 4.1.3.3. 庇護から合理化へ(1914-1932):プリマヴェーシ、グノーマンの経営時代・・・・・125 4.2. 1907年の経営危機とモーザーの離脱 4.2.1. ヴェルンドルファーへの資金依存・・・・・128 4.2.2. ディータ・モーザーへの援助要請をめぐるモーザーとヴェルンドルファーの対立・・・・・130 4.2.3. モーザーの主張 4.2.3.1. 個人資産に依拠する経営への批判・・・・・132 4.2.3.2. 方針転換の提言・・・・・132 4.2.3.3. 顧客側の問題・・・・・133 4.2.3.4. ホフマンとの関係・・・・・134 4.3. 1907年の大転換:デザインにみる経営戦略 4.3.1. 中心デザイナーの変化:ホフマン=モーザー体制から複数メンバーの活躍へ・・・・・135 4.3.2. 新たなデザイン様式:装飾の復活 4.3.2.1. 背景・・・・・137 4.3.2.2. 金属工芸・・・・・139 4.3.2.3. グラフィック作品・・・・・141 4.3.3. 事業の拡大 4.3.3.1. 販売店、支店・・・・・142 4.3.3.2. 外部企業との連携:製陶会社「ウィーン陶器」・・・・・145 4.3.3.3. 「キャバレー・フレーダーマウス」(1907):新設部門への活力・・・・・1465. 「ウィーン工房」のブランド確立へ:帝都の美術工芸を担う 5.1. ウィーン分離派の決裂(1905):芸術様式と商業性をめぐる立場の相違 5.1.1. クリムト・グループの離脱・・・・・150 5.1.2. 対立要因:ギャラリー・ミートケ、ウィーン工房への批判・・・・・152 5.1.3. 妥協案の頓挫とクリムト・グループの声明・・・・・153 5.2. <クンストシャウ1908>にみる「総合芸術」の新たな展開 5.2.1. 展覧会の構想・・・・・155 5.2.2. 公的支援の獲得・・・・・157 5.2.3. 希薄な政治性・・・・・158 5.2.4. ウィーン工房展示室に現れた商業的要素 5.2.4.1. 展覧会の会場構成・・・・・161 5.2.4.2. クリムトの作品販売意欲・・・・・163 5.2.4.3. ウィーン工房展示室・・・・・165 5.3. 「国家的理由から」:オーストリア工作連盟の設立(1912) 5.3.1. ウィーンの産業振興部局:工作連盟以前の産業促進会議・・・・・170 5.3.2. ドイツ工作連盟(1907)への参加・・・・・171 5.3.3. オーストリア・グループの独立 5.3.3.1. 活動概要・・・・・174 5.3.3.2. 多民族国家のアイデンティティ・・・・・175 5.3.3.3. 春季オーストリア工芸展(1912)にみるオーストリア工芸の多様性・・・・・178 5.3.3.4. 大規模な出発・・・・・181 5.4. 「ウィーンらしさ」への立脚:1910年代前半の産業活性化の理想と現実 5.4.1. オーストリア工作連盟の活動目的・地域・・・・・184 5.4.2. 国民経済への視点・・・・・185 5.4.3. 理想からの乖離・・・・・187 5.4.4. アドルフ・ロースの工作連盟批判・・・・・190 5.5 オーストリアのアイデンティティとは:ケルンでの工作連盟展(1914) 5.5.1. オーストリア・グループの団結・・・・・193 5.5.2. オーストリア・パヴィリオンの独自性 5.5.2.1. 一般展示室、ウィーン工房展示室、オーストリアの装飾文化の披露・・・・・195 5.5.2.2. オーストリア・パヴィリオンの建築的特徴・・・・・197 5.5.3. オーストリア・パヴィリオンの成果・・・・・1996. 第一次世界大戦下のウィーン工房:女性メンバーの躍進と国家協力 6.1. 「芸術家工房」(1916)における美的工芸品製作 6.1.1. 工作連盟運動の失速:ウィーン工房の主導的立場の継続・・・・・201 6.1.2. 「芸術家工房」開設:低迷する生産と経営の救済策・・・・・202 6.1.3. 芸術家工房の主要女性メンバー 6.1.3.1. フェリーツェ・リックス・・・・・205 6.1.3.2. マリア・リカルツ・・・・・208 6.1.3.3. マティルデ・フレーグル・・・・・209 6.1.3.4. ヒルデ・イェッサー・・・・・210 6.1.4. 陶器作品の新傾向 6.2. モード領域の成長:テキスタイル部門、モード部門での女性メンバーの活動 6.2.1. 1900年代のテキスタイル生産・・・・・214 6.2.2. 1910年代の女性メンバーによるテキスタイルデザインとポール・ポワレへの影響・・・・・215 6.2.3. モード部門の女性メンバーの製作領域、作風 6.2.3.1. マリア・リカルツによるモード画・・・・・219 6.2.3.2. 戦時下のモード画集:『モード・ウィーン』(1914-1915)、『婦人の生活』(1916)・・・・・221 6.3. 女性デザイナー養成拠点:ホフマンとチゼックによるデザイン教育の意義 6.3.1. 応用芸術教育と女性・・・・・224 6.3.2. ヨーゼフ・ホフマンの建築専門クラス:他領域の工芸制作の実践・・・・・225 6.3.3. フランツ・チゼックの装飾形態学クラス:「感覚のリズム化の訓練」 6.3.3.1. 女性メンバーの作風とペッヒェ、ホフマンの作風の関係・・・・・228 6.3.3.2. チゼックの独自性と世紀転換期デザイン教育の継承・・・・・229 6.3.3.3. 教育成果:自由な感性の発露・・・・・231 6.4. 国家協力と経営努力 6.4.1. 中立国での販売促進運動・・・・・234 6.4.2. 「オーストリア的」工芸における民族的表現の欠如・・・・・237 6.4.3. ウィーン工房側の利点・・・・・2397. 1920年代から終焉まで:装飾的デザインと変貌する国家、社会との距離 7.1. 新共和国のデザインの方向性をめぐる混乱と対立 7.1.1. オーストリア工作連盟の再出発:工芸活動の継続・・・・・241 7.1.2. <クンストシャウ1920>展の審美的世界・・・・・242 7.1.3. ホフマンとウィーン工房のオーストリア工作連盟脱退・・・・・247 7.2. 終戦直後のウィーン工房再建過程:ドイツへの接近と企業的性格の強化 7.3. 現代産業装飾芸術国際博覧会(1925)への参加 7.3.1. パリの「アール・デコ」・・・・・254 7.3.2. オーストリアの出展作品 7.3.2.1. オーストリア・パヴィリオン・・・・・255 7.3.2.2. グラン・パレ・・・・・257 7.3.3. ホフマンとウィーン工房に対する批判 7.3.3.1. ウィーン工房の展示状況・・・・・258 7.3.3.2. 商業面、芸術面での不首尾・・・・・259 7.3.4. 博覧会に見るオーストリアのアール・デコの特徴とウィーン工房の出展意義・・・・・262 7.4. ブランド・イメージとしての装飾 7.4.1. 1926年移行の提携企業の拡大:統一的企業イメージの必要性・・・・・264 7.4.2. 装飾的デザイン対する批判の高まり・・・・・265 7.4.3. 根本的な議論の不在・・・・・268 7.5. 最後の5年間:芸術性の維持と経営合理化 7.5.1. ウィーン工房設立25周年(1928)・・・・・271 7.5.2. 1928-1929年の経営業績の回復 7.5.2.1. 組織の中央集権化・・・・・273 7.5.2.2. 外国企業及び外国市場の重要性・・・・・274 7.5.3. ウィーン工房の終焉・・・・・276【結論】1. オーストリア近代デザイン運動の基盤:産業・芸術・国家の近代化・・・・・2782. デザイン企業への転換:デザインの商品価値・・・・・2803. 近代デザイン運動団体のブランドへの変容・・・・・2814. ウィーン工房と「装飾」・・・・・2835. ウィーン工房のデザイン史上の意義と今日性・・・・・283【資料編】図版図版出典年表文献目録
1 0 0 0 OA 防災都市づくり計画の活用と地域防災計画・都市計画マスタープランとの連携の実態に関する研究
- 著者
- 佐藤 雄哉
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.2, pp.237-244, 2019-10-25 (Released:2019-10-28)
- 参考文献数
- 9
本研究は、防災都市づくり計画の活用実態を把握している。また、防災都市づくり計画の記述内容を地域防災計画や都市計画マスタープランの記述内容と比較した。本研究では以下のことが明らかになった。現在、防災都市づくり計画は27計画策定されており、21計画が公表されていた。6計画は都市計画区域外も計画対象区域としていたが、15計画は都市計画区域内しか計画対象区域としていなかった。袋井市では、都市計画マスタープランの見直しと同時に防災都市づくり計画も策定されており、連携が図られていた。
- 著者
- 朝倉 徹
- 出版者
- 日本大学教育学会
- 雑誌
- 教育學雑誌 (ISSN:02884038)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, pp.140-150, 2000