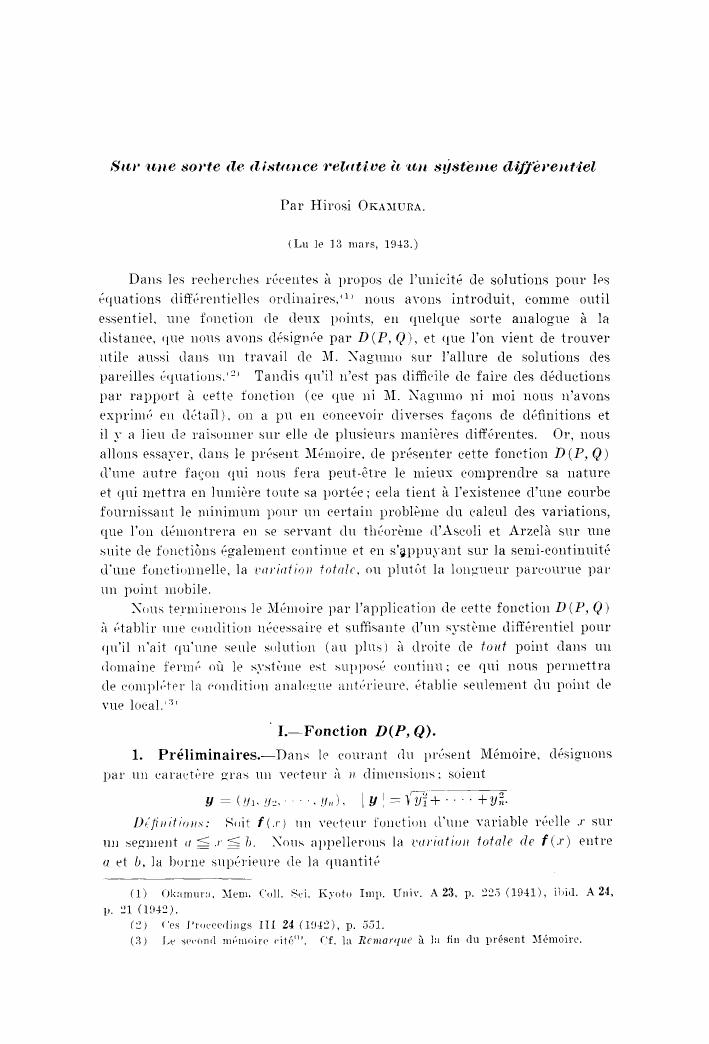1 0 0 0 福島原発事故から6年の現実
- 著者
- 佐久間 順
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.4, pp.230, 2017
1 0 0 0 OA <論説>クィルダルの葬送 : 『モンゴル秘史』に見える一事件について
- 著者
- 原山 煌
- 出版者
- 史学研究会 (京都大学文学部内)
- 雑誌
- 史林 = THE SHIRIN or the JOURNAL OF HISTORY (ISSN:03869369)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.3, pp.384-403, 1974-05-01
個人情報保護のため削除部分あり
1 0 0 0 ピアノ教師向け悪癖発見支援システムの設計と実装および評価
- 著者
- 松井 遼太 長谷川 麻美 竹川 佳成 平田 圭二 柳沢 豊
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.4, pp.789-797, 2020-04-15
本稿では,ピアノ演奏時の悪癖アノテーション機能を持つ,ピアノ教師向け悪癖発見支援システムの構築について述べる. ピアノ演奏者にとって正しい指使いを身につけることは,高度な演奏技術を修得するうえで必須となる. 指使いは身体や運動に依存するため,個人の体格や弾き方に影響されやすい.そのため,演奏者が誤った指使いを身につけた場合,指使いは悪癖として定着しやすく,定着後に修正することが難しい.したがってピアノ教師は,生徒の指使いに関する悪癖を発見し,指導する. しかし,生徒に悪癖があっても上手に演奏できている場合もあり,教師が一聴しただけでは悪癖の発見が難しい.一方,悪癖を視覚的に判断する手段も存在するが,演奏時の手指の動きは素早いため,教師は実時間で単方向から見ただけでは生徒の悪癖を見逃してしまう. そこで,提案システムは生徒の演奏を3視点から撮影した映像それぞれをコマ送り再生できる機能,打鍵間隔や打鍵の強さを可視化する機能を持つ.これにより,教師は単に映像を見るよりも効率良く生徒の悪癖を発見できる.また,提案システムは深層学習を用いた悪癖アノテーション機能により,演奏中に悪癖がある箇所を推定し,教師の見逃しを防止できる. 一般的な動画再生機能を持つツールを使用した従来手法群と,提案システムを使用した提案手法群を比較した評価実験の結果,提案手法群が悪癖発見に役立つことが示唆された.
1 0 0 0 OA 12 台湾におけるQ版神仙ブームとその背景 -信仰文化の商品化と消費をめぐる一考察-
- 著者
- 志賀 市子 Shiga Ichiko
- 出版者
- 神奈川大学 国際常民文化研究機構
- 雑誌
- 国際常民文化研究叢書3 -東アジアの民具・物質文化からみた比較文化史-=International Center for Folk Culture Studies Monographs 3 -Comparative Cultural History from the Perspective of East Asian Mingu and Material Culture-
- 巻号頁・発行日
- pp.151-167, 2013-03-01
本稿は2000年代の台湾において一種のブームとなっているQ版神仙のキャラクター商品に注目し、ブームの背景の分析を通して、台湾における信仰文化の商品化と消費をめぐる社会状況についての考察を試みるものである。Q版神仙のQは、英語のcute(キュート、かわいい)の諧音(発音をもじったもの)であり、Q版神仙とは、日本の漫画やアニメのキャラクターに見られるような「かわいい」形象に変身させた神仙キャラクターを指す。近年台湾の寺廟では、より多くの参拝客を呼びよせるために廟内に土産物ショップを設け、Q版神仙の公仔(フィギュア)やその携帯ストラップ、帽子、Tシャツなど、さまざまな商品を販売するところが増えてきている。本稿ではまずQ版神仙ブームがいつ頃から、どのような背景のもとに興ってきたのかを、一つはコンビニエンスストア競争が巻き起こしたブームから、もう一つは台湾政府が推し進める文化創意産業計画との関連から論じた。次に台湾中部の媽祖廟を事例として、Q版媽祖のキャラクター商品がどのように開発され、販売されているのか、その実態を明らかにした。最後に台中県の著名な媽祖廟、大甲鎮欄宮を事例として、近年の進香活動に見る新たな展開や信者層の変化に注目し、Q版神仙商品の売れ行きとの関連性について検討した。また結論部分では、台湾のローカルな文化とグローバルな形象をミックスさせたQ版神仙は、21世紀の台湾における新しい文化創出のひとつであると指摘した。
1 0 0 0 OA フラクタル次元を用いた人間行動動線の定量的分析
- 著者
- 横山 秀史 永田 茂 山崎 文雄 片山 恒雄
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 土木学会論文集 (ISSN:02897806)
- 巻号頁・発行日
- vol.1992, no.450, pp.181-187, 1992-07-20 (Released:2010-08-24)
- 参考文献数
- 20
緊急時の人間行動を定量化するための指標として, 動線のフラクタル次元を用いることを提案し, 迷路を用いた被験者実験の結果と, 過去の火災事例に適用して有用性を検討した. その結果, フラクタル次元が, 脱出時間, 歩行距離, 行動範囲などで評価できない人間行動の複雑さの度合を定量的に表していることがわかった.
1 0 0 0 OA 臨床心理面接におけるカウンセラーの効果的な自己開示 ―クライエントの期待という視点から―
- 著者
- 鈴木 孝 佐々木 淳
- 出版者
- 日本カウンセリング学会
- 雑誌
- カウンセリング研究 (ISSN:09148337)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.3, pp.145-156, 2019-02-28 (Released:2020-10-06)
- 参考文献数
- 25
臨床心理面接にて,カウンセラー(以下,Co.)がクライエント(以下,Cl.)に対して自己開示をする効果が指摘されており,多くのCo. が自己開示を使用している。その効果については実証研究が蓄積されてきた。しかし,どのような自己開示をCl. が求めているか,そしてCo. がその期待にどう応じるのかは明らかにされていない。そこで本研究では,Co. の自己開示について,Cl. の期待とCo. の実際の応答との差異を検討することを目的とした。心理援助職14名(Co. 役)と大学生53名(Cl. 役)を対象に,Cl. がCo. に自己開示を求めた仮想事例を提示し,Co. 役には自身がすると予想する応答を,Cl. 役には自身がCo. に求める応答を回答させた。Co. の気持ちの開示を求めた仮想事例では,傾聴に徹することが両者に共通する応答として見いだされた。一方で,Co. の見立ての開示を求めた仮想事例では,Cl. 役は解決策の開示を期待したのに対し,多くのCo. 役が解決策を提示しないと予想した。Cl. の期待とCo. の応答が異なる点について,面接における時間軸の観点から考察し,Co. に求められる姿勢を論じた。
- 著者
- Hirosi OKAMURA
- 出版者
- THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN , The Mathematical Society of Japan
- 雑誌
- Nippon Sugaku-Buturigakkwai Kizi Dai 3 Ki (ISSN:03701239)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.514-523, 1943 (Released:2009-06-09)
1 0 0 0 OA とかちマダニじてん
共同利用・共同研究拠点事業「マダニバイオバンク整備とベクターバイオロジーの新展開」(通称マダニプロジェクト)(平成29年度~平成33年度)http://www.obihiro.ac.jp/~protozoa
1 0 0 0 IR 労働者代表選出制度と団結権保障 : ILOにおける労働者代表制度から
- 著者
- 大和田 敢太
- 出版者
- 滋賀大学
- 雑誌
- 滋賀大学経済学部研究年報 (ISSN:13411608)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.25-51, 2007
- 著者
- 井部 正之
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経エコロジー (ISSN:13449001)
- 巻号頁・発行日
- no.106, pp.108-111, 2008-04
「海上の2つの訴訟では、全国で初めてというのが1つ、全国2件目というのが1つあり、全国から注目されています」 これらの訴訟は同県の旧海上町(旭市)と銚子市、東庄町の1市2町にまたがる場所に建設を予定している産業廃棄物の管理型処分場を巡って起こされたものだ。2つの訴訟とは、事業者のエコテック(千葉市)に対する処分場の建設差し止め訴訟と、設置許可を出した千…
1 0 0 0 OA 女子再発性尿路感染症と下部尿路機能
- 著者
- 小柳 知彦 石川 登喜治
- 出版者
- 社団法人 日本泌尿器科学会
- 雑誌
- 日本泌尿器科學會雑誌 (ISSN:00215287)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.1, pp.67-74, 1973 (Released:2010-07-23)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 1 1
153 female patients with recurrent urinary infection were seen between July 1971 and December 1971 at the Urology clinic of the Hokkaido University Hospital. The age distribution was from 2 year-to 76 year-old. 25 cases harbored well explicable underlying conditions for recurrent infection. Other 128 cases required more detailed functional studies to explain its pathogeneses and to outline the proper treatment. Distal urethral stenosis, the majority of which was found in women over 50 year old, was thought to be etiologically significant in only 12% of the cases. Faulty voiding habit either by infrequent voiding or by frequent holding of the urge to void, was the primary cause of recurrence in 48%. Latent uninhibited ngB was found in 10%. Success rate in the prevention of recurrence was increased by the regimen of frequent voiding among infrequent voiders and by the concommitant administration of anticholinergic in patients with uninhibited ngB. The role of hydrostatic pressure must be a significant factor in patients with recurrent urinary infection.
- 著者
- 穂積 謙吾
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集 2020年度日本地理学会秋季学術大会
- 巻号頁・発行日
- pp.131, 2020 (Released:2020-12-01)
水産物の安定供給に向け養殖業への期待が高まる中、全国的な養殖生産は縮小傾向にある。しかし一部地域では養殖生産が活発であり、そこでは養殖業者による何らかの特徴的な経営戦略が講じられていると考えられる。 養殖業者の経営戦略について従来の地理学では、養殖業者すなわち生産主体にのみ焦点を当てられてきた(前田2018など)。これに対して、生産主体の動向を流通主体と関連付けて分析する必要性が指摘されている(林2013など)。実際に漁業経済学では、養殖魚を産地で一括集荷し、消費地へと一括出荷する中間流通業者の重要性や、養殖業者と中間流通業者の間の密接な取引関係に注目されている(濱田2003など)。 そこで本研究では、養殖業の主要産地である愛媛県宇和島市のうち宇和島地区を事例に、中間流通業者との取引関係から見た養殖業者の経営戦略を明らかにした。本研究の遂行に際しては、宇和島地区で活動を行う中間流通業者6社および養殖業者16経営体に対してのヒアリング調査を2019年8月〜10月に実施した。 宇和島地区においては、中間流通業者10数社および養殖業者31経営体が活動を行っている。宇和島地区のみならず宇和島市における中間流通業者の基本的な役割は、養殖業者に餌料を販売するとともに、その見返りとして養殖業者の生産した養殖魚を買い取り、主に卸売市場へ出荷することである。また、自社の販売するブランド品の生産(以下、業者ブランド品)を、特定の養殖業者に委託する中間流通業者も見られる(竹ノ内2011など)。 ヒアリング調査の結果、以下の3つの生産・出荷の形態が確認された。 第一に、市場流通で取り扱われる養殖魚を生産し、餌料購入先の中間流通業者に対して出荷する形態である。市場流通向けの養殖魚の買取価格は不安定な市況動向を受け日々変動するため、養殖業者においては事業収入を増加させるための戦略が取られている。具体的には、取引関係のある中間流通業者より市場での養殖魚の売れ行きに関する情報を取得し、それを踏まえた生産・出荷調整を行う養殖業者が見られた。また、中間流通業者と買取価格に関する交渉を行い、養殖魚の供給が不足している場合には市況より高値で養殖魚を販売する養殖業者も見られた。 第二に、中間流通業者による委託を受け業者ブランド品を生産する形態である。中間流通業者より一定の評価を受けた養殖業者は業者ブランド品の生産を委託されているが、業者ブランド品は市場外流通で取り扱われるため、買取価格は市況動向の影響を受けず一定である。従って業者ブランド品の生産により、安定した事業収入を確保できる。 第三に、養殖業者自身で商品開発と販路開拓を行った独自ブランド品を生産する形態である。業者ブランド品と同様に市場外流通で取り扱われる独自ブランド品も価格が一定であるため、独自ブランド品の生産により事業収入の安定化が可能となる。なお、独自ブランド品の生産に際しては自社製造もしくは独自に仕入れた餌料を使用しており、中間流通業者より餌料を殆ど購入していないため、この形態においては中間流通業者との関係性は希薄である。 各々の養殖業者における3つの生産・出荷形態の選択および組み合わせと、養殖業者の労働力規模との間には関連性が確認された。具体的には、市場流通向けの養殖魚のみを生産しているのは12経営体、独自ブランド品も生産しつつも市場流通向けの養殖魚を中心に生産しているのは1経営体である。これらの養殖業者の多くは従業者数が2〜4名と比較的小規模である。そのため、厳格な品質管理や通年の出荷など多大な負担を要するブランド品の生産には消極的であり、生産の負担が比較的少ないものの買取価格が不安定な市場流通向けの養殖魚に特化するとともに、その中で事業収入を高めようとする動きが見られた。一方、他の3経営体は業者ブランド品もしくは独自ブランド品を中心に生産している。これらの養殖業者は、従業者数が5〜10名と比較的大規模であり、品質管理や通年出荷への労働力配分が可能となっている。そこで事業収入の安定化を図るべく、負担は大きいものの価格が安定するブランド品を生産していた。 このように宇和島地区の養殖業者は、自らの経営資源に合わせながら、中間流通業者との取引関係を活用して事業収入を増大もしくは安定化させ、不安定な市況動向への対応を図っていると考えられる。竹ノ内徳人2011.産地流通業者による養殖マダイ価値創造に向けた取り組み.地域漁業研究51(3):67-84.濱田英嗣2003.『ブリ類養殖の産業組織 - 日本型養殖の展望』成山堂書店.林紀代美2013.水産物流通研究における研究動向と今後の課題.金沢大学人間科学系研究紀要5:1-34.前田竜孝2018.愛知県西尾市一色町における養鰻生産者の関係性とその変化.人文地理70(1):73-92.
1 0 0 0 IR 司法の立ち位置ということ(1)伊方3号機広島高裁抗告審決定に寄せて
- 著者
- 安念 潤司
- 出版者
- 中央ロー・ジャーナル編集委員会
- 雑誌
- 中央ロー・ジャーナル (ISSN:13496239)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.3, pp.127-146, 2018-12
火山噴火についての基礎的知識を整理した後、伊方原発3号機について火山影響評価がどのようになされたかを概観したもの。
- 著者
- Takeo Imai Katsuhiko Taguchi Yoko Ogawara Daijiro Ohmori Fumiyuki Yamakura Hidenori Ikezawa Akio Urushiyama
- 出版者
- The Japanese Biochemical Society
- 雑誌
- The Journal of Biochemistry (ISSN:0021924X)
- 巻号頁・発行日
- vol.130, no.5, pp.649-655, 2001 (Released:2008-11-18)
- 参考文献数
- 32
An extremely thermostable [4Fe-4S] ferredoxin was isolated under anaerobic conditions from a hyperthermophilic archaeon Thermococcus profundus, and the ferredoxin gene was cloned and sequenced. The nucleotide sequence of the ferredoxin gene shows the ferredoxin to comprise 62 amino acid residues with a sequence similar to those of many bacterial and archaeal 4Fe (3Fe) ferredoxins. The unusual Fe-S cluster type, which was identified in the resonance Raman and EPR spectra, has three cysteines and one aspartate as the cluster ligands, as in the Pyrococcus furiosus 4Fe_ferredoxin. Under aerobic conditions, a ferredoxin was purified that contains a [3Fe-4S] cluster as the major Fe-S cluster and a small amount of the [4Fe-4S] cluster. Its N-terminal amino acid se-quence is the same as that of the anaerobically-purified ferredoxin up to the 26th residue. These results indicate that the 4Fe ferredoxin was degraded to 3Fe ferredoxin during aerobic purification. The aerobically-purified ferredoxin was reversibly converted back to the [4Fe-4S] ferredoxin by the addition of ferrous ions under reducing conditions. The anaerobically-purified [4Fe-4S] ferredoxin is quite stable; little degradtion was observed over 20 h at 100°C, while the half-life of the aerobically-purified ferredoxin is 10h at 100°C. Both the anaerobically-and aerobically-purified ferredoxins were found to function as electron acceptors for the pyruvate-ferredoxin oxidoreductase purified from the same archaeon.
1 0 0 0 思春期病棟における強迫性障害の入院治療
- 著者
- 関谷 秀子
- 出版者
- 日本精神分析学会
- 雑誌
- 精神分析研究 (ISSN:05824443)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.2, pp.166-174, 2008-04-25
- 参考文献数
- 4
1 0 0 0 男性と付き合いたいが付き合えない青春期女性の精神療法
- 著者
- 関谷 秀子
- 出版者
- 日本精神分析学会
- 雑誌
- 精神分析研究 (ISSN:05824443)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.1, pp.74-78, 2003-02-25
- 参考文献数
- 9
1 0 0 0 OA 力士梅ケ谷一代記
- 著者
- 田中霜柳子 (順次郎) 著
- 出版者
- 名倉亀楠
- 巻号頁・発行日
- 1892
1 0 0 0 OA パリ : 誕生から現代まで(XVI)
- 著者
- クールティヨン P. 金柿 宏典 Kanagaki Hironori
- 出版者
- 福岡大学研究推進部
- 雑誌
- 福岡大学人文論叢 = Fukuoka University Review of Literature & Humanities (ISSN:02852764)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.3, pp.1041-1065, 2006-12
1 0 0 0 OA 国内外における一般向け医薬品等情報システムの現状とその取り組み
- 著者
- 山本 美智子
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)
- 巻号頁・発行日
- vol.141, no.3, pp.393-402, 2021-03-01 (Released:2021-03-01)
- 参考文献数
- 21
With the progress of medical treatment, information on drugs, etc. is overflowing on the media and the Internet, and some of them are leading to uncertain information for the purpose of profit, and some of them are wrong information or inaccurate information, and the effect on the patient is regarded as a problem. In Japan, information on public pharmaceuticals for patients and consumers is provided on the Internet, but its utilization is not sufficient. In the Pharmaceuticals and Medical Devices Act, it is stated that “Citizens shall endeavor to use pharmaceuticals, etc., properly and deepen their knowledge and understanding of their efficacy and safety”. On the other hand, there is a variety of information available on the Internet, and simply searching does not necessarily lead to reliable information. It is necessary to provide information with a mechanism to ensure that the information is reliable so that it can lead to appropriate medical care. Overseas, medical information infrastructure systems, including highly reliable public pharmaceuticals based on evidence, have been developed. Examples include National Health Service (NHS) in the United Kingdom, MedlinePlus in the United States, and National Prescribing Service (NPS) MedicineWise in Australia. In the era of digital health, it is necessary to discuss issues and prospects for the construction and dissemination of information provision infrastructure that meets the needs of patients and consumers from the perspective of industry, government, academia, and patients.