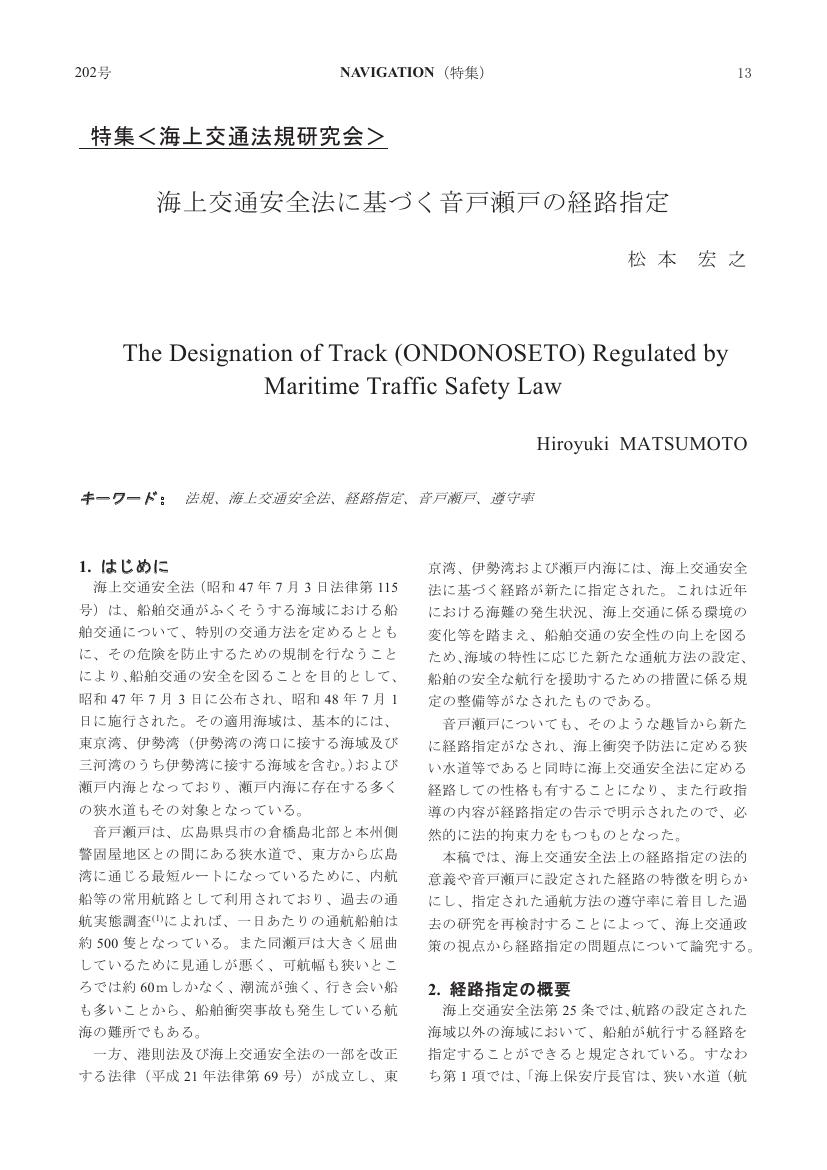<p>ハシボソガラスは,硬い殻に包まれたオニグルミの種子を食べるために,しばしば車に轢かせて割る.この行動は,車という人間の作り出した道具を利用する点で興味深い行動である.しかし,これに関する研究は1990年代に仙台市で研究されて以来行われていない.そこで本研究では,2016年の10–12月に函館市内において,この行動の観察を行い,仙台市で観察された行動と比較した.その結果,仙台市で観察されたクルミ割り行動とはいくつかの違いが見られた.特に大きな違いは設置方法についてであった.仙台では信号に止まった車の前にクルミを置く行動が観察されていた.これはクルミを割るには効率的な方法と思われる.しかし本研究の観察では,ハシボソガラスは電線などの高い所からクルミを落として設置していた.函館市におけるハシボソガラスのクルミ割り行動は仙台市の事例に比較するとまだ効率化が進んでいないと推測された.この違いをもたらす要因として,環境条件およびクルミの状態の違いなどが考えられた.</p>
1 0 0 0 NHKホールパイプオルガン自動演奏装置(予稿なし)
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- テレビジョン学会技術報告 (ISSN:03864227)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.10, 1986
- 著者
- 守屋 淳 三沢 善一郎
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- テレビジョン学会技術報告 (ISSN:03864227)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.5, pp.19-24, 1994
At NHK, we have introduced Simultaneous Program Production using HDTV and NTSC, for public recordings of television musical programs at. NHK Hall. This enable us to produce (record or broadcast) in two different television standards efficiently, using an HDTV OB van system and an HDTV downconverting system. In 1992, we started this simultaneous production at NHK Hall as an addition to previous production facilities. A new OB van was also introduced to this system in August 1993, equipped with an HDTV digital video switcher. Through the operation of this system, we were able to mature our simultaneous production method, and we are recieving satisfactory results.
1 0 0 0 OA 「眠るアリアドネ」 : 原作推定のための古代模刻目録
- 著者
- 大木 綾子 Oki Ayako
- 出版者
- Seminar on History of Art, Graduate School of Comprehensive Human Sciences, University of Tsukuba
- 雑誌
- 藝叢 : 筑波大学芸術学研究誌 = Bulletin of the study on philosophy and history of art in University of Tsukuba (ISSN:02894084)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.65-86, 1996
著作権保護のため、すべての掲載図版に墨消し処理を施しています。
- 著者
- 小郷 直人 鈴木 慎一 濱住 啓之
- 出版者
- 一般社団法人映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会技術報告 (ISSN:13426893)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.9, pp.41-44, 2013-02-13
NHK紅白歌合戦やゴルフ中継などに使用している42GHz帯ミリ波モバイルカメラの伝搬をより安定化,高信頼化させるため,送信,および受信アンテナの検討を行っている.今回,NHKホールにおける運用を考慮して,送信アンテナと受信アンテナについて,ビーム幅が異なるものを設計,試作し,伝搬実験を行うことで比較,評価した.その結果,NHKホールの環境においては,送信アンテナはビーム幅を広くし,受信アンテナはビーム幅を絞ることで伝搬特性が安定することを確認したので報告する.
- 著者
- 鈴木 慎一 小郷 直人 濱住 啓之
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会技術報告 (ISSN:13426893)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.37-40, 2013
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 1
ハイビジョン映像を低圧縮・低遅延で無線伝送する高性能なワイヤレスハイビジョンカメラ「ミリ波モバイルカメラ」は,ゴルフ中継や紅白歌合戦などの様々な番組撮影で使用されている.今回,ミリ波モバイルカメラの安定運用を目的として,復調装置から出力されるFFT演算結果とビタビ復号で訂正したビット数の情報を用いて,伝搬特性および伝送特性を解析するリアルタイム解析システムの開発を行った.本システムは,複数系統の受信信号に応じた受信CNRや遅延プロファイル特性に加え,MIMO多重伝送の伝送特性の把握に必要な送信相関・受信相関などの伝搬特性をリアルタイムで解析し,その解析結果をPCの一画面上で表示することができる.本稿では,本システムの詳細について説明するとともに,本システムを用いて測定したNHKホールの伝搬特性の測定結果について報告する.
1 0 0 0 OA 海上交通安全法に基づく音戸瀬戸の経路指定
- 著者
- 松本 宏之
- 出版者
- 公益社団法人 日本航海学会
- 雑誌
- 日本航海学会誌 NAVIGATION (ISSN:09199985)
- 巻号頁・発行日
- vol.202, pp.13-20, 2017 (Released:2018-05-21)
1 0 0 0 新NHKホールパイプオルガンの音響設計
- 著者
- 望月 広幸
- 出版者
- 一般社団法人 日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.12, pp.738-742, 1973
- 著者
- 折橋 浩司
- 出版者
- 日本フランス語フランス文学会
- 雑誌
- フランス語フランス文学研究 (ISSN:04254929)
- 巻号頁・発行日
- vol.96, 2010
1 0 0 0 マテバシイ樹冠における1枚の葉の代表性について
<B>はじめに</B>樹木は,多数の同じような形をした葉(個葉)によって構成されている。個葉は,その機能的な独立性のため,測定や解析の最小単位として扱われることが多い。しかし,ここで問題になるのは,多くの場合,一枚一枚の葉の機能的なバラつき不明であり,実質的な蒸散・生産能力評価が難しいことである。樹冠において,光合成・蒸散量のある時間における単葉ごとの違い,あるいは樹冠の位置による違いは大きい。その一方で,久米ら(2002)は,数枚の単葉の光合成の日平均値を用いることによって,単木レベルの樹冠蒸散量を高い精度で推定した。このことから,単葉が示す分散特性には時間や位置に依存した特殊性が存在することが伺われるが,理論的根拠は示されていなかった。そこで,樹冠における蒸散・光合成のばらつきを,年間の観測データから解析し,その特性を抽出し,樹冠における1枚の葉がどの程度の代表性を持つのかを明らかにし,何故数枚の単葉の光合成の日平均値によって,樹冠蒸散量を高い精度で推定できるのかを明らかにした。<BR><B>方法</B>対象林分は,九州大学福岡演習林のマテバシイ人工林(22年生)で,平均樹高は9mである。この林分には1998年に微気象観測用と樹冠観察用の2つの観測タワーが建設され,微気象観測用タワーでは,日射・長波放射・気温・相対湿度・風速が高さ別に10分間隔で測定されており,林内には林内雨・樹幹流・土壌水分・樹液流測定用ヒートパルス装置などが測定・設置されている。この樹冠観察用タワーを用いて,マテバシイの樹冠の個葉の光合成・蒸散速度の日変化を2000年7月から2001年7月まで,LI-COR LI-6400を用い,晴天日に10回(日)測定した。測定は,光量子入射量(PAR),CO2濃度,葉面飽差,葉温などが,実際の環境条件にできるだけ近くなるように調節し,葉面の位置や方向の違いが反映されるようにした。樹冠を上層と下層の2層に分け,それぞれの層で3つの別の枝についている葉を,朝から夕方まで1時間から2時間おきに測定した。そして,葉の本来持っている光合成能力のバラツキを測定するために,2001年7月初旬に樹冠頂部で5本の別の樹の枝に付いている葉について,葉内CO2濃度(Ci)と光合成速度(A)の関係(A-Ci曲線),またPARと光合成速度(A)の関係(A-PAR曲線)を測定した。<BR><B>結果及び考察</B> 2000年7月に,樹冠最上層の葉において,A-Ci曲線と,A-PAR曲線を測定した結果,異なる樹木の枝につく葉の間のバラツキは非常に小さかった。従って,個々の葉が本来持っている潜在的光合成能力には大きな差がない。ところが,野外の日変化の過程,特に夏季の晴天日においては,光合成の日中低下の影響で,この関係から大きく外れ,潜在的光合成能力を元にした光合成-蒸散モデルが,夏季においては上手く適合しなかった(過大評価する)。このことは,ペンマン-マンティース式による蒸散量の計算結果との比較においても示された。<BR> ある時間における光合成・蒸散速度の個葉間のバラツキは比較的大きい。これは,(1)葉の向きが様々であり,その位置によってある時間における光の当り方が大きく異なること,(2)午前中に強光が当っていた葉では,午後には光合成の日中低下の影響で午前中に光が当っていなかった葉よりも光合成速度が低下することなどが原因として挙げられる。それにもかかわらず,野外で一日を通して1__から__2時間おきに測定したデータから求められた光合成・蒸散速度の平均値,あるいは日積算値では,個葉間のバラツキは年間を通して小さかった。この理由は,(1)樹冠上部においては,どの位置の葉も太陽の移動のために1日に当る光の量にはあまり大きな差がないこと,(2)日中低下が生じる葉でも,午前中にはかなりの量の光合成を行っており,午後の低下の影響があまり大きくならないこと,(3)樹冠下部においても,日光合成量は上部からの積算葉面積指数の増加に伴ってほぼ同じように減少し,樹冠の同じ層に位置する葉同士では日平均値のバラツキは小さいためであることがわかった。<BR> これらの結果は,マテバシイの樹冠において,一枚の葉の代表性は高く,同時に多くの葉をたくさん測定するよりかは,少数の葉を1日を通して測定するほうが,実際の光合成蒸散量の推定には有効であると同時に,その精度にもかなり信頼性が置けるものであることを示している。また,樹冠内のいくつかの異なった高さ(異なった積算葉面積指数)の位置で測定すれば,より高い精度の推定値を得ることができるであろう。<BR>
1 0 0 0 IR フローベール初期作品群における女性の形象とファム・ファタルの系譜
- 著者
- 大鐘 敦子
- 出版者
- 関東学院大学法学部教養学会
- 雑誌
- 関東学院教養論集 (ISSN:09188320)
- 巻号頁・発行日
- no.29, pp.29-46,
フローベールの初期作品群には、後期のジャンルを超えた大作家になる以前の様々な作品が40 以上もあり、初期をどう捉えるかいくつかの見解がある。こうしたなか、初期作品における女性像は、後期に描かれるファム・ファタル的な女性像と異なり、ロマンティスムに影響をうけた宿命に屈する女性像たちが中心であった。フローベールの初期作品群におけるファム・ファタル的女性像の萌芽はどのようなものだったのだろうか。
1 0 0 0 IR 愛を叫ぶ『新エロイーズ』 -永久にこだまする十八世紀愛の書簡-
- 著者
- Julie Brock ジュリー ブロック
- 巻号頁・発行日
- 2005-03-31
京都工芸繊維大学 工芸学部研究報告 第53巻 人文(2004) pp.39-62ルソーの『新エロイーズ』についての紹介と考察。この小説はフランスにおける恋愛観の歴史を辿る上で見逃せないだけでなく、フランス人、ともすると全ての現代人の心の底流に潜んでいるであろう、「純粋な恋愛」や「情熱的感情」への思慕、或いは人間の中にある「自然的なものとしての道徳への」憧憬を呼び覚ますものが凝縮されている作品として、むしろ現代人にとっては新鮮に捉えることができることが可能かもしれない。本論ではまず、この作品の書かれた時代背景及び作者ルソーの生涯について概観し、次にその着想と構成について述べる。その後、物語のあらすじを紹介し、最後に『新エロイーズイーズ』成功の理由に迫る。
1 0 0 0 OA 『関西大学百年史』の編纂を振り返って(一) -「十年仕事」の来し方行く末
- 著者
- 熊 博毅
- 出版者
- 関西大学年史編纂委員会
- 雑誌
- 関西大学年史紀要 (ISSN:02894009)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.47-62, 1997-03-31
1 0 0 0 IR フランス文学に見る恋愛観 -12世紀から18世紀前半まで-
- 著者
- Julie Brock ジュリー ブロック
- 巻号頁・発行日
- 2004-03-31
フランスの恋愛文学を紹介しながらフランス文化における恋愛観を考察する。第一章では『トリスタンとイゾルテ』を主な題材にして中世の宮廷風恋愛観と恋愛小説の誕生、第二章では、コルネイユの『ル・シッド』とラファイエット夫人の『クレーヴの奥方』を扱い古典的恋愛観、恋愛物語の衰退と再生について、第三章では18世紀前半のアベ・プレヴォーの『マノン・レスコー』を取り上げて、その小説に見られる恋愛観とロマンティスムの源泉を探る。京都工芸繊維大学 工芸学部研究報告 第52巻 人文(2003) pp.161-198
1 0 0 0 「ペ-ル・デュシェ-ヌ」における聖職者批判と非キリスト教化の問題
- 著者
- 柳原 邦光
- 出版者
- 学術雑誌目次速報データベース由来
- 雑誌
- 史学研究 (ISSN:03869342)
- 巻号頁・発行日
- no.186, pp.p63-83, 1990-03
1 0 0 0 OA 人体特異功能の存在とその意義
- 著者
- 宋 孔智
- 出版者
- International Society of Life Information Science
- 雑誌
- 国際生命情報科学会誌 (ISSN:13419226)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.198-214, 1999-03-01 (Released:2019-04-30)
- 参考文献数
- 9
この論文は4つ実験シリーズに基づき、特異功能の存在に関して報告する。第1実験シリーズでは、被験者張宝勝が透明なガラス瓶の中からメタクリル酸樹脂(PMMA)チップを取り出した。ガラス瓶に損壊は見られなかった。第2シリーズでは、実験試料は透明なガラス管に入れられたスプリング形状の長い針金であった。被験者はガラス管から針金を取り出したが、ガラス管は損壊していなかった。第3シリーズでは、我々は試料が容器から出る途中の状態を一連の写真で撮影した。第4シリーズでは、1角紙幣(人民元)が2枚のPMMA板の間に封入された。被験者は紙幣に焼けこげを生じさせ、多数の穴を作ることができた。一連の実験で、すべての試料容器には異常が見られなかった。これらの実験結果は、特異功能に物理的・生理的なメカニズムが存在していることを示唆している。
1 0 0 0 IR 赤色蛍光性複素環化合物の合成--有機EL発光材料の開発
- 著者
- 又賀 駿太郎 五郎丸 英貴 Costea Ion アンドリーセン スヴェン ティーマン ティース 澤田 剛 高橋 和文
- 出版者
- 九州大学機能物質科学研究所
- 雑誌
- 九州大学機能物質科学研究所報告 (ISSN:09143793)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.2, pp.157-164, 2000
- 被引用文献数
- 1
Oxadiazolopyridine compounds have seen synthesized with the aim of preparing red fluorescent organic material for organic electrolum inescent devices. 10-Oxoindenooxadiazolopyridines, which were synthesized from acetophenone derivatives in 4 steps, show red fluorescence in the solid state, albeit with a weak intensity. 10-Hydroxy derivatives emit fluorescence of yellow to orange color, however these compounds are instable in air. Oxadiazolopyridenes having thiophene and furan rings at the 4- and 7-positions, prepared from the corresponding heterocyclic methyl ketones, emit intense red fluorescence above 600nm in the solid state. Of special note is 4,7-di(5'-phenyl-2'-thienyl)oxadiazolopyridine which shows red fluorescence at 669nm. An EL device using 5'-phenyl-2'-thienyl derivative as a light-emitting materials was fabricated by Kyushu Matsushita corporation. This device emitted red EL at 680nm. In the cyclic voltammogram, oxadiazolopyridines show a reversible redox wave at -0.9~-1.17V. The oxadiazolopyridine ring having an electron-withdrawing substituent was reduced at low cathodic potential.
1 0 0 0 OA The Frog in Space (FRIS) Experiment Onboard Space Station Mir: Final Report and Follow-on Studies
- 著者
- Masamichi Yamashita Akemi Izumi-Kurotani Yoshihiro Mogami Makoto Okuno Tomio Naitoh Richard J. Wassersug
- 出版者
- Japanese Society for Biological Sciences in Space
- 雑誌
- Biological Sciences in Space (ISSN:09149201)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.4, pp.313-320, 1997 (Released:2006-02-01)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 11 17
The “Frog in Space” (FRIS) experiment marked a major step for Japanese space life science, on the occasion of the first space flight of a Japanese cosmonaut. At the core of FRIS were six Japanese tree frogs, Hyla japonica, flown on Space Station Mir for 8 days in 1990. The behavior of these frogs was observed and recorded under microgravity. The frogs took up a “parachuting” posture when drifting in a free volume on Mir. When perched on surfaces, they typically sat with their heads bent backward. Such a peculiar posture, after long exposure to microgravity, is discussed in light of motion sickness in amphibians. Histological examinations and other studies were made on the specimens upon recovery. Some organs, such as the liver and the vertebra, showed changes as a result of space flight; others were unaffected. Studies that followed FRIS have been conducted to prepare for a second FRIS on the International Space Station. Interspecific diversity in the behavioral reactions of anurans to changes in acceleration is the major focus of these investigations. The ultimate goal of this research is to better understand how organisms have adapted to gravity through their evolution on earth.
- 著者
- 大槻 忠男
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.1093, pp.el16-19, 2001-05-28
日本企業のリストラはまだまだこれからが本番だと思っている。政府の構造改革がどのような痛みを伴うかにもよるが、やはりあと2年ぐらいはかかるだろう。