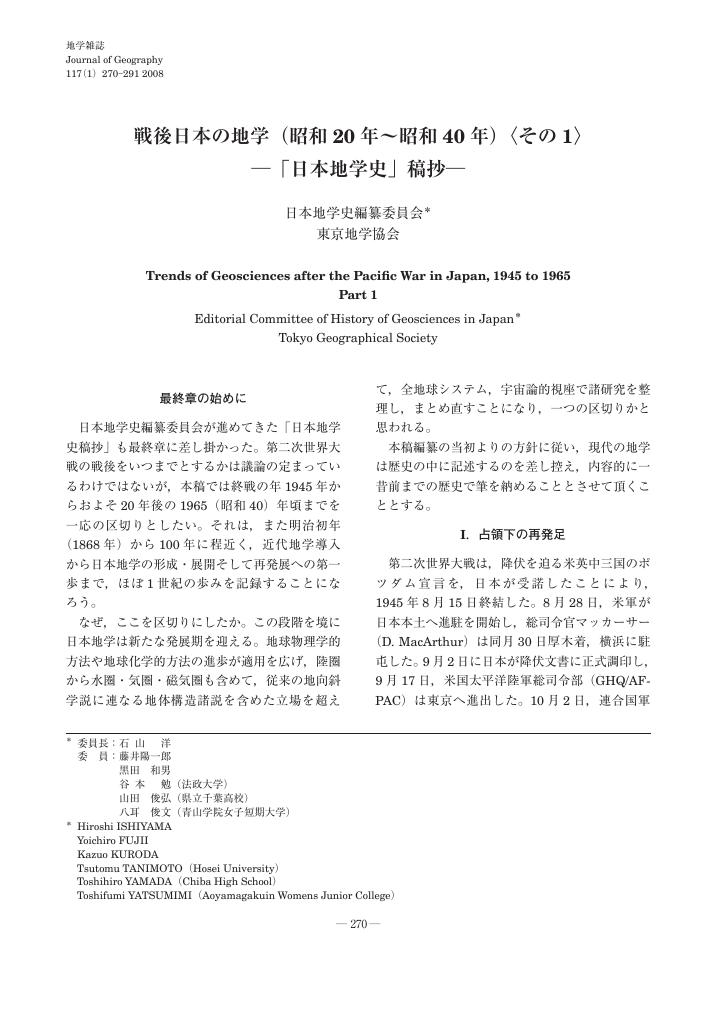1 0 0 0 IR 鹿児島県大隅半島内之浦方言における二型アクセントの痕跡
- 著者
- 髙城 隆一
- 出版者
- 東京大学大学院人文社会系研究科・文学部言語学研究室
- 雑誌
- 東京大学言語学論集 = Tokyo University linguistic papers (TULIP) (ISSN:13458663)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, pp.267-282, 2020-10-31
本稿では、先行研究によって「一型アクセント」であるとされてきた鹿児島県の大隅半島東部で話されている内之浦方言のアクセント体系を記述し、二型アクセントの痕跡が今なお残存することを指摘する。拡張語を2つ以上使用した文中での名詞の発音を観察すると、ある話者の発音では鹿児島市方言の二型アクセントと類似する、対立する2 種類のアクセント型が現れることから、この話者が鹿児島市方言と同じ二型アクセントに近い体系を意識下に持っていると考える。さらに、拡張語を単独で発音した際にはアクセント型の対立が見られない別の話者も、文中での発音においては2 種類のアクセント型が比較的安定して現れることが明らかになった。両話者の体系にはそれぞれ鹿児島市方言とのアクセント型の対応や語末音素による条件づけが想定でき、これは二型アクセントから変化したものであると考えられる。論文 Articles
1 0 0 0 OA 胆嚢壁の損傷を伴う犬の気腫性胆嚢炎の1例
- 著者
- 井上 寛也 砂原 央 谷 健二 井芹 俊恵 堀切園 裕 板本 和仁 伊藤 晴倫 中市 統三
- 出版者
- 一般社団法人 日本獣医麻酔外科学会
- 雑誌
- 日本獣医麻酔外科学雑誌 (ISSN:21896623)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.3+4, pp.41-45, 2020 (Released:2021-02-16)
- 参考文献数
- 11
12歳齢、雄のミニチュアダックスフンドが急に発症した嘔吐と食欲不振を主訴として、山口大学動物医療センターに来院した。血液検査では肝酵素と炎症マーカーの上昇が見られた。また、腹部の超音波検査ならびにX線CT検査では、胆嚢内にガスの貯留と結石が認められた。また、胆嚢内のガスの一部は腹腔内にも存在している可能性が示唆され、胆嚢破裂が疑われた。試験開腹では、肉眼的に重度な炎症を伴い、肝葉と癒着した胆嚢が認められた。胆嚢は肝葉との癒着の剥離の後に切除され、切除された胆嚢は肉眼的に内外の2層に解離しており、病理組織学的検査では重度の壊死を伴う化膿性炎症が認められた。また、その内容物から腸球菌が分離された。以上のことから、本症例は腸球菌の胆嚢内への感染による胆嚢壁の損傷を伴った気腫性胆嚢炎と診断された。動物の手術後の回復は良好であった。
- 著者
- 松本 淳 奥田 綾子 内田 佳美 小儀 直子 小儀 悦子
- 出版者
- 一般社団法人 日本獣医麻酔外科学会
- 雑誌
- 日本獣医麻酔外科学雑誌 (ISSN:21896623)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.3+4, pp.52-57, 2020 (Released:2021-02-16)
- 参考文献数
- 12
5歳、日本猫、避妊済みの雌猫が食欲不振と開口障害を主訴に来院した。一般身体検査で、左側頭部に硬性の腫瘤性病変を認め、FeLV検査は陰性であった。その腫瘤性病変に対し、診断と減容積を目的とする切除生検を行い、骨軟骨腫と病理組織診断された。その後、2回の外科的切除を実施したが、完全切除には至らず、開口障害の改善にとどまった。切除生検後53ヶ月目から腫瘍病変の増大速度の低下とレントゲン透過性の亢進像が認められ、最後の59ヶ月間では1.3 mmの増大にとどまった。16歳時に骨軟骨腫とは別の要因により死亡した。約10年間の長期的経過観察中、腫瘍は存在したものの、転移はなく、開口障害もなく、通常の摂食行動が可能であった。
1 0 0 0 対馬市厳原町豆酘方言における動詞アクセントの例外について
- 著者
- 中島 良光
- 出版者
- [日本方言研究会]
- 雑誌
- 日本方言研究会研究発表会発表原稿集
- 巻号頁・発行日
- vol.95, pp.57-64, 2012
1 0 0 0 OA 青森県出身者の社会関係資本と地域間移動の関係
- 著者
- 石黒 格
- 出版者
- 日本教育社会学会
- 雑誌
- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, pp.33-55, 2018-05-31 (Released:2020-03-13)
- 参考文献数
- 51
進学,就業において非常に厳しい制約下にある青森県の若者の現状を,進学,就業の実態と社会関係資本の利用という観点から検討した。筆者らが独自に行った3つの調査データの分析から,以下の結果を得た。1)青森県では,威信の高い大学に入学する機会が強く制約されているが,中堅以下の大学への入学機会への制約は弱い。2)そのため,学力の高い若者に対して,選択的に移動の誘因が存在する。3)青森県在住の若者は,南関東在住の若者と比べて労働時間は等しく,勤続年数は長いが,収入は低い。4)青森県在住の若者の社会関係は地域的で,そのために時間が経過しても残存しやすい。5)青森県在住の若者にとって,社会関係が就業機会獲得の重要な経路となっており,特に低学歴の若者でこの傾向が強い。以上の結果および先行研究から,青森県では,学力および経済的に有利な立場にいる若者には大都市へと移動する誘因が存在するのに対して,相対的に不利な立場にいる若者にはそうした誘因は小さく,むしろ豊かでサポーティブな社会関係が出身地に留まる誘因となっていることが示唆された。こうした誘因の二重構造は,相対的に有利な若者が,より多くの利益を得る構造を有しており,格差の再生産装置と評価しうる。しかし一方で,大都市に移動する利益の小さい,資源の乏しい若者を地域に包摂し,移行における不確実性のリスクから保護する機能を果たしているとも理解できる。
1 0 0 0 OA Satisfaction and satisfaction affecting problem behavior in different types of adopted dogs
- 著者
- Simona NORMANDO Francesca BERTOMORO Omar BONETTI
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- pp.20-0394, (Released:2021-02-23)
- 被引用文献数
- 3
Many dogs are relinquished worldwide, so it is important to enhance adoptions’ success. We aimed at investigating factors associated with owners’ satisfaction with adopted dogs, both in general and focusing on galgos. Data on 392 dogs (191 galgos) were gathered using an online survey, investigating dogs’ and owners’ demographics, satisfaction with the adopted dog and post-adoption behavior. Satisfaction was affected by different variables in galgos’ owners as compared to non-sighthound non-podenco dogs’ ones, with only the presence of disobedience on walks negatively affecting satisfaction in both samples. Depending on dogs’ type, the presence of some behavioral problems was associated with decreased satisfaction with the dog (e.g., destructiveness for galgos, or separation problems for non-sighthound non-podenco dogs), whereas that of others increased it (e.g., not being interested in social interactions with dogs for galgos, and shadowing for non-sighthound non-podenco dogs). The variables most often being predictors of the behaviors influencing satisfaction were dog type,with being a galgo as a negative predictor, and dog’s age, with being older as a negative predictor. Further studies on dog adopters’ satisfaction are needed.
- 著者
- 石濱 裕規 並木 重宏
- 出版者
- 一般社団法人 日本リハビリテーション工学協会
- 雑誌
- リハビリテーション・エンジニアリング (ISSN:13423444)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.1, pp.37-48, 2021-02-01 (Released:2021-02-17)
- 参考文献数
- 63
- 著者
- 吉葉 恭行
- 出版者
- 東北大学史料館
- 雑誌
- 東北大学史料館紀要 (ISSN:1881039X)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.15-37, 2011-03
1 0 0 0 OA ヤコブ・ニューマンのクリティカル・ペダゴジー論 ―ヘンリー・ジルーとの比較を通して―
- 著者
- 植松 千喜
- 出版者
- 日本カリキュラム学会
- 雑誌
- カリキュラム研究 (ISSN:0918354X)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.1-13, 2018 (Released:2019-05-29)
The purpose of this paper is to examine Jacob Neumann’s critical pedagogy theory. In North America, critical pedagogy is led by two scholars―Michael Apple and Henry Giroux. Giroux is especially famous as a successor to Paulo Freire, and there are some studies on Giroux in Japan. However, interpretations of Freire which are different from Giroux’s one have not yet received proper consideration in Japan. Therefore, this paper focuses on the critical pedagogy theory of Neumann, whose arguments are distinctively interpretations of Freire.Neumann points out that critical pedagogy’s main dilemma is to reconcile one aspect as political activity with students’ intellectual freedom in classrooms through criticism against Bill Bigelow’s classroom practice. As a result, it can be seen from Neumann’s critical pedagogy theory that there are two major attitudes: (1) a positive attitude toward the practice which is inquired by teacher and student dialog, (2) a respectful attitude towards the everyday efforts by teachers combined with an affirmative attitude toward the change in teachers’ everyday slight practices.Neumann focuses on “generative themes,” particularly in Freire’s practices, which he interprets as a process that involves teachers’ and students’ commitment to learning together through the medium of the world. Also, Neumann considers Freire’s theory and practice to be limited by the situation, apolitical, and to be opened to different discourses in a book-review article addressed to a book written by Peter Roberts who is researcher of Freire.His attitude toward critical pedagogy and his interpretation of Freire are not aimed at the realization of radical political goals, but at respectful changes in teachers’ everyday slight practices and students’ intellectual freedoms. In this, his attitude is different from that of Giroux. Neumann thinks that teachers can put critical pedagogy into practice through their individual beliefs and knowledge, even though they may be limited by their circumstances.As mentioned above, Neumann’s argument demonstrates a practical strategy for critical pedagogy that teachers who don’t adopt a radical belief which is similar to critical pedagogy scholars can struggle jointly. Critical pedagogy, which aims for a world in which diverse people can view one another positively, is contradictory if it does not consider teachers who are not “leftist” and students who are not politically active. Critical pedagogy needs to clear up this contradiction in order to change society toward its goal.
1 0 0 0 OA ポストモダニズムの不可能性 : リベラル・コミュニタリアン論争を精読する
- 著者
- 森本 奈理
- 出版者
- 文教大学
- 雑誌
- 文学部紀要 = Bulletin of The Faculty of Language and Literature (ISSN:09145729)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.1, pp.37-58, 2015-09-16
1 0 0 0 IR <書評>バウハウス 1919-1933 ハンス・マリア・ウイングラー編 1962年
- 著者
- 宮島 久雄
- 出版者
- 関西意匠学会
- 雑誌
- デザイン理論 (ISSN:09101578)
- 巻号頁・発行日
- no.3, pp.74-77, 1964-11-11
1 0 0 0 人造人間表象の変遷に関する研究:近代以降の科学思想の影響から
本研究は、20世紀初めのドイツ語圏の文学作品等における「人造人間」表象について、当時の科学の発展を踏まえつつ検討することで、文学と科学の相互作用を明らかにするとともに、人間観および科学観に迫ることを目的とする。20世紀初めには、単為生殖や臓器移植実験が成功し、ドイツ圏で科学者たちは「一元論」という世界観を形成した。これらの成果は、熱狂的にあるいは戯画的に文学や映画に取り込まれ、ハンス・ハインツ・エーヴェルスの『アルラウネ』や『フントフォーゲル』、フリッツ・ラングの『メトロポリス』等が現れた。人造人間表象の分析から、当時の人間観の変化、および科学と社会の関係が明らかにされるだろう。
1 0 0 0 OA 戦後日本の地学(昭和20年~昭和40年)〈その1〉―「日本地学史」稿抄―
- 著者
- 日本地学史編纂委員会 東京地学協会
- 出版者
- 公益社団法人 東京地学協会
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.117, no.1, pp.270-291, 2008-02-25 (Released:2010-02-10)
- 参考文献数
- 102
- 被引用文献数
- 3 3
1 0 0 0 OA 113) 小学生の体型とボディイメージ、摂食障害との関連
- 著者
- 森 千鶴 嘉糠 美津希
- 出版者
- 一般社団法人 日本看護研究学会
- 雑誌
- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.3, pp.3_218, 2003-06-24 (Released:2020-06-19)
- 参考文献数
- 6
1 0 0 0 OA ボディイメージとセルフイメージ(第2報) : 体重の課題認知と自己評価的意識の関係
- 著者
- 竹内 聡 早野 順一郎 堀 礼子 向井 誠時
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.8, pp.697-703, 1993-12-01 (Released:2017-08-01)
Social pressure for thinness has been emphasized as a cause of recent increase in the prevalence of eating disorders. We have previously found that female junior-high-school students are strongly possessed with their body weight (BW) and body physique and that their self-esteem is associated with their body image. However, only a little fraction of people actually suffer from eating disorders, indicating that individual differences in the reactivity to the social pressure are also important in the etiology of the disease. This study aimed to examine the hypothesis that the BW over'estimation is associated with low self-esteem independently of actual BW in adolescent females. We performed a questionnaire survey on the relationship between self-esteem and body image in 714 students (361 male, 353 female) in an urban coeducational public junior-high-school. The self-esteem was evaluated by means of Kajita's self-esteem scale. The body image was evaluated from the relationship between obesity index and an adjective expression of physique (fat, average, lean) selected by subjects. Based on the relationship between obesity index and adjective expression of physique, subjects were divided into three groups as follow : "over-estimators" were as- signed when "fat" was selected by subjects with an obesity index of < 0% and when "average" was selected by those with an obesity index of < -20% ; in the opposite cases assigned were "under-estimators"; and otherwise "approximate-estimators" were assigned. Additionally, the subjects in "appropriate-estimator" with an obesity index of < 0% were specially defined as "nonover-estimators". Cluster analysis performed on the responses to 23 items of the self-esteem scale showed that the items could be divided into three categories, which were respectively named "self-acceptance", "superiority", and "defense". The appropriate-estimators were 94.7 and 87.8% of male and fe-male students, respectively, whereas the under-estimators were 3.5 and O% and the over-estimators were 1.8 and 12.2%, respectively (p < 0.001). The frequency of over-estimator increased with advancing school grade in the female students (7.l%, 9.6%, and 19.0% for 1 st, 2 nd and 3 rd grade ; p < 0.018), but no significant difference was found in the male students. Analysis focused on the differences between the over- and non-over-estimators in the female subjects revealed that the over-estimators was lower in the self-acceptance score than the non-over-estimators (p=0.022), although no differences was found in the superiority or defense scores. Stepwise discriminant analysis revealed that self-acceptance was a significant discriminator between the two groups even when obesity index and school grade were forced to enter (p < 0.001). These results not only confirm our previous finding that female students desire their BW Iower than medically ideal / BW but also support the hypothesis that low self-acceptance may impair the acceptance of bodyimage and result in the over-estimation of BW in adolescent females.
1 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1943年09月29日, 1943-09-29
1 0 0 0 OA 江戸時代までの相続と女性
- 著者
- 本田 弘子
- 出版者
- 日本法政学会
- 雑誌
- 法政論叢 (ISSN:03865266)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.89-101, 1978-05-20 (Released:2017-11-01)
- 著者
- 数藤 雅彦
- 出版者
- 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所
- 雑誌
- 奈良文化財研究所研究報告
- 巻号頁・発行日
- no.21, pp.91-95, 2019-01-17
1 0 0 0 OA [B13] ウェブブラウザでの3Dデータ資料表示:立体資料閲覧の可能性と課題
- 著者
- 土屋 紳一
- 出版者
- デジタルアーカイブ学会
- 雑誌
- デジタルアーカイブ学会誌 (ISSN:24329762)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.2, pp.67-70, 2018-03-09 (Released:2018-05-18)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1
早稲田大学演劇博物館では、2015年4月に立体資料の3DデータをWebGL[1]技術によってブラウザのみで閲覧を可能としたシステムを公開した。立体資料の3Dデータは、画像・音声・動画とは異なり、表示をするためのパラメータが非常に多い。さらに、3Dデータを操作するためのインターフェイスなどを作成しなくてはならず、公開までのハードルが高い。しかし今後、3Dプリンタの普及やVR・AR技術の進歩などを考慮すると、かつてないほどの3Dデータ活用が広がるとみられる。課題と向き合いながら公開資料数を増加させ続けているのは、将来のデジタルアーカイブにとって、重要な役割を担うと考えているからだ。当館が立体資料の公開において重視してきた、表示のパラメータと操作のためのインターフェイス、効率的かつ高精度の3Dデータ化の事例報告と、現在も解決できていない課題を発表する。