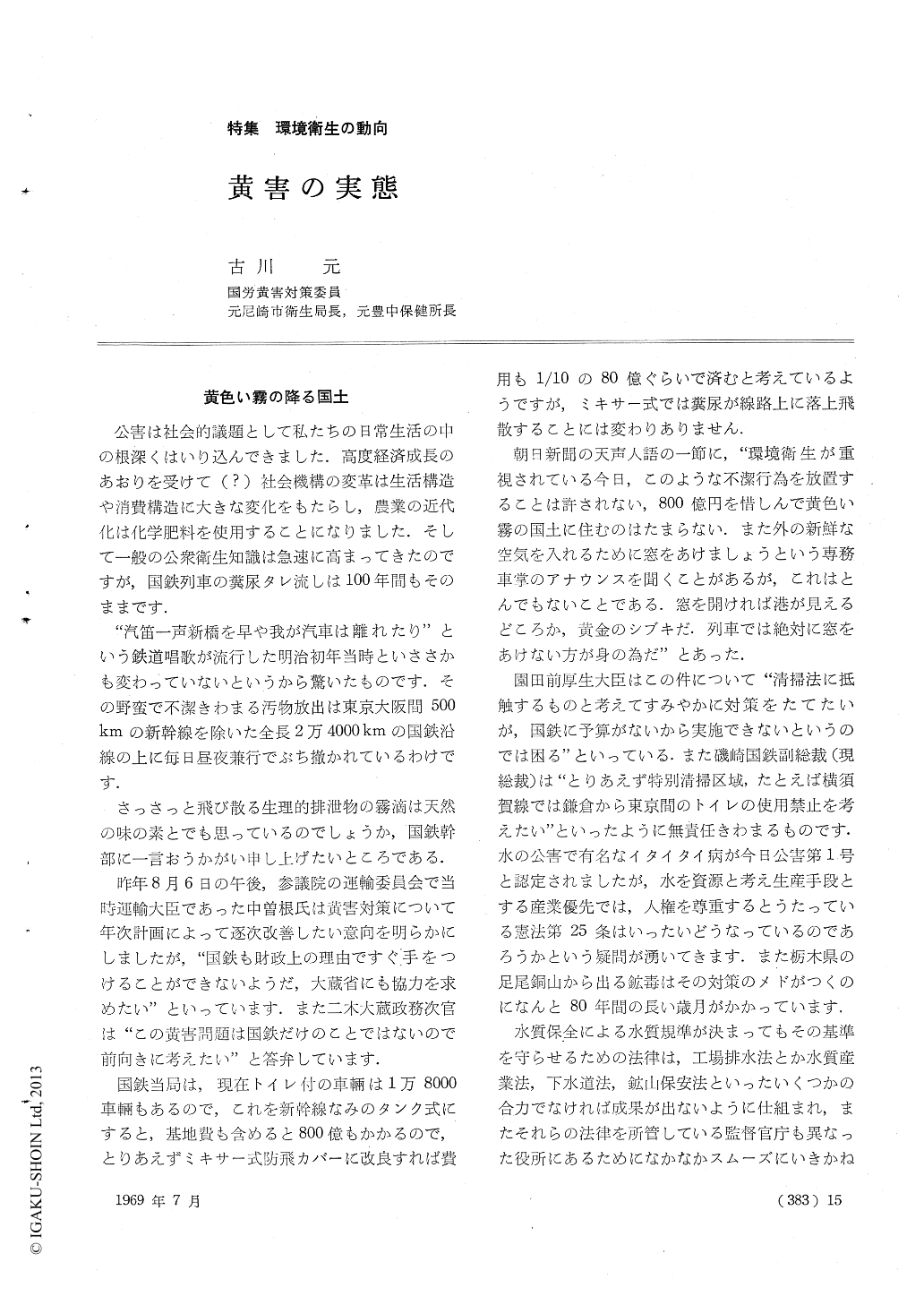1 0 0 0 OA 古琉球の首里城神女祭祀と聖域の盛衰
- 著者
- 伊從 勉
- 出版者
- 建築史学会
- 雑誌
- 建築史学 (ISSN:02892839)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, pp.2-46, 2011 (Released:2018-08-17)
1 0 0 0 グループ総出で自動車向けの用途開拓--トヨタ、生プラ事業を加速
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経バイオビジネス (ISSN:13464426)
- 巻号頁・発行日
- no.8, pp.66-68, 2002-01
10月27日から千葉市で開催された第35回東京モーターショー2001。この展示会に、トヨタ自動車は1台の車を参考出品した。車の名は「ES3(イー・エス・キュービック)」。生分解性プラスチックであるポリ乳酸を原料とした自動車用内装部品を、世界で初めて搭載した自動車だ
- 著者
- NAKAYAMA,Hiroto
- 出版者
- Entomological Society of Japan
- 雑誌
- Entomological science
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.1, 2002-03-25
Japanese species of the genus Peromitra Enderlein are revised. Five species are recognized and four of them are described as new to science : P. fimbriata sp. nov., P. purpurea sp. nov., P. pilosa sp. nov. and P. hikosana sp. nov. A known Japanese species are redescribed and discussed. A key to Japanese species is provided.
1 0 0 0 OA 平安時代の内匠寮
- 著者
- 芳之内 圭
- 出版者
- 関西大学史学・地理学会
- 雑誌
- 史泉 (ISSN:03869407)
- 巻号頁・発行日
- vol.106, pp.1-18, 2007-07-31
1 0 0 0 OA 睡眠時無呼吸症候群とうつ病 ~両者の関連性を検討する~
- 著者
- 池上 あずさ
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.2, pp.58-62, 2018 (Released:2018-06-29)
閉塞性睡眠時無呼吸(以下OSA)とうつ病が同じ患者に並存することがある。PSG検査による解析では、OSAは 睡眠中の上気道の閉塞による無呼吸などの呼吸イベントから覚醒反応を生じたための睡眠構築不良(すなわち不眠)がその病態の本質であり、その結果、日中の眠気、倦怠感や集中力低下、認知機能の低下に加えてうつ症状も引き起こす。OSAとうつ病の合併については、ヨーロッパ五か国の延べ18980人の一般人口を対象とした調査でOSAの17.6%にうつ病がみられたとのOhayonらの報告をはじめとして、合併率が7~63%と幅が広い。これは、OSAに対する合併をDSM-Ⅳに基づいたうつ病の診断ではなく、うつの重症度を見る問診票で評価したものなどであったためと考えられた。しかし、ランダムに選択された個人の長期的な2つの大規模疫学研究ではどちらも年齢、BMI、アルコールや血圧、心血管疾患などの交絡因子を検討したうえでOSAのうつ病発症の調整オッズ比を、Peppardらは1.8倍、Chenらは2.18倍と報告しており、OSAとうつ病発症の間の密接な関係を示唆している。OSAとうつ病の重症度については、8論文で直接の関連性を肯定し、9論文は否定していた。しかし、眠気とうつ病の重症度、さらには低酸素血症とうつ病の重症度については関連性を認めていた。橋爪らは、OSAにうつ病を合併している患者8名に対してCPAP療法によるうつ病の治療効果を検討し、Beck Depression Inventry(BDI)とHamilton Depression Scale( HDS)両方のうつ症状のスケールで改善したと報告した。自験例であるが、他院でうつ病として治療中に当院を紹介され、PSGにてOSAと診断された20名(男性12名、女性8名)についてOSA治療後の経過を追跡した。OSA診断前には、全例抗うつ剤や抗不安薬あるいは睡眠導入剤を投与されていた。20例中14名にCPAP療法を導入し、継続できた12例中7例においてうつ症状と不眠の改善により服用中の薬物を減量ないしは中止することができた。口腔内歯科装置で治療された2例中1例は同様に不眠が改善した。一方、中長時間作用型のベンゾジアゼピン(以下BZ)系睡眠導入剤多剤服用例においては、無呼吸低呼吸指数(AHI)と覚醒反応指数(ArI)の間に大きな乖離があり、無呼吸・低呼吸時に覚醒反応を認めない症例も散見された。OSAのうつ症状発現のメカニズムは複雑であり、今後の研究成果が期待されるが、遺伝的要因、肥満と心血管危険因子を背景に頻回な覚醒反応を伴う睡眠の分断化、間欠的低酸素血症とそれによる炎症性サイトカイン、睡眠・覚醒機構に影響するセロトニンやノルアドレナリン、γ―アミノ酪酸(GABA)などの阻害性及び興奮性神経伝達物質が潜在的に関与し、眠気のレベルや本人の病前性格、社会的なストレスなどが複合的に合わさって形成されると考えられる。従って、CPAPを使用しても昼間の眠気が強いOSA患者は、うつ病の合併を考慮すべきであろう。うつ病患者の場合、抗うつ剤の影響で肥満となり、OSAを悪化させる一方で不眠に対して使用したBZ系薬剤によりOSAがマスクされるという状況も考えられる。つまり、治療に反応しないうつ病においては、OSA合併を常に念頭に置く必要がある。OSAとうつ病は、両者がそれぞれに対して潜在的危険因子になり得ると考えられる。
- 著者
- 竹中 平蔵
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経コミュニケーション (ISSN:09107215)
- 巻号頁・発行日
- no.455, pp.85-87, 2006-02-01
この1月から「通信・放送の在り方に関する懇談会」と銘打った直轄の組織を立ち上げた竹中総務相。その懇談会は通信と放送を取り巻く制度だけでなく,NHKとNTTの在り方まで視野に入れており,幅広い層の関心を一手に集めている。しかも懇談会の会期はわずか半年。「改革は短期決戦でないとうまくいかない」とする竹中大臣に,懇談会を立ち上げた背景と進め方を聞く。
1 0 0 0 OA 流動化処理土の力学特性と今後の課題
- 著者
- 木幡 行宏
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集F (ISSN:18806074)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.4, pp.618-627, 2006 (Released:2006-10-20)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 4 6
流動化処理土は,各種構造物の裏込めや地中構造物の埋戻しの際に適切な締固めができない場合に対して建設発生土を有効に利用するために開発されたものであり,締固めが不要で適度な流動性を持たせた泥状の土に固化材を適量に混合して固化効果を期待することが基本概念である.近年,社会的に再資源化が大きな時流となり,都市部で流動化処理土が広く利用されるようになってきた.本論文では,流動化処理土の実績と動向を概観し,埋戻し材として用いられる低強度の流動化処理土とシールドトンネルのインバート材に用いられる流動化処理土の力学特性を概説するとともに,靭性を改善して耐震性を向上させるために繊維質材料を流動化処理土に混合した繊維材混合流動化処理土の力学特性を述べる.また,今後の流動化処理土における課題について述べる.
- 著者
- 佐伯 万騎男 江草 宏
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.144, no.6, pp.277-280, 2014
- 被引用文献数
- 1
骨粗鬆症治療薬は骨吸収抑制薬と骨形成促進薬に分類される.従来の骨粗鬆症治療薬は骨吸収抑制薬が主流であったが,破骨細胞と骨芽細胞の活性が共役する機構が存在するために長期的には骨形成が低下して効果が減弱したり副作用が生じたりする問題点があった.骨形成促進薬anabolic agent としてはヒト副甲状腺ホルモン(parathyroid hormone:PTH)製剤であるテリパラチドが現在唯一の治療薬である.我々は破骨細胞におけるnuclear factor of activated T cells (NFAT)シグナルをターゲットとした骨吸収抑制薬の創薬を当初の目的として,RAW264.7 細胞を用いたセルベースアッセイ系を構築し,様々な化合物ライブラリーを用いた創薬スクリーニングを行ってきた.スクリーニング中に多くのNFAT 活性化小分子化合物を発見し,これらの破骨細胞を活性化させる化合物が,anabolic therapy に使用できる可能性があるのではないかと考えた.Anabolic agent として唯一臨床応用されているPTH 製剤が血中のカルシウム濃度を上昇させるしくみの一つに,骨吸収の促進がある.したがって,PTH の骨吸収促進という教科書的事実に固執していたら,テリパラチドが骨形成促進薬として開発されることもなかったであろう.PTH の持続的投与は骨吸収の促進をもたらすが,間歇的投与intermittent PTH(iPTH)treatment によるPTH の骨形成促進作用に注目したことが,テリパラチドという骨形成促進薬の開発につながった.我々はこのテリパラチドの例をヒントに,あえて破骨細胞の活性化薬をスクリーニングすることから,新しい骨形成促進薬を開発できないかと考えている.
- 著者
- 酒井 恭徳 藤井 威生 マイケル ロックラン 中川 正雄
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. ITS (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.101, no.99, pp.1-6, 2001-05-22
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 2
車々間通信の使用は将来のITS(Intelligent Transport Systems:高度道路交通システム)において, 車両同士での情報交擬のために欠かせない技術である. 本論文では対向車の干渉を考慮した車々間通信において, DS/SS(直接拡散)方式を用いた場合とFH/SS(周波数ホッピング)方式を用いた場合を計算機シミュレーションにより比較する. その中で特に, 対向車をトラヒックモデルを用いて生起させた場合の車両の認識率に注目して検討を行う. その結果からDS/SS方式では遠近問題により対向車が大きな干渉となること, そしてFH/SS方式では遠近問題がほとんど起きないため, 対向車の干渉が十分に抑えられることを明らかにする. さらに, 車両認識率において, 距離が離れた車両に対する性能がFH/SS方式の利用により大幅に改善することを示す.
1 0 0 0 OA デイケア・作業所に通所中の統合失調症患者が自己の生き方におりあいをつけるプロセス
- 著者
- 神宝 貴子 國方 弘子
- 出版者
- 一般社団法人 日本看護研究学会
- 雑誌
- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.5, pp.5_71-5_78, 2008-12-01 (Released:2016-03-05)
- 参考文献数
- 18
デイケア・作業所に通所中の統合失調症患者が,自己の生き方に対してどうおりあいをつけているのかそのプロセスを明らかにすることを目的に,統合失調症患者12名を研究参加者に,自己の生き方についての思いをインタビューし,質的帰納的に分析した。その結果,≪気が楽になる≫≪今におりあいをつける≫≪過去に向き合う≫≪未来を見つめる≫【自分はこれでいい】の5つのカテゴリーが抽出され,【自分はこれでいい】が中核カテゴリーであった。ある出来事を契機にあるいは時間をかけながら≪気が楽になる≫ことで,≪今におりあいをつける≫ことが出来,さらに≪過去に向き合う≫ことが出来,病状の変化により【自分はこれでいい】という気持ちが揺らぎながらも【自分はこれでいい】と生き方に対して納得していく。しかし,将来への不安は大きく,今に近い≪未来を見つめる≫ことをしながら一日一日を納得しながら生きていた。
1 0 0 0 IR 日本文学研究室紹介 現在の研究課題(学科紹介)
- 著者
- 工藤 浩
- 雑誌
- 日本工業大学研究報告 = Report of researches, Nippon Institute of Technology (ISSN:21895449)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.2, pp.44-45, 2020-10
I gave an outline about the directionality of a past study and the future study. I specialize in a study of the Japanese ancient literature. I aim at Kojiki and Nihonsyoki and religious service and the investigation of the relationship with the family. As another theme, I comment on Sendaikujihongi. I want to try to make use of a part of results of research in a lecture of our institute.
1 0 0 0 IR 月報を読む (5) : 筑摩書房版世界文学全集 月報細目 : (前半)
- 著者
- 藤井 哲 Fujii Tetsu
- 出版者
- 福岡大学研究推進部
- 雑誌
- 福岡大学人文論叢 = Fukuoka University Review of Literature & Humanities (ISSN:02852764)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.2, pp.665-700, 2020-09
1 0 0 0 黄害の実態
黄色い霧の降る国土 公害は社会的議題として私たちの日常生活の中の根深くはいり込んできました.高度経済成長のあおりを受けて(?)社会機構の変革は生活構造や消費構造に大きな変化をもたらし,農業の近代化は化学肥料を使用することになりました.そして一般の公衆衛生知識は急速に高まってきたのですが,国鉄列車の糞尿タレ流しは100年間もそのままです. "汽笛一声新橋を早や我が汽車は離れたり"という鉄道唱歌が流行した明治初年当時といささかも変わっていないというから驚いたものです.その野蛮で不潔きわまる汚物放出は東京大阪間500kmの新幹線を除いた全長2万4000kmの国鉄沿線の上に毎日昼夜兼行でぶち撤かれているわけです.
1 0 0 0 IR 低成長,経済の国際化過程での家族経営と生活様式の変容
- 著者
- 戸島 信一
- 出版者
- 九州大學農學部
- 雑誌
- 九州大学農学部学芸雑誌 (ISSN:03686264)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.3, pp.193-210, 1998-03
日本資本主義はポスト高度成長下で国内的また国際的に大きな変化を迫られ,また遂げてきた.例えば高度成長期には工業=製造業の飛躍的発展によって労働市場が著しく拡大し,また大衆消費財の国内市場拡大や労働運動による統一的ベースアップ闘争(春闘)もあって,賃金水準は全体的に上昇し,底上げされた.しかし,高度工業化社会段階に到達した日本経済はオイルショックを期に,雇用調整や賃金抑制を迫られ,重厚長大型から軽薄短小型への産業構造の再編を迫られた.そして徹底したコスト削減,省資源・省エネ対策によって国際競争力を短期間で回復し,以前よりさらに強化することに成功し集中豪雨的に輸出を拡大し,貿易黒字を稼ぐことになる.しかしそれは貿易黒字の堆積→円高→コストダウン努力→国際競争力強化→貿易黒字増大→円高の一層の進行という「悪魔のサイクル」に陥ることにもなった.円高は国内の賃金水準の相対的上昇をもたらし,賃金水準の低い地域への生産拠点の移動=資本輸出を進行させることになった.また一方でポスト高度成長下の,合理化,省資源・省エネ対策を契機とするME革命は,生産と生活の社会化を極限にまで推し進めてきた.それによって従来の労働市場の構造や,生活様式を変化させつつある.労働市場においては,高度成長期とは逆に,企業規模別や産業別あるいは雇用形態による賃金格差構造の固定・拡大が進行している.労働市場は第3次産業の展開によって拡大はしているが,パートタイム労働者の増加が顕著であり,またリストラや景気変動による労働力の解雇や流動化が頻繁に行われるようになっている.このようなことは終身雇用制や年功序列賃金制を動揺させることになりひいては労働者の企業への帰属意識・忠誠心を弱化させることにならざるをえない.このことは日本資本主義を支えた会社本位主義・法人資本主義(奥村,1995)=会社は永遠に不滅という幻想,の崩壊を意味する.このように経済の徹底した国際化,ボータレス化の進行は従来の日本経済の発展を支えてきた経済構造,さらには産業政策の構造,制度構造の改変をも迫ることになる.そしてこの貿易の自由化の進展とその黒字の拡大,またME革命による著しい技術革新は,国内農業を益々窮地に陥れることになる.円高の進行による,国内農産物の国際競争力の低下や2次,3次産業との所得・賃金格差の拡大は農業,農村からの慢性的労働力流出現象を引き起こしてきた.しかし,農村の労働力は無尽蔵ではない.また農村でも少子化現象が波及したこともあって,農業労働力不足問題が本格化し,家族経営の存続問題が発生するに至る.家族経営の再編成,サポートシステムの構築なくして農業の担い手の確保は困難になっている.とりわけ農業は地域的産業としての特質を持ち,その帰趨は地域経済,生活の問題に影響を与える.また生活様式の面では,ME革命による労働の軽量化,週休2日制の普及・拡大=労働時間の短縮,男女雇用平等や育児休業の制度化=女性の労働環境の改善など,仕事の場面の変化によってライフスタイル,特に女性のそれに大きな変化がもたらされつつある.ME化は耐久消費財の性能,利便性を高め家事労働時間の一層の節約をもたらす.かつて「主婦業」を成立させていた熟練労働としての家事はME革命によって非熟練化したし,また家事サービス業の展開はそれを外部化することを促進した.このようなME革命による労働場面での労働の軽量化・単純化の進行と家庭内における家事の技術革新と外部化による家事労働時間の減少が,主婦層の就業者化,特にパート労働者化を促進した.さらにME革命による生活の技術革新,特に冷凍冷蔵庫,電子レンジ,電子ジャーの普及は,家族いっせいの食事とその食物の分配権を握る主婦の権利と義務を無意味化し.家族の個食化を進行させている.また装置系の技術革新と家事の商品化・外部化は生活技術のない単身者のサバイバルを可能にした.つまり,生活技術の著しい非熟練化によって大都市地域での男子単身世帯の成立を容易にし,中高年の単身赴任を可能にした.生活技術の革新は家族の分裂,個族化を引き起こす要因にもなることを意味する.さらに子供に個室を与え,パーソナルユースのテレビや電話(コードレスフォン)を与えるによって,子供は家族の管理外で直接外部と通信・交渉し情報を取得することが可能になった(上野,1994,p180~185).このように生活における個別化の進行は留まることをしらないかにみえる.家族の凝集力,家族の文化,家族生活の共同性は喪われていくのであろうか.賃金・所得の格差構造は,経済の国際化の進展の中では国内の需給関係を通じて修正される可能性は少ない.農業労働や家事労働は最も価値の低い労働として序列づけられたきた.周知のようにアメリカでは移民や移動する低賃金労働力を利用して労働集約的な農業部門が成立してきた.わが国ではまだ法的に認めれれているわけではないが,一部に途上国からの低賃金労働力の導入がみられる.また農業後継者の配偶者を途上国に求めている.この路線でいけば最終的に農業生産のほとんどを海外に移転するという発想になる.またわが国でも戦前は家事使用人を農村からの出稼ぎによって調達していたし,現在既に欧米各国ではみられているように,家事労働力を途上国からの出稼ぎ労働力に依存するという発想になる.しかしそれでは南北問題の解決どころか南北格差を固定し,国際矛盾を益々激化していくことになる.
1 0 0 0 自然災害リスクに関する地理空間情報の伝え方の工夫
- 著者
- 栗栖 悠貴 小島 脩平 稲澤 容代
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2016, 2016
近年、地理院地図に代表されるように地理空間情報技術のめざましい発達により、誰でも容易に地理空間情報を扱えるようになった。その結果、災害対応をはじめ様々な分野で地理空間情報は効果的に活用されている。しかし、平成26年8月豪雨や平成27年9月関東・東北豪雨に伴う被害状況を振り返ると、事前に土砂災害危険箇所や浸水想定区域などの自然災害リスクに関する地理空間情報が被災地で十分浸透していたとは言い難い。その原因の1つにそれらの情報からリスク情報を解読する難しさがある。自然災害リスクに関する地理空間情報を分かりやすく伝えることは、被害軽減対策の1つとして重要である。<br>本報告は、災害時の被害軽減対策を促すために重要な自然災害リスクに関する地理空間情報を分かりやすく伝えるための工夫を紹介するものである。効果的に伝える工夫として次の方法がある。<br>①土地の成り立ちと自然災害リスクの関係をワンクリックで確認できる地形分類データ。<br>②身近な自然災害リスクを伝えるハザードマップポータルサイト。<br>③浸水被害範囲の時系列変化がわかる地点別浸水シミュレーション検索システム。<br>しかし、これらはツールであり利用されなければ被害軽減にはつながらない。<br>そのため、今後有用なツールを活用してもらうような広報活動をしていくことが必要である。
1 0 0 0 大正三年櫻島噴火記事
1 0 0 0 大正三年桜島噴火記事
1 0 0 0 国分郷土誌
- 著者
- 国分郷土誌編纂委員会編
- 出版者
- 国分市
- 巻号頁・発行日
- 1997