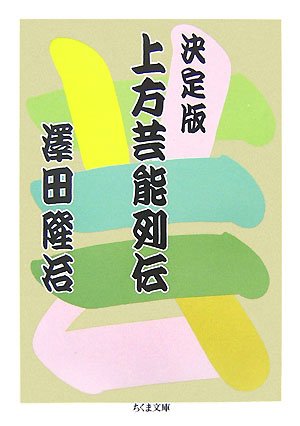- 著者
- 岡田 正則
- 出版者
- 日本評論社
- 雑誌
- 法律時報 (ISSN:03873420)
- 巻号頁・発行日
- vol.91, no.6, pp.55-57, 2019-06
- 著者
- 岡田 正則
- 出版者
- 早稲田大学法学会
- 雑誌
- 早稲田法学 = The Waseda law review (ISSN:03890546)
- 巻号頁・発行日
- vol.95, no.3, pp.225-241, 2020
- 著者
- 岡田 正則
- 出版者
- 日本評論社
- 雑誌
- 法学セミナー (ISSN:04393295)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.6, pp.12-18, 2020-06
- 著者
- 水口 浩一 久保田 雅也
- 出版者
- 一般社団法人 日本小児神経学会
- 雑誌
- 脳と発達 (ISSN:00290831)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.5, pp.337-341, 2016 (Released:2016-09-09)
- 参考文献数
- 20
【目的】人工呼吸器に依存する重症心身障害児 (重症児) は, 少ない摂取エネルギーでも, ときに栄養過多による肥満が問題となる. 長期人工呼吸管理中の蘇生後脳症児5例に対し, 生体インピーダンス法 (BIA) で体組成を測定, 病態とエネルギー必要量を検討した. 【対象・方法】年齢1~9歳. 体組成は多周波数BIA (InBody S20®) を用い, 体脂肪率, 骨格筋量, 除脂肪体重 (FFM) を測定した. 各症例の経過を後方視的に検討した. 【結果】体脂肪率は40~60%と高く, 全例で肥満, 過栄養状態であった. また, 骨格筋量と, FFMが減少していた. 適切な摂取エネルギー量の検討後は210~350kcal/日と極めて少なく, FFMあたり25~42kcal/kg/日で維持できていた. 【考察】人工呼吸管理を要す蘇生後脳症児の体組成は, 体脂肪が増加し, FFMは減少する. FFMが基礎代謝量に強く相関するため, 本病態では体重を用いたエネルギー必要量の設定では過栄養となる. FFMを基準にしたエネルギー必要量の設定が望ましい. 【結語】BIAを用いた体組成の把握は, 重症児の栄養管理の一助となる.
1 0 0 0 OA なぞかけフォーカシングの試み : 状況と表現が交差する“その心”
- 著者
- 岡村 心平
- 出版者
- 関西大学大学院心理学研究科心理臨床学専攻
- 雑誌
- Psychologist : 関西大学臨床心理専門職大学院紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.1-10, 2013-03-12
本論は、筆者が考案したなぞかけを用いたフォーカシング「なぞかけフォーカシング」を紹介する。導入では、 (1) 日本独自の言葉遊びである「なぞかけ」について、特にカケ・トキ・ココロという3つの構造をもった三段なぞと呼ばれるものについて説明し、 (2) 状況についてのメタファーとして機能するハンドル表現の特徴と、 (3) その意味を問いかけるアスキングの機能について示した上で、 (4) なぞかけとフォーカシングの構造の間の共通性について理論的に検討した。次に、そのような理論的知見を参照しながら作成した「なぞかけフォーカシング簡便法」について紹介し、その実践例を提示した。考察では、 (1) なぞかけフォーカシングの手順が、フォーカシングのプロセスを特徴づける「交差」と「浸り」を生じさせるために、どのように機能しているのかについて論じ、 (2) “その心は”というなぞかけのアスキングと通常のアスキングの中の“What's the crux of it?”という応答との比較と、その訳語としての妥当さについて検討し、 (3) フォーカシングにおける「問いかける」というプロセスと、なぞかけフォーカシングのもつ特徴の共通性についてのさらなる論考を行った。最後に、なぞかけフォーカシングを心理療法的応答の「稽古」として利用することの意義について、今後の展望を示した。
1 0 0 0 OA Gendlinにおけるメタファー観の進展
- 著者
- 岡村 心平
- 出版者
- 関西大学大学院心理学研究科心理臨床学専攻
- 雑誌
- Psychologist : 関西大学臨床心理専門職大学院紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.9-18, 2015-03-12
心理療法におけるメタファーの機能は、Freudの『夢解釈』以来、現在でも重要なトピックのひとつである。特に、人間性心理学分野におけるメタファーの機能について考える上で、Eugene Gendlinのメタファー論を参照することは重要である。本論文では、Gendlinのメタファー観の推移を概観することを目的として、3つのテキストを挙げる。その3つとは、“Experiencing and the Creation of the Meaning (Gendlin 1962/1997)” 、“Let Your Body Interpret Your Dreams (Gendlin 1986)” 、“Crossing and Dipping (Gendlin 1991/1995)” である。これら3つのメタファー論を俯瞰した結果、時代の推移を経て、Gendlinのメタファー観、特に状況の捉え方に変化が見受けられた。この変化は、Gendlinのメタファー観のある種の「進展」と捉えられる。最後に、この状況の捉え方により進展されたGendlinのメタファー論が持つ臨床的な特徴について論じた。
1 0 0 0 交差と創造性 : 新たな理解を生み出す思考方法
- 著者
- 岡村 心平
- 出版者
- 日本人間性心理学会
- 雑誌
- 人間性心理学研究 = The Japanese journal of humanistic psychology (ISSN:02894904)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.1, pp.89-100, 2017
1 0 0 0 OA 完全陰的応力更新による拡張下負荷面モデルに基づく弾塑性解析
- 著者
- 安食 拓哉 岡 正徳 橋口 公一
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学会論文集 (ISSN:21879761)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.839, pp.16-00029, 2016 (Released:2016-07-25)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 4 6
Elastoplastic analysis of solid structures under cyclic loadings is increasingly required in recent years. To this end, it is necessary to adopt elastoplastic model capable of describing cyclic loading behavior and to employ stress integration algorithm that enables effective and robust calculation. The subloading surface model excluding a purely-elastic domain is capable of describing the cyclic loading behavior in addition to the monotonic loading behavior. The complete implicit stress-update algorithm by return-mapping based on the closest-point projection for the extended subloading surface model is formulated in this article. In addition, the consistent tangent modulus tensor required for the accurate calculation by the return-mapping is formulated in the inverse matrix form. They are implemented into the implicit finite element program through the user-subroutine. We simulate elastoplastic behavior of metals to assess calculation accuracy and efficiency of the proposed algorithm. Numerical experiments for cyclic loading behavior of metals are shown in order to verify the accuracy and the efficiency of the computer program based on the return-mapping and the consistent tangent modulus tensor.
1 0 0 0 OA 創傷被覆材を応用した歯肉増大法 ―長期経過症例―
- 著者
- 児玉 利朗 香月 麻紀子 北条 彩和子
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本歯周病学会
- 雑誌
- 日本歯周病学会会誌 (ISSN:03850110)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.4, pp.435-441, 2015-01-30 (Released:2015-02-18)
- 参考文献数
- 23
1 0 0 0 福祉国家の哲学的基礎(下)潜勢的可能性としてのケイパビリティ
- 著者
- 橋本 努
- 出版者
- 岩波書店
- 雑誌
- 思想 (ISSN:03862755)
- 巻号頁・発行日
- no.1093, pp.68-87, 2015-05
1 0 0 0 福祉国家の哲学的基礎(上)潜勢的可能性としてのケイパビリティ
- 著者
- 橋本 努
- 出版者
- 岩波書店
- 雑誌
- 思想 (ISSN:03862755)
- 巻号頁・発行日
- no.1092, pp.51-71, 2015-04
1 0 0 0 吉本新喜劇名場面集 : 1959-1989
1 0 0 0 OA 西洋古代における死とその表象
- 著者
- 芳賀 京子
- 出版者
- 東北大学大学院文学研究科 東北文化研究室
- 雑誌
- 東北文化研究室紀要 (ISSN:13430939)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, pp.96-98, 2013-03-29
- 著者
- 竹内 祐介
- 出版者
- 社会経済史学会
- 雑誌
- 社会経済史学 (ISSN:00380113)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.5, pp.447-467, 2009
日本・朝鮮・満洲間の穀物需給をめぐる帝国内分業は,戦間期を通じて大きく再編成された。産米増殖計画による米生産および対日輸出の増加は米の生産地である朝鮮南部に代替食糧としての満洲粟需要を創出し,日本・朝鮮・満洲間に米の対日輸出を軸とした「米と粟の帝国内分業」を成立させた。しかし1927〜28年にかけて,米価低落による粟価の相対的上昇に伴い,粟の輸入量は大きく減少し,以後その傾向が続いていった。但し,その需要変化の様相は地域によって異なっていた。まず北部では咸鏡線の拡張と,同沿線が工業化されるに従って粟の新規市場として登場し需要が維持された。他方朝鮮南部では(1)都市部では工業化による生活水準の上昇によって米需要が高まることによって,(2)農村部では産米増殖計画による灌漑施設の整備と肥料使用の増加が麦類の増産をも促進させる条件となったことで,麦類の自給的消費を可能にし,粟需要を減少させた。すなわち,産米増殖計画に加えて工業化という新たな軸が登場することにより,米の対日輸出を軸とした穀物間の帝国内分業は,穀物需要の地域差を生み出す形で再編成されたのである。
1 0 0 0 OA ヘルシー・ディペンデンシーと援助要請風土認知が援助要請におよぼす影響
- 著者
- 池田 亜紗 磯崎 三喜年
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第83回大会 (ISSN:24337609)
- 巻号頁・発行日
- pp.3C-009, 2019-09-11 (Released:2020-09-26)
- 著者
- 石﨑 直人 鎌田 洋一 古畑 勝則 小西 良子
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品衛生学会
- 雑誌
- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.4, pp.132-137, 2020-08-25 (Released:2020-10-02)
- 参考文献数
- 34
ブドウ球菌食中毒(SFP)は黄色ブドウ球菌(SA)が産生する嘔吐毒であるブドウ球菌エンテロトキシン(SEs)により引き起こされる.SEsには古典型と新型が存在するが,近年食品から両方の型を有するSAが多く検出されている.なかでもブドウ球菌エンテロトキシンQ (SEQ)はSFPにつながる潜在的なリスクが高いと考えられている新型SEsである.そこで,食品中におけるSAの菌数と古典型SEAおよびSEQの産生量との相関性を,スクランブルエッグをモデルとして条件をpH 6.0,7.0および8.0,塩分濃度0.5および1.0%,静置温度25℃に設定し検討した.SAの菌数はすべての条件で24時間後では107/10 g以上,48時間後では109/10 gとなった.SEAの産生はすべての条件で24時間後に確認された.SEQは,NaCl 1.0%加スクランブルエッグではいずれのpHにおいても24時間後に検出されたが,NaCl 0.5%下でのpH7.0と8.0では24時間では検出されなかった.SEQの産生量はSEA量より少なかったが,SEQは比較的低いpHおよび水分活性のスクランブルエッグにおいては産生されやすく,SFPの発症に関与する可能性があることが示唆された.
- 著者
- 田川 拓海 Tagawa Takumi
- 出版者
- 筑波大学大学院博士課程文芸・言語研究科応用言語学コース
- 雑誌
- 筑波応用言語学研究 (ISSN:13424823)
- 巻号頁・発行日
- no.15, pp.59-72, 2008-11-30