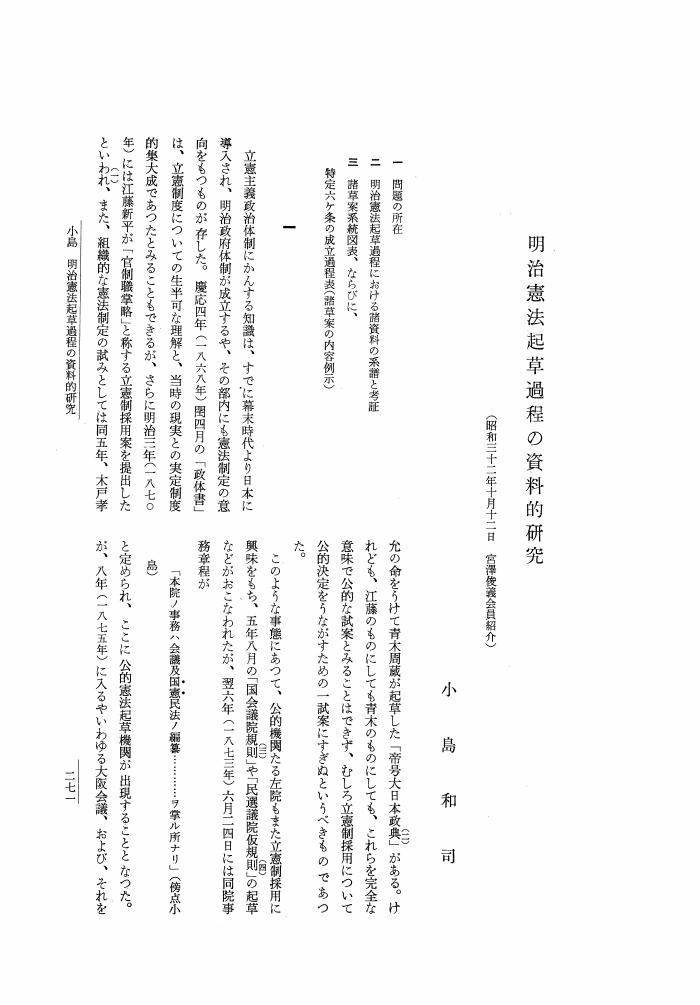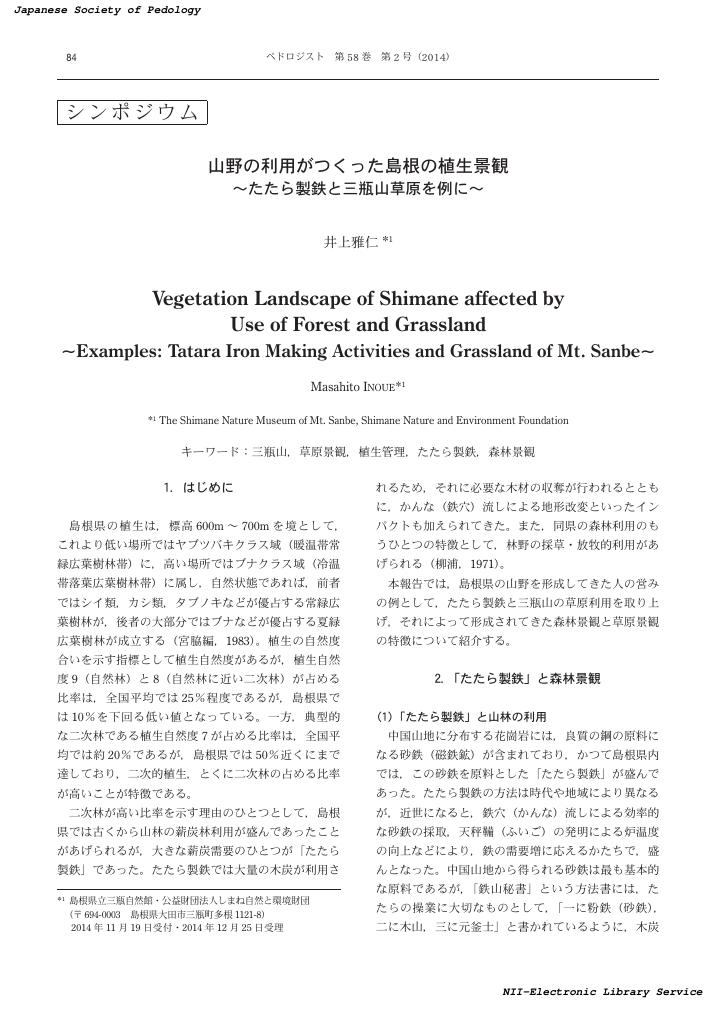1 0 0 0 OA ボーダー・エコノミー : サバにおけるブギス移民の生活戦略
- 著者
- 伊藤 眞
- 出版者
- 首都大学東京都市教養学部人文・社会系 東京都立大学人文学部
- 雑誌
- 人文学報. 社会人類学分野 (ISSN:03868729)
- 巻号頁・発行日
- no.408, pp.31-47, 2009-03-31
1 0 0 0 OA 明治憲法起草過程の資料的研究 (昭和三十二年十月十二日 宮澤俊義会員紹介)
- 著者
- 小島 和司
- 出版者
- 日本学士院
- 雑誌
- 日本學士院紀要 (ISSN:03880036)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.3, pp.271-299, 1957 (Released:2007-05-30)
1 0 0 0 OA 山野の利用がつくった島根の植生景観 : たたら製鉄と三瓶山草原を例に
- 著者
- 井上 雅仁
- 出版者
- 日本ペドロジー学会
- 雑誌
- ペドロジスト (ISSN:00314064)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.2, pp.84-87, 2014-12-31 (Released:2018-06-30)
1 0 0 0 OA 日本の常緑広葉樹林の群落体系-Ⅳ : 各地域の常緑広葉樹林の配分-3
- 著者
- 藤原 一絵
- 出版者
- 横浜国立大学環境科学研究センター
- 雑誌
- 横浜国立大学環境科学研究センター紀要 = Bulletin of the Institute of Environmental Science and Technology, Yokohama National University (ISSN:0286584X)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.99-149, 1986
1 0 0 0 OA 医用液晶ディスプレイの最大輝度が認識時間に及ぼす影響―ランドルト環を使った視覚評価―
- 著者
- 土井 康寛 松山 倫延 池田 龍二 橋田 昌弘
- 出版者
- 公益社団法人 日本放射線技術学会
- 雑誌
- 日本放射線技術学会雑誌 (ISSN:03694305)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.7, pp.581-588, 2016 (Released:2016-07-20)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 1
This study was conducted to measure the recognition time of the test pattern and to investigate the effects of the maximum luminance in a medical-grade liquid-crystal display (LCD) on the recognition time. Landolt rings as signals of the test pattern were used with four random orientations, one on each of the eight gray-scale steps. Ten observers input the orientation of the gap on the Landolt rings using cursor keys on the keyboard. The recognition times were automatically measured from the display of the test pattern on the medical-grade LCD to the input of the orientation of the gap in the Landolt rings. The maximum luminance in this study was set to one of four values (100, 170, 250, and 400 cd/m2), for which the corresponding recognition times were measured. As a result, the average recognition times for each observer with maximum luminances of 100, 170, 250, and 400 cd/m2 were found to be 3.96 to 7.12 s, 3.72 to 6.35 s, 3.53 to 5.97 s, and 3.37 to 5.98 s, respectively. The results indicate that the observer’s recognition time is directly proportional to the luminance of the medical-grade LCD. Therefore, it is evident that the maximum luminance of the medical-grade LCD affects the test pattern recognition time.
1 0 0 0 生み残されたベトナム戦争孤児たち
ベトナム戦争の終結は1975年だが,それまでの約10年間にアメリカ軍は南ベトナムの,ほぼ全域に布陣していた.南北のベトナムが統一する2年前の1973年に,約50万人のアメリカ軍は撤収してベトナムを去ったが,兵士たちが残した戦争孤児は,南ベトナムの各地で生み残された.その正確な数字は公表されていない.が,海外のジャーナリズムの推測では,数万人とされる.孤児を出産した母親はベトナム女性であることは言うまでもないが,その多くの女性たちが,戦乱の中,孤児たちを養育することは不可能だった.それに統一後の社会主義国の中で,敵兵の白や黒の肌色の子どもを連れて歩くことは,憚れたようである. 一方,ベトナム戦争に派兵していた韓国軍兵士の戦争孤児の場合は,東洋人の黄色のため,孤児院などの施設に引き取られる数は少なかったようである.ベトナム戦争の終結の直前に,アメリカ政府は,戦争孤児たちを首都のサイゴンから航空機でアメリカに移送している.里子としてアメリカに渡った子どもの数は,全体の10%程度とされる.
1 0 0 0 OA 11 アトピー性皮膚炎患者の乾燥性皮膚に対する合成洗濯洗剤の影響
- 著者
- 梅本 尚可 杉浦 久嗣 上原 正巳
- 出版者
- 一般社団法人 日本アレルギー学会
- 雑誌
- アレルギー (ISSN:00214884)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.2-3, pp.239, 1996-03-30 (Released:2017-02-10)
1 0 0 0 IR 東京大学「古典講習科」の人々
- 著者
- 町田 三郎
- 出版者
- 九州大学文学部
- 雑誌
- 哲学年報 (ISSN:04928199)
- 巻号頁・発行日
- no.51, pp.p59-78, 1992-03
1 0 0 0 国文学研究史ノート(日本文学研究史の検討)
- 著者
- 深萱 和男
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.2, pp.185-192, 1963
1 0 0 0 OA 零落企業の復活戦略・企業文化と統合的リーダーシップ : 事例研究・日立造船
- 著者
- 柳川 高行
- 雑誌
- 白鴎大学論集 = Hakuoh Daigaku ronshu : the Hakuoh University journal (ISSN:09137661)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.1, pp.345-365, 1995-12-01
1 0 0 0 OA 住宅におけるカビアレルギーとその予防に関する研究
- 著者
- 吉澤 晋 飯倉 洋治 松前 昭廣 菅原 文子 小峯 裕己
- 出版者
- 一般財団法人 住総研
- 雑誌
- 住宅総合研究財団研究年報 (ISSN:09161864)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.313-329, 1991 (Released:2018-05-01)
近年,喘息その他のアレルギー性疾患が社会的な問題となって来ている。その原因としては食物以外に,大気汚染,ダニ,花粉,カビ等居住環境に関連した多くのものが挙げられているが,特にカビは住宅の断熱性・気密性の向上と生活様式の変化に関連しでいるものと考えられている。この研究は,カビ・アレルギーの実態,患者の居住環境のカビ汚染の実態,評価方法,成育条件等の調査を通して,被曝量の予測,総合的対策について検討したものである。まず小児アレルギー疾患とカビについて住宅構造との関連について既知の知見をまとめた。住宅室内に成育するカビについての調査を夏季・冬季に行ない,成育する状況およびその主要なカピの属・種を求めた。さらに在来からの知見により,住宅に成育するカビの主要なもののまとめを行なった。住宅の空気経路による被曝の評価のためには,多数の住宅における測定が必要であり,患者家族に測定を依頼するためにパッシプ型の測定器の基本特性を求めた。カビ粒子に対して,12時間程度の被曝を計測する落下法が利用できることが分かった。カビの成育について,壁面の水蒸気圧と結露の影響を実際の住宅で調査を行なった。また,各種の相対湿度に対する建築材料,畳等におけるカビの成育速度,および更に温度変動を与えた時の成育速度への影響等を求めた。最後にこれらの調査に基づいて,住宅室内におけるカビ・アレルギーの防止対策の提案を行なっている。
1 0 0 0 OA 新しい都市交通システム
- 著者
- 新谷 洋二
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電氣學會雜誌 (ISSN:00202878)
- 巻号頁・発行日
- vol.94, no.10, pp.857-864, 1974-10-20 (Released:2008-11-20)
- 参考文献数
- 50
1 0 0 0 OA ロマン・ヤコブソンの造格論を展開する ――「周縁性」が意味すること
- 著者
- 朝妻 恵里子
- 出版者
- 日本ロシア文学会
- 雑誌
- ロシア語ロシア文学研究 (ISSN:03873277)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, pp.77-97, 2013 (Released:2019-05-07)
1 0 0 0 OA アレルギー性肉芽腫性血管炎
- 著者
- 長沢 俊彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本アレルギー学会
- 雑誌
- アレルギー (ISSN:00214884)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.1, pp.1-7, 1991-01-30 (Released:2017-02-10)
- 被引用文献数
- 11
- 著者
- 朝妻 恵里子
- 出版者
- ロシア語研究会「木二会」年報編集委員会
- 雑誌
- ロシア語研究 : ロシア語研究会「木二会」年報 (ISSN:13442813)
- 巻号頁・発行日
- no.24, pp.91-99, 2014
- 著者
- 谷川 建司 小川 順子 小川 翔太 ワダ・マルシアーノ ミツヨ 須川 まり 近藤 和都 西村 大志 板倉 史明 長門 洋平 木村 智哉 久保 豊 木下 千花 小川 佐和子 北浦 寛之
- 出版者
- 早稲田大学
- 雑誌
- 基盤研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 2019-04-01
本研究は、日本映画史上最大の構造的転換期・構造的変革期をなす1960年代末~70年代を対象とし、その社会経済的実態を次に掲げる問題群の解明を通して明らかにし、その歴史的位相を確定する。即ち、①スタジオ・システムの衰退・崩壊の内実とその産業史的意味、②大量宣伝・大量動員手法を確立した角川映画の勃興、③映画各社が試みた経営合理化と新たな作品路線の模索、④「ピンク映画」の隆盛の実態とその影響、⑤異業種からの映画産業界への人材流入の拡大とそのインパクト、である。上記の五つの括りに因んだ映画関係者をインタビュイーとして抽出し、研究会一回につき1名をゲストとして招聘し、精度の高いヒアリングを実施する。
1 0 0 0 海洋化学における痕跡物質の分析法
- 著者
- 中山 英一郎
- 出版者
- 日本分析化学会
- 雑誌
- ぶんせき (ISSN:03862178)
- 巻号頁・発行日
- vol.294, pp.475-483, 1999-06
- 参考文献数
- 30
1 0 0 0 OA 酸化物-金属界面原子層の光電子分光法による解析
- 著者
- 吉武 道子
- 出版者
- 公益社団法人 日本金属学会
- 雑誌
- 日本金属学会誌 (ISSN:00214876)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.11, pp.408-414, 2014 (Released:2014-11-01)
- 参考文献数
- 18
At metal oxide (AO)-metal (M) interfaces, metal (M) atoms can make bonds with metal oxide through either oxygen (O) atoms or metal (A) atoms that composed of the oxide. Examples of the identification of an element at the interface in atomic level using photoelectron spectroscopy have been demonstrated for alumina, zinc oxide and cerium oxide. Software, which predicts interface bonding according to a method developed by the author, and which is open to public, is presented. It is demonstrated that the difference in the interface bonding species has great influence on the band offset, the energy difference between the Fermi level and the valence band in the band energy diagram. The observations of such difference in band offset using photoelectron spectroscopy are also provided.