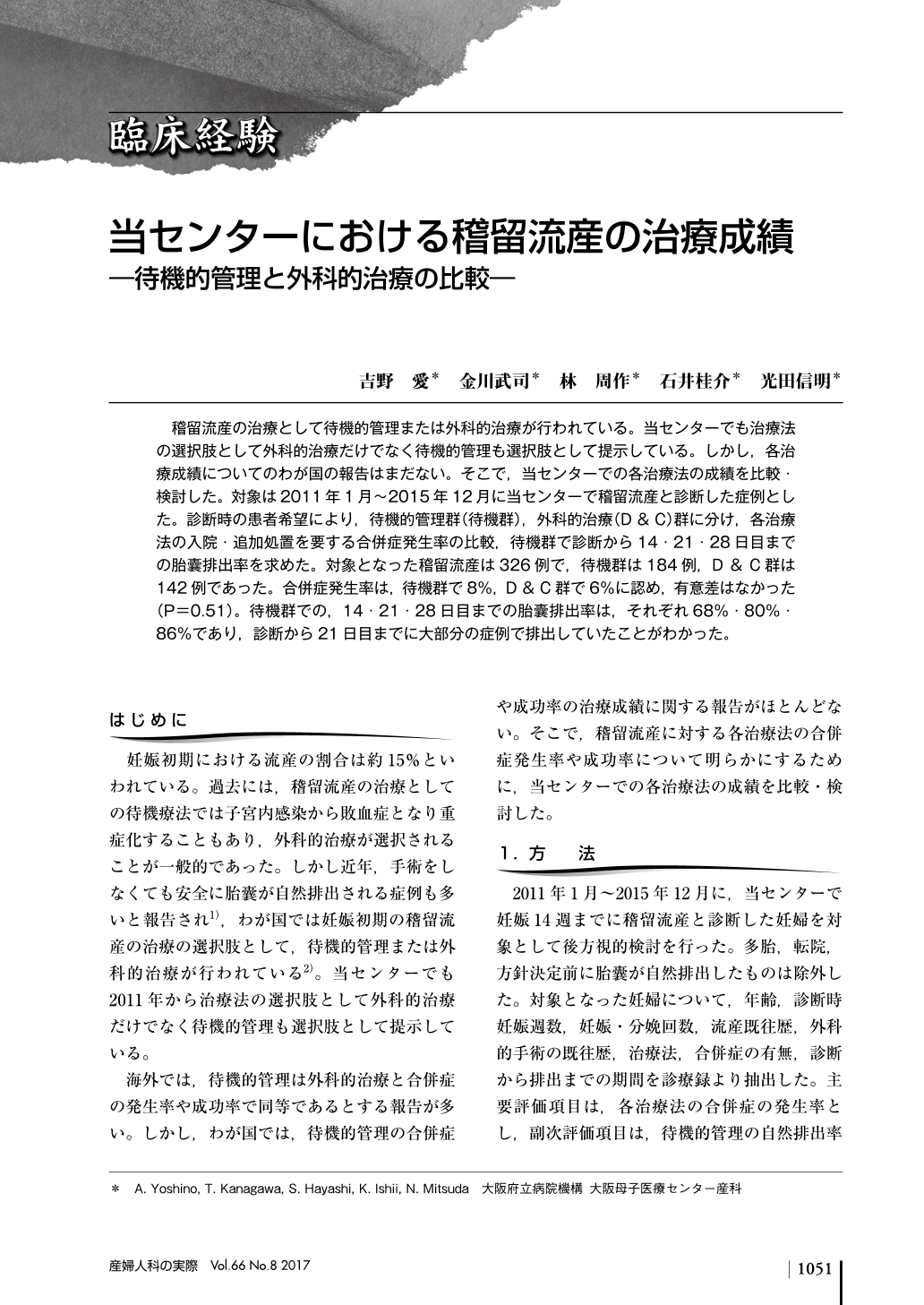- 著者
- 吉成 知也 渡辺 麻衣子 大西 貴弘 工藤 由起子
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品衛生学会
- 雑誌
- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.4, pp.119-125, 2020-08-25 (Released:2020-10-02)
- 参考文献数
- 27
フモニシンはフザリウム属菌が生産するカビ毒で,主にトウモロコシやその加工品に検出される.近年,遊離型のフモニシンに加え,そのモディファイド化合物もトウモロコシ加工品に存在することが報告されてきた.モディファイドフモニシンの毒性や汚染実態については明らかになっていないことが多い.本研究では,日本人の健康に対するモディファイドフモニシンのリスクを評価するために,日本に流通するトウモロコシ加工品に含まれるモディファイドフモニシンを解析した.食品検体中の遊離型とモディファイドフモニシンをまとめてアルカリ処理し,加水分解フモニシンへと変換し,LC-MS/MSで定量した値を全フモニシン量とした.コーンフレーク,コーンスナック,コーンフラワーおよびコーンスープにおける全フモニシン量は,遊離型フモニシンに対してそれぞれ4.7,2.8,2.1および1.2倍であった.全フモニシン量を用いて日本人におけるコーンスナックとコーンフレークからのフモニシンの一日平均摂取量を算出した結果,遊離型フモニシンを用いて算出した場合の3倍となった.これらの結果より,フモニシンの真のリスクを評価するためには,モディファイドフモニシンも含める必要があると考えられた.
- 著者
- 中島 崇行 大塚 健治 富澤 早苗 増渕 珠子 八巻 ゆみこ 上條 恭子 吉川 聡一 髙田 朋美 小鍛治 好恵 渡邊 趣衣 大澤 佳浩 橋本 常生
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品衛生学会
- 雑誌
- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.4, pp.154-160, 2020-08-25 (Released:2020-10-02)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 2
食品中の残留農薬分析において,ある農薬の定量値が正しいかどうかを確認するため,異なる機器を使用して定量値の確認を行うことがしばしばあるが,それぞれの機器の値が完全に一致することは珍しい.本研究では,食品毎にどの程度違いがあるかを比較するため,当研究室の日常検査法を用い,121成分,6種類(グレープフルーツ,ばれいしょ,パプリカ,キャベツ,ほうれんそう,玄米)の食品について,GC-MS/MSおよびLC-MS/MSそれぞれの機器で妥当性評価を実施し,その結果を主に真度に着目して比較した.その結果,GC-MS/MSでは,上述の食品において97,111,110,118,111,63成分が基準に適合した.一方LC-MS/MSでは,50,114,103,112,100,103成分が基準に適合した.これら両機器の結果の差は,主にマトリクス効果によるものだと考えられ,マトリクス効果の補正によりそれぞれの真度は近似した.しかし真度の一致度については食品試料による差が大きく,特に玄米ではマトリクス効果を補正しても両機器の真度の差は20%以上であった.
- 著者
- 添田 直樹 久保 拓真 根本 幾
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告 : 信学技報 (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.111, no.367, pp.27-29, 2011-12-20
音楽聴取時における,注意の脳活動に対する影響を測定するために,音色(timbre)注意,旋律線(melody注意時のfMRIを撮像し,統計解析を行った.4種類の旋律,3種類の音色を組合せた第1フレーズ(non-manipulated)を作成した.それと比較するために第1フレーズに「変化をさせない」「旋律の1音のみを変化させる」「音色のみを変化させる」「音色と旋律の1音を変化させる」いずれかの操作をした第2フレーズ(manipulated)を続けて配置した.ただし,第2フレーズは第1フレーズより全音高くした.被験者にはランダムに配置した2フレーズ(第1フレーズ+第2フレーズ)を続けて聞かせ,2フレーズの間の違い(全音の違いは考慮しない)の有無を判断させた.コントロール刺激としてホワイトノイズを使用した.14人の被験者のグループ検定で,音色注意時,旋律線注意時で共通する賦活部位は,一次聴覚野を含む左右の上側頭回であった.旋律注意時のみに賦活する部位は,左の運動前野であった.音色注意時のみ賦活する部位は見られなかった.
1 0 0 0 福山市内で市販される乳および乳飲料のアフラトキシンM1汚染調査
- 著者
- 小野 高明 上田 三都子 辻 正康 川本 千代実 山根 伸久
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品衛生学会
- 雑誌
- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.4, pp.148-153, 2020-08-25 (Released:2020-10-02)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1
福山市内を流通する乳のアフラトキシンM1 (AFM1)汚染と時期および地域による関連性を知るため,2018年6月~2019年1月にかけて夏期および冬期の各1回調査を行った.また,AFM1汚染の知見が少ない乳飲料について,福山市内を流通する同時期の乳飲料のAFM1汚染度を乳と比較した.結果はすべての乳でAFM1の基準値(0.5 μg/kg)未満となった.時期別の比較では夏期の牛乳1検体がEUの基準値(加熱処理乳:0.050 μg/kg)を超える濃度(0.07 μg/kg)を示したが,AFM1汚染度に有意差はなかった(p>0.05).地域別の比較では,乳のAFM1汚染度について冬期は中国地方のほうがその他地方より有意に高く,夏期は有意に低かった.乳のAFM1汚染は,時期または地域による直接的な関連性があるわけではなく,供与する飼料の種類,量,管理方法による影響を受けると考えられた.乳および乳飲料の比較では,乳飲料のAFM1汚染度のほうが有意に低かった(p<0.01).夏期の乳飲料1検体から最も高濃度(0.08 μg/kg)のAFM1を検出した.乳飲料のAFM1汚染は,原材料の汚染の程度,それらの配合割合および加工による影響を受けると考えられ,製品の無脂乳固形分の増加がAFM1汚染の増加要因となると推定された.
1 0 0 0 LC-MS/MSを利用した迅速簡便な6種類防かび剤分析法の開発
- 著者
- 吉光 真人 上野 亮 松井 啓史 小阪田 正和 内田 耕太郎 福井 直樹 阿久津 和彦 角谷 直哉
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品衛生学会
- 雑誌
- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.4, pp.143-147, 2020-08-25 (Released:2020-10-02)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 1
われわれはLC-MS/MSを用いた迅速簡便な6種類防かび剤分析法を開発した.イマザリル,o-フェニルフェノール,チアベンダゾールに加えて,2011年以降に防かび剤としての利用が認められたフルジオキソニル,アゾキシストロビン,ピリメタニルを測定対象とした.迅速かつ簡単な分析法の確立を目指し,残留農薬分析法と抽出操作を共通化した.また,試料からの抽出液1 mLを充填剤量500 mgのOasis HLBカラムに負荷,アセトニトリル8 mLで溶出する精製法を採用した.次いで,オレンジ,グレープフルーツ,レモンに6種類の防かび剤を添加して添加回収試験を行ったところ,真度は89.7から100.0%,室内精度および併行精度はそれぞれ,1.5から5.0%,0.5から4.9%となり,食品中に残留する農薬等に関する試験法の妥当性評価ガイドラインの目標値を達成した.定量限界は,o-フェニルフェノールでは1 mg/kg,その他の防かび剤では0.2 mg/kgとなり,防かび剤の基準値よりも低い値であった.本分析法の有用性を確認するため,2017~2019年に市販柑橘類の分析を行ったところ,検出された防かび剤は表示との整合性が確認された.また,基準値を超過する濃度の防かび剤が検出された検体はなかった.
1 0 0 0 牛胆嚢内胆汁のカンピロバクター汚染状況と分離株の性状
- 著者
- 佐々木 貴正 岩田 剛敏 上間 匡 朝倉 宏
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品衛生学会
- 雑誌
- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.4, pp.126-131, 2020-08-25 (Released:2020-10-02)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 3
カンピロバクターは,食品媒介性感染症における最も重要な原因菌の1つである.カンピロバクター感染症の際に抗菌薬が使用されることは稀であるが,症状が重度である場合や長期間持続する場合には使用されることがある.カンピロバクター感染症の原因の1つは,カンピロバクターに汚染された牛肝臓の喫食である.牛肝臓は,と畜場において胆汁により表面と内部が汚染される可能性がある.以上のことから,われわれは,と畜場において,胆汁のカンピロバクター汚染状況およびその分離株の性状を調査した.カンピロバクターは35.7%(55/154)から分離され,C. jejuniとC. fetusが上位2菌種であった.C. jejuniでは,テトラサイクリン(63.0%)とシプロフロキサシン(44.4%)に高率な耐性が認められた.Multi-locus sequence typingにより,C. jejuniは12型に分類され,ST806が最も多く,37.0%を占めていた.すべてのC. fetusは全身性疾患の原因となることがあるC. fetus subsp. fetusと同定された.C. fetusでは,シプロフロキサシン(66.6%),ストレプトマイシン(58.3%)およびテトラサイクリン(33.3%)に高率な耐性が認められた.すべてのC. fetusは,ST3 (16株)およびST6 (8株)に分類された.16株のST3のうち,15株(93.8%)はストレプトマイシンとシプロフロキサシンの両方に耐性であった.本調査結果は,牛胆汁の高率なカンピロバクター汚染とその分離株の高率な薬剤耐性を示していている.と畜場における牛肝臓の胆汁汚染防止は,カンピロバクター感染のリスク低減策の1つである.
1 0 0 0 OA 物研連報告
- 著者
- 久保 亮五
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.12, pp.918, 1985-12-05 (Released:2020-06-17)
1 0 0 0 OA 腰椎前彎の増強に関与する短縮筋の影響
- 著者
- 近藤 敏朗 清家 矩彦 鶯 春夫 岡 陽子 唐川 美千代 平島 賢一 別部 隆司 嶋田 悦尚
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.31 Suppl. No.2 (第39回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.C0247, 2004 (Released:2004-04-23)
【はじめに】 今回、姿勢性腰痛症の患者を対象として、腰椎前彎の増強因子となる短縮筋に着目し、どのような筋の短縮が腰椎前彎に影響しているのかを検討したので、若干の考察を加え報告する。【対象及び方法】 当院外来患者のうち、1)腰痛症と診断され、股関節・膝関節疾患の既往歴がなく神経症状を訴えていない者、2)大井らによる腰仙角測定法で、30°以上の腰椎前彎の増強がみられる者、3)Kraus-Weberテスト変法大阪市大方式で体幹筋力が40点以上である者12名を対象とした。性別は男性4名、女性8名、年齢は46.6±10.1歳であった。 方法は、指床間距離(以下、FFD)、SLR、トーマステスト、尻上り現象を測定した。それぞれの異常値は、FFDは0cm未満、SLRは90°未満、トーマステストは陽性を異常、伸張時痛がみられる場合を制限、尻上り現象は陽性を異常、踵が臀部につかない場合を制限とした。【結果】 異常が認められた者は、FFD:6名、SLR:5名、トーマステスト:異常0名、制限5名の計5名、尻上り現象:異常5名、制限6名の計11名となった。特に、トーマステストが制限なしの場合でも、尻上り現象ではほとんどの患者に異常が認められた。この結果より、主に短縮が認められた筋は大腿直筋であると考えられた。 また、腰仙角が40°未満の者でFFD、SLR、トーマステストの項目に問題がない場合でも、尻上り現象に異常又は制限がみられる者は4名中全員であったが、腰仙角が40°以上の者では、ほとんどの項目に異常又は制限が認められた。今回の対象者では、トーマステストは正常でも尻上り現象は異常というような者やFFDが異常でもSLRは正常といったような者がみられた。このことより、腰仙角が40°未満の患者ではハムストリングスや腸腰筋等の短縮よりも、大腿直筋や腰背筋群の短縮が腰椎前彎により影響していることが示唆された。【考察】 今回の結果より、ハムストリングスや腸腰筋等の短縮よりも、大腿直筋や腰背筋群の短縮が腰椎前彎により影響していることが示唆された。また、今回の対象者はKraus-Weberテスト変法大阪市大方式により体幹の筋力低下を除外しているため、体幹の筋力低下がなくても腰椎前彎の増強は起こることが考えられた。 ゆえに、腰仙角が40°以上で短縮筋が多くみられるような場合を除き、ハムストリングス・腸腰筋のストレッチングよりも、大腿直筋・腰背筋群のストレッチングを重点的に行う治療体操が適していると考えられる。なお、今回の研究では、実際の治療効果を判定することが出来なかったため、今後の課題としては、実際の治療により腰椎前彎ならびに腰痛症が改善されたかを追及していくことと考えている。
1 0 0 0 OA 多面的指標を用いた競技場面での集中状態からみるメンタルトレーニングの効果
- 著者
- 笹塲 育子 上田 智章 山森 信人 佐久間 春夫
- 出版者
- 日本バイオフィードバック学会
- 雑誌
- バイオフィードバック研究 (ISSN:03861856)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.1, pp.3-17, 2016 (Released:2017-10-29)
- 参考文献数
- 32
今日, 競技力向上に必要不可欠な一側面として心理面の強化が世界的に認知されており, メンタルトレーニングはその代表的なアプローチの一つである. その効果については, 定性的・定量的両側面からの評価が望ましいが, 未だ多くがアスリートの主観的な報告に留まっており課題である. また, 世界レベルのエリートアスリートが体験している高強度なプレッシャーについて, 実験室と実際の競技現場では大きなギャップが生じていることに着目する必要がある. そこで本研究では, 実験室で習得されたメンタルスキルが実際の競技場面においてどのように応用され機能しているのかについて, パフォーマンス直前の集中状態を含めたメンタルトレーニングの効果を明らにすることを目的とした. 実験1では, エリートアスリート (個人採点競技種目オリンピック代表選手1名) を対象に実験室において20日間の呼吸法トレーニングを実施し, さらに競技場面への応用について検証した. 実験室場面および競技場面でのトレーニング効果は, 生理的指標, パフォーマンス指標, 内省報告の多面的な側面から検討を行った. さらに, 実験1の結果に基づいて実験2では, 類似した競技特性を持つ学生選手への適用を試みた. 結果, 生理的指標からはStress Eraser (SE) ポイントの増大および呼吸数の減少により呼吸法トレーニングの効果が実証された. 加えて, パフォーマンス指標からは呼吸法トレーニングの実施が競技成績の向上に役立ちパフォーマンス直前の適切な集中状態をつくりあげるセルフコントロールスキルの一つとして機能していたことが示唆された. 最後に, 内省報告からは, アスリートが主観的に感じていた呼吸法習得過程の困難さやトレーニング効果, また実験室場面と競技場面とのズレが, SEポイントや呼吸数などの生理的指標の結果と一致していたことなどが明らかとなった.
1 0 0 0 OA ヨトウガの生活史と夏眠
- 著者
- 正木 進三 境 隆
- 出版者
- 日本応用動物昆虫学会
- 雑誌
- 日本応用動物昆虫学会誌 (ISSN:00214914)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.3, pp.191-205, 1965-09-25 (Released:2009-02-12)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 22 30
ヨウトガの生活史と休眠については,すでにかなりの知見がある。それらを検討してみると,本州以南の個体群においては,休眠性を左右する光周期反応の分析結果と生活史の野外観察の結果との間に一致しない点がある。これは春夏世代のさなぎの特性-夏眠-についての理解が不充分なためであると考えられるので,弘前産のヨトウガを用いて夏眠と環境条件との関係を分析し,また北海道や本州南部からえた材料と比較した。その結果,ヨトウガのさなぎの発育には,不休眠,夏型休眠,冬型休眠の3様式があることが確かめられた。幼虫期の短日処理によって冬型休眠がえられるが,長日処理をうけると不休眠あるいは夏型休眠のいずれかの発育様式をとる。長日下に生じたさなぎの夏眠率と夏眠の長さは環境および遺伝的要因によって支配されている。高温では夏眠率も夏眠期間もともに増加するが,温度の低下につれて夏眠は弱まり,ある限界温度以下になるとまったく消失してしまう。また北の系統は夏眠の遺伝的能力が低いが,南下するにつれて個体群の性質は夏眠強化の傾向を示す。夏眠に対する幼虫期の環境の影響は未知の点が多いが,一応以上の知見にもとづいて,日本列島におけるヨトウガの生活史の地理的勾配変異の様相を模式的に描いた。
1 0 0 0 OA 熟成に及ぼす湿度の影響 ウィスキーの熟成に関する研究 (第3報)
- 著者
- 蓮尾 徹夫 斎藤 和夫 寺内 敬博 蓼沼 誠 佐藤 信
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.12, pp.966-969, 1983-12-15 (Released:2011-11-04)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 3
同一樽内に入れたエチルアルコール水溶液を温度15℃ 湿度を46%, 61%, 93%の3つにかえた1年間の貯蔵試験を行った結果, 湿度の低い場合には樽内のアルコール濃度は高くなり, 湿度の高い場合には樽内のアルコール濃度は低くなった。酢酸, 酢酸エチル, アセトアルデヒドは貯蔵中に増加するが湿度による影響は少なかった。フェノール化合物, 紫外部吸収, 着色度は時間とともに増加するが, 揮散量を補正した条件では, 湿度の低いところで最も少なかった。官能検査では条件Aが最も良く次いでB, Cの順となった。特にCは良好とはいえなかった。このことより熟成によるウイスキーの良化にはある程度の揮散を伴う条件が必要であることがわかった。最後にMOラクトンの合成をはじめとし, 本研究遂行に当り種々御教示いただきました大阪国税局鑑定官室吉沢淑室長に深謝いたします。
稽留流産の治療として待機的管理または外科的治療が行われている。当センターでも治療法の選択肢として外科的治療だけでなく待機的管理も選択肢として提示している。しかし,各治療成績についてのわが国の報告はまだない。そこで,当センターでの各治療法の成績を比較・検討した。対象は2011 年1 月〜2015 年12 月に当センターで稽留流産と診断した症例とした。診断時の患者希望により,待機的管理群(待機群),外科的治療(D & C)群に分け,各治療法の入院・追加処置を要する合併症発生率の比較,待機群で診断から14・21・28 日目までの胎囊排出率を求めた。対象となった稽留流産は326 例で,待機群は184 例,D & C 群は142 例であった。合併症発生率は,待機群で8%,D & C 群で6%に認め,有意差はなかった(P=0.51)。待機群での,14・21・28 日目までの胎囊排出率は,それぞれ68%・80%・86%であり,診断から21 日目までに大部分の症例で排出していたことがわかった。
1 0 0 0 OA マイクロホン感度の単一指向性を利用する3次元音源方向の検出
- 著者
- 岡田 徳次 佐藤 秀幸 三富 堅太郎
- 出版者
- The Society of Instrument and Control Engineers
- 雑誌
- 計測自動制御学会論文集 (ISSN:04534654)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.1, pp.13-20, 2001-01-31 (Released:2009-03-27)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 2
This paper proposes the measurement principle of a sound source direction in the three-dimensional space. Such kind of differences like the transferring time, phase shift, and level of the sound wave are treated for the measurement in general. Our approach is to use the differences of sound levels by taking the advantage of unidirectional characteristics of the condenser microphone's sensitivity so that the direction is obtained by the simple signal processing. Basically the minimum number of the microphone set is four for composing a tetrapod arrangement. Formulation of the relations among the differences of the sound levels is shown. Also, the logical processing is introduced to remove the affect of the microphone's backside undesirable irregular sensitivity. The calculation procedure for determining the direction is extracted, and experimental results are shown to verify the validity of the measurement.
1 0 0 0 OA 明冶期における芸術概念とその社会的機能 : 旧派洋画家とパノラマ館を中心に
- 著者
- 蔵屋 美香
- 出版者
- 美術科教育学会
- 雑誌
- 美術教育学:美術科教育学会誌 (ISSN:0917771X)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.265-274, 1991-12-31 (Released:2017-06-12)
1 0 0 0 毛染めブリーチ中の過硫酸塩によるアナフィラキシーの1例
36歳,女性,美容師。毛染めブリーチの使用直後に全身性のアナフィラキシー症状が出現した。プリックテストで毛染めブリーチ中に含まれている過硫酸塩が陽性を示したため,自験例を同剤によるアナフィラキシーと診断した。過硫酸塩は,遅延型アレルギーによる接触皮膚炎および即時型アレルギーでは吸入による喘息症状をきたしやすいことが知られているが,即時型反応の機序で接触により生じる接触蕁麻疹ないしアナフィラキシーの報告は少なく,とりわけ日本人における発症はまれである。しかし本邦でも,毛染めブリーチ剤の使用によって過硫酸塩による接触蕁麻疹ないしアナフィラキシーがおこりうることに留意するべきである。
1 0 0 0 IR 検索エンジン「百度」の検索結果から見た中国語の時間詞と時刻表現
- 著者
- 小出 敦
- 出版者
- 京都産業大学
- 雑誌
- 京都産業大学論集 人文科学系列 (ISSN:02879727)
- 巻号頁・発行日
- no.42, pp.87-96, 2010-03
1.はじめに2.検索条件と検索の対象3.検索結果4.各時間詞が指す時間の範囲5.学習者のための時間詞と時刻表現の表
1 0 0 0 IR 3世紀におけるゴート人の侵入
- 著者
- 井上 文則
- 出版者
- 京都大学大学院文学研究科
- 雑誌
- 西洋古代史研究 = Acta academiae antiquitatis kiotoensis = The Kyoto journal of ancient history (ISSN:13468405)
- 巻号頁・発行日
- no.13, pp.1-23, 2013
3世紀においてゴート人は, ローマ帝国に繰り返し侵入し, 251 年には時の皇帝デキウスを敗死させるなどの深刻な事態を帝国にもたらした. この時期のゴート人の侵入を巡っては, その侵攻が何時, 何度あったのか, といった基本的な事実についてすら論争があるが, 本稿では特に3世紀におけるゴート人の侵攻の性格は, いったいどのようなものであったのか, さらにはそもそも当時のゴート人とはどのような集団であったのかという問題を考察の中心に据えて議論を行い, 併せてこの時期の侵入がゴート, ローマの双方にもった歴史的意義について考察を加えた. 考察の結果, ゴート人は, 通説が考えてきたようなバルト海南岸からの移住民ではなく, フランク人やアレマンニ人同様, 黒海北岸の地で3 世紀に新たに形成された民族であったこと, また, その侵入は単なる略奪を目的としたものであったとはいえ, 3 世紀の一連の侵入を通してゴート人が形成されていったことが明らかになった. ゴート人の侵入を促したのは, ササン朝の攻撃を受けて混乱するローマ帝国であったのであり, この意味では帝国の混乱がゴート人の形成, 強大化に寄与したのであった. ただし, 3世紀においては未だ, ゴート人は黒海北岸における支配的な集団ではなく, ローマ帝国への侵入に際しても, 侵入者の一部を構成していたにすぎないと考えられることも指摘した.In the third century, the Roman Empire was repeatedly invaded by the Goths. In 251, the Emperor Decius was defeated and killed in Abrittus by the Gothic king Cniva; from the late 250's on, the Goths again and again attacked the cities of Asia Minor from the sea; and in 268 the Goths carried out a large scale invasion, reaching as far as the Aegean Sea. According to A. Alföldi and P. Heather, the Goths appeared in the Black Sea region during the third century, having migrated from the Baltic Sea region. Through the impetus of these migrations, the Goths invaded the Roman Empire through a series of raids. In this article, by examining each of these invasions individually, the author draws the following conclusions: Firstly, that the Goths were not newcomers in the Black Sea region but formed in that region, similarly to the Franks and Alammani, and that they raided the Empire not through the impetus of migrations but by taking advantage of the military crisis caused by the Sassanids. It is no coincidence that the Sassanid civil war in the 270s began when the Gothic invasions ended. Secondly, that during the third century, the Goths were no more than one of many invaders of the Roman Empire. It was probably not until the fourth century that the Goths became the dominant power in the Black Sea region, and we must be cautious not to adopt a Goths-centric view.
1 0 0 0 OA クラウドコンピューティングを統合するソフトウェア開発方法論
クラウドコンピューティングを統合する開発技術に関する次の成果を得た.1)Linked Dataを用いたクラウドデータ連携アーキテクチャの提案とプロトタイプによる実証評価.2)構成定義言語TOSCAを用いたクラウド連携の設計方法論の提案とプロトタイプによる実証評価.これらの成果はクラウドコンピューティングに関する国際会議等で論文として発表している.さらに,Linked Dataを用いて複数組織間でデータを連携するためのインタフェース仕様を開発し,実証実験で有効性を示した.これは,国際標準化団体OASIS内にTCを設置し,本研究代表者が議長として国際標準化を進めている.
- 著者
- 佐久間 由梨
- 出版者
- 専修大学人文科学研究所
- 雑誌
- 専修大学人文科学研究所月報 = Senshu University Institute of Humanities monthly bulletin (ISSN:03878694)
- 巻号頁・発行日
- no.293, pp.25-48, 2018-05