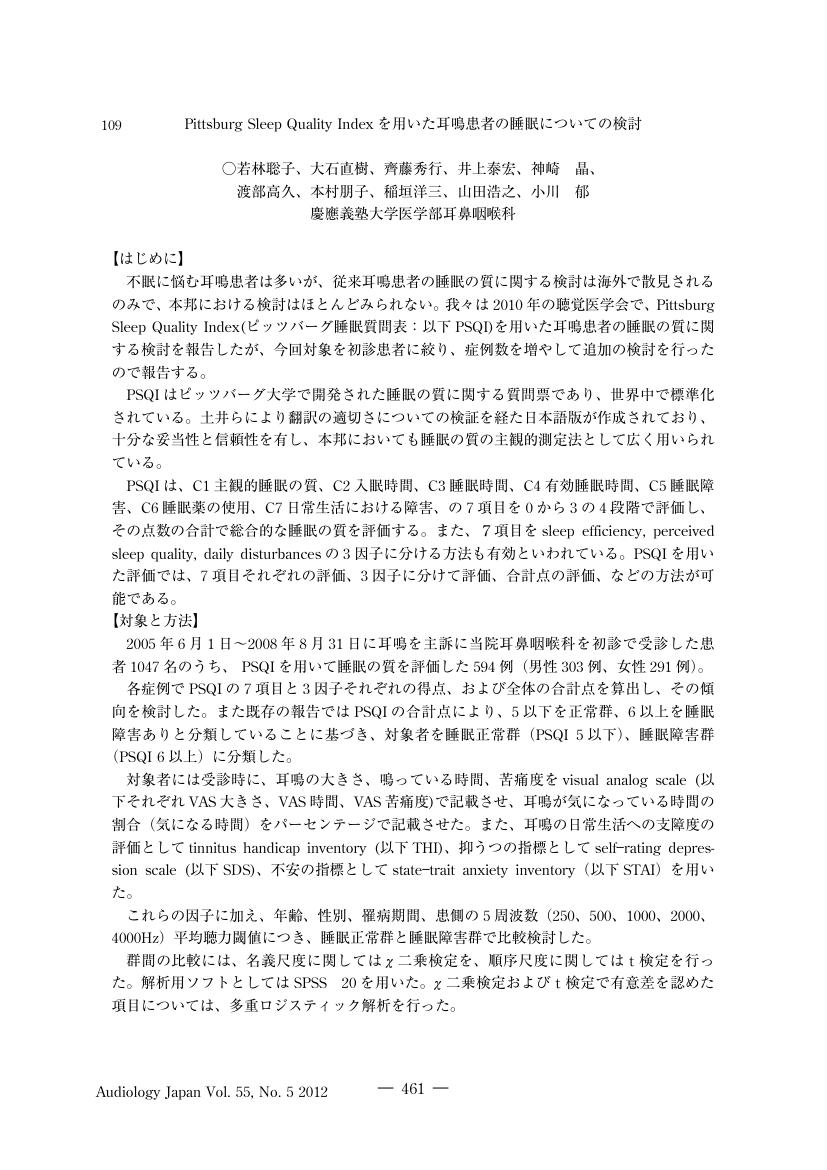1 0 0 0 IR <論文>視線パターンと選択行動との関連性-戦略形ゲームにおけるアイトラッカー実験-
- 著者
- 栗原 崇 小林 伸
- 出版者
- 早稻田大學政治經濟學會
- 雑誌
- 早稻田政治經濟學雜誌 (ISSN:02877007)
- 巻号頁・発行日
- no.389, pp.2-17, 2016-03-31
1 0 0 0 OA VCG-equivalent in Expectationメカニズム
- 著者
- 藤田 悦誌 岩崎 敦 東藤 大樹 横尾 真
- 出版者
- 日本ソフトウェア科学会
- 雑誌
- コンピュータ ソフトウェア (ISSN:02896540)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.3, pp.3_156-3_167, 2014-07-25 (Released:2014-09-10)
本論文では,新しい公開型オークションメカニズムのクラスとして,VCG-equivalent in expectationメカニズムを提案する.正直な戦略の組が事後ナッシュ均衡となる公開型オークションメカニズムはクエリの回答が回答者の財の割当と支払額に影響を与えない無関係なクエリを送信する必要がある.露呈される情報に関して参加者が弱い誘因を持つ場合,無関係なクエリを送信するメカニズムは望ましくない.本論文で新しく提案するVCG-equivalent in expectationメカニズムは,割当はVickrey-Clarke-Groves (VCG)メカニズムと等しく,支払額はVCGの支払額の期待値とするメカニズムである.本論文では,VCG-equivalent in expectationメカニズムにおいて,正直な戦略の組が逐次的均衡となること,及び,無関係なクエリを送信しないVCG-equivalent in expectationメカニズムを構築する手法を示した.さらに,提案メカニズムの現実的な応用事例への適用可能性を示すため,日本の第四世代の周波数オークションに適用可能なメカニズムを示した.
- 著者
- 若林 聡子 大石 直樹 齊藤 秀行 井上 泰宏 神崎 晶 渡部 高久 本村 朋子 稲垣 洋三 山田 浩之 小川 郁
- 出版者
- 一般社団法人 日本聴覚医学会
- 雑誌
- AUDIOLOGY JAPAN (ISSN:03038106)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.5, pp.461-462, 2012 (Released:2013-12-05)
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- 宇野 重規
- 出版者
- 信山社
- 雑誌
- 法と哲学 = Law and philosophy = Droit et philosophie = Recht und Philosophie (ISSN:2188711X)
- 巻号頁・発行日
- no.6, pp.45-54, 2020-05
1 0 0 0 現代刑法の理論と実務[各論](第8回)強盗の罪
- 著者
- 松宮 孝明
- 出版者
- 日本評論社
- 雑誌
- 法学セミナー (ISSN:04393295)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.5, pp.99-105, 2020-05
- 著者
- 松宮 孝明
- 出版者
- 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 = Trends in the sciences (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.5, pp.58-63, 2020-05
1 0 0 0 現代刑法の理論と実務[各論](第10回)詐欺・恐喝の罪(2)
- 著者
- 松宮 孝明
- 出版者
- 日本評論社
- 雑誌
- 法学セミナー (ISSN:04393295)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.7, pp.99-105, 2020-07
- 著者
- 松宮 孝明
- 出版者
- 日本評論社
- 雑誌
- 法律時報 (ISSN:03873420)
- 巻号頁・発行日
- vol.92, no.8, pp.128-131, 2020-07
1 0 0 0 現代刑法の理論と実務[各論](第11回)背任の罪
- 著者
- 松宮 孝明
- 出版者
- 日本評論社
- 雑誌
- 法学セミナー (ISSN:04393295)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.8, pp.116-122, 2020-08
- 著者
- 松宮 孝明
- 出版者
- 日本評論社
- 雑誌
- 法学セミナー (ISSN:04393295)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.9, pp.99-104, 2020-09
1 0 0 0 OA 傷害胃粘膜における酸分泌変化と調節機序
- 著者
- 竹内 孝治 加藤 伸一 香川 茂
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.120, no.1, pp.21-28, 2002 (Released:2003-01-28)
- 参考文献数
- 40
胃粘膜に軽微な傷害が発生した場合,酸分泌は著しく減少し,胃内アルカリ化が生じる.このような酸分泌変化は非ステロイド系抗炎症薬ばかりでなく,一酸化窒素(NO)合成酵素阻害薬の前処置によっても抑制される.特にNO合成酵素阻害薬の存在下に胃粘膜傷害を発生させた場合,胃酸分泌は“減少反応”から“促進反応”に転じ,この変化はヒスタミンH2拮抗薬,肥満細胞安定化薬,および知覚神経麻痺によって抑制される.すなわち傷害胃粘膜では,プロスタグランジン(PG)およびNOを介する酸分泌の抑制系に加えて,粘膜肥満細胞,ヒスタミンおよび知覚神経を介する酸分泌の促進系も活性化されており,両者のバランスによって傷害胃での酸分泌反応が決定されている.通常は抑制系が促進系を凌駕しているために“酸分泌減少”として出現するが,NO合成阻害薬では抑制系が抑制される結果,促進系が顕在化し,“酸分泌促進”を呈する.傷害発生に伴い管腔内に遊離されてくるCa2+はNO合成酵素の活性化において必要であり,管腔内Ca2+の除去も胃内アルカリ化を抑制する.興味あることに,PGは傷害胃の酸分泌変化において両面作用を有しており,“抑制系”の仲介役に加えて,“促進系”の促通因子としての作用も推察されている.また,傷害胃で認められる酸分泌変化に関与するPGやNOはそれぞれCOX-1およびcNOS由来のものであり,傷害後に認められる胃内アルカリ化は選択的COX-2阻害薬やiNOS阻害薬によっては影響されない.このように,傷害胃粘膜の酸分泌反応は正常胃粘膜とは明らかに異なり,内因性PGに加えて,NO,ヒスタミン,知覚神経を含めた複雑かつ巧妙な調節系の存在が推察される.このような酸分泌変化は障害発生に対する適応性反応の一つであり,傷害部への酸の攻撃を和らげることにより,傷害の進展を防ぎ,損傷部の速やかな修復を促す上で極めて重要である.
1 0 0 0 OA 腹式呼吸(横隔膜呼吸)効果の検討
- 著者
- 松尾 善美 山本 洋史 米田 稔彦 三木 明徳
- 出版者
- 一般社団法人 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会
- 雑誌
- 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌 (ISSN:18817319)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.2, pp.300-306, 2003-12-20 (Released:2018-04-10)
- 参考文献数
- 25
腹式呼吸(横隔膜呼吸)により,1回換気量の増加,呼吸数・酸素換気当量・死腔換気率の減少,さらにPaO2 上昇やPaCO2 減少が報告されている.呼吸補助筋の収縮抑制と胸腹部運動の同期性を伴った意識下での呼吸コントロールが成功したときに,腹式呼吸は,換気効率を改善し,呼吸困難感を緩和する可能性がある.しかし,安定期COPD患者では,必ずしも完全な腹式呼吸パターン習得がその目標にはならない.
- 著者
- Zhichao Ma Jie Qi Li Gao Jun Zhang
- 出版者
- International Heart Journal Association
- 雑誌
- International Heart Journal (ISSN:13492365)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.5, pp.1022-1033, 2020-09-29 (Released:2020-09-29)
- 参考文献数
- 41
- 被引用文献数
- 7
Cardiac hypertrophy is one of the significant risk factors that result in maladaptive cardiac remodeling and heart failure, and exercise is known to exert cardioprotection. In this research, the cardioprotective function and exercise mechanisms were explored.The rats underwent transverse aortic constriction (TAC) or a sham operation. The rats that received TAC were randomly assigned to five groups: (1) rats subjected to a sham operation as control group (SC), (2) rats that underwent TAC group (TC), (3) TAC and moderate-intensity exercise group (TE), (4) TE plus 3-MA group (TEM), and (5) TE plus Compound C group (TEC). The heart function was measured via echocardiography. Histological analysis and relative protein testing were conducted to analyze collagen deposition and apoptosis. Furthermore, western blot was employed to measure the protein expression of relevant signaling pathways. Impaired cardiac function, interstitial fibrosis, enhanced apoptosis, and ER stress were observed in the TAC-induced left ventricular hypertrophy. Exercise attenuated TAC-induced cardiac dysfunction, interstitial fibrosis, and ER stress-related apoptosis. In addition, exercise significantly improved autophagy and upregulated AMPK phosphorylation. Furthermore, AMPK inhibitor Compound C repressed the activation of AMPK, and autophagy inhibitor 3-methyladenine reversed exercise-induced autophagy. All of these abolished the protection of exercise against cardiac dysfunction and fibrosis induced by TAC.Our results indicated that 4 weeks of treadmill exercise could alleviate pressure overload-induced LV dysfunction and remodeling via an autophagy-dependent mechanism, which was induced by enhancing autophagy through the activation of AMPK.
1 0 0 0 OA 拡張された自然神学の具体化としての「科学技術の神学」─東アジアの文脈で─
本研究は、拡張された自然神学を、科学技術と東アジアという二つの文脈で具体化するという研究目的にむけて進められてきた。まず、科学技術の文脈。特に、原子力、脳科学、AI、遺伝子工学といった現代において問題化しつつある諸問題について、宗教思想(特にキリスト教思想)との接点が人間理解(人格概念)にある点が明らかになった。科学技術の神学においては倫理学から文明論までがその射程に入れられねばならない。次に、東アジアの文脈。その成果は、『東アジア・キリスト教研究とその射程』としてまとめられた。無教会キリスト教、特に矢内原忠雄の原子力論において、科学技術と東アジアの二つの文脈を結びつける可能性が示された。
1 0 0 0 日本のカトリック殉教者と歴史的記憶
- 著者
- 芦名 定道 TRONU MONTANE CARLA
- 出版者
- 京都大学
- 雑誌
- 特別研究員奨励費
- 巻号頁・発行日
- 2016-11-07
トロヌ・カルラ外国人特別研究員との共同研究では、2018年度も外国人特別研究員によって日本国内と海外において活発な研究発表がなされたが、受入研究者の側の研究を含めるならば、次の4点に、研究成果をまとめることができる。(1)キリシタン時代のキリスト教を担ったイエズス会について、その宣教方針である「適応主義」を、キリスト教思想における「適応の原理」として取り出すことができ、また諸修道会における日本人殉教者の顕彰の在り方についてもその実態の比較検討がなされた。(2)キリシタン研究を東アジアのキリスト教研究へと方法論的に関連付けること、また、その中に東アジアにおけるカトリック諸修道会の動向を結びつけることが試みられた。これは重要な成果である。(3)キリシタン殉教を、江戸幕府の宗教政策を経て、明治から現代までのキリスト教思想史につなぐことがなされた。これは、以下に述べるパネル発表で論じられ、論文化された。(4)現代の記憶論・証言論を参照しつつ、現代キリスト教思想における殉教論の可能性を考察した。これについても、次に述べるパネル発表で論じられ、論文化された。共同研究はさまざまな成果を生みだしたが、最大の成果は、次のパネル発表とその論文化である。パネル発表は、日本宗教学会・第77回学術大会(大谷大学、9月9日)において、「日本におけるキリシタン殉教者の歴史的記憶」として実施された。このパネルは、外国人特別研究員と受入研究者のほかに、淺野淳博氏(新約聖書学者)と狭間芳樹氏(キリシタン研究者)を加え、4名の発表者によって、構成された。このパネルでは、新約聖書研究者を加えることによって、日本のキリシタン殉教がキリスト教史(特に古代の殉教史)に実証的に関連付けられることができたが、今後の研究では、こうした時代を越えた比較研究の実施が重要であることが明らかになった。
1 0 0 0 経済関係のグローバル化に対応する経済行政法理論の構築
本研究の目的は、国際・国家・地域の各レベルにおける人々や団体の連携を通じた新たな公共的制御のあり方を、経済行政法の面から構想することである。そして本研究は、(1)グローバル化した経済活動に対する主権国家による制御と多元的に構成された国際的な組織や手続による制御との関係および両者の功罪に関し、主要国の理論的到達点を明らかにし、(2)その調査結果に基づき、個別行政領域について日本法との比較検討を行い、(3)E・オストロムの集合的行動領域の規範理論に着目して、“市場でも国家でもない”領域に対応する経済行政法理論の提示を試みる。
- 著者
- 宇野 重規 谷澤 正嗣 森川 輝一 片山 文雄 石川 敬史 乙部 延剛 小田川 大典 仁井田 崇 前川 真行 山岡 龍一 井上 弘貴 小野田 喜美雄
- 出版者
- 東京大学
- 雑誌
- 基盤研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 2017-04-01
研究の二年目にあたる平成30年度は定例の研究会を続け、通史的な視点の確立と全体的枠組みの決定を目指した。その目的は、共和主義、立憲主義、リベラリズムを貫く座標軸を見定めることにあった。この目的に向けて、まずは18世紀における共和主義と立憲主義の関係について集中的に検討を行った。その成果は、社会思想史学会において分科会「アメリカ政治思想史研究の最前線」を企画し、石川敬史が「初期アメリカ共和国における主権問題」報告することにつながった。この報告は主権論に即して、初期アメリカにおける思想対立をヨーロッパの思想との連続性において捉えるものであった。第二にプラグマティズムとリベラリズムの関係についても考察を進めた。具体的には研究会を開催し、研究代表者である宇野重規が「プラグマティズムは反知性主義か」と題して報告を行なった。これはプラグマティズムをアメリカ思想史を貫く反知性主義との関係において考察するものであり、プラグマティズムの20世紀的展開を検討することにもつながった。さらに小田川大典が「アメリカ政治思想史における反知性主義」と題して報告を行い、アメリカ思想史の文脈における反知性主義について包括的に検討した。さらに上記の社会思想史学会においては、谷澤正嗣が「A・J・シモンズの哲学的アナーキズム」と題して報告を行っている。これは現代アメリカのリベラリズム研究におけるポイントの一つである政治的責務論において重要な役割を果たしたシモンズの研究を再検討するものである。人はなぜ自らの政治的共同体に対して責務を負うのか。この問題を哲学的に検討するシモンズの議論は、アメリカ思想におけるリベラリズムと共和主義の関係を考える上でも重要な意味を持つ。シモンズを再検討することも、本年度の課題である通史的な視点の確立に向けて大きな貢献となった。
1 0 0 0 書評・紹介 川島京子著「日本バレエの母 エリアナ・パヴロバ」
- 出版者
- 早稲田大学文学学術院演劇映像研究室
- 雑誌
- 演劇映像 (ISSN:13454315)
- 巻号頁・発行日
- no.55, pp.62-65, 2014