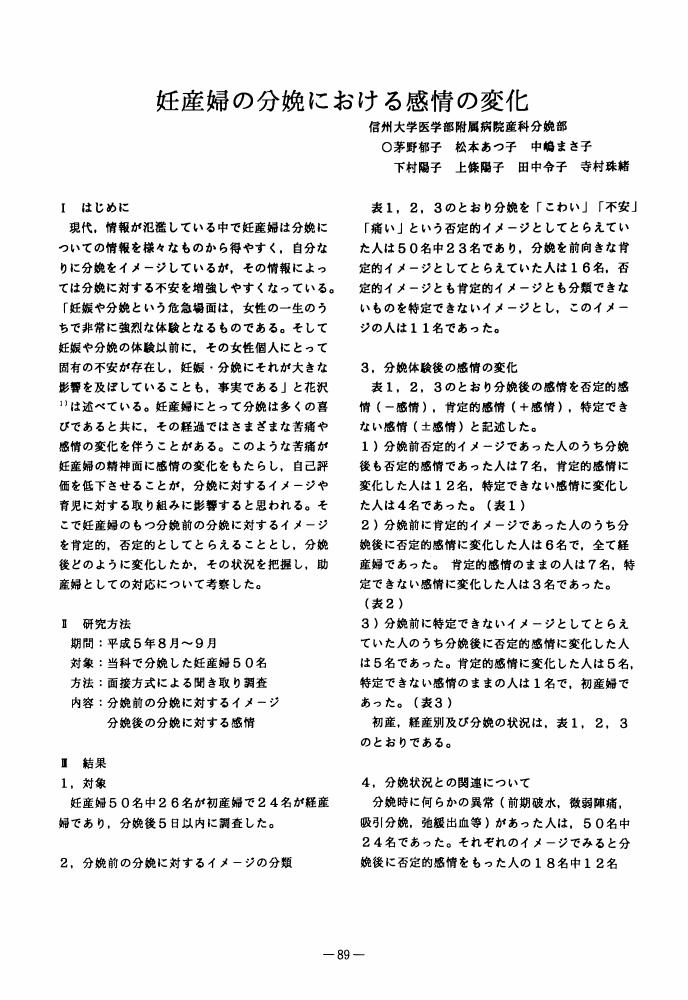1 0 0 0 IR ドイツの自殺幇助に関する法律とその問題点
- 著者
- 浅見 昇吾
- 出版者
- 総合人間科学部看護学科
- 雑誌
- 上智大学総合人間科学部看護学科紀要 = Journal of Department of Nursing, Faculty of Human Sciences, Sophia University (ISSN:24239526)
- 巻号頁・発行日
- no.3, pp.15-21, 2017
特別寄稿
1 0 0 0 IR 翻訳 刑法的に規制された死 : 業としての自殺援助という新しい刑法上の構成要件
- 著者
- デュトゲ グンナー 神馬 幸一 神馬 幸一
- 出版者
- 日本比較法研究所
- 雑誌
- 比較法雑誌 (ISSN:00104116)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.3, pp.209-228, 2016
近時,ドイツ刑法典の一部改正により,新217条「業としての自殺援助罪(geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung)」が2015年12月10日から施行された。本稿は,その動向を批判的に検討するものである。 当地において,この新条項導入以前,自殺関与は,法文上,禁止されていなかった。しかし,判例上,それを無に帰すかのような解釈論が展開され,実際上,自殺関与を巡る刑法上の取扱いは,動揺していた。このような法的状況を前提としていることもあり,今回の新規立法は,その論理構造に様々な矛盾を含んでいる点が批判されている。 また,この新規立法は,今後,ドイツにおける終末期医療の現場で,どのような波及的悪影響(ないしは萎縮効果)を及ぼし得るのかということも本稿では検討されている。 このように医師介助自殺に関する刑法的規制には多くの問題が伴う。そして,当該刑法的規制は,リベラルな法治国家の原則に反するものと批判されている。ここでいうリベラルな法治国家とは,ドイツ連邦通常裁判所が提示した言葉に従えば「全ての市民における居場所」として把握されるものである(BVerfGE 19, 206 [216])。そのような姿勢を貫徹するならば,確かに,一定の生き方ないし死に方を「正しいもの」として掲げることは,断念されなければならない。このことが本稿では強調されている。 このドイツの新規立法により生じたとされる自殺の禁忌化がもたらす問題性は,自殺幇助罪規定を有する我が国にも同様に当てはめることが可能であろう。この新規立法に関して展開された生命倫理と法を巡るドイツの議論を検証することは,我が国において関連する論点への示唆を得るためにも,その意義が認められるように思われる。
1 0 0 0 OA 第9回日本助産学会学術集会集録一般口演第5群
- 著者
- 平野 実良
- 出版者
- 新潟産業大学経済学部
- 雑誌
- 新潟産業大学経済学部紀要 (ISSN:13411551)
- 巻号頁・発行日
- no.55, pp.19-28, 2020-02
地域通貨は、地域経済の活性化、住民福祉の支援、社会問題の解決、コミュニティの活性化などを目指し、発行主体・参加主体・発行方式・目的・規模といった点において多種多様なものが存在している。我が国では、1990年代後半から2000年代前半にかけて多くの地域通貨が生み出されたが、2005年頃をピークにして下降している。地域通貨には、始めることはそれほど難しくないようであるが運営(継続)していくことは難しい、という特徴があると考えられる。運営上の課題はいくつかあるが、中でも流通量・発行量が重要あるいは一番大事な指標といわれている。本稿では、新潟県柏崎市で流通している地域通貨:風輪通貨を事例とし、2017年度に実施した柏崎市活性化を目指す地域通貨流通のための市民意識・消費動向調査をとおして商店街利用状況、商店街に対する不満、不足している業種、および、地域通貨と風輪通貨の認知度や関心の度合いなどの現状と課題を明らかにし、商店街活性化に対しての地域通貨の利活用方法を検討する。これは、商店街の状況を精査することにより現状や課題を把握し、その中から重要度や優先度の高いものを見つけ出し、その課題に対して風輪通貨をどのように利活用すれば適切かつ効率的に効果を最大限に発揮できるかを考えた結果として有意義なものである。
1 0 0 0 平遺跡 : 緊急発掘調査報告書
- 著者
- 新津市教育委員会[編]
- 出版者
- 新津市教育委員会
- 巻号頁・発行日
- 1983
1 0 0 0 OA 成果を発信しよう ─理学療法士のための論文執筆のすすめ─
- 著者
- 市橋 則明
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.44 Suppl.3(第52回日本理学療法学術大会(千葉))
- 巻号頁・発行日
- pp.15-18, 2017 (Released:2017-10-20)
- 参考文献数
- 1
- 著者
- 金澤 有紘
- 出版者
- 公益社団法人 高分子学会
- 雑誌
- 高分子論文集 (ISSN:03862186)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.5, pp.442-452, 2016-09-25 (Released:2016-09-23)
- 参考文献数
- 49
異種モノマー間の交差生長反応を伴う共重合系として,ビニルエーテルとオキシランのビニル付加・開環同時カチオン共重合に関する最近の研究を概説する.オキシラン由来のオキソニウムイオン生長種にビニルモノマーが付加しないため,これらのモノマーの共重合は一般に難しいとされてきた.そこで,オキソニウムイオン生長種の開環反応により炭素カチオン種を生成するようモノマー構造・開始剤系に着目し,適切に設計することで,両モノマー間の交差生長反応を伴った共重合が進行することを明らかとした.本報ではさらに,交差生長反応の頻度に影響を与える因子,ケトンを用いた三元共重合系の構築,アルコキシオキシラン・環状ホルマールを用いた制御カチオン共重合系の設計に関する研究結果についても述べる.
1 0 0 0 OA メディアの解釈と消費行動 "ピンク"とバービー
- 著者
- 熊坂 賢次
- 出版者
- 日本消費者行動研究学会
- 雑誌
- 消費者行動研究 (ISSN:13469851)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.91-108, 1994-09-20 (Released:2009-05-29)
1 0 0 0 OA ホームヘルスケアのための便座内蔵型血圧計測システムの試作
- 著者
- 田中 志信 本井 幸介 野川 雅道 山越 健弘 山越 憲一
- 出版者
- 公益社団法人 日本生体医工学会
- 雑誌
- 生体医工学 (ISSN:1347443X)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.3, pp.467-474, 2006 (Released:2008-05-01)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1
The daily monitoring of health conditions at home is a very important subject not only as an effective scheme for the early diagnosis and treatment of cardiovascular and other diseases, but also for the prevention and control of such diseases. From this point of view, we have been developing a fully automated “non-conscious” monitoring system for home healthcare. In this paper, we describe the structural details of a newly developed blood pressure (BP) measurement system built into a toilet seat and some results obtained using the system. The principle used for BP measurement was the volume-oscillometric method. A reflectance-type photoplethysmographic sensor was installed in an appropriate position on the toilet seat, and it was automatically lifted and lowered using a newly designed helicoid-type actuator. Systolic (SBP) and mean BP (MBP) were obtained using the arterial volume pulsation signal obtained by the sensor. In order to evaluate the accuracy of the BP measurements, simultaneous measurements were carried out using two types of commercially available BP monitors (upper arm and wrist). Simultaneous measurement using an “invasive technique” via catheterization to the right brachial artery was also conducted. From the results obtained (bias[s.d.] for SBP; Upper arm: -1.20 [7.90] mmHg, Wrist: 0.44 [7.28] mmHg, Invasive: -0.41 [4.91] mmHg, bias [s.d.] for MBP; Upper arm: 4.40 [6.91] mmHg, Wrist: 5.07 [8.04] mmHg, Invasive: 3.68 [5.69] mmHg), reasonable accuracy of the present system was clearly demonstrated. This system, which requires no cumbersome procedures for BP measurement such as cuff setting, proper positioning of measuring site and so on, appears to be a useful means for long-term home healthcare monitoring.
1 0 0 0 OA 戦時期におけるホワイトカラーの給与統制と賃金管理
- 著者
- 田口 和雄 大島 久幸
- 出版者
- 高千穂大学 高千穂学会
- 雑誌
- 高千穂論叢 = THE TAKACHIHO RONSO (ISSN:03887340)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.2, pp.99-120, 2019-11-25
- 著者
- 松山 信彦 佐藤 博友 松村 真悟 浅利 佳紀 佐々木 長市
- 出版者
- 日本作物学会東北支部
- 雑誌
- 日本作物学会東北支部会報 (ISSN:09117067)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, pp.45-46, 2013-12-20 (Released:2017-10-02)
- 出版者
- 京都
- 雑誌
- Asphodel (ISSN:02857715)
- 巻号頁・発行日
- no.55, pp.206-227, 2020-07-27
翻訳
1 0 0 0 アジア太平洋博覧会-福岡'89 公式記録
- 出版者
- アジア太平洋博覧会協会
- 巻号頁・発行日
- 1990
1 0 0 0 OA 岩石鉱物学・地質学的にみた骨材の選択
- 著者
- 丸 章夫 柳田 力
- 出版者
- 公益社団法人 日本コンクリート工学会
- 雑誌
- コンクリート工学 (ISSN:03871061)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.11, pp.85-89, 1981-11-15 (Released:2013-04-26)
- 参考文献数
- 12
- 著者
- 伊藤 憲二
- 出版者
- 日本科学史学会 ; 2014-
- 雑誌
- 科学史研究. [第Ⅲ期] = Journal of history of science, Japan. 日本科学史学会 編 (ISSN:21887535)
- 巻号頁・発行日
- no.292, pp.344-355, 2020-01
1 0 0 0 IR 最低賃金が企業の全要素生産性に与える影響 : 日本の製造業を対象とした実証分析
- 著者
- 岩崎 雄也 Iwasaki Yuya
- 出版者
- 青山学院大学大学院経済学・法学・経営学三研究科
- 雑誌
- 青山社会科学紀要 (ISSN:02863901)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.2, pp.1-17, 2019-03-01
人口減少社会を迎えたわが国において,生産性の向上が大きな課題となっている。そうした中,最低賃金の引き上げが企業の新陳代謝を促し,マクロの生産性の向上に寄与するとの見方があるが,最低賃金が生産性,とりわけ全要素生産性(TFP)にどのような影響を与えるのか,日本を対象に研究を行った例はほとんどない。一方,海外の先行研究では,最低賃金がTFPに与える影響について,理論分析,実証分析,ともに存在する。理論分析としてはAghion et al.(2003)があり,その理論モデルでは,最低賃金の上昇が企業の研究開発投資を減少させ,結果としてTFPが減退すると結論づける。また,実証分析は蓄積が多く,最低賃金がTFPに与える影響は正であるとする結果と,負であるとする結果の双方が存在する。これらの状況を踏まえたうえで,本論文では,最低賃金が企業のTFPに正と負いずれの影響を与えるのか明らかにすること,および,Aghionらの理論が日本で適合するのか否か検証することを目的として実証分析を行った。対象期間は1986年から2007年,対象業種は製造業とし,分析にあたっては都道府県別の完備パネルデータを使用した。結果として,日本の製造業において,最低賃金の上昇は企業のTFPに負の影響を与えることが明らかになった。また,バブル崩壊後の「失われた10年」の時期における負の影響は,Aghionらの理論モデルと整合的であることが分かった。
1 0 0 0 「ネコは手押し一輪車」と自動通訳する機器
- 出版者
- 日経BP
- 雑誌
- 日経コンストラクション = Nikkei construction (ISSN:09153470)
- 巻号頁・発行日
- no.742, 2020-08-24
飛島建設とロゼッタは、ウエアラブル機器をヘルメットに装着するだけで、外国人技術者との自動同時通訳などが可能になるシステム「e-Sense(イーセンス)」を開発した(写真1、図1)。建設現場と遠隔地との情報共有機能や作業内容を記録するレコーダー機能も搭…
1 0 0 0 Twitterからの意見抽出モデル構築のための教師データ作成手法
- 著者
- 野崎 雄太 櫻井 義尚
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌数理モデル化と応用(TOM) (ISSN:18827780)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.2, pp.69-83, 2020-08-28
本論文では,教師データセットの作成において,事例をランダムに選び,アノテーションすると不均衡データになってしまう課題に対して,機械的なプレフィルタリングを用いたサンプリングにより,不均衡化を緩和するアノテーション手法PSSA(Prefilter based Stepwise Sampling for Annotation)を提案する.また,辞書フィルタを用いたPSSAによるTwitterからの意見抽出モデルを構築し,提案手法の有効性を示した.まず,辞書フィルタを用いたPSSAによる,不均衡化の緩和効果の検証のため,ツイートのアノテーション実験を行い,次にアノテーション段階での不均衡データ対策の有効性を検証するため,意見抽出モデルを構築し,アノテーション手法と前処理,機械学習構築手法の組合せの違いによるモデル精度の違いを検証した.最後に,アノテーションを行うサンブル選択に辞書フィルタを用いることによる影響を分析するため,各辞書フィルタを適用した場合とフィルタリングしなかった場合のモデル精度を比較した.以上の比較実験を通して,提案するアノテーション手法の優位性を多角的に検証した.
1 0 0 0 OA 軍艦の居住性
- 著者
- 江頭 健
- 出版者
- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会
- 雑誌
- 造船協会誌 (ISSN:03861503)
- 巻号頁・発行日
- vol.331, pp.95-103, 1957-05-25 (Released:2018-02-25)