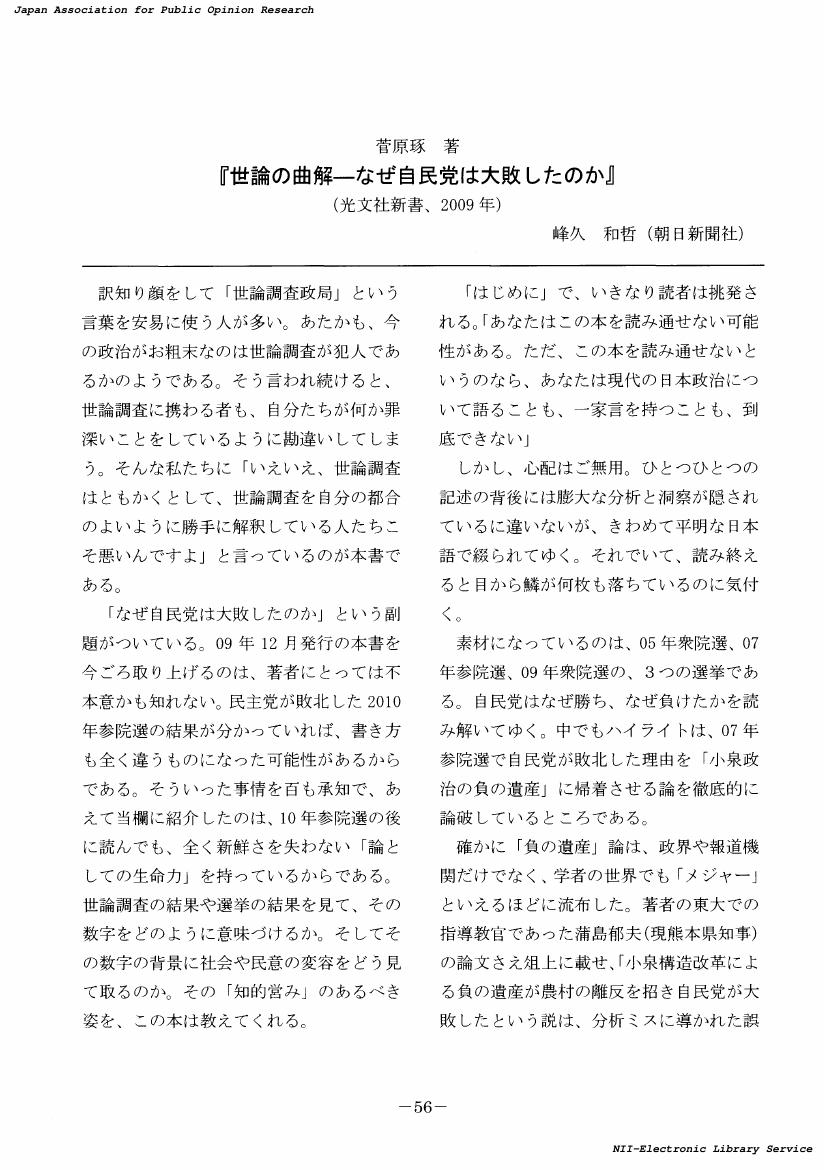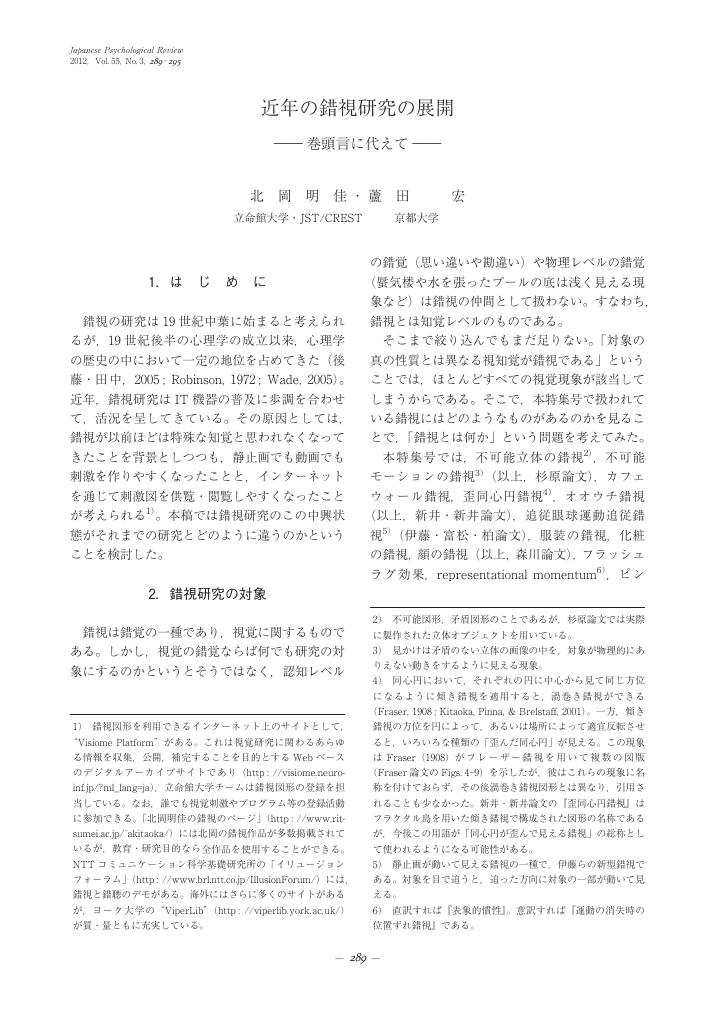1 0 0 0 OA のれん計上企業の将来業績と財務特性 組織再編成功企業の財務特性に関する実証分析
- 著者
- 奥原 貴士
- 出版者
- 四日市大学
- 雑誌
- 四日市大学論集 (ISSN:13405543)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.2, pp.37-55, 2018 (Released:2018-05-21)
- 参考文献数
- 17
1 0 0 0 OA デジタル音源のサンプリング周波数が聴取者の心理・生理状態に及ぼす影響
- 著者
- 大湾 麻衣 入戸野 宏
- 出版者
- 日本生理心理学会
- 雑誌
- 生理心理学と精神生理学 (ISSN:02892405)
- 巻号頁・発行日
- pp.2003br, (Released:2020-07-04)
- 参考文献数
- 25
ハイレゾリューション音源はCDより時間方向あるいは振幅方向の解像度が高く,その高周波成分が生理状態に影響を及ぼすという報告がある。本研究では192 kHz/24bitで録音された自然環境音(オリジナル音源)にフィルタをかけ,高周波成分(>22 kHz)をカットした2種類の音源(サンプリング周波数192 kHzと44.1 kHz)を作成した。24名の大学生が3種類の音刺激をランダムな順で聴取した。脳波のシータ帯域(4.0–8.0 Hz)とスローアルファ帯域(8.0–10.5 Hz)のトータルパワーは,サンプリング周波数が高い音を聴取しているときの方が高くなった。主観的気分や音質評価には明瞭な条件差が認められなかった。この結果は,CDよりもサンプリング周波数が高い音源は,意識的に違いに気づかなくても生理状態に影響を及ぼすことを示唆している。
1 0 0 0 OA 企業結合により取得した無形資産と概念フレームワーク
- 著者
- 飯塚 雄基 Iitsuka Yuki
- 出版者
- 福岡大学研究推進部
- 雑誌
- 福岡大学商学論叢 = Fukuoka University Review of Commercial Sciences (ISSN:02852780)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.3, pp.571-610, 2019-12
1 0 0 0 OA 非財務指標研究の回顧と展望
- 著者
- 安酸 建二 乙政 佐吉 福田 直樹
- 出版者
- 神戸大学経済経営学会
- 雑誌
- 国民経済雑誌 (ISSN:03873129)
- 巻号頁・発行日
- vol.198, no.1, pp.79-94, 2008-07
財務情報に過度に依存した経営によるさまざまな弊害が,先行研究においてしばしば指摘されてきた。この弊害に対する解決策の一つとして,業績管理システムに非財務指標を組み込むことが重要視されている。本稿では,まず,非財務指標をめぐる論点として,非財務指標が財務業績に対する先行指標になる可能性,および,戦略の実現に向けて経営者・管理者の意思決定や行動に影響を与える可能性の二つを取り上げ,非財務指標研究を業績管理システム研究の流れの上に位置づける。次に,非財務指標の可能性に関連する実証的証拠を検討する。最後に,今後の非財務指標研究の方向性を示す。
1 0 0 0 OA 菅原琢著, 『世論の曲解-なぜ自民党は大敗したのか』, 光文社新書, 2009年
- 著者
- 峰久 和哲
- 出版者
- 公益財団法人 日本世論調査協会
- 雑誌
- 日本世論調査協会報「よろん」 (ISSN:21894531)
- 巻号頁・発行日
- vol.106, pp.56-57, 2010-10-31 (Released:2017-03-31)
1 0 0 0 OA 1988年イギリス教育改革法の主要点と問題点
1 0 0 0 IR 生得的な脅威感知システム-ウロコのテクスチヤーがあるからヘビが怖い-
- 著者
- 川合 伸幸
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. IMQ, イメージ・メディア・クオリティ : IEICE technical report (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.112, no.161, pp.1-6, 2012-07-20
- 参考文献数
- 21
私たちは、誰かが怒っている顔やヘビなどを見れば恐怖を感じる。これは経験によって学習した情動反応なのか、生得的にもっている脅威感知システムによるのだろうか。成人を対象とした実験で、ヘビやクモをすばやくみつけられることを実験的に示し、これらに対する敏感性を確認した。つづいて、3-5歳の子どもでも同じ結果が得られることを確認した。このことは経験の効果が弱いことを示している。さらに、ヘビを見たことのないサルでも同じ結果が得られることを示し、これらの対象に対する敏感さは進化的に培われた生得的なものであることを確認した。では、生まれる前からどのようにヘビを認識できることになっているのだろうか。これは脳の視床にある核が特定のパタンに反応することで恐怖センターである扁桃体を賦活させるためと考えられる。そのパタンとはヘビに特徴的なウロコであり、これが鍵となってヘビへのすばやい反応を喚起させていると考えられる。Humans are afraid of specific stimuli, such as angry faces and snakes. It has been a long debate on whether such fear responses are acquired through learning or an innate one. A series of our studies demonstrated that a picture of snake among those of flowers was also quickly detected by human adults. We also found that even young children of three years old detected a picture of snake among flower pictures, which suggests that humans are innately sensitive to snakes. Further, we found that macaque monkeys reared in a laboratory with no experience with snakes also detected snake pictures quickly. These results strongly suggest that snakes and/or angry face are phylogenetic fear-relevant stimuli, and that the exaggerated sensitivity to snakes by humans and monkeys have evolutional routes. A hypothesis and our on-going studies suggest scale is the key to snake fear.
- 著者
- Masataka Nobuo Hayakawa Sachiko Kawai Nobuyuki
- 出版者
- Public Library of Science
- 雑誌
- PloS one (ISSN:19326203)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.11, 2010-11
- 被引用文献数
- 2
Humans as well as some nonhuman primates have an evolved predisposition to associate snakes with fear by detecting their presence as fear-relevant stimuli more rapidly than fear-irrelevant ones. In the present experiment, a total of 74 of 3- to 4-year-old children and adults were asked to find a single target black-and-white photo of a snake among an array of eight black-and-white photos of flowers as distracters. As target stimuli, we prepared two groups of snake photos, one in which a typical striking posture was displayed by a snake and the other in which a resting snake was shown. When reaction time to find the snake photo was compared between these two types of the stimuli, its mean value was found to be significantly smaller for the photos of snakes displaying striking posture than for the photos of resting snakes in both the adults and children. These findings suggest the possibility that the human perceptual bias for snakes per se could be differentiated according to the difference of the degree to which their presence acts as a fear-relevant stimulus.
1 0 0 0 OA 雪ダム構想と豪雪地帯水土保全機能強化モデル事業
- 著者
- 石川 政幸
- 出版者
- 一般社団法人 日本治山治水協会
- 雑誌
- 水利科学 (ISSN:00394858)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.6, pp.23-47, 1995-02-01 (Released:2019-04-30)
- 参考文献数
- 20
1 0 0 0 OA 岩波情報科学辞典
- 著者
- 郡司 隆男
- 出版者
- 日本ソフトウェア科学会
- 雑誌
- コンピュータ ソフトウェア (ISSN:02896540)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.4, pp.4_387-4_389, 1991-07-15 (Released:2018-11-05)
1 0 0 0 OA イスラムと西アフリカの物質文化
- 著者
- 竹沢 尚一郎 Shoichiro Takezawa
- 出版者
- 国立民族学博物館
- 雑誌
- 国立民族学博物館研究報告別冊 = Bulletin of the National Museum of Ethnology Special Issue (ISSN:0288190X)
- 巻号頁・発行日
- vol.012, pp.533-593, 1990-03-30
1 0 0 0 OA Importance of knee flexion range of motion during the acute phase after total knee arthroplasty
- 著者
- Tomohiro OKA Osamu WADA Tsuyoshi ASAI Hideto MARUNO Kiyonori MIZUNO
- 出版者
- Japanese Society of Physical Therapy
- 雑誌
- Physical Therapy Research (ISSN:21898448)
- 巻号頁・発行日
- pp.E9996, (Released:2020-08-05)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 16
Background: We investigate the association with knee flexion range of motion (ROM) during the acute phases and that at 12 months after total knee arthroplasty (TKA). We also clarified the cut-off ROM during the acute phases in predicting the goal of knee flexion ROM at 12 months. Methods: In this retrospective study, 193 patients with knee osteoarthritis (female:144 patients, age:73.2 ± 7.7 years) who underwent unilateral TKA at an orthopedic clinic were recruited. They underwent assessments of knee flexion ROM at 5 days, 1 month, and 12 months after TKA. The goal of knee flexion ROM at 12 months after TKA was set at 120°. Single and logistic-regression analyses were performed with the dependent variables including the outcome of the goal of knee flexion ROM at 12 months, and the independent variables included knee flexion ROM at 5 days and 1 month, separately. We calculated the cut-off ROM at 5 days and 1 month for predicting the goal of knee flexion ROM at 12 months with receiver operating curve analysis. Results: Knee flexion ROM at 5 days and 1 month were significantly associated with the goal of that at 12 months (p < 0.01). The cut-off ROM were 85° at 5 days and 105° at 1 month separately. Conclusions: Our results suggest the importance of early improvement in knee flexion ROM after TKA, and that at 1 month postoperatively indicates the likelihood of achievement of the goal of knee flexion ROM at 12 months after TKA.
1 0 0 0 OA 近年の錯視研究の展開 ―巻頭言に代えて―
- 著者
- 北岡 明佳 蘆田 宏
- 出版者
- 心理学評論刊行会
- 雑誌
- 心理学評論 (ISSN:03861058)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.3, pp.289-295, 2012 (Released:2018-08-18)
1 0 0 0 OA Waardenburg症候群1型の2症例 難聴の遺伝カウンセリング
- 著者
- 齊藤 優子 田中 里江子 硲田 猛真 間 三千夫 船越 宏子 池田 浩己 芝埜 彰 輿田 茂利 夜陣 真司 北野 博也 榎本 雅夫
- 出版者
- 耳鼻咽喉科展望会
- 雑誌
- 耳鼻咽喉科展望 (ISSN:03869687)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.4, pp.236-241, 2005-08-15 (Released:2011-03-18)
- 参考文献数
- 15
Waardenburg症候群は内眼角と涙点の側方偏位, 広く高い鼻根, 正中部眉毛過形成, 虹彩異色症, 先天性感音難聴, 前頭部白髪の6主徴を特徴とする常染色体優性遺伝形式をとることが多い遺伝性疾患である。本邦でも多くの報告がなされているが症状の発現や程度は様々である。今回, 新生児聴覚スクリーニング検査から発見されたWaardenburg症候群1型の2例 (父子症例) を経験し, 遺伝カウンセリング, 聴力所見を中心に難聴の浸透率や難聴の表現型などについて検討した。父子の症例であるが感音難聴, 虹彩異色の発現及びその程度に違いが認められた。父親には難聴はみられなかったが, 患児は暗一側性の高度難聴を認めた。
1 0 0 0 日本国憲法の「は」と、その構文
- 著者
- 中村 幸弘
- 出版者
- 國學院大學綜合企画部
- 雑誌
- 國學院雜誌 = The Journal of Kokugakuin University (ISSN:02882051)
- 巻号頁・発行日
- vol.114, no.12, pp.17-28, 2013-12
1 0 0 0 OA 摂取カゼインレベルが腎臓および尿中のカルシウム量に及ぼす影響
- 著者
- 阿左美 章治 平塚 静子 北野 隆雄 江指 隆年
- 出版者
- 公益社団法人 日本栄養・食糧学会
- 雑誌
- 日本栄養・食糧学会誌 (ISSN:02873516)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.2, pp.117-122, 1994-04-10 (Released:2010-02-22)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 3 3
生後4週齢のフィッシャー系雌ラットにカゼインをタンパク質源とし, その含有量をそれぞれ10%, 20%, 40%とした飼料, すなわち10%カゼイン食 (C-10), 20%カゼイン食 (C-20), 40%カゼイン食 (C-40) を5週間与えカルシウム (Ca), リン (P), マグネシウム (Mg) の出納実験を行った。また, ミネラル出納に影響を及ぼす腎臓についてその肥大や組織の形態学的な観察を実施した。さらにCaの恒常性に関する血清中のCa量, PTH量, 大腿骨や腎臓中のCa量についても検討した。結果は以下のとおりであった。1) Caの尿中排泄率はC-40が3群中最高値を示した。2) 腎臓の肥大はC-10, C-40に認められるもののC-10についてはCaの尿への高排泄を伴わなかった。3) C-10の腎臓Ca量はC-40のおよそ60倍を示し遠位尿細管部に著しいCaの沈着が認められた。4) C-40の血清中遊離Ca量は3群中最低値を示した。5) C-40の血清中PTH量は3群中最高値を示した。6) C-10の大腿骨中Ca量は3群中最低値を示した。以上の結果から, タンパク質の摂取レベルに対するCa代謝の対応は腎臓を中心に異なることが考えられた。
1 0 0 0 OA 美術初心者は絵画から何を読み取るか? ―具象絵画鑑賞時の発話による探索的な検討
- 著者
- 田中 吉史
- 出版者
- 日本認知科学会
- 雑誌
- 認知科学 (ISSN:13417924)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.26-49, 2018-03-01 (Released:2018-09-01)
- 参考文献数
- 34
Beginners of art appreciation generally have “reality constraints” in that they show a strong tendency to insist on identifying depicted objects and their realistic expression in artwork. We examined the effect of reading commentaries on artwork on the relaxation of reality constraints and the time taken by appreciators to respond to paintings. In the first session of the experiment, 24 pairs of participants appreciated one of two paintings:either one by van Gogh (“Terrasse du caf´e le soir”) or one by Sisley (“Landscape in summer”). In the second session, the participants appreciated two paintings, by Renoir and Matisse, with the help of any of the following three methods: reading commentaries on the objects depicted in each painting, reading commentaries on the formal aspects of the paintings, and reading no commentary. In the third session, the participants viewed a painting (either van Gogh’s or Sisley’s) that they had not viewed in the first session. In each session, the participants freely talked to one another while viewing the painting for 5 minutes. The verbal protocols and gestures, such as pointing to objects in the painting, in the first and the third sessions were analyzed. In the case of the van Gogh painting, the participants generally tended to focus on the salient objects in the painting in the early stage of appreciation and to gradually shift their attention to more peripheral objects. The participants shown the formal commentary tended to focus on formal aspects of the painting, especially on the exaggerated perspective integrating the objects. On the contrary, in the case of the Sisley painting, the participants showed a strong tendency to insist on identifying the depicted objects. The characteristics of the paintings and the effects of the commentaries are discussed.
1 0 0 0 OA 美術作品を記憶して描くことの教育的効果 児童の形状ストックという観点から
- 著者
- 髙橋 文子
- 出版者
- 美術科教育学会
- 雑誌
- 美術教育学:美術科教育学会誌 (ISSN:0917771X)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, pp.313-326, 2017 (Released:2019-09-03)
- 参考文献数
- 18
小学生及び幼児を対象に,美術作品を記憶して描くことによる教育的効果を,形状ストックという観点から検討した。美術作品を見た後,作品を見ないで描く記憶画と,作品を見ながら描く観察画の2枚のスケッチを描写するプログラムを,4歳~12歳児を対象に行った。形状ストックという事物レベルで描かれた物を比較することで,児童の認識,感受の様子をリアルに検討することが可能であった。記憶スケッチには,児童のもつ絵画意識が強く反映されていた。記憶スケッチプログラムは,形や色,印象等の感覚の精度を高め,より質の高い認識や感受を生み出すことを確認した。
1 0 0 0 OA 龍樹の六十頌如理論について
1 0 0 0 OA 炎症性関節炎患者に対する患者教育についてのEULARリコメンデーション
- 著者
- 房間 美恵 中原 英子 金子 祐子 竹内 勤
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床リウマチ学会
- 雑誌
- 臨床リウマチ (ISSN:09148760)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.3, pp.181-187, 2019-09-30 (Released:2019-11-02)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 1
2010年にTreat to Target(T2T)(目標達成に向けた治療)リコメンデーションが提唱され,この概念は日本でも,全国的な普及活動によりリウマチ診療に従事する医療者に浸透してきた.この中のoverarching principles(基本的な考え方)で最初に述べられているのが医師と患者との「shared decision making(共同意思決定)」であるが,患者が自身の病気や治療を理解し,共同意思決定プロセスに参画するためには患者教育が必須である. 2015年にEULARから,2つの基本的な考え方と8つの推奨事項からなる炎症性関節炎患者に対する患者教育のリコメンデーションが提唱された.基本的な考え方の中では,患者教育は医療者と患者が双方向で行うべきであること,患者自身が病気と付き合いながら生活を自己管理できるように支援すること,そしてこれら実現のために医療者は患者と十分コミュニケーションを取りながら共同意思決定を行うことが必要不可欠であることが示されている.患者教育とT2T実践,共同意思決定は密接に関連しあう.患者教育をすべての炎症性関節炎患者の標準治療の一部として実施できるよう,その課題を評価し,より良い教育支援に向けて多職種協働で取り組むことが重要である.