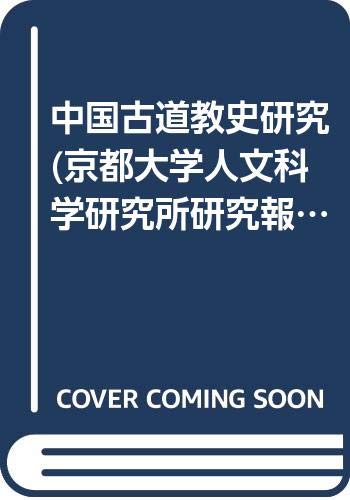1 0 0 0 次世代施設園芸の全国展開 : 攻めの農業の旗艦
- 著者
- 阿部 龍文
- 出版者
- 智山勧学会
- 雑誌
- 智山学報 (ISSN:02865661)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, pp.183-192, 2005
1 0 0 0 ようこそ絵本図書館へ(第11回)LGBTを考えるきっかけに
- 著者
- 児玉 ひろ美
- 出版者
- 診断と治療社
- 雑誌
- チャイルドヘルス (ISSN:13443151)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.11, pp.860-862, 2019-11
1 0 0 0 カント法哲学の超越論的性格:所有権論を中心として
- 著者
- 松本 和彦
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- no.1993, pp.161-169, 1994
1 0 0 0 OA THA術後MRSA感染症に対する局所高濃度抗菌薬投与による治療経験
- 著者
- 生田 拓也
- 出版者
- 西日本整形・災害外科学会
- 雑誌
- 整形外科と災害外科 (ISSN:00371033)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.2, pp.284-286, 2020-03-25 (Released:2020-04-30)
- 参考文献数
- 8
THA術後MRSA感染症に対して局所高濃度抗菌薬投与を行いインプラントを温存し感染を沈静化できた1例を経験したので報告した.症例は86歳,女性,当院で左THAを行い順調に経過し外来にて経過観察を行っていたが,術後2ヶ月時に尻餅をついてから左臀部痛が出現してきた.術後3ヶ月の再来時に創部より排膿があり,術後感染と診断した.起因菌はMRSAであった.関節切開掻爬を行い,術後はGM 240 mg/dayにて持続洗浄を行った.術後3週でGM 120 mg/dayとし,術後4週まで持続洗浄を継続した.術後3週でCRPは陰性化(0.3 mg/dl以下)し,術後6ヶ月時再発を認めていない.人工関節術後感染においてはbiofilmが形成されていることが想定され,抗生剤はMIC(minimum inhibitory concentration)よりMBEC(minimum biofilm eradication concentration)を基準として投与量を決める必要がある.本法はMBECを維持できる投与を行うことが可能であり有用であった.
1 0 0 0 OA 杉山寧 ―「永遠なるもの」と「乾いたもの」への希求―
- 著者
- 松田 真理子 Mariko MATSUDA 京都文教大学臨床心理学部臨床心理学科 Kyoto Bunkyo University Department of Clinical Psychology Faculty of Clinical Psychology
- 雑誌
- 臨床心理学部研究報告 = Reports from the Faculty of Clinical Psychology, Kyoto Bunkyo University (ISSN:18843751)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.87-101, 2014-03-31
Yasushi Sugiyama was a famous Japanese painter who lived through the periods of Meiji, Taisho, and Showa. In 1909, he was born as the eldest son of Ukichi Sugiyama who ran a stationery shop in Asakusa, Tokyo, and his wife, Michi. As his father died when he was six, his mother raised her two sons by herself. In 1928, he entered the Department of Japanese-style Painting of the former Tokyo Art School, and studied under Eikyu Matsuoka, a younger brother of Kunio Yanagida. His graduation work painted in 1933, “No” (field), won the first prize, and he soon attracted attention from the art world. He married a lady named Motoko Shinohara at the age of 27. Following the death of his mentor, Matsuoka, he developed tuberculosis and struggled with the disease through his 30s. When he was 42 years old, “Europe” (1951), presented at the 7th Japan Fine Arts Exhibition, attracted great attention. In 1958, his eldest daughter, Yoko, married a writer, Yukio Mishima. From around 1970, when Mishima committed suicide, Sugiyama started to draw a series of (five) pictures of naked women under the theme of a hymn to life, and received the Order of Cultural Merit in 1974. However, following this period, he retired from public life and stopped sending his drawings to public exhibitions. From around 1980, he drew a series of fantastic pictures with serenity set in Cappadocia, which give the impression that time had stopped in them. In 1993, Sugiyama died on the morning of his 84th birthday. There is no recorded evidence suggesting that Sugiyama had psychological problems or consulted a psychiatrist. However, according to Satoshi Katoʼs view of his personality, Sugiyama might have had schizophrenia spectrum disorder, since he pursued eternity; refused to pander to secularity; was a night person; longed for aridity; and was hypersensitive to light. His life was full of ups and downs; Sugiyama had been through the deaths of his biological father in early childhood and Eikyu Matsuoka - his mentor father-figure, a twelve-year battle with tuberculosis, and the suicide of Yukio Mishima, his son-in-law. Although he was at the height of his prosperity as a winner of the Order of Cultural Merit at one stage in his life, he did not cling to that worldly success. He withdrew from secular society, and continued exploring powerful and dynamic expressions to search for eternity. As he had a schizotypal personality and hoped to withdraw from the world, Sugiyama did not think twice before secluding himself to live in quiet retirement. This eventually helped him maintain both his mental stability and physical health, and he was able to live long, devoting himself to his creative activities.
1 0 0 0 OA 災害用ARアプリケーションの開発とロケモシェアによる情報共有
- 著者
- 木下 拓也 梶原 薪 中山 功一
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第34回全国大会(2020)
- 巻号頁・発行日
- pp.4D3GS1202, 2020 (Released:2020-06-19)
佐賀県では,大雨による土砂災害や洪水などの災害が多い.国土交通省国土地理院は,洪水や土砂災害,津波などの災害リスク情報を地図に重ねて表示させた「重ねるハザードマップ」を公開している.「重ねるハザードマップ」は,地図上にどの地域がどれだけ浸水するかを色分けしたものである.しかし,使用者が住んでいる地域が実際にどれだけ浸水するかを体感的に理解するには情報が少ない.そこで本研究では,AR(拡張現実)を用いて,使用者の地域がどれだけ浸水するかを体感的に認識することができるシステムを提案する.また,災害時にAR使用中の画像をサーバーに送信することにより,システム提供側はその画像を防災対策等に使うことができる.
1 0 0 0 IR 境界性パーソナリティ特性尺度開発の試み
- 著者
- 斎藤 富由起 Fuyuki Saito 千里金蘭大学 生活科学部 児童学科
- 出版者
- 千里金蘭大学
- 雑誌
- 千里金蘭大学紀要 (ISSN:13496859)
- 巻号頁・発行日
- pp.65-72, 2007
「パーソナリティ障害ほどの重篤さはないが、BPDと類似した認知・行動パターン」は、境界性パーソナリティ特性(Borderline Personality Trait)と呼ぶことが出来る。BPT研究では信頼性と妥当性を備えた質問紙が作成されていないため、量的研究が遅れていた(加来・斎藤・守谷・末武、2005)。そこで本研究では、境界性パーソナリティ特性尺度の標準化を試みた結果、信頼性と基準関連妥当性の高い5因子38項目の尺度が作成された(α=90)。本尺度の因子は弁証法的行動療法における主要4スキルとの適合性が高いため、効果的な介入法と予防法の観点から、主要4スキルを尺度化し両要因の関連性を検討すること、また見捨てられ不安尺度や二分法的思考尺度との関連を求め、本尺度と境界性パーソナリティ障害との関連を検討することが今後の課題として指摘された。
- 著者
- 野口 邦夫
- 出版者
- 日本テレワーク学会
- 雑誌
- 日本テレワーク学会誌 (ISSN:13473115)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.1, pp.51-55, 2013
現在およびこれからの日本の雇用型テレワークの労働契約のあり方・考え方を雇用契約の起源の史的考察をもとに考える。グローバリゼーションの進展のなか、日本的雇用慣行は国内外とも通用しなくなる。雇用による仕事の仕方は、日本国内にとどまらず世界規模で考えないといけない。日本の労働法の労働契約は、形式的にはジョブをもとにした契約である。しかし実際の運用は、属する組織とのメンバーシップ契約(身分契約)的となっている。メンバーは長期雇用慣行、年功賃金制度待遇であることから、簡単には解雇されない(解雇権濫用の法理などの判例法理)。ただし、これは正社員のみであり、非正規社員ではジョブ契約の色彩をおびる。日本では非正規雇用の形態で働く人が3割を超えており、従来の正社員基準のメンバーシップ型雇用契約では対応できない。一方日本において、テレワークが普及しない理由としては、労務管理ができないといわれることが多い。これは日本の労働契約はメンバーシップ(その組織に属するメンバーである人事)の管理であり、仕事そのもののジョブの管理ではないからである。以上から、グローバル時代における日本の雇用型テレワークの労働契約は、メンバーシップ型雇用契約からジョブ型雇用契約にワークシフトすべきと提言する。
1 0 0 0 OA 二つの夢合わせ譚と頼朝六十六部聖伝承(<特集>中世における「聖なるもの」)
- 著者
- 佐藤 晃
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.7, pp.26-38, 1996-07-10 (Released:2017-08-01)
源頼朝を聖性化するかのごとき伝承、すなわち頼朝の前生を六十六部聖であったとする伝承の生成に関連して、頼朝に関する二つの夢合わせ譚(真名本曾我物語等に見られるものと、平治物語に見られるもの)について考察を試みた。そして、延慶本平家物語に見られるような日本国大将軍をめぐる言説に、日本国=六十六ヶ国という水平的国土観の表出を考え、それが頼朝をこれらの夢合わせ譚、ひいては六十六部聖伝承に結び付ける背景にあったのではないかと考えた。
1 0 0 0 IR 松本和彦著 『カントの批判的法哲学』
- 著者
- 江藤 正也
- 出版者
- 北陸大学
- 雑誌
- 北陸大学紀要 = Bulletin of Hokuriku University (ISSN:21863989)
- 巻号頁・発行日
- no.47, pp.129-154, 2019-09-30
本学教員が2018 年度に学術図書出版助成を受けた著書の「書評」である。 松本和彦著『カントの批判的法哲学』 慶応義塾大学出版会 2018 年8月 A5 版(上製本 )896頁 書評執筆者:江藤正也(北陸大学 未来創造学部 元教授)
1 0 0 0 OA 健常者における長下肢装具装着下での歩行パターン
- 著者
- 髙尾 耕平 北原 あゆみ 森岡 研介 高崎 恭輔 大工谷 新一
- 出版者
- 関西理学療法学会
- 雑誌
- 関西理学療法 (ISSN:13469606)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.73-76, 2013 (Released:2013-12-28)
- 参考文献数
- 4
The purpose of this study was to examine the influence of a knee and ankle foot orthosis (KAFO) on normal gait. The subjects were 9 healthy males with a mean age of 23.2 ± 1.1 (range 20-31) years. Alterations in the angles of the trunk, hip, knee, and ankle were examined during walking with and without a KAFO using a three-dimensional motion analysis system (UM-CAT II). From the results, three patterns were defined, all of which could be considered types of compensation for the limitation of motion caused by KAFO.
1 0 0 0 OA プレ・メトロの一方式としてのLRT導入
- 著者
- 小山 徹
- 出版者
- 交通権学会
- 雑誌
- 交通権 (ISSN:09125744)
- 巻号頁・発行日
- vol.2014, no.31, pp.64-67, 2014 (Released:2017-04-10)
1 0 0 0 IR ビッドル来航と海防問題
- 著者
- 上松 俊弘
- 出版者
- 史学研究会 (京都大学文学部内)
- 雑誌
- 史林 (ISSN:03869369)
- 巻号頁・発行日
- vol.85, no.1, pp.64-87, 2002-01
個人情報保護のため削除部分あり本稿の目的は、ビッドル来航時の日本側の対応、およびその後の洋式軍艦導入問題を分析することにより、弘化・嘉永期の海防政策とビッドル来航の意味を問うことにある。そのビッドルは、弘化三年(一八四六) に本格的な帆船戦列艦を率いて来航したが、その際日本との対応において開戦の危機が生じたのであった。このビッドルショックともいうべき事件により、幕府は海防政策の見直しをすすめたが、そのなかで洋式軍艦の導入問題が焦点の一つとなった。洋式軍艦導入による海上防御を主張する浦賀奉行の意見は、海防四家や海防掛などが主張する台場による陸上防御案の前に幕府内部での合意を得ることができなかった。したがって、阿部政権は陸上防御の海防方針をとり、その後の御備場見分の際に提出された復命書をほぼ完全に実施していったのである。Commodore Biddle's expedition, which culminated in his anchoring of a squadron American warships in the vicinity of Uraga bay in 1846, nearly led to war, and accordingly caused a political crisis, as the Tokugawa bakufu struggled with the notion of how to defend Japan from foreign navies. This study intends to reveal the parameters of debate concerning the defense of Japanese waters during the years 1846-53, particularly regarding whether or not japan was to purchase a western-style warship. The bakufu official in charge of the defense of Uraga bay (the Uraga bugyo 奉行) advocated the purchase of a western-style warship, but they were overruled by the both the bakufu official in charge of naval defense (the kaibo kakari 海防掛) and the four daimyo houses responsible for naval defenses (the kaibo yonke 海防四家), who in fact advocated the construction of coastal batteries. Accordingly, the Abe regime had no choice but to promote the creation of these coastal batteries.
- 著者
- by Tadao Kano and Kokichi Segawa
- 出版者
- Seikatsusha
- 巻号頁・発行日
- 1945
1 0 0 0 OA 香川県小学校教員検定試験問題集
1 0 0 0 IR 山川菊栄の産児調節論
- 著者
- 曽和 幸生
- 出版者
- 北海道大学大学院文学研究科映像・表現文化論講座
- 雑誌
- 層 : 映像と表現
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.129-148, 2019-03
1 0 0 0 OA いわゆる “ハウス病” 症候群の本態とその予防に関する研究
- 著者
- 若月 俊一 松島 松翠 荒木 紹一 筒井 淳平 白井 伊三郎 高松 誠
- 出版者
- 一般社団法人 日本農村医学会
- 雑誌
- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.4, pp.399-413, 1973-01-10 (Released:2011-02-17)
長野, 愛知, 三重, 徳島, 福岡の5地区において, 同一の調査方法により, ハウス栽培従事者の健康調査を行なった。調査人員は, 昭和45年415名 (男230名, 女185名), 昭和46年458名 (男185名, 女273名) であるが, 別に対照として, 一般農家を昭和45年152名 (男73名, 女79名), 昭和46年281名 (男118名, 女163名) 同一方法で調査した。このうち農繁閑期を通じて同一人を調査できた30代, 40代のものについて, ハウス栽培状況及び健康状況を分析した結果は次の如くである。1) 各地域におけるハウス栽培状況の比較調査対象農家1戸あたりのハウス栽培面積は, 三重。が最も多く, 29.7a, 長野が13.5aでもっとも少なかった。暖房の設備状況は, 各地域によって異なるが, そのうち煙突を装備しているものは, 愛知, 三重, 徳 島では大部分であるが, 長野及び三重では約半数に過ぎなかった。その他副室, 換気窓, 面側扉の設備は地域により差異がある。農薬はハウス内でかなり使われており, 有機硫黄剤が多いが, その他の強毒性殺虫剤も多かった。2) 各地域及び農繁閑期における健康状態の比較労働時間は, 一般に農繁期, しかも女子に多く, 睡眠時間は, 逆に農繁期, 女子は少ない。ハウス栽培作業の最盛期には, ハウス内作業は1日8時間にも及んでいる。農夫症症候群は農繁期に多く, 症状としては, 肩こり, 腰痛が多く, 男子に比べて女子に多い。自覚的疲労症状も同様で農繁期に多く, 女子に多い傾向にある。地域別では, 農夫症症候群は三重, 福岡に多く, 疲労症状の発現率は福岡に多くみられた。検査成績では, 女子に貧血の傾向がみられるが, とくに農繁閑期で大きな差はみられない。地域別には若干の違いがみられた。血清コリンエステラーゼ活性値が20%近く異常値を示したことは, 今後ハウス内の, dermal absorption riskのほかに, inhalational exposureの危険についてもさらに深い調査を行なわねばならないことを示すものと思われる。3) ハウス栽培農家と対照農家の健康状態の比較労働時間は, ハウス栽培農家の方が対照農家に比べて多く, とくに女子において著明である。睡眠時間は, ハウス栽培農家の方が少ない傾向がみられた。農夫症症候群は, 農繁期にはハウス栽培農家に多い傾向がみられ, 症状として, 肩こり, 腰痛, めまい, 不眠などがハウス栽培農家に多い。疲労症状もとくに農繁期には, ハウス栽培農家に高いが, 「頭が重い」「全身がだるい」「肩がこる」「体のどこかがだるい」「足がだるい」 といった症状が多くみられた。また検査成績では, ハウス栽培農家に肝機能異常や血清コリンエステラーゼ活性値低下を示すものが若干みられた。以上の結果により, ハウス栽培従事者には, 一般農家にくらべて, とくに農夫症, 疲労症状等, 自覚症状が多くみられており, これらはハウス病症候群と呼ばれる症候群の一部を構成している。そして, その原因として高温多湿の作業環境, 農薬散布, 作業姿勢等が考えられるが, 今後, 予防対策として, ハウス内の構造の改善, とくに大型換気扇の設置, また労働条件の改善, とくに農薬散布方法の改善等が必要であろう。さいごに, 去る第5回国際農村医学会 (ブルガリヤ・バルナ市) における東欧諸国の研究や調査の発表では, ハウス栽培における農薬散布が原因する健康障害のテーマが, 少なからずとりあげられていたことをとくに付記する。