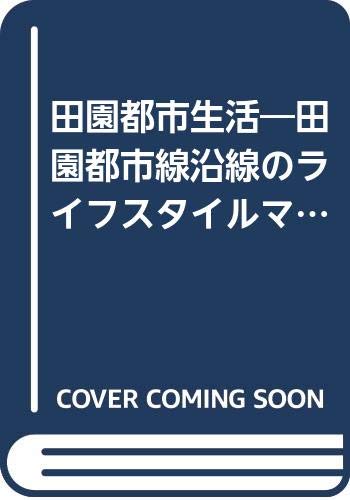1 0 0 0 OA サケ科魚類の致死性雑種と染色体異常
- 著者
- 伊藤 大一輔 藤原 篤志 阿部 周一
- 出版者
- Japanese Society of Animal Breeding and Genetics
- 雑誌
- 動物遺伝育種研究 (ISSN:13459961)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.1, pp.65-70, 2006-06-01 (Released:2010-03-18)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 5 3
1 0 0 0 OA 入院患者に対する後頸部温罨法と生理学的指標,主観的睡眠および快感情の関連
- 著者
- 加藤 京里
- 出版者
- 日本看護技術学会
- 雑誌
- 日本看護技術学会誌 (ISSN:13495429)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.3, pp.10-18, 2012-01-15 (Released:2016-08-01)
- 参考文献数
- 27
本研究は,入院患者に対する後頸部温罨法について,生理学的指標,主観的睡眠および快感情との関連を明らかにすることを目的とした.入院中の女性 (61.8 ± 22.2歳) 6名を対象者とし,連続した3日間,就寝前に 40℃ 10分間の後頸部温罨法を実施した. 後頸部温罨法を実施後,実施前に比較して手掌皮膚温が有意に上昇した (p=0.039)鼓膜温は有意な変化は認められなかった.対象者は後頸部温罨法によって温かさと気持ちよさを感じていた.温罨法施行中の快には,唾液アミラーゼが低下するような休息的快と,唾液アミラーゼが上昇する活動的快が含まれた.夜間の主観的睡眠状況については,研究前と研究3日目の比較において OSA睡眠調査票得点における総得点 (p=0.011),疲労回復得点 (p=0.008) が上昇し,睡眠の改善をみせた. 後頸部温罨法は,唾液アミラーゼの上昇を伴う活動的快と唾液アミラーゼの低下を伴う休息的快が生じ,手掌の皮膚温上昇をもたらし,睡眠を促す可能性があることが示された.
1 0 0 0 OA 5.血液疾患 1)血球検査
- 著者
- 宮地 勇人
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.97, no.12, pp.2966-2973, 2008 (Released:2012-08-02)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1
末梢血検査は,各血球の定量,大きさや細胞形態に関連したパラメータ測定および評価を行う.自動血球分析装置では,血球数に加え,白血球分類,網赤血球数が自動化され,高い測定精度と信頼性がもたらされた.一部の機種は,新規項目として,網血小板,網赤血球ヘモグロビン量,破砕赤血球定量,末梢血幹細胞などが測定できる.また,免疫学的測定が導入され,免疫学的血小板数測定やリンパ球サブセットなどに利用されている.
- 著者
- 伊藤 守康
- 出版者
- 明治神宮国際神道文化研究所
- 雑誌
- 神園 = Journal of the Meiji Jingu Research Institute (ISSN:18832725)
- 巻号頁・発行日
- no.18, pp.183-194, 2017-11
1 0 0 0 OA 重力勾配テンソルの固有ベクトルを用いた断層あるいは構造境界の傾斜角の推定
- 著者
- 楠本 成寿
- 出版者
- 社団法人 物理探査学会
- 雑誌
- 物理探査 (ISSN:09127984)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.4, pp.277-287, 2015 (Released:2017-03-02)
- 参考文献数
- 58
- 被引用文献数
- 3 4
ダイクのように,一様な傾きをもつ2次元的な構造の傾斜角推定に用いられる手法を,断層や構造境界の傾斜角推定に応用した。応用に先立ち,断層あるいは構造境界の傾斜角の推定に応用できるかどうかの数値テストを行った。その結果,それらの傾斜角を推定でき,推定された傾斜角の分布から正断層と逆断層の違いを識別できることが明らかになった。実フィールドへの応用として,伊予灘から別府湾を経て豊肥火山地域に至る地域周辺の重力異常に本手法を適用し,既存研究で得られている構造傾斜角と調和的な傾斜角分布を得た。
1 0 0 0 OA 反張膝の膝過伸展域での運動学的特性
- 著者
- 平川 善之 野原 英樹 北條 琢也 蓮尾 幸太 山崎 登志也 原 道也 花田 弘文 渡辺 誠士
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.32 Suppl. No.2 (第40回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.C0331, 2005 (Released:2005-04-27)
【目的】反張膝はスポーツ障害・外傷に結びつくマルアライメントの一つである。臨床上、反張膝が原因と思われる半月板・靭帯損傷や、膝を徒手的に強制過伸展させることで再現できる膝蓋下や膝窩の疼痛を経験する。しかしこの疼痛を説明できる反張膝の過伸展域での運動動態を現したものはみられない。そこで今回健常者を対象に、膝過伸展角度を測定後、X線透視下にて膝伸展0°位(以下0°位)及び最大努力伸展位(以下HE位)の2条件の膝関節肢位で形態的特長を分析し、興味ある知見が得られたので報告する。【対象】下肢に疾患を有しない健常者19名(男性10名女性9名)36肢、平均年齢25.4±4.2歳である。【方法】a、膝過伸展角度の測定:被検者全員を立位にて、膝を最大過伸展させ、大転子・膝関節中央・外果を結んだ線を計測した。伸展角度15°以上を重度過伸展群(以下A群)、5°以上15°未満を中度過伸展群(以下B群)、5°以下を非過伸展群(以下C群)に分類した。b、X線透視:X線透視は全被験者に本研究の十分な説明を行い、同意を得た上で行った。東芝製透視装置(KXO-15C)を使用し、被験者は座位で矢状面より透視下にて大腿骨が真側面となるよう調節し、0°位とHE位の2肢位を3秒間静止させ録画した。録画した映像を画面上でトレースし以下の項目を測定した。脛骨関節面傾斜角(以下TJA):中点法により求めた大腿骨長軸と脛骨関節面のなす角とし、膝の前方で大腿骨側を計測した。脛骨前方変位量(以下TAD):大腿骨長軸と平行に大腿骨外・内顆と脛骨外・内顆に接する線を作図しその距離を測定し、大腿顆部最大前後径で除して標準化した。これらの形態的数値を基に0°位、HE位で、各群間を比較することにより、過伸展域での運動学的特性を分析した。統計処理は分散分析(有意水準5%未満)および多重比較(有意水準1%未満)を用いた。【結果】1:被検者の内訳はA群5名、B群6名、C群8名であり、平均膝過伸展角度は7.5°(±4.5°)であった。2:TJAは被験者の群間および膝関節肢位の両方の主効果が有意であった。HE位においてA群はC群よりも有意に大きかった。3:TADは群間の主効果に有意差はなかった。【考察】結果2、3より、0°位では膝過伸展角度の程度に関らず、各群間で形態的な特徴はみられないが、HE位ではA群はC群と比べ、脛骨前方変位に差はなく脛骨関節面の傾斜が大きくなることがわかった。このことはC群に比べてA群では、0°位から過伸展する際に、いわゆる「滑りと転がり運動」のうち、「滑り」に差はないが「転がり」が強いと考察された。これにより膝前方では脛骨関節前面と大腿骨関節面が衝突し、ここが支点となって後方では大腿・脛骨間距離が開大し、関節構成体の緊張の増大が起こることが推測される。このため強制過伸展により膝蓋下や膝後面に疼痛を生じさせる機序が考えられた。
1 0 0 0 OA 反張膝の有無によるヒール歩行の運動学的特性
- 著者
- 百瀬 伸平 小山田 美咲 柏倉 由佳 高橋 千央 田口 彩乃 大川 孝浩 山﨑 敦
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.42 Suppl. No.2 (第50回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.0964, 2015 (Released:2015-04-30)
【目的】健常者の反張膝の有無による歩行時の関節角度,関節モーメントに有意差がないことの報告(河原ら,2010)はみられるが,ヒール歩行と反張膝との関連についての報告はみられない。今回,反張膝の有無が裸足歩行およびヒール靴を着用した歩行について運動学的分析を行ったので報告する。【方法】対象は,1年以内に整形外科疾患のない足のサイズ24.5cmの健常女性22名とした。実験に先行してプラスチック角度計にて立位で膝関節伸展角度を計測し,5°以上のものを反張膝群,5°未満のものを非反張膝群とした。関節角度・関節モーメントの計測には,光学式三次元動作分析装置(VICON Nexus,VICON社)および床反力計(Force Platform OR6-7,AMTI社)を用いた。サンプリング周波数100Hzで計測したデータをもとに,股関節屈曲-伸展,膝関節屈曲-伸展および外反-内反,足関節背屈-底屈の関節角度および関節モーメントを算出した。なお関節モーメントは,対象者の体重で除して正規化を行った。裸足歩行およびヒール歩行は自由歩行速度で行った。ヒール靴はヒール高7cmのものを使用した。ヒール靴に慣れさせるため,トレッドミル上で3分間の歩行練習を行った。この際の歩行速度は,事前に算出した10m歩行速度とした。反射マーカの変位から左足趾離地から右踵離地(立脚中期)を決定し,この期間の関節角度・関節モーメント(最大値)を分析対象とした。また,表面筋電図の計測には多チャネルテレメータシステム(WEB-7000,日本光電社)を使用した。内側広筋,外側広筋,半腱様筋,大腿二頭筋,前脛骨筋を対象に,サンプリング周波数1,000Hzで計測し,単位時間当たりの積分筋電図を求めた。これらのデータは,各筋の最大等尺性収縮時の積分筋電図をもとに正規化し,積分筋電図(%IEMG)を算出した。統計学的分析には,SPSS Statistics21を使用した。反張膝群,非反張膝群ともに,裸足歩行およびヒール歩行の比較を対応のあるt検定にて行った(有意水準5%)。【結果】関節角度は,非反張膝群,反張膝群ともにヒール歩行で,股関節屈曲,膝関節屈曲・内反,足関節底屈角度がやや増加していた。股関節伸展モーメントは,非反張膝群,反張膝群に関わらず,裸足に比してヒール歩行で有意に高値を示していた(p<0.01)。膝関節では,非反張膝群の伸展モーメントが裸足歩行に比してヒール歩行で高値を示していた(p<0.01)。また外反モーメントについては,両群ともにヒール歩行で有意に高値を示していた(p<0.001)。一方の足関節底屈モーメントは,非反張膝群,反張膝群ともにヒール歩行で低値を示したが,有意差は認められなかった。%IEMGは,非反張膝群において内側・外側広筋にてヒール歩行で有意に高値を示していた(p<0.001)。また反張膝群では,半腱様筋においてヒール歩行で有意に低値を示していた(p<0.01)。【考察】ヒールを着用した立位姿勢では上半身後方移動,骨盤後方移動を行うことで,姿勢の不安定性を制御している(友國ら,2008)。つまり,ヒールを着用することで足関節が底屈位に固定されて下腿が前傾するため,膝関節屈曲,股関節屈曲位とする代償がみられたことになる。今回の結果では,股関節伸展および膝関節伸展モーメントが,裸足歩行に比してヒール歩行時に高値を示しており,動的状況下においても同様の制御が伺えるものと考えられる。膝関節の屈曲角度は,両群ともにヒール歩行でやや増加していたが,膝関節モーメントは非反張膝群のみで有意に高値を示していた。一方の筋活動をみると,反張膝群では半腱様筋においてヒール歩行で有意に低値を示していた。つまり,反張膝群のヒール歩行では,膝関節の屈曲モーメントをあまり必要としないことが示唆される。また,外反モーメントが両群ともにヒール歩行で有意に高値であったことは,足部の運動の関与が伺える。裸足歩行では荷重量の増大に伴い,足部は内反から外反へと運動の変換がなされるが,支持面の狭いヒール歩行ではこの運動が十分になされない。つまり,膝関節内反角度の増大に伴い,外反モーメントの発揮が求められたことが示唆される。【理学療法学研究としての意義】現代社会においてはヒール靴の使用頻度は非常に高いものの,女性に多い反張膝と関係性を示した研究はみられなかったことから,理学療法士として社会的貢献の一助となりえる。
- 著者
- 田中 唯太 小倉 加奈代 西本 一志
- 出版者
- 情報処理学会
- 雑誌
- インタラクション2012論文集 (情報処理学会シンポジウムシリーズ) (ISSN:13440640)
- 巻号頁・発行日
- vol.2012, no.3, pp.917-922, 2012-03-17
食卓で共有されている大皿料理から料理を取るとき,共食者間でのインタラクションが期待されるが,大皿料理が持つコミュニケーション活性化機能が十分発揮される形で共有されていない為に,大皿料理を介したインタラクションは限定的である.本研究では,お酒の「お酌」行為に注目し,お酌が持つコミュニケーション機能を「自分の皿に料理を取ることを禁止する」という手法を用いて大皿料理に持ち込む.提案した手法の妥当性を検証しつつ,食卓コミュニケーション支援メディアGiantCutleryの実装を行い,食卓で用いることで初期的な評価実験を行った. : It is expected that interactions among tablemates arise when tey dish out foods from a platter at a dinner time. However, the interactions are actually restricted because the platter's potential of vitalizing dinner-table communications is not effectively exploited. We focus on "Oshaku", a Japanese habit: the tablemates pour the platters at a dinner time. This paper investigates whether Oshaku behavior can be incorporated into the platter. Inaddition, we developed GiantCutley, which is a support medium for dining-table communications. We report results of apilot study for estimating effectiveness of GiantCutlery.
1 0 0 0 小脳損傷と高次脳機能障害:損傷部位と各障害との関係
- 著者
- 手塚 純一 大塚 洋子 長田 正章 岩井 良成
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2010, pp.BbPI2176, 2011
【目的】<BR> 長い間、小脳は純粋に姿勢の制御や随意運動の調節を行なうための神経基盤であると考えられてきた。1980年代半ばから、神経心理学・解剖学・電気生理学などの発展により、運動・前庭機能以外にも様々な認知過程に関与することが明らかになってきた。1998年にはSchmahmannとShermanが小脳病変によって生じる障害の4要素(遂行機能障害・空間認知障害・言語障害・人格障害)を小脳性認知・情動症候群(CCAS)として提唱した。しかしながらリハビリテーションの領域では小脳と高次脳機能についての報告は散見されるが症例報告に留まっており、特に理学療法における報告は少ない。本研究の目的は、小脳の損傷部位と臨床症状の関係について量的研究を行ない、理学療法における小脳損傷に伴う高次脳機能障害に対する対処の必要性を明らかにすることである。<BR>【方法】<BR>1.対象:<BR> 対象は2008年1月から2010年10月の間に脳卒中を急性発症し当院に入院した患者連続895例のうち、小脳に限局した病変を有する39例である。除外基準は1)脳室穿破、2)水頭症、3)発症前より明らかな認知機能低下を有する例とした。<BR>2.方法<BR> 調査項目は年齢、性別、梗塞・出血の種別、画像所見、臨床症状とした。画像所見は入院時に撮影した頭部CTもしくはMRI画像を利用し、小脳の損傷部位を虫部、中間部、半球部に分け列挙した。臨床症状は意識清明となった時点での運動失調、見当識障害、注意障害、記憶障害、言語障害、空間認知障害、人格障害について次の基準で有無を判定し列挙した。運動失調は鼻指鼻試験もしくは踵膝試験での陽性反応を、人格障害はFIM(Functional Independence Measure)社会的交流項目での減点を認めた場合に有とした。それ以外はMMSE(Mini-Mental State Examination )、HDS-R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)の、見当識障害:見当識項目、注意障害:計算項目及び逆唱項目、記憶障害:遅延再生項目、言語障害:物品呼称項目もしくは語想起項目、空間認知障害:図形模写項目、において減点を認めた場合に有とした。<BR>3.解析<BR> 損傷部位と臨床症状に関連があるかを、フィッシャーの正確確率検定を用いて検討した。なお統計学的判定の有意水準は5%未満とした。<BR>【説明と同意】<BR> 本研究は個人情報を匿名化した上で、その取り扱いについて当院の規定に則り申請し許可を得た。<BR>【結果】<BR>1.最終対象者<BR> 39例中5例は脳室穿破、水頭症もしくは発症前からの認知機能低下を有し対象から除外した。従って最終対象者は34例(男性18例、女性16例、平均年齢70.2±11.0歳)であった。<BR>2.脳損傷様式<BR> 小脳梗塞11例、小脳出血23例、損傷部位は虫部~半球部に渡るものが15例、虫部~中間部が8例、中間部~半球部が9例、半球部のみが2例であった。<BR>3.臨床症状<BR> 項目毎に発生数を計上すると、運動失調31例(91.2%)、記憶障害23例(67.6%)、見当識障害17例(50.0%)、注意障害14例(41.2%)、言語障害9例(26.5%)、人格障害5例(14.7%)、空間認知障害5例(14.7%)であった。上記の症状の多くは合併し、総合すると24例(70.6%)に何らかの高次脳機能障害を認めた。半球部に損傷がある26例のうち22例(84.6%)に何らかの高次脳機能障害を認めた。半球部に損傷がない8例のうち6例(75.0%)には高次脳機能障害を認めなかった。<BR>4.解析<BR> 検定の結果、有意な独立性を認めた項目は1)虫部~中間部の損傷と運動失調の発生率(p<0.01)、2)半球部の損傷と何らかの高次脳機能障害の発生率(p<0.01)、3)半球部の損傷と記憶障害の発生率(p<0.001)であった。<BR>【考察】<BR> 半球部は歯状核から視床外側腹側核を経由して運動前野や前頭前野・側頭葉に投射し、小脳-大脳ループとして認知機能に関与している。本研究で半球部損傷の多くに高次脳機能障害を認めたことは、SchmahmannとShermanの報告と一致した結果となった。多くの例に記憶障害を認めたことにより、CCASの概念で取り上げられている作動記憶の障害や視空間記憶の障害だけでなく、エピソード記憶の障害にも小脳が関与している可能性が示唆された。<BR> 記憶障害・注意障害等による生活指導の定着率低下や、人格障害による練習の拒否等の問題は、理学療法の進行に大きな影響を与える。半球部に損傷を認めた場合には、高次脳機能障害の有無を精査し対処していく必要があると考える。今後は半球部損傷のみの症例数を増やすと同時に、各臨床症状の半球部における責任領域について検討を重ねていきたい。<BR>【理学療法学研究としての意義】<BR> 小脳損傷に伴う高次脳機能障害は患者の学習や社会復帰において多大な影響を与える要素であり、理学療法においてもその研究と対策は重要である。本研究はその一助となると考える。
1 0 0 0 OA リアルタイム UNIX RX-UX 832
- 著者
- 日本電気マイコンテクノロジー (株)
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測と制御 (ISSN:04534662)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.11, pp.1053-1054, 1990-11-10 (Released:2009-11-26)
1 0 0 0 OA 味覚の形成とその発達
- 著者
- 鳥居 邦夫
- 出版者
- 日本海水学会
- 雑誌
- 日本海水学会誌 (ISSN:03694550)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.3, pp.197-204, 1994 (Released:2013-02-19)
- 参考文献数
- 22
1 0 0 0 OA 味覚の形成とその発達
- 著者
- 鳥居 邦夫
- 出版者
- 日本口腔・咽頭科学会
- 雑誌
- 口腔・咽頭科 (ISSN:09175105)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.1, 1994-08-31 (Released:2010-06-28)
- 著者
- 中島 大輔
- 出版者
- 鹿児島大学
- 雑誌
- 経済学論集 = Journal of economics and sociolgy, Kagoshima University (ISSN:03890104)
- 巻号頁・発行日
- no.87, pp.41-79, 2016-10-17
- 著者
- 森山 清徹
- 出版者
- 佛教大学文学部
- 雑誌
- 文学部論集 (ISSN:09189416)
- 巻号頁・発行日
- no.80, pp.15-34, 1996-03
本稿は,Santideva(c.650-700) のBodhicaryavatara(BCA)及びそれに対するPrajnakaramati(11c)の注釈(panjika)(BCAP)より,唯識派の自己認識(svasamvedana)の理論に対する批判部分の検証と和訳である。Santidevaの自己認識批判は, Candrakirti(c.600-650)の自己認識批判の単なる反復ではなく,彼独自の新理論の展開をも示すものである。つまり, Candrakirtiは,ミーマーンサ一学派のKumarliaによるDignagaの自己認識の理論一量,所量,量果の同体論―に対する批判を受けDignagaを批判したのであるが,Santidevaは,Dharrnakirti(c.600-650) の自己認識の理論をも批判している。自己認識批判シャーンティデーヴァプラジュニャーカラマティディグナーガダルマキールティ
1 0 0 0 OA 少子化対策と不妊治療への保険適用 : バイオエシックスの視座から
- 著者
- 仙波 由加里
- 出版者
- 日本生命倫理学会
- 雑誌
- 生命倫理 (ISSN:13434063)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.190-197, 2003-09-18 (Released:2017-04-27)
- 参考文献数
- 36
近年、日本では少子高齢化が社会問題として注目され、これを打開するために政府は少子化対策をすすめている。この中で不妊に注目し、不妊治療に保険適用しようとする動きがある。しかし、少子化対策の本来の目的は出生回復させることであり、不妊当事者の利益を第1に考えているわけではない。Warwickは家族計画プログラムの検討の際に、(1)自由(2)正義(3)福祉(4)真実の告知(5)安全・生存という5つの倫理原則を設けた。少子化対策として不妊治療に保険適用する場合も、これらの原則に照らすと様々な問題を抱えていることがわかる。バイオエシックスの視座に立てば、不妊治療への保険適用は、少子化対策としてではなく、リプロダクティブライツの尊重や不妊当事者のQOL向上の視点から検討していくことが必要である。
1 0 0 0 OA 情報検索時代の事例研究(その2)―アインシュタインの碑の物語―
- 著者
- 藤野 清次 久野 孝子
- 雑誌
- 研究報告人文科学とコンピュータ(CH)
- 巻号頁・発行日
- vol.2014-CH-101, no.3, pp.1-8, 2014-01-18
大量の情報 (ほとんど無用のゴミかもしれないが) の中から検索で,自分が欲しい有用な情報を探す時代がやってきた 1) 10) 11) 12) 13).現代社会においてデジタル情報資源は日々増加の一途を辿り減ることはない.そこで,1922 年 12 月福岡の和風旅館栄屋に泊ったアインシュタイン博士の軌跡を博士の碑という糸口からインターネットによる情報検索を活用し追跡した.その調査結果を以下に報告する.
1 0 0 0 OA 食物名考 I
- 著者
- 池添 博彦
- 出版者
- 帯広大谷短期大学
- 雑誌
- 帯広大谷短期大学紀要 (ISSN:02867354)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.A1-A22, 1984 (Released:2017-06-09)
1 0 0 0 OA ラレタイとテモライタイの意味と用法に関する考察
- 著者
- 熊井 浩子
- 出版者
- 静岡大学国際交流センター
- 雑誌
- 静岡大学国際交流センター紀要 (ISSN:13471260)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.1-21, 2010-03-30
- 出版者
- 枻出版社
- 巻号頁・発行日
- 2000