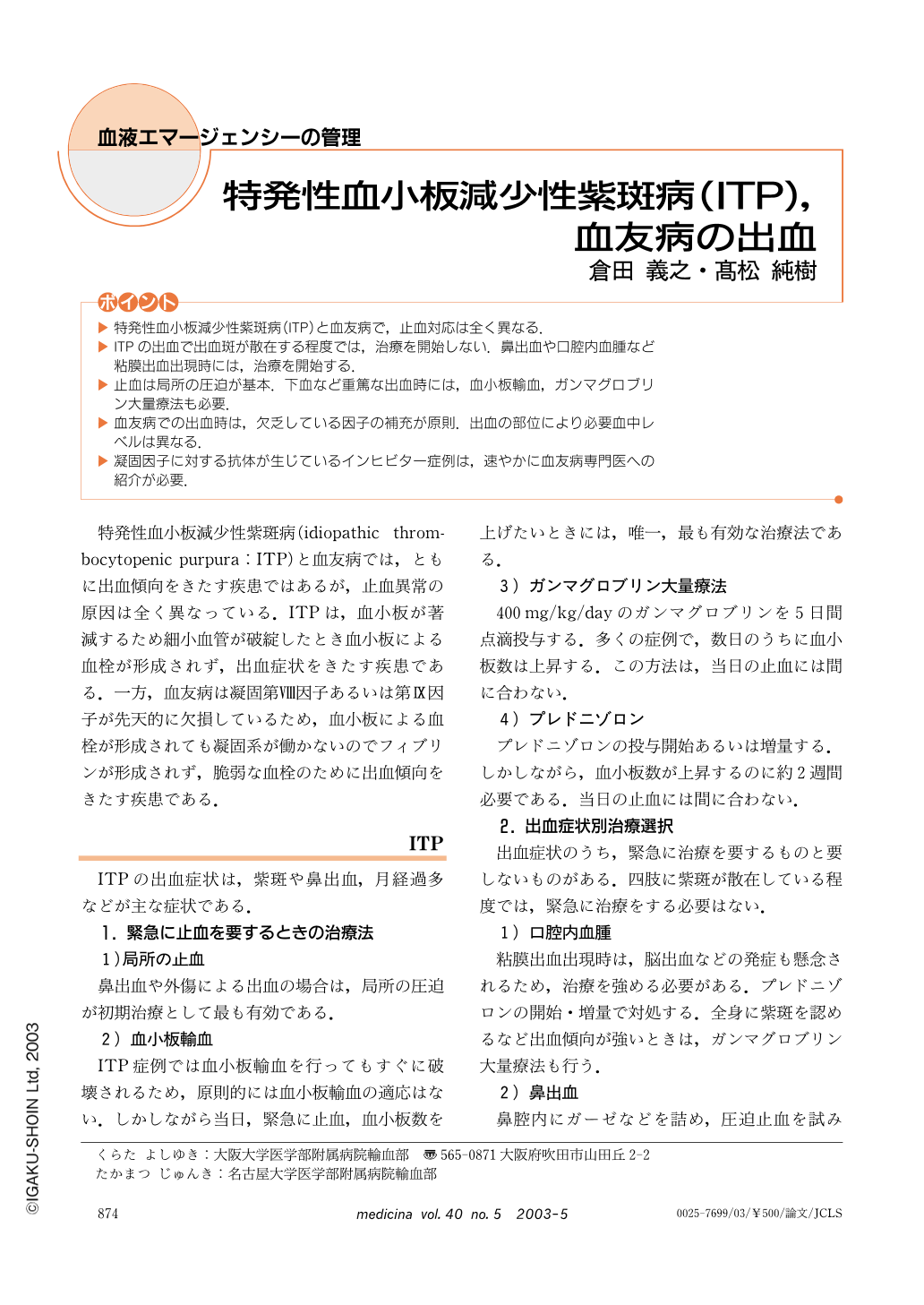1 0 0 0 OA 十日物語 : デカメロン
1 0 0 0 OA 十日物語 : デカメロン
1 0 0 0 トクヴィルにおけるアソシアシオンの概念
- 著者
- 富永 茂樹
- 出版者
- 社会学研究会
- 雑誌
- ソシオロジ (ISSN:05841380)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.3, pp.1-17,107, 1979
Nous allons examiner, ici, la notion d'association qu'a proposée Alexis de Tocqueville dans son De la démocratie en Amérique et qu'il a considérée comme un des meilleurs moyens pour défendre la liberté menacée à la société démocratique.<br> En résumant ses analyses, nous pouvons dire qu'il faut pour constituer une association les quatre conditions: (1) un but commun, (2) la participation volontaire, (3) la validité du contrat, et enfin, (4) l'existence d'une action réciproque. Ensuite, ce type de groupe a deux fonctions sociales; c'est d'une part d'être un groupe intermédiaire dans la société totale, et d'autre ·part, de jouer le rôle important de rapport entre les individus qui s'engagent dans )'association. La première fonction est politique et la seconde est morale ou psychologique.<br> Quant à la première fonction, nous pouvons y trouver la ressowrce d'une force restreignant le pouvoir de l'Etat qui va toujours s'agrandir avec le dévelowement de la démocratie. C'est un rôle pour ainsi dire de contrepoids à la centralisation dont est chargée l'association.<br> En ce qui concerne l'autre fonction, il est possible de la considérer comme une sorte de controle social, de régulation sociale pour les individus qui se trouvent atomisés et solitaires au sein de la société démocratique. Ce n'est rien d'autre que le lien social disparu que Tocqueville allait rechercher dans l'association.<br> L'importance de la théorie sociologique de Tocqueville se comprendra bien, quand nous remarquons ses deux fonctions de l'association dont chacune devait répondre aux problèmes sociaux de son temps (et peut-être aujourd'hui encore). C'est à partir de l'examen rn inuti eux de la notion d'association que nous pouvons situer Tocqueville au milieu de la tradition féconde de la sociologie française au XIXème siècle.
1 0 0 0 OA 拘縮肩に対するサイレントマニピュレーションの臨床成績
- 著者
- 古賀 唯礼 本多 弘一 後藤 昌史 中村 秀裕 久米 慎一郎 志波 直人 大川 孝浩
- 出版者
- 西日本整形・災害外科学会
- 雑誌
- 整形外科と災害外科 (ISSN:00371033)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.3, pp.540-543, 2019-09-25 (Released:2019-12-17)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1
〈目的〉拘縮肩に対するサイレントマニピュレーション(SM)の治療成績を検討した.〈対象と方法〉拘縮肩症例26肩(平均年齢57.5歳)に対し,皆川らの方法に準じSMを施行し,経時的に評価した.〈結果〉術前/術後6ヵ月後の各平均値は,屈曲:109±25.4°/148±12.2°(P<0.0001),外転:96±38.8°/152.9±23.9°(P<0.0001),外旋:26.4±14.3°/43.8±18.7°(P<0.0001),内旋:L5±3.3/Th11±2.7椎体(P<0.0001)といずれも改善を認めた.またJOAスコア:40.9±9.6/65.6±9.6(P<0.0001),UCLAスコア:15.9±3.9/27.3±5.5(P<0.0001),およびVisual analogue scale(VAS)はVAS rest:26.3±33.8/5.1±10.9(P=0.0123),VAS night:38.1±33.6/4.7±8.9(P=0.0007),VAS motion:67.5±24.7/17±15(P<0.0001)といずれも改善した.〈結語〉SMは拘縮肩に対して有効な治療法と思われる.
1 0 0 0 OA 台湾の少子化と非婚化にみる祖先祭祀の行く末
- 著者
- 上水流 久彦
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集 日本文化人類学会第53回研究大会 (ISSN:21897964)
- 巻号頁・発行日
- pp.E21, 2019 (Released:2019-10-01)
台湾漢人社会では、男性子孫をもうけ、その子孫が祖先祭祀を行うことが当然とされてきた。男性は結婚し、男子を得ることでそれが可能となった。また女性は婚出し、そこで男子を生み、花婿側の祖先祭祀を継続させ、自分を祭祀する者を確保してきた。しかし、台湾社会では少子化と非婚化が進んでおり、男子が祖先崇拝を継承することを一層困難にしている。台湾の漢人はこの事態をどのように認識し、対処しているのだろうか。本発表では、伝統的な祖先祭祀から逸脱すると思われる「娘しかいない家庭」、「姉妹しかいない女性」、「未婚で子どもがいない女性」の聞き取りから、初歩的検討を行う。その検討からは、男性は「一族」という単位が祭祀の解決方法として選択肢に入っているが、女性にはない点、祭祀継承の観念よりも、「親と子」の単位の祭祀の重視されている点が明らかとなった。
1 0 0 0 OA 行政アーバンデザインの実態と課題に関する考察
- 著者
- 中農 一也 鳴海 邦碩 澤木 昌典
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.991-996, 2002-10-25 (Released:2017-11-07)
- 参考文献数
- 8
行政アーバンデザインは、全国画一的な都市づくりから地域の個性を活かした地域環境に相応しい都市づくりに変えようとする意識のある自治体が主体的に取り組んできたものである。1971年の横浜市を皮切りに、1980年代から全国的な広がりを見せ、多くの自治体に「都市デザイン室」や「都市景観課」などの行政アーバンデザインを推進するセクションが組織化され、主に都市景観条例を制度的根拠として、個性的なまちづくりが展開されてきた。しかしその一方で、根拠法の脆弱さや行政の厚い縦割りの壁などのシステム上の理由などから様々な課題も抱えている。「都市型社会」へ移行する21世紀において、都市の再構築が各自治体において最重要課題となっており、ますます行政アーバンデザインの積極的な取り組みが求められている.また、近年、特定非営利活動促進法の制定等のように市民主体のまちづくりへの大きな潮流が見られ、一部の自治体において、既に組織の再編や新たな条例制定等の動きがあり、今後、行政アーバンデザインの取り組み方やシステムの見直しが一層進むことが予想される。本研究は、筆者の一人が直接的に携わった沖縄県那覇市都市デザイン室の実践を通して行政アーバンデザインの現状と実態を明らかにし、全体的な実践システムの問題点と課題の考察を行うことを目的とし、今後求められる行政アーバンデザインのあり方についての知見を得る。
1.文献検討および解析プロトコルの検討:本研究では、①母親がマインドフルネス・トレーニングを実践することにより、母親および発達障害児(ASD、ADHD)においてどのような効果が生じるかについて検討すること、②ペアレント・トレーニングおよびマインドフルネス・トレーニングが有するそれぞれの特徴の違いに着目し、両トレーニングの長所を生かした育児支援方策のあり方を検討すること、の2点を主な目的として、文献検討および解析プロトコルの検討を行った。母親のアウトカムとして、育児ストレスの変化をはじめ、養育スタイルや主観的幸福感の変化にも着目すること、子のアウトカムとして、行動面および情緒面の変化を捉える必要性があることが示唆された。また、母親の既往歴、母親以外の者(父親など)の育児関与の有無、母親・子のストレスを生じさせるライフイベントの有無、子の投薬変更の有無、などを調整因子として含める必要性があることが示唆された。2.各アプリケーションの開発:文献検討および解析プロトコルの検討を行った上で、本研究で使用するペアレント・トレーニングおよびマインドフルネス・トレーニングのスマートフォン用アプリケーションを作成した。作成の際は、①各トレーニングの動機づけの維持、②各トレーニングの日々の達成度の記録、の2点が可能なように工夫を行った。なお、広く研究参加者を募集するために、スマートフォンはiPhoneおよびアンドロイドで実施できるようにしている。
- 著者
- 小田内 隆
- 出版者
- 立命館大学人文学会
- 雑誌
- 立命館文學 = The journal of cultural sciences (ISSN:02877015)
- 巻号頁・発行日
- no.657, pp.1117-1111, 2018-03
1 0 0 0 OA 元号と武家
- 著者
- 北爪 真佐夫 Masao KITAZUME 札幌学院大学人文学部 Faculty of Humanities Sapporo Gakuin University
- 雑誌
- 札幌学院大学人文学会紀要 = Journal of the Society of Humanities (ISSN:09163166)
- 巻号頁・発行日
- no.68, pp.1-32, 2000-09-30
わが国の元号は中国より移植したもので, 最初の元号は「大化」(645)といわれているが「大宝」とみた方が確度がたかいとみることができよう。いずれにしても249程の「元号」が今日まで使用されてきているのだが, 現在の「平成」を除けばその決定権は天皇にあったものとみてよいであろう。法制史家滝川政次郎氏は元号大権とは「天皇が元を建て, 元を改められる権利であって, この権利は臣下の者の干犯を許さない天皇に専属せる権利」(同氏著「元号考讃」)であるといっておられる。古代国家の確立期に整備導入された元号制は十二世紀末あたりから確立した武家権門としての鎌倉幕府ならびにそれ以降の「武家」とはどんな関係にあったのか, こうした検討を通じて平安末期以降の「国王」及び「王権」の特質はどの点にあったのかに接近しようとの試みが本稿の課題である。なお封建時代を通じて元号制度が存続し得た理由として考えられるのは三代将軍家光の言といわれる「年号ハ天下共二用フルコトナレバ」という一言に端的に示されているし, それ以前でいえば, 「公武」ならんで用いるものとの考え方が定着しているのである。つまり, 「元号」はある天皇の時代を意味するものでなく, ましてや天皇の独占物でなくなったことが, 封建制下でも, なお維持存続した理由とみてよいであろう。
1 0 0 0 OA 抗ウイルス物質産生細菌による魚類ウイルス病の制御
- 著者
- 吉水 守 絵面 良男
- 出版者
- Japanese Society of Microbial Ecology / Japanese Society of Soil Microbiology / Taiwan Society of Microbial Ecology / Japanese Society of Plant Microbe Interactions / Japanese Society for Extremophiles
- 雑誌
- Microbes and Environments (ISSN:13426311)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.4, pp.269-275, 1999-12-31 (Released:2009-10-05)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 7 10
Many bacteria producing anti-viral substances were isolated from the aquatic environment. Fish intestinal bacteria such as Aeromonas spp. and Vibrio spp. producing anti-viral substances were isolated from intestinal contents of masu salmon (Oncorhynchus masou), Japanese flounder (Paralichthys olivaceus) and barfin flounder (Verasper moseri). These Aeromonas strains produced anti-infectious hematopoietic necrosis virus (IHNV) substances and Vibrio strains showed anti-IHNV, Oncorhynchus masou virus (OMV) and barfin flounder nervous necrosis virus (BF-NNV) activities. When Aeromonas spp. strains M-26 and M-38 were mixed with food pellets and fed to rainbow trout (O. mykiss) and masu salmon, both bacteria became dominant in the intestinal microflora and anti-IHNV activity was observed in homogenates of intestinal contents. These rainbow trout and masu salmon fed the Aeromonas spp. showed more resistance to the artificial IHNV challenge test. Barfin flounder fed Vibrio sp. strain 2IF6a with Altemia salina showed the anti-OMV and BF-NNV activities in the intestinal contents. Larvae fed the Vibrio sp. showed a higher survival rate than the fish cultured using the virus free sea water.
1 0 0 0 特発性血小板減少性紫斑病(ITP),血友病の出血
- 著者
- 倉田 義之 髙松 純樹
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- medicina (ISSN:00257699)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.5, pp.874-877, 2003-05-10
ポイント ・特発性血小板減少性紫斑病(ITP)と血友病で,止血対応は全く異なる. ・ITPの出血で出血斑が散在する程度では,治療を開始しない.鼻出血や口腔内血腫など粘膜出血出現時には,治療を開始する. ・止血は局所の圧迫が基本.下血など重篤な出血時には,血小板輸血,ガンマグロブリン大量療法も必要. ・血友病での出血時は,欠乏している因子の補充が原則.出血の部位により必要血中レベルは異なる. ・凝固因子に対する抗体が生じているインヒビター症例は,速やかに血友病専門医への紹介が必要.
- 著者
- 井上 武史 中倉 智徳 苅谷 千尋 高村 学人
- 出版者
- 立命館大学政策科学会
- 雑誌
- 政策科学 = 政策科学 (ISSN:09194851)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.2, pp.137-153, 2008-02
- 著者
- 齋木 喜美子
- 出版者
- 日本教育方法学会
- 雑誌
- 教育方法学研究 (ISSN:03859746)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.1-8, 1999
This study is described on children's cultural activities in Yaeyama in the recent times, mainly on the practice of Takuji Iwasaki. In 1897 Takuji Iwasaki was assigned to Ishigakijima as the head of the local meteorological observatory from the Central Meteorological Observatory. Since then, for 40 years, he made efforts to preserve the local nature and folklore, and develop the local education, in addition to the weather observation and he left great achievements. Especially, he was quick to find children's talents. He made efforts to make opportunities to report children's cultures and made efforts to bring up talented persons of the next generation. In this study I mention an aspect of a history of local educational practice in Japan in the recent times by making his practice and their significance clear.
- 著者
- Keiji Nagata Yuyu Ishimoto Shinichi Nakao Shoko Fujiwara Toshiko Matsuoka Tomoko Kitagawa Masafumi Nakagawa Masakazu Minetama Mamoru Kawakami
- 出版者
- The Japanese Society for Spine Surgery and Related Research
- 雑誌
- Spine Surgery and Related Research (ISSN:2432261X)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.3, pp.177-185, 2018-07-25 (Released:2018-07-27)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 5
Introduction: The aims of the present study were 1) to examine the association between neck and shoulder pain (NSP) and lifestyle in the general population and 2) to examine if sagittal spino-pelvic malalignment is more prevalent in NSP.Methods: A total of 107 volunteers (mean age, 64.5 years) were recruited in this study from listings of resident registrations in Kihoku region, Wakayama, Japan. Feeling pain or stiffness in the neck or shoulders was defined as an NSP. The items studied were: 1) the existence or lack of NSP and their severity (using VAS scale), 2) Short Form-36 (SF-36), 3) Self-Rating Questionnaire for Depression (SRQ-D), 4) Pain Catastrophizing Scale (PCS), 5) a detailed history consisting of 5 domains as being relevant to the psychosocial situation of patients with chronic pain, 6) A VAS of pain and numbness to the arm, and from thoracic region to legs. The radiographic parameters evaluated were also measured. Participants with a VAS score of 40 mm or higher and less were divided into 2 groups. Association of SF-36, SRQ-D, and PCS with NSP were assessed using multiple regression analysis.Results: In terms of QoL, psychological assessment and a detailed history, bodily pain in SF-36, SRQ-D, and family stress were significantly associated with NSP. A VAS of pain and numbness to the arm, and from thoracic region to legs, was significantly associated with NSP. There were no statistical correlations between the VAS and radiographic parameters of the cervical spine. Among the whole spine sagittal measurements, multiple logistic regression analysis showed that sacral slope (SS) and sagittal vertical axis (SVA) were significantly associated with NSP.Conclusion: In this study, we showed the factors associated with NSP. Large SS and reduced SVA were significantly associated with NSP, while cervical spine measurements were not.
1 0 0 0 OA エイベックスレイブ94における高精細度三次元画像による同時体感
- 著者
- 服部 裕之 秋山 広和 片柳 幸夫 山内 英夫 藤川 勝則 大場 省介 前澤 健司 渡部 敏明 寺内 裕史 須田 純郎
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- テレビジョン学会技術報告 (ISSN:03864227)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.11, pp.21-25, 1995-02-17 (Released:2017-10-13)
We would like to report the event "AVEX RAVE 94" which took place on August 1994 at Tokyo Dome. This program was recorded using four channel surround sound and three dimension high definitional video system was sent via satellite to Osaka. Our intention was for the audience to experience the exciting virtual reality effect.
1 0 0 0 鹿児島大学農学部演習林報告
- 著者
- 鹿児島大学農学部附属演習林 [編]
- 出版者
- 鹿児島大学農学部演習林
- 巻号頁・発行日
- 1968
1 0 0 0 OA 大江宏設計 神武天皇聖蹟顕彰碑の設計過程
- 著者
- 石井 翔大
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.747, pp.949-955, 2018 (Released:2018-05-30)
- 参考文献数
- 5
This study aims to elucidate Hiroshi Ohe's activities in the Ministry of Education and to consider the architectural view of Ohe before the world war II. Hiroshi Ohe (1913-1989) worked as a technician at the Ministry of Education from 1938 to the beginning of 1941 and was involved in the construction of the Jinmu Emperor's honoring monument and the National History Museum. This study collected and analyzed primary materials such as sketches, drawings, and documents created by Ohe during the Ministry of Education's Technical Time, which have been stored in the Ohe Architecture Atelier (formerly Ohe Hiroshi Architects). The design process of Jinmu Emperor's honoring monument from the first stage to the fourth stage can be considered a process of a gradual reduction in the conceptions of Ohe. It is assumed that the theme of Ohe's sketches in the first stage was to superpose the space containing the monument by creating a plan and sequence in order to gradually join the area on the outside to that on the inside. Therefore, it can be pointed out that Ohe's intention in the later years, which emphasizes the psychological changes in people who experience building, has already been taken into account in the design of the monument. In the later years, Ohe developed criticism against modernist architecture, advocating the principle of “interminglement and coexistence” and arguing about the importance of roofing and decoration. It is assumed that the sketch of Fig. 11 contains the themes of roofing and decoration, deviating from simplicity that is one of the features of modernism architecture. Therefore, this sketch is considered an important material foretelling the construction of Ohe during the later years.