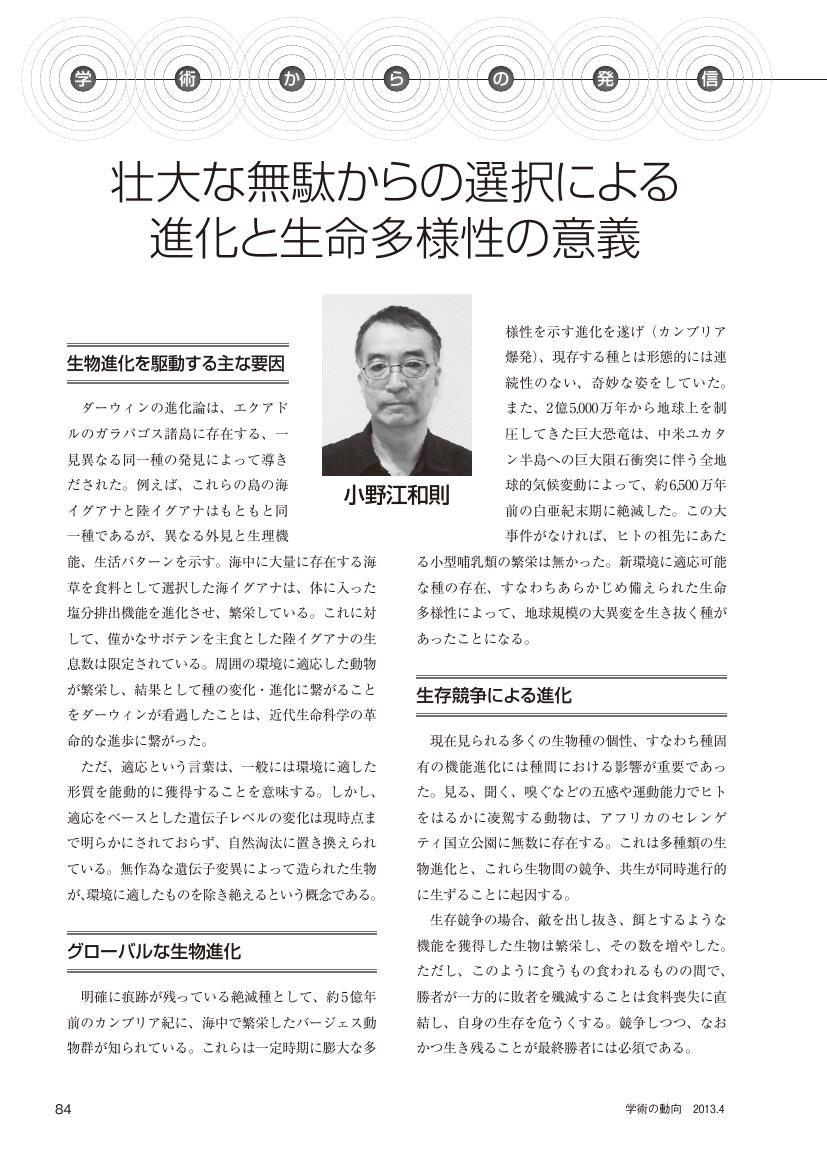- 著者
- 大平 充宣 田畑 泉
- 出版者
- Japan Society of Physiological Anthropology
- 雑誌
- The Annals of physiological anthropology (ISSN:02878429)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.3, pp.319-323, 1992-05-01 (Released:2008-02-08)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 3 4
Blood lactate level begins to increase at a certain work load or oxygen consumption which is called as anaerobic threshold (AT). However, numerous studies showed that anaerobic glycolysis is not the cause of the enhanced accumulation of blood lactate during exercise. Increased lactate production is seen even in fully aerobic muscles. Some studies suggest that elevation of lactate is due to a temporary imbalance between the rates of pyruvate formation by aerobic glycolysis and pyruvate utilization in the Krebs cycle. These results clearly suggest
1 0 0 0 OA 対人援助職者に対する認知療法によるストレスマネジメントプログラムの効果
- 著者
- 竹田 伸也 太田 真貴 松尾 理沙 大塚 美菜子
- 出版者
- 公益財団法人 パブリックヘルスリサーチセンター
- 雑誌
- ストレス科学研究 (ISSN:13419986)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, pp.44-51, 2015 (Released:2016-01-15)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 1
The present study investigated the effects of a stress management program by the cognitive therapy for human service provider. The program consisted of the lecture and exercise which divided the cognitive therapy into six steps, and was carried out for 3 hours. After the program, statistically significant differences were found between pre and post program on the scores of STAI-S score, “understanding of the cognitive model” score, “self-efficacy in the awareness of their own feelings” score, “self-efficacy in the awareness of their negative thought ” score, “self-efficacy of looking back upon a thought, when it falls into an unpleasant feeling” score, and “self-efficacy over creation of positive thought” score. These suggest that this program improved stress responses, and human service provider might perform the cognitive therapy by themselves.
1 0 0 0 OA 日本語ノ構音ニ關スル考察
- 著者
- 懸田 克躬
- 出版者
- 口腔病学会
- 雑誌
- 口腔病學會雜誌 (ISSN:03009149)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.2, pp.136-145, 1937 (Released:2010-12-08)
- 参考文献数
- 16
著者ハ, 口蓋圖Palatogrammト舌圖Linguagrammトヲ取ツテ, 日本語音ノ構音機構ヲ檢シテ, 次ノ諸點ニ就テ多少從來ノ諸家ト異ナル所見ヲ得, 其成績ニ基イテ二三ノ考察ヲ加ヘタ。(1) 二重母音的ニ發セラレル「イ」ハiトeトノ中間ニハアルガiニ近イ。(2) 「ヤ」「ヨ」頭音 (半母音) ノ構音デハ, 舌ノ位置ハ「イ」デナクテ「エ」デアルト云ハレテ居ルガ, 著者ニ於テハ多クノ場合矢張「イ」ニ近イ。(3) 「サ」行音「シ」ハ∫iデハナク, ソノ子音ノ構音ハsトcトノ中間ニアツテ, 寧ロ後者ニ近イ。(4) 「カ」行子音ノ構音部位ハ「キ」「ケ」「ク」「カ」「コ」ノ順ニ後退スル。(5) 「ラ」行音中, 「ロ」音デハ口蓋ト舌トノ間ニ細イ間隙ヲ殘ストイフコト (Edwards) ハ通例ニハ妥當シナイ。「ラ」行音ハ少クトモ語頭ニ於テハ, 皆一種ノ破音デアル。
- 著者
- 窪寺 俊之
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.5, pp.353-363, 2010-05-01 (Released:2017-08-01)
- 参考文献数
- 4
人間は,「我と汝」「我と我」「我と神的存在」との関係の中で生きている.「いのち」が危機に直面すると「我と我」「我と神的存在」の関係が顕著に意識される.その関係性をよりいっそう意識化し,活性化して患者の「いのち」の土台,意味,希望を見出す援助がスピリチュアルケアである.「我と我」「我と神的存在」の関係を重視する視点は,患者の存在,現状,将来をより全体的視点から見直すことを促す.その結果,見失った自己の生きる意味,目的,希望の気づきにつながる.そこに自己回復という「癒し」がある.医療者には,患者の言葉,態度の中にスピリチュアルな側面を見て取る感性と解釈法が求められる.
1 0 0 0 IR 文学史から文学場へ : 室生犀星と日本近代詩(1)
- 著者
- 上田 和弘
- 出版者
- 岡山大学グローバル・パートナーズ, 岡山大学教育開発センター, 岡山大学言語教育センター, 岡山大学キャリア開発センター
- 雑誌
- 大学教育研究紀要 = Bulletin of higher education, Okayama University (ISSN:18815952)
- 巻号頁・発行日
- no.10, pp.15-34, 2014-12
ある時代のある特定の時期に書かれ発表されたさまざまな文学テクストをながめたばあい、ときにジャンルさえ越えて、そこに流行語のようにいくつかのある特徴的な語や表現が時を同じくして出現してくることがある。それはもちろん作家(詩人)から作家(詩人)へのなんらかの影響関係がそこにあったからだとまずは考えられよう。しかしこれは必ずしもたんに一方から他方への単方向的な影響というのではなく、作家(詩人)たちのあいだで、いくつかの条件があわさって、ほとんど同時発生的にある共通ないし類似の語や表現が生まれたり用いられたりすることもあったのではないか、また、あくまで個々の作品から遡及的にしか見いだされぬとしても、そうした共通ないし類似の語や表現を生みだすことを可能にした、ある時代のある特定の時期に成立していたと想定される表現可能態の言語空間がそこに潜在していたのではないか――本稿は、その空間をピエール・ブルデューの用語を借りて「文学場」の名で呼んで、20 世紀初頭における日本の近代詩と19 世紀中葉におけるフランスの近代詩をそうした「文学場」という観点からとらえなおす試みである。
1 0 0 0 OA 順向, 逆向, および同時マスキング条件における聴覚マスキング・パターン
- 著者
- 宮崎 謙一 佐々木 隆之
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.2, pp.106-112, 1981-07-20 (Released:2010-07-16)
- 参考文献数
- 36
- 被引用文献数
- 1 1
To investigate the temporal course of the frequency characteristics of the response elicited in the auditory system, pure-tone masking patterns were obtained at several time positions relative to the onset or the offset of the masker. The simultaneous masking patterns obtained suggest that the shape of the response distribution remained almost unchanged during the masker, although they are less informative compared to the other conditions because of interaction effects between the masker and the probe. The forward masking data illustrate the decay course of the distribution and are believed to give more reliable informations as to the frequency selectivity of the auditory system. The backward masking data, however, fail to give any tenable suggestions. The phenomenon of the shift in the maximum-masking-frequency was observed in all conditions and its underlying mechanisms were discussed.
1 0 0 0 OA 在宅要介護老人の介護者のストレス
- 著者
- 松岡 英子
- 出版者
- 日本家族社会学会
- 雑誌
- 家族社会学研究 (ISSN:0916328X)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.5, pp.101-112,142, 1993-07-25 (Released:2010-02-04)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 8 2
This paper discusses and estimates the various factors on stress which have been used with family caregivers for the impaired elderly, and explores the factors influencing the stress of family caregivers, using the conceptual components of stress : “Stressor”, “Perception of caregivers”, “Resources” and “Stress response”. The sample consists of 873 family caregivers for the impaired elderly living in Nagano prefecture, of which 712 (81.6%) were valid responses. A questionnaire was developed to investigate present stress symptoms of the caregivers. Principal component analysis, Cronbach's alpha, Multivariate analysis of variance and Multivariate analysis of convariance are used to look at the relationships between factors on the stress of caregivers. The findings show that, the conceptional components, “Stress response” is related to the other components “Stressor”, “Perception of caregivers” and “Resources”. As for “ Stress response”, there were nine significant factors influencing the stress level of family caregivers. They are the elderly person's mental status, the quality of service, traditional caregiving ideology, the caregiver's health, the caregiver's job status, the emotional attachments in family relations, the emotional support from relatives, the emotional support from friends and neighbors, and instrumental support in the case of emergency from relatives.
- 著者
- 大高 恵莉 大高 洋平 森田 光生 横山 明正 近藤 隆春 里宇 明元
- 出版者
- 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会
- 雑誌
- The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine (ISSN:18813526)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.10, pp.673-681, 2014 (Released:2014-11-12)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 2 8
目的:動的バランス機能の評価法であるMini-Balance Evaluation Systems Test(Mini-BESTest)の日本語版を作成し,その妥当性を検証した.方法:Guilleminらのガイドラインに準じ日本語版Mini-BESTestを作成した.バランス障害群20 名(平均年齢65.4±18.7 歳)及び健常群7 名(平均年齢69±5.9 歳)に日本語版Mini-BESTest,Berg Balance Scale(BBS),国際版転倒関連自己効力感尺度(FES-I),Activities-specific Balance Confidence Scale(ABC Scale)を実施し,Spearmanの順位相関係数を求めた.結果:日本語版Mini-BESTestの平均施行時間は20.0 分で,BBS(r=0.82,p<0.01),FES-I(r=-0.72,p<0.01),ABC Scale(r=0.80,p<0.01)と有意な相関を認めた.分布の非対称性を示す指標である歪度(skewness)はそれぞれBBS -1.3,日本語版Mini-BESTest -0.47であった.結論:日本語版Mini-BESTestは既存のバランス評価法との併存的妥当性を示し,かつBBSのような天井効果を認めない点で優れていると考えられた.
1 0 0 0 戊辰戦争研究の成果と課題 (特集・幕末維新軍事史)
- 著者
- 亀掛川 博正
- 出版者
- 錦正社
- 雑誌
- 軍事史学 (ISSN:03868877)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1, pp.38-57, 1996-06
1 0 0 0 OA 壮大な無駄からの選択による進化と生命多様性の意義
- 著者
- 小野江 和則
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.4, pp.4_84-4_87, 2013-04-01 (Released:2013-08-02)
1 0 0 0 OA 医療研究開発における知的財産と産学官連携
- 著者
- 内海 潤 神谷 直慈
- 出版者
- 日本小児血液・がん学会
- 雑誌
- 日本小児血液・がん学会雑誌 (ISSN:2187011X)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.3, pp.254-260, 2018 (Released:2018-10-27)
- 参考文献数
- 11
我が国では現在,「産」(企業)と「学」(アカデミア)が連携して国産の医薬品や医療機器の研究開発を進める活動が,かつてないほどに盛んになってきている.「官」(国)がファンディングし,産学官連携という形になることも多い.医療製品が実用化される際に必須の2つの行政的な手続きがある.それは薬事承認の取得と知的財産権の確保である.すなわち,医療製品を製造販売しようとする者は,製品を知的財産権(主に特許権)で競合他者から守り,国の薬事審査の承認を得て,事業化ができるのである.医薬品や医療機器などの医療製品は,製造販売を行うのは企業で,ユーザーは医療従事者と患者であるが,その研究開発・性能験評価の過程からアカデミア及び医療機関の関与が必須である.それゆえ,円滑な研究開発を進めるうえでは,医療製品の研究開発に係る産学関係者が,知的財産に係る仕組みと特徴を知ることが極めて重要である.ただし,医薬品と医療機器では,特許の価値と取扱いも異なっており,留意が必要である.本稿では,医薬品と医療機器の研究開発における産学連携の意義と仕組みと知的財産の係わりについてまとめた.さらに,従来は産学連携の取組みが少なかった小児科領域における国の施策についても言及した.
1 0 0 0 OA 新任教員,講義の荒海にこぎ出す(はじめての講義)
- 著者
- 畠山 温
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 大学の物理教育 (ISSN:1340993X)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.3, pp.149-152, 2011-11-15 (Released:2018-12-27)
- 参考文献数
- 4
1 0 0 0 OA ある小学校におけるA(H1N1)pdm09パンデミックインフルエンザの感染伝播動態の解析
- 著者
- 清水 宣明 片岡 えりか 西村 秀一 脇坂 浩
- 出版者
- 一般社団法人 日本環境感染学会
- 雑誌
- 日本環境感染学会誌 (ISSN:1882532X)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.2, pp.96-104, 2012 (Released:2012-06-05)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 2 1
インフルエンザの流行では,曝露歴が少なく活動性が高い児童が密集して長時間生活する小学校が感染の増幅器となることが懸念され,そこでの対策は地域の感染制御において重要な位置を占める.しかし,その流行の仕組みについての知見は少ない.本研究では,三重県多気郡明和町立下御糸小学校(全校児童163名)における2009年10月から2010年1月までのA(H1N1)pdm09パンデミックインフルエンザの発症状況を解析した.流行期間は79日間で罹患率は49.1%,1日あたりの平均発症は1.01人であった.児童発症日数は43.0%で,そのうち3人以下と比較的少人数の発症日が80.0%を占めた.5人以上と比較的多くの発症があった日は13.3%に過ぎなかった.発症認識の24時間前から他への感染可能なウイルス量が排出されたと仮定して,潜伏期間と発症日時から児童間の感染可能性の連鎖を推定した.発症児童の感染源は,学級内が50.0~66.7%,学級外(家庭を含む)が33.4~50.0%程度であった.下御糸小学校での流行は,急激で連続的な拡大ではなく,児童が学級外で感染して学級内で数人に感染させることもあるが,その感染可能性の連鎖はすぐに切れるということの繰り返しによって徐々に進行し,その途中で,集団感染の可能性のある同時多発発症が数回起こった可能性が示唆された.
1 0 0 0 OA 全部分グラフ指示子に基づく決定木の勾配ブースティング
- 著者
- 横山 侑政 瀧川 一学
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第31回全国大会(2017)
- 巻号頁・発行日
- pp.1K13, 2017 (Released:2018-07-30)
グラフ分類問題において、従来研究では部分グラフ指示子の線形モデルで表現可能な仮説クラスの学習に制限されていた。そこで、本研究では非線形モデルである決定木を弱学習器に用いた勾配ブースティングを提案する。本手法では、決定木の学習は全部分グラフ指示子に基づいて行う。いくつかのベンチマークデータセットに対して実験を行うことで、その性能を評価する。
1 0 0 0 OA <講演>犠牲の論理とキリスト教への問い
- 著者
- 高橋 哲哉 Tetsuya Takahashi
- 雑誌
- 神学研究 (ISSN:05598478)
- 巻号頁・発行日
- no.63, pp.1-14, 2016-03-20
- 著者
- 中道 憲明 松村 昇 塩野 将平 丹治 敦 戸山 芳昭 池上 博泰
- 出版者
- 日本肩関節学会
- 雑誌
- 肩関節 (ISSN:09104461)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.3, pp.477-480, 2007
There are numerous reports of success with an open Bankart repair, using low recurrence of dislocation. Few studies indicate that subscapularis (SSC) tenotomy may result in postoperative SSC insufficiency. The purpose of this research was to measure the subscapularis muscle strength, muscle area and signal intensity by magnetic resonance imaging after the open Bankart procedure.<BR>A total of 22 patients were observed prospectively for a mean of 33 months (range 17-51 months). There were 11men and 1woman. The mean patient age at the surgery was 22.8 years old (range, 18-36 years old). All patients were right-handed. 8 patients had injured their shoulder of their dominant extremity. Internal rotation (IR) at 45 degrees abduction was at 60 degrees per second. The peak torques of both extremities was measured at the day before the operation, 6 months and 12 months after the operation. We calculated the ratio of the affected side to the unaffected side. The peak torques of ER and IR of the pre-operation were 13.5% and 18.5% respectively lower than those of the unaffected side. The peak torques of ER and IR that were measured at 6 months after the operation were 27.6% and 21.1% respectively lower than those of the unaffected side. The peak torques of ER and IR that were measured at 12 months after the operation were 18.4% and 0.2% respectively lower than those of the unaffected side. The area at 12 months after surgery was not significantly different from the preoperative area. However, the signal intensity at 12 months after surgery was significantly higher than that in the preoperative signal intensity. An open Bankart procedure using an L-shaped tenotomy approach did not decrease SSC muscle strength and volume. This procedure approach may lead to the deterioration of the subscapularis muscle.
1 0 0 0 自己決定権と内発的義務--<生命圏の政治学>の手前で
- 著者
- 川本 隆史
- 出版者
- 岩波書店
- 雑誌
- 思想 (ISSN:03862755)
- 巻号頁・発行日
- no.908, pp.15-33, 2000-02
1 0 0 0 OA サーバサイドWebアプリケーションによる静的および動的コンパイル言語の性能比較
- 著者
- 上田 陽平 小原 盛幹
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌プログラミング(PRO) (ISSN:18827802)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.17, 2020-01-29
Webアプリケーション開発においては,動的コンパイル言語やスクリプト言語が実装言語として選択されることが多い.これは,静的コンパイル言語に比べてデプロイに必要な時間が短く,新しい機能やバグ修正を迅速にリリースでき,開発生産性の向上に寄与するためと考えられる.しかし,近年のコンテナ技術や継続的インテグレーション・継続的デリバリーの普及により,静的コンパイル言語を用いたWebアプリケーションの開発においても動的コンパイル言語やスクリプト言語と遜色ない生産性を実現する環境が整いつつある.本発表では,静的コンパイル言語のGoと動的コンパイル言語のJavaおよびJavaScriptで実装されたWebアプリケーションの性能評価結果を報告する.WebアプリケーションであるAcme Airベンチマークの各言語での実装を使用して性能評価を行い,Goによる実装はJavaScriptに対して約1.6倍,Javaに対して約1.8倍のスループットを達成することを確認した.性能プロファイルの分析によると,GoのWebフレームワークはJavaのWebフレームワークに比べてREST型Webリクエストの処理に必要なコードフットプリントが少なく,また,動的型付けのJavaScriptと比較して静的型付けのGoはランタイム検査のオーバヘッドが少ないことが判明した.GoはJavaおよびJavaScriptに対して優位な性能を示しており,Webアプリケーションにおいても静的コンパイル言語の普及が期待される.