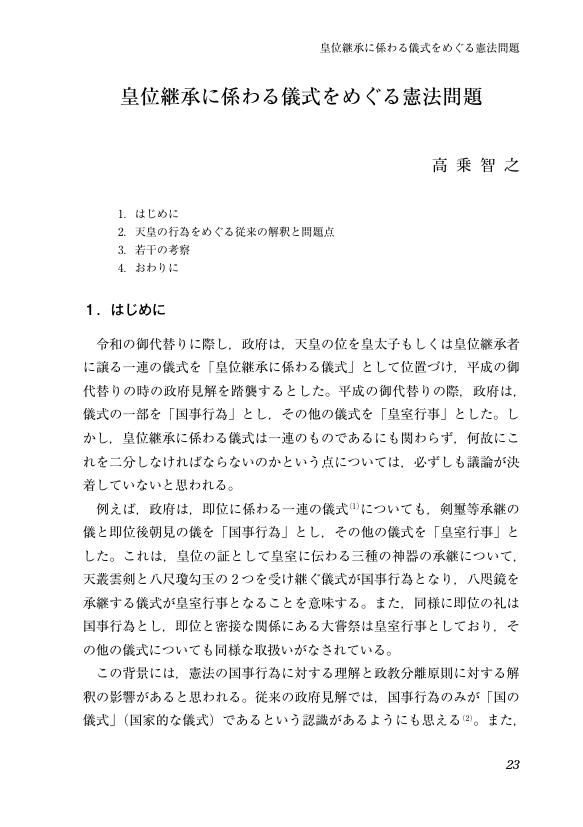6 0 0 0 OA 皇位継承に係わる儀式をめぐる憲法問題
- 著者
- 高乗 智之
- 出版者
- 憲法学会
- 雑誌
- 憲法研究 (ISSN:03891089)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, pp.23, 2020 (Released:2020-11-05)
6 0 0 0 IR 「日本語教師は食べていけない」言説 : 『月刊日本語』の分析から
- 著者
- 丸山 敬介
- 出版者
- 京都
- 雑誌
- 同志社女子大学大学院文学研究科紀要 = Papers in Language, Literature, and Culture of the Graduate School of Doshisha Women's College of Liberal Arts (ISSN:18849296)
- 巻号頁・発行日
- no.16, pp.1-38, 2016-03
『月刊日本語』(アルク)全291冊を分析し、「日本語教師は食べていけない」言説の起こりと定着との関係を明らかにした。 創刊直後の88~89年、日本語学校の待遇が悪くてもそれは一部の悪質な学校の問題であって、それよりも日本語教師にはどのような資質が求められるかといった課題に興味・関心が行っていた。ところが、91年から92年にかけて待遇問題が多くの学校・教師に共通して見られる傾向として取り上げるようになり、それによって読者たちは「食べていけない」言説を形作ることになった。 90年代後半には、入学する者が激減する日本語学校氷河期が訪れ、それに伴って待遇の悪さを当然のこととする記事をたびたび掲載するようになった。「食べていけない」が活字として登場することもあり、言説はより強固になった。一方、このころからボランティア関係の特集・連載を数多く載せるようになり、読者には職業としない日本語を教える活動が強く印象付けられた。 00に入ってしばらくすると、「食べていけない」という表現が誌上から消えた。さらに10年に近くなるにしたがって、日本語を学びたい者が多様化し、教師不足をいく度か報じた。しかし、だからといって教師の待遇が目立って好転したわけではなく、不満を訴える教師は依然として多数を占めていた。そう考えると、言説はなくなったのではなく、むしろ広く浸透し一つの前提として読者には受け止められていたと考えられる。
6 0 0 0 OA 留保なきノイズ主義 : ヴィヴェンザのインダストリアル・ノイズ
- 著者
- 根本 裕道 ネモト ヒロミチ Hiromichi Nemoto
- 雑誌
- 立教映像身体学研究 = Rikkyo review of new humanities
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.5-27, 2015
- 著者
- 川西 諭 田村 輝之
- 出版者
- 行動経済学会
- 雑誌
- 行動経済学 (ISSN:21853568)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.87-104, 2019-04-16 (Released:2019-04-15)
- 参考文献数
- 51
本稿では,グリット(Grit)とマインドセット(Mindset)という2つの心理学概念に関する研究を紹介し,労働生産性向上をめぐる議論への含意,および行動経済学研究への応用の可能性について議論する.グリットとは,長期的な目標達成に向かって「やり抜く力」であり,本稿で紹介するマインドセット研究は「固定思考」と「成長思考」という2つの対極をなす思考を問題とする.既存のグリット研究とマインドセット研究はいずれも私たちの能力のうち,努力によって後天的に獲得される資質が常識的に考えられているよりも重要であること,そして資質の獲得が私たちの心理や思考によって強く影響を受けることを指摘している.これらの研究に照らすと,労働生産性を低水準にしている原因として,人々の考え方が,先天的資質を重視する固定思考に偏ってしまっている認知バイアスが浮かび上がる.
6 0 0 0 OA 三重県桑名市にみるプレイス・ブランディングの展開
- 著者
- 伊藤 孝紀
- 出版者
- 一般社団法人 日本デザイン学会
- 雑誌
- デザイン学研究特集号 (ISSN:09196803)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.2, pp.74-77, 2020-11-30 (Released:2021-04-16)
6 0 0 0 OA サーボ計算機と小形精密歯車
- 著者
- 中田 孝
- 出版者
- 公益社団法人 精密工学会
- 雑誌
- 精密機械 (ISSN:03743543)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.336, pp.1-11, 1963-01-05 (Released:2009-06-30)
- 参考文献数
- 10
6 0 0 0 OA 江戸幕府の政務処理と幕藩関係 家斉期の行列道具を素材として
- 著者
- 山本 英貴
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.126, no.6, pp.62-84, 2017 (Released:2018-10-20)
小稿は、奥右筆文書に収録される諸大名より幕府に提出された行列道具の所持願、その願い出を認めるかどうかを記した幕府役人の評議書などを総合的に分析し、江戸幕府の政務処理の流れを復元したものであり、家斉期の幕府と藩(大名家)との関係について、次の点を明らかにすることができた。 まず、行列道具の所持願の処理過程について、大名が月番老中に提出した所持願は、月番より大目付・目付に渡され、それは両名より、願い出を認めるか否かを記した評議書とともに、月番へ返上された。行列道具の所持は、大名の家格に関わる問題であり、願い出の採否については、月番と他の老中とが大目付・目付の評議書を参考に、合議により決めていた。その際、老中が採否にあたって重視したのが、願い出を認めると他の大名に支障が出るか、という点であった。この基準があればこそ、幕府は大名に行列道具を持たせることを、その家格と序列を操作するための手段として活用できたのである。 次に、家斉期の幕政については従来、将軍家斉の子女と縁組した大名は官位が上昇したりする不公平なもの、として理解されてきた。小稿においても、家斉の息女と縁組した会津松平・鍋島の両家が、以前に断られた所持願を、新規に先例を提示することなく認められていた点を確認した。その一方で、家斉の子女と縁組していない藤堂家も、前述の基準により、新規に先例を提示することなく、これまで断られていた所持願を認められた、という事実を明らかにした。 以上により、小稿では、家斉期に行列道具の所持願が多く認められた背景として、①家斉の子女と縁組した大名に道具の所持が認められ、それ以外の大名も幕府に所持願を出したこと、②老中を始め幕府の諸役人に、他の大名との兼ね合いから所持願を認めようとの考えがあったこと、の二点を明らかにしたのである。
- 著者
- 谷川 彩月
- 出版者
- 環境社会学会
- 雑誌
- 環境社会学研究 (ISSN:24340618)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, pp.114-129, 2017-12-20 (Released:2020-11-17)
- 参考文献数
- 19
本稿の目的は,長期的な里地里山保全に向け,農地全体での資材投入量を削減する手法のひとつとして慣行農家による減農薬栽培の導入プロセスに着目し,彼らがどのようにして減農薬栽培へ取り組むに至ったのかを明らかにすることである。持続可能性に関わる問題では,長期的・累積的な行為の集積結果として問題が発生しうるため,長期的に里地里山を保全していくには,農地全体で投入資材を削減していくことが必要である。そのため,現状で圧倒的多数をしめる慣行農家に投入資材の削減を促すようなしかけが必要となってくる。本稿では,変革志向性が弱い農家を取り込んで減農薬栽培が普及している宮城県登米市を事例として,それを成立させたしくみと農家による取り組みへの意味づけを明らかにした。くわえて,減農薬栽培の学習プロセスによって,当該地域では慣行農法や転作作物を含めた田畑全体での減農薬化が進んでいること,多くの農家の参加を許容できる環境保全米のあり方が,多様な動機の集積による「結果としての環境保全」と呼べる状況を作り出していることを確認した。明確なイシュー志向を持たない層の行動変容を促すには,行動変容を促すような技術・思想あるいは施策と,彼らの生活世界との接合点を見いだすことが重要であるということが明らかとなった。
- 著者
- 佐藤 佑太郎 松田 涼 石川 直人 山田 尚幸 松田 直樹
- 出版者
- 一般社団法人日本理学療法学会連合
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- pp.12370, (Released:2023-07-21)
- 参考文献数
- 25
【目的】橋出血による感覚機能と注意機能に低下を認めた1症例に対し,注意の内的焦点化(Internal focus of attention:以下,IFA)と外的焦点化(External focus of attention:以下,EFA)に着目した理学療法の有効性を確認することとした。【症例紹介】橋出血により重度の感覚機能と注意機能低下を認めた1例とした。回復期入棟時(30病日)~84病日までは臥位での右下肢筋出力向上トレーニング,EFAによる教示を意識した立位荷重練習,歩行練習を主体に実施した。84~124病日では,IFAによる教示を意識したバランス練習や課題特異的な動作練習を主体に実施した。感覚・注意機能,バランス・歩行機能は改善し,屋外歩行自立を獲得し自宅退院となった。【結論】感覚・注意機能低下を認める症例に対しては,介入初期はEFAによる教示を中心に行い,注意・感覚機能の改善に伴いIFAによる教示を用いた介入の実施が有効である可能性が示された。
6 0 0 0 OA 出店者の動向と経験からみた「行田はちまんマルシェ」の意義
- 著者
- 佐藤 寛輝 張 思遠 本多 一貴 佐藤 颯哉 吉田 国光
- 出版者
- 東北地理学会
- 雑誌
- 季刊地理学 (ISSN:09167889)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.1, pp.3-15, 2023 (Released:2023-04-21)
- 参考文献数
- 31
本稿は,埼玉県行田市で毎週日曜日に開催されている「行田はちまんマルシェ」を事例にマルシェという空間の利用が,出店者の経済活動や日常生活にいかなる役割を果たしているのかを明らかにした。マルシェへ農作物や飲食物,工芸品などを出品する出店者が,各人の生産活動もしくは日常生活のなかで,マルシェでの直売という行為をどのように位置づけながら利用し,出店者にとっていかなる経験を生み出しているのかを分析した。そして,マルシェという空間の利用を通じて得られた経験,もしくはマルシェでの直売活動によって他所で得られた経験が生産者の経済活動や日常生活にいかなる役割を果たすのかを考察した。その結果,マルシェ自体は出店者にとって経済的機能を期待する空間とはなっていなかったが,出店者の出店を通じて様々なスケールで得た経験が常設店舗や他所の出店先での経済活動には直接的,間接的にポジティブに作用していた。この作用は経済規模として小さいものの,出店者のマルシェでの活動を媒介して中心市街地を超えた行田市という広い範囲に及んでいた。マルシェは開催を主導した自治体からみると商品を販売するイベントであった。他方,マルシェという空間を主に利用する出店者にとっては市場的価値を期待するものではなく,出店者のマルシェで得た経験は出店者が行田市各所で経済活動を展開させる際にポジティブに作用するものであった。