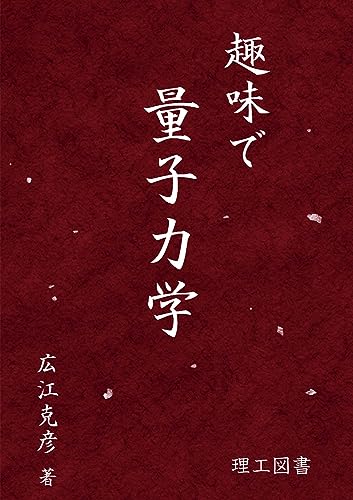6 0 0 0 OA 脳卒中片麻痺患者における装具療法の進め方—セパレートカフ式長下肢装具の活用—
- 著者
- 増田 知子
- 出版者
- 日本義肢装具学会
- 雑誌
- 日本義肢装具学会誌 (ISSN:09104720)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.1, pp.22-27, 2013-01-01 (Released:2014-04-15)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 6
脳卒中片麻痺患者に対し,長下肢装具を使用して運動療法を行う目的と実際の進め方,神経機構を基にした歩行トレーニングの考え方について述べた.歩行能力の向上に従い,長下肢装具から短下肢装具へのカットダウンが検討される.変化が大きく明確な基準が存在しないこの過程を円滑に進めるためには,より細かく段階を刻み,双方向への変更が可能な「セパレートカフ式長下肢装具」の活用が有効であり,使用例を交えて紹介した.セラピストは,治療戦略において装具を効果的に使用できるよう,装具自体に施す工夫に加え,その使い方に関しても,探究し習熟する必要がある.
6 0 0 0 OA 硝酸塩/亜硝酸塩の不足は代謝症候群,血管不全,心臓突然死を引き起こす
- 著者
- 喜名 美香 坂梨 まゆ子 新崎 章 筒井 正人
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.151, no.4, pp.148-154, 2018 (Released:2018-04-07)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 3 4
一酸化窒素(NO)はL-arginineからNO合成酵素(NOSs)を介して産生されが,最近,その代謝産物である亜硝酸塩(NO2-)および硝酸塩(NO3-)からNOが産生される経路が発見された.レタスやホウレン草などの緑葉野菜には硝酸塩が多く含有されている.しかし,硝酸塩/亜硝酸塩(NOx)の不足が病気を引き起こすか否かは知られていない.本研究では,『食事性NOxの不足は代謝症候群を引き起こす』という仮説をマウスにおいて検証した.私達は過去に,NOSs完全欠損マウスの血漿NOxレベルは野生型マウスに比して10%以下に著明に低下していることを報告した.この結果から,生体のNO産生は主として内在するNOSsによって調節されていること,外因性NO産生系の寄与は小さいことが示唆されたが,低NOx食を野生型マウスに長期投与すると意外なことに血漿NOxレベルは通常食に比して30%以下に著明に低下した.この機序を検討したところ,低NOx食負荷マウスでは内臓脂肪組織のeNOS発現レベルが有意に低下していた.重要なことに,低NOx食の3ヵ月投与は,内臓脂肪蓄積,高脂血症,耐糖能異常を引き起こし,低NOx食の18ヵ月投与は,体重増加,高血圧,インスリン抵抗性,内皮機能不全を招き,低NOx食の22ヵ月投与は,急性心筋梗塞死を含む有意な心血管死を誘発した.低NOx食負荷マウスでは内臓脂肪組織におけるPPARγ,AMPK,adiponectinレベルの低下および腸内細菌叢の異常が認められた.以上,本研究では,食事性NOxの不足がマウスに代謝症候群,血管不全,および心臓突然死を引き起こすことを明らかにした.この機序には,PPARγ/AMPKを介したadiponectinレベルの低下,eNOS発現低下,並びに腸内細菌叢の異常が関与していることが示唆された.
6 0 0 0 OA 刺激伝導系縦横無尽
- 著者
- 加藤 貴雄
- 出版者
- 一般社団法人 日本不整脈心電学会
- 雑誌
- 心電図 (ISSN:02851660)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.1, pp.44-48, 2015 (Released:2015-08-03)
6 0 0 0 OA 資料紹介 仙台の浮世絵師・熊耳耕年の 月岡芳年塾入門記
- 著者
- 堀川 浩之
- 出版者
- 国際浮世絵学会
- 雑誌
- 浮世絵芸術 (ISSN:00415979)
- 巻号頁・発行日
- vol.171, pp.40-63, 2016 (Released:2021-04-08)
- 著者
- Keiichi Kojima Hiroshi C. Watanabe Satoko Doi Natsuki Miyoshi Misaki Kato Hiroshi Ishikita Yuki Sudo
- 出版者
- The Biophysical Society of Japan
- 雑誌
- Biophysics and Physicobiology (ISSN:21894779)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.179-188, 2018 (Released:2018-09-07)
- 参考文献数
- 42
- 被引用文献数
- 7 9
Anion channelrhodopsin-2 (ACR2), a light-gated channel recently identified from the cryptophyte alga Guillardia theta, exhibits anion channel activity with exclusive selectivity. In addition to its novel function, ACR2 has become a focus of interest as a powerful tool for optogenetics. Here we combined experimental and computational approaches to investigate the roles of conserved carboxylates on the anion transport activity of ACR2 in Escherichia coli membrane. First, we replaced six conserved carboxylates with a neutral residue (i.e. E9Q, E56Q, E64Q, E159Q, E219Q and D230N), and measured anion transport activity using E. coli expression system. E159Q and D230N exhibited significantly lower anion transport activity compared with wild-type ACR2 (1/12~1/3.4), which suggests that E159 and D230 play important roles in the anion transport. Second, to explain its molecular aspects, we constructed a homology model of ACR2 based on the crystal structure of a cation channelrhodopsin (ChR). The model structure showed a cavity formed by four transmembrane helices (TM1, TM2, TM3 and TM7) similar to ChRs, as a putative anion conducting pathway. Although E159 is not located in the putative pathway, the model structure showed hydrogen bonds between E159 and R129 with a water molecule. D230 is located in the pathway near the protonated Schiff base (PSB) of the chromophore retinal, which suggests that there is an interaction between D230 and the PSB. Thus, we demonstrated the functional importance and the hypothetical roles of two conserved carboxylates, E159 and D230, in the anion transport activity of ACR2 in E. coli membrane.
6 0 0 0 OA 木曽三川・庄内川および矢作川流域における堆積土砂量に基づく完新世中期以降の侵食速度
- 著者
- 羽佐田 紘大
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)
- 巻号頁・発行日
- vol.94, no.4, pp.187-210, 2021-07-01 (Released:2023-02-19)
- 参考文献数
- 121
- 被引用文献数
- 1
濃尾平野,矢作川下流低地の堆積土砂量を基に,木曽三川・庄内川および矢作川流域における完新世中期以降の侵食速度を1,000年ごとに求めた.過去6,000年間の侵食速度は,木曽三川・庄内川流域で0.29~0.55mm/yr,矢作川流域で0.15~0.29mm/yrと算出された.流域の平均傾斜から推定した侵食速度は,それぞれ0.45,0.16mm/yr,また,体積計算範囲外側の土砂堆積を考慮した侵食速度は,それぞれ0.37~0.64,0.26~0.48mm/yrとなった.これらの値には桁が異なるほどの違いはないことから,低地の堆積土砂量から流域の長期的な侵食速度の傾向をある程度見出すことが可能であると指摘できる.ただし,矢作川流域の各侵食速度の差については,三河湾の土砂堆積の過大評価や山地に分布する花崗岩類の崩壊のしやすさが影響した可能性がある.体積計算範囲外側における土砂堆積の考慮の有無にかかわらず,両流域の侵食速度は1,000年前以降が最大であった.これは流域での森林伐採などの影響によると考えられる.
6 0 0 0 OA なぜウェブで炎上が発生するのか ―日本のウェブ文化を手がかりとして
- 著者
- 平井 智尚
- 出版者
- 公益財団法人 情報通信学会
- 雑誌
- 情報通信学会誌 (ISSN:02894513)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.4, pp.4_61-4_71, 2012 (Released:2012-06-22)
- 参考文献数
- 39
本論ではウェブで炎上がなぜ起こるのかという問題を日本のウェブ文化の観点から明らかにする。炎上とはブログ、ミクシィ、ツイッターなどに投稿されたメッセージの内容に対して、批判や非難が巻き起こる現象を指し、ブログの普及以後、たびたび発生している。それに伴い、炎上に対する社会的な認知も高まり、新聞、雑誌、ニュースサイトなどで言及が行われている。しかし、学術的なアプローチをとった考察は今のところ多くはなく、考察の余地も残されている。本論ではまず炎上の事例を歴史的に整理する。次いで、先行研究への言及をかねてフレーミング現象との比較検討を行う。この作業を通じてフレーミングと炎上の違いを示したうえで、電子掲示板2ちゃんねるの文化と、若年層が担う携帯電話の文化の両面から炎上が起こる理由の説明を行っていく。そして最後に、炎上とは対極に位置するように見えるウェブと公共性に関する考察を展開していく。
6 0 0 0 OA 電気の周波数と電圧(世界•日本)
- 著者
- 門井 龍太郎
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電氣學會雜誌 (ISSN:00202878)
- 巻号頁・発行日
- vol.111, no.12, pp.1011-1014, 1991-12-20 (Released:2008-11-20)
- 参考文献数
- 7
6 0 0 0 OA 産業・労働分野への認知行動療法の適用と課題
- 著者
- 松永 美希 土屋 政雄
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 認知行動療法研究 (ISSN:24339075)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.2, pp.133-142, 2020-05-31 (Released:2020-10-23)
- 参考文献数
- 29
本稿では、主に職場メンタルヘルス対策における予防の枠組みから、認知行動療法の適用と課題について報告した。一次予防では、広く健康な人々にもストレスへの気づきや対応を促すためにも認知行動療法を活用したストレスマネジメントが有用である。二次予防では、メンタルヘルス不調者への早期介入に認知行動療法の諸技法は適しており、職場調整をねらった他職種や人事労務との連携においても認知行動療法による問題理解の明快さは有用である。三次予防では、休職者の復職支援や精神障害者の職場適応に向けた症状コントロールや働き方に関する意思決定などに認知行動療法が適用されている。近年では、これらの予防的取り組みにおいて、マインドフルネスやアクセプタンス&コミットメント・セラピーといった第三世代の活用事例も増えている。今後は、生産性の向上などポジティブな側面にも認知行動療法の適用を広げていくことが課題である。
6 0 0 0 OA サクラてんぐ巣病研究の新展開
- 著者
- 升屋 勇人 菊地 泰生 佐橋 憲生
- 出版者
- 日本森林学会
- 雑誌
- 日本森林学会誌 (ISSN:13498509)
- 巻号頁・発行日
- vol.97, no.3, pp.153-157, 2015-06-01 (Released:2015-08-01)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 1
サクラてんぐ巣病菌 Taphrina wiesneri はソメイヨシノをはじめとするサクラ類に大きな被害を及ぼしている。本菌の全ゲノム解読と近縁な 3 種 (モモ縮葉病菌, スモモふくろみ病菌, ポプラ葉ぶくれ病菌) との比較ゲノム解析の結果, Taphrina 属菌のゲノムは 4 種の間で, ゲノムサイズ, 遺伝子数, 遺伝子の種類の点で類似していることがわかった。同時に, 4 種の菌はそれぞれの宿主に適応し寄生を成立させるような, 染色体重複による寄生性関連遺伝子数の増加や, 遺伝子水平転移による新たな遺伝子の獲得などが起こっており, これらの違いが各宿主への寄生成立や病徴の違いに関与していることが示唆された。さらに, オーキシン, サイトカイニン, アブシジン酸など, 多くの植物ホルモンの合成にかかわる遺伝子が同定できた。本病原菌が宿主植物体内でこれらの植物ホルモンを生産し宿主のホルモンバランスが乱れることが, 奇形誘導に深く関与していると考えられた。今後, 得られたゲノム情報を活用した病原菌の生理生態の解明とそれに基づく生態的防除法や, 病原菌の生存に関わる特定の遺伝子をターゲットにした農薬の開発が可能になってくると予想される。
6 0 0 0 OA 海底資源探査技術の事例 - 3次元海底資源探査船『RAMFORM TITAN』の紹介
- 著者
- 森 英男
- 出版者
- 公益社団法人 日本マリンエンジニアリング学会
- 雑誌
- マリンエンジニアリング (ISSN:13461427)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.5, pp.659-663, 2015-09-01 (Released:2016-12-03)
- 参考文献数
- 1
- 著者
- 芦川 晋
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.1, pp.102-117, 2017 (Released:2018-06-30)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 1
本稿の目的は, 現代社会を踏まえて社会構築主義が提示する「物語的な自己論」を吟味し, より実態に即した「物語的な自己論」の展開可能性を模索することにある. そのために, まず, シカゴ学派にはじまるアメリカ社会学における自己論の洗練過程を, G. H. ミード/H. ブルーマー (象徴的相互作用論), H. ベッカー (レイベリング理論), E. ゴッフマン (対面的相互作用論) の順で検討をする.その結果, まだこれらの議論には十分使い出があることが分かる. ミード/ブルーマーの他者の役割取得論は習慣形成論でもあった. レイベリング論になると, 役割に代わって「人格」概念が重視され, 習慣より「経歴」が問題になる. ゴッフマンの議論では, 相互行為過程における「人格」概念のもつ意義がより突き詰められ, 「経歴」や「生活誌」という概念を用いてパーソナル・アイデンティティを主題化し, すでに簡単な自己物語論を展開していた.ところが, J. グブリアムとJ. ホルスタインは自らが物語的な自己論を展開するにあたって, わざわざ振り返った前史の意義をまともに評価できていない. そのもっとも顕著な例は「自己」と「パーソナル・アイデンティティ」を区別できない点にある.そこで本稿では前史を踏まえたうえで, ゴッフマンのアイデアを継承するかたちで自己物語の記述を試みてきたM. H. グッディンの議論をも参照して, より精緻で現実に即した自己物語論の展開を試みる.
6 0 0 0 OA 統合失調症患者の手記を対象とした発症前生活エピソードに関する研究
- 著者
- 宮島 直子
- 出版者
- 日本精神保健看護学会
- 雑誌
- 日本精神保健看護学会誌 (ISSN:09180621)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.1, pp.116-127, 2010-06-30 (Released:2017-07-01)
- 参考文献数
- 25
本研究の目的は,統合失調症患者の手記から,発症前エピソードを生活の視点で抽出し,その概要を記述することである.手記を研究対象とすることは,研究に関わるプライバシーの問題を解決するとともに当事者に詳細に尋ねることによる過重なストレスを与えない方法として,有効と考えた.研究の手順および分析方法は,まず手記から発症前生活エピソードが記述されている文章をすべて抜き出し,一文を一データとした.次にデータは,意味内容から抽象度を上げコード化し,それぞれのコードは類似性を基にカテゴリー化した.そして得られたカテゴリーの関連性を検討し,カテゴリーについての説明可能な軸を抽出した.結果として,9冊の手記から3,401のデータを得た.データから138の二次コードを抽出し,それらは13のカテゴリーに分類できた.そして,それらのカテゴリーは6つの軸で説明することができた.軸は,【対人関係をめぐる苦痛】【認識の歪み】【的外れな対処】【状況把握の困難】【日常生活上の障壁】【仮面の生活】であった.【状況把握の困難】は,人間の言動の根幹に影響を与え,他のすべての軸に関連する中核的存在とみなすことができた.それぞれの軸について,過去の文献と比較検討し,その妥当性を確認した.
6 0 0 0 モレキュラーシーブの新たな使用法
- 著者
- 安川 知宏 久田 智也 中島 華子 増田 隆介 北之園 拓 山下 恭弘 小林 修
- 出版者
- 公益社団法人 有機合成化学協会
- 雑誌
- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.4, pp.353-361, 2023-04-01 (Released:2023-04-08)
- 参考文献数
- 57
Molecular sieves are type A zeolites with specific sized pores and are commonly used in organic synthesis to capture small molecules such as water. In addition to their trapping effect, they also have acidic and basic active sites and are used as solid acid-base catalysts. Usually, heat-drying treatments are performed prior to use, but the heat treatment methods, such as microwave ovens or heat guns, are not standardized, which could cause problems in reproducibility of reactions. Particularly, for reactions requiring acid/base sites of molecular sieves, these treatment methods are considered more sensitive because the structure of the active sites changes upon heating. In this article, we propose new methods of activation when using molecular sieves and their application to continuous-flow reactions.
6 0 0 0 OA 有機結晶へのマテリアルズインフォマティクス応用
- 著者
- 谷口 卓也
- 出版者
- 日本結晶学会
- 雑誌
- 日本結晶学会誌 (ISSN:03694585)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.2, pp.139-144, 2023-05-31 (Released:2023-06-06)
- 参考文献数
- 16
Organic crystals have presented flexible features in contrast with inorganic crystals, and are expected for the future applications of optoelectronics and active matters. Pharmaceuticals are also the utilization of the organic crystal family. This article presents the basis of the data science in organic crystals, and a few examples of application of my research. An attempt is to screen the structural phase transition of organic crystals, and another topic is to compare structural representation of molecular and crystal structures regressed by graph neural network.
6 0 0 0 OA 国立科学博物館上野本館に展示されているマンボウ属大型剥製の再同定
- 著者
- 澤井 悦郎
- 出版者
- 国立大学法人 鹿児島大学総合研究博物館
- 雑誌
- Ichthy, Natural History of Fishes of Japan (ISSN:24357715)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, pp.6-11, 2023-01-10 (Released:2023-01-11)
- 著者
- 平野 真理
- 出版者
- 日本パーソナリティ心理学会
- 雑誌
- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.2, pp.94-106, 2010-11-20 (Released:2011-02-15)
- 参考文献数
- 37
- 被引用文献数
- 46 59
レジリエンスは誰もが身につけられる精神的回復力であると言われているが,レジリエンスを導く多様な要因の中には後天的に身につけやすいものと,そうでないものがあると考えられる。本研究では,それらの資質的・獲得的な要因を分けて捉えるために,Cloningerの気質–性格理論(TCI)を用いて二次元レジリエンス要因尺度(BRS)を作成することを目的とした。大学生ら246名を対象に調査を行い,TCIとの関連性から選出された項目の探索的因子分析により,資質的レジリエンス要因として「楽観性」「統御力」「社交性」「行動力」,獲得的レジリエンス要因として「問題解決志向」「自己理解」「他者心理の理解」の7因子が見出された。さらに759名へ調査を行い,確認的高次因子分析および既存尺度との関連から,BRSの二次元構造と妥当性が確認された。また,TCIの気質・性格との関連性から,下位尺度の基準関連妥当性が確認された。
- 著者
- 池田 浩 縄田 健悟 青島 未佳 山口 裕幸
- 出版者
- 特定非営利活動法人 組織学会
- 雑誌
- 組織科学 (ISSN:02869713)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.1, pp.49-59, 2022-09-20 (Released:2022-12-02)
- 参考文献数
- 31
本研究では,リーダーシップの新しい関係性アプローチとしてセキュアベース・リーダーシップの可能性と独自性に着目した.107チームの調査から,セキュアベース・リーダーシップは「安全」と「探索」の2機能を加えた3因子で構成され,既存のリーダーシップ理論とも独立していることが明らかになった.さらに,セキュアベース・リーダーシップは心理的安全性を醸成し,チーム成果に結実することが明らかにされた.