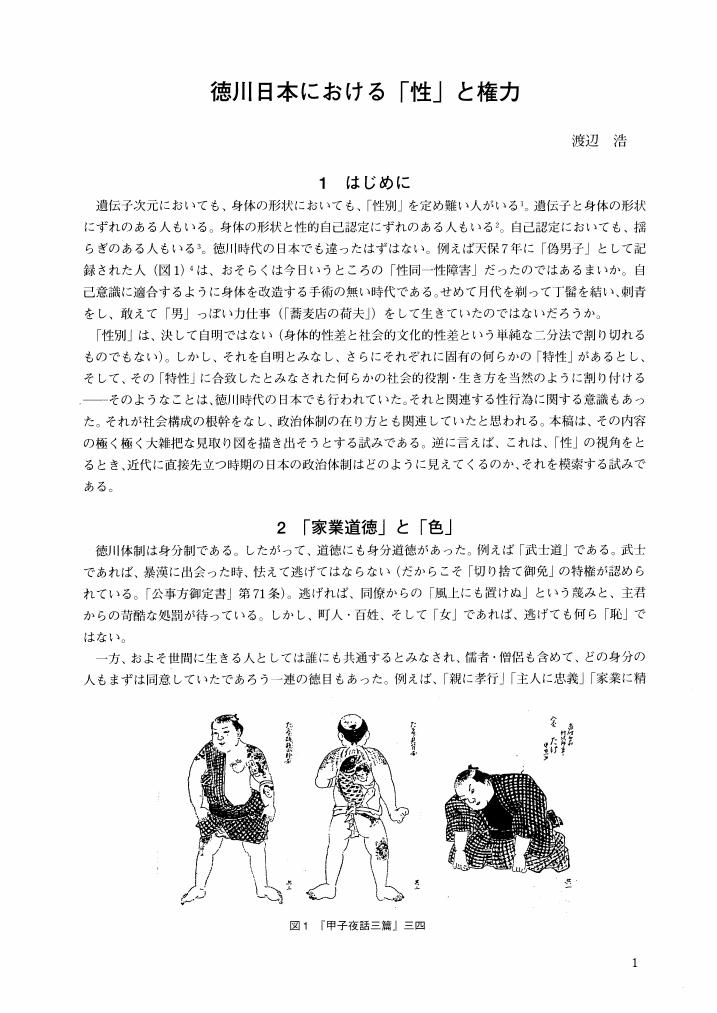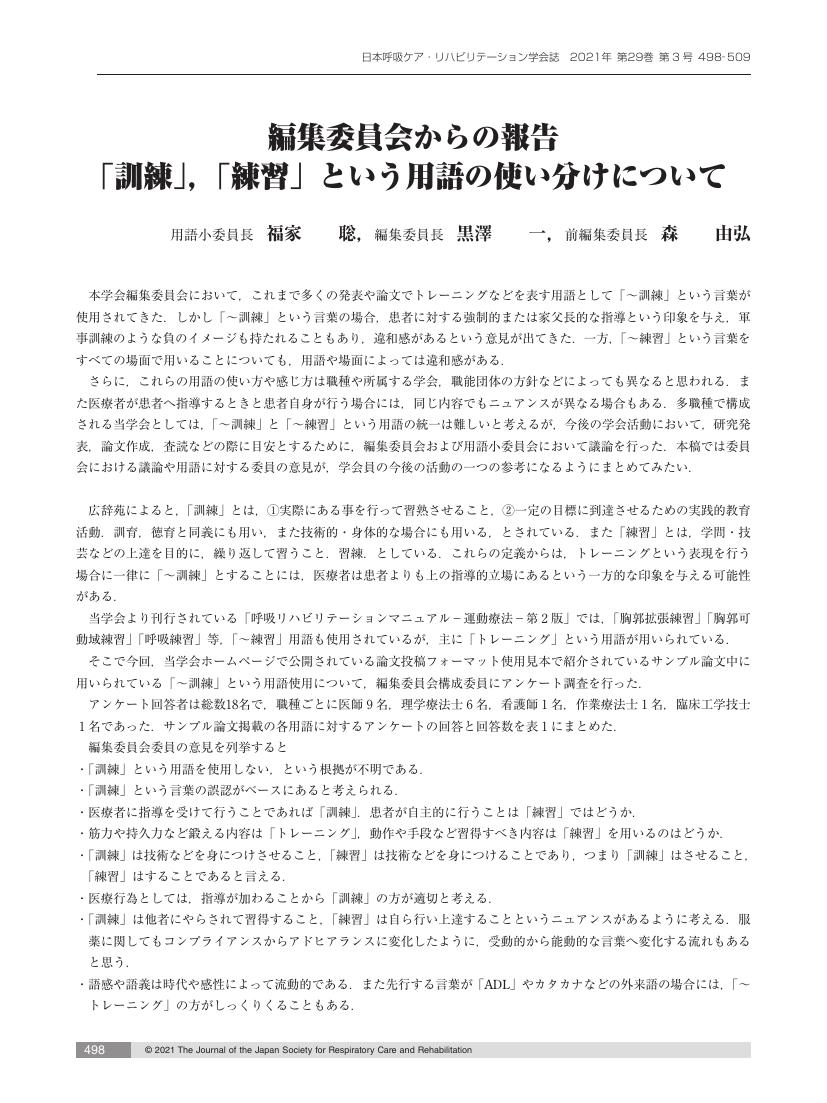6 0 0 0 OA 徳川日本における「性」と権力
- 著者
- 渡辺 浩
- 出版者
- 政治思想学会
- 雑誌
- 政治思想研究 (ISSN:1346924X)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.1-29, 2001-05-10 (Released:2012-11-20)
6 0 0 0 OA 「地域代表」と「全国民の代表」: 最高裁判例を素材に
- 著者
- 松田 聰子
- 出版者
- 桃山学院大学総合研究所
- 雑誌
- 桃山法学 = St. Andrew's University Law Review (ISSN:13481312)
- 巻号頁・発行日
- no.33, pp.1-40, 2020-10-14
- 著者
- 勝部 元 Hajime Katsube
- 雑誌
- 総合研究所報 = ST. ANDREW'S UNIVERSITY, BULLETIN OF RESEARCH INSTITUTE (ISSN:03850811)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.1, pp.15-30, 1982-09-30
6 0 0 0 OA 「柔道人口を考える」
6 0 0 0 OA 赤子と母のいのちを守るための江戸時代の民間療法
- 著者
- 沢山 美果子 Mikako Sawayama
- 出版者
- 国立民族学博物館
- 雑誌
- 国立民族学博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Ethnology (ISSN:0385180X)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.3, pp.459-483, 2016-01-28
本稿では,江戸時代,とくに女と子どものいのちを救うための努力がなされていった18 世紀後半以降の民間療法に焦点をあてる。歴史人口学の研究成果によれば,江戸時代,女性が出産でいのちを失う率は高く,また乳児死亡率も高かった。「家」の維持・存続を願う人々にとって,女と子どものいのちを守ることは,重要な課題であった。そのため,江戸時代には,人々の生活経験をもとにした様々な民間療法が生みだされていた。ここでは,仙台藩の上層農民の家に写本として残された民間療法,その支藩である一関藩の在村医が書き残した民間療法を手がかりに,江戸時代の人々は,身体という内なる自然に起きる危機としての妊娠,出産にどのように対処し,母と赤子のいのちを守ろうとしたのか,そこには,どのような自然と人間をめぐる人々の認識や身体観が示されているかを探った。 考察の結果,次のことが明らかとなった。江戸時代後期には,人々が生活の中で経験的に蓄積してきた身体をめぐる民間の知恵を文字化した民間療法が広く流布していくが,そこに記された,妊娠・出産をめぐる処方,とりわけ対処が困難な難産の処方では,自然の生産物である動植物や清浄な身体からの排泄物が用いられる。それは,脅威としての自然を恵としての自然につくりかえ,自然と人間の一体化を図り身体を回復させることで,内なる自然に起きた困難を取り除こうとする試みであった。そこには,江戸時代の人々の,自然と人間を切り離せないものとして捉える捉え方が示されている。
6 0 0 0 OA ブロッホ思想の21世紀以降的可能性 『希望の原理』コメント
- 著者
- 石塚 正英
- 出版者
- 特定非営利活動法人 頸城野郷土資料室
- 雑誌
- 頸城野郷土資料室学術研究部研究紀要 (ISSN:24321087)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.4, pp.1-29, 2023 (Released:2023-05-09)
6 0 0 0 OA 単眼カメラによるVisual SLAMの原理と3次元再構成の実装例
- 著者
- 小林 祐一
- 出版者
- 一般社団法人 システム制御情報学会
- 雑誌
- システム/制御/情報 (ISSN:09161600)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.2, pp.57-62, 2020-02-15 (Released:2020-08-15)
- 参考文献数
- 18
6 0 0 0 OA 有馬郡守護について
- 著者
- 小林 基伸
- 出版者
- 大手前大学・大手前短期大学
- 雑誌
- 大手前大学人文科学部論集 (ISSN:13462105)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.39-52, 2001
6 0 0 0 OA 現職教師は授業経験から如何に学ぶか
- 著者
- 坂本 篤史
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.4, pp.584-596, 2007-12-30 (Released:2013-02-19)
- 参考文献数
- 63
- 被引用文献数
- 6 5
本研究は, 現職教師の学習, 特に授業力量の形成要因に関し, 主に2000年以降の米国での研究と日本での研究を用いて検討し, 今後の展望を示した。現職教師の学習を1) 授業経験からの学習, 2) 学習を支える学校内の文脈, 3) 長期的な成長過程, という3つの観点から包括的に捉えた。そして, 教師を“反省的実践家”と見なす視点から、現職教師の学習の中核を授業経験の“省察 (reflection)”に据えた。授業経験からの学習として教職課程の学生や新任教師の研究から, 省察と授業観の関係や, 省察と知識形成の関係が指摘された。学校内の文脈としては教師共同体や授業研究に関する研究から, 教師同士の葛藤を通じた相互作用や, 校内研修としての授業研究を通じた学習や同僚性の形成が示唆された。長期的な成長過程としては, 教師の発達研究や熟達化研究から, 授業実践の個性化が生じること,“適応的熟達者 (adaptive expert)”として発達を遂げることを示した。今後の課題として, 現職教師の個人的な授業観の形成過程に関する研究, 教師同士が学び合う関係の形成に関する実証的研究方法の開発, 日本での教師の学習研究の促進が挙げられた。
6 0 0 0 OA 組織の徳倫理学 組織不祥事を評価する枠組みの提案
- 著者
- 杉本 俊介
- 出版者
- 日本経営倫理学会
- 雑誌
- 日本経営倫理学会誌 (ISSN:13436627)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.253-265, 2022-03-20 (Released:2022-11-03)
This paper provides a theoretical basis for organizational virtue and proposes a framework for ethical evaluation of organizational scandals that cannot be assessed using individual virtue standards. I first review traditional virtue ethics and show its limitations. Next, I focus on how organizational virtue can overcome these limitations and examine previous research. I then define an organizational virtue as a character trait that helps stakeholders flourish and propose a framework for organizational virtue ethics based on this definition. Finally, I attempt an ethical evaluation of the Japan Post Insurance scandal within the proposed framework.
6 0 0 0 OA 日本降伏後における南方軍の復員過程 : 1945年~1948年
- 著者
- 増田 弘
- 出版者
- 東洋英和女学院大学現代史研究所
- 雑誌
- 現代史研究 = Contemporary History Research
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.1-159, 2013-03-31
6 0 0 0 OA スイッチOTC点眼薬の使用性に関する製品間の比較検討
- 著者
- 村上 雅裕 中谷 真由美 安田 恵 天野 学
- 出版者
- Japanese Society of Drug Informatics
- 雑誌
- 医薬品情報学 (ISSN:13451464)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.3, pp.209-213, 2016 (Released:2017-02-14)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1
Objective: The squeezing force and one-drop weight, suggested to directly influence adherence, were measured in 6 eye drop products containing a switch OTC drug, ketotifen fumarate, to investigate useful information for product selection.Methods: The squeeze force, one drop weight, and pH were measured using a digital force gauge, analytical balance, and pH meter, respectively. Information on additives contained in each product was collected from package inserts. For the total number of drops, the number per 10 mL was calculated from the obtained value.Results: The maximum squeeze force was 14.8 N of Irice AG Guard, and the one drop weight (33.2 mg) of Raferusa®AL was the minimum. The total number of drops per 10 mL was 215 in Sutto eyes Z, being the minimum. The pH was in the range of 5.2-5.7. On comparison of additives among the products, a cooling agent was contained in only 2 products.Discussion: Since the squeeze force was in the range of 5.3-14.8 N, it was less likely that the squeeze force reduces usability. Since the one-drop weights of 2 products were more than 10 mg lower than the weights of the other products, the dose may be insufficient and the effect may not be attained. The pH was within the acceptable range in all products. Two products contain a cooling agent as an additive, and this has to be explained beforehand. Information related to usability, actual feeling of the effect, and sense of the use of the products containing ketotifen fumarate was collected.
6 0 0 0 OA 編集委員会からの報告 「訓練」,「練習」という用語の使い分けについて
- 著者
- 福家 聡 黒澤 一 森 由弘
- 出版者
- 一般社団法人 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会
- 雑誌
- 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌 (ISSN:18817319)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.3, pp.498-499, 2021-06-20 (Released:2021-06-20)
6 0 0 0 OA 高機能広汎性発達障害にともなう語用障害:特徴,背景,支援
- 著者
- 大井 学
- 出版者
- 日本コミュニケーション障害学会
- 雑誌
- コミュニケーション障害学 (ISSN:13478451)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.2, pp.87-104, 2006-08-31 (Released:2010-04-21)
- 参考文献数
- 100
- 被引用文献数
- 10
高機能広汎性発達障害をもつ個人にみられる語用障害について,特徴,背景,および支援について議論した.語用障害の定義にふれつつ,きわめて多彩な語用障害を診断区分などの個人差を考慮しつつ包括的に展望した.言語行為,精神状態を示す語,間接発話の理解,質問と応答,会話のやり取り,ナラティヴ,人称・呼びかけ形式,言語の推論,指示と結束,ユーモア・しゃれに分けて研究経過を振り返った.語用障害の背景として,心の理論と関連性,中枢性統合,実行機能,全般的な記号論の欠陥,その他の諸説を一覧した.支援について,ソーシャル・ストーリー,ソーシャル・スキル・トレーニング,心の理論の教育,個別的な語用論的アプローチおよび社会-語用論的グループ指導について述べた.今後の課題として,単一事例の徹底した会話データ検索,日本語語用論研究の臨床応用,神経語用論的研究,長所を生かす形で語用論を学べる包括的プログラムの整備をあげた.
6 0 0 0 OA 編集後記
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.8, pp.794, 2023 (Released:2023-08-01)
6 0 0 0 OA 人の子と禿鷲 マタイ24, 28/ルカ17, 37によせて
- 著者
- 大貫 隆
- 出版者
- 学校法人 自由学園最高学部
- 雑誌
- 生活大学研究 (ISSN:21896933)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.1, pp.30-43, 2023 (Released:2023-08-04)
- 参考文献数
- 36
マタイ24, 28/ルカ17, 37に,「死体のあるところはどこでも,そこに禿鷲たちが集まるであろう」というイエスの発言がある.共観福音書の研究においては,マタイとルカ福音書に共通する語録資料(通称Q資料)の一部とみなされている.この語録は私が過去二十年来続けてきたイエスの「神の国」のイメージ・ネットワークの新たな網の目として追加的に「積分」可能である.このことを論証することが本論考の課題である.私見では,プルタルコス『倫理論集』の一篇「自然現象の原因について」918Cとルクレティウス(前99年頃?55年頃)『事物の本性について』IV, 679に,内容上も文言上も最も顕著な並行事例が見つかる.それは死肉があれば,場所の如何を問わずどこにでも集まってくる禿鷲の超能力を称える格言であった(以上第II節).福音書記者マタイとルカがQ資料に加えた編集とその神学的意味を分析(第III節)することによって,Q資料がこの格言を用いていた意味が復元できる.すなわち,すでに死から復活して今は天にいるイエスが間もなく再臨するが,その再臨が人間の居場所を問わず目に見えるものだということである.生前のイエスにとっては,同じ「人の子」という語は自己呼称ではなく,自分が宣べ伝えている「神の国」が間もなく地上に実現する時に出現するはずの超越的救済者を指していた.この違いを考慮に入れた上であれば,生前のイエス自身が問題の格言をその「人の子」の到来の普遍的な可視性を言い表すイメージとして,稲妻のイメージとワンセットで用いたことに「さもありなん」の蓋然性がある.その到来は稲妻のひらめきが地上の特定の「あそこ」や「ここ」に限定されないのとまったく同じように,地上のどこでも目に見える宇宙大の出来事だというのである(第IV節).
6 0 0 0 OA 二條城行幸時の饗応献立における南蛮菓子―新史料を用いて―
- 著者
- 荒尾 美代
- 出版者
- 一般社団法人 日本家政学会 食文化研究部会
- 雑誌
- 会誌食文化研究 (ISSN:18804403)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.20-26, 2022-12-25 (Released:2023-07-25)
本稿の目的は、二條城行幸時の饗応献立記録のある新史料を紹介し、寛永時代の京都における南蛮菓子の受容の一端を明らかにすることである。新史料に記されている献立は、饗応を受ける対象者別になっており、人数が明記されていることに特色がある。「あるへいとう」は最低1,803名分、「かすてら」は最低1,367名分が用意されたと考えられた。特に京都の多数の公家と地下役人へ振る舞われたことは、京都の人々に「あるへいとう」や「かすてら」を知らせるきっかけになったのではないかと思量する。また、全国から参集した国大名や諸大名へも振る舞われた可能性もあり、南蛮菓子が地方へ伝播するのに一役買ったのではないかとも考えられた。
- 著者
- 沼崎 一郎
- 出版者
- 国立婦人教育会館
- 雑誌
- 国立婦人教育会館研究紀要 = Journal of the National Women's Education Centre of Japan
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.15-23, 2000-11-01
6 0 0 0 OA 奨学金制度改革がもたらしたもの : 教員養成系学部の動向をもとに(IV 投稿論文)
- 著者
- 藤森 宏明
- 出版者
- 日本教育政策学会
- 雑誌
- 日本教育政策学会年報 (ISSN:24241474)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.183-197, 2007-06-30 (Released:2017-12-02)
The purpose of this paper is to analyze the effectiveness for the teacher-training course of two policies in 1990s, which were the abolishment of the system of exemption of refund and new Scholarship system that was founded by the Japan Scholarship Foundation (Nihon Ikuei- Kai). The Japan Scholarship Foundation runs an exemption system of refund for the student that becomes a teacher. However, as a reconstruction of the system, this system was abolished and the new Scholarship was established, which was more need - based than usual and was a loan which charged interest. As a result, it is found that by these reforms the ratio of the students decreased, who had the higher academic ability, the bigger possibility of becoming a teacher, and belonged to the lower-income group. And the ratio of the students increased, who did not have higher academic ability, the smaller possibility of becoming a teacher, and belonged to higher-income group. It implies the two things shown below. One is that the abolished system had been running efficiently, the other is that the new system is not compatible with "academic ability", "household economy", which are the basic idea of the Japan Scholarship Foundation.
6 0 0 0 OA 太陽光直接励起レーザーの現状と将来
- 著者
- 佐伯 拓 今崎 一夫 中塚 正大
- 出版者
- 一般社団法人 レーザー学会
- 雑誌
- レーザー研究 (ISSN:03870200)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.2, pp.120-126, 2009-02-15 (Released:2015-08-04)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 2 2
The recent rapid progresses of the laser technologies make possible to convert from solar power to laser