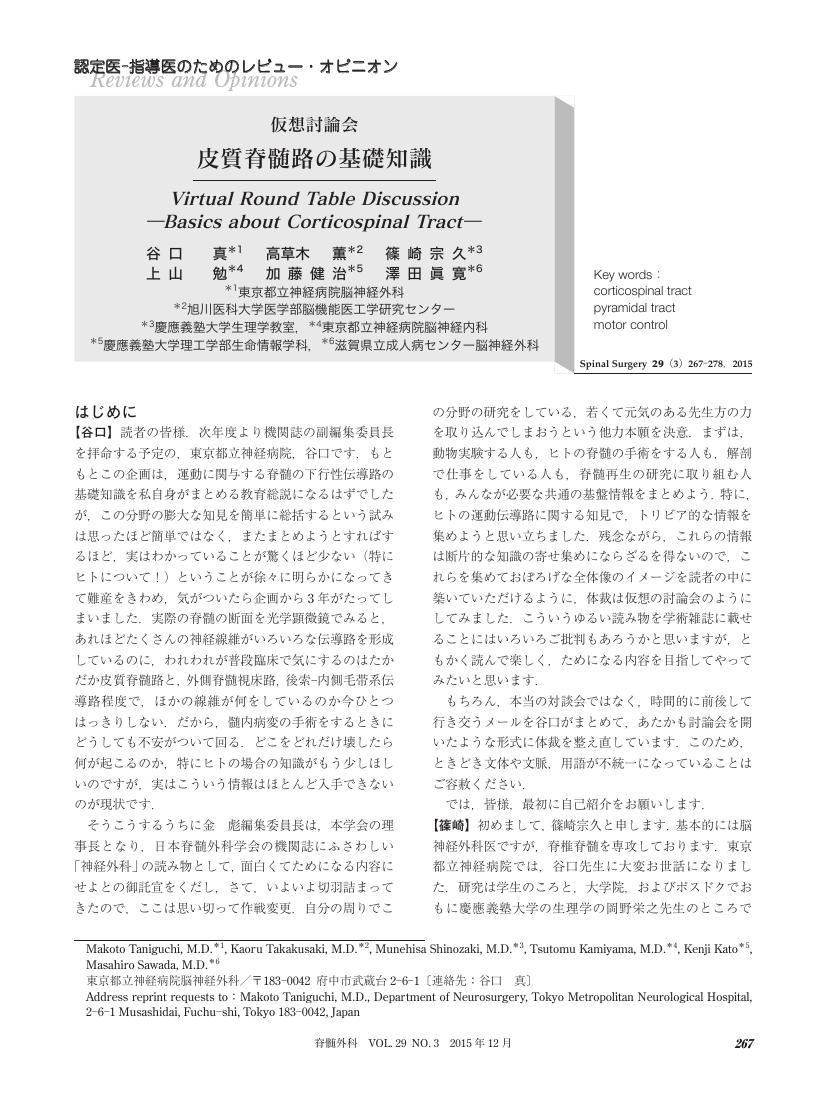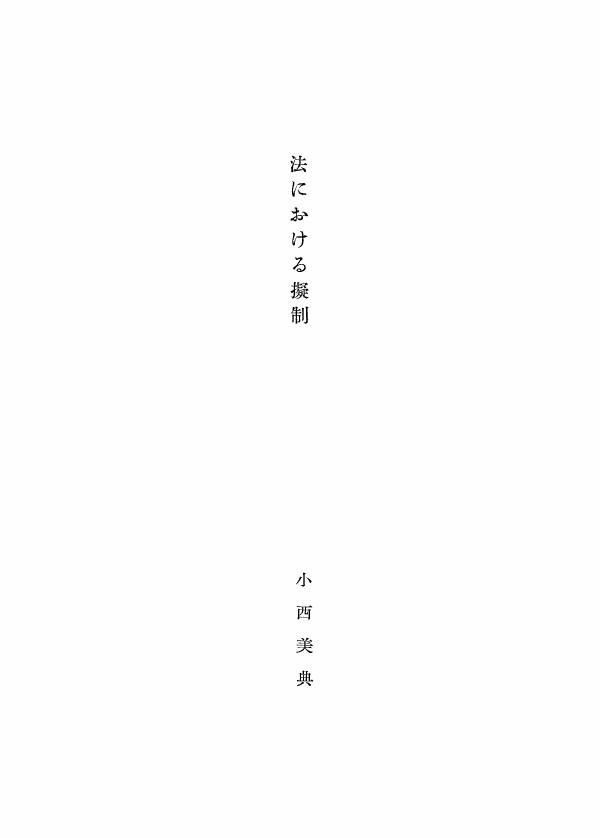6 0 0 0 OA 仮想討論会 皮質脊髄路の基礎知識
6 0 0 0 OA 線香等から放出される揮発性有機化合物類,アルデヒド類及び有機酸の調査
- 著者
- 大貫 文 菱木 麻佑 斎藤 育江 保坂 三継 中江 大
- 出版者
- 一般社団法人 室内環境学会
- 雑誌
- 室内環境 (ISSN:18820395)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.15-25, 2015 (Released:2015-06-01)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 1
室内で燃焼させて使用する線香類について,燃焼時に放出される化学物質を分析し,線香類を使用した際に推定される室内空気中化学物質濃度を算出した。方法は,市販の線香類12試料を燃焼させ,その煙を空気採取用バッグに採取し,バッグ内の揮発性有機化合物類,アルデヒド類及び有機酸類の濃度を測定した。その結果から,試料重量当たり及び燃焼時間当たりの物質放出量を求め,室内空気中の有害物質等濃度を推定した。検出されたのは48物質で,アセトアルデヒド,イソプレン,酢酸,アクロレイン及びベンゼン等の放出量が多かった。48物質合計値の6割以上を有機酸類が占めた試料も見られた。同じ銘柄で煙の量が異なる製品の放出量(μg/h)を比較した結果,煙が「ほとんどない」と標榜していた試料における48物質の合計放出量は「ふつう」の試料の約25%で,なかでも,酢酸及びホルムアルデヒドの放出量が少なかった。また,主に室内で使用する9試料を1時間燃焼させた後の空気中有害物質濃度を推定した(室内容積20 m3,換気回数0.5回/時)。主な物質の濃度範囲は,ベンゼンが11~77 μg/m3,1,3-ブタジエンが4.8~14 μg/m3,アセトアルデヒドが22~160 μg/m3で,アセトアルデヒドについては,6試料が厚生労働省による室内空気中濃度の指針値を超過すると推定された。
6 0 0 0 OA Acute Distal Migration and Shortening of the Flow-Redirection Endoluminal Device: A Case Report
- 著者
- Yasuhiko Nariai Tomoji Takigawa Akio Hyodo Kensuke Suzuki
- 出版者
- The Japanese Society for Neuroendovascular Therapy
- 雑誌
- Journal of Neuroendovascular Therapy (ISSN:18824072)
- 巻号頁・発行日
- pp.cr.2023-0011, (Released:2023-05-26)
- 参考文献数
- 24
Objective: The flow diverter (FD) is a promising device. Apart from two main complications, hemorrhagic and ischemic ones, stent migration is reportedly an unusual complication. In particular, distal migration of the FD has rarely been reported. We report a case of asymptomatic acute distal migration of the flow-redirection endoluminal device (FRED).Case Presentation: A 50-year-old woman was incidentally diagnosed with an unruptured right internal carotid–ophthalmic artery aneurysm with a maximum diameter of 8.0 mm, and she subsequently underwent endovascular treatment with FRED. Based on the vessel diameter (3.8 mm proximal and 3.6 mm distal to the aneurysm), a 4.0-mm-diameter and 18-mm-long FRED was deployed without postoperative complications. However, on MRA 12 months after treatment, the aneurysm was not occluded; angiography showed distal migration of the FRED. The postoperative MRA and skull X-ray images were retrospectively reviewed to determine the period of the migration. The skull X-ray images and the signal loss area due to the FRED on MRA 1 day after the treatment had already demonstrated the migration of the FRED. In the second treatment, a 4.0-mm-diameter and 23-mm-long FRED was deployed in an overlapping fashion up to the proximal part of the carotid siphon. Prompt identification of distal migration of the FD without neurologic signs could be challenging.Conclusion: It is important to follow up meticulously with MRA and skull X-ray images after FD treatment for detecting stent migrations as early as possible.
6 0 0 0 OA 利用者数からみた日本の動物園・水族館の特性
- 著者
- 土居 利光
- 出版者
- 首都大学東京 大学院 都市環境科学研究科 観光科学域
- 雑誌
- 観光科学研究 (ISSN:18824498)
- 巻号頁・発行日
- no.10, pp.39-48, 2017-03-15
動物園及び水族館の評価に関して取り上げられることが多い利用者数は,利用者の関心を示す一つの指標とされることから,10年間にわたる利用者数の変動やその理由などを調査し,利用者数の評価について考察した。年間の総利用者数は,園館によって大きく異なるが,基本的には立地する場所の人の集積度合いで決まってくる。一方,年度によって大きな違いがある場合においても,各年度の総利用者数に占める月別利用者数の割合は,連休などの時期を反映したパターンを示した。これは,動物園などを利用することが「その場所に行くことが望ましい」という規範の下での選択の結果であることを示していると考えられるため,評価において利用者数は,利用者の関心度合いを示す補助的な指標としてとらえるべきである。
- 著者
- 篠原 稔
- 出版者
- 一般社団法人日本体力医学会
- 雑誌
- 体力科学 (ISSN:0039906X)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.3, pp.365-368, 2012-06-01 (Released:2012-06-15)
- 参考文献数
- 4
Publishing scientific papers in English is a major part of professional activities for researchers in the biomedical field. This is because new knowledge becomes most valuable when shared with people around the world, whereas papers written in a local language are difficult to be shared with. Unfortunately, the style of scientific writing is often critically unsatisfactory in manuscripts written in English by researchers who use English as a second language. These researchers are strongly encouraged to learn essential aspects of writing scientific papers in English. To foster the ability for writing scientific papers, young researchers outside of English-speaking countries should be encouraged to take a hands-on education in scientific writing and reviewing in English, and discouraged to publish papers and books in a local language. Increased availability of hands-on education by qualified researchers would be urged for strengthening research capabilities in the biomedical field.
6 0 0 0 OA 埼玉県初記録 17 種を含むカマバチ類 29 種の分布記録 (ハチ目カマバチ科)
- 著者
- 半田 宏伸 三田 敏治
- 出版者
- 埼玉県立自然の博物館
- 雑誌
- 埼玉県立自然の博物館研究報告 (ISSN:18818528)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.119-126, 2023 (Released:2023-07-16)
6 0 0 0 OA スギ花粉症に対する漢方薬併用療法の臨床効果
- 著者
- 今中 政支 峯 尚志 山崎 武俊
- 出版者
- 一般社団法人 日本東洋医学会
- 雑誌
- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.6, pp.611-616, 2009 (Released:2010-03-03)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1 1
スギ花粉症の薬物療法の治療成績を向上させるために即効性を期待できる漢方薬を西洋薬に併用し臨床効果を検討した。アレルギー性鼻炎に対する漢方薬として第一選択とされている小青竜湯例(20名)の有効率は45%と芳しくない成績であった。一方,越婢加朮湯例(24名)では有効率64%と良好な成績であった。重症例に処方される麻黄湯,越婢加朮湯併用(大青竜湯の簡便方)例(7名)は有効率72%であった。麻黄と石膏の消炎作用の増強目的に小青竜湯と五虎湯を併用した症例(16名)では有効率87%とさらに良好な結果であった。経口ステロイド薬の使用を余儀なくされた症例は皆無であった。副作用は胃もたれを訴えた1名のみであった。11種類の漢方薬を使用した全体の治療成績は有効率83%と極めて良好な結果であった。漢方薬を併用することにより,薬物療法の臨床効果の向上を図ることができた。
6 0 0 0 OA 創刊の辞
- 著者
- 河合 忠一
- 出版者
- 一般社団法人 日本循環器学会
- 雑誌
- 循環器専門医 (ISSN:09189599)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.1, 1993-03-25 (Released:2018-05-28)
6 0 0 0 OA 新プラトン主義と中世ドイツ神秘思想に於ける「一性」の問題
- 著者
- 吉田 喜久子
- 出版者
- 宗教哲学会
- 雑誌
- 宗教哲学研究 (ISSN:02897105)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.60-77, 1988 (Released:2018-03-15)
Im neuplatonischen Denken wird alles als Resultat der Entfaltung des Einen, der ersten Hypostase, angesehen. Das Eine, welches in keinem Sinne Differenz und Andersheit enthält, ist für alles Seiende einschließlich der menschlichen Seele sowohl der Ursprung wie auch Ziel, zu dem die Seele über den Geist, d. h. über die in sich durch Differenz relationale Einheit, zurückkehren soll. Die Einheit des Einen wurde innerhalb des Christentums vor allem von den mystischen Strömungen tradiert. Erstmals bei Meister Eckhart ist das neuplatonische Eine mittels der proklischen negatio negationis, doch im von Eckhart veränderten Sinne, zum entscheidenden Element einer christlichen Ontologie geworden. Obgleich das Eine bei Eckhart, das grundsätzlich wohl aus seinen religiös erfahrenen Überzeugungen stammt, nicht nur vom Standpunkt der historischen Einflüsse oder Zusammenhänge zu erklären ist, kann die Notwendigkeit, warum bei Eckhart das neuplatonische Eine sich mit dem christlichen absoluten Sein verbinden muß, schon im neuplatonischen Einen selbst gefunden werden. Wegen dieses Einen konnte Eckhart, anders als Thomas von Aquin, das Sein, welches die ganze Struktur der mittelalterlichen Metaphysik stützt, auf seine Absolutheit hin untersuchen. Doch das Eine ist bei Eckhart nicht nur die Einheit als einziges Wesen der Dreiheit Gottes, weil es sowohl ontologischer als auch soteriologischer Grund für die Beziehung des Menschen zu Gott ist.
6 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1918年07月11日, 1918-07-11
6 0 0 0 OA 法における擬制
- 著者
- 小西 美典
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.1961, pp.161-178, 1962-04-30 (Released:2009-02-12)
- 参考文献数
- 20
6 0 0 0 OA 大衆性尺度の構成──“大衆の反逆”に基づく大衆の心的構造分析──
- 著者
- 羽鳥 剛史 小松 佳弘 藤井 聡
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.5, pp.423-431, 2008 (Released:2011-10-15)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 7 5
This study developed a scale measuring the spiritual vulgarity of the masses, based upon Ortega's “The revolt of the masses” (1957). A questionnaire was constructed with forty items, based on Ortega's descriptions of the characteristics of the spiritual vulgarity of the masses. The questionnaire was completed by 200 university students. The results of factor analysis of the vulgarity measurements yielded two subscales; autistic attitude and contumelious attitude. The two scales were correlated with other existing measures of social values, which was further evidence of validity.
6 0 0 0 OA 香りの分類における心理学的検討
- 著者
- 若田 忠之 齋藤 美穂
- 出版者
- Japan Society of Kansei Engineering
- 雑誌
- 日本感性工学会論文誌 (ISSN:18845258)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.5, pp.591-601, 2014 (Released:2014-12-26)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 5 3
Classification of fragrances has not accepted widely, because the range of stimuli was very wide and words of evaluation were a little. This study picked up essential oils, and selected words from prior questionnaire. Purpose of this study was to classify fragrances by psychological method. This study consisted of 2 experiments, A and B. The same materials and procedures were used in both experiments. Subjects were asked to evaluate fragrances by SD(semantic differential) method. In experiment A, a total of 220 subjects were joined and 15 pair words were used. In experiment B, 75 subjects were joined and 18 pair words were used. Cluster analysis and Factor analysis were used for analyzing the data. As a result, in both experiments, 11 clusters and 3 factors were observed, and clusters of citrus fragrances were showed. The factor of “Pleasantness” was showed in the first factor. This factor was common both experiments.
- 著者
- 小野田 亮介
- 出版者
- 日本読書学会
- 雑誌
- 読書科学 (ISSN:0387284X)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.2, pp.53-68, 2023-05-30 (Released:2023-07-16)
- 参考文献数
- 13
本研究の目的は,日本の成人による図書探索の特徴を明らかにすることである。予備調査では,大学生(n=209)に本の選び方に関する自由記述を求め,図書探索で参照する24の情報源と,図書探索志向性を測定する項目を抽出した。研究1では,大学生を含む成人(n=346)を対象とした調査を実施し,図書探索において外的指標を重視する「レビュー参照志向」と,直感や偶然性を重視する「セレンディピティ志向」の2因子から構成される図書探索志向性尺度を作成した。研究2では,750名の成人を対象として(1)図書探索における情報参照と,(2)図書探索志向性の傾向が読書行動といかに関連しているかについて,読書者と不読書者の対比による検討を行った。分析の結果,成人は本の内容に関する情報源と,本との出会いの偶然性を重視して図書を探索していることが明らかになった。また,図書探索において偶然性を重んじるセレンディピティ志向性が読書行動をとる確率を高める可能性も示された。これらの結果から,偶然性や直感に基づく図書探索を支援することが成人の読書行動を促す可能性が示唆された。
6 0 0 0 OA 光海底ケーブル開発の歴史I —歴史に学ぶ技術の進歩—
- 著者
- 新納 康彦
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会誌 (ISSN:13405551)
- 巻号頁・発行日
- vol.130, no.10, pp.694-697, 2010-10-01 (Released:2010-10-01)
- 参考文献数
- 9
本記事に「抄録」はありません。
- 著者
- 横浜市歴史博物館編成
- 出版者
- 横浜市歴史博物館
- 巻号頁・発行日
- 2010