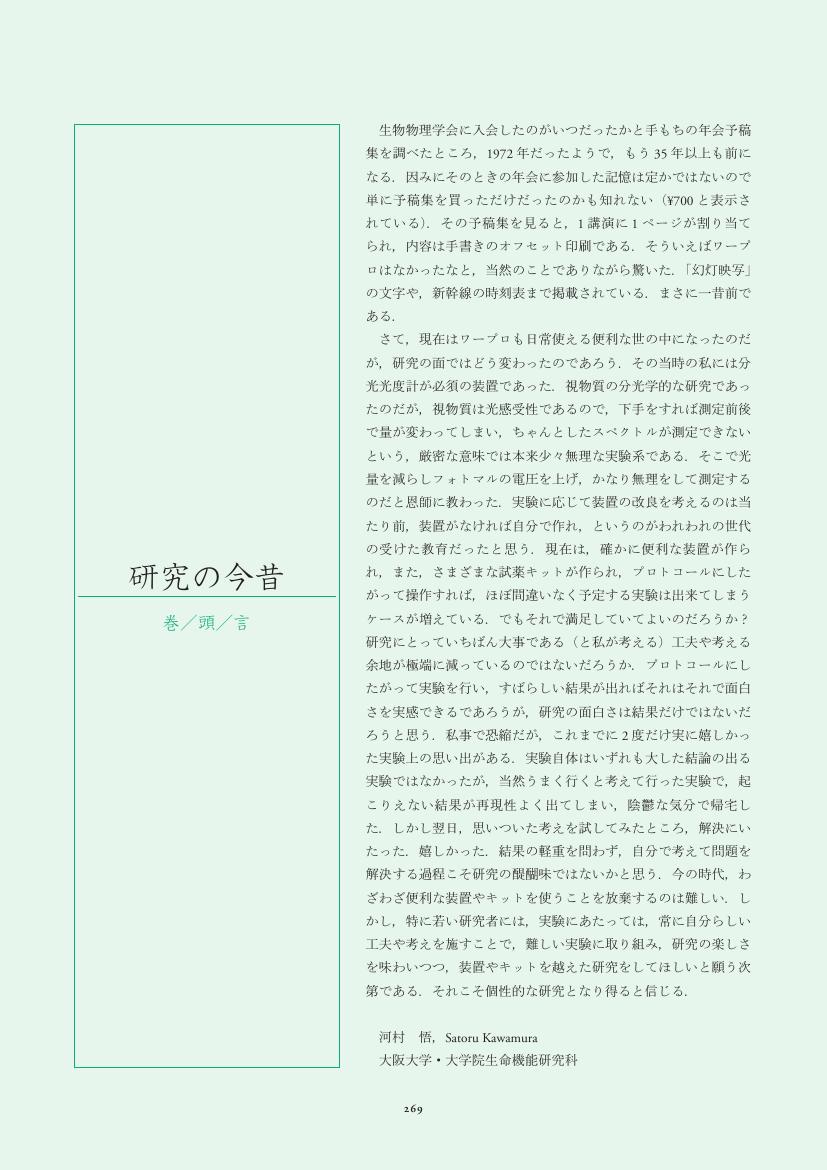3 0 0 0 OA テキストを対象とした評価情報の分析に関する研究動向
- 著者
- 乾 孝司 奥村 学
- 出版者
- 一般社団法人 言語処理学会
- 雑誌
- 自然言語処理 (ISSN:13407619)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.3, pp.201-241, 2006-07-10 (Released:2011-03-01)
- 参考文献数
- 122
- 被引用文献数
- 13 28
インターネットが普及し, 一般の個人が手軽に情報発信できる環境が整ってきている. この個人の発信する情報には, ある対象に関するその人の評価等, 個人の意見が多く記述される.これらの評価情報を抽出し, 整理し, 提示することは, 対象の提供者である企業や, 対象を利用する立場の一般の人々双方にとって利点となる.このため, 自然言語処理の分野では, 近年急速に評価情報を扱う研究が活発化している.本論文では, このような現状の中, テキストから評価情報を発見, 抽出および整理, 集約する技術について, その基盤となる研究から最近の研究までを概説する.
3 0 0 0 OA 地震発生についての相転移論
- 著者
- 笠原 順三 大野 一郎 飯田 汲事
- 出版者
- 公益社団法人 日本地震学会
- 雑誌
- 地震 第2輯 (ISSN:00371114)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.3, pp.201-209, 1969-11-30 (Released:2010-03-11)
- 参考文献数
- 7
When a crystal structure of ammonium fluoride, NH4F, reversibly transforms from Wurtzite structure to NaCl structure at ca. 4kb, a number of small elastic shocks are accompanied with the volume change by the rapid phase transition for polycrystalline specimen. These shocks are also generated during the lowering pressure run, where NaCl structure transforms to Wurtzite structure. If we assume that each of the shocks corresponds to a phase transition in a small volume in the specimen, the amount of the reactant is given by the accumulated number of shocks. Fitting the bulk rate of the phase transition by the equation of the rate theory; dX/dt=K(1-X)p, where X is the mole fraction of the reactant at the time t, we obtain p≈1 and K≈10-1sec-1. The present result shows that the phase transition is the first order reaction and the bulk rate of the phase transition is in the order of 10-1sec-1, although the process of the phase transition is not continuous but is the superposition of very rapid ones with elastic wave radiation.
- 著者
- Nobue Takaiso Haruki Nishizawa Sachie Nishiyama Tomio Sawada Eriko Hosoba Tamae Ohye Tsutomu Sato Hidehito Inagaki Hiroki Kurahashi
- 出版者
- Fujita Medical Society
- 雑誌
- Fujita Medical Journal (ISSN:21897247)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.3, pp.59-61, 2016 (Released:2016-08-31)
- 参考文献数
- 13
The genetic etiology of female infertility is almost completely unknown. Recently, the egg membrane protein JUNO was identified as a receptor of the sperm-specific protein IZUMO1 and their interaction functions in sperm-egg fusion in fertilization. In the present study, we examined 103 women with infertility of unknown etiology. We analyzed the JUNO gene in these cases by PCR and Sanger sequencing. We identified seven variants in total: four common, two synonymous, and a previously unidentified intronic mutation. However, it is not clear from these variants that JUNO has a major role, if any, in infertility. Many factors affect sterility and a larger cohort of patients will need to be screened in the future because the cause of female infertility is highly heterogeneous.
3 0 0 0 OA 飼育方法の違いが雌ユキヒョウの内分泌動態に及ぼす影響について
- 著者
- 木下 こづえ 稲田 早香 浜 夏樹 関 和也 福田 愛子 楠 比呂志
- 出版者
- 日本繁殖生物学会
- 雑誌
- 日本繁殖生物学会 講演要旨集 第102回日本繁殖生物学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.1034, 2009 (Released:2009-09-08)
【背景】ユキヒョウは単独性の季節多発情型交尾排卵動物であるにもかかわらず、国内の飼育下個体群は主に施設面での制約のため雌雄を通年で同居させている場合が多い。このような本来の生態とは異なる状態で飼育すると、繁殖を含めた様々な生理面に悪感作が生じると考えられるが、これを科学的に証明した報告は少ない。そこで本研究では、飼育方法の違いが雌の繁殖に及ぼす影響を内分泌学的側面から詳細に検討した。【方法】妊娠歴のある2頭の雌AとBおよび妊娠歴のない雌Cをそれぞれ2007年4月から1年間および2006年6月から3年間にわたって供試した。前2者は雄と通年別居飼育を行い、本種においてエストラジオール-17β(E2)と正の相関関係にある発情行動(Kinoshitaら, 2009)が見られた日にのみ雄と同居させた。Cについては研究1年目は雄と通年同居飼育を行い、2年目は発情行動が見られてから雄との同居を始め、3年目は再度通年で同居飼育を行った。研究期間中週2~7回の頻度で新鮮糞を採取し、その中に排泄されたE2およびコルチゾールの含量をKinoshitaら(2009)の方法に準じてEIA法で測定した。【結果】通年同居飼育を行わなかった場合の年間糞中E2濃度の変動幅は、雌A、BおよびCがそれぞれ0.13~5.44、0.11~12.03および0.19~13.05μg/gであり、Aは1月からBとCは10月から上昇し始め、3頭ともで上昇期間中に交尾行動が確認された。一方、通年同居飼育を行ったCのE2濃度は、初年度が0.11~6.45で、3年目が0.07~4.44μg/gであり、ともに通年同居飼育を行わなかった2年目よりも低く明確な上昇も見られず、常に雄が居たにもかかわらず両年とも交尾行動はなかった。またCにおいて、通年同居を行った年の糞中コルチゾール濃度は0.26~11.20μg/gの範囲で変動し、通年同居飼育を行わなかった年の0.05~6.58μg/gに比べて有意に高い値を示した。以上の結果から、ユキヒョウでは本来の生態に反する通年同居飼育を行うと個体にストレスが掛り、繁殖能力も低下する可能性が高く、種の保存を目的とした飼育下個体群管理には別居飼育が有用であると考えられた。
3 0 0 0 OA 機械総合メーカーにおけるエンジニアがもつべき流体機械の知識・技術
- 著者
- 新倉 和夫
- 出版者
- 一般社団法人 ターボ機械協会
- 雑誌
- ターボ機械 (ISSN:03858839)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.13-18, 2003-01-10 (Released:2011-07-11)
3 0 0 0 OA Elsberg症候群を呈した急性散在性脳脊髄炎(ADEM)の2例
- 著者
- 浜田 英里 岡本 憲省 奥田 文悟 中村 俊平 川尻 真和 小原 克彦 三木 哲郎 大塚 奈穂子
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.94, no.11, pp.2379-2381, 2005-11-10 (Released:2008-06-12)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1 1
尿閉を呈した脳脊髄髄膜炎2症例の臨床的特徴を検討した.いずれも感冒症状後に意識障害や脊髄症・神経根症を伴って発症し,ステロイドが有効であった点,髄液の細胞蛋白の上昇がみられた点などからウイルス感染を契機とした急性散在性脳脊髄炎(ADEM)と診断した.ステロイドを中心とした治療により神経徴候と尿閉は比較的速やかに改善した.尿閉の成因として無菌性髄膜炎に伴う急性仙髄神経根障害とそれに随伴した一過性の括約筋障害(Elsberg症候群)が考えられた.
3 0 0 0 OA 研究の今昔
- 著者
- 河村 悟
- 出版者
- 一般社団法人 日本生物物理学会
- 雑誌
- 生物物理 (ISSN:05824052)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.5, pp.269-269, 2008 (Released:2008-09-25)
3 0 0 0 OA A case of acute postoperative transitory sialadenosis of the submandibular glands in a healthy dog
- 著者
- Andrea CATTAI Silvia LEVORATO Paolo FRANCI
- 出版者
- 公益社団法人 日本獣医学会
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- pp.16-0324, (Released:2016-09-11)
A 1-year-old healthy female cross-breed dog, weighing 4.5 kg, was scheduled for elective neutering. Fentanyl (5 µg/kg) and propofol (4 mg/kg) were administered intravenously (IV) to induce anesthesia, which was maintained with isoflurane and a constant fentanyl infusion rate (10 µg/kg/hr). During the recovery from the anesthesia, the presence of bilateral dense submandibular masses was recognized, as was the excessive secretion of saliva. An ultrasound examination was performed and revealed bilateral abnormally-diffused enlargement of the submandibular salivary glands. A cytology examination was conducted, and no signs of abnormality were found. The size of the swellings subsequently diminished, completely subsiding after 2 hr, as did the hyper-salivation. To the authors’ knowledge, this represents the first case report of an acute transient swelling of submandibular glands after general anesthesia in a dog.
3 0 0 0 OA 1. ガウスーボネの定理―角度は保存されている―
- 著者
- 今岡 春樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会
- 雑誌
- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.5, pp.227-232, 1996-05-25 (Released:2010-09-30)
3 0 0 0 OA 国産蚕品種による絹箏弦の開発-繭品種による絹弦の物理的特性-
- 著者
- 清水 重人 徳丸 吉彦 金子 敦子
- 出版者
- 日本シルク学会
- 雑誌
- 日本シルク学会誌 (ISSN:18808204)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.47-52, 2012 (Released:2013-03-30)
- 参考文献数
- 6
Polyester and nylon strings for the koto, a traditional Japanese string instrument, are popular in Japan because of their strength and affordability. However, many players prefer silk strings because of their elongation and tone. We have been attempting to develop highly durable silk strings by using original Japanese silkworm races. Here, we studied the physical properties and durability of silk strings made from the various cocoons. We found significant differences in the physical properties and durability of the strings from different races, including ‘Koishimaru’ and ‘Platinum Boy.’ (E-mail: shimizu@silk.or.jp)
3 0 0 0 OA シクエストレート菌Octaviania(ホシミノタマタケ属)の分子系統とその多面的評価
3 0 0 0 OA 医学・薬学領域に寿けるマイクロカプセル
- 著者
- 近藤 保
- 出版者
- 一般社団法人 日本人工臓器学会
- 雑誌
- 人工臓器 (ISSN:03000818)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.3, pp.761-766, 1982-06-15 (Released:2011-10-07)
- 参考文献数
- 16
3 0 0 0 OA 群馬県吾妻地域における中期中新世以降の火山岩類と変質
- 著者
- 中村 庄八 藤本 光一郎 中山 俊雄 方違 重治
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.122, no.8, pp.397-412, 2016-08-15 (Released:2016-09-02)
- 参考文献数
- 42
群馬県北西部の吾妻地域は日本海拡大時に形成された関東北部のリフト帯の縁辺部に位置し,中新世から現在に至る断続的な火山活動で特徴づけられている.日本海拡大以降の本州中央部の地質構造形成や火成活動を考えるうえで重要な地域と考えられる.本見学コースの吾妻川中・上流域では,中新世にはバイモーダルな海底火山活動が中心だが,鮮新世以降陸上の環境となって安山岩質からデイサイト質の火山活動が主体となった.しかし,地層の連続性が乏しく層理も明瞭でなく,変質作用を広汎に受けていることによって進まなかった地層の分布や層序の解明は近年になってようやく前進するに至った.また,本地域は長年にわたって議論されてきた八ッ場ダム建設地を含み,応用地質的にも興味深い地域である.本巡検においては,開析された火山体を構成する塊状の溶岩や火山砕屑岩を特徴づける鮮新世の八ッ場層と同時期ないしその一連の火山活動に関連した岩脈・貫入岩体および酸性変質帯を,また,前期更新世に新たに活動を開始した菅峰火山を構成する火山岩,さらに,後期更新世に浅間火山の活動により流下した応桑岩屑なだれ堆積物,草津白根火山の熱水活動により形成された殺生河原の変質帯の見学を行う.
3 0 0 0 OA ポストモダン符号理論としてのネットワーク,置換,形式化 1:モダン符号理論
- 著者
- 萩原 学
- 出版者
- 一般社団法人 日本応用数理学会
- 雑誌
- 応用数理 (ISSN:24321982)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.33-38, 2016 (Released:2016-07-27)
- 参考文献数
- 15
- 著者
- Hayao Ozaki Takashi Abe Alan E. Mikesky Akihiro Sakamoto Shuichi Machida Hisashi Naito
- 出版者
- 一般社団法人日本体力医学会
- 雑誌
- The Journal of Physical Fitness and Sports Medicine (ISSN:21868131)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.1, pp.43-51, 2015-03-25 (Released:2015-03-23)
- 参考文献数
- 69
- 被引用文献数
- 2 13
This paper reviews the existing literature about muscle hypertrophy resulting from various types of training to document the significance of mechanical and metabolic stresses, and to challenge the conventional ideas of achieving hypertrophy that exclusively rely on high-load resistance training. Low-load resistance training can induce comparable hypertrophy to that of high-load resistance training when each bout or set is performed until lifting failure. This is attributable to the greater exercise volume and metabolic stress achieved with low-load exercise at lifting failure, which, however, results in a prolonged exercise bout. Endurance exercises (walking and cycling) at moderate intensity are also capable of eliciting muscle hypertrophy, but at much slower rates (months rather than weeks) in limited muscle or age groups. Blood flow restriction (BFR) in working muscles, however, accelerates the development of metabolic fatigue, alleviating the time consuming issue associated with low-load or endurance training. These alternative training methods, however, cannot completely replace conventional high-load resistance training, which provides superior strength gain as well as performance improvement even for trained individuals. The alternative approaches, therefore, may be considered for those who are less enthusiastic or under certain medical conditions, or who have limited or no access to proper equipment. However, people should be aware that low-load resistance training or endurance training entails substantial effort and/or discomfort at lifting failure or with BFR. Understanding the advantages and disadvantages of each method will help in assigning the most suitable training program for each client’s goals and needs.
3 0 0 0 OA 第59回社員総会・講演会「高度情報化社会の将来と情報専門家の役割」
- 著者
- 山﨑 久道
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.9, pp.484-489, 2016-09-01 (Released:2016-09-01)
- 著者
- (一社)情報科学技術協会 試験実施委員会
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.9, pp.473-476, 2016-09-01 (Released:2016-09-01)
3 0 0 0 OA 急性虫垂炎手術後52年目に発症した遺残虫垂炎の1例
- 著者
- 浦山 雅弘 原 隆宏
- 出版者
- 日本臨床外科学会
- 雑誌
- 日本臨床外科学会雑誌 (ISSN:13452843)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.2, pp.417-420, 2002-02-25 (Released:2009-01-22)
- 参考文献数
- 9
症例は62歳女性,約52年前急性虫垂炎で手術を受けており,その創部周囲に発赤,疼痛が出現し来院した.血液学的に炎症所見を認め,腹部X線およびCT検査にて糞石様所見があり,虫垂炎が疑われた.虫垂炎の手術既往があったため,抗生物質投与で経過観察したが,翌日,腹部所見が増悪したため,手術を施行した. 52年前の創部は筋層が離開しており,皮下に炎症を伴った虫垂が約2cmほど遺残しており,先端が癒着していた.定型的に虫垂切除を施行した.術後経過は良好であった. 一般に,虫垂切除術の既往があれば,右下腹部痛を示す急性腹症の際に急性虫垂炎は除外され得る.自験例は初回手術時に遺残した虫垂に再度炎症を生じた遺残虫垂炎の症例で,非常に稀な例と考えられた.近年,虫垂炎の診断には超音波が有用とされているが,本症例ではCT検査がより有用であった.
3 0 0 0 OA レーザーによる一般的な事故・ヒヤリハット事例
- 著者
- 橋新 裕一
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本レーザー医学会
- 雑誌
- 日本レーザー医学会誌 (ISSN:02886200)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.4, pp.456-462, 2012-02-15 (Released:2014-02-05)
- 参考文献数
- 18
「事故は起きる」ものと絶えず認識しておくべきである.社団法人レーザー学会が約1 年間に亘ってアンケート調査を実施した.著者はホームページや文献で事故例を調査した.事故の多くは実験室で起こった.また,日本で一般的に用いられているNd:YAG レーザーによる事故が多かった.中心窩が傷害を受けた事故では,視力障害を招く.著者はCO2レーザーやNd:YAG レーザーで火傷したり,服を焦がしたりした経験を持つ.KrF エキシマレーザーで角膜に傷害を被った経験もあった.これらの事故の発生状況などの詳細を紹介する.安全対策として,光波長に合わせた防護ゴーグルを着用することが重要である.また,定期的な安全教育を継続することも肝要である.
3 0 0 0 OA 8.済州島の柿渋染め
- 著者
- 李 善愛
- 出版者
- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会
- 雑誌
- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.1, pp.34-39, 1998-01-25 (Released:2010-09-30)
- 参考文献数
- 22