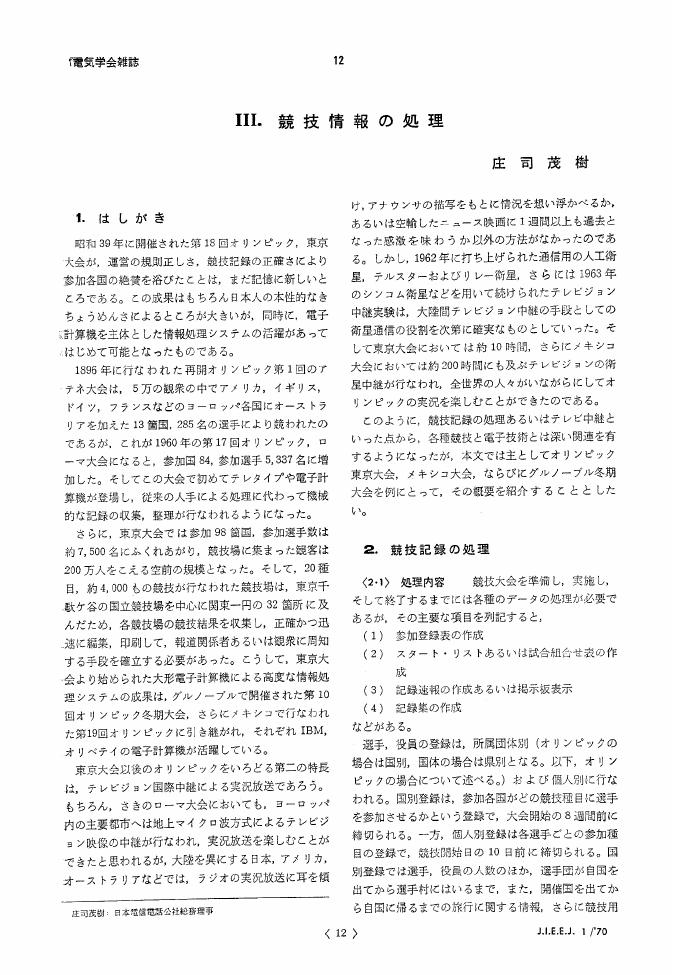6 0 0 0 OA イギリスにおける日本研究の現状 : ロンドン大学,シェフィールド大学,オックスフォード大学の日本研究機関を訪ねて(共同研究奨励金グループ活動報告書「表象としての<日本>-国際日本学の新展開-」)
- 著者
- 村井 まや子
- 出版者
- 神奈川大学
- 雑誌
- 人文学研究所報 (ISSN:02877082)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, pp.112-114, 2007-03
6 0 0 0 OA 十竹齋書畫譜 不分卷
- 著者
- (明) 胡正言 撰
- 巻号頁・発行日
- 1600
6 0 0 0 OA ネーザルハイフロー療法の適応と限界
- 著者
- 富井 啓介
- 出版者
- 一般社団法人 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会
- 雑誌
- 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌 (ISSN:18817319)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.53-57, 2015-04-30 (Released:2015-09-11)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1
ネーザルハイフロー(NHF)は患者の一回換気量や呼吸数の影響を受けずFiO2をある程度一定に保ちながら,上下気道の死腔に溜まった呼気ガスを鼻腔内への高流量ガスで洗い出し,死腔換気量を減少させることで,呼吸仕事量を減らすことができる.また口を閉じれば気道をある程度陽圧に保つこともできる.さらに加温加湿器と熱線入り回路で37℃相対湿度100%の混合ガスを供給でき,快適性と気道の粘液線毛クリアランスを維持し排痰を促すことができる.このような利点から高い陽圧を必要としない酸素投与全般,すなわち高圧PEEPを必要としないⅠ型呼吸不全や積極的な換気補助を必要としない軽症のⅡ型呼吸不全などが適応となる.多くの場合NPPVの前段階もしくは離脱期に使用され,会話,飲食,排痰,リハビリなどが可能で一般病棟でも実施できるが,終末期を除いて改善が得られない時はNPPVのすぐ開始できる環境での実施が望ましい.
6 0 0 0 OA III. 競技情報の処理
- 著者
- 庄司 茂樹
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電氣學會雜誌 (ISSN:00202878)
- 巻号頁・発行日
- vol.90, no.1, pp.12-19, 1970-01-20 (Released:2008-04-17)
- 著者
- 安部 悠 内田 文雄
- 出版者
- 一般社団法人日本建築学会
- 雑誌
- 学術講演梗概集. E-2, 建築計画II, 住居・住宅地, 農村計画, 教育 (ISSN:13414526)
- 巻号頁・発行日
- vol.2011, pp.477-478, 2011-07-20
- 著者
- 寺内 大輔 谷本 由貴美
- 出版者
- 初等教育カリキュラム学会
- 雑誌
- 初等教育カリキュラム研究 (ISSN:21876800)
- 巻号頁・発行日
- no.5, pp.41-56, 2017-03-31
本論文は,筆者のひとりである寺内が授業者となって行った,小学校における授業実践をとおして,ジョン・ゾーン(John Zorn)の考案した集団即興演奏の方法《コブラ(Cobra)》の教育的意義を検討するものである。寺内は,以前,2013年に広島市立A小学校第5学年児童を対象に,簡易化されたルールによる《コブラ》の実践を行い,多様な表現を引き出す活動としての意義や,児童一人ひとりの〈ストレングス〉を生かすための実践としての可能性を考察した(寺内2015)。本論文では,2015年に同小学校第4学年児童を対象にして行った実践を対象とする。前述した2013年の実践での考察をふまえ,児童の普段の姿をよく知る学級担任である谷本との振り返りをとおして,児童一人ひとりが自らの〈ストレングス〉をどのように生かしているかを検討するとともに,《コブラ》を学習材とした活動にどのような学びが埋め込まれているかを検討した。In this thesis, we examine the educational value of Cobra, one of John Zorn's masterpieces of group improvisation, as learning material through performances in classes at an elementary school where Terauchi, one of the authors, taught. In 2013, Terauchi felt that performances of Cobra could empower and encourage various kinds of expression among fifth-grade students in an elementary school in Hiroshima(Terauchi 2015). We also examined classwork for fourth-grade children in the same school, and on the basis of previous classwork, from 2013, we considered how children might become empowered, using their own strengths. We also consider "situated learning" from the viewpoint of Tanimoto, who as a homeroom teacher, is very familiar with children's usual characteristics.本稿は,寺内の学位論文「ジョン・ゾーン《コブラ》の研究―即興演奏を素材としたコラージュとゲームをめぐる考察―」(2016)付録1「《コブラ》の教育的意義の検討―筆者による2つの授業実践を通して」第2章「小学校音楽科における実践2―2015年実践」の内容を一部修正したものである。本研究は,JSPS科研費15K04501の助成を受けたものである。
- 著者
- 中塚 武
- 雑誌
- 日本地球惑星科学連合2019年大会
- 巻号頁・発行日
- 2019-03-14
〇はじめに-文理融合と言う課題 歴史学や考古学と地球惑星科学は、ともに過去におきた出来事を対象に含み、長い時間を掛けて進む、いわゆる歴史的プロセスを扱う学問分野である。その共通の特性を生かして、さまざまな共同研究が行われてきた。しかし文理融合にはさまざまな課題があり、その背景には学問の根源的な目的の違いという問題があった。ここでは、総合地球環境学研究所(地球研)で2014年から5年間にわたって行われた研究プロジェクト「高分解能古気候学と歴史・考古学の連携による気候変動に強い社会システムの探索」(気候適応史プロジェクト)の経験から、歴史学・考古学と地球惑星科学の協働の活性化の方向性について議論したい。〇気候適応史プロジェクトの基本構造 地球研は文理融合の手法を用いて地球環境問題の解決に資するプロジェクトを全国の大学等から多数公募し、時間を掛けて準備と審査を繰り返したのち期限を定めて本格的な研究を行わせる大学共同利用機関である。古気候学者である私は、その枠組みの中で2010年から全国の古気候学、歴史学、考古学の関係者に呼びかけて、3つのステップからなる気候適応史プロジェクトの構想を作った。1)最新の古気候学の手法を用いて過去数千年間の日本の気候を年単位で復元する、2)得られた古気候データを歴史学・考古学の膨大な史・資料と詳細に対比する、3)気候と社会の関係の無数の事例を比較分析して、気候変動に強い社会と弱い社会の特徴を明らかにする。このプロジェクトでは当初、文献史料から天候を解読する歴史気候学を除くと、理系から文系への一方的な情報の流れだけを想定していたが、実際には両者の緊密な相互作用により、事前の想定を遥かに越えた研究の進展があった。以下、プロジェクトで最も重視した古気候復元指標である樹木年輪セルロースの酸素同位体比を用いた夏の降水量の復元を例にして、文理融合の効果と課題について述べる。〇文理融合による研究の進展と課題 樹木年輪セルロースの酸素同位体比は、年輪古気候学に独特の難しさがあった日本のような温暖湿潤域で高精度の気候復元を可能にした画期的なプロキシーであり、プロジェクトでは、そのデータを日本全国で過去数千年間にわたって早期に構築することを目指していた。文系の研究者は、当初、年輪古気候データのユーザーとしてのみ位置づけられていたが、実際にはさまざまなレベルでデータ構築自体に大きく貢献することになる。理系から文系へは高精度の古気候情報と共に、酸素同位体比を用いた新しい年輪年代情報が提供されたが、それに対して文系から理系には以下のような反応があった。1.出土材や建築古材の積極的な提供、2.データの史・資料による批判、3.データの時空間的な精度と範囲の改善要求である。理系の側にとって1は全面的に歓迎できるが、2,3は耳が痛く、自らの発想からは生まれにくい。しかし3の要求が、世界で初めて酸素と水素の同位体比を組み合わせて、年輪古気候学が最も苦手とする長周期の気候復元を可能にした。その結果、2の批判も克服して、過去数千年間に亘る年~千年のあらゆる周期の気候変動の復元に成功し、古気候学・歴史学・考古学の研究は一気に進展したが、プロジェクトの目的である肝心の「気候変動に強い社会システムの探索」の方はなかなか進まなかった。文理を越えた学問の根源的な目的への相互理解が足りなかったからである。〇おわりに-相互理解が協働の基本 空前の長さと精度を持つ高分解能古気候データの構築という気候適応史プロジェクトの成果は、文理双方の学問的なニーズが緊密に相互作用した結果である。当初は理系データの文系への提供だけを考えていたが、実際には相手のニーズを無視した一方的なデータの押し付けはうまく行かず、文理を超えた相互批判が重要であった。これは、文系のデータを理系が利用する場合でも同じである。一方で、文理融合が個別分野の発展を促すだけでなく、真の「融合」になるためには、より深いレベルでの相互理解が必要であった。私が気候適応史プロジェクトの中で気付いた最も重要な事実は、「歴史学者や考古学者は、必ずしも現代の問題の解決のために、歴史の研究をしている訳ではない」ということである。もちろん、それには意味がある。文系の歴史研究が重視するのは、研究対象とする時代の人々の価値観の違い、つまり歴史上の各時代の人々の多様性を理解し、現代の私たちを相対化することである。現代が過去と違うのと同様に、未来も現代とは違う以上、未来志向で現在の問題を解決していくためには、法則性の発見を重視する理系の研究者と、多様性の理解を重視する文系の研究者が、相互に尊重し合って未来に向って共に考えていくスタンスが必要である。そのことに気が付いたことが私にとってプロジェクトの最も重要な教訓であった。
6 0 0 0 IR 馬の人に対する視覚・聴覚認知に関する研究
- 著者
- 川嶋 舟 福本 瑠衣 内山 秀彦 Schu Kawashima Fukumoto Rui Uchiyama Hidehiko
- 出版者
- 東京農業大学
- 雑誌
- 東京農業大学農学集報 (ISSN:03759202)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.3, pp.159-164, 2013-12
馬は使役動物として人の生活において重要な役割を担ってきた。近年では動物介在療法へも応用を広げ,人と馬との新たな関係を構築しつつある。しかしながら,馬の認知能力については,科学的な研究不足から長い間正しい理解がされずにいた。馬の認知能力を理解することは,飼育方法・訓練の効率化,飼育環境の適切な改良,そして馬を用いた福祉的活動の発展といった応用につながると考えられる。そこで本研究は,馬の認知能力の中でも,特に人の認識状況下における聴覚および視覚情報認知の関係性を明らかにし,馬と人との関係性について考察することを目的とした。十分にトレーニングされた馬において,管理で用いられる個体の呼称や指示に関する音声刺激を提示し,馬の行動を観察,得点化した。このとき実験補助者,馬の管理者,既知の人物,未知の人物の音声刺激に対する得点の比較を行った。得られたデータから,耳の動き,目線,接近行動に有意な点数の違いがみられた。耳の動きは,未知の者と比較したとき,有意に実験補助者ならびに馬管理者の音声刺激に対する点数が高く注意を向けていた。また,目線は既知の者より未知の者が有意に高い点数となり未知のものを注視した。さらに人に対する接近行動は,未知の者と比べ管理者や既知の者の音声刺激に対し有意に近い位置を示した。これらの結果から,馬は聴覚,視覚によって人ならびに状況を認知し,人物を弁別と記憶をしていることが示唆された。またその認知過程には第一に聴覚情報を受容し,特に未知の者など認識がなく情報の一致性がない場合,視覚情報を用いてこの統合を行い,行動に移行すると考えられた。これらのことは,馬との相互関係において,積極的に声をかけることが動物介在療法など様々な活動下での対象者の認識を強め,あるいは信頼関係という領域を築く上で極めて重要であると考えられる。
6 0 0 0 OA 「第三の消費文化」の概念とその意義
- 著者
- 間々田 孝夫 ママダ タカオ Takao Mamada
- 雑誌
- 応用社会学研究 = The journal of applied sociology
- 巻号頁・発行日
- vol.53, pp.21-33, 2011
6 0 0 0 OA 道具を使う手と脳の働き
- 著者
- 入來 篤史
- 出版者
- The Robotics Society of Japan
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.6, pp.786-791, 2000-09-15 (Released:2010-08-25)
- 参考文献数
- 13
6 0 0 0 OA アテネの疫病はマールブルグ病, または, エボラ熱か?
- 著者
- 斉藤 博
- 出版者
- 埼玉医科大学
- 雑誌
- 埼玉医科大学進学課程紀要 (ISSN:0287377X)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.15-25, 2000-03-31
- 被引用文献数
- 3
アテネの疫病は, トゥキュディデスの『戦史』2巻には記載されているが, 『ヒポクラテス全集』(『全集』)には記載されていない.アテネの疫病は, 出血性, 発熱性ウイルス性感染症であるマールブルグ病, エボラ熱, 或いは, その類似疾患と考えられる.『戦史』と『全集』の色彩表現は関連性があったと推測される.『戦史』の3巻以降には色彩表現は殆ど認められないが, トゥキュディデスが疫病に罹り, その合併症であるブドウ膜炎による後天性色覚異常になったためと推測される.ヒポクラテスの生年をBC 460年頃とすると, アテネの疫病はBC 430年であるから, 彼は当時30歳代と推測される.『全集』にはアテネの疫病の記載がないが, ヒポクラテスがアテネの疫病に関与しなかったか, 或いは, 後に記載が脱落したかは不明である.
6 0 0 0 OA 維新史蹟但馬出石に隠れたる木戸松菊公遺芳集
6 0 0 0 OA いじめ加害者達の社会的スキルといじめ継続期間の関連
- 著者
- 大野 晶子
- 出版者
- 日本女子大学
- 雑誌
- 日本女子大学大学院人間社会研究科紀要 (ISSN:13459805)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.149-161, 2008-03
- 著者
- 河口 明人
- 出版者
- 北海道大学大学院教育学研究院
- 雑誌
- 北海道大学大学院教育学研究院紀要 (ISSN:18821669)
- 巻号頁・発行日
- vol.112, pp.1-26, 2011-06-30
要旨】文化は「遊び」の中から発生し,日常を超えた「遊び」は自由な創造性の根源であり,文明の駆動力である。ギリシャ社会が獲得した宗教的生活の核心的象徴である祭典は,互いに死力を尽くす戦闘状態にあったポリス間の一切の戦闘を禁止するという驚くべき秩序を保って継続された。それは,宣戦布告もない不断の戦闘状態に晒される精神的緊張と抑圧からの解放であるとともに,アゴン(競争)によって,常に他者を凌駕しようと意欲したギリシャ人の善と美を創造する身体への憧憬の源泉でもあった。祭典がテストしたのは,人間の境界を越え行く精神と身体が一体化したアレテー(卓越性)である。ポリスの命運に自由な生存を託し,最善を尽くさんとする不滅の行動原理を堅持したギリシャ人は,感性に支えられた生存の意思(生き甲斐)によって生命を意義づけた歴史的民族であった。
6 0 0 0 OA 2.バイオマーカー測定の意義と限界
- 著者
- 一ノ瀬 正和
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.98, no.12, pp.3026-3032, 2009 (Released:2012-08-02)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1
気管支喘息の診断及び管理において,スパイロメトリーによる閉塞性障害の評価や気道過敏性検査がこれまで行われてきた.一方,喘息の本態である「気道炎症」に関しても,喀痰,呼気ガス,呼気凝縮液といった検体を用いた方法が臨床応用されつつある.これら所謂「バイオマーカー」の中でも呼気一酸化窒素濃度測定は非侵襲的で発作期にも行えることから,今後のさらなる展開が期待される.
6 0 0 0 OA 「正倉院漆箜篌」の復元 : 実際に手にとってみて
- 著者
- 杤尾 麗
- 出版者
- 中京大学
- 雑誌
- 文化科学研究 (ISSN:09156461)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.58-45, 2006
6 0 0 0 公衆衛生政策と人権:私権制限を伴う政策の正当性評価の基準と手続き
- 著者
- 佐藤 元
- 出版者
- 公益財団法人 医療科学研究所
- 雑誌
- 医療と社会 (ISSN:09169202)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.2, pp.63-78, 2005
公衆衛生政策は私的権利の制限(私権制限)を伴うことが多い。私権に関わる例としては,公衆衛生情報と個人のプライバシー,コミュニケーション政策と表現の自由,検疫・隔離や強制的入院と個人の自律や自由,安全衛生基準と経済活動の自由などの間に見られる対立が挙げられる。国家・自治体は公共の福祉のために私権を正当に制限し得るとされるが,公衆衛生領域における政府の責務と権限が拡大する中,人権保護に関する議論を整理し制度を整えることは重要な課題である。本稿は,現代の米国における議論を総括紹介し,今後の議論に資すことを目的とした。公衆衛生政策を人権保護の観点から検討する際には,正当性,合理性,経済的負担と効率,私権制限の程度,公平性,政策相互の整合性が系統的に評価されることが望ましい。また,こうした評価を制度化し実効性のあるものとするためには,正当な法的手続きと政治過程の透明性確保が重要と考えられる。前者は,実質的正当性と形式的正当性の両者からなる。
6 0 0 0 OA 知識としての言語を話す能力 -ダメットの議論を手掛かりに-
- 著者
- 佐藤 暁
- 出版者
- 日本科学哲学会
- 雑誌
- 科学哲学 (ISSN:02893428)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.1, pp.1-16, 2012-07-30 (Released:2013-06-05)
- 参考文献数
- 6
Dummett argued that practical ability is knowledge if and only if having an ability is described as knowing some propositions. He asserts that the ability to speak a language is knowledge itself, because we cannot attempt to speak a language unless we can speak the language. However, it is not clear why such an ability is knowledge itself. In this study, we reinforce his argument by defining knowledge of how to do things as knowledge based on learning experience. We cannot speak a language without learning experience. Moreover, if one gains an ability through learning experience, this means that he at least knows some propositions.