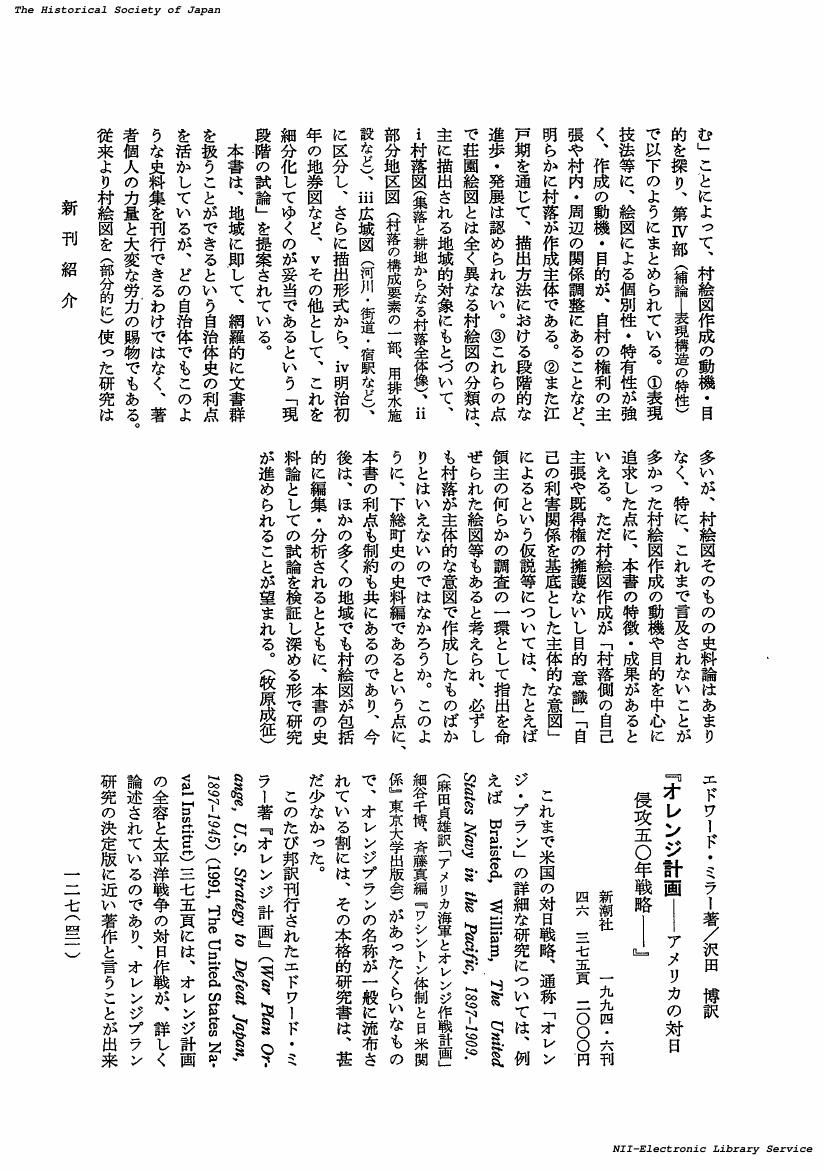- 著者
- 石田 明日香 高柳 昌芳 保科 架風 岩山 幸治
- 出版者
- 日本計算機統計学会
- 雑誌
- 計算機統計学 (ISSN:09148930)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.2, pp.99-126, 2023 (Released:2024-01-11)
- 参考文献数
- 16
現在, バスケットボールの選手評価に使われる指標には, 評価値の信頼性に関する情報を得ることや選手同士の相乗効果に関する評価が難しいという問題がある. これに対し本論文では, チームメイトや対戦相手など同時に出場している選手の能力や, チームメイトとの相乗効果を考慮に入れたモデルをベイズ推定することでそれらの問題を解決する選手評価が可能になることを示した. また, 選手の攻撃・守備能力などの事後分布を解析的に導出することで, 選手の能力評価値やそれらのアフィン変換で得られる指標のベイズ信用区間を構築し, 能力値の推定の不確実性についても評価できることを示した. これは, マルコフ連鎖モンテカルロ法を利用するよりも計算コストを抑えることが可能である. また, アメリカ National Basketball Association (NBA) のデータを利用し, 既存手法との比較検証を実施し, 提案手法は既存手法よりも妥当な選手評価を提供することを確認した.
2 0 0 0 OA 社会主義と社会民主主義の関係
- 著者
- 瀬戸 宏
- 出版者
- 社会主義理論学会
- 雑誌
- 社会主義理論研究 (ISSN:24367354)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.51-71, 2022-10-05 (Released:2023-01-05)
2 0 0 0 OA 表色系
- 著者
- 日置 隆一
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- テレビジョン (ISSN:18849644)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.12, pp.975-985, 1969-12-01 (Released:2011-03-14)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 OA 二光子干渉によるアンチバンチング
- 著者
- 小芦 雅斗 平野 琢也 松岡 正浩
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.8, pp.649-652, 1995-08-05 (Released:2008-04-14)
- 参考文献数
- 15
2 0 0 0 OA アナログテレビの規格 (1) -EIA RS170A-
- 著者
- 宇野 潤三
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- テレビジョン学会誌 (ISSN:03866831)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.2, pp.169-172, 1990-02-20 (Released:2011-03-14)
- 参考文献数
- 3
NTSC方式スタジオ機器規格として代表的な, EIA-RS170A規格を紹介する.
2 0 0 0 OA 神経回路の構造と機能を明らかにする新規G欠損狂犬病ウイルストレーシング法
- 著者
- 小坂田 文隆
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.146, no.2, pp.98-105, 2015 (Released:2015-08-10)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 1 1
脳は,ニューロンが多段階の階層構造をもつ複雑な生体情報処理システムである.この情報処理システムの中核を担うのは神経回路であり,神経回路の破綻は神経・精神疾患における様々な機能障害を引き起こす.我々は,狂犬病ウイルスの経シナプス感染能を利用した新規神経回路解析法を開発してきた.G欠損狂犬病ウイルスベクターは,①投射ニューロンを逆行性に標識できる,②特定のニューロンに入力する細胞群を標識できる,③神経接続と細胞形態との対応付けができる,④神経接続と回路機能との対応付けができることなどから,神経回路の構造と機能を解析する強力なツールとして急速に普及し始めている.本稿では,G欠損狂犬病ウイルスを用いた経シナプストレーシング法,ウイルス作製方法および哺乳類脳への適用方法を紹介する.
- 著者
- 工藤 美知尋
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.104, no.3, pp.421-422, 1995-03-20 (Released:2017-11-30)
- 著者
- Tamie Nakajima Setsuko Ohta Hiroshi Morita Youko Midorikawa Shohei Mimura Nobuo Yanagisawa
- 出版者
- Japan Epidemiological Association
- 雑誌
- Journal of Epidemiology (ISSN:09175040)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.1, pp.33-41, 1998 (Released:2007-11-30)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 21 32
On the night of June 27, 1994, about 12 liters of sarin were released by terrorists in Matsumoto City, Japan. In order to investigate the epidemic, community-based questionnaire surveys were conducted. The subjects were all inhabitants (2052 people) living and staying in an area of 1050 meters from north to south and 850 meters from east to west including the sarin release site. Participants included 1743 people who answered the questionnaire at the first survey; those with symptoms were contacted for follow-up at four months and one year after the episode. The number of sarin victims were 471 persons. Muscarinic signs were common to all victims; nicotinic signs were only seen in severely affected victims. The geographical distribution of sarin victims was closely related to the direction of the wind. Three weeks after the intoxication, 129 victims still had some symptoms such as dysesthesia of the extremities. At that time, many victims had begun to experience asthenopia, which was even more frequent at four months. Although victims who felt sarin-related symptoms had decreased by a year, some still had symptoms such as asthenopia. Sarin released in a suburban area affected approximately 500 inhabitants living nearby; some still had symptoms a year after the intoxication. J Epidemiol, 1998; 8 : 33-41.
2 0 0 0 OA 脊椎疾患に対するピラティスによる運動療法の可能性
- 著者
- 藤谷 順三 西良 浩一
- 出版者
- 一般社団法人 日本脊椎脊髄病学会
- 雑誌
- Journal of Spine Research (ISSN:18847137)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.6, pp.869-877, 2023-06-20 (Released:2023-06-20)
- 参考文献数
- 12
腰痛診療ガイドライン2019(改訂第2版)に示されたように,腰痛治療の選択肢として運動療法は重要である.近年,Motor Controlの概念に基づくピラティスの有効性が注目されている.ピラティスのコンセプトは,Joint by Joint Theoryに基づき,低可動な胸椎・股関節は可動性(mobility)を,過可動な頸椎・腰椎は安定性(stability)を向上させることで,脊椎へのメカニカルストレスを低減・分散させることである.ピラティスによる運動療法を行う際は,呼吸に伴う体幹筋群のdraw-in & bracing,脊柱や四肢の長軸方向の伸長,脊柱の分節的な動き,四肢の分離運動,全身の統合を常に意識させる.また,疾患によってアプローチが異なり,例えば,腰椎後弯症の場合は,胸椎のmobilityを向上させた上で,腰椎・骨盤(コア)のstabilityを図る.一方,腰椎椎間板ヘルニア術後の場合は,まずコアの安定を図り再発予防につなげる.現在,当院を拠点に関連病院と連携し,ピラティスによる運動療法を推進している.今後,ピラティスが腰痛患者の運動療法のゴールドスタンダードとなるべく,検討を重ねたい.
- 著者
- 長谷部 政治
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.2, pp.88-96, 2023-08-09 (Released:2023-08-30)
- 参考文献数
- 38
温帯地域では季節の移り変わりによって外部環境が劇的に変化する。このような四季が存在する地域の生物の多くは1日の日長変化から季節を読み取り,生理状態や行動を適切に調節している。体内で約24時間周期のリズムを刻む体内時計である概日時計が,この日長測定に重要な役割を果たしていると考えられている。一方で,情報処理の中枢である脳神経回路内で,概日時計に基づいた日長情報がどのような神経シグナルを介して伝達され,細胞レベルでどのような日長応答を起こしているのかは長年不明であった。著者らの研究グループは,明瞭な日長応答を示すカメムシなどの野外採集昆虫を用いて,細胞レベルでの生理学的解析とRNA干渉法による遺伝子発現操作解析を組み合わせることで,この概日時計に基づいた日長情報の神経処理機構の解明に取り組んできた。本稿ではまず,概日時計に基づいた日長測定機構のこれまでの研究の歴史について紹介する。続いて,近年著者らが生殖機能に明瞭な日長応答を示すホソヘリカメムシを用いて明らかにした,日長情報を伝達する神経シグナルとそれを受け取った生殖制御細胞での日長応答について紹介したい。
2 0 0 0 OA 実験的糖尿病発症ラットにおいてマイタケ投与が耐糖能および尿糖排泄に及ぼす効果について
- 著者
- 堀尾 拓之 大鶴 勝
- 出版者
- 公益社団法人 日本栄養・食糧学会
- 雑誌
- 日本栄養・食糧学会誌 (ISSN:02873516)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.4, pp.299-305, 1995-08-10 (Released:2010-02-22)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 4 4
The effects of Maitake (Grifola frondosa) on blood glucose level in rats with streptozotocin-induced diabetes were investigated. Diabetic rats were produced by injecting 80mg/kg streptozotocin (STZ) into 2-day-old neonates. From the age of 9 weeks, the rats were given Maitake as a dietary admixture at 20% food weight for 180 days. Diabetic rats showed obvious diabetic symptoms such as hyperglycemia, hyperphagia, polydipsia, polyuria and glucosuria. The diabetic levels of blood glucose, water consumption, urine volume and glucosuria were significantly decreased in the rats fed Maitake. From these results, it may be considered that the bioactive substances present in Grifola frondosa ameliorate the symptoms of diabetes.
2 0 0 0 OA 日本における夜間光と各種統計指標との相関関係
- 著者
- 大友 翔一
- 出版者
- 一般社団法人 地理情報システム学会
- 雑誌
- GIS-理論と応用 (ISSN:13405381)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.1, pp.23-28, 2021 (Released:2023-10-03)
- 参考文献数
- 11
In recent years, the application of satellites and big data to the economic field has been expanding rapidly. In particular, it has become clear that the intensity of night light acquired by satellites is correlated with social and economic indicators such as gross domestic product, employment, population, and education in each country. In this paper, I first describe the method of calculating the night light intensity in Japan by prefecture and city. Next, in order to understand the versatility of the night light data, I examine the relationship between the intensity of night light at the city level and various socio-economic indicators and data published by public sectors, using Japan as a case study. Based on the results of the various analyses, it is assumed that night light can be used as a proxy variable for these various indicators. Finally, I describe the possibility of using night light to perform a rapid analysis on the stagnation of economic activity under sudden social events, such as the COVID-19 pandemic.
2 0 0 0 OA 上古時代の帽に就て
- 著者
- 後藤 守一
- 出版者
- 一般社団法人 日本人類学会
- 雑誌
- 人類學雜誌 (ISSN:00035505)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.5, pp.230-251, 1940 (Released:2010-06-28)
- 著者
- 井村 行子
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.91, no.11, pp.1757, 1982-11-20 (Released:2017-11-29)
2 0 0 0 OA メタバースの利用による買い物を目的とした外出行動の変化に関する研究
- 著者
- 圖師 礼菜 森本 章倫
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.3, pp.1048-1055, 2023-10-25 (Released:2023-10-25)
- 参考文献数
- 13
近年のコロナウイルスの蔓延により,アバターを介した多人数参加型の仮想空間であるメタバースの利用への注目が高まっている.メタバースは,従来のオンラインサービスを複合した機能を有するほか,空間内での自由な行動を可能とし,サイバー空間上へ生活空間を拡大すると言える.本研究ではメタバースについての概念整理を行うことで,メタバース上への生活空間の拡大について検討したほか,都市計画へのメタバースの活用についても考察を行った.さらに,生活行動のひとつである買い物行動に着目したアンケート調査を実施し,メタバースの利用意向及び外出行動の変化意識についても把握した.以上より,メタバースは買い物を目的とした外出の代替となり,外出行動が減少する可能性を示唆した.
- 著者
- 奥村 彰久
- 出版者
- 公益社団法人 日本ビタミン学会
- 雑誌
- ビタミン (ISSN:0006386X)
- 巻号頁・発行日
- vol.93, no.7, pp.283-290, 2019-07-25 (Released:2020-07-31)
The Committee on Pediatric Nutrition of the Child Health Consortium of Japan investigated vitamin B1 deficiency caused by excessive consumption of ionic beverages. In the national survey, we obtained clinical data from 33 children. Twenty-one children had a problem with the nurturing home environment. The median duration of excessive ionic beverage intake was 3.5 months and the daily intake was 1,000 mL or more in 25 children. Infectious diseases were the most common reason for excessive ionic beverage consumption. The symptoms of vitamin B1 deficiency were nonspecific, and about half of the cases had neurological sequelae. The questionnaire survey of parents on their awareness of ionic beverages and their actual usage of ionic beverages for their young children showed to be generally good. Having a positive opinion about the benefits of ionic beverages was associated with the risk of their excessive consumption. The questionnaire survey of pediatric practitioners showed that pediatricians’ attitudes toward children’s consumption of ionic beverages were generally appropriate. Pediatric specialists showed more appropriate attitudes toward children’s consumption of ionic beverages than non-pediatric specialists. It will be important to notify the potential harm of excessive ionic beverage consumption to prevent the occurrence of new cases.
2 0 0 0 OA チアミンとプリオンタンパク質
- 著者
- 山元 誉子 廣村 信 田鶴谷(村山) 恵子
- 出版者
- 公益社団法人 日本ビタミン学会
- 雑誌
- ビタミン (ISSN:0006386X)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, no.12, pp.616-618, 2014-12-25 (Released:2017-08-10)
- 著者
- 今井 敦
- 出版者
- 日本独文学会
- 雑誌
- ドイツ文学 (ISSN:24331511)
- 巻号頁・発行日
- vol.164, pp.73-90, 2022 (Released:2023-08-06)
Die vorliegende Arbeit verfolgt das Vorhaben, die Technikkritik des Schriftstellers Friedrich Georg Jünger (1898-1977) aus der heutigen Sicht zu beleuchten und seinen Stellenwert in der kultur- und technikkritischen Strömung des 20. Jahrhunderts zu bestimmen. Zu diesem Zweck befasst sie sich mit seiner Schrift: »Die Perfektion der Technik«, deren erster Teil erstmals 1946 und deren zweiter Teil, ursprünglich unter dem Titel »Maschine und Eigentum« als selbständiger Band, 1949 erschien. Nachgegangen wird den folgenden Fragen: erstens, in welcher Hinsicht Jüngers Technikkritik als Vorwegnahme von Ideen der heutigen Ökologiebewegung anzusehen ist und was sie von Ansichten der ihm vorausgehenden Kultur- und Technikkritiker unterscheidet, zweitens, wer bzw. was das Subjekt des ‚Willens zur Macht‘ ist, als dessen Manifestation er die Technik auslegt, und drittens, welche Art von Ausweg aus der Krise bzw. Umkehr er voraussieht. Friedrich Georg Jünger sieht in der neuzeitlichen Technik einen Automatismus, der an Natur und Mensch grenzenlosen „Raubbau“ treibt und in planetarischer Hinsicht zur Verlustwirtschaft führt. Alle Gegenstände, den Menschen eingeschlossen, werden als Bestände des Nutzbaren aufgefasst, durch Normierung und Standardisierung als Menge des Gleichen ausgerechnet, mobilisiert, bearbeitet und zum Verbrauch geliefert. Der technische Fortschritt verändert nicht nur Natur und Mensch, sondern verwandelt die Gesellschaftsformen in eine maschinenentsprechende, d. h. „das technische Kollektiv“. In der letzten Phase der Perfektionierung schließen sich all die Kollektive zum „Universalarbeitsplan“ zusammen, der somit an die Weltherrschaft gelangt. Jünger zufolge ist die neuzeitliche Technik kein neutrales Werkzeug, sondern an sich der ‚Wille zur Macht‘, dessen mechanischer Automatismus, zwar vom Menschen in Bewegung gesetzt, aber längst nicht mehr gestoppt oder gelenkt werden kann. Die Vollendung der technischen Herrschaft veranlasst aber den Regress der unterdrückten Natur, der sich möglicherweise als folgenschwerer Betriebsunfall offenbart. Auf jeden Fall ergibt sich eine globale Verarmung, die auch vernichtende Weltkriege herbeiführen kann. (View PDF for the rest of the abstract.)
2 0 0 0 OA mRNAワクチン,医薬を支える基盤技術と今後の展望
- 著者
- 内田 智士
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 化学と教育 (ISSN:03862151)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.1, pp.12-15, 2023-01-20 (Released:2024-01-01)
- 参考文献数
- 5
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対してメッセンジャーRNA(mRNA)ワクチンが実用化された背景には,mRNAの設計や送達に関する長年の多岐にわたる技術開発があった。本稿では,mRNAの化学修飾や脂質性ナノ粒子を中心に基盤技術を説明したのち,mRNAワクチン,医薬の課題と今後の展望に触れる。
2 0 0 0 OA 19世紀初頭 の石炭産業における原価会計 ―イギリス北東地域の記録をもとに―
- 出版者
- 日本経営会計学会
- 雑誌
- 経営会計研究 (ISSN:13490419)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.45-58, 2020 (Released:2024-01-10)