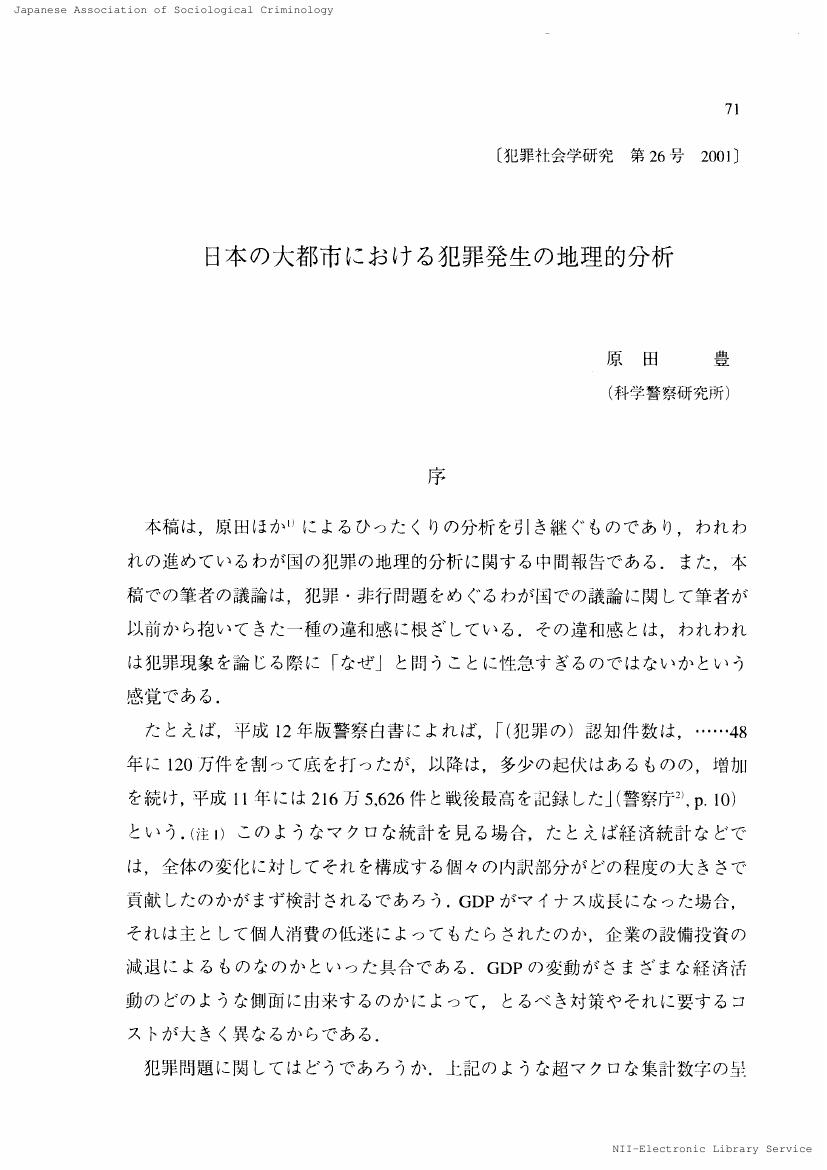- 著者
- 木村 學 鵜沢 潔 成瀬 央 島田 明佳 影山 和郎 村山 英晶 高橋 太郎
- 出版者
- JAPAN SOCIETY FOR COMPOSITE MATERIALS
- 雑誌
- 日本複合材料学会誌 = Journal of the Japan Society for Composite Materials (ISSN:03852563)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.2, pp.129-134, 2001-03-15
1 0 0 0 IR 知恩院「韋駄天立像」の見た正月二日
- 著者
- 山西 泰生
- 出版者
- 佛教大学
- 雑誌
- 佛教大学宗教文化ミュージアム研究紀要 (ISSN:13498444)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.59-69, 2009-03-30
1 0 0 0 構造可変型ビデオレート画像処理システム『韋駄天』
- 著者
- 佐々木 繁 佐藤 龍哉 岩瀬 洋道 後藤 敏行
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告コンピュータビジョンとイメージメディア(CVIM)
- 巻号頁・発行日
- vol.1985, no.26, pp.1-8, 1985-07-18
We developed a high-speed image processing system called IDATEN which can continuously process time-varying images at video speed. The basic design concept was the improvement of overall performance of the image processor system by adopting a new architecture. This paper proposes a "variable- structure pipeline" architecture which uses a network to allow communication among any of the processing modules. We expanded the Benes multi-stage switching network to produce a flexible high-speed pipeline processor. The experiments show the ease of programming and the effectiveness of this system.We developed a high-speed image processing system called IDATEN, which can continuously process time-varying images at video speed. The basic design concept was the improvement of overall performance of the image processor system by adopting a new architecture. This paper proposes a "variable- structure pipeline" architecture, which uses a network to allow communication among any of the processing modules. We expanded the Benes multi-stage switching network to produce a flexible, high-speed pipeline processor. The experiments show the ease of programming and the effectiveness of this system.
1 0 0 0 OA 東京オリンピック・メインスタジアムへの観戦客に対する新宿御苑を活用した動線計画
- 著者
- 渡部 大輔 鳥海 重喜 田口 東
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.3, pp.1341-1348, 2017-10-25 (Released:2017-10-25)
- 参考文献数
- 15
本研究では,東京オリンピック・メインスタジアムへの観戦客の入場に際し,新宿御苑を活用した動線計画の提案を行い,時間拡大ネットワークに基づいた徒歩流動モデルにより計画の妥当性について評価した.まず,既存研究や先行事例から動線計画と入場管理の調査を行った.そして,徒歩流動モデルとして,新宿駅の各路線のホームから御苑を経由し,メイン会場までの平面ネットワークを設定し,所要時間と待機時間をコストとして表現した時間拡大ネットワークを構築した上で,容量制約付き最小費用流問題により観戦客の配分を行うモデルを構築した.そして,本モデルにより,駅構内や御苑内に滞留する人数を把握することで,セキュリティチェックのゲート数やゲート通過時間等の影響を分析し,御苑内のセキュリティチェックに必要な設備や面積の検討を行った.その結果,今回想定した観戦客の移動需要(約25,000人)と条件設定に対して,円滑な入場を行うために必要なゲートの数と面積を見積もることができた.
1 0 0 0 IR 刑事裁判の公開原則と被告人のプライバシーの権利(1)
- 著者
- 笹倉 香奈
- 出版者
- 一橋大学
- 雑誌
- 一橋法学 (ISSN:13470388)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.1, pp.295-324, 2007-03
- 著者
- 鈴木 秀美
- 出版者
- 慶応義塾大学法学研究会 ; 1922-
- 雑誌
- 法学研究 = Journal of law, politics and sociology (ISSN:03890538)
- 巻号頁・発行日
- vol.91, no.1, pp.71-95, 2018-01
1 0 0 0 OA セラミック外論 (12)
- 著者
- 素木 洋一
- 出版者
- 公益社団法人 日本セラミックス協会
- 雑誌
- 窯業協會誌 (ISSN:00090255)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.785, pp.C167-C178, 1961-05-01 (Released:2010-04-30)
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 煙中の見透し距離について (I)
- 著者
- 神 忠久
- 出版者
- Japan Association for Fire Science and Engineering
- 雑誌
- 日本火災学会論文集 (ISSN:05460794)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.2, pp.1-8, 1970 (Released:2013-06-18)
- 被引用文献数
- 1
A smoke chamber is designed to perform the measurement of visibility through fire smoke (see Fig.3). The chamber is provided with an illumination apparatus and two kinds of sign. One of the signs is the placard and the other is the lighted sign which is backlighted with a projector. The brightness of the lighted sign can be controlled freely, and that of the placard can be set in four stages. Nearly white smoke is generated by heating filter-paper in an electric furnace.Experiments were performed to get the relation among the brightness of sign, the visual distance, and the extinction coefficient of smoke in the instant of obscuration threshold. In this case the distances the between observer and the object were 5.5 m, 10.5 m, and 15.5 m.The extinction coefficient (σ) in the instant of obscuration threshold may be theoretically given byσ≒1/V ln BE0/δckL ………(1)where V ; Visual distanceBE0 ; Brightness of signδc ; Threshold of brightness-contrast (δc≒0.01 under the condition of general illumination)L ; Intensity of external light (Illumination)k=σs/σ (Ratio depending on the nature of smoke, k≒1 for nearly white smoke)σs ; Mean light-scattering coefficientFrom Eq. (1), the extinction coefficient in the instant of obscuration threshold is logarithmically proportional to the brightness of sign for a given smoke (nearly white smoke), a given intensity of external light, and a given visual distance. If the dimensionless brightness (BE0/L) is constant, the relation between σ and V is given byσ · V ≒ const.The results of experiment are shown in Fig.4~Fig.12 The agreement between the results and the theoretical values calculated from Eq. (1) concerning the brightness of sign is good as shown in Fig.11. The visibility of the placard is about (2~4)/σ and that of the lighted sign is about (5~10)/σ.In the case of escape through real fire smoke, the visibility should be lower than that of experiment, because the effects of physiology and psychology must be considered.
1 0 0 0 OA 正義の内部観測
- 著者
- 花野 裕康 Hanano Hiroyasu
- 出版者
- 福岡大学研究推進部
- 雑誌
- 福岡大学人文論叢 = Fukuoka University Review of Literature & Humanities (ISSN:02852764)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.1, pp.55-83, 2012-06
- 著者
- 藤井 郁雄 阿部 昌之 早川 謙二 兼松 顕
- 出版者
- The Pharmaceutical Society of Japan
- 雑誌
- Chemical and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:00092363)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.11, pp.4670-4673, 1984-11-25 (Released:2008-03-31)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 2 4
3, 4-Dimethoxy trans-6-morphinanone (1) and its cis isomer (2) were prepared stereoselectively from thebaine (3) and dihydrocodeinone (9), respectively. A general way of spectrally differentiating between these two stereoisomers is discussed.
1 0 0 0 OA ツツまれる音 - 「言挙げせぬ国」における逆説の美学をめぐって -
- 著者
- 木村 直弘 KIMURA Naohiro
- 出版者
- 岩手大学教育学部
- 雑誌
- 岩手大学教育学部研究年報 (ISSN:03677370)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, pp.81-106, 2009-02-28
日韓文化の比較研究で知られる李御寧イオリョンは、日本語について次のように指摘している。 ごく日常的な言葉でも、日本語を習う時にいつも苦労するのは、日本語はあまりに厚化粧していて素顔の意味が隠されていることだ。要するに、言葉の表と裏のズレである。激しい場合には、言葉自体の意味とそれが示していることが、まるっきり反対のことがあるからである(1)。 韓国語ではなるべく事実を「包み」込まないで伝えようとするのに対し、日本語の場合、物事を示すというよりはそれを「包む」といった感覚が強いと主張する李は、この相違の由来を日本における「包み文化」と「奥の美学」に措定する。「隠すことによってその特性をあらわす」前者は必ずしも日本の専売特許ではなくアジア一般に見られる特徴でもあるが、特に日本の場合、それは「形式論理では割り切れないパラドックスを生かした文化(2)」として特徴づけられる。「包む」ことによって「奥」を創出する後者も同様であり、「包むことによって、奥に隠すことによって、そして逆に心が表にあらわれるパラドックス(3)」の上に成り立っている。そして、それは「日本人らしさ」の要因のようにみなされている「慎ましさ」(「包む」=「慎む」)や「奥床しさ」が根差す文化的基底と言いうる。 前稿(4)では、喪葬という霊魂にかかわる両義的時空間に介在する哭声とその騒音性に着目し、そこに付された儀礼的機能の変遷に焦点をあてて論じたが、「つつみ隠す」という国風文化的心性と古代以来の「言霊思想」や、竹筒に通ずる「つつむ」構造を持った鼓つづみについての考察を割愛せざるをえなかった。そこで、この小論では前稿を補足するものとして、慎つつむ=「包む」というすぐれて日本的な表現方法について、楽器の象徴論や、「ツツミ」に関連する「ウツ」「コト」といった言葉の意味論、そしてそこに看取できる境界的な可逆性、往還性といった視座から光をあてることを目的としている。
1 0 0 0 IR 西洋中世における個人(人格)の成立に関する予備的考察
- 著者
- 阿部 謹也
- 出版者
- 一橋大学
- 雑誌
- Study series
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.1-36, 1990-03-31
1 0 0 0 OA 三世の光
- 著者
- [皓月比丘尼] [著]
- 巻号頁・発行日
- vol.巻の3, 1830
- 著者
- 原田 豊
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.71-92, 2001 (Released:2017-03-30)
1 0 0 0 固定資産評価基準解説
- 著者
- 自治省固定資産税課編
- 出版者
- 地方財務協会
- 巻号頁・発行日
- 1983
1 0 0 0 固定資産評価基準解説
- 著者
- 自治省固定資産税課編
- 出版者
- 地方財務協会
- 巻号頁・発行日
- 1981