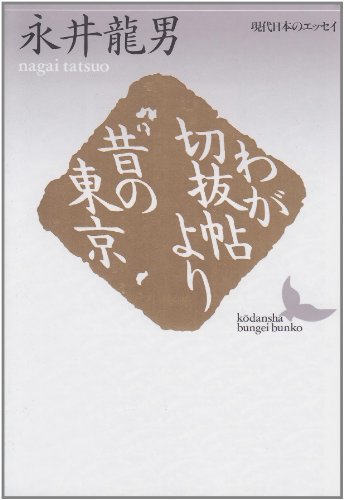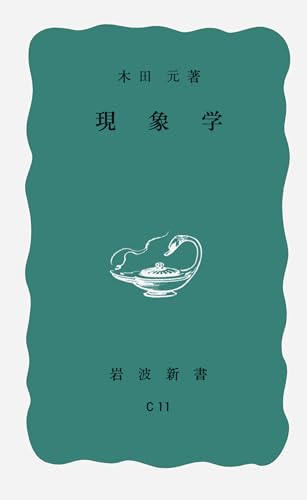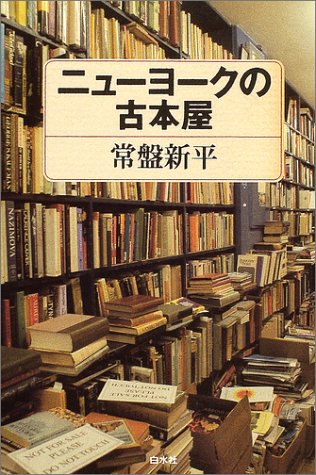1 0 0 0 OA 社会的課題解決に向けた「知の統合」推進の「場」の構築
- 著者
- 原 辰次
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.12, pp.12_18-12_22, 2017-12-01 (Released:2018-05-09)
- 参考文献数
- 6
1 0 0 0 IR 空海の言語哲学
- 著者
- 高橋 隆 Takashi Takahashi 平安女学院短期大学英文科
- 雑誌
- 平安女学院短期大学紀要 = Bulletin of Heian Jogakuin (St.Agnes') College (ISSN:02870878)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.35-45, 1986
1 0 0 0 OA 一億民の書 : 新体制必携
1 0 0 0 OA 科学技術の状況に係る総合的意識調査(NISTEP定点調査2017)報告書
- 著者
- 文部科学省 科学技術・学術政策研究所 科学技術・学術基盤調査研究室
- 出版者
- 科学技術・学術政策研究所
- 巻号頁・発行日
- 2018-04 (Released:2018-04-02)
1 0 0 0 わが切抜帖より ; 昔の東京
1 0 0 0 歩行連動画像と後退背景画像の相対速度を用いた移動広告の提案
- 著者
- 鼻崎 将 古森 光 吉田 直人 米澤 朋子
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 研究報告ヒューマンコンピュータインタラクション(HCI) (ISSN:13426893)
- 巻号頁・発行日
- vol.2015, no.4, pp.1-4, 2015-01-07
- 被引用文献数
- 1
本稿では,壁面へのプロジェクションを用いて,ユーザの歩行状態を判定したうえで,その前方に提示され続ける移動広告システムを提案する.また,背景との相対速度による浮き彫り効果を考慮し,背景画像をユーザの進行方向と逆方向に進めることとした.このことで,広告をより目立たせ,さらに広告の世界観とスピード感を与えることを狙う.このシステムを用いることで,広告への注意をひきつけ,さらに,ユーザの歩行速度変化や方向転換に応じた広告提示位置の内容の変容など,広告とのインタラクションに多様性をもたらすことが期待される.
1 0 0 0 IR ポーの女性像とその女性観を探る (1)
- 出版者
- 田園調布学園大学
- 雑誌
- 紀要 (ISSN:02875268)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.93-122, 1997-03-20
1 0 0 0 公害の政治学 : 水俣病を追って
1 0 0 0 IR 幕末・明治期の船舶用蒸気機関運用技術について
- 著者
- 坂本 卓也
- 出版者
- 佛教大学大学院
- 雑誌
- 佛教大学大学院紀要. 文学研究科篇 (ISSN:18833985)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, pp.55-71, 2018-03-01
幕末期以降日本に導入された蒸気船について、その心臓部である蒸気機関の運転と修理・建造技術の国内化過程の検討を行った。分析の時期は幕末から明治期とし、国内における技術導入の牽引役となった幕府海軍と日本海軍を主な分析対象とした。幕末期の運転技術について、長崎海軍伝習所や軍艦操練所などで技術伝習が行われるが、実地訓練の不足などにより、その技術には大きな不安を抱えたままであった。また修理・建造技術についても、長崎と横浜の両製鉄所において外国人の技術伝習が行われるが、彼らの指導下から脱することはできなかった。明治期以降には、イギリス海軍機関士の体系的な教育や遠洋航海により運転技術の向上が見られ、明治二〇年(一八八七)には国内化を達成している。修理・建造技術についても横須賀造船所におけるフランス人技術者による指導や、留学生の派遣による技術向上により、明治四〇年頃までには国内化を達成している。幕末明治蒸気船蒸気機関運用
1 0 0 0 ニューヨークの古本屋
1 0 0 0 花岡事件の人たち : 中国人強制連行の記録
1 0 0 0 中国冷凍野菜の取り組み経緯について(読物企画)
- 著者
- 伊東 敏行
- 出版者
- 日本農薬学会
- 雑誌
- Journal of pesticide science (ISSN:1348589X)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.1, pp.66-72, 2010
- 被引用文献数
- 1
日本冷凍食品協会によれば、2008年の冷凍食品生産額は国内生産量約6600億円、海外輸入を合わせると約9000億円を超える規模となっている。2008年における日本の冷凍食品消費量は約250万トンであり、そして国民一人当たりの消費量は現在約19.4kgである。これが、現在の日本における冷凍食品の実態である。この中で、味の素冷凍食品株式会社(以下、当社)は、主な業務としてギョーザやシュウマイなどを代表とする冷凍食品の製造・販売を行っており、年間約1100億円の販売規模に達している。その生産拠点は国内9工場、海外8工場の合計17工場になる。一方、現在日本における食料自給率はカロリーベースで40%であり、そのため海外からの食料輸入に依存せざるを得ない状況にあることは周知のとおりである。冷凍食品においても図1のとおり、その輸入量(冷凍野菜輸入量+調理冷凍食品輸入量)は、約100万トンであり、われわれ冷凍食品を製造するメーカーにとっても国産のみならず海外に原料を求めまた製品生産を検討し、それに依存していかなければならない現状にある。その輸入食材は、検疫を通過後国内に流通するが、検疫では食品のリスクを想定し、残留農薬等色々な検査が行われているが、さらに国内のお客様から安心・安全の信頼を得るためには輸入食材の残留農薬に対する各企業の対応は避けて通れない状況にある。ここでは、当社における取り組みを中心に、中国冷凍野菜の製造行程における残留農薬に対する対応状況について紹介する。
1 0 0 0 OA 線引き制度運用からみた地方都市の商業施設立地動向
- 著者
- 小林 剛士 鵤 心治 石村 壽浩
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.626, pp.811-818, 2008-04-30 (Released:2008-08-20)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 1
The purpose of this paper is to clarify the relation for commercial act between the Non-Area Divided City Yamaguchi and the Area Divided City Hofu, which is adjacent to Yamaguchi. At first, we investigated the trend of commercial locate among three area, central district, use district and suburb using data of the building confirmation in those city. Then we calculated the rate of consumption and absorption about commercial act in case study. At last, using those data, we considerate the relation for commercial act between the each case study and show the issue about the district that commercial facilities has accumulated on operating the City Planning Act in local city.
1 0 0 0 官能評価による市販加工肉シュウマイの品質特性の比較
- 著者
- 吉田 順子 添田 博 菊池 英夫 神山 かおる 早川 文代
- 出版者
- 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品科学工学会誌 : Nippon shokuhin kagaku kogaku kaishi = Journal of the Japanese Society for Food Science and Technology (ISSN:1341027X)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.2, pp.85-94, 2009-02-15
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1
シュウマイの中でも最も生産量の多い肉シュウマイに焦点を当て,8種類の肉シュウマイの評価用語および評価方法を設定し,各試料の官能特性を明らかにした.その結果,以下の結果を得た.<BR>(1) 分析型パネルによる評価用語収集により135語が得られた.専門家パネル4人によって用語を整理し,第一次用語リスト61語を作成した.<BR>(2) 第一次用語リストについて,パネリスト全員に5段階のカテゴリー尺度を用いて試料を評価させた.クラスター分析の結果,61語は20のクラスターに分類された.クラスター分析結果について専門家パネルによる討議を行い,最終的にシュウマイの評価用語を選定し,19語を決定した.<BR>(3) 分散分析の結果,19用語中18語に試料間の有意差が見られた.ジューシー感が強いと,油っぽさが強い傾向がみられたが,一部例外もみられた.有意差のある評価項目間の相関係数の数は,肉の味が最も多かった.肉の味は,肉のくさみ,肉粒の大きさ,弾力感と正の相関があった.従って,肉の味の強さは,様々な評価項目と相関性が高く,肉シュウマイの評価では中核的な項目であることが推察された.<BR>(4) データを一元的に把握するために主成分分析を行った.その結果,第5軸までが意味のある主成分として抽出された.第1軸は「肉の存在感」,第2軸は「味付けの濃さ」,第3軸は「肉汁の量」と解釈した.試料の主成分得点と評価項目の因子負荷量を用いて散布図を作成したところ,それぞれの試料の特徴を読み取ることのできる肉シュウマイの官能特性マッピングを得た.<BR>(5) 8試料以外の肉シュウマイでも,得られた評価方法が適用できるのか否かを検討するために,新たに7種類の肉シュウマイの評価を行なったところ,同様の傾向がみられ,広範囲の肉シュウマイの品質特性を客観的に把握できることがわかった.
- 著者
- Kuniko YOSHIMURA Aya MATSUU Kai SASAKI Yasuyuki MOMOI
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- pp.17-0499, (Released:2018-05-11)
- 被引用文献数
- 2
Sirtuin-1 (SIRT1) is a nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+)-dependent histone deacetylase with a large number of protein substrates. It has attracted a lot of attention in association with extending lifespan. The objective of this study was to enable the evaluation of SIRT1 expression in peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) from dogs by flow cytometry. Three transcript variants were amplified from PBMCs by reverse transcription PCR and the nucleotide sequences were analyzed. On the basis deduced amino acid sequence, a monoclonal antibody against human SIRT1, 1F3, was selected to detect canine SIRT1. Canine SIRT1 in peripheral blood mononuclear cells was successfully detected by western blotting using this antibody. Intracellular canine SIRT1 was also detected in permeabilized 293T cells transfected with a canine SIRT1 expression plasmid by flow cytometry using this antibody. SIRT1 was detected in all leukocyte subsets including lymphocytes, granulocytes and monocytes. The expression level was markedly different among individual dogs. These results indicated that the method applied in this study is useful for evaluating canine SIRT1 levels in PBMCs from dogs.
- 著者
- Keishi Moriwaki Tetsushiro Takeuchi Naoki Fujimoto Toshiki Sawai Yuichi Sato Naoto Kumagai Jun Masuda Shiro Nakamori Masaki Ishida Norikazu Yamada Mashio Nakamura Hajime Sakuma Masaaki Ito Kaoru Dohi
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- pp.CJ-18-0083, (Released:2018-05-12)
- 参考文献数
- 36
- 被引用文献数
- 5
Background:The present study was conducted to assess the cardiovascular effects of dipeptidyl peptidase-4 inhibitors (DPP4i) on coronary flow reserve (CFR), left ventricular (LV) function and endothelial function of the peripheral artery by comparison with those of α-glucosidase inhibitors (αGI) in patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM) and coronary artery disease (CAD).Methods and Results:We randomly assigned 30 patients with T2DM and CAD to receive either sitagliptin or voglibose, and 28 patients (age 69±9 years, 75% male, hemoglobin A1c [HbA1c] 6.62±0.48%) completed the study (14 in each group). CFR and LV function, assessed by cardiac magnetic resonance imaging, and endothelial function, assessed by reactive hyperemia peripheral arterial tonometry (RH-PAT), were measured at baseline and 24 weeks after treatment. Clinical and laboratory parameters, including HbA1c level, plasma active glucagon-like peptide-1 concentrations, and biomarkers of inflammation, were unchanged in both groups after 24 weeks of treatment. CFR were unchanged in both the αGI group (3.01±0.98 at baseline and 3.06±0.8 after treatment, P=NS) and the DPP4i group (4.29±2.04 at baseline and 3.63±1.31 after treatment, P=NS), with no interaction effect. LV functional parameters and the reactive hyperemia index also remained unchanged after the 24-week treatment.Conclusions:DPP4i did not improve CFR, LV function or endothelial function of the peripheral artery in patients with relatively well-controlled T2DM and CAD.
1 0 0 0 OA 関東平野における樹木衰退の1999年~2001年の状況
- 著者
- 松本 陽介 小池 信哉 河原崎 里子 上村 章 原山 尚徳 伊藤 江利子 吉永 秀一郎 大貫 靖浩 志知 幸治 奥田 史郎 石田 厚 垰田 宏
- 出版者
- 森林立地学会
- 雑誌
- 森林立地 (ISSN:03888673)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.2, pp.53-62, 2002-12-25 (Released:2017-04-03)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 1
関東地方の丘陵部を含む平野部全域を対象として,スギなどの樹木について衰退の現況を,目視による樹木衰退度判定法によって調査した。その結果,スギの衰退が最も顕著であり,ヒノキなどの常緑針葉樹類,イチョウ,ケヤキなどにも衰退が認められた。いっぽう,メタセコイアおよびヒマラヤスギでは衰退個体がほとんど見いだせなかった。スギの衰退は,関東平野のほぼ全域で認められ,関東平野の北西部に位置する前橋市周辺や熊谷市周辺,および久喜市周辺,これらに隣接する群馬県下および埼玉県下の利根川沿いの地域で特に著しかった。次いで,水戸市北方の那珂川や久慈川沿いの地域,および銚子市周辺の太平洋に面した地域で衰退度が高く,千葉市周辺および町田市周辺でも比較的衰退度が高かった。