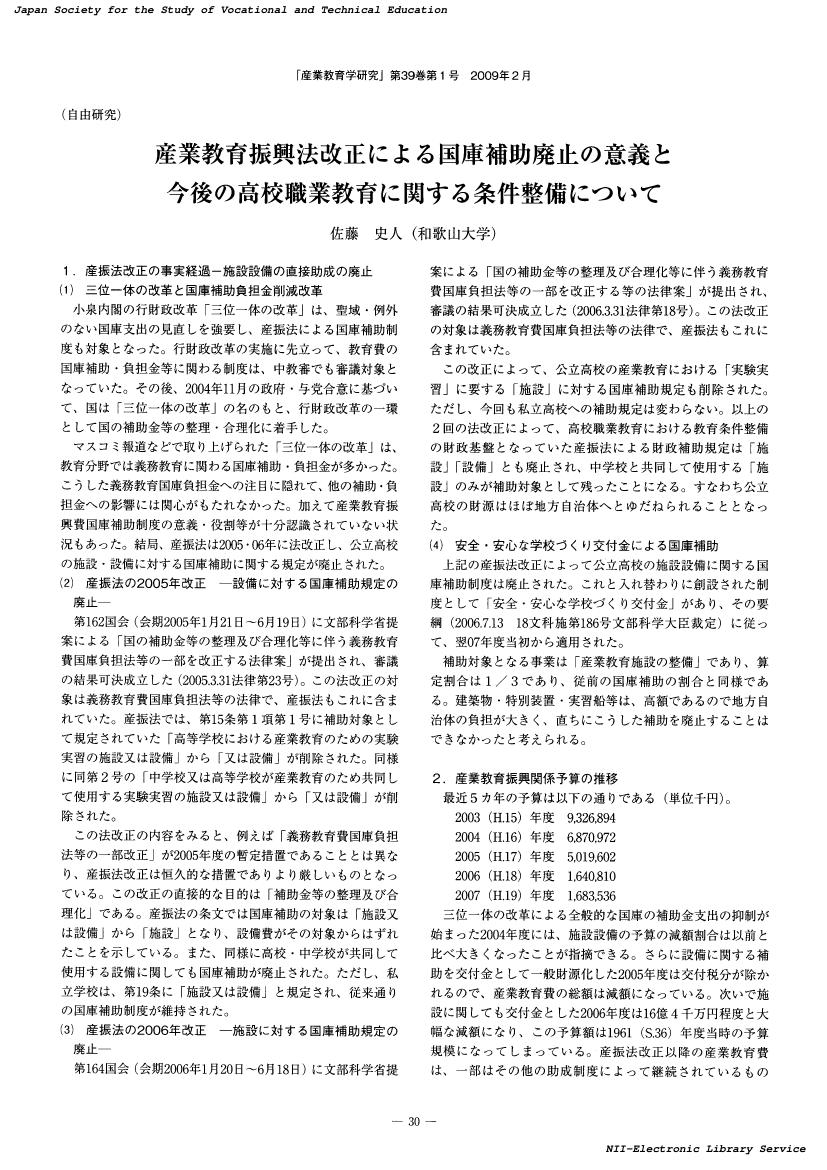- 著者
- 見平 典
- 出版者
- 有斐閣
- 雑誌
- 法社会学 (ISSN:04376161)
- 巻号頁・発行日
- no.83, pp.99-109, 2017
1 0 0 0 0音 : 新国誠一詩集
1 0 0 0 IR 発達障害者の障害受容の心理社会的プロセスに関する調査研究
- 著者
- 中村 恵子 Nakamura Keiko
- 出版者
- 新潟青陵学会
- 雑誌
- 新潟青陵学会誌 (ISSN:1883759X)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.1, pp.21-31, 2017-03
The purpose of this study is to clarify the psychosocial process of disability acceptance of the people with development disabilities who are going to employment transfer support offices. A semi-structured interview was conducted with 8 people with development disabilities who were diagnosed withdevelopment disabilities and were going to employment transfer support offices. As the result of analyzing the result of the interview with a modified grounded theory approach, 5 categories and 12 concepts were extracted. The people with development disabilities who were in troubles like dropout, disemployment, and depression, etc, <searched for supporting organizations> <because they wanted to get out of their current situations>, and eventually started going to the offices. They are deepening the ≪recognition of the development disabilities≫by checking the disability characteristics and behavior characteristics,reinterpreting their experiences like troubles in working and human relationships, and finding similarities with familiar people with disabilities. The ≪recognition of the development disability≫ that is a corecategory also has impacts on the <appropriate self-control> and the <self-metacognition>.本研究は、就労移行支援事業所に通所する発達障害者の障害受容の心理社会的プロセスを明らかにすることを目的とした。発達障害の診断を受け、就労移行支援事業所に通所する発達障害者8名を対象として、半構造化面接を行った。修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチを用いて面接内容を分析した結果、5つのカテゴリーと12の概念が抽出された。 中退や離職、鬱病といった状況に陥った発達障害者が<このままではいけないという思い>から<支援機関探し>を行った結果、事業所に通所するに至っている。障害特性と行動特性を照合したり、仕事や人間関係上のトラブルなどの経験を再解釈したり、障害をもつ身近な人と自分の似ているところを見つけたりして、≪発達障害であることの認識≫を深めている。コアカテゴリーである≪発達障害であることの認識≫は、<適切な自己コントロール>や<自分についてのメタ認識>にも影響を与えている。
1 0 0 0 IR 内部重力波の基本特性と砕波機構に関する基礎的研究
- 著者
- 谷 晋
- 出版者
- 東海大学
- 雑誌
- 東海大学文明研究所紀要 (ISSN:02850818)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.145-153, 1998
Acorns of the two deciduous oaks, Querucus serrata and Q. acutissima, were collected from four secondaty forests in Kanagawa in late autumn, 1994. Curculio dentipes was dominant over C. robustus in acorn of Q. acutissima, and utilized acorn of Querucus serrata monopolistically. Differences in utilization of acorn as food resources were discussed. Parasitic rate decreased at good harvest. It suggested that mast seeding of the oaks functioned effectively as the escape from Curculio beetles.
1 0 0 0 OA 予感に満ちた城 -E.T.A.ホフマンの「世襲領」における城と幽霊の描写について-
- 著者
- 亀井 伸治
- 出版者
- 早稲田大学大学院文学研究科
- 雑誌
- 早稲田大学大学院文学研究科紀要. 第2分冊, 英文学フランス文学ドイツ文学ロシヤ文学中国文学 (ISSN:13417525)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, pp.101-111, 2000
1 0 0 0 OA 3Dプリンティング技術のものづくりへの活用方法~積層造形の基礎と応用~
- 著者
- 安齋 正博
- 出版者
- 一般社団法人 日本ゴム協会
- 雑誌
- 日本ゴム協会誌 (ISSN:0029022X)
- 巻号頁・発行日
- vol.87, no.9, pp.376-381, 2014 (Released:2015-03-20)
- 参考文献数
- 9
Recently, the degree of attention of 3D printer increases and its use has been spreading. 3D printers taken up here are as follows; stereo lithography, selective laser sintering, ink jet printing, fused deposition molding, and laminated object manufacturing. Can 3D printer change Japan’s manufacturing industry? It is described about the foundation and application whether it is fit for what kind of use. The examples of the application is raised in the following; produce (rapid manufacturing, on-demand parts, inspection), create (model, capture, sculpt), measure (precision metrology, inspection reporting, 3D documentation), prototyping (design verification, functional validation), and others.
- 著者
- 有田 郁夫
- 出版者
- 裳華房
- 雑誌
- 遺伝 (ISSN:03870022)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.9, pp.p41-45, 1985-09
- 著者
- 佐藤 史人
- 出版者
- 日本産業教育学会
- 雑誌
- 産業教育学研究 (ISSN:13405926)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.1, pp.30-31, 2009-02-25 (Released:2017-07-18)
- 著者
- 佐藤 史人 坂口 謙一 佐々木 享
- 出版者
- 和歌山大学
- 雑誌
- 和歌山大学教育学部教育実践総合センター紀要 (ISSN:13468421)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.101-110, 2007
1 0 0 0 IR 都市部の生活保護率に影響を与える要因について(芸術・保健体育・家政・技術科学編)
- 著者
- 関根 美貴
- 出版者
- 愛知教育大学
- 雑誌
- 愛知教育大学研究報告. 芸術・保健体育・家政・技術科学・創作編 (ISSN:13461818)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, pp.63-68, 2007-03-01
1 0 0 0 OA NEWSの適応と手技
- 著者
- 後藤 修 竹内 裕也 北川 雄光 矢作 直久
- 出版者
- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会
- 雑誌
- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.8, pp.1632-1640, 2015 (Released:2015-08-29)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1
内視鏡と腹腔鏡を用いて胃を開放させずに任意の部位を過不足ない範囲で全層切除する非穿孔式内視鏡的胃壁内反切除術(non-exposed endoscopic wall-inversion surgery:NEWS)について概説した.腹腔内汚染や医原性腹膜播種の可能性を理論的に払拭できる本法は,経口的に回収できる腔内もしくは壁内発育型胃粘膜下腫瘍や,リンパ節転移陰性が期待できるが内視鏡治療が技術的に困難な早期胃癌が良い適応となる.さらに,本術式をセンチネルリンパ節ナビゲーション手術と融合させることで,リンパ節転移の可能性が否定できない早期胃癌に対してもより低侵襲な胃機能温存手術を提供することができる.正確な漿膜マーキング,腹腔鏡下漿膜筋層切開・縫合,内反した病変周囲の粘膜切開,縫合糸近傍の粘膜下層切開など,技術的にも新規性に富む過程が満載されている.解決すべき課題は多いが,本法は内視鏡を用いたより理想的な胃癌低侵襲手術の一つとして期待が寄せられている.
1 0 0 0 台籍元日本海軍陸戦隊軍人軍属いずこに
1 0 0 0 2足歩行安定性を向上する足裏実装型非接触センサの開発
- 著者
- 有田 輝 米田 将允 鈴木 陽介 下条 誠 明 愛国
- 出版者
- 一般社団法人 日本ロボット学会
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.9, pp.669-680, 2017 (Released:2017-12-15)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 1
For bipedal robots walking on uneven terrain, lack of information about a terrain may cause serious reduction of the stability. To solve the problem, the purpose of this paper is to develop a sensor which can be mounted on robot's soles and propose methods which can increase the stability of bipedal walk with the sensor. The sensor should detect information including relative posture and relative distance between the sole of the swing leg and the floor, when the robot execute the walk by ZMP-based control. In this paper, the sensor has been designed based on Net-Structure Proximity Sensor (NSPS) and a prototype has been developed. The developed sensor is with thin structure, light weight, less wirings (four wires only) and fast response (<1[ms]). Experimental results show that the sensor can output necessary relative posture and positon between the sole and the floor for walk control. Besides, the sensor has been mounted to the soles of a hobby robot and its feasibility is shown by controlling robot so that its sole can land on a tilted floor with maximum contacting area to improve the stability.
1 0 0 0 OA 〈論文〉シモーヌ・ヴェイユにおける問題としての実在 : 『重力と恩寵』を中心に
- 著者
- 浅井 聡
- 出版者
- 筑波大学人文社会科学研究科現代語・現代文化専攻
- 雑誌
- 論叢 現代語・現代文化 (ISSN:18830358)
- 巻号頁・発行日
- no.16, pp.51-77, 2016-03-31
- 著者
- Katsuyuki V. Ooyama
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- Journal of the Meteorological Society of Japan. Ser. II (ISSN:00261165)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.1, pp.369-380, 1982 (Released:2007-10-19)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 48 225
航空機観測の進歩に伴ない,台風の一般構造およびエネルギー収支については,1960年代の初めごろまでに.かなりよくわかってきた。しかし,これらの知識を力学的に統一して台風の生成発達を説明する理論は容易に生れなかった。現在の台風理解の因となった最初の発達理論が出るためには,力学的問題としての台風の認識,特に種々の要因の相対的重要度,を再考する必要があった。雲のパラメータ化が成功の原因のように云われるが,実は,問題認識上の変化がそのような雲の扱いを一応許されるものとした。雲のパラメータ化を技術的にのみ応用すると,その後の種々の線型理論(いわゆるCISK)に見られるような物理的混乱を引きおこす。一方,台風の理解のためには,線型理論は不充分であり,理論の概念としての妥当性および限度は非線型数値モデルによる実験によってのみ評価されることとなった。数値モデルの進歩により,台風成生の理解のためには,雲のパラメータ化を取り除く必要があることもわかってきた。この論文は,歴史を逆転するかの如く見える最近の発展の裏にある真の進歩を概念的に解明することを目的とする。
- 著者
- 高木 伸哉 池田 裕美 川瀬 貴博 長澤 麻央 チョウドリ V.S. 安尾 しのぶ 古瀬 充宏
- 出版者
- Japanese Society of Pet Animal Nutrition
- 雑誌
- ペット栄養学会誌 (ISSN:13443763)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.2, pp.67-72, 2013
カテコールアミンの前駆体であるL-チロシンの長期投与は慢性ストレスがもたらす行動を緩和することが知られているが、急性ストレス時にL-ならびにD-チロシンの効果を比較した報告はない。本研究では、急性ストレスに対するL-チロシンとD-チロシンの経口投与がマウスの行動に及ぼす影響と脳内の両チロシン濃度に及ぼす影響を調査した。オープンフィールドにおける行動量にL-ならびにD-チロシンの効果は認められなかった。経口投与35分後にL-チロシン投与により血漿L-チロシン濃度は急激に上昇したが、D-チロシンの投与では血漿D-チロシンの緩やかな上昇が観察された。興味深いことに、対照区の各脳部位(大脳皮質、海馬、線条体、視床、視床下部、脳幹ならびに小脳)において、D-チロシンの濃度はL-チロシンの1.8-2.5倍高かった。すべての脳部位において、L-チロシンの投与によりL-チロシン含量は増加したが、D-チロシンの投与でD-チロシン濃度の上昇は認められなかった。上記より、急性投与したL-チロシンとD-チロシンは行動量に影響しないが、L-チロシンとD-チロシンの脳内移行の様相は異なると結論づけられた。